1 / 1
大人になるために僕らのすることときたら
しおりを挟む
底冷えする夜なのに暖かいのは、いつもは一人で過ごしているこの空間にもう一人いるからだろうか。
こたつの上には鍋を煮立たせているカセットコンロ。立ち上る湯気と熱気のお陰で、薄っすら上気しているはずの頬がごまかされている。
「もうエアコン切ってもよさげやな。」
こたつから脚を出してフリースを脱いだ敦人が床に置いてあったリモコンに手を伸ばす。近くにいた遥希が、ああ、と気付いてリモコンを取り、ボタンを押してからテレビ横のスペースに戻した。
電子音に続いて軽く振動音を立てながらエアコンがのっそりと口を閉じてゆく。
「なぁ、これってどんくらい待つか分かる? 牡蠣と鱈がどんどん縮んで無くなりそうやで救出せなあかんよな。」
敦人は秋から一人暮らしを始めていた。
英文科の授業に加えて教免課程を取っているために受けている授業数も多い上、実家から通っているとサークル活動をする時間もない。だから夏休みの短期バイトでまとまった額の貯金を作り、さらに家庭教師先まで決めて親に頼み込んだのだった。
学校まで自転車で約十分、この八畳のワンルームは夏休み前に学生が出て空いたせいか相場よりずっと安い家賃で提示されていた。
建物外観はお世辞にも綺麗とは言えないものだったが、共用部分は潔癖症気味な管理人のお陰でこざっぱりと磨き上げられていた。部屋の壁紙も、『ほとんど汚れてないからこのままで借りてもらえないか』と聞かれたところを、一か月目の家賃の割引と引き換えに交渉成立。まさに掘り出し物件だった。
十月の大学内交流スポーツ大会で遥希に再会した時、敦人は真っ先に引っ越すことを伝えた。野球の試合の最中、三塁の上だった。
サードの守備をしていた遥希に、ランナーとして塁に進んできた敦人がまるで道端で会ったようにその話をしたのだった。
「ハル! もうすぐ一人暮らしするから、遊びに来いよ。」
大学に入ってからは学部も校舎も違うから実際に顔を合わせるのは入学式以来初めてだった。たまにメッセージアプリでやり取りするのは、お互いの学食の内容や、相変わらずサッカーの話。
そんな状況で久しぶりに会っていきなり部屋に誘われた遥希は、嬉しいとか驚いたと言う感情を通り越して妙に冷静に答えてしまった。
「じゃあ寒くなったら鍋しに行く。」
後から考えればあれは敦人なりの(笑えない)冗談だったのかもしれない。
例年より早い冬の訪れにそろそろ遊びに行こうかと遥希が逡巡していた矢先、能天気な声で敦人から電話がかかってきた。
「ハル、俺やけど今週末暇やったら鍋せん? 泊まってもらっても大丈夫やし。」
+
狭いこたつの中で体勢を変えるたびに足が当たるので、遥希は落ち着かなかった。久しぶりに一緒にいるとどうも意識してしまう。
遥希は鍋に集中する敦人をおいて立ち上がり、空いた器を洗い出した。学生向けの小さなキッチンスペースで洗ったものを一つづつ拭いては片づけながら敦人の様子を眺め、誰かと一緒に住むってこんな感じなのかなと想像した。
同じ大学に通っているけれど遥希は実家暮らしをしていた。兼業農家の家の台所はいつも祖母が取り仕切っていて、遥希はほとんど料理をしたことがなかった。そんな遥希の目からも、材料を全部一緒に入れて火をつけた敦人の家事経験値は自分と大して変わらなく見えた。
「敦人はいつも料理してんの? 調味料と食器がやけに充実してるのが謎なんだけど。」
正直、敦人が買いそうもないポップな柄の食器が混ざっていたから「彼女できたの?」と聞きたかった。でも肯定された時の精神的ダメージを考えると変に遠回しな質問になってしまう。
「あー、してるようなしてないような。皿洗ってくれてありがとう。それね、春に大学卒業した兄ちゃんが実家に戻ってきたんだけど、一人暮らしの時の皿とかを全部持って帰ってきたんだよ。それを勿体無いって母さんが取って置いてて、そのまま渡された。こたつも、この辺のも全部兄ちゃんのやつ。」
敦人はこたつの上の鍋周りをぐるっと指さして笑った。綺麗にしてあるけど新品ではなかった理由はそれかとは納得した。
「彼女と半同棲してたらしいんだけど、インテリアコーディネーターなんやって。」
「なるほど、だから敦人が買わなさそうなおしゃれな食器があるんだ。」
「そうそう、って微妙に失礼なこと言われてる気がするわ。ていうか、彼女が置いてったの、とか聞いてくれんの?」
それは冗談なのか、現実の話なのか遥希には判断が付かなかった。
どちらともともとれる表情で自分の方を見る敦人に、何とか笑顔を作って「いるの?」と返した。だめだ、きっとひどい顔してる。
口角を無理やり上げているけれど、遥希が保とうとしている繊細な何かが今にも崩れそうなのは敦人にも伝わっていた。意地悪かもしれないけれど、それを見るとどうしても気持ちのどこかにむずかゆい嬉しさが沸き起こる。
「うん?」
だから曖昧に語尾を上げながら答えて、また鍋をつつく振りをしたのだった。
そんな様子に遥希はそれ以上その話題を引き延ばしたくなかった。
「一人暮らしってどう?」
「えー、飯と掃除と洗濯と戸締りとか、まあとにかく色々面倒。でも夜中に人が来ても大丈夫だし、親に気を遣わずにしたいことができて楽しいよ。」
やっぱり彼女がいるのかな、と思うと改めて自分の気持ちを心の中のどこか違う場所に追いやらなくては、と遥希は考えてしまう。
「こっちにいないとESSにも参加できないし。」
英会話のできる英語教師を目指す敦人にとっては、英会話教室ほどお金のかからないESSに絶対に入りたかったらしい。マイペースにきちんとやりたいことを進めてゆく敦人のそういうところを遥希は尊敬していた。
「敦人は偉いな。うちは英語スピーチとかさせる授業は必須でもない限りとる奴は少ないよ。」
「ふうん、そんなもんなのかな。」
テレビのチャンネルを変えていた敦人は、ふと思い出したようにスマホを手に取り何かを熱心に確認し出した。
「あ! ハル、こっち来いよ!」
という声に反応して遥希が後ろから覗き込むと、サッカーの試合の映像が流れていた。敦人の右肩に手をのせながら、左手の中にあるスマホ画面に肩越しに顔を近づけた。
「何点差?」
「二点差。後二分だし勝つだろうな。」
「後二分か。」
画面に映し出されるスペイン一部リーグの試合の動画には、米粒より小さい選手たちが走り回っている。敦人の肩に顎を置いて見入っていると、遥希が見やすいように画面の向きが変わり、敦人の頭が遥希の頭にくっついた。
このまま横を向けば、頬に唇の触れる近さだ。その距離と反比例するように、本当に触れるために超えなければいけない壁は果てしなく高くて、それを思うと切なくなった。友達としてならいくらでも近づけるのに、敦人を抱きしめることはできない。
試合は間もなく終了する。黙ったまま二人で画面を見ているけれど、勝利がほぼ確定しているから、勝ち負けよりも一秒ずつ減ってゆく残時間の方が気になった。敦人の背中が、そこに寄り掛かっている遥希の体重を支えてくれる。
高校の時もよくこうやってスポーツ関係の雑誌を見ていたことを思い出す。
制服を着て、勉強して、それなりに楽しかった毎日。みんな同じような顔をしていたけれど、敦人のいる所だけが明るかった。
窮屈だったけれど毎日近くにいることができた。あの頃の空気が体の中に蘇える。こうやって二人きりで敦人の部屋にいることができるのは幸せだと思う。
すぐ横にある少し癖のある黒い髪がふわふわと頬に当たり、遥希の身体に淡い衝動が広がってゆく。
友達としてならこんなに近くにいることができる敦人を、別の欲求を持って抱き寄せたいというのは過ぎた望みなのかな。常識が邪魔をして身体はうごかない。
五秒前、四、三......試合終了のホイッスルが鳴る一瞬手前で敦人の頭が微かに動き、敦人が遥希の髪にそっと頬を摺り寄せた。遥希の心臓がキュッとした。隣を向きたい、敦人は今どんな表情をしているのだろうか。
そんな遥希の気持ちに気づいた様子もなく、敦人はしばらく静かに遥希の髪に頬を埋めていた。
さむっ。
敦人は背中を震わせて浅くなっていた眠りから覚めた。こたつからはみ出た上半身に遥希がかけてくれたらしい毛布がずり落ちて、あらぬ場所に丸まっている。
二人で一本ずつビールを飲んだ記憶はある。けれど酔ってたのは主に敦人で、遥希は「うち、親父も母さんも強いから、多分遺伝。」と言って赤くなることもなく飲んでいた。鍋が終わった後遥希は黙々と机の上を片付けていたっけ。それから、テレビつけてぽつぽつと話しながらぼんやりお茶を飲み、「眠いから布団入るよ。敦人は?」「んー、もうちょっとしたら。」って会話したのが午前一時くらいだったような……。
ぼんやりと思い出しながら、二つ敷いた布団の片方にこんもりとした山がある光景を不思議な気分で見ていた。
遥希が寝ると言った時に、風邪引くから切ってと頼んだのは自分だったっけ。数時間前に切ったこたつの温もりはとうに消え、暖まっていた部屋も冬の寒さの前に一気に冷え込んでいる。
暗い部屋に浮かび上がる時計の電光表示は午前二時十分。
丑三つ時か、どうりで寒いわけだよ。寝ぼけた頭で脈絡のないことを考えながらトイレに行って歯を磨く。いつもの自分の布団の上に這ってゆき、隣の布団にくるまった遥希を見下ろした。
お互い声変わり前から知ってる。今更ながら長い付き合いだ。
中一の時の林間学校では、学年全員が大広間で雑魚寝をした。夜中に目が覚めた敦人が数人の友達とこっそり廊下に出ようとした時、今夜みたいに寝ていた遥希の横を通り過ぎたのだ。廊下の薄明かりに浮かんだ寝顔になぜか引き留められた。
みんなで入った大きな風呂場で、早々と大人の身体になったやつを羨んだり、自分の身体を隠したり、見せびらかしたりして浮ついた雰囲気の中、別のクラスだった遥希と初めて話をした。数日前に切ったばかりの髪の長さが気に食わない言っていたけれど、枕の上で見るその髪型はするんとした遥希の輪郭によく似合っていた。
ずっと敦人の記憶に張り付いていたあの時のあどけない顔が目の前の遥希に重なってくる。
すっかり大人になっちゃったな。ヒゲが伸びかけている顎をそっと撫でてみた。ん、とくすぐったそうに下唇を突き出して遥希は顔を振った。あの頃と同じように警戒心の欠片もなく熟睡しやがって。こうして見る遥希は、敦人がまだ性別とか恋愛なんて意識していなかった頃と変わらない。
自分とは違う顔のラインを興味深げに覗きこむ敦人の気配を感じたのか、遥希は寝返りを打って上を向き薄眼を開けた。暗さに目が慣れるまで眉根を寄せたまま視線を彷徨わせているのが無防備で:弄(いら)いたくなってくる。しばらく待っていると斜め上に敦人の存在を認めて、腕で顔を隠してしまった。
腕を退けたらどんな表情をしてるのだろう、というのは純粋な好奇心からくる欲求じゃないことくらい自覚している。
「敦人、まだ起きてんの? 今何時?」
掠れた声の後、唾を飲む音が聞こえた。
「ん、二時過ぎ。もう寝る。ハル、もしかして喉渇いてる?」
「や、大丈夫。」
夜独特の静けさと遠くから聞こえる車や風の音。この地方で一番底冷えする時期の深夜の布団は冷たい。身体をすべりこませたけれどなかなか暖まらなくって腕や脚を擦っていると、隣で寝がえりを打つ気配がした。
「寒い? 大丈夫?」
「大丈夫じゃない、凍え死ぬ。」
隣から笑いを含んだ声。どことなく緊張しているように聞こえるのは敦人自身が意識しすぎてるだけだろうか。
「......こっち温かいけど、入る?」
とっさに理解できず予想していなかった言葉に心臓が走り出す。
友達として言っている? この年になって友達と一緒の布団で寝るなんてことあるのか?
近づけばきっと我慢できなくなる。こんな狭いシングルの布団に入ればいやおうなしに身体は触れるのだから。
そこに入っていいってってことは、それなりに身体の距離も近くなる。自分勝手な期待を持ちつつ一歩踏み込もうとしたときに拒絶されたら取り返しがつかない、と不安もよぎる。
推理小説と違って人の心なんて読めないんだ。
「いやなら別にいいけど。」
声が微かに震えて聞こえるのは、自分の思い込みなのかもしれない。でもさっき試合を見ていた時、遥希は自然に敦人に触れていた。だから安心して顔を寄せたんだった。優しく受け入れるような空気が体のうちに蘇り、胸の奥がまた甘く震えた。これは自分の勘違いじゃないはずだ。
「いいの? やった。」
できるだけ何でもないことのように喜んでみせながら、敦人は弾む気持ちを抑えられなかった。雑魚寝した時と違う気持ちを持っている自分を遥希はどう思うのか。
間近にいるからようやく顔が見えるほどのささやかな夜の光。暗闇の中で自分の気持ちもる体温のようにに静かに伝わればいいのに。
敦人は冷たい布団の中で遥希に向かってにじり寄ってゆく。薄暗がりの中、すぐ隣でこちらを向き、掛布団を僅かに持ち上げてくれているのが見えた。自分を呼んでいる暖かい空気に素直に従って遠慮なく手足を突っ込み、身体をねじ込んでゆく。布団を支えていた腕が敦人の肩の上に落ち、するりと撫でながら引っ込んでゆく。
「あったけ。生き返るわ。」
「あっためておきましたよ、信長様。」
「お、木下藤吉郎か! 草履より足をあっためてくれ。」
「マジか、足フェチ?」
「逆だろ、俺の足をあっためて欲しい。」
「僕はやんないよ。」
冷たく言い放った遥希の顔に向かって敦人は祈るように両手を合わせて突き出した。
「えー、ハルちゃんお願いします。お手々が冷たい、お手々がちんちんする。」
「足じゃないのかよ! つか、それ久しぶりに聞いた。ごんぎつね?」
「ちげーよ、手袋を買いにだろ。ごんじゃ俺撃ち殺されるやん。」
狭いシングル布団の中で向かい合い背中を丸めてひとしきり笑うと、敦人が冷えた手を遥希の襟元に突っ込もうとしてきた。
「マジでやめ! 冷たいって!」
あまりの冷たさに逃げる遥希と追う敦人。身をよじって暴れすぎて上掛けから出てしまい、急いで引っ張り上げて身体を寄せあった。
「あぶねーあぶねー。」
「凍死するとこやったな。」
距離が近すぎるせいで二人とも気恥ずかしくって口を閉じた。遥希はぎこちなく目をそらし、うつ伏せになって腕に顎をのせ、目の前にある本棚を見る振りをした。
薄辛い部屋の中、水に変わる直前の薄い氷を指で押すような緊張感と期待。静かな時間が長くなるほど、残り時間が減ってゆく、試合終了間際みたいだ。
「ハルは一人暮らしせえへんの? 彼女できても、実家だとお家デートでエッチなことできんやんな。」
「いないし、したことないし。」
「あ……っそっか。俺も、そういえば一人暮らしやけどおらんし、したことないわ。」
随分間延びした答えに、遥希が怪訝な顔で問いただした。
「ええ? さっき彼女おるっていったやん。」
「言ってない、言ってない。いないよ。」
焦って全力で否定した敦人に、なんだよそれ、って視線をよこす。ぷつんと途切れる会話。一分にも満たない間を我慢できなくて遥希が口を開いた。
「この状況って、どっちかが女なら合意したってことになるのかな?」
「ああ? 一緒の布団に入ってること? むしろ合意なくやられちゃうかもよ。」
「襲われちゃうのか。」
どこにも着地しない会話。言葉が消えると、感情が前に出てくるんだ。それをうまくコントロールできるか、遥希にはよく分からなかった。
「じゃあさ、友達同士なら? うっかりキスとかしちゃってもこの状況なら『布団に入ったくせに』ってなるかな。」
沈黙が落ちる。それは、男女の友達の話なんだろうか。それとも今の二人のことなのか。首を動かして敦人を見ても答えはもらえない。遥希の上を一秒一秒時間が過ぎてゆく。
何秒経ったのだろうか。しんとした部屋の中で躊躇いがちに敦人が口を開いた。
「してみる?」
やけに落ち着いた敦人の声は、遥希の耳には全然違う人が話してるように聞こえた。二人とも目を開けたまま身じろぎもしない。じりじりと過ぎる時間が内側で高まる気持ちを押し上げてゆく。
(してみる、って何を?)
閉じていた遥希の唇が緩んで薄く開かれた。そこから出る言葉を待たず、敦人は数十センチの距離をぐっと詰めた。身を乗り出して伏し目がちに顔を近づけてくる敦人の瞼のカーブがくっきりと際立っているのを見ながら、遥希はやっと理解した。さっきの言葉は『キスしてみる?』ってことだったと。
自分の心臓がはっきり脈を打っているのを他人事のように感じながら目を閉じた。
遠慮がちに重なる唇。初めてのキスはただ乾いた皮膚と皮膚が僅かに触れただけだった。なのに、身体の奥がきゅうと締め付けられた。あっさりと離れたのが物足りなくて顎を少し突き出すと、すぐにもう一度来た。その感触だけに集中する。
何も見ずにいると溢れる気持ちの出口がなくなりそうで、遥希は目を開いた。
お互い鼻先が触れるくらいの距離に直り、困ったような顔をした敦人がまたそっとキスをした。それだけだった。
敦人にとっては友達同士でふざけてしたキスかもしれない。でも一度手に入れたものは、もう手放せない。どんどん欲が深くなってゆく。何度でもしたい、触れたい、貪って、耽りたい、めちゃくちゃにして暴きたい。暴れ出しそうな身体を理性という曖昧なもので無理やり押さえ込んで、遥希は視線を下げた。
目の前にはくっきりした敦人の喉仏が見える。
「ごめん、平気?」
ごめん、って何? 平気って何?、と少し意地悪な気持ちになって顔を上げると、敦人が落ち着かなさそうに目を瞬かせていた。
「大丈夫。敦人は?」
口にした後で気が付いた。たかがキスしたくらいでお互い随分と間の抜けた質問だ。そんな風に冷静でいたのは遥希だけだったようだ。敦人は昂った気持ちを落ち着けるように大げさに深呼吸した後、両手で顔を隠した。
「俺は、大丈夫じゃない……あー、びびったわ! 初めてキスした。」
「初めてなの?」
「うん。うん? あれ? そういやこの前したのは......」
「この前、キスしたんだ。」
うっかり口を滑らせてしまった敦人は、しまったという顔をして遥希を見た。苦い表情で真っ直ぐに自分を見る遥希に、敦人は一番まずいタイミングで一番言ってはいけないことを口走ったと自覚して慌てた。
「あ、の。夏にバイト、イベントのバイトしたんだけど、一人暮らしのお金ためるためにさ。そのバイトが終わった後に全員で打ち上げに行って、で、その時……した、いやされたというか。なんか、俺言い訳ばっかやな。ごめん......」
取り繕うとすればするほど焦ってしまい、モゴモゴと誤魔化すように語尾が小さくなってゆく。その様子に遥希の気分はますます落ち込んでいった。
なんだ、結局そういうことじゃないか。女の子と仲良くやっているんなら、何もこんな風に自分を揶揄う必要なんてないのに。
傷は浅い方がいい、変な期待なんかしたくないし、今ならふざけたんだろ、冗談だろ、笑えよ、で済ませられる。
「別に謝らなくても……その子、敦人が好きだったんやろ?」
遥希の声はやけに冷たく敦人の耳に響いた。間違ったものを口にして吐き出そうとするような表情は、さっきまで布団の中でじゃれ合った親密な空気を打ち消そうとしているようですらだった。
「違う、違うと思う。バイトでちょっと話しただけやし、もう連絡しいへんって決めたから。」
実はその後も何度か遊びに行こうと誘われていた。『みんなで』と言われて行ってみたら、来たのは彼女ともう一組のカップルだけ。遊ぶのはそれなりに楽しかったけれど、それ以上の気持ちは持てなかったのだ。今目の前にいる幼馴染に対して抱くような、甘やかしたり甘えたいと言う親密な感情も性的な欲求も湧いてこなかったのだ。
硬い表情の遥希の顔に敦人の指先が触れて、こめかみにかかる前髪を優しくよける。その感触に縋り付きそうになるのを押しとどめ、遥希は身体を回して敦人に背を向けていい捨てた。
「多少でも好意がなきゃキスなんてせんやろ。」
そう言いながら、じゃあ自分たちのキスは何だったんだろう、と遥希は思う。何であって欲しいのだろう、と。突然女の子とのキスの話をする敦人の気持ちは全く理解できなかった。
いつもの遥希らしくない。やけに突っかかってくるし、拗ねたような声色だった。それはつまりどういうことなんだろうかと少し考え、敦人は急に嬉しそうに口角を上げた。
「あのさ、つまりそれって今のキスもそう考えていいの? ハルには、俺とキスしてもいいくらいの好意があったってことだよな?」
「その女の子にキスされた時、敦人はキスされてもいいくらいの好意をその子にもってたってことだよね。」
にべもない言葉に、敦人も流石にムッとした。
「お前さ、そういうのずるい。」
「ずるくない、そっちが最初に言ったことだろ。」
「じゃあ謝るからこっち向いてよ。」
応えることができなかった。敦人が謝らなきゃならないことなんて何もない。自分が何を言ってるのか自覚して恥ずかしさでいっぱいになった。敦人の顔を見たらきっと全部バレてしまう。
真剣に悩んでいる遥希の脇腹に、突然指先が遊んだ。
「なー! 拗ねてないでこっち向けよー!」
「ひ、ずるい! やめろって! ばか! ガキんちょかよ!」
擽ったさに何度手を除けても、遥希の指をかわしながら敦人はしつこく擽ってきた。脚をばたつかせているうちに上に着ていたトレーナーが捲れて、ようやく温まった敦人の指が直接腹に触れてくる。擽ったさよりもうごめく指にこれまで隠してきたものを導き出されるのが怖くて強く手を掴んだら内側から指先を絡め取られた。
背中越しに身体が近づいてくる。敦人の膝が遥希の腿裏に当たり、ハッとしたように離れる。
整えようとしても遥希の荒れた息はおさまらなかった。耳奥で響く心臓の音がうるさくて頭がクラクラする。そんな気持ちを知ってか知らずか、敦人が後ろでゆっくりと息を吸う音が聞こえた。
「ハル、ええと、遥希さん。」
急に改まった口調になり、何を言うのか全く想定できずに遥希は身構えた。
「そんな固まらんといて……いや俺がさ、今キスしたせいでちょいテンパっていらんこと言っちゃったんですが、テンパったのはつまり嫌だったとかそういう訳じゃなくて、むしろ、あの。」
ぐるぐると所在なく歩き回るような言い方には、どことなく遥希の出方を伺うような響きがあった。分かってる、六年越しの付き合いだ。意固地になった時の遥希の扱いはよく分かっていた。
「つまり、ハルはどういうつもりなんかなーって……」
それから、敦人の生真面目な手が遥希の手を捕まえたまま、脇腹から移動して遠慮がちに腰骨の上に触れた。
しまい込んでいた欲望を理性で押さえていたのに、その感触が遥希の中のすべてをひっくり返してくる。
「な、ハル……」
背中に触れる身体、耳元にかかる息、低い声、あからさまに誘いかけてくる。
「なにが言いたいんだよ。」
「今度は、ハルからしてほしい。」
腰にかかる手が腹を這い身体に巻き付いてゆく。微かに後ろに引っ張られ、こっちを向けと促してくる。それに逆らうことなく振り向いた遥希が、敦人の首に手を添えて唇を塞いだ。躊躇いはなかった。
もう一度、今度は身体を起こして上から覆いかぶさるようにキスをする。遥希だって初めてだった。だから、したいように敦人と唇を重ねた。柔く吸い、ずらしてまた重ね、唇同士で捏ねるように食み、緩んだ隙間に自分の隙間を合わせ、ただ敦人のことだけを考えて没入してゆく。
舌を絡め、お互いに熱くなった身体を求めて服を引き剥がしあった。膝を曲げた敦人の足首から下着を引き抜くと、次は身体を支配したくなる。
掌で太腿の厚い筋肉をなぞってゆけば、重ねた唇の隙間からくぐもった熱い息が漏れ始める。湿りけを帯びた呼吸に合わせて積み上げられてゆく官能が強い占有欲を呼び起こす。
行き場の分からない二人の手が身体をかき抱き合う。もうゼロ距離なのに、まだ近づき足りなかった。
腹の間で屹立が蜜を垂らしながら睦み合い、熱量を高めてゆく。擦れあうたびにもっと刺激が欲しいと切なく脈動する。なのにそんな中で急に敦人が覆いかぶさっていた遥希の肩を押して身体の間に隙間を作った。
突然の拒絶に驚いて遥希は上半身を起こした。
(やっぱりいざとなるとダメなのかな。)
遥希は冷たい部屋の空気に身震いして毛布を肩に引き上げ、もう一度敦人の横に寝転んだ。
落ち着いて、相手を責めないこと。仕方ないんだから。生理的に嫌われたらもう友達にもなれないんだから。
「やっぱ、嫌?」
今止めるなら、もういっそ殺してほしい。強引に続ける? いやダメだ。違う、最初からキスなんてしなけりゃよかったんだ、泊まりに来なきゃよかったんだ。
葛藤する気持ちを押し殺しているうちに自分がどんな表情にしているのか気づいていなかった。
「違う、嫌じゃないからそんな怖い顔すんなよ。あの、今更やけど、ハルが好きやけど俺したことないから……続けたいは続けたいんやけど。」
(したことないから? 続けた……?)
「どうすればいい? ググって……っ!」
また訳のわからないことを言い出しそうな気配を感じ、遥希はキスして敦人を黙らせた。優しく上唇を吸った。さっきと違い湿った唇同士がなごり惜しむようにゆっくりと離れてゆく。
「敦人、いちいち心臓に悪すぎる。殺す気か?」
「……完全殺人やな。」
「も、そういうのいらんわ。」
呆れた様子の遥希がゴツンと音がしそうな勢いで頭突きして、そのまま鼻と鼻をくっつけた。
「僕も、好きや。」
「ありがとう、で、とりあえず今は出したい。ヤバイ、苦しい、入れたい、出したい。って、あれ、どっちがどうする?」
「ばか敦人、もう黙れよ……」
+
浅いまどろみの中、記憶と夢がごちゃ混ぜになって身体を包んでいた。
限界だと言っていた敦人を口でいかせて、それから敦人の太腿を使って自分も満足したのだった。いや、素股をしたのは自分だったっけ? お互い我慢しなくてもいいとわかった瞬間、気持ちが満たされて……。
(すごい幸福感……)
だから遥希は自分に、これは夢だからと言い聞かせながらゆっくりと意識を浮上させたのだ。
脚を動かすと乾いた精液が皮膚を引っ張り、ああ、やっぱり夢じゃなかったのかと遥希は人ごとのように考えた。
背中にあたる感覚が家のベッドと違う。狭い布団の端っこで腕をはみ出させながら寝ていた。寝相が悪くて掛け布団を引っ張ってる敦人をしばらく見ていると、目を覚まして薄目を開けた。
「おはよう。」
「ん、起きとったんか。」
鷹揚にあくびしながら敦人がしっかりと目を開けた。やけに白っぽい朝の光の中で同じ布団に入っていると眩しさに戸惑ってしまう。
「あー」とも「うー」ともつかない声を出して眼を瞬かせていた敦人が、腕を伸ばしてスマホを取った。難しい顔をしながら画面に指を走らせて唸っている。
「今日用事あった? 僕そろそろ帰るわ。」
布団の外に失敗作みたいに丸められた下着を見つけ、遥希は足指で引っ掛けて引き寄せた。
「あかん、一緒にドラッグストアいこ。速攻行ってこよ。後で俺が雑炊作るから、一緒にくおう。」
「朝一で何買うの?腹減るから行く前に食べようよ。」
「ローションとゴム、なかったら見つかるまではしごする。見つかるまで帰りませーん。」
「なんだよそのやる気。」
あきれ顔した遥希の頬が徐々に赤くなってゆくのを見て敦人は楽しそうに笑った。
「分かってるくせに。俺大人の階段上りたいんやけど。ハルと一緒に。」
無邪気に言ってのける敦人の笑顔を目に焼き付けて遥希は立ち上がる。
「シャワー借りる。」
「おう。」
敦人は脱ぎ散らかした二人分のトレーナーを布団の下から引き出している。ああ、この鼻歌なんだっけ。
「なあ。」
バスルームの扉を開けたまま遥希が顔を出す。
「何?」
「僕もやり方がよく分からんから、調べといて。ほいでさ、まあ、どっちでもいいけど両方試してみたくはある。」
それだけ言って急いでドアを閉めた。トレーナーから頭を出した敦人が、扉の向こうでどんな表情をしているのか、見なくたって簡単に想像できる。
いつも通り笑ってるはずだ。
中学の時も、高校の時も、サッカー見に行った時も、球技大会もテスト勉強した時も。敦人は遥希に笑いかけてくれていた。
その笑顔を思い浮かべて遥希は「敵わないな。」と小さな声で言った。
完
こたつの上には鍋を煮立たせているカセットコンロ。立ち上る湯気と熱気のお陰で、薄っすら上気しているはずの頬がごまかされている。
「もうエアコン切ってもよさげやな。」
こたつから脚を出してフリースを脱いだ敦人が床に置いてあったリモコンに手を伸ばす。近くにいた遥希が、ああ、と気付いてリモコンを取り、ボタンを押してからテレビ横のスペースに戻した。
電子音に続いて軽く振動音を立てながらエアコンがのっそりと口を閉じてゆく。
「なぁ、これってどんくらい待つか分かる? 牡蠣と鱈がどんどん縮んで無くなりそうやで救出せなあかんよな。」
敦人は秋から一人暮らしを始めていた。
英文科の授業に加えて教免課程を取っているために受けている授業数も多い上、実家から通っているとサークル活動をする時間もない。だから夏休みの短期バイトでまとまった額の貯金を作り、さらに家庭教師先まで決めて親に頼み込んだのだった。
学校まで自転車で約十分、この八畳のワンルームは夏休み前に学生が出て空いたせいか相場よりずっと安い家賃で提示されていた。
建物外観はお世辞にも綺麗とは言えないものだったが、共用部分は潔癖症気味な管理人のお陰でこざっぱりと磨き上げられていた。部屋の壁紙も、『ほとんど汚れてないからこのままで借りてもらえないか』と聞かれたところを、一か月目の家賃の割引と引き換えに交渉成立。まさに掘り出し物件だった。
十月の大学内交流スポーツ大会で遥希に再会した時、敦人は真っ先に引っ越すことを伝えた。野球の試合の最中、三塁の上だった。
サードの守備をしていた遥希に、ランナーとして塁に進んできた敦人がまるで道端で会ったようにその話をしたのだった。
「ハル! もうすぐ一人暮らしするから、遊びに来いよ。」
大学に入ってからは学部も校舎も違うから実際に顔を合わせるのは入学式以来初めてだった。たまにメッセージアプリでやり取りするのは、お互いの学食の内容や、相変わらずサッカーの話。
そんな状況で久しぶりに会っていきなり部屋に誘われた遥希は、嬉しいとか驚いたと言う感情を通り越して妙に冷静に答えてしまった。
「じゃあ寒くなったら鍋しに行く。」
後から考えればあれは敦人なりの(笑えない)冗談だったのかもしれない。
例年より早い冬の訪れにそろそろ遊びに行こうかと遥希が逡巡していた矢先、能天気な声で敦人から電話がかかってきた。
「ハル、俺やけど今週末暇やったら鍋せん? 泊まってもらっても大丈夫やし。」
+
狭いこたつの中で体勢を変えるたびに足が当たるので、遥希は落ち着かなかった。久しぶりに一緒にいるとどうも意識してしまう。
遥希は鍋に集中する敦人をおいて立ち上がり、空いた器を洗い出した。学生向けの小さなキッチンスペースで洗ったものを一つづつ拭いては片づけながら敦人の様子を眺め、誰かと一緒に住むってこんな感じなのかなと想像した。
同じ大学に通っているけれど遥希は実家暮らしをしていた。兼業農家の家の台所はいつも祖母が取り仕切っていて、遥希はほとんど料理をしたことがなかった。そんな遥希の目からも、材料を全部一緒に入れて火をつけた敦人の家事経験値は自分と大して変わらなく見えた。
「敦人はいつも料理してんの? 調味料と食器がやけに充実してるのが謎なんだけど。」
正直、敦人が買いそうもないポップな柄の食器が混ざっていたから「彼女できたの?」と聞きたかった。でも肯定された時の精神的ダメージを考えると変に遠回しな質問になってしまう。
「あー、してるようなしてないような。皿洗ってくれてありがとう。それね、春に大学卒業した兄ちゃんが実家に戻ってきたんだけど、一人暮らしの時の皿とかを全部持って帰ってきたんだよ。それを勿体無いって母さんが取って置いてて、そのまま渡された。こたつも、この辺のも全部兄ちゃんのやつ。」
敦人はこたつの上の鍋周りをぐるっと指さして笑った。綺麗にしてあるけど新品ではなかった理由はそれかとは納得した。
「彼女と半同棲してたらしいんだけど、インテリアコーディネーターなんやって。」
「なるほど、だから敦人が買わなさそうなおしゃれな食器があるんだ。」
「そうそう、って微妙に失礼なこと言われてる気がするわ。ていうか、彼女が置いてったの、とか聞いてくれんの?」
それは冗談なのか、現実の話なのか遥希には判断が付かなかった。
どちらともともとれる表情で自分の方を見る敦人に、何とか笑顔を作って「いるの?」と返した。だめだ、きっとひどい顔してる。
口角を無理やり上げているけれど、遥希が保とうとしている繊細な何かが今にも崩れそうなのは敦人にも伝わっていた。意地悪かもしれないけれど、それを見るとどうしても気持ちのどこかにむずかゆい嬉しさが沸き起こる。
「うん?」
だから曖昧に語尾を上げながら答えて、また鍋をつつく振りをしたのだった。
そんな様子に遥希はそれ以上その話題を引き延ばしたくなかった。
「一人暮らしってどう?」
「えー、飯と掃除と洗濯と戸締りとか、まあとにかく色々面倒。でも夜中に人が来ても大丈夫だし、親に気を遣わずにしたいことができて楽しいよ。」
やっぱり彼女がいるのかな、と思うと改めて自分の気持ちを心の中のどこか違う場所に追いやらなくては、と遥希は考えてしまう。
「こっちにいないとESSにも参加できないし。」
英会話のできる英語教師を目指す敦人にとっては、英会話教室ほどお金のかからないESSに絶対に入りたかったらしい。マイペースにきちんとやりたいことを進めてゆく敦人のそういうところを遥希は尊敬していた。
「敦人は偉いな。うちは英語スピーチとかさせる授業は必須でもない限りとる奴は少ないよ。」
「ふうん、そんなもんなのかな。」
テレビのチャンネルを変えていた敦人は、ふと思い出したようにスマホを手に取り何かを熱心に確認し出した。
「あ! ハル、こっち来いよ!」
という声に反応して遥希が後ろから覗き込むと、サッカーの試合の映像が流れていた。敦人の右肩に手をのせながら、左手の中にあるスマホ画面に肩越しに顔を近づけた。
「何点差?」
「二点差。後二分だし勝つだろうな。」
「後二分か。」
画面に映し出されるスペイン一部リーグの試合の動画には、米粒より小さい選手たちが走り回っている。敦人の肩に顎を置いて見入っていると、遥希が見やすいように画面の向きが変わり、敦人の頭が遥希の頭にくっついた。
このまま横を向けば、頬に唇の触れる近さだ。その距離と反比例するように、本当に触れるために超えなければいけない壁は果てしなく高くて、それを思うと切なくなった。友達としてならいくらでも近づけるのに、敦人を抱きしめることはできない。
試合は間もなく終了する。黙ったまま二人で画面を見ているけれど、勝利がほぼ確定しているから、勝ち負けよりも一秒ずつ減ってゆく残時間の方が気になった。敦人の背中が、そこに寄り掛かっている遥希の体重を支えてくれる。
高校の時もよくこうやってスポーツ関係の雑誌を見ていたことを思い出す。
制服を着て、勉強して、それなりに楽しかった毎日。みんな同じような顔をしていたけれど、敦人のいる所だけが明るかった。
窮屈だったけれど毎日近くにいることができた。あの頃の空気が体の中に蘇える。こうやって二人きりで敦人の部屋にいることができるのは幸せだと思う。
すぐ横にある少し癖のある黒い髪がふわふわと頬に当たり、遥希の身体に淡い衝動が広がってゆく。
友達としてならこんなに近くにいることができる敦人を、別の欲求を持って抱き寄せたいというのは過ぎた望みなのかな。常識が邪魔をして身体はうごかない。
五秒前、四、三......試合終了のホイッスルが鳴る一瞬手前で敦人の頭が微かに動き、敦人が遥希の髪にそっと頬を摺り寄せた。遥希の心臓がキュッとした。隣を向きたい、敦人は今どんな表情をしているのだろうか。
そんな遥希の気持ちに気づいた様子もなく、敦人はしばらく静かに遥希の髪に頬を埋めていた。
さむっ。
敦人は背中を震わせて浅くなっていた眠りから覚めた。こたつからはみ出た上半身に遥希がかけてくれたらしい毛布がずり落ちて、あらぬ場所に丸まっている。
二人で一本ずつビールを飲んだ記憶はある。けれど酔ってたのは主に敦人で、遥希は「うち、親父も母さんも強いから、多分遺伝。」と言って赤くなることもなく飲んでいた。鍋が終わった後遥希は黙々と机の上を片付けていたっけ。それから、テレビつけてぽつぽつと話しながらぼんやりお茶を飲み、「眠いから布団入るよ。敦人は?」「んー、もうちょっとしたら。」って会話したのが午前一時くらいだったような……。
ぼんやりと思い出しながら、二つ敷いた布団の片方にこんもりとした山がある光景を不思議な気分で見ていた。
遥希が寝ると言った時に、風邪引くから切ってと頼んだのは自分だったっけ。数時間前に切ったこたつの温もりはとうに消え、暖まっていた部屋も冬の寒さの前に一気に冷え込んでいる。
暗い部屋に浮かび上がる時計の電光表示は午前二時十分。
丑三つ時か、どうりで寒いわけだよ。寝ぼけた頭で脈絡のないことを考えながらトイレに行って歯を磨く。いつもの自分の布団の上に這ってゆき、隣の布団にくるまった遥希を見下ろした。
お互い声変わり前から知ってる。今更ながら長い付き合いだ。
中一の時の林間学校では、学年全員が大広間で雑魚寝をした。夜中に目が覚めた敦人が数人の友達とこっそり廊下に出ようとした時、今夜みたいに寝ていた遥希の横を通り過ぎたのだ。廊下の薄明かりに浮かんだ寝顔になぜか引き留められた。
みんなで入った大きな風呂場で、早々と大人の身体になったやつを羨んだり、自分の身体を隠したり、見せびらかしたりして浮ついた雰囲気の中、別のクラスだった遥希と初めて話をした。数日前に切ったばかりの髪の長さが気に食わない言っていたけれど、枕の上で見るその髪型はするんとした遥希の輪郭によく似合っていた。
ずっと敦人の記憶に張り付いていたあの時のあどけない顔が目の前の遥希に重なってくる。
すっかり大人になっちゃったな。ヒゲが伸びかけている顎をそっと撫でてみた。ん、とくすぐったそうに下唇を突き出して遥希は顔を振った。あの頃と同じように警戒心の欠片もなく熟睡しやがって。こうして見る遥希は、敦人がまだ性別とか恋愛なんて意識していなかった頃と変わらない。
自分とは違う顔のラインを興味深げに覗きこむ敦人の気配を感じたのか、遥希は寝返りを打って上を向き薄眼を開けた。暗さに目が慣れるまで眉根を寄せたまま視線を彷徨わせているのが無防備で:弄(いら)いたくなってくる。しばらく待っていると斜め上に敦人の存在を認めて、腕で顔を隠してしまった。
腕を退けたらどんな表情をしてるのだろう、というのは純粋な好奇心からくる欲求じゃないことくらい自覚している。
「敦人、まだ起きてんの? 今何時?」
掠れた声の後、唾を飲む音が聞こえた。
「ん、二時過ぎ。もう寝る。ハル、もしかして喉渇いてる?」
「や、大丈夫。」
夜独特の静けさと遠くから聞こえる車や風の音。この地方で一番底冷えする時期の深夜の布団は冷たい。身体をすべりこませたけれどなかなか暖まらなくって腕や脚を擦っていると、隣で寝がえりを打つ気配がした。
「寒い? 大丈夫?」
「大丈夫じゃない、凍え死ぬ。」
隣から笑いを含んだ声。どことなく緊張しているように聞こえるのは敦人自身が意識しすぎてるだけだろうか。
「......こっち温かいけど、入る?」
とっさに理解できず予想していなかった言葉に心臓が走り出す。
友達として言っている? この年になって友達と一緒の布団で寝るなんてことあるのか?
近づけばきっと我慢できなくなる。こんな狭いシングルの布団に入ればいやおうなしに身体は触れるのだから。
そこに入っていいってってことは、それなりに身体の距離も近くなる。自分勝手な期待を持ちつつ一歩踏み込もうとしたときに拒絶されたら取り返しがつかない、と不安もよぎる。
推理小説と違って人の心なんて読めないんだ。
「いやなら別にいいけど。」
声が微かに震えて聞こえるのは、自分の思い込みなのかもしれない。でもさっき試合を見ていた時、遥希は自然に敦人に触れていた。だから安心して顔を寄せたんだった。優しく受け入れるような空気が体のうちに蘇り、胸の奥がまた甘く震えた。これは自分の勘違いじゃないはずだ。
「いいの? やった。」
できるだけ何でもないことのように喜んでみせながら、敦人は弾む気持ちを抑えられなかった。雑魚寝した時と違う気持ちを持っている自分を遥希はどう思うのか。
間近にいるからようやく顔が見えるほどのささやかな夜の光。暗闇の中で自分の気持ちもる体温のようにに静かに伝わればいいのに。
敦人は冷たい布団の中で遥希に向かってにじり寄ってゆく。薄暗がりの中、すぐ隣でこちらを向き、掛布団を僅かに持ち上げてくれているのが見えた。自分を呼んでいる暖かい空気に素直に従って遠慮なく手足を突っ込み、身体をねじ込んでゆく。布団を支えていた腕が敦人の肩の上に落ち、するりと撫でながら引っ込んでゆく。
「あったけ。生き返るわ。」
「あっためておきましたよ、信長様。」
「お、木下藤吉郎か! 草履より足をあっためてくれ。」
「マジか、足フェチ?」
「逆だろ、俺の足をあっためて欲しい。」
「僕はやんないよ。」
冷たく言い放った遥希の顔に向かって敦人は祈るように両手を合わせて突き出した。
「えー、ハルちゃんお願いします。お手々が冷たい、お手々がちんちんする。」
「足じゃないのかよ! つか、それ久しぶりに聞いた。ごんぎつね?」
「ちげーよ、手袋を買いにだろ。ごんじゃ俺撃ち殺されるやん。」
狭いシングル布団の中で向かい合い背中を丸めてひとしきり笑うと、敦人が冷えた手を遥希の襟元に突っ込もうとしてきた。
「マジでやめ! 冷たいって!」
あまりの冷たさに逃げる遥希と追う敦人。身をよじって暴れすぎて上掛けから出てしまい、急いで引っ張り上げて身体を寄せあった。
「あぶねーあぶねー。」
「凍死するとこやったな。」
距離が近すぎるせいで二人とも気恥ずかしくって口を閉じた。遥希はぎこちなく目をそらし、うつ伏せになって腕に顎をのせ、目の前にある本棚を見る振りをした。
薄辛い部屋の中、水に変わる直前の薄い氷を指で押すような緊張感と期待。静かな時間が長くなるほど、残り時間が減ってゆく、試合終了間際みたいだ。
「ハルは一人暮らしせえへんの? 彼女できても、実家だとお家デートでエッチなことできんやんな。」
「いないし、したことないし。」
「あ……っそっか。俺も、そういえば一人暮らしやけどおらんし、したことないわ。」
随分間延びした答えに、遥希が怪訝な顔で問いただした。
「ええ? さっき彼女おるっていったやん。」
「言ってない、言ってない。いないよ。」
焦って全力で否定した敦人に、なんだよそれ、って視線をよこす。ぷつんと途切れる会話。一分にも満たない間を我慢できなくて遥希が口を開いた。
「この状況って、どっちかが女なら合意したってことになるのかな?」
「ああ? 一緒の布団に入ってること? むしろ合意なくやられちゃうかもよ。」
「襲われちゃうのか。」
どこにも着地しない会話。言葉が消えると、感情が前に出てくるんだ。それをうまくコントロールできるか、遥希にはよく分からなかった。
「じゃあさ、友達同士なら? うっかりキスとかしちゃってもこの状況なら『布団に入ったくせに』ってなるかな。」
沈黙が落ちる。それは、男女の友達の話なんだろうか。それとも今の二人のことなのか。首を動かして敦人を見ても答えはもらえない。遥希の上を一秒一秒時間が過ぎてゆく。
何秒経ったのだろうか。しんとした部屋の中で躊躇いがちに敦人が口を開いた。
「してみる?」
やけに落ち着いた敦人の声は、遥希の耳には全然違う人が話してるように聞こえた。二人とも目を開けたまま身じろぎもしない。じりじりと過ぎる時間が内側で高まる気持ちを押し上げてゆく。
(してみる、って何を?)
閉じていた遥希の唇が緩んで薄く開かれた。そこから出る言葉を待たず、敦人は数十センチの距離をぐっと詰めた。身を乗り出して伏し目がちに顔を近づけてくる敦人の瞼のカーブがくっきりと際立っているのを見ながら、遥希はやっと理解した。さっきの言葉は『キスしてみる?』ってことだったと。
自分の心臓がはっきり脈を打っているのを他人事のように感じながら目を閉じた。
遠慮がちに重なる唇。初めてのキスはただ乾いた皮膚と皮膚が僅かに触れただけだった。なのに、身体の奥がきゅうと締め付けられた。あっさりと離れたのが物足りなくて顎を少し突き出すと、すぐにもう一度来た。その感触だけに集中する。
何も見ずにいると溢れる気持ちの出口がなくなりそうで、遥希は目を開いた。
お互い鼻先が触れるくらいの距離に直り、困ったような顔をした敦人がまたそっとキスをした。それだけだった。
敦人にとっては友達同士でふざけてしたキスかもしれない。でも一度手に入れたものは、もう手放せない。どんどん欲が深くなってゆく。何度でもしたい、触れたい、貪って、耽りたい、めちゃくちゃにして暴きたい。暴れ出しそうな身体を理性という曖昧なもので無理やり押さえ込んで、遥希は視線を下げた。
目の前にはくっきりした敦人の喉仏が見える。
「ごめん、平気?」
ごめん、って何? 平気って何?、と少し意地悪な気持ちになって顔を上げると、敦人が落ち着かなさそうに目を瞬かせていた。
「大丈夫。敦人は?」
口にした後で気が付いた。たかがキスしたくらいでお互い随分と間の抜けた質問だ。そんな風に冷静でいたのは遥希だけだったようだ。敦人は昂った気持ちを落ち着けるように大げさに深呼吸した後、両手で顔を隠した。
「俺は、大丈夫じゃない……あー、びびったわ! 初めてキスした。」
「初めてなの?」
「うん。うん? あれ? そういやこの前したのは......」
「この前、キスしたんだ。」
うっかり口を滑らせてしまった敦人は、しまったという顔をして遥希を見た。苦い表情で真っ直ぐに自分を見る遥希に、敦人は一番まずいタイミングで一番言ってはいけないことを口走ったと自覚して慌てた。
「あ、の。夏にバイト、イベントのバイトしたんだけど、一人暮らしのお金ためるためにさ。そのバイトが終わった後に全員で打ち上げに行って、で、その時……した、いやされたというか。なんか、俺言い訳ばっかやな。ごめん......」
取り繕うとすればするほど焦ってしまい、モゴモゴと誤魔化すように語尾が小さくなってゆく。その様子に遥希の気分はますます落ち込んでいった。
なんだ、結局そういうことじゃないか。女の子と仲良くやっているんなら、何もこんな風に自分を揶揄う必要なんてないのに。
傷は浅い方がいい、変な期待なんかしたくないし、今ならふざけたんだろ、冗談だろ、笑えよ、で済ませられる。
「別に謝らなくても……その子、敦人が好きだったんやろ?」
遥希の声はやけに冷たく敦人の耳に響いた。間違ったものを口にして吐き出そうとするような表情は、さっきまで布団の中でじゃれ合った親密な空気を打ち消そうとしているようですらだった。
「違う、違うと思う。バイトでちょっと話しただけやし、もう連絡しいへんって決めたから。」
実はその後も何度か遊びに行こうと誘われていた。『みんなで』と言われて行ってみたら、来たのは彼女ともう一組のカップルだけ。遊ぶのはそれなりに楽しかったけれど、それ以上の気持ちは持てなかったのだ。今目の前にいる幼馴染に対して抱くような、甘やかしたり甘えたいと言う親密な感情も性的な欲求も湧いてこなかったのだ。
硬い表情の遥希の顔に敦人の指先が触れて、こめかみにかかる前髪を優しくよける。その感触に縋り付きそうになるのを押しとどめ、遥希は身体を回して敦人に背を向けていい捨てた。
「多少でも好意がなきゃキスなんてせんやろ。」
そう言いながら、じゃあ自分たちのキスは何だったんだろう、と遥希は思う。何であって欲しいのだろう、と。突然女の子とのキスの話をする敦人の気持ちは全く理解できなかった。
いつもの遥希らしくない。やけに突っかかってくるし、拗ねたような声色だった。それはつまりどういうことなんだろうかと少し考え、敦人は急に嬉しそうに口角を上げた。
「あのさ、つまりそれって今のキスもそう考えていいの? ハルには、俺とキスしてもいいくらいの好意があったってことだよな?」
「その女の子にキスされた時、敦人はキスされてもいいくらいの好意をその子にもってたってことだよね。」
にべもない言葉に、敦人も流石にムッとした。
「お前さ、そういうのずるい。」
「ずるくない、そっちが最初に言ったことだろ。」
「じゃあ謝るからこっち向いてよ。」
応えることができなかった。敦人が謝らなきゃならないことなんて何もない。自分が何を言ってるのか自覚して恥ずかしさでいっぱいになった。敦人の顔を見たらきっと全部バレてしまう。
真剣に悩んでいる遥希の脇腹に、突然指先が遊んだ。
「なー! 拗ねてないでこっち向けよー!」
「ひ、ずるい! やめろって! ばか! ガキんちょかよ!」
擽ったさに何度手を除けても、遥希の指をかわしながら敦人はしつこく擽ってきた。脚をばたつかせているうちに上に着ていたトレーナーが捲れて、ようやく温まった敦人の指が直接腹に触れてくる。擽ったさよりもうごめく指にこれまで隠してきたものを導き出されるのが怖くて強く手を掴んだら内側から指先を絡め取られた。
背中越しに身体が近づいてくる。敦人の膝が遥希の腿裏に当たり、ハッとしたように離れる。
整えようとしても遥希の荒れた息はおさまらなかった。耳奥で響く心臓の音がうるさくて頭がクラクラする。そんな気持ちを知ってか知らずか、敦人が後ろでゆっくりと息を吸う音が聞こえた。
「ハル、ええと、遥希さん。」
急に改まった口調になり、何を言うのか全く想定できずに遥希は身構えた。
「そんな固まらんといて……いや俺がさ、今キスしたせいでちょいテンパっていらんこと言っちゃったんですが、テンパったのはつまり嫌だったとかそういう訳じゃなくて、むしろ、あの。」
ぐるぐると所在なく歩き回るような言い方には、どことなく遥希の出方を伺うような響きがあった。分かってる、六年越しの付き合いだ。意固地になった時の遥希の扱いはよく分かっていた。
「つまり、ハルはどういうつもりなんかなーって……」
それから、敦人の生真面目な手が遥希の手を捕まえたまま、脇腹から移動して遠慮がちに腰骨の上に触れた。
しまい込んでいた欲望を理性で押さえていたのに、その感触が遥希の中のすべてをひっくり返してくる。
「な、ハル……」
背中に触れる身体、耳元にかかる息、低い声、あからさまに誘いかけてくる。
「なにが言いたいんだよ。」
「今度は、ハルからしてほしい。」
腰にかかる手が腹を這い身体に巻き付いてゆく。微かに後ろに引っ張られ、こっちを向けと促してくる。それに逆らうことなく振り向いた遥希が、敦人の首に手を添えて唇を塞いだ。躊躇いはなかった。
もう一度、今度は身体を起こして上から覆いかぶさるようにキスをする。遥希だって初めてだった。だから、したいように敦人と唇を重ねた。柔く吸い、ずらしてまた重ね、唇同士で捏ねるように食み、緩んだ隙間に自分の隙間を合わせ、ただ敦人のことだけを考えて没入してゆく。
舌を絡め、お互いに熱くなった身体を求めて服を引き剥がしあった。膝を曲げた敦人の足首から下着を引き抜くと、次は身体を支配したくなる。
掌で太腿の厚い筋肉をなぞってゆけば、重ねた唇の隙間からくぐもった熱い息が漏れ始める。湿りけを帯びた呼吸に合わせて積み上げられてゆく官能が強い占有欲を呼び起こす。
行き場の分からない二人の手が身体をかき抱き合う。もうゼロ距離なのに、まだ近づき足りなかった。
腹の間で屹立が蜜を垂らしながら睦み合い、熱量を高めてゆく。擦れあうたびにもっと刺激が欲しいと切なく脈動する。なのにそんな中で急に敦人が覆いかぶさっていた遥希の肩を押して身体の間に隙間を作った。
突然の拒絶に驚いて遥希は上半身を起こした。
(やっぱりいざとなるとダメなのかな。)
遥希は冷たい部屋の空気に身震いして毛布を肩に引き上げ、もう一度敦人の横に寝転んだ。
落ち着いて、相手を責めないこと。仕方ないんだから。生理的に嫌われたらもう友達にもなれないんだから。
「やっぱ、嫌?」
今止めるなら、もういっそ殺してほしい。強引に続ける? いやダメだ。違う、最初からキスなんてしなけりゃよかったんだ、泊まりに来なきゃよかったんだ。
葛藤する気持ちを押し殺しているうちに自分がどんな表情にしているのか気づいていなかった。
「違う、嫌じゃないからそんな怖い顔すんなよ。あの、今更やけど、ハルが好きやけど俺したことないから……続けたいは続けたいんやけど。」
(したことないから? 続けた……?)
「どうすればいい? ググって……っ!」
また訳のわからないことを言い出しそうな気配を感じ、遥希はキスして敦人を黙らせた。優しく上唇を吸った。さっきと違い湿った唇同士がなごり惜しむようにゆっくりと離れてゆく。
「敦人、いちいち心臓に悪すぎる。殺す気か?」
「……完全殺人やな。」
「も、そういうのいらんわ。」
呆れた様子の遥希がゴツンと音がしそうな勢いで頭突きして、そのまま鼻と鼻をくっつけた。
「僕も、好きや。」
「ありがとう、で、とりあえず今は出したい。ヤバイ、苦しい、入れたい、出したい。って、あれ、どっちがどうする?」
「ばか敦人、もう黙れよ……」
+
浅いまどろみの中、記憶と夢がごちゃ混ぜになって身体を包んでいた。
限界だと言っていた敦人を口でいかせて、それから敦人の太腿を使って自分も満足したのだった。いや、素股をしたのは自分だったっけ? お互い我慢しなくてもいいとわかった瞬間、気持ちが満たされて……。
(すごい幸福感……)
だから遥希は自分に、これは夢だからと言い聞かせながらゆっくりと意識を浮上させたのだ。
脚を動かすと乾いた精液が皮膚を引っ張り、ああ、やっぱり夢じゃなかったのかと遥希は人ごとのように考えた。
背中にあたる感覚が家のベッドと違う。狭い布団の端っこで腕をはみ出させながら寝ていた。寝相が悪くて掛け布団を引っ張ってる敦人をしばらく見ていると、目を覚まして薄目を開けた。
「おはよう。」
「ん、起きとったんか。」
鷹揚にあくびしながら敦人がしっかりと目を開けた。やけに白っぽい朝の光の中で同じ布団に入っていると眩しさに戸惑ってしまう。
「あー」とも「うー」ともつかない声を出して眼を瞬かせていた敦人が、腕を伸ばしてスマホを取った。難しい顔をしながら画面に指を走らせて唸っている。
「今日用事あった? 僕そろそろ帰るわ。」
布団の外に失敗作みたいに丸められた下着を見つけ、遥希は足指で引っ掛けて引き寄せた。
「あかん、一緒にドラッグストアいこ。速攻行ってこよ。後で俺が雑炊作るから、一緒にくおう。」
「朝一で何買うの?腹減るから行く前に食べようよ。」
「ローションとゴム、なかったら見つかるまではしごする。見つかるまで帰りませーん。」
「なんだよそのやる気。」
あきれ顔した遥希の頬が徐々に赤くなってゆくのを見て敦人は楽しそうに笑った。
「分かってるくせに。俺大人の階段上りたいんやけど。ハルと一緒に。」
無邪気に言ってのける敦人の笑顔を目に焼き付けて遥希は立ち上がる。
「シャワー借りる。」
「おう。」
敦人は脱ぎ散らかした二人分のトレーナーを布団の下から引き出している。ああ、この鼻歌なんだっけ。
「なあ。」
バスルームの扉を開けたまま遥希が顔を出す。
「何?」
「僕もやり方がよく分からんから、調べといて。ほいでさ、まあ、どっちでもいいけど両方試してみたくはある。」
それだけ言って急いでドアを閉めた。トレーナーから頭を出した敦人が、扉の向こうでどんな表情をしているのか、見なくたって簡単に想像できる。
いつも通り笑ってるはずだ。
中学の時も、高校の時も、サッカー見に行った時も、球技大会もテスト勉強した時も。敦人は遥希に笑いかけてくれていた。
その笑顔を思い浮かべて遥希は「敵わないな。」と小さな声で言った。
完
1
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

平凡なSubの俺はスパダリDomに愛されて幸せです
おもち
BL
スパダリDom(いつもの)× 平凡Sub(いつもの)
BDSM要素はほぼ無し。
甘やかすのが好きなDomが好きなので、安定にイチャイチャ溺愛しています。
順次スケベパートも追加していきます


家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!
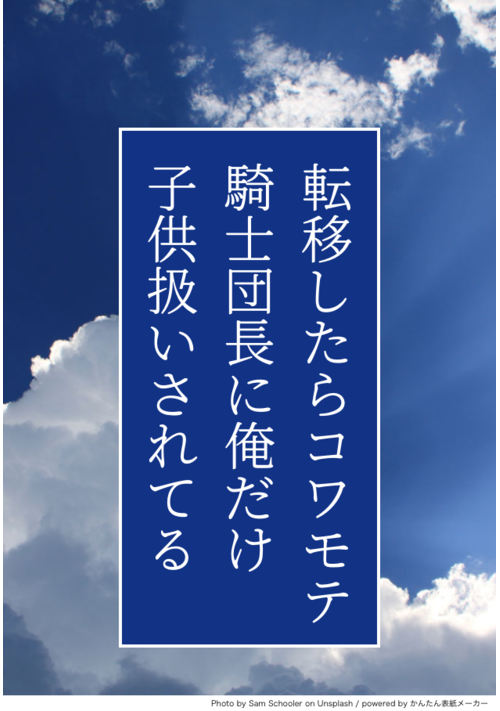
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。


【BL】国民的アイドルグループ内でBLなんて勘弁してください。
白猫
BL
国民的アイドルグループ【kasis】のメンバーである、片桐悠真(18)は悩んでいた。
最近どうも自分がおかしい。まさに悪い夢のようだ。ノーマルだったはずのこの自分が。
(同じグループにいる王子様系アイドルに恋をしてしまったかもしれないなんて……!)
(勘違いだよな? そうに決まってる!)
気のせいであることを確認しようとすればするほどドツボにハマっていき……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















