25 / 37
第四章
【3】 闇は嗤い哭く 1
しおりを挟む
まるで高いところから落ちるような感覚にビクリとして、あたしは目を覚ました。
あたりは暗い。
天井がある。背中の下が柔らかい。どこかの家の中だ。
考えてから、ここが病院の一室だと思い出した。
暑くなんかないのに、汗をぐっしょりかいていた。
荒く息を繰り返す。
部屋の中は決して狭くはないが、息が詰まる。
闇が迫ってくるようでずっしりとしたカーテンも重苦しい。
あたしは大きくひとつ深呼吸をしてから、ベッドから起き上がった。ポンチョのフードを深くかぶり、枕元に置いていた眼鏡をかける。
パドルを持って部屋の外に出た。廊下は静かで、誰もいない。やっぱり見張りすらもいない。
またひとつ深呼吸をする。
夜の少し冴えた空気が肺に入ってきて、昂ぶっていた気持ちが少しだけ引いていく気がする。
ロビーに出ると、話し声が聞こえてきた。
だけど人影はなく、ボソボソとくぐもって何を言っているか分からない。
息を潜めて、耳をすませる。多分、地下へ続く階段の先からだ。
身をかがめて降りていくと、下にはカフェがあって、ガラス張りのドアの向こうには、「福大前 地下鉄」の表示が見える。
ここから地下鉄につながっているのか。
「だから、どうしてあんたの言うことを聞かないといけないの? 何かと交換してくれるわけ?」
杏樹の声が奥から聞こえた。
このまま進むと気付かれるかも知れない。あたしは階段の途中に身をかがめて、足を止めた。
「あいつは俺の獲物だって言っただろ」
イラだち気味の声が応えた。
ケヤキ通りで会ったあの吸血鬼の少年の声だった。
杏樹は、博登《ひろと》と呼んでいたか。
「ここはわたしの管轄よ。もうわたしが招き入れたんだから、わたしのものよ」
大げさなため息が落ちる。
「どうしてそこまで構う」
「さあね。あんたが怒るのがおもしろいのかも」
「いい加減にしておいた方が身のためだぞ」
杏樹の笑い声があがった。
「どうするって言うのよ。同士討ちでもするつもり? あたしたち、ただでさえ人間に比べて数が少ない上に、あのヤクザ達にだいぶやられちゃったのに、もっと減らしてどうするの」
黙れ、と少年が声を抑えて言った。
あどけない声がどす黒い熱をもって、闇に低く響く。
「好きにしろ。忠告はした」
「あはは、忠告ね。ありがと」
杏樹の楽しげな笑い声が近づいてくる。
あたしは身をかがめたまま、音をたてないように階段をあがった。
隠れていると、地下から小さな人影が上がってくる。
少女はロビーに姿を見せると、そのまま階段を上がっていく。ピタピタと裸足の音がロビーに響いた。
あたしは何気なく、隠れながらその後を追った。
隣の建物とつながった連絡通路の途中に、少女は立ち尽くしていた。
カーテンを開け放して、雲の切れ間から見える星空を眺めている。
曇天は時折切れ間を見せて、月の光が鋭く差し込むが、その時だけやたらと明るかった。
今は大きなふちの帽子もかぶっていない。フリルでいっぱいの洋服も着ていない。
ティーシャツに身軽なスウェットだけをまとった杏樹は、折れそうな細く長い手足をした、ただのか弱い少女だった。どこか心細そうな。
少女はふとあたしを見ると、軽く笑った。
「夜討ち? 夜這い?」
明るい声が月明かりの廊下に響く。
あたしのパドルを指さして、明るいテンションで言う。
「あんたそれいつも持ち歩いてるの? 邪魔くさいわねえ。あんまりうろうろされると、みんなが恐がって困るんだけど」
「だったら見張りをたてておけ。ここの人間はあんたに怯えてないようだったけど、人間を飼うような吸血鬼は、やっぱり恐がられているのか」
「いちいちそんなことに人手を割けないのよ。よく知らないひとを警戒するのは当たり前でしょ」
――人間を飼っている。
杏樹はケヤキ通りでそう言っていたし、あたしたちを連れてきたときも否定しなかった。
だけどやっぱり彼らは、飼育する者とされる者には見えない。共存しているように思える。
人間の大人達は、杏樹のことは警戒していなかったが、あたしのことは遠巻きにしていた。当然か。
「あんたどれくらい飲んでないの?」
杏樹は少しの頓着もなく言った。
「なんで飲んでないと思うんだ」
「そんなの顔色を見れば分かるでしょ」
鏡を見ていないから応えられない。
でも自分がひどい顔色をしているのは想像がついた。少し息も苦しい気がする。
あたしを襲ったあのときの吸血鬼みたいになっているに違いない。
「一日200mlあれば数日耐えられるわよ。その間にニワトリの血なんかももらえばもっともつわ。我慢もほどほどにしておかないと、体がもたないわよ」
「分かってる」
「自虐も自罰も結構だけど、死ぬ気がないのならほどほどになさい。飢餓感が人間の比じゃないの分かってるでしょ。そのうち正気を保てなくなって、誰彼構わず襲うようになる。その時犠牲になるのは、一番身近にいる人間よ。あんただけの問題じゃない」
――知ってる。
自分ではどうしようもない飢餓感。
このまま飢えて死にたいと思うのに、勝手に体が生きようとする。紘平に襲いかかりそうになって、それが恐くて恐くてたまらなかった。
吸血鬼に噛まれると死ぬ。
だけど、ごくわずかの人間が、感染して同じようになってしまう。
あたしは紘平を吸血鬼にしてしまうかもしれない。もし紘平も吸血鬼になったら――この不安も心細さも、このどうしようもない孤独からも逃れられる。
どこかそう思う自分がいて、それが恐くて、あたしは逃げてきた。考えるたびに嫌悪感で苦しい。
よそへ行けば、よその知らない人間なら、食料としてみられるのではないかと思った。
杏樹の言葉は、どこか頼りない少女の見た目に反して、厳しい。そしてとても大人びている。
あたしは自分よりも背丈の小さな少女を見て問うた。
「あんたはいつから吸血鬼なんだ」
「十三の時よ」
杏樹はしれっと言った。
あたしは微妙な表情になる。それを見て、杏樹は肩をすくめる。
「はいはい、聞いたのはそれじゃないよね。十年ばかし前からよ」
窓に手を当てて、雲の切れ間を見ながら、少女は言った。
「あの頃、本州で大きい地震があったとかで、人間も吸血鬼もこっちに流れて来たのよ」
「――ああ、確か、そんなことがあったような。あたしのいたところに近い海沿いは大きい町があったから、うちの方にも少し流れてきた」
「その時にやってきた余所者の吸血鬼に、がぶりとやられたわけ」
夜の色に染まった顔で笑う。その表情は、少女の体とアンバランスだ。
「そう、わたしこんなナリだけど、本当は二十三なの。パンデミックだとかで混乱が起き始めた頃、まだほんとに小さい子供だった。そうこうしてるうちに、台風で水害があって、親はわたしをつれてここに逃げ込んで、そのままここにいたの。本当なら安全なはずだったわ。大人達も油断してたのかもね。たくさん襲われて死んだわ。親たちも」
杏樹はあたしを振り返って、意地悪く笑った。
「だからわたし、よそ者は大嫌いなの。吸血鬼も大嫌い。特に、よそからやってきた吸血鬼なんて、最低最悪、心底消えてほしい」
あの、博登とか言う奴につっかかるのはそのせいか。でもどうして――
思ったところで、杏樹は肩をすくめて言った。
「あんたも同じでしょ。わたしと同じで、吸血鬼が大嫌い」
そうだ。あたしは、吸血鬼が憎い。もともと吸血鬼が嫌いだった。そうでない人なんてほとんどいないだろう。好きでこうなった訳じゃない。
吸血鬼が嫌い。だけど自分も同じになってしまった。
だから自分も嫌いだった。
「あの、――史仁《ふみひと》、とかいうのは」
弓を持って馬を繰っていた少年。
彼は人間だろう。人と吸血鬼が共存していると言っても、史仁は人間なのに、まるで吸血鬼側の者のように人間を見張っている。
気がつけばいつも、杏樹を守るように寄り添っていた。
――人間からも、吸血鬼からも。何者からも。
「史仁はここで生まれた。あの子は泣き虫で、わたしの後ろをついて回るような子だった。身近な人達が死んで、わたしが噛まれた時、あの子本当にぐしゃぐしゃに大泣きして大変だった。あの子はそれから変わったの」
「あんたたち、姉弟なのか」
杏樹はあたしを振り返る。おかしそうにくすくすと笑いながら言った。
「姉弟、ね。恋人には見えない?」
――人間と吸血鬼が?
思わず顔をしかめたあたしに、杏樹は声を上げて笑った。また軽やかな声が、人のいない病院に響く。
そして、ぱたりと笑うのをやめた。
「正直ねえ。言いたいことはわかるわよ。嘘よ、別に恋人でも何でもないわ。わたしたち、年は違うけど幼なじみなの」
少女の顔を縁取る藍色の影が、彼女が笑っているのを教えてくれる。だけど、悲哀の色だ。
「吸血鬼は老けないし、怪我もすぐ治っちゃうけど、本当のとこの寿命はまだ全然分かってない。どう考えても体が無理してる状態だもの、明日ころっと死ぬかも知れない。それにあの子はどんどん大人になる。わたしはずっとこのままよ。どうしろっていうのよ。間違えて感染なんかさせたら、後悔してもしきれない」
ただ一緒にいるだけでも、乖離していく。
このウイルスに感染した者は老いていかない。傷がすぐに治る。尋常でない身体能力を持つ。
まるで脳のリミッターがはずれてしまったかのように。それは体に無理を強いているはずだ。
突然ことんと死んでしまうかもしれない。
実際、今までそうやって死んだ者がいたとしても、それがあたしたちの寿命――病なのだから寿命とは言わないのだろうが、それが余命の限界なのだったとしても、本当にそうなのか分からない。
それを研究するような組織はどこにもない。
「……なんで、人間の血なんだ」
あたしは思わずつぶやいだ。
せめて意思をはかれないような、言葉を交わせない他の生き物なら。
こんなに奪い合うようなことにはならなかった。
居場所を失うこともなかった。
「自分の体で生成できないものを外から補ってるんじゃないかって、ここにいた先生が言ってたわ」
急激な回復力のせいか。
それともウイルスに感染して、何かが破壊されいているのか。
分からないけれども。
「あんたはいつからなの。ひよっこちゃん」
「2、30日ぐらい前。新月と満月を一回ずつ見た」
「そう」
杏樹は明るく声をあげた。
「無理して我慢しないことね。どうにもならないんだから」
十年分のあきらめと葛藤を、軽やかに笑った。
あたりは暗い。
天井がある。背中の下が柔らかい。どこかの家の中だ。
考えてから、ここが病院の一室だと思い出した。
暑くなんかないのに、汗をぐっしょりかいていた。
荒く息を繰り返す。
部屋の中は決して狭くはないが、息が詰まる。
闇が迫ってくるようでずっしりとしたカーテンも重苦しい。
あたしは大きくひとつ深呼吸をしてから、ベッドから起き上がった。ポンチョのフードを深くかぶり、枕元に置いていた眼鏡をかける。
パドルを持って部屋の外に出た。廊下は静かで、誰もいない。やっぱり見張りすらもいない。
またひとつ深呼吸をする。
夜の少し冴えた空気が肺に入ってきて、昂ぶっていた気持ちが少しだけ引いていく気がする。
ロビーに出ると、話し声が聞こえてきた。
だけど人影はなく、ボソボソとくぐもって何を言っているか分からない。
息を潜めて、耳をすませる。多分、地下へ続く階段の先からだ。
身をかがめて降りていくと、下にはカフェがあって、ガラス張りのドアの向こうには、「福大前 地下鉄」の表示が見える。
ここから地下鉄につながっているのか。
「だから、どうしてあんたの言うことを聞かないといけないの? 何かと交換してくれるわけ?」
杏樹の声が奥から聞こえた。
このまま進むと気付かれるかも知れない。あたしは階段の途中に身をかがめて、足を止めた。
「あいつは俺の獲物だって言っただろ」
イラだち気味の声が応えた。
ケヤキ通りで会ったあの吸血鬼の少年の声だった。
杏樹は、博登《ひろと》と呼んでいたか。
「ここはわたしの管轄よ。もうわたしが招き入れたんだから、わたしのものよ」
大げさなため息が落ちる。
「どうしてそこまで構う」
「さあね。あんたが怒るのがおもしろいのかも」
「いい加減にしておいた方が身のためだぞ」
杏樹の笑い声があがった。
「どうするって言うのよ。同士討ちでもするつもり? あたしたち、ただでさえ人間に比べて数が少ない上に、あのヤクザ達にだいぶやられちゃったのに、もっと減らしてどうするの」
黙れ、と少年が声を抑えて言った。
あどけない声がどす黒い熱をもって、闇に低く響く。
「好きにしろ。忠告はした」
「あはは、忠告ね。ありがと」
杏樹の楽しげな笑い声が近づいてくる。
あたしは身をかがめたまま、音をたてないように階段をあがった。
隠れていると、地下から小さな人影が上がってくる。
少女はロビーに姿を見せると、そのまま階段を上がっていく。ピタピタと裸足の音がロビーに響いた。
あたしは何気なく、隠れながらその後を追った。
隣の建物とつながった連絡通路の途中に、少女は立ち尽くしていた。
カーテンを開け放して、雲の切れ間から見える星空を眺めている。
曇天は時折切れ間を見せて、月の光が鋭く差し込むが、その時だけやたらと明るかった。
今は大きなふちの帽子もかぶっていない。フリルでいっぱいの洋服も着ていない。
ティーシャツに身軽なスウェットだけをまとった杏樹は、折れそうな細く長い手足をした、ただのか弱い少女だった。どこか心細そうな。
少女はふとあたしを見ると、軽く笑った。
「夜討ち? 夜這い?」
明るい声が月明かりの廊下に響く。
あたしのパドルを指さして、明るいテンションで言う。
「あんたそれいつも持ち歩いてるの? 邪魔くさいわねえ。あんまりうろうろされると、みんなが恐がって困るんだけど」
「だったら見張りをたてておけ。ここの人間はあんたに怯えてないようだったけど、人間を飼うような吸血鬼は、やっぱり恐がられているのか」
「いちいちそんなことに人手を割けないのよ。よく知らないひとを警戒するのは当たり前でしょ」
――人間を飼っている。
杏樹はケヤキ通りでそう言っていたし、あたしたちを連れてきたときも否定しなかった。
だけどやっぱり彼らは、飼育する者とされる者には見えない。共存しているように思える。
人間の大人達は、杏樹のことは警戒していなかったが、あたしのことは遠巻きにしていた。当然か。
「あんたどれくらい飲んでないの?」
杏樹は少しの頓着もなく言った。
「なんで飲んでないと思うんだ」
「そんなの顔色を見れば分かるでしょ」
鏡を見ていないから応えられない。
でも自分がひどい顔色をしているのは想像がついた。少し息も苦しい気がする。
あたしを襲ったあのときの吸血鬼みたいになっているに違いない。
「一日200mlあれば数日耐えられるわよ。その間にニワトリの血なんかももらえばもっともつわ。我慢もほどほどにしておかないと、体がもたないわよ」
「分かってる」
「自虐も自罰も結構だけど、死ぬ気がないのならほどほどになさい。飢餓感が人間の比じゃないの分かってるでしょ。そのうち正気を保てなくなって、誰彼構わず襲うようになる。その時犠牲になるのは、一番身近にいる人間よ。あんただけの問題じゃない」
――知ってる。
自分ではどうしようもない飢餓感。
このまま飢えて死にたいと思うのに、勝手に体が生きようとする。紘平に襲いかかりそうになって、それが恐くて恐くてたまらなかった。
吸血鬼に噛まれると死ぬ。
だけど、ごくわずかの人間が、感染して同じようになってしまう。
あたしは紘平を吸血鬼にしてしまうかもしれない。もし紘平も吸血鬼になったら――この不安も心細さも、このどうしようもない孤独からも逃れられる。
どこかそう思う自分がいて、それが恐くて、あたしは逃げてきた。考えるたびに嫌悪感で苦しい。
よそへ行けば、よその知らない人間なら、食料としてみられるのではないかと思った。
杏樹の言葉は、どこか頼りない少女の見た目に反して、厳しい。そしてとても大人びている。
あたしは自分よりも背丈の小さな少女を見て問うた。
「あんたはいつから吸血鬼なんだ」
「十三の時よ」
杏樹はしれっと言った。
あたしは微妙な表情になる。それを見て、杏樹は肩をすくめる。
「はいはい、聞いたのはそれじゃないよね。十年ばかし前からよ」
窓に手を当てて、雲の切れ間を見ながら、少女は言った。
「あの頃、本州で大きい地震があったとかで、人間も吸血鬼もこっちに流れて来たのよ」
「――ああ、確か、そんなことがあったような。あたしのいたところに近い海沿いは大きい町があったから、うちの方にも少し流れてきた」
「その時にやってきた余所者の吸血鬼に、がぶりとやられたわけ」
夜の色に染まった顔で笑う。その表情は、少女の体とアンバランスだ。
「そう、わたしこんなナリだけど、本当は二十三なの。パンデミックだとかで混乱が起き始めた頃、まだほんとに小さい子供だった。そうこうしてるうちに、台風で水害があって、親はわたしをつれてここに逃げ込んで、そのままここにいたの。本当なら安全なはずだったわ。大人達も油断してたのかもね。たくさん襲われて死んだわ。親たちも」
杏樹はあたしを振り返って、意地悪く笑った。
「だからわたし、よそ者は大嫌いなの。吸血鬼も大嫌い。特に、よそからやってきた吸血鬼なんて、最低最悪、心底消えてほしい」
あの、博登とか言う奴につっかかるのはそのせいか。でもどうして――
思ったところで、杏樹は肩をすくめて言った。
「あんたも同じでしょ。わたしと同じで、吸血鬼が大嫌い」
そうだ。あたしは、吸血鬼が憎い。もともと吸血鬼が嫌いだった。そうでない人なんてほとんどいないだろう。好きでこうなった訳じゃない。
吸血鬼が嫌い。だけど自分も同じになってしまった。
だから自分も嫌いだった。
「あの、――史仁《ふみひと》、とかいうのは」
弓を持って馬を繰っていた少年。
彼は人間だろう。人と吸血鬼が共存していると言っても、史仁は人間なのに、まるで吸血鬼側の者のように人間を見張っている。
気がつけばいつも、杏樹を守るように寄り添っていた。
――人間からも、吸血鬼からも。何者からも。
「史仁はここで生まれた。あの子は泣き虫で、わたしの後ろをついて回るような子だった。身近な人達が死んで、わたしが噛まれた時、あの子本当にぐしゃぐしゃに大泣きして大変だった。あの子はそれから変わったの」
「あんたたち、姉弟なのか」
杏樹はあたしを振り返る。おかしそうにくすくすと笑いながら言った。
「姉弟、ね。恋人には見えない?」
――人間と吸血鬼が?
思わず顔をしかめたあたしに、杏樹は声を上げて笑った。また軽やかな声が、人のいない病院に響く。
そして、ぱたりと笑うのをやめた。
「正直ねえ。言いたいことはわかるわよ。嘘よ、別に恋人でも何でもないわ。わたしたち、年は違うけど幼なじみなの」
少女の顔を縁取る藍色の影が、彼女が笑っているのを教えてくれる。だけど、悲哀の色だ。
「吸血鬼は老けないし、怪我もすぐ治っちゃうけど、本当のとこの寿命はまだ全然分かってない。どう考えても体が無理してる状態だもの、明日ころっと死ぬかも知れない。それにあの子はどんどん大人になる。わたしはずっとこのままよ。どうしろっていうのよ。間違えて感染なんかさせたら、後悔してもしきれない」
ただ一緒にいるだけでも、乖離していく。
このウイルスに感染した者は老いていかない。傷がすぐに治る。尋常でない身体能力を持つ。
まるで脳のリミッターがはずれてしまったかのように。それは体に無理を強いているはずだ。
突然ことんと死んでしまうかもしれない。
実際、今までそうやって死んだ者がいたとしても、それがあたしたちの寿命――病なのだから寿命とは言わないのだろうが、それが余命の限界なのだったとしても、本当にそうなのか分からない。
それを研究するような組織はどこにもない。
「……なんで、人間の血なんだ」
あたしは思わずつぶやいだ。
せめて意思をはかれないような、言葉を交わせない他の生き物なら。
こんなに奪い合うようなことにはならなかった。
居場所を失うこともなかった。
「自分の体で生成できないものを外から補ってるんじゃないかって、ここにいた先生が言ってたわ」
急激な回復力のせいか。
それともウイルスに感染して、何かが破壊されいているのか。
分からないけれども。
「あんたはいつからなの。ひよっこちゃん」
「2、30日ぐらい前。新月と満月を一回ずつ見た」
「そう」
杏樹は明るく声をあげた。
「無理して我慢しないことね。どうにもならないんだから」
十年分のあきらめと葛藤を、軽やかに笑った。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

喜劇・魔切の渡し
多谷昇太
大衆娯楽
これは演劇の舞台用に書いたシナリオです。時は現代で場所はあの「矢切の渡し」で有名な葛飾・柴又となります。ヒロインは和子。チャキチャキの江戸っ子娘で、某商事会社のOLです。一方で和子はお米という名の年配の女性が起こした某新興宗教にかぶれていてその教団の熱心な信者でもあります。50年配の父・良夫と母・為子がおり和子はその一人娘です。教団の教え通りにまっすぐ生きようと常日頃から努力しているのですが、何しろ江戸っ子なものですから自分を云うのに「あちし」とか云い、どうかすると「べらんめえ」調子までもが出てしまいます。ところで、いきなりの設定で恐縮ですがこの正しいことに生一本な和子を何とか鬱屈させよう、悪の道に誘い込もうとする〝悪魔〟がなぜか登場致します。和子のような純な魂は悪魔にとっては非常に垂涎を誘われるようで、色々な仕掛けをしては何とか悪の道に誘おうと躍起になる分けです。ところが…です。この悪魔を常日頃から監視し、もし和子のような善なる、光指向の人間を悪魔がたぶらかそうとするならば、その事あるごとに〝天使〟が現れてこれを邪魔(邪天?)致します。天使、悪魔とも年齢は4、50ぐらいですがなぜか悪魔が都会風で、天使はかっぺ丸出しの田舎者という設定となります。あ、そうだ。申し遅れましたがこれは「喜劇」です。随所に笑いを誘うような趣向を凝らしており、お楽しみいただけると思いますが、しかし作者の指向としましては単なる喜劇に留まらず、現代社会における諸々の問題点とシビアなる諸相をそこに込めて、これを弾劾し、正してみようと、大それたことを考えてもいるのです。さあ、それでは「喜劇・魔切の渡し」をお楽しみください。

【完結】20-1(ナインティーン)
木村竜史
ライト文芸
そう遠くない未来。
巨大な隕石が地球に落ちることが確定した世界に二十歳を迎えることなく地球と運命を共にすることになった少年少女達の最後の日々。
諦観と願望と憤怒と愛情を抱えた彼らは、最後の瞬間に何を成し、何を思うのか。
「俺は」「私は」「僕は」「あたし」は、大人になれずに死んでいく。
『20-1』それは、決して大人になることのない、子供達の叫び声。

学園のアイドルに、俺の部屋のギャル地縛霊がちょっかいを出すから話がややこしくなる。
たかなしポン太
青春
【第1回ノベルピアWEB小説コンテスト中間選考通過作品】
『み、見えるの?』
「見えるかと言われると……ギリ見えない……」
『ふぇっ? ちょっ、ちょっと! どこ見てんのよ!』
◆◆◆
仏教系学園の高校に通う霊能者、尚也。
劣悪な環境での寮生活を1年間終えたあと、2年生から念願のアパート暮らしを始めることになった。
ところが入居予定のアパートの部屋に行ってみると……そこにはセーラー服を着たギャル地縛霊、りんが住み着いていた。
後悔の念が強すぎて、この世に魂が残ってしまったりん。
尚也はそんなりんを無事に成仏させるため、りんと共同生活をすることを決意する。
また新学期の学校では、尚也は学園のアイドルこと花宮琴葉と同じクラスで席も近くなった。
尚也は1年生の時、たまたま琴葉が困っていた時に助けてあげたことがあるのだが……
霊能者の尚也、ギャル地縛霊のりん、学園のアイドル琴葉。
3人とその仲間たちが繰り広げる、ちょっと不思議な日常。
愉快で甘くて、ちょっと切ない、ライトファンタジーなラブコメディー!
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

如月さんは なびかない。~クラスで一番の美少女に、何故か告白された件~
八木崎(やぎさき)
恋愛
「ねぇ……私と、付き合って」
ある日、クラスで一番可愛い女子生徒である如月心奏に唐突に告白をされ、彼女と付き合う事になった同じクラスの平凡な高校生男子、立花蓮。
蓮は初めて出来た彼女の存在に浮かれる―――なんて事は無く、心奏から思いも寄らない頼み事をされて、それを受ける事になるのであった。
これは不器用で未熟な2人が成長をしていく物語である。彼ら彼女らの歩む物語を是非ともご覧ください。
一緒にいたい、でも近づきたくない―――臆病で内向的な少年と、偏屈で変わり者な少女との恋愛模様を描く、そんな青春物語です。
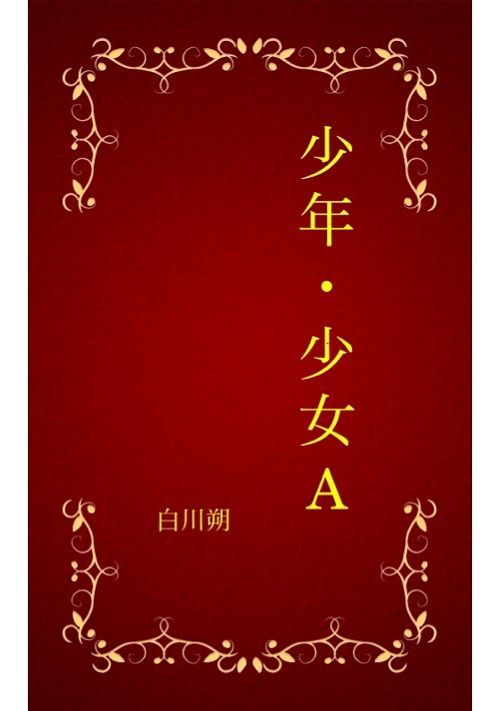

つくも神と腐れオタク
荒雲ニンザ
大衆娯楽
鈴は爆誕して16年の腐れオタク少女。
隣に住む幼馴染みの慧ちゃんと一緒に、人生初のコミケに挑むことに。
だが力が足りない彼女たちは、文明の利器『ぱしょこん』を持っていなかったのだ。
そんな折、父親の仕事先の同僚がドイツに帰ることになり、行き場がなくなった自作パソコンを譲り受けたとかいう超絶ラッキーが舞い降りる!
我は力を手に入れた!とバリにウキウキで電源を入れた鈴と慧の前に、明治時代の大学生のような格好をしたホログラム?が現れた。
機械に疎い2人はAIだと思ったが、『奴』は違う。
「あのぉ……小生、つくも神なる者でして……」
同人誌の発祥は明治時代。
ことあるごとにつくも神から発生する厄難に巻き込まれながら、何とかオタ活に励んで冬コミを目指す若者たちのほのぼのギャグコメディだよ。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















