68 / 76
68. 白はしぶとい
しおりを挟む「茉里、顔色悪いけど大丈夫?」
親友との、週末のランチ。いつもの時間に、いつものお店。
それなのに安心できない、いつもと違う私。
心配そうに私の顔を覗き込む彩可に、私は笑顔で「大丈夫」と告げた。無理やりに作った笑顔だということを、彼女はすぐに気づいただろう。けれもも、それを振り切るように私は別の話題に話を始めた。
あの衝撃の事実を知ってから約二週間が過ぎた。未だに毎日、そのことについて考え続けているけれども、答えは出ていない。そもそも、答えが必要な問題なのかもわからないけれども。
彩可には、まだ何も話していない。私の様子がおかしいことには気づいているようだけれども、決して踏み込んでくることはない。
「最近、仕事の方は? 順調?」
クルクルとパスタをフォークに巻きつけながら、彩可が訊ねる。
「うん。ちょっと前に、初めて私がメインでお客さんにプレゼンした案件があったんだけどね、プレゼンの数日後に、正式な発注のオファーがあったんだ!」
「すごいじゃん! 良かったね!」
満面の笑顔で喜んでくれる親友の様子が嬉しくて、私も自然と笑顔になる。
「菊地さんにも褒めてもらったんじゃない? 何か、ご褒美でも貰った?」
無邪気な彩可の言葉に、一瞬で胃がズドンと重くなった。何も知らない彩可は、私と菊地さんの関係が順調だと思っているんだから、仕方がない。
どうにか誤魔化そうと、私は表情を変えないようにと必死に頬の筋肉に力を込めながら、手元のフォークに視線を落とした。
「特になにかしてもらった訳じゃないけど、すごく喜んでくれたよ」
幸いなことに、この言葉は嘘じゃなかった。
クライアントからの正式発注のメールに気づいたのは、私が一番最初だった。静かに、目の前の文章が見間違いではないことを理解しようとしていたとき、笹山さんが喜びの声を上げた。その瞬間、私は笹山さんに視線を向けると、それをすぐに隣にいた菊池さんへと移してしまった。
たぶん、同時だったんだと思う。驚いた表情のまま、私たちは見つめ合っていた。
驚きに見開かれていた菊地さんの瞳が、何かを理解したかのようにだんだんと喜びの感情で満たされていくのを、私はただ見つめていた。ゆっくりと上がっていく口角に、喜びを噛み締めるようにキュッと結ばれた唇。彼の表情を見ているうちに、自然と私の表情も緩んでいった。
「中谷さん、笹山さん、受注おめでとう。頑張ってくれて、ありがとうございます」
そんな言葉を課長からもらっている間も、菊地さんは誇らしげな笑顔で静かな拍手を贈ってくれた。その純粋な喜びの表現に、心が温まった。
今すぐ、抱きつきたい。
優しく、強く、抱きしめてほしい。
いつもみたいに、頭を撫でて欲しい。
心のなかに浮かんだ欲求に気づいたとき、私はハッとした。菊地さんに裏切られたはずなのに、そんな欲望を抱いた自分が自分でも信じられなかった。
慌てて目を逸らすと、視界の隅で菊地さんが残念そうに笑ったのが見えた気がした。
「ふーん、そうなんだ。私、菊地さんはサプライズが好き、みたいなイメージを勝手に持ってたかも」
彩可の言葉に、私は現実へと意識を引き戻した。器用にフォークへパスタとイカを巻き付ける親友の手先に感心しながら、私は小さく頷いた。
「確かに、相手のために何かしてあげたいって気持ちは、強い人だね」
そう答えながら、今まで菊地さんが私のためにしてくれた数々の優しさがよみがえってくる。
単純な女かもしれないけれども、どんな裏があっても、あの優しさが本心からくるものだったらいいな、と心から願うようになった。自分の中で美化しているだけなのかもしれないけれども、あの日々は私の中で大切な日常だった。
クスリ、と笑う声が聞こえて、顔を上げた。
なんだかニヤニヤした表情で、彩可が私を見つめている。
「何?」
なんだか気恥しくて、慌ててフォークをパスタの群れに突っ込んだ。
「んー? いい表情してるなって。茉里がそんな風に穏やかな笑顔を見せることって、そんなに多くなかったからさ。菊地さんと一緒にいると、茉里は幸せになれるんだなーって、噛み締めてたところ」
悪気のない親友の言葉に、胸がチクリと痛んだ。
そう、私は幸せだった。ただ、それをすべて壊された今、残るのは虚しさばかりだ。
「結婚式で二人に会えるの、楽しみだな」
何気ない彩可の一言で、私は大切なことを忘れていたのに気づいた。そういえば、彩可の結婚式には菊地さんと一緒に行くことになっていたんだった。
どうしよう?
やはり、彩可に本当のことを伝えるべきだろうか?
でも、この流れではなんだか伝えづらい。
「私は、彩可と亘くんの幸せな姿を見られるのが楽しみだな」
私はとっさにそうごまかして、最近ではすっかりと慣れてしまったニセモノの笑顔を顔に張り付けた。心の痛みを、徹底的に無視して。
夕方になり、彩可と別れてひとりで帰路につく。最寄駅から自宅への道を歩きながら、彩可の結婚式のことを考える。
結婚式の間だけ、まだ付き合っているふりをしてくれないか、と頼めば、きっと菊地さんは二つ返事で了承してくれるだろう。でも、そんなニセモノの関係で親友の結婚式に出るのは、なんだか間違っている気がした。
はぁ、と大きなため息をもらせば、不意に背後からカラカラとした笑い声が聞こえた。振り返らなくても、それが誰だかわかった。この独特の笑い声の持ち主は、1人しかいない。
「随分と大きなため息だけど、悩み事?」
後ろから聞こえる声を無視して、私は足を早める。
「え、ちょっと、無視はないでしょ、無視は」
慌てた声と共に、アスファルトを蹴って走り始める音が聞こえたかと思えば、目の前に皓人さんの顔が現れた。驚いて足を止めれば、満足げににんまりと微笑む。
皓人さんが靴の件を謝りに来た日を皮切りに、なぜだか皓人さんは度々、私の家の周辺で待ち伏せをするようになった。何度突き放しても、どれだけ冷たい態度を取っても、数日以内に皓人さんは舞い戻ってくる。
「暇なの?」
そう問いかければ、むっとしたように唇を尖らせてこちらを見返してくる。
「今日の茉里ちゃんは、意地悪だね」
分かりやすく拗ねた表情を作る彼の姿に、思わず笑いが漏れそうになるのをぐっと我慢する。一瞬でも隙を見せてしまえば、負け、な気がする。
「意地悪されるのが嫌なら、帰ってくれて構わないけど。もう、戻ってこなくても私は気にしないし」
つっけんどんにそう答えて、皓人さんの隣をすり抜けようとする。けれども、私の腕はいとも簡単に彼の手につかまってしまう。
このやりとりを、もう何度繰り返しただろうか。意味がないと分かっていても同じことを繰り返してしまう私は、本当にバカだ。
「そんな冷たいこと言わないでよ。何かむしゃくしゃしてるなら、気晴らしにパーっと肉でも食べに行く? あ、焼肉おごろうか? お高めのおいしい焼き肉屋さん知ってるんだ」
コテン、と小首を傾げて訊ねる姿は、もう見慣れてしまった。近頃は苛立ちすら感じていたその仕草に、近頃は再びときめきを感じるようになってしまった。絶対に態度にも表情にも出さないけれども、皓人さんはきっとそのことに気づいている。そういうところが、本当に憎たらしい。
「行かない。お一人でどうぞ。それか、菊地さんと行けば?」
ぶっきらぼうに言い放った瞬間、皓人さんの瞳が寂しそうに光った。
どうやら、あの一軒以来、菊地さんと皓人さんの関係はすっかり拗れてしまったらしい。菊地さんの名前を出す度に、皓人さんを包む空気が一気に負のものへと変化する。彼の言動から察するに、菊地さんが皓人さんに対しての怒りを抱き続けているようだ。
「玄也、今日は元気そうだった?」
捨てられた子犬のような表情と声音で、皓人さんは訊ねてくる。
ついつい頭を撫でたくなる衝動を、必死に抑える。こういう母性本能をくすぐるところも、本当に憎たらしい。
「今日は土曜日だから仕事休み。会社に行ってないんだから、菊地さんの様子なんて知らないよ」
そう答えつつも、意識はすぐに菊地さんの方へと向いてしまう。
会社では、なるべく変わらずに接するようにしている。まだ少しぎこちないし、以前のような親しい空気は出し切れていないと思う。けれども、私たちの間に何かあったのでは、と疑う人は今のところいなさそうだ。少なくとも、一番一緒に過ごす時間の多い笹山さんは気づいていない。それに、課長も。あとは、なんだかんだで仁科さんがフォローしてくれてもいて、どうにか成り立っている。
それでも、菊地さんは以前のような活気を失っている。疲れているようにも見えるし、毎日寂しげだ。会社の人たちは、多忙すぎて疲れていると思っているようだったが、その原因に無関係ではない私としては、複雑な心境だ。
「そんなに気になるなら、謝って許してもらえば?」
私の言葉に、皓人さんはすぐに首を振った。
「今の状況じゃあ、何を言っても無駄だよ。ねえ茉里ちゃん、本当に玄也と話しをするつもりはないの?」
皓人さんの問いかけに、私は下唇をぎゅっと噛み締めた。
いったい何度、この質問をされただろうか。
断る度に、なんだか罪悪感のようなものを感じてしまって、良い気分ではない。私は騙された側で、被害者なはずなのに。
「私の気持ちは変わらないから。じゃあね」
別れの言葉を述べて皓人さんの手を振り払うなり、私はそそくさと建物の中へと足を早めた。背中に感じる皓人さんの視線は、とにかく無視することにした。
しつこい皓人さんとは反対に、菊地さんは何も言ってこない。
私の意思を尊重してくれているのだろう。あれ以来、話しをしたいとは一度も言ってこない。それを時折、寂しいと思ってしまう馬鹿な私がいる。そんな風に思ってしまうのは、あきらめずに何度も私の前に現れる皓人さんのせいだ。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

CODE:HEXA
青出 風太
キャラ文芸
舞台は近未来の日本。
AI技術の発展によってAIを搭載したロボットの社会進出が進む中、発展の陰に隠された事故は多くの孤児を生んでいた。
孤児である主人公の吹雪六花はAIの暴走を阻止する組織の一員として暗躍する。
※「小説家になろう」「カクヨム」の方にも投稿しています。
※毎週金曜日の投稿を予定しています。変更の可能性があります。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
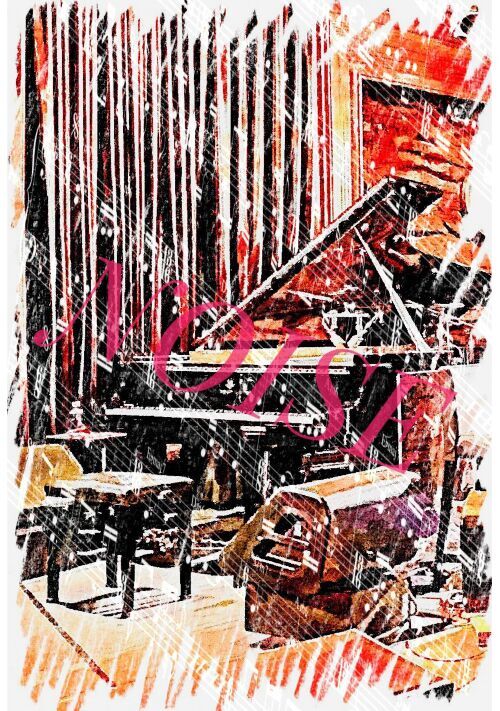
NOISE
セラム
青春
ある1つのライブに魅せられた結城光。
そのライブは幼い彼女の心に深く刻み込まれ、ピアニストになることを決意する。
そして彼女と共に育った幼馴染みのベース弾き・明里。
唯一無二の"音"を求めて光と明里はピアノとベース、そして音楽に向き合う。
奏でられた音はただの模倣か、それとも新たな世界か––––。
女子高生2人を中心に音を紡ぐ本格音楽小説!

サンタの村に招かれて勇気をもらうお話
Akitoです。
ライト文芸
「どうすれば友達ができるでしょうか……?」
12月23日の放課後、日直として学級日誌を書いていた山梨あかりはサンタへの切なる願いを無意識に日誌へ書きとめてしまう。
直後、チャイムの音が鳴り、我に返ったあかりは急いで日誌を書き直し日直の役目を終える。
日誌を提出して自宅へと帰ったあかりは、ベッドの上にプレゼントの箱が置かれていることに気がついて……。
◇◇◇
友達のいない寂しい学生生活を送る女子高生の山梨あかりが、クリスマスの日にサンタクロースの村に招待され、勇気を受け取る物語です。
クリスマスの暇つぶしにでもどうぞ。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















