32 / 76
32. 黒と新幹線
しおりを挟む「待たせてごめん。おはよう」
絵に描いたような、爽やかな笑顔と挨拶に、見惚れてしまいそうになるのをなんとか堪えて、いつも通り挨拶の言葉を舌に乗せた。菊地さんのスーツ姿も、おはようも、いつもと変わらないはずなのに妙に照れてしまうのは、二人きりでの待ち合わせという、レアなシチュエーションのせいだろうか。
「発車までまだ時間あるよな。ちょっと、売店でも寄ろうか」
「はい」
菊地さんの後について歩きながら、やはり気恥ずかしさを感じる。あれだけ意識しないように、と自分に言い聞かせていたくせに、こんな簡単なことで照れて浮かれてしまう自分が情けない。
「中谷はなんか欲しいものある? 朝ごはん、ちゃんと食べてきた?」
そう問いかけながら、菊地さんは店内をぐんぐんと進んでいく。
「私は大丈夫です。朝ごはんも、ちゃんと食べてきたので」
笑顔で答えながら、昨夜の晩ごはんのあまりものだったけど、と心のなかで付け加える。最近はなんだかんだと理由をつけて皓人さんと会う回数を減らしているからか、自宅でご飯を食べる頻度が増えている。以前の生活に戻りつつあるだけなのに、一人で食べるご飯がたまに虚しい。
「そっか。じゃあ、飲み物ぐらいかな。たぶん、昼ご飯は客先でしっかりしたやつが用意されてるから、腹にスペース作っておいた方がいいし」
言いながら、菊地さんは青汁の紙パックへと手を伸ばした。意外なチョイスだな、と思わずじっと見つめてしまう。
「何? 中谷も青汁飲む?」
ちょっと意地悪な表情で訊ねられて、私は慌てて首を振った。
「じゃあ、何がいい?」
菊地さんの言葉に、私は飲料コーナーをぐるりと見回した。選択肢が多いと、何を迷ったらいいのかすら分からなくなる。何を選ぶのが正解なんだろうか。いっそのこと、菊地さんが選んでくれればいいのに。でも、そうしたら青汁になりそうだし、それはちょっと嫌だな。やっぱり、いつものミルクティーにするべきか、でも、新幹線でミルクティー飲んだら気持ち悪くなるかな?
うーん、と迷う私の頭上から、小さく吹き出す音が聞こえた。顔を上げれば、菊地さんが笑いを堪えるように口元を覆っていて。恥ずかしくて頬に熱が集まる。
「早く決めないと新幹線、行っちゃうぞ」
無慈悲にもそんな言葉をかけられ、菊地さんには私を助ける気がないことを確信する。慌てた私は咄嗟に、オレンジジュースを掴んだ。それがいつも皓人さんの家で飲んでいたものだときづいた時には、すでに菊地さんが私の手からそれを奪い取っていて。再び彼に声をかけられたときには、すでにお会計が終わっていた。白いレジ袋を片手にぶら下げて、改札へと向かう菊地さんの背中を、早足で追いかけた。
「中谷は、乗り物酔いとかする方?」
ホームで並んで新幹線を待ちながら、菊地さんは訊く。記憶を辿ってみても、そもそも乗ったことのある乗り物の種類も回数も限られていて、答えに少し困る。
「たぶん、大丈夫です」
「たぶん?」
「たぶん」
歯切れの悪い私の答えを情けないと思うのに、菊地さんは全く気にしていなさそうだ。
「俺は、たまに乗り物酔いするタイプなんだ。だから、気を紛らせるために中谷にちょっかい出すかもしんないから、よろしくね」
再び、青年なような少し意地悪な微笑みを向けられて、胸が微かにときめいた。
これから2時間半、この人と二人きりなんだよね。
改めてその事実を認識して、妙な緊張感と共に唾をごくり、と飲み込んだ。
新幹線に乗り込んで、指定された座席を探す。思っていたよりも狭い車内に、再び緊張感が込み上げてくる。
「俺、通路側な」
そう言いながら、菊地さんは私に、先に座席列へ入るようにと手で促す。席に座れば、菊地さんが隣に腰かける。隣同士の座席を購入したのだから当たり前のことなのに、触れていないけれども体温を感じられるだけの距離感が、なんだかこそばゆい。
「そんなに俺と一緒にいたかった?」
新幹線が動き出すのとほぼ同じタイミングで、菊地さんが問いかける。思わず動揺して、言葉にならない声が口から洩れる。
「他にも空いてる席あるのに、わざわざ隣同士の座席指定してさ」
そう言われて始めて、周囲の空席に気付いた。菊地さんから新幹線のチケットを予約するように言われて、特段何も考えずに、当たり前のように隣同士の指定席を購入した。そこには疚しい気持ちも、特別な意味も、何もなかった。それなのに、こうやってわざわざ口に出されると、まるで下心を指摘されたような気がして。羞恥心で途端にカーッと顔に熱が集まった。
「べ、別に」
と、慌てて否定しようとすると、堪えきれなかったかのように、菊地さんが笑い始めた。お腹を抱えながらクツクツと喉仏を震わせる姿を見て、ようやく、からかわれていたことに気付く。
「今日の菊地さん、ちょっと意地悪ですね」
ようやく菊地さんの笑いが収まった頃合いに、ポツリ、と呟いた。
「えー、こんなに優しくしてるのに?」
なんて言葉と共に、首筋にひんやりとした何かが当てられた。「ひゃ」なんて間抜けな声と共に、座席の上で飛び上がる私を見て、またも菊地さんは声を上げて笑う。
恥ずかしさやら情けなさで、私のうっすらと目尻に涙が浮かび始める。こんな風にからかわれることに慣れていないので、妙にドギマギしてしまう。拗ねたように唇を尖らせれば、ポン、ポン、と頭の上に優しい手が乗る。
「悪い、からかいすぎた」
と謝る声の端には笑いの余韻が残っている。
改めて、菊地さんから先ほどの冷たさの正体、売店で購入したオレンジジュースが手渡される。お礼を言いながら受け取って、お金を払っていないことを思い出す。
「すみません、代金」
「あー、こんなの全然、気にしなくていいから」
大丈夫、という彼の言葉に、改めてお礼を言う。
「水も買ってあるから、ここ挟んどくぞ」
座席の裏の、網のかかったポケットに、水のペットボトルが挟み込まれる。
確かに、優しい。
会社じゃないからか、はたまた二人きりだからか、いつもより少し意地悪だけれども、でもやっぱり優しい。
レジ袋をガサゴソといわせながら、菊地さんは青汁の紙パックを取り出す。
ストローを出して、刺して、咥える。
たったそれだけの簡単な動作なのに、どうしてこんなにもドキドキしてしまうのだろう。この簡単な動作に、どうして色気を感じてしまうのだろう。
「青汁、好きなんですか?」
場違いな胸の高鳴りを誤魔化すように、わざと明るい声を作って問いかける。
「好きっていうか、もう習慣だな。毎朝飲んでるからさ、いつの間にか欠かせなくなっちゃって」
「へえ」
菊地さんの意外な答えに、思わず気のない相槌をうってしまう。クールなイメージの菊地さんと青汁なんて、意外な組み合わせだ。てっきり、朝はブラックコーヒーなのかな、なんて思っていた。
けど、実は甘いものが好きだったり、人のからかい方はちょっと子供っぽかったり、面倒見がよくて優しかったり。実際の菊地さんと、クールなイメージとは、結構ギャップが多いのかもしれない。
「今朝はいつもとルーティンが違ったから、飲み忘れちゃったんだよ」
そう言って菊地さんは青汁を振ってみせる。
「確かに、今朝はいつもと違いましたよね。ぬいぐるみでおしゃべりしたり」
待ち合わせ場所で見た光景を思い出しながら、私は言う。すると、明らかに動揺したらしい菊地さんは、青汁でむせかけてストローから唇を離した。
「まさか、見てたのか?」
「はい、バッチリと」
珍しく照れ臭そうな表情を見せる菊地さんに、私の胸はなぜだかときめいた。
こんな表情をすることもあるんだ。
ついついニヤついてしまう頬を、必死で誤魔化そうと下唇を噛み締めた。
「子供、好きなんですか?」
あの時、菊地さんはスーツが汚れてしまうのもお構いなしに、躊躇することなく跪いた。そんなこと、子供が好きな人じゃないと、なかなか出来ないことだ。菊地さんは子供の目線に合わせて、子供の心情に合わせて、対応していた。あれを咄嗟に、しかも自然に出来る人はそんなに多くないと思う。
「好きだよ」
ドクン。
自分に言われたわけじゃないのに、耳が、心臓が、思わず錯覚してしまいそうになった。それだけ、私はこの言葉に飢えていたのだろうか。それとも、菊地さんだから?
「子供、かわいいじゃん。弟がもう結婚してて、子供もいてさ。たまに会いに行くんだけど、めちゃくちゃかわいくて。幸せそうで、羨ましいよ」
そう語る菊地さんはすごく優しい表情をしていて、きっとその笑顔を弟さんのお子さんにも向けているんだろうな、と容易に想像がついた。
「弟さん、いらっしゃるんですね」
「うん。姉貴と俺と弟の三人きょうだい」
「真ん中なんですね。ちょっと意外です」
「そう?」
「面倒見が良いから、一番上なのかなって、思ってました」
話しながら、今までどれだけの場面で菊地さんに救われてきたのかを改めて実感した。本当に、面倒見が良くて優しい、良い先輩だ。弟さんにとっても、きっと良いお兄さんなんだろうな。
でも、女性との接し方が上手だから、お姉さんがいるのは納得だ。そう考えると、意外じゃないのかもしれない。姉、かあ。
「私にもいますよ、姉。しかも、複数。義理ですけどね」
無意識に、口から言葉がこぼれ落ちた。こぼれ落ちてから、自分で驚いた。自分から彼女たちの話をするのは、もしかしたら初めてかもしれない。
ちらり、と隣を見上げれば、少し心配そうな表情で菊地さんが私の顔を覗き込んでいた。
「父の再婚相手の連れ子で。悪い人たちじゃないんですけど、いい人でもなくて。大学に入ってからは、ほとんど会ってないんですけどね」
自分で始めてしまった話だから、どうにか落ちを付けないと、と思って紡いだ言葉は、予想以上のダメージで。この話をするには、まだ早いと悟った。
私は口をつぐむと、そっと窓の外を見つめる。ぐんぐんと流れていく景色は、ここがもう東京ではないことを示している。
「まあ、家族ってのはそれぞれだからな」
ごくり、と飲み込む音の後に、菊地さんの声が優しく耳に届く。
「家族に限らず、人間関係って本当にそれぞれだし、正解も不正解も、普通も何もないから」
そっと、無防備な私の右手に、菊地さんの暖かい手が重なった。ポン、ポン、と励ますかのようなテンポで、優しくリズムを刻む。ポン、ポン、とあやすみたいなテンポで、優しくリズムを刻む。
その優しさと温かさに、心臓がドクンドクンと早いスピードで音を立てる。
金沢に付くまで、あと約2時間。
早く過ぎてほしいような、ゆっくりであってほしいような、もどかしい気持ちのまま、私は車窓を見つめた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

CODE:HEXA
青出 風太
キャラ文芸
舞台は近未来の日本。
AI技術の発展によってAIを搭載したロボットの社会進出が進む中、発展の陰に隠された事故は多くの孤児を生んでいた。
孤児である主人公の吹雪六花はAIの暴走を阻止する組織の一員として暗躍する。
※「小説家になろう」「カクヨム」の方にも投稿しています。
※毎週金曜日の投稿を予定しています。変更の可能性があります。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
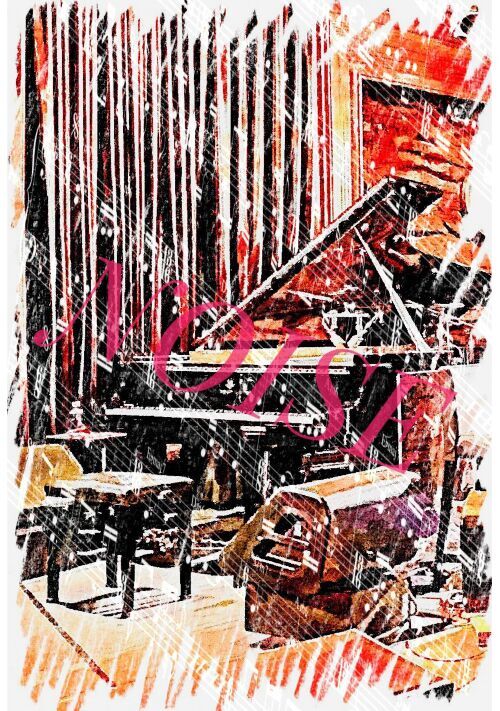
NOISE
セラム
青春
ある1つのライブに魅せられた結城光。
そのライブは幼い彼女の心に深く刻み込まれ、ピアニストになることを決意する。
そして彼女と共に育った幼馴染みのベース弾き・明里。
唯一無二の"音"を求めて光と明里はピアノとベース、そして音楽に向き合う。
奏でられた音はただの模倣か、それとも新たな世界か––––。
女子高生2人を中心に音を紡ぐ本格音楽小説!


サンタの村に招かれて勇気をもらうお話
Akitoです。
ライト文芸
「どうすれば友達ができるでしょうか……?」
12月23日の放課後、日直として学級日誌を書いていた山梨あかりはサンタへの切なる願いを無意識に日誌へ書きとめてしまう。
直後、チャイムの音が鳴り、我に返ったあかりは急いで日誌を書き直し日直の役目を終える。
日誌を提出して自宅へと帰ったあかりは、ベッドの上にプレゼントの箱が置かれていることに気がついて……。
◇◇◇
友達のいない寂しい学生生活を送る女子高生の山梨あかりが、クリスマスの日にサンタクロースの村に招待され、勇気を受け取る物語です。
クリスマスの暇つぶしにでもどうぞ。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















