1 / 2
密室の白骨
しおりを挟む
男はLGS(軽量鉄骨)に固定した石膏ボードの真新しい表面にセメントを塗り、泥を擦り付け、周囲の床からかき集めた埃をばら撒く。たちまち新品のパネルが古びたコンクリートのような雰囲気になり、その出来栄えに満足する。
次にそのパネルの周辺に速乾セメントを塗りたくった後LGSごと立ち上げ、扉の有ったパネルの代わりにそれで空間を塞ぐ。
最後にLGSの上部を天井に渡された鉄骨とバーナーで接合し、底辺はアンカー・ボルトで固定する。
やっと終わった。これでどんな力が掛ろうと、少なくとも人力ではびくともしないだろう。
仕上げは地上に繋がるハッチだが、こればかりは日曜大工レベルではどうしようもない。自分一人の力では無理なので建築業者に既に発注をしてある。二日後には重量が百キロはある鉄板が取り付けられる手はずだ。
男は地上に這い出ると細巻きの煙草に火をつけ一服吹かしつけた。
「お晩でございます、先生」
突然、背後から声を掛けられ喉から心臓が飛び出そうになる。慌てて振り向くと月明かりの下で腰の曲がった老人が佇んでいた。
「ハッチが壊れたっていうんで頑丈な鉄板に替えて頂けるとか。その下見ですか? ご苦労様です。地上げ屋の買収も断って頂いて……儂なんか身寄りも無いから、ここを追い出されたら他に行く当てなどありゃしません。何とお礼を申し上げて良いのやら」
声を掛けてきた主が長屋に住む喜一(きいち)爺さんだと判り安堵する。
「いやいや、礼には及びませんよ。喜一さんたちがお元気なうちは、この長屋をどうこうはしません。安心して長生きしてください。じゃ、夜も遅いので。お休みなさい」
「はい、お休みなさい」
喜一老人の声を背中で受け、先生と呼ばれた男は暗闇の中へゆっくりと去っていった。
東京近郊のK市。一昔前は農地が広がる長閑な田園地帯であったが、都心への通勤の便が良いことからK市と共に鉄道会社が第三セクターを立ち上げ、大規模な再開発に乗り出したのがバブル全盛期。駅舎移転と新駅前の再開発を行うと共に、マンション建設や宅地造成に注力したのだった。
以後、都心に通勤するサラリーマンのベッドタウンとして人気を博し、人口が増加し続けている。新駅前や幹線道路沿線に全国チェーンのGMSが相次ぎ出店したことで、旧駅前の地元商店街はシャッター通りと化し、次々と地上げされていった。
旧駅前が昔とは様相が徐々に変化していく中で、戦前からこの地にある民間の佐々木総合病院だけは増加する人口に比例して患者数が増え活況を呈していた。
夜勤の看護士に業務引継ぎを行い、帰り支度を済ました萩原(はぎわら)裕美(ゆみ)は足早にエレベーターホールに向かっていた。
程なく到着したエレベーターに乗り込んだ彼女は1FではなくB1のボタンを押す。
途中で誰も乗って来ませんように。ゆっくりと降下するゴンドラの中で、裕美は心の中で祈る。
業務を終え私服に着替えた看護士が地下に降りていくなど、どう考えても妙である。病院のスタッフに見咎められでもしたら大変だ。万一誰かが乗り込んできても顔が見えないように操作盤の方に俯き加減に身を寄せる。
b幸いエレベーターは途中階に停止する事なく、ノンストップで地階に到着した。
左右の廊下を見やり誰もいないのを確かめると、裕美は素早くエレベーターから出て、廊下の突き当たりを更に右に折れ、建物の奥へと足早に進む。
もうここまで来れば誰に会う恐れもない。この先にあるのは遺体安置所と今は使われていない部屋があるだけだ。
遺体安置所を横目に小走りで通り過ぎ、廊下の突き当たりの部屋のドアをそっと開ける。
中は真っ暗だ。部屋に数歩足を踏み入れた途端、背後から抱きすくめられる。
「きゃっ」と声を上げる間もなく振り向かされ、口に柔らかい唇が押し当てられた。
熱い舌が口に挿入されてくると、裕美は積極的に自分から舌を絡ませる。
男性の手が胸を掴み、もう片方の手がヒップの辺りを這い回る。
飽くこと無く互いの舌を貪る間も男性の手は忙しく動き、ブラウスのボタンを外すとブラジャーをずり上げる。
「ああ、先生。乱暴にしないで」男の頭を抱え胸元に押し付ける。
「ああ、ごめんよ。もう待ちきれなくて、つい力が入ってしまった。さ、後ろを向いて。そこに机があるから両手をそこに付くんだ」
同じ内科の医師、関谷(せきや)が裕美のスカートを捲り上げる。
「やはり、ここでするの? 何だか薄気味悪くて落ち着かないわ」
「仕方ないだろ。これまでは空き病室が有ったしベッドも自由に使えたが、今は病室もベッドにも空きがない。だから総務部長に無理を言って鍵を借りてきたんだ。さあ、早く」
関谷に促され、手探りで机の端を確かめた裕美は、両手を付きヒップを後方に突き出すと、顔を真っ直ぐ正面に向ける。暗闇に目が慣れた裕美は、周囲の様子を伺う。
今は倉庫代わりに利用されているらしくキャビネットやダンボール箱が壁いっぱいに乱雑に積まれている様子がぼんやりと見える。正面突き当たりにもダンボールの重なりがあるようだが、詰まれた箱の段数が低いためその向こう側にドアが有るのに気がついた。
「ねえ、先生。この奥にも部屋が有るの?」
「ああ、僕も知らなかったが、防空壕らしい。総務部長が教えてくれたのさ」
背後に回った関谷が裕美のショーツをずりさげながら答える。
「この病院は戦前からあるだろ。空襲に備えて患者を避難させる大きな防空壕を作ったって話だ。それを先代の院長がシェルターに改造したらしい。尤ももう何十年も使用されてないし、そのドアも錆付いて開けることさえ出来ないから本当のところは誰も知らない。ベッド数が足りないって言いながらこんな部屋が手付かずだなんておかしいよな。まあ、そんなことはどうでもいいさ。今は二人だけの時間を楽しもう」
関谷が会話を切り上げる。
彼を受入れようと、顔を正面に向き直る裕美。その時、正面のドアのガラス越しに何かチラッと白いものが目に入った気がした。
「先生、待って」裕美は机から手を離し、腰に回した関谷の手を払いのけた。
「おいおい、何だよ。これからという時に」
そんな関谷に構わず身なりを整えながら、裕美は奥の部屋の目の前まで近づきドアのガラス越しに中を覗き込む。確かに何か白い物体がぼうっと浮かんでいる。
「あ、あれ見て……ミイラが――」
裕美のただならぬ様子に関谷も側に近づいて中を覗き込んだ。
「ミイラ? そんな物有る訳ないだろ。暗くて良く判らないな、明かりを点けよう」
「待って、ガラスが反射して余計に中が見えなくなるわ。先生、ペンライトを持っているでしょ」
関谷は診察用のペンライトを胸ポケットから取り出し内部を照らす。
内部は酷く荒れていて壁が崩れているのか床には土砂が散乱している。その上に覆いかぶさるようにしている人間の頭蓋骨と腕の骨がはっきりと浮かび上がる。目の窪んだ穴がじっとこちらを見詰めている。
「きゃーっ」「ウワー」二人が同時に叫ぶ。
関谷は恐怖のあまりペンライトを落とすと、愛人を置き去りにしたまま一目散に逃げ出した。
「病院からミイラ化した死体」 戦時中、生埋めになった患者の可能性も
植草真一は、関東日報の朝刊一面に大きく報じられている白骨の記事を熱心に読んでいた。
「どうだ、俺の書いた記事は? だが、その後の警察の調べでは白骨はそんなに古いものじゃ無いようだ。精々、死後五、六年って事らしい。性別は女性で年齢は三十歳前後、身長は百六十センチ、腕の骨に打撲によるヒビが見られるが、それはドアや窓ガラス、壁を叩いたためになったものと思われる。暴行や死に至るような怪我の可能性は無く餓死又は窒息死と見られ、そのため綺麗なミイラ状態で発見された――凄いな、白骨だけでこれだけの情報が読み取れるんだ」
友人で新聞記者の栗橋雄太が手帳のメモを見ながら話す。
「ふふん、白骨だから相当古いと決め付けちゃ駄目だ。動物が死ぬと先ず蛆が湧き出してくる。僕は小学生の頃、通学路途中の溝にドブネズミが死んでいるのを発見してね。それから毎日、登下校の度に観察をしていたから良く知っている。内臓を蛆が食い荒らすと同時に外側の毛や皮は、他のネズミやカラス達が剥ぎ取っていくのだ」
「うえっ、止せよ。よくそんなものを観察する気になるな」
「何を言っているのだ。厳粛な死の後に何が起きるのか見守ってやることが務めだろ」
どうしてドブネズミの最期を看取るのが務めなのか栗橋には全く理解できない。
「そして大体一年から三年もすれば白骨化する。水中で二年から五年、土中だともう少し時間が掛かって約七年から十年できれいな白骨の出来上がりさ。性別は目視でも判断出来る程男女で差がある。年齢は骨髄や化骨核の変化で推定するのさ」
「嫌ね、何の話をしているのよ」
コーヒーの入ったマグカップを三つ載せたトレーを持って部屋に入ってきた真一の妹の奈(な)緒(お)が言う。
栗橋が植草家にしょっちゅう出入りしているのは、真一と親友ということも有るが、奈緒の顔見たさでやってくるのだ。
植草家の兄妹は近隣でも評判の美男美女である。兄の真一は色白で見るからに文学青年といった雰囲気を漂わせている。一方、妹の奈緒は、黙って大人しくしていれば良家のお嬢様なのに格闘技が(それも観戦ではなく実戦が)大好きというお転婆(てんば)娘なのだ。
両親は既に他界し、大きな屋敷には二人の他に先代の頃からの住み込みの使用人が二人と愛犬が一匹いるだけである。
先祖は代々地元の郷士であり、所有する土地と資産は相当なものらしい。父親は文化人類学の研究の傍ら郷土史編纂にも尽力した人物であった。
そんな恵まれた環境の中で生まれ育ったせいなのか、植草真一には浮世離れしたところが有った。定職に就かず気儘に絵を描いたり同人誌に雑文を掲載したりしている。
彼の名前と一字違いで「僕は散歩と雑学が好き」などのエッセイで知られる植草甚一に負けず劣らず、彼も博学で世の中のありとあらゆる事象に精通している。そのため新聞記者の栗橋は良く知恵を授かりにやってくる。
今回も真一に或る謎を解明して貰おうとやってきたのであった。
「あ、奈緒さん、いつもコーヒーを有難う。変な方向に話が逸れたけど病院で見つかった白骨の話をしていたものだから」
「ああ、その事件ね。私は恋人を置き去りにして我先に逃げた医者が許せない。呆れた腰抜け野郎ね、回し蹴りでも喰らわしてやりたいわ」そう言ってトレーを持ったまま回し蹴りをする。
真正面に坐っていた栗橋の眼前ですらりと形の良い脚が空を切る。思わず仰け反ってしまう栗橋。
「おいおい、コーヒーがこぼれるぞ」
「大丈夫、ほら。体幹を鍛えているからこれくらいでは軸がぶれないわ」
「そんな事を言っているのじゃ無い。お客様の前で大股拡げて……ほら雄太がびっくりしている。自分の妹ながら嘆かわしい」
「あら、ごめんあそばせ。はい、雄太さん、コーヒーを召し上がれ」
にっこりと微笑みながらマグカップを栗橋の前に置く。
「あ、いや。どうも」しどろもどろになりながら顔を真っ赤にした栗橋が答える。
先刻、一瞬では有ったがスカートが翻った拍子に奈緒の太腿の付け根まで見えてしまったのだ。勿論、レギンスを穿いているので何が見えたという訳でもないのだが。
「それで、この件がどうしたと言うのだ」
植草に促されてやっと用件を思い出した栗橋が口を開く。
「ああ、それそれ。警察の公式発表は事故死だが実際は事件の疑いもあるようなんだ」
植草はコーヒーを飲みかけた手を止めた。
「事件? じゃあ、誰かが閉じ込めたって事か?」
「ああ、だけどそこで厄介な問題が持ち上がったんだ。担当の刑事がオフレコで教えてくれたんだが、彼が言うには、通報を受けた警察が白骨を回収するのに大変な苦労をしたらしい。と言うのも防空壕は戦後シェルターに改造したものの全く使われておらず、病室に通じるドアは完全に錆びついて開かなかったのだ。ドア自体を破壊しようにも密閉性の高い頑丈なドアだし窓ガラスも金網入りの割れない奴だ。やっとのことでそれを外したが、五、六年どころじゃ無くてもう何十年もの間そんな状態だったようだ。女性は必死で脱出を試みたのか、ドアや周りの壁の至る所に血みどろの引掻いた跡が残っていた。可哀想に余程苦しかったのだろう、何しろシェルターだから機密性が半端じゃ無い、徐々に酸素がなくなって苦しみながら死んでいったようだ」
「ちょっと待てよ。じゃあその女性はどこからその部屋に侵入できたのだ?」
「そこだよ、それが謎なんだ。閉じ込めるどころか、どうやってそこへ入れたのか? 刑事の話によると、三十坪程度の広さだそうだ。ドアは二重になっていて有事の際は頑丈なシャッターが下り完全密閉が保たれる。当然、四方は窓一つない壁が取り囲んでいる。尤も天井に濾過機能の付いた空調が備えられているが、その排気ダクトは人が入れる程大きくは無い。シェルターだから当然だろうな。だがそれが故に警察は頭を悩ませているんだ。先刻も言ったようにシャッターこそ下りてはいないが、唯一の脱出口であるドアは錆付いて動かない。つまり……」
「密室だったという訳か」
「さすが、察しが良いな。だから警察は病院のオーナーである佐々木院長親子の犯行とみて、任意で事情聴取したんだ」
「じゃあ、一磨も取調べを受けているのか?」
「当然さ、あいつは院長の息子で副院長だからな。警察は親子が何らかの方法で女性を幽閉して死なせてしまったのではないかと考えていた」
「まさか、あの一磨が……」
植草が絶句するのも当然で、佐々木一磨は彼や栗橋と同級生であり幼馴染でもあるのだった。
「心配ないさ、結局彼等も何も知らないようだし、それに……」
「ん? どうした」
「結局、警察は事故として処理したんだ、どうも何処からか圧力が掛ったようだ。それで、当時はドアが錆付いてなくて、そこから侵入したのだと無理矢理結論付けて一件落着さ。どうしてそんな場所に死体が有ったのか大きな謎で、それを解明せずに事故扱いするのは納得がいかないって担当の刑事はぼやいていたよ。彼はまだ佐々木親子をクロだと思っているんだが、現在は上司の命令で身元の確認作業に専念している。佐々木総合病院に押しかけていたマスコミも潮が引いたように雲散霧消しちまった。今は被害者探しに懸命だ。全くマスコミも勝手なものだ」
「他人事のように言うなよ。お前も、マスコミの一員じゃなかったっけ?」
「それはそうだが……」痛いところを突かれた栗橋は一瞬たじろいだが、気を取り直して話を進める。
「どうだ、真一。興味をそそられる事件だろ? 俺も事件記者としての血が騒ぐんだ。
被害者はどこから侵入したのか? 自殺なのか、はたまた他殺なのか? 他殺となると密室殺人って事になる。センセーショナルな事件だ」
「ははーん、お前の腹のうちが読めた。さしずめ僕をおだてて密室の謎を解明させ、それをスクープしようって魂胆だろ」
「密室の白骨か、面白いじゃない兄さん。どうせ暇を持て余しているのでしょ」奈緒が口を挟む。
「今は作品の仕上げに忙しいんだ」余計なことを言うんじゃないと植草が眉を顰める。
「道楽で描いている絵じゃない。どうせ売れる当てもないのだから後回しにして、雄太さんに協力してあげましょうよ」奈緒が言いにくいことをズケズケと言った。
「いいか、密室殺人なんてものは有り得ない。古今東西の推理小説では犯人が苦労して密室を構築するが、およそ現実的じゃない。今回の事件はフェル博士が指摘した内の一つ、偶発的に密室になってしまった可能性が考えられるが……」
「フェル博士って誰だ?」
「フェル博士を知らないのか? ジョン・ディクスン・カーの『三つの棺』を読んでないな」
「何だ、ミステリー小説の話か」
「密室については、コナン・ドイルやディクスン・カーのみならず、日本でも江戸川乱歩や天城一、二階堂黎人、柄刀一などがその構成要件の分類を試みている。例えば――」
「ちょっと待ってくれ。密室の講義は勘弁してくれ」栗橋が慌てて止める。
植草が薀蓄を傾け始めると一晩中でも喋り続けるのだ。
「ん? 興味があるって言うから解説してやっているのに……兎に角、密室殺人など有りえない。ドアが存在してその鍵が掛っている場合は、如何に鍵を密室に戻すかだの、犯人が部屋にいただの様々な可能性が考えられる。しかし今回はドアそのものが錆付いて開かないというのだから、うーん……これは難問だ」
その様子を見詰めていた栗橋はしめしめとほくそえんだ。気乗りがしないと言いながらもどうやら植草は謎の解明に興味を惹かれたようだ。
うまく行ったわねとでも言うように、奈緒がウインクを寄越した。
栗橋が帰った後、植草は彼が持ち込んだ謎についてじっくりと考える。密室殺人など有り得ない、絶対に何かカラクリがあるはずだ。だが、その現場はシェルターである。シェルターというからには部屋は完全に密閉されているであろうし出入口以外に蟻の這い出る隙間もないであろう。
そこまで考えて植草はふと思い出した。そういえば、佐々木総合病院の地下にシェルターが有ったという話は誰かから聞いたことがある。そうだ、親父が話していたのだ。
幼い頃の記憶を思い起こす。たしか当時は新聞の地方版にも載る程話題だったらしい。元々は戦中に防空壕として作られたそうだ。尤も物資の無い時代だからコンクリート製では無かったようで、そのままでは落盤を生じる危険性があるので、戦後になってコンクリートで補強しシェルターに作り変えたと聞いた。
当時は核シェルターっていうのが持て囃された時期だった事もあり、密閉性も強化したという。佐々木由宇磨、つまり現在の院長琢磨氏の父親だが、相当先進的な思考の持ち主だったようだ。
シェルターに改築する以前の防空壕については、親父の書き残した郷土史にも確か記述が有ったと記憶している。
早速、植草は書斎で本を探す。既に他界した父親は、彼と奈緒に様々な資産を遺してくれたが、彼が一番大事にしているのが書斎の天井近くにまでの棚にぎっしり詰め込まれた大量の書物であった。専門分野の民俗学や文化人類学に関わる書物は当然ながら、その他の人文、文芸、芸術など、多趣味だった父親らしくそのジャンルは多岐にわたる。
その中から父親が編纂した郷土史を何冊か取り出す。
たしか大戦中のことであるから昭和十五、六年から二十年の間だろうと見当をつけてページをパラパラとめくる。あった、これだ。昭和十九年の十二月。
植草は文章に目を通す。
その年の十一月に米軍は東京に始めて空襲を実施。以来翌年に跨って百回を越える空襲を行った。中でも三月の東京大空襲は罹災者が百万人を越える大規模なものだった。
空襲の標的は軍事施設ばかりでなく無差別攻撃化し民家や病院でさえ焼夷弾の餌食となっていった。当時佐々木総合病院には、戦争による多くの負傷者が運び込まれており、防空壕はそんな最中に建設されたようだ。
件の防空壕は病院の患者だけでなく、近隣の住民も避難できるように別の出入口が検討されたと有る。だが実際に作られたのかどうかについての記載は無かった。
当時の簡単な地図も掲載されており、それを見る限り防空壕自体の規模はとてつもなく広かった。おそらく百坪はありそうだ。病院の敷地は一部で、同じく佐々木家が所有する周辺一帯の住民が避難できるよう大部分は隣接する長屋や民家を含めその一画の地下に作られたようだ。
そこまで目を通して植草は意外に思う。こんな大きな防空壕とは思わなかった。たしか雄太は三十坪程度と言ってたはずだ。そのうえ、近隣の住民が避難できる別の出入口が検討されたとある。その出入口が実際に作られたかどうかは判らないが、もしそれが作られていたとするならば……。
植草は書斎を出て自分の部屋のパソコンを立ち上げる。
もし別の出入口が有るとすれば、当時の地図に記されている長屋周辺にあるはずだ。だ
が、現在はビルや宅地が立ち並び、既に長屋などは取り壊されている。
正確な現状を把握しようと、グーグル・マップの衛星写真を開き調べる。その結果、周辺の長屋や民家は立ち退き、跡地に新しい住宅やビルが建てられているが、唯一病院の裏手に今でも長屋が存続することが判明した。
翌日、実際に現地をこの目で確認しようと目的地にやってきた植草真一はその場で天を見上げた。周りを背の高いビルに取り囲まれ、まるでそこだけが四角く切り取られたように、青空と白い雲がぽっかりと浮かび上がっているように見えた。
この長屋に陽射しが当たるのは一日の内のほんの数時間、いや一時間程度であろうか? そう考えながら、視線を長屋に戻す。よくこんな場所に古い長屋が残っていたものだ。この場所だけが昭和のまま取り残されているように思えた。
「こんにちは。何かこの長屋に用ですかな?」
いつの間にか傍らに煙草を手にした老人が近づいていた。
「あ、いえ。僕は郷土の歴史を調査している者なのですが、確かこの辺りに昔の防空壕が残っているとお伺いしたものですから……その件について何かご存知じゃ有りませんか」
「ああ、そう言えばもう何十年も前に同じように調査に来られた方がおりましたな。偉い学者さんで、確か植草さんと仰いましたかな」
「それは僕の父です」
「おお、そうでしたか。あの方のご子息でいらっしゃる、そうですか」
老人は満面の笑みを浮かべ、うんうんと一人で頷く。「ほれ、そこの足元の鉄板が防空壕への入口ですじゃ」
植草は老人の指差す地面に膝まずき、鉄板の持ち手に手を掛けた。
「無理じゃ。あんた一人の力では持ち上がりませんわな。従来は粗末な木の扉だったのじゃが、あれは六年ほど前になるかのう、旦那さんが危険じゃからと頑丈な鉄板に取替えられたのじゃ。今のように平和な時代にはもう用のないものじゃからのう」
老人は地主の佐々木琢磨の事を旦那さんと呼んでいるようだ。植草は汚れた手をはたき、諦めて立ち上がる。
「そうですか、残念です、中を見たかったのですが……」もう一度辺りを見回し老人に話しかける。「昔はこの辺りは木造建築や長屋が多かったのに、いつの間にかここだけになってしまったのですね」
「旦那さんのお陰でのう。儂等が住んでおる間は取り壊さんと、目の前のビルが建つ時も土地売却の話を断って下さったんじゃ」
そう言って老人は美味そうに煙草をふかした。
「良い香りですね。おや、ダビドフのマグナムじゃないですか。高級煙草ですね」
「いやいや、儂はもっぱらゴールデンバットなんじゃが、これは旦那さんからの貰いものでのう」
そう言って目を細める老人に改めて礼を述べると植草はその場を後にした。
植草は家に戻ると早速栗橋に連絡をした。栗橋が再び植草家を訪れたのは夕方近かった。
「やはり親父の郷土史に防空壕の記載が有ったぞ。だが三十坪どころの規模じゃない。あの一画の地下がすべて防空壕になっていたようだ。そして別の出入口が長屋の下にあった」開口一番、そう言って植草は調査の結果を栗橋に話して聞かせた。
「ちょ、ちょっと待てよ。長屋だって? 長屋なんてどこに有るんだ。あの一画は北西向きに病院と外来用の駐車場だろ。駐車場の角は本通りに面していて、右折して駐車場沿いに歩いていくとマンションだ。その建物は南東の駅前通りまで続く。駅前通りはマンションの隣に商業ビルと民家だ。そこで南西の公園通りにぶつかる。角を曲がって立ち並ぶ民家の隣はもう介護施設と病院だ。これで時計回りに一周してスタート地点に戻る。長屋などどこにも無いぞ」
栗橋が言い募ると、植草は「実は僕も知らなかったんだ」と言いながらパソコンを立ち上げ、グーグルを開いた。
「良く見てみろ。その一角の中心に木造の建物があるだろ」
そう言われて栗橋はモニターを凝視する。
確かに植草の指摘どおり病院、マンション、ビル、介護施設に四方を囲まれた建物が存在した。
「しかし、ここの住民はどこから出入りしているのだ? これじゃあ、陸の孤島状態じゃ無いか」
「長屋の住民は介護施設の中庭から出入り出来るようになっている。まあ、実際はマンションと外来駐車場との狭い路地から行き来しているようだがね。そっちのほうが通りへ出るのは近いし、駅もそちらの方向だ」
「へえ、昨日すぐに調べてくれたのか。待てよ、思い出した。そう言われればビルや介護施設が建つ前は、あの一帯は古びた民家や長屋だったな」
「そうでございますよ、それでも当時としては立派なものでございました。今でこそ瀟洒な家が多くなりましたが昔は田んぼや野っ原ばかりが目立つ片田舎でございましたからねえ。簡素なバラック同然の家が多くございました」
声のするほうを見上げると、住込み家政婦の牧原房(まきはらふさ)江(え)が茶菓子を盆に載せて立っていた。
「あ、房江さん。お邪魔しています。奈緒さんはお出かけですか?」
「ふふ、お茶を入れたのがお嬢様で無くて、皺くちゃ婆でお気の毒様」
栗橋の下心を見透かしたように言う。
「いやそんな。それより話を続けて下さい」顔を真っ赤にしながら栗橋が先を促す。
そんな様子をにこやかに見詰めながら房江が話を続ける。
「はいはい。あの一角もどんどん長屋や古い家が取り壊されて、立派な建物に変わっていったのですよ。ビルがバブルの頃、平成になってマンションが建ち、一番最近建てられたのが介護施設だったですかしらねえ。六年前の事でございます」
「へえ、房江さん良く覚えているのですね」
「そりゃもう。なんせ佐々木家の坊ちゃんが、ご結婚された年ですから」
「他人の結婚した年を覚えているのですか」
そう栗橋が感心すると、房江は片手を顔の前で左右に振った。
「いいえ、その為に看護婦の吉田さんがお辞めになったので良く覚えているのでございます。本当に綺麗で優しくて思いやりのある良い看護婦さんでしたのに」
「房江さん、今は看護婦じゃ無くて看護士です。で、その吉田さんの退職と病院長の息子、一磨(かずま)の結婚とどう関係が……あ、ひょっとして」
「そうなのでございます。人様の内情を軽々しく口には出来ないのですが、一磨坊ちゃんと吉田ゆかりさんは秘かにお付き合いをされていらして……」
「一磨って奴は昔からもてたからね」
栗橋と植草は佐々木一磨とは同い年で小学校、中学校と同級の仲であった。
「そうか奴が別の女性と結婚したので、病院に居づらくなったのか」
「一磨坊ちゃんは酷い男でございます。吉田さんを散々おもちゃにしておいて、ご自身は以前いらしたT大学病院の教授に気に入られて、そのご息女をお娶りになったのです。口さがの無い連中は政略結婚だと噂しております」
「政略結婚? ほう、それはどうして?」
「T大学病院と縁故が出来て、週に何回か若い医者を派遣してもらっているのだそうですよ。今はどこも医者不足でございましょう? ご多分に漏れず佐々木病院も総合病院ですから手が足りなくて困っていらしたそうです」
「やけに詳しいですね。だけど人様の内情を軽々しく口にして大丈夫なんですか」
栗橋の問いかけに植草が答える。
「房江さんにとって病院はご近所の老人との憩いの場、井戸端会議の場なのだ。どうせ仲の良い婦長からの情報だろ? て事は町内の長老連中には知れ渡っているさ」
「あら、いやですわ坊ちゃま。まるで人をスピーカーみたく仰らないで下さいまし」
そう言って房江はまるで少女のように恥じらい頬を染めた。可憐な乙女ならいざ知らず、皺くちゃ婆さんの仕草である。その不気味さに栗橋は少し背筋が寒くなった。
「房江さん、頼むから坊ちゃんって呼ばないでくれ」
「いいえ、永くご奉公させて頂きました旦那様のご子息なのですから、そう呼ばせて頂きます」きっぱりと房江が言う。
植草は肩をすくめ、話を戻した。
「それで吉田ゆかりさんは病院を辞めてからどうしたの?」
「さあ、それが全くお見かけしなくなりましてね、別の病院に移られた訳でも無さそうですし、郷里にでも戻られたのかなとお噂をしておりましたが、その内に人の口端にも上らなくなりまして……」
「房江さん、吉田さんがいなくなったのは確かに六年前なの?」房江の話を遮るように植草が尋ねる。
「ええ、今お話したとおり良く覚えております。あの頃は色々ございましてね、堀さんの愛人騒動やら何やら……ですから良く覚えております」房江が自信たっぷりに頷く。
「ああ、そんな騒ぎが有りましたね。商工会理事でこの町の有力者でもあった堀清三郎の一件でしょ? 当時、市長だった堀が東京で愛人を囲っていることがばれた。その愛人を世話したのが地元建設会社の片山建設だという噂が立った。ところが、その片山建設が市役所の新庁舎の工事請負を落札したものだから黒い噂が飛び交いましたね。俺も散々記事で書きたてたので覚えています。愛人と噂されていた黒田麗子は姿を消し、彼女の実家にまでマスコミは押しかけたが所在は掴めず仕舞いだった。その上贈収賄の確たる証拠も無く、結局は反対派が流したデマということで落ち着いたのでしたね。堀は次の市長選には落選したものの、今や商工会の会長になっている」
植草が膝を揺すっている。話が度々脱線するのでいらついているようだ。話を戻すように口を開く。
「そうすると白骨死体が死後五、六年経過、看護士が姿を消したのも六年前になるな」ポツリと呟く。
「まさか、それが事実だとすれば大変だ。先ず、警察にどこからか圧力が掛かった事。防空壕は長屋の真下にある事。その長屋を頑として取り壊さない佐々木家。そして政略結婚の妨げになる看護士が被害者となれば、犯人は……」
恐ろしい考えに思い至り栗橋が絶句する。
「一磨が怪しいと言いたいのだろ。まあ待て、そんなに軽々しく決め付けるもんじゃない。それに僕は密室の謎を解くために調査を行っているのだ。犯人が誰かなんて興味ないね」
「しかし、俺たちの幼馴染が殺人者かも判らないのだ。他人事じゃないだろ」
「だからといって我々に何が出来る? そんな事は警察に任せておけばいいさ。それより密室の謎について話を聞かないのならもう帰ってくれ」
「ちょ、ちょっと待てよ。誰も話を聞かないなんて言ってないぞ。是非聞かせてくれ」
「雄太、未だ話してなかったが昨日長屋に出向いたとき、そこの住人の喜一という爺さんに防空壕について尋ねてみた。やはり別の出入口が存在した」
「何だって、本当か」
「ハッチが壊れかけていたので六年前に頑丈な鉄板に取り替えられたそうだ」
「長屋側の防空壕ハッチが頑丈な鉄板に取り替えられたのも六年前。益々一磨が怪しいじゃないか。そう思わないか? 真一」
「奴にそんな酷いことができるかなあ。まあ犯人が誰かはさておき、別の出入口が存在するということは事件の様相が大きく異なってくる。その出口を密閉して女性を中に閉じ込めてしまえば良いだけだ。そして酸素が無くなり女性は窒息死さ」
「つまり密室の中で被害者は未だ生きていた。息が苦しくなって、唯一病院に通じるドアを何とか開けようと試みたってことか」
「そういうことさ。当然誰かが関与していたとしても、被害者が死に至る瞬間には部屋にはいない。つまり作られた密室に生きたまま幽閉された可能性が高いと言うことさ。謎でも何でもない」
「じゃ、閉じ込めた犯人は、被害者が確実に死ぬかどうか判らないじゃないか」
「そうだね。しかし余程のことが起こらない限り多分死ぬと考えていただろうさ。未必の故意になるのかな」
「この場合は密室の故意だ、なんちゃって」自分で言ったジョークに一人で受けて、栗橋は手を叩いて笑う。
そんな栗橋に房江が冷たい視線を投げる。植草も何事も無かったように話を続ける。
「やはり生きたまま幽閉したに違いない。つまり直接手を汚す事無く死に至らしめた」
「ううむ、それなら何らかの事故で閉じ込められ、そのまま窒息死した、つまり事件性の無い事故死と結論付けた警察の説明も納得がいくよな。しかしだからといって一磨が潔白という証拠にはならない。それにまだ謎は残るぞ。警察が現場に踏み込んでいるのだ。そんな別の出入り口が有れば気がつくだろう」
「恐らくコンパネか石膏ボードで即席の壁を作って塞いだのさ。裏側にLGS(簡易鉄骨)を立てれば済む」
「そんなものは壁を調べれば直ぐにばれるじゃないか」
「いいか、外気を遮断、完全密閉で換気にも濾過装置がついているほどのシェルターだ。爆撃に遭ってもびくともしない鉄板入りの壁だと誰もが思い込んでいる。警察もまさかその一部が偽造だとは夢にも思わない。先入観ってやつさ。勿論、捜査を続けていれば早晩発見されただろう。だからこそ圧力を掛けて調査を切り上げさせる必要があったのさ」
「よし、犯人はともあれ密室の謎は解けた。記事にしてもいいだろ? 真一」
「いや、待て。まだ記事にしないでくれ。それより房江さんに未だ聞きたいことが有る」
「何でございましょう、坊ちゃま」
「だから坊ちゃまは止してくれって言っているだろ」植草が苦虫を噛み潰したような表情でそうぼやきながらも先を続ける「佐々木一磨や親父さんは煙草を吸うかな?」
突然の無関係な問いかけに、栗橋と房枝は思わず顔を見合わせる。
「お二人はお医者様ですよ。健康に害になる事などなさりません。お酒も嗜む程度だと聞いています」戸惑いながら房江が答えた。
4
最終電車がK市駅を出ていく。降り立つ客の姿はまばらだ。駅前の商店街も既にシャッターが降ろされ看板の明かりも消されている。唯一の明かりは歩道に沿って並ぶ街路灯のみである。
佐々木総合病院周辺も今は真っ暗だ。その暗がりに乗じて蠢く影が四つ。
「ああん、堪んない。スリルでぞくぞくしちゃう」
「しっ、黙って歩けよ。だから来ないで良いと言ったのに」
病院とマンションの間の路地、いや隙間を蟹歩きで進みながら植草が奈緒に言う。
その日の午後のことであった。植草が外出から戻ると栗橋から電話が掛ってきたのだ。
「おい、やはり一磨は怪しいぞ」
「まだそんなことを言っているのか?」
「いいから聞けよ。今朝俺は一磨を直撃取材してきたんだ。俺の質問にのらりくらりといい加減にあしらっていやがったが、吉田ゆかりの名前を口にした途端、奴の顔色が変わったぜ。その後不機嫌になったかと思ったら癇癪を起こして、突然取材は中止だと怒鳴って俺を追い返しやがった。やはり奴は絶対怪しい」
栗橋が勢い込んで捲くし立てるのを聞きながら植草は大きくため息をついた。
「そんなに一磨を殺人者に仕立て上げたいのか?」
「真一こそ何を根拠に一磨がシロだと言い張るんだ?」
「その証拠を今夜見せてやるよ。長屋側の出入口を調査するから一緒に来いよ」
栗橋は二つ返事で承諾をしたが、計画を聞きつけた奈緒が自分も同行するといってきかなかったのだ。おまけに執事である斎藤まで連れてきている。
「兄さん、そう邪険にするものじゃ無いわ。もし悪漢に襲われでもしたら、兄さんと栗橋さんじゃてんで敵わないでしょ。私と斎藤がコテンパンに――」
「判った、判った。それより斎藤さん、大丈夫ですか」
華奢な三人と違い武術で鍛えた肉体を持つ大男の斎藤にはこの体制で歩くのは苦行に近い。うんうんと唸り体中を擦り傷だらけにしながら牛歩で進んでいる。
漸く長屋の前に辿り着いたときにはブロック塀に擦れた全員の洋服が真白になっていた。
「ああもう、嫌になっちゃう。折角のスタイルが台無し」
「どうしてそんな黒装束で来たのですか?」栗橋が呆れた顔で尋ねる。
「スパイだって忍者だってキャッツ・アイだって他人の家に侵入するには黒ずくめと相場が決まっているでしょ。ルパン三世だって、普段は赤いジャケットだけど――」
尚も言い募る彼女を遮るように植草が言う。
「頼むから静かにしてくれ。栗橋も相手にするんじゃない。大体お前たちには緊張感が無さすぎる、遊びで来ているのじゃあないんだぞ」
そう小声で叱責しながら植草はLEDのペンライトで周囲を照らす。
栗橋は後日、記事にする時のために周辺の様子を頭に叩き込む。長屋は五軒連なっており、その奥、つまり介護施設との境に少し空間があるようだ。そちらにそっと忍び寄る。
奥は共同便所になっており、その手前の地面が大きな鉄板で覆われていた。丁度下水溝か地下ケーブルの埋設箇所によく敷いてある鉄板に似ている。
「ここかな?」そう呟くと植草が鉄板を持ち上げようとするがビクともしない。
「何をぼさっと眺めている。手伝えよ」
慌てて片側を持つが二人の力でも動かない。見かねた斎藤が二人を脇に下がらせると、やおら鉄板の持ち手を掴む。「ふんむ」と唸り、鉄板を持ち上げる。
ゴトッと鈍い音と共に鉄板が動いた。
「ほら、やっぱり私たちが来て良かったでしょ」
まるで自分が持ち上げたかのように奈緒が得意げに言う。
鉄板の下は直ぐに階段となっており、一向はゆっくりとそれを降りていく。地下の地面に降り立った所で壁に突き当たる。植草がLEDのペンライトを点し周囲を照らす。左に短い廊下が続いていた。つまり階段から折れ曲がって廊下となっていたのだ。廊下の先にドアが有った。
近づいて仔細に観察する。こちら側のドアもやはりシェルター用の頑丈なドアが取り付けてあるようだ。但し病院側のドアと大きく違うのは目の前のドアが全く錆付いておらず最近まで使用していたと思われる事であった。
ドアには鍵が掛っておらず簡単に開いた。ドア横の照明スイッチをオンにする。
煌々と照らされる室内を見回し全員が驚愕の声を上げた。広さ五十坪以上はあろうかと思われる室内、そこにはソファー、ベッドやテレビなど生活に必要な家具、電気製品が揃えられており隅にはバス・トイレも完備されていた。
「シェルターだから当然と言えば当然だが、それにしても凄い装備だな。高級ワンルーム・マンションのようだ」栗橋が辺りを見回して感心する。
「やはり思ったとおり部屋の一部が間仕切りしてある。見ろよ、奥の壁を」
植草が指差す。一面頑丈な壁で仕切られているが、奥の一部分だけは軽量鉄骨がむき出しで立てられそこに石膏ボードが取り付けられてある。
ボードの表面をノックするように植草がコツコツと叩いている。
「結構な厚みが有るようだ。斎藤さん、このパネルを思い切り蹴破ってくれますか」
「大丈夫か? それ位で突き破れるんだろうか」栗橋が訝る。
「内側からだと鉄骨の支柱ががっちりと組まれていて容易に突き破れないが、こちらからだと鉄骨とパネルを留めているビスさえ外れればパネルは簡単に内側に倒れる」
「皆さんは危ないですから後ろに下がってください」
斎藤が間仕切りに対峙すると全員に声を掛け、パネルの底辺の両角を思い切り足で蹴りつける。二度、三度、徐々にパネルの下部が鉄骨から浮く。
次にパネルの上部を拳で思い切り叩く。こちらは力が入れにくくびくともしない。
「斎藤、これを使ったら」いつの間にか奈緒がハンマーを手にしている。
「お前、いつの間にそんな物を」
「兄さんたちは見通しが甘いのよ。これ位の用意周到さが無いようじゃ駄目ね。やはり私が付いてなければ何にも出来ないじゃない」奈緒が得意げに鼻を動かして言う。
兄妹が言い合う間も斎藤は上のビス止めを外していく。やがて、パネルが一枚完全に鉄骨から剥がれ、フワッと内側にたおれていった。
鉄骨をすり抜けて全員が内側の部屋に潜りこむ。
内側は三十坪程度の広さで、こちら側で白骨が発見されたのだ。
間仕切りの内側には、セメントを上塗りし本物の壁と見紛う細工が施してある。
「成る程、頑丈なシェルターといった先入観で見れば、完全にコンクリートの壁だな。植草、お前の推理は当たっていたな。しかしそうなるといよいよ犯人は一磨に決まりじゃないのか? それとも親父の琢磨か」
「だからそうじゃない。犯人は別にいる。僕にはどうしても引っ掛かる点が幾つか有って、それを調べていたんだ。昼間はわざわざ法務局にも出向いた」
「法務局? 一体何を調べに行ったんだ?」
「土地の所有者さ。面白いことが判ったよ。この一帯の土地は元々佐々木家が所有していた事は知っているな。戦前の中央病院は内科専門で、駐車場も無く建物ももっと小さかった。当時、車などそうざらに持っている人はいなかったからね。総合病院として規模を拡大したのは戦後だし、駐車場を作ったのはもっと後の八十年代になってからだ。増築や改装を重ねるたびに佐々木家は周辺の土地を売って資金にしたようだ」
「それは知っているさ。マンションや商業ビル、宅地になっているのは見れば判る」
「じゃ、介護施設はどうだ? 長屋は?」
「介護施設は佐々木家が経営しているのだろ? 長屋だって、こんな八方塞りな場所は売れないだろ」
「私もそう思っていた。病院の付属施設として介護施設が有るんだとばかり思い込んで、てっきり佐々木家が経営していると思っていたわ」奈緒も意外だった様子でそう言う。
「だが実際は違った。施設と長屋の土地も他人に売却していたんだ」
「一体誰に? いや、それよりどうして気がついたんだ?」
「今回の犯人は、すべて人間の思い込みを上手く利用している」
「どういう事だ」
「いいかい。先ず警察も関係者も全員が、頑丈なシェルターだから蟻の這い出る隙間もない密室だと思い込んでいた事。実際はご覧のとおりさ。
第二に、この一帯の土地は佐々木家が所有しており、介護施設も当然病院の関連施設だと思い込んでいた。お前たちだって先刻までそう思っていただろ。
第三は通り沿いにビルやマンションが立ち並び、長屋などとうの昔に取り壊されているものと思い込んでいた。無理もない、この土地に永く住み着いている住民ほど誤った思い込みをしているのさ。かく言う僕自身も最初はそうだった。危うく一磨を疑うところだった」
「それらのことにいつ気がついたんだ?」
「警察が乗り込んだ時の様子をお前が話してくれただろ。漠然とだが何か引っかかった。部屋の大きさは三十坪程度だと言っていたよな。患者を収容するシェルターにしては狭い。そこで親父の文書を調べたら、近隣の住民も収容することも検討されたと記載されている。それが事実なら、そんなちっぽけな規模であるはずが無い。実際の部屋はもっと大きいはずだと考えたのさ。となると位置関係から地下のシェルターは病院の敷地をはみ出していることになる。そこで長屋の存在に気がついた。
b実際の目で確かめようと長屋を訪れた際に、喜一爺さんは旦那さんに煙草を貰ったと話してくれた。その時は、佐々木琢磨の事を指していると思っていた。しかし佐々木家の親子は煙草を吸わない」
「あっ、それで房江さんに確認していたのか」やっと合点がいった栗橋が納得する。
「あの時、喜一爺さんに旦那さんとは誰のことなのか確かめるべきだった。そうすれば法務局で調べなくとも直ぐに判明した」
「で、買い取った人物は誰なのだ」
「それは――」
植草が言いかけたその時、背後から男の声がした。全員が声のするほうを振り返ると堀清三郎が猟銃を構えて立っていた。
「こんな夜更けに何の騒ぎだ。コソ泥でも無いようだが、お前たち全員不法侵入で訴えてやる。大人しくしろ」そう言ってみんなの顔をにらみつける。
「おや植草の倅にそっちは雄太か。この悪ガキ共、大人になってもやんちゃが直らんようだな」見知った顔で安心したのか堀は構えていた猟銃を下ろす。
「堀さん、この壁はいつ建てられたのですか?」植草が尋ねる。
「いつだったかなど覚えておらん。その壁が隣地との境界線だからな、壁を立てたことを人様にどうこう言われる筋合いじゃない」
「しかしこのシェルターから白骨が出たのはご存知ですよね」
「勿論、知っている。しかしあの死体は病院側にあったのだろう。私には関係のない事だ。それに警察は既に事故死で片付けたのだ。お前たちは何を余計な詮索をしている」
「堀さん、貴方がこの土地を買ったのは介護施設用地としての目的と、もう一つはこのシェルターですね。ここならば誰の目を憚ることなく好きなことが出来る。業者から賄賂を受け取る事もね。しかし、女性を幽閉したとなると事は重大です」
厳しい口調で堀を糾弾する植草の言葉に栗橋は驚いて声を上げる。
「何だって、堀さんが看護士の吉田ゆかりをここに閉じ込めたと言うのか?」
「そうじゃない。閉じ込められたのは愛人さ」
「あ、黒田麗子か……」
「おい、雄太。植草の小倅の言うことを本気にするんじゃない。どうせ当てずっぽうで喋っているのだ。おい小倅、そこまで言うなら証拠はあるのか?」
「今警察は白骨の身元割り出しにやっきになっています。だが、膨大な失踪者や家出人リストからそれを探し当てるのは不可能に近い。しかし、逆に特定の人間がその白骨であるかどうかならば即座に割り出せます。DNA、歯の治療痕など、現在の科学捜査なら分析方法は幾らでも有ります。試しに黒田麗子さんと比較して貰いましょうか?」
「ふふん、小倅が得意げにぺらぺら喋りおって、馬鹿な奴だ。今の状況が判っておらんようだな。そこまで知っているのならば不法侵入程度では済まさん。悪いがお前たちも麗子同様ここで死んでもらう」堀が再び猟銃を構えなおす。
「どうして黒田麗子さんを?」植草が問う。
「仕方が無かったのだ。戦後すぐには片田舎だったK市もいまや政令指定都市のY市に次ぐ規模に成長した。誰のお陰だと思う。第三セクターを立ち上げ、駅舎移転と新駅前の再開発。すべて私の計画と実行力が有った上での成果だ。すべてはK市市民のためを思えばこそ、なのだ。ところがそんなやり方をワンマンだと言い出す馬鹿者たちが私のスキャンダルを暴露して失脚を図ろうとした。麗子は奴等に買収され私を裏切ったのだ」
「それは、自白ととって良いのですか?」
「ああ、冥土の土産に聞かせてやろう。この土地を購入したときは地下室があるなどとは知らなかった。病院との境界線に頑丈な壁を立てて秘密の部屋として使用していたのだが彼女を殺害するのに此処を利用することを思いついたのだ。LGS(軽量鉄骨)に固定した石膏ボードの真新しい表面にセメントを塗り、泥を擦り付け、周囲の床からかき集めた埃をばら撒いた。これで新品のパネルが古びたコンクリートのような雰囲気になる。次にそのパネルの周辺に速乾セメントを塗りたくった後LGSごと立ち上げ、扉の有ったパネルの代わりにそれで空間を塞いだのだ。
完全に部屋を塞ぐ前にもう一度中の様子を覗いたが、仰臥する彼女は微動だにしない事を確認した。当然だ、睡眠薬を飲ませたからな。最後にLGSの上部を天井に渡された鉄骨とバーナーで接合し、底辺はアンカー・ボルトで固定した。
地上に繋がるハッチだが、こればかりは日曜大工レベルではどうしようもないから、自分一人の力では無理なので建築業者に既に発注をした。どうだ? これで完全な密室の完成だ。これで誰にも知られないで完全犯罪を成し遂げられる。そう、そのはずだったのだ。それをお前たちは余計なお節介を……」
「完全犯罪などありえません。それに理由はどうあれ人を簡単に死に至らしめて良い訳がない。それに貴方は自分のお陰でK市が立派な都市になったと言いますが、それが住民にとって喜ばしいことばかりじゃないのですよ。新駅前や幹線道路沿線に全国チェーンのGMSが相次ぎ出店したことで、旧駅前の地元商店街はシャッター通りと化し、次々と地上げされていった。それだけじゃない。市立病院の建設計画はリーマンショックのお陰で頓挫したままです。増加し続ける住民は中央総合病院に頼るしかないのが実情です。しかし慢性の医者不足で病床も不足している。このままではK市の医療行政は破綻をきたします。佐々木一磨はそのために交際していた女性と別れ、T大学病院の教授の娘を娶(めと)る道を選んだのです」
「そうだったのか。一磨は病院や住民の事を考えて恋人と別れたのか」
栗橋は一瞬でも一磨を疑った自分を恥じる。
「うるさい。住民すべてが満足のいく行政など夢物語だ。一部の犠牲は仕方の無いことだ。それに麗子もミイラになって即身仏としてめでたく成仏したさ。お前たちもそうしてやる」
二人が口論している隙に奈緒と斎藤がアイコンタクトを取り、じりじりと間合いを詰める。堀がそれに気づく。
「おい、動くんじゃない。そこの小娘、お前だけこっちへ来い」
「小娘? 失礼ね」膨れっ面をしながら奈緒が堀のほうに近づく。
堀は強引に奈緒の腕を引っ張り人質に取ると、栗橋に向かって命令する。
「そこの棚に麻紐のロープが有るだろう。それで他の男を後ろ手に縛り上げろ。先ずそっちの図体の大きい奴からだ。ほら、早くしろ」
堀が右手に猟銃を抱え込み、左腕で奈緒を締め付ける。
栗橋はどうしたものかと植草の顔を見る。「言われたとおりにしろ」とばかりに植草が頷く。斎藤も目だけは堀を睨みつけているが、両手を後ろに回して大人しくしている。
無理も無い、奈緒が人質に取られている以上逆らえない。
でもこの危機的状況を何とか打開出来ないものだろうか。
他の二人は堀の命令にやけに従順だが、一体どういうつもりなのだろうかと、斎藤の手首に紐をかけながら栗橋は思った。
植草が拘束されている奈緒に目で合図を送る。
その瞬間、「トウリャー」と気合のこもった声とともに、堀の身体が宙を舞う。そのまま背中から地面に叩きつけられた。
栗橋の脇をすり抜け斎藤が仰向けになった堀の上に圧し掛かる。奈緒が猟銃を奪う。
一瞬の出来事で栗橋には何が起きたのか理解できなかった。
「堀さん、人質の人選を間違えましたね。選りによって一番手強い相手を懐に呼び込んじゃ駄目です。背負い投げを誘っているようなものだ」植草が気の毒そうに言う。
「小娘なんて言うからよ」奈緒が堀に向かってアカンベーをする。
植草も斎藤も奈緒が心配で大人しくしていた訳ではなかった。逆に彼女の反撃を待ち構えていたのだ。ようやく栗橋は納得できた。
「やったぞ、これは大スクープだ」
安心した栗橋はデジタルカメラであちらこちらを撮りまくる。
「雄太、ご多忙中恐れ入るがね、先ずは警察に連絡をしたらどうだ」
植草が、堀を縛り上げる斎藤を手助けしながらそう言うのだった。
警察に連行された堀清三郎は全てを自供した。
他社より早くスクープ出来た栗橋は、自分の記事を見せびらかしながら植草に話しかける。
「幼馴染の一磨が犯人でなくて本当に良かった」
「良く言うよ。彼が犯人だと記事に書こうとしたくせに」
「面目ない。だから、あの時はまだ記事にするなと言ったのか」
「そうさ、調べるうちに真犯人は別にいると確信したからね。だが犯人ではなかったものの、一磨の行為も余り褒められたことじゃない」
「そうだな。病院や住民のためとはいえ、政略結婚のために吉田ゆかりさんを捨て、病院からも追い出したんだからな。でも彼女は郷里に戻って結婚した。今や二児の母として幸せに暮らしているそうだ」
「そうか、それを聞いて安心した」
「しかし未だに判らない。何故今まで白骨が発見されなかったんだ? あの部屋は倉庫として利用されていたのならこれまでにも人の出入りは有っただろ。ドアの窓ガラス越しに見えそうなものだが」
「普通は、すぐに照明を点けるだろ。室内が明るくなると窓は鏡のように反射して奥は見えない。今回は医者と看護士が真っ暗闇に目が慣れるまで部屋にいたからこそ見えたのさ」
「あ、成程」
「それより僕が理解できないのは、一体そんな暗闇の中で医者と看護士は何をしていたのだろうか? そちらの方が謎だ」
「何をしていた? 決まっているじゃないか。男女が人目を忍んで二人きりなんだぜ」
栗原が呆れたように言う。
「駄目よ、雄太さん。お兄さんは博識だけれど、こと男女の事となるとからっきし疎いんだから」
奈緒はそう口を挟むと栗原に向かってウインクを寄越した。
完
次にそのパネルの周辺に速乾セメントを塗りたくった後LGSごと立ち上げ、扉の有ったパネルの代わりにそれで空間を塞ぐ。
最後にLGSの上部を天井に渡された鉄骨とバーナーで接合し、底辺はアンカー・ボルトで固定する。
やっと終わった。これでどんな力が掛ろうと、少なくとも人力ではびくともしないだろう。
仕上げは地上に繋がるハッチだが、こればかりは日曜大工レベルではどうしようもない。自分一人の力では無理なので建築業者に既に発注をしてある。二日後には重量が百キロはある鉄板が取り付けられる手はずだ。
男は地上に這い出ると細巻きの煙草に火をつけ一服吹かしつけた。
「お晩でございます、先生」
突然、背後から声を掛けられ喉から心臓が飛び出そうになる。慌てて振り向くと月明かりの下で腰の曲がった老人が佇んでいた。
「ハッチが壊れたっていうんで頑丈な鉄板に替えて頂けるとか。その下見ですか? ご苦労様です。地上げ屋の買収も断って頂いて……儂なんか身寄りも無いから、ここを追い出されたら他に行く当てなどありゃしません。何とお礼を申し上げて良いのやら」
声を掛けてきた主が長屋に住む喜一(きいち)爺さんだと判り安堵する。
「いやいや、礼には及びませんよ。喜一さんたちがお元気なうちは、この長屋をどうこうはしません。安心して長生きしてください。じゃ、夜も遅いので。お休みなさい」
「はい、お休みなさい」
喜一老人の声を背中で受け、先生と呼ばれた男は暗闇の中へゆっくりと去っていった。
東京近郊のK市。一昔前は農地が広がる長閑な田園地帯であったが、都心への通勤の便が良いことからK市と共に鉄道会社が第三セクターを立ち上げ、大規模な再開発に乗り出したのがバブル全盛期。駅舎移転と新駅前の再開発を行うと共に、マンション建設や宅地造成に注力したのだった。
以後、都心に通勤するサラリーマンのベッドタウンとして人気を博し、人口が増加し続けている。新駅前や幹線道路沿線に全国チェーンのGMSが相次ぎ出店したことで、旧駅前の地元商店街はシャッター通りと化し、次々と地上げされていった。
旧駅前が昔とは様相が徐々に変化していく中で、戦前からこの地にある民間の佐々木総合病院だけは増加する人口に比例して患者数が増え活況を呈していた。
夜勤の看護士に業務引継ぎを行い、帰り支度を済ました萩原(はぎわら)裕美(ゆみ)は足早にエレベーターホールに向かっていた。
程なく到着したエレベーターに乗り込んだ彼女は1FではなくB1のボタンを押す。
途中で誰も乗って来ませんように。ゆっくりと降下するゴンドラの中で、裕美は心の中で祈る。
業務を終え私服に着替えた看護士が地下に降りていくなど、どう考えても妙である。病院のスタッフに見咎められでもしたら大変だ。万一誰かが乗り込んできても顔が見えないように操作盤の方に俯き加減に身を寄せる。
b幸いエレベーターは途中階に停止する事なく、ノンストップで地階に到着した。
左右の廊下を見やり誰もいないのを確かめると、裕美は素早くエレベーターから出て、廊下の突き当たりを更に右に折れ、建物の奥へと足早に進む。
もうここまで来れば誰に会う恐れもない。この先にあるのは遺体安置所と今は使われていない部屋があるだけだ。
遺体安置所を横目に小走りで通り過ぎ、廊下の突き当たりの部屋のドアをそっと開ける。
中は真っ暗だ。部屋に数歩足を踏み入れた途端、背後から抱きすくめられる。
「きゃっ」と声を上げる間もなく振り向かされ、口に柔らかい唇が押し当てられた。
熱い舌が口に挿入されてくると、裕美は積極的に自分から舌を絡ませる。
男性の手が胸を掴み、もう片方の手がヒップの辺りを這い回る。
飽くこと無く互いの舌を貪る間も男性の手は忙しく動き、ブラウスのボタンを外すとブラジャーをずり上げる。
「ああ、先生。乱暴にしないで」男の頭を抱え胸元に押し付ける。
「ああ、ごめんよ。もう待ちきれなくて、つい力が入ってしまった。さ、後ろを向いて。そこに机があるから両手をそこに付くんだ」
同じ内科の医師、関谷(せきや)が裕美のスカートを捲り上げる。
「やはり、ここでするの? 何だか薄気味悪くて落ち着かないわ」
「仕方ないだろ。これまでは空き病室が有ったしベッドも自由に使えたが、今は病室もベッドにも空きがない。だから総務部長に無理を言って鍵を借りてきたんだ。さあ、早く」
関谷に促され、手探りで机の端を確かめた裕美は、両手を付きヒップを後方に突き出すと、顔を真っ直ぐ正面に向ける。暗闇に目が慣れた裕美は、周囲の様子を伺う。
今は倉庫代わりに利用されているらしくキャビネットやダンボール箱が壁いっぱいに乱雑に積まれている様子がぼんやりと見える。正面突き当たりにもダンボールの重なりがあるようだが、詰まれた箱の段数が低いためその向こう側にドアが有るのに気がついた。
「ねえ、先生。この奥にも部屋が有るの?」
「ああ、僕も知らなかったが、防空壕らしい。総務部長が教えてくれたのさ」
背後に回った関谷が裕美のショーツをずりさげながら答える。
「この病院は戦前からあるだろ。空襲に備えて患者を避難させる大きな防空壕を作ったって話だ。それを先代の院長がシェルターに改造したらしい。尤ももう何十年も使用されてないし、そのドアも錆付いて開けることさえ出来ないから本当のところは誰も知らない。ベッド数が足りないって言いながらこんな部屋が手付かずだなんておかしいよな。まあ、そんなことはどうでもいいさ。今は二人だけの時間を楽しもう」
関谷が会話を切り上げる。
彼を受入れようと、顔を正面に向き直る裕美。その時、正面のドアのガラス越しに何かチラッと白いものが目に入った気がした。
「先生、待って」裕美は机から手を離し、腰に回した関谷の手を払いのけた。
「おいおい、何だよ。これからという時に」
そんな関谷に構わず身なりを整えながら、裕美は奥の部屋の目の前まで近づきドアのガラス越しに中を覗き込む。確かに何か白い物体がぼうっと浮かんでいる。
「あ、あれ見て……ミイラが――」
裕美のただならぬ様子に関谷も側に近づいて中を覗き込んだ。
「ミイラ? そんな物有る訳ないだろ。暗くて良く判らないな、明かりを点けよう」
「待って、ガラスが反射して余計に中が見えなくなるわ。先生、ペンライトを持っているでしょ」
関谷は診察用のペンライトを胸ポケットから取り出し内部を照らす。
内部は酷く荒れていて壁が崩れているのか床には土砂が散乱している。その上に覆いかぶさるようにしている人間の頭蓋骨と腕の骨がはっきりと浮かび上がる。目の窪んだ穴がじっとこちらを見詰めている。
「きゃーっ」「ウワー」二人が同時に叫ぶ。
関谷は恐怖のあまりペンライトを落とすと、愛人を置き去りにしたまま一目散に逃げ出した。
「病院からミイラ化した死体」 戦時中、生埋めになった患者の可能性も
植草真一は、関東日報の朝刊一面に大きく報じられている白骨の記事を熱心に読んでいた。
「どうだ、俺の書いた記事は? だが、その後の警察の調べでは白骨はそんなに古いものじゃ無いようだ。精々、死後五、六年って事らしい。性別は女性で年齢は三十歳前後、身長は百六十センチ、腕の骨に打撲によるヒビが見られるが、それはドアや窓ガラス、壁を叩いたためになったものと思われる。暴行や死に至るような怪我の可能性は無く餓死又は窒息死と見られ、そのため綺麗なミイラ状態で発見された――凄いな、白骨だけでこれだけの情報が読み取れるんだ」
友人で新聞記者の栗橋雄太が手帳のメモを見ながら話す。
「ふふん、白骨だから相当古いと決め付けちゃ駄目だ。動物が死ぬと先ず蛆が湧き出してくる。僕は小学生の頃、通学路途中の溝にドブネズミが死んでいるのを発見してね。それから毎日、登下校の度に観察をしていたから良く知っている。内臓を蛆が食い荒らすと同時に外側の毛や皮は、他のネズミやカラス達が剥ぎ取っていくのだ」
「うえっ、止せよ。よくそんなものを観察する気になるな」
「何を言っているのだ。厳粛な死の後に何が起きるのか見守ってやることが務めだろ」
どうしてドブネズミの最期を看取るのが務めなのか栗橋には全く理解できない。
「そして大体一年から三年もすれば白骨化する。水中で二年から五年、土中だともう少し時間が掛かって約七年から十年できれいな白骨の出来上がりさ。性別は目視でも判断出来る程男女で差がある。年齢は骨髄や化骨核の変化で推定するのさ」
「嫌ね、何の話をしているのよ」
コーヒーの入ったマグカップを三つ載せたトレーを持って部屋に入ってきた真一の妹の奈(な)緒(お)が言う。
栗橋が植草家にしょっちゅう出入りしているのは、真一と親友ということも有るが、奈緒の顔見たさでやってくるのだ。
植草家の兄妹は近隣でも評判の美男美女である。兄の真一は色白で見るからに文学青年といった雰囲気を漂わせている。一方、妹の奈緒は、黙って大人しくしていれば良家のお嬢様なのに格闘技が(それも観戦ではなく実戦が)大好きというお転婆(てんば)娘なのだ。
両親は既に他界し、大きな屋敷には二人の他に先代の頃からの住み込みの使用人が二人と愛犬が一匹いるだけである。
先祖は代々地元の郷士であり、所有する土地と資産は相当なものらしい。父親は文化人類学の研究の傍ら郷土史編纂にも尽力した人物であった。
そんな恵まれた環境の中で生まれ育ったせいなのか、植草真一には浮世離れしたところが有った。定職に就かず気儘に絵を描いたり同人誌に雑文を掲載したりしている。
彼の名前と一字違いで「僕は散歩と雑学が好き」などのエッセイで知られる植草甚一に負けず劣らず、彼も博学で世の中のありとあらゆる事象に精通している。そのため新聞記者の栗橋は良く知恵を授かりにやってくる。
今回も真一に或る謎を解明して貰おうとやってきたのであった。
「あ、奈緒さん、いつもコーヒーを有難う。変な方向に話が逸れたけど病院で見つかった白骨の話をしていたものだから」
「ああ、その事件ね。私は恋人を置き去りにして我先に逃げた医者が許せない。呆れた腰抜け野郎ね、回し蹴りでも喰らわしてやりたいわ」そう言ってトレーを持ったまま回し蹴りをする。
真正面に坐っていた栗橋の眼前ですらりと形の良い脚が空を切る。思わず仰け反ってしまう栗橋。
「おいおい、コーヒーがこぼれるぞ」
「大丈夫、ほら。体幹を鍛えているからこれくらいでは軸がぶれないわ」
「そんな事を言っているのじゃ無い。お客様の前で大股拡げて……ほら雄太がびっくりしている。自分の妹ながら嘆かわしい」
「あら、ごめんあそばせ。はい、雄太さん、コーヒーを召し上がれ」
にっこりと微笑みながらマグカップを栗橋の前に置く。
「あ、いや。どうも」しどろもどろになりながら顔を真っ赤にした栗橋が答える。
先刻、一瞬では有ったがスカートが翻った拍子に奈緒の太腿の付け根まで見えてしまったのだ。勿論、レギンスを穿いているので何が見えたという訳でもないのだが。
「それで、この件がどうしたと言うのだ」
植草に促されてやっと用件を思い出した栗橋が口を開く。
「ああ、それそれ。警察の公式発表は事故死だが実際は事件の疑いもあるようなんだ」
植草はコーヒーを飲みかけた手を止めた。
「事件? じゃあ、誰かが閉じ込めたって事か?」
「ああ、だけどそこで厄介な問題が持ち上がったんだ。担当の刑事がオフレコで教えてくれたんだが、彼が言うには、通報を受けた警察が白骨を回収するのに大変な苦労をしたらしい。と言うのも防空壕は戦後シェルターに改造したものの全く使われておらず、病室に通じるドアは完全に錆びついて開かなかったのだ。ドア自体を破壊しようにも密閉性の高い頑丈なドアだし窓ガラスも金網入りの割れない奴だ。やっとのことでそれを外したが、五、六年どころじゃ無くてもう何十年もの間そんな状態だったようだ。女性は必死で脱出を試みたのか、ドアや周りの壁の至る所に血みどろの引掻いた跡が残っていた。可哀想に余程苦しかったのだろう、何しろシェルターだから機密性が半端じゃ無い、徐々に酸素がなくなって苦しみながら死んでいったようだ」
「ちょっと待てよ。じゃあその女性はどこからその部屋に侵入できたのだ?」
「そこだよ、それが謎なんだ。閉じ込めるどころか、どうやってそこへ入れたのか? 刑事の話によると、三十坪程度の広さだそうだ。ドアは二重になっていて有事の際は頑丈なシャッターが下り完全密閉が保たれる。当然、四方は窓一つない壁が取り囲んでいる。尤も天井に濾過機能の付いた空調が備えられているが、その排気ダクトは人が入れる程大きくは無い。シェルターだから当然だろうな。だがそれが故に警察は頭を悩ませているんだ。先刻も言ったようにシャッターこそ下りてはいないが、唯一の脱出口であるドアは錆付いて動かない。つまり……」
「密室だったという訳か」
「さすが、察しが良いな。だから警察は病院のオーナーである佐々木院長親子の犯行とみて、任意で事情聴取したんだ」
「じゃあ、一磨も取調べを受けているのか?」
「当然さ、あいつは院長の息子で副院長だからな。警察は親子が何らかの方法で女性を幽閉して死なせてしまったのではないかと考えていた」
「まさか、あの一磨が……」
植草が絶句するのも当然で、佐々木一磨は彼や栗橋と同級生であり幼馴染でもあるのだった。
「心配ないさ、結局彼等も何も知らないようだし、それに……」
「ん? どうした」
「結局、警察は事故として処理したんだ、どうも何処からか圧力が掛ったようだ。それで、当時はドアが錆付いてなくて、そこから侵入したのだと無理矢理結論付けて一件落着さ。どうしてそんな場所に死体が有ったのか大きな謎で、それを解明せずに事故扱いするのは納得がいかないって担当の刑事はぼやいていたよ。彼はまだ佐々木親子をクロだと思っているんだが、現在は上司の命令で身元の確認作業に専念している。佐々木総合病院に押しかけていたマスコミも潮が引いたように雲散霧消しちまった。今は被害者探しに懸命だ。全くマスコミも勝手なものだ」
「他人事のように言うなよ。お前も、マスコミの一員じゃなかったっけ?」
「それはそうだが……」痛いところを突かれた栗橋は一瞬たじろいだが、気を取り直して話を進める。
「どうだ、真一。興味をそそられる事件だろ? 俺も事件記者としての血が騒ぐんだ。
被害者はどこから侵入したのか? 自殺なのか、はたまた他殺なのか? 他殺となると密室殺人って事になる。センセーショナルな事件だ」
「ははーん、お前の腹のうちが読めた。さしずめ僕をおだてて密室の謎を解明させ、それをスクープしようって魂胆だろ」
「密室の白骨か、面白いじゃない兄さん。どうせ暇を持て余しているのでしょ」奈緒が口を挟む。
「今は作品の仕上げに忙しいんだ」余計なことを言うんじゃないと植草が眉を顰める。
「道楽で描いている絵じゃない。どうせ売れる当てもないのだから後回しにして、雄太さんに協力してあげましょうよ」奈緒が言いにくいことをズケズケと言った。
「いいか、密室殺人なんてものは有り得ない。古今東西の推理小説では犯人が苦労して密室を構築するが、およそ現実的じゃない。今回の事件はフェル博士が指摘した内の一つ、偶発的に密室になってしまった可能性が考えられるが……」
「フェル博士って誰だ?」
「フェル博士を知らないのか? ジョン・ディクスン・カーの『三つの棺』を読んでないな」
「何だ、ミステリー小説の話か」
「密室については、コナン・ドイルやディクスン・カーのみならず、日本でも江戸川乱歩や天城一、二階堂黎人、柄刀一などがその構成要件の分類を試みている。例えば――」
「ちょっと待ってくれ。密室の講義は勘弁してくれ」栗橋が慌てて止める。
植草が薀蓄を傾け始めると一晩中でも喋り続けるのだ。
「ん? 興味があるって言うから解説してやっているのに……兎に角、密室殺人など有りえない。ドアが存在してその鍵が掛っている場合は、如何に鍵を密室に戻すかだの、犯人が部屋にいただの様々な可能性が考えられる。しかし今回はドアそのものが錆付いて開かないというのだから、うーん……これは難問だ」
その様子を見詰めていた栗橋はしめしめとほくそえんだ。気乗りがしないと言いながらもどうやら植草は謎の解明に興味を惹かれたようだ。
うまく行ったわねとでも言うように、奈緒がウインクを寄越した。
栗橋が帰った後、植草は彼が持ち込んだ謎についてじっくりと考える。密室殺人など有り得ない、絶対に何かカラクリがあるはずだ。だが、その現場はシェルターである。シェルターというからには部屋は完全に密閉されているであろうし出入口以外に蟻の這い出る隙間もないであろう。
そこまで考えて植草はふと思い出した。そういえば、佐々木総合病院の地下にシェルターが有ったという話は誰かから聞いたことがある。そうだ、親父が話していたのだ。
幼い頃の記憶を思い起こす。たしか当時は新聞の地方版にも載る程話題だったらしい。元々は戦中に防空壕として作られたそうだ。尤も物資の無い時代だからコンクリート製では無かったようで、そのままでは落盤を生じる危険性があるので、戦後になってコンクリートで補強しシェルターに作り変えたと聞いた。
当時は核シェルターっていうのが持て囃された時期だった事もあり、密閉性も強化したという。佐々木由宇磨、つまり現在の院長琢磨氏の父親だが、相当先進的な思考の持ち主だったようだ。
シェルターに改築する以前の防空壕については、親父の書き残した郷土史にも確か記述が有ったと記憶している。
早速、植草は書斎で本を探す。既に他界した父親は、彼と奈緒に様々な資産を遺してくれたが、彼が一番大事にしているのが書斎の天井近くにまでの棚にぎっしり詰め込まれた大量の書物であった。専門分野の民俗学や文化人類学に関わる書物は当然ながら、その他の人文、文芸、芸術など、多趣味だった父親らしくそのジャンルは多岐にわたる。
その中から父親が編纂した郷土史を何冊か取り出す。
たしか大戦中のことであるから昭和十五、六年から二十年の間だろうと見当をつけてページをパラパラとめくる。あった、これだ。昭和十九年の十二月。
植草は文章に目を通す。
その年の十一月に米軍は東京に始めて空襲を実施。以来翌年に跨って百回を越える空襲を行った。中でも三月の東京大空襲は罹災者が百万人を越える大規模なものだった。
空襲の標的は軍事施設ばかりでなく無差別攻撃化し民家や病院でさえ焼夷弾の餌食となっていった。当時佐々木総合病院には、戦争による多くの負傷者が運び込まれており、防空壕はそんな最中に建設されたようだ。
件の防空壕は病院の患者だけでなく、近隣の住民も避難できるように別の出入口が検討されたと有る。だが実際に作られたのかどうかについての記載は無かった。
当時の簡単な地図も掲載されており、それを見る限り防空壕自体の規模はとてつもなく広かった。おそらく百坪はありそうだ。病院の敷地は一部で、同じく佐々木家が所有する周辺一帯の住民が避難できるよう大部分は隣接する長屋や民家を含めその一画の地下に作られたようだ。
そこまで目を通して植草は意外に思う。こんな大きな防空壕とは思わなかった。たしか雄太は三十坪程度と言ってたはずだ。そのうえ、近隣の住民が避難できる別の出入口が検討されたとある。その出入口が実際に作られたかどうかは判らないが、もしそれが作られていたとするならば……。
植草は書斎を出て自分の部屋のパソコンを立ち上げる。
もし別の出入口が有るとすれば、当時の地図に記されている長屋周辺にあるはずだ。だ
が、現在はビルや宅地が立ち並び、既に長屋などは取り壊されている。
正確な現状を把握しようと、グーグル・マップの衛星写真を開き調べる。その結果、周辺の長屋や民家は立ち退き、跡地に新しい住宅やビルが建てられているが、唯一病院の裏手に今でも長屋が存続することが判明した。
翌日、実際に現地をこの目で確認しようと目的地にやってきた植草真一はその場で天を見上げた。周りを背の高いビルに取り囲まれ、まるでそこだけが四角く切り取られたように、青空と白い雲がぽっかりと浮かび上がっているように見えた。
この長屋に陽射しが当たるのは一日の内のほんの数時間、いや一時間程度であろうか? そう考えながら、視線を長屋に戻す。よくこんな場所に古い長屋が残っていたものだ。この場所だけが昭和のまま取り残されているように思えた。
「こんにちは。何かこの長屋に用ですかな?」
いつの間にか傍らに煙草を手にした老人が近づいていた。
「あ、いえ。僕は郷土の歴史を調査している者なのですが、確かこの辺りに昔の防空壕が残っているとお伺いしたものですから……その件について何かご存知じゃ有りませんか」
「ああ、そう言えばもう何十年も前に同じように調査に来られた方がおりましたな。偉い学者さんで、確か植草さんと仰いましたかな」
「それは僕の父です」
「おお、そうでしたか。あの方のご子息でいらっしゃる、そうですか」
老人は満面の笑みを浮かべ、うんうんと一人で頷く。「ほれ、そこの足元の鉄板が防空壕への入口ですじゃ」
植草は老人の指差す地面に膝まずき、鉄板の持ち手に手を掛けた。
「無理じゃ。あんた一人の力では持ち上がりませんわな。従来は粗末な木の扉だったのじゃが、あれは六年ほど前になるかのう、旦那さんが危険じゃからと頑丈な鉄板に取替えられたのじゃ。今のように平和な時代にはもう用のないものじゃからのう」
老人は地主の佐々木琢磨の事を旦那さんと呼んでいるようだ。植草は汚れた手をはたき、諦めて立ち上がる。
「そうですか、残念です、中を見たかったのですが……」もう一度辺りを見回し老人に話しかける。「昔はこの辺りは木造建築や長屋が多かったのに、いつの間にかここだけになってしまったのですね」
「旦那さんのお陰でのう。儂等が住んでおる間は取り壊さんと、目の前のビルが建つ時も土地売却の話を断って下さったんじゃ」
そう言って老人は美味そうに煙草をふかした。
「良い香りですね。おや、ダビドフのマグナムじゃないですか。高級煙草ですね」
「いやいや、儂はもっぱらゴールデンバットなんじゃが、これは旦那さんからの貰いものでのう」
そう言って目を細める老人に改めて礼を述べると植草はその場を後にした。
植草は家に戻ると早速栗橋に連絡をした。栗橋が再び植草家を訪れたのは夕方近かった。
「やはり親父の郷土史に防空壕の記載が有ったぞ。だが三十坪どころの規模じゃない。あの一画の地下がすべて防空壕になっていたようだ。そして別の出入口が長屋の下にあった」開口一番、そう言って植草は調査の結果を栗橋に話して聞かせた。
「ちょ、ちょっと待てよ。長屋だって? 長屋なんてどこに有るんだ。あの一画は北西向きに病院と外来用の駐車場だろ。駐車場の角は本通りに面していて、右折して駐車場沿いに歩いていくとマンションだ。その建物は南東の駅前通りまで続く。駅前通りはマンションの隣に商業ビルと民家だ。そこで南西の公園通りにぶつかる。角を曲がって立ち並ぶ民家の隣はもう介護施設と病院だ。これで時計回りに一周してスタート地点に戻る。長屋などどこにも無いぞ」
栗橋が言い募ると、植草は「実は僕も知らなかったんだ」と言いながらパソコンを立ち上げ、グーグルを開いた。
「良く見てみろ。その一角の中心に木造の建物があるだろ」
そう言われて栗橋はモニターを凝視する。
確かに植草の指摘どおり病院、マンション、ビル、介護施設に四方を囲まれた建物が存在した。
「しかし、ここの住民はどこから出入りしているのだ? これじゃあ、陸の孤島状態じゃ無いか」
「長屋の住民は介護施設の中庭から出入り出来るようになっている。まあ、実際はマンションと外来駐車場との狭い路地から行き来しているようだがね。そっちのほうが通りへ出るのは近いし、駅もそちらの方向だ」
「へえ、昨日すぐに調べてくれたのか。待てよ、思い出した。そう言われればビルや介護施設が建つ前は、あの一帯は古びた民家や長屋だったな」
「そうでございますよ、それでも当時としては立派なものでございました。今でこそ瀟洒な家が多くなりましたが昔は田んぼや野っ原ばかりが目立つ片田舎でございましたからねえ。簡素なバラック同然の家が多くございました」
声のするほうを見上げると、住込み家政婦の牧原房(まきはらふさ)江(え)が茶菓子を盆に載せて立っていた。
「あ、房江さん。お邪魔しています。奈緒さんはお出かけですか?」
「ふふ、お茶を入れたのがお嬢様で無くて、皺くちゃ婆でお気の毒様」
栗橋の下心を見透かしたように言う。
「いやそんな。それより話を続けて下さい」顔を真っ赤にしながら栗橋が先を促す。
そんな様子をにこやかに見詰めながら房江が話を続ける。
「はいはい。あの一角もどんどん長屋や古い家が取り壊されて、立派な建物に変わっていったのですよ。ビルがバブルの頃、平成になってマンションが建ち、一番最近建てられたのが介護施設だったですかしらねえ。六年前の事でございます」
「へえ、房江さん良く覚えているのですね」
「そりゃもう。なんせ佐々木家の坊ちゃんが、ご結婚された年ですから」
「他人の結婚した年を覚えているのですか」
そう栗橋が感心すると、房江は片手を顔の前で左右に振った。
「いいえ、その為に看護婦の吉田さんがお辞めになったので良く覚えているのでございます。本当に綺麗で優しくて思いやりのある良い看護婦さんでしたのに」
「房江さん、今は看護婦じゃ無くて看護士です。で、その吉田さんの退職と病院長の息子、一磨(かずま)の結婚とどう関係が……あ、ひょっとして」
「そうなのでございます。人様の内情を軽々しく口には出来ないのですが、一磨坊ちゃんと吉田ゆかりさんは秘かにお付き合いをされていらして……」
「一磨って奴は昔からもてたからね」
栗橋と植草は佐々木一磨とは同い年で小学校、中学校と同級の仲であった。
「そうか奴が別の女性と結婚したので、病院に居づらくなったのか」
「一磨坊ちゃんは酷い男でございます。吉田さんを散々おもちゃにしておいて、ご自身は以前いらしたT大学病院の教授に気に入られて、そのご息女をお娶りになったのです。口さがの無い連中は政略結婚だと噂しております」
「政略結婚? ほう、それはどうして?」
「T大学病院と縁故が出来て、週に何回か若い医者を派遣してもらっているのだそうですよ。今はどこも医者不足でございましょう? ご多分に漏れず佐々木病院も総合病院ですから手が足りなくて困っていらしたそうです」
「やけに詳しいですね。だけど人様の内情を軽々しく口にして大丈夫なんですか」
栗橋の問いかけに植草が答える。
「房江さんにとって病院はご近所の老人との憩いの場、井戸端会議の場なのだ。どうせ仲の良い婦長からの情報だろ? て事は町内の長老連中には知れ渡っているさ」
「あら、いやですわ坊ちゃま。まるで人をスピーカーみたく仰らないで下さいまし」
そう言って房江はまるで少女のように恥じらい頬を染めた。可憐な乙女ならいざ知らず、皺くちゃ婆さんの仕草である。その不気味さに栗橋は少し背筋が寒くなった。
「房江さん、頼むから坊ちゃんって呼ばないでくれ」
「いいえ、永くご奉公させて頂きました旦那様のご子息なのですから、そう呼ばせて頂きます」きっぱりと房江が言う。
植草は肩をすくめ、話を戻した。
「それで吉田ゆかりさんは病院を辞めてからどうしたの?」
「さあ、それが全くお見かけしなくなりましてね、別の病院に移られた訳でも無さそうですし、郷里にでも戻られたのかなとお噂をしておりましたが、その内に人の口端にも上らなくなりまして……」
「房江さん、吉田さんがいなくなったのは確かに六年前なの?」房江の話を遮るように植草が尋ねる。
「ええ、今お話したとおり良く覚えております。あの頃は色々ございましてね、堀さんの愛人騒動やら何やら……ですから良く覚えております」房江が自信たっぷりに頷く。
「ああ、そんな騒ぎが有りましたね。商工会理事でこの町の有力者でもあった堀清三郎の一件でしょ? 当時、市長だった堀が東京で愛人を囲っていることがばれた。その愛人を世話したのが地元建設会社の片山建設だという噂が立った。ところが、その片山建設が市役所の新庁舎の工事請負を落札したものだから黒い噂が飛び交いましたね。俺も散々記事で書きたてたので覚えています。愛人と噂されていた黒田麗子は姿を消し、彼女の実家にまでマスコミは押しかけたが所在は掴めず仕舞いだった。その上贈収賄の確たる証拠も無く、結局は反対派が流したデマということで落ち着いたのでしたね。堀は次の市長選には落選したものの、今や商工会の会長になっている」
植草が膝を揺すっている。話が度々脱線するのでいらついているようだ。話を戻すように口を開く。
「そうすると白骨死体が死後五、六年経過、看護士が姿を消したのも六年前になるな」ポツリと呟く。
「まさか、それが事実だとすれば大変だ。先ず、警察にどこからか圧力が掛かった事。防空壕は長屋の真下にある事。その長屋を頑として取り壊さない佐々木家。そして政略結婚の妨げになる看護士が被害者となれば、犯人は……」
恐ろしい考えに思い至り栗橋が絶句する。
「一磨が怪しいと言いたいのだろ。まあ待て、そんなに軽々しく決め付けるもんじゃない。それに僕は密室の謎を解くために調査を行っているのだ。犯人が誰かなんて興味ないね」
「しかし、俺たちの幼馴染が殺人者かも判らないのだ。他人事じゃないだろ」
「だからといって我々に何が出来る? そんな事は警察に任せておけばいいさ。それより密室の謎について話を聞かないのならもう帰ってくれ」
「ちょ、ちょっと待てよ。誰も話を聞かないなんて言ってないぞ。是非聞かせてくれ」
「雄太、未だ話してなかったが昨日長屋に出向いたとき、そこの住人の喜一という爺さんに防空壕について尋ねてみた。やはり別の出入口が存在した」
「何だって、本当か」
「ハッチが壊れかけていたので六年前に頑丈な鉄板に取り替えられたそうだ」
「長屋側の防空壕ハッチが頑丈な鉄板に取り替えられたのも六年前。益々一磨が怪しいじゃないか。そう思わないか? 真一」
「奴にそんな酷いことができるかなあ。まあ犯人が誰かはさておき、別の出入口が存在するということは事件の様相が大きく異なってくる。その出口を密閉して女性を中に閉じ込めてしまえば良いだけだ。そして酸素が無くなり女性は窒息死さ」
「つまり密室の中で被害者は未だ生きていた。息が苦しくなって、唯一病院に通じるドアを何とか開けようと試みたってことか」
「そういうことさ。当然誰かが関与していたとしても、被害者が死に至る瞬間には部屋にはいない。つまり作られた密室に生きたまま幽閉された可能性が高いと言うことさ。謎でも何でもない」
「じゃ、閉じ込めた犯人は、被害者が確実に死ぬかどうか判らないじゃないか」
「そうだね。しかし余程のことが起こらない限り多分死ぬと考えていただろうさ。未必の故意になるのかな」
「この場合は密室の故意だ、なんちゃって」自分で言ったジョークに一人で受けて、栗橋は手を叩いて笑う。
そんな栗橋に房江が冷たい視線を投げる。植草も何事も無かったように話を続ける。
「やはり生きたまま幽閉したに違いない。つまり直接手を汚す事無く死に至らしめた」
「ううむ、それなら何らかの事故で閉じ込められ、そのまま窒息死した、つまり事件性の無い事故死と結論付けた警察の説明も納得がいくよな。しかしだからといって一磨が潔白という証拠にはならない。それにまだ謎は残るぞ。警察が現場に踏み込んでいるのだ。そんな別の出入り口が有れば気がつくだろう」
「恐らくコンパネか石膏ボードで即席の壁を作って塞いだのさ。裏側にLGS(簡易鉄骨)を立てれば済む」
「そんなものは壁を調べれば直ぐにばれるじゃないか」
「いいか、外気を遮断、完全密閉で換気にも濾過装置がついているほどのシェルターだ。爆撃に遭ってもびくともしない鉄板入りの壁だと誰もが思い込んでいる。警察もまさかその一部が偽造だとは夢にも思わない。先入観ってやつさ。勿論、捜査を続けていれば早晩発見されただろう。だからこそ圧力を掛けて調査を切り上げさせる必要があったのさ」
「よし、犯人はともあれ密室の謎は解けた。記事にしてもいいだろ? 真一」
「いや、待て。まだ記事にしないでくれ。それより房江さんに未だ聞きたいことが有る」
「何でございましょう、坊ちゃま」
「だから坊ちゃまは止してくれって言っているだろ」植草が苦虫を噛み潰したような表情でそうぼやきながらも先を続ける「佐々木一磨や親父さんは煙草を吸うかな?」
突然の無関係な問いかけに、栗橋と房枝は思わず顔を見合わせる。
「お二人はお医者様ですよ。健康に害になる事などなさりません。お酒も嗜む程度だと聞いています」戸惑いながら房江が答えた。
4
最終電車がK市駅を出ていく。降り立つ客の姿はまばらだ。駅前の商店街も既にシャッターが降ろされ看板の明かりも消されている。唯一の明かりは歩道に沿って並ぶ街路灯のみである。
佐々木総合病院周辺も今は真っ暗だ。その暗がりに乗じて蠢く影が四つ。
「ああん、堪んない。スリルでぞくぞくしちゃう」
「しっ、黙って歩けよ。だから来ないで良いと言ったのに」
病院とマンションの間の路地、いや隙間を蟹歩きで進みながら植草が奈緒に言う。
その日の午後のことであった。植草が外出から戻ると栗橋から電話が掛ってきたのだ。
「おい、やはり一磨は怪しいぞ」
「まだそんなことを言っているのか?」
「いいから聞けよ。今朝俺は一磨を直撃取材してきたんだ。俺の質問にのらりくらりといい加減にあしらっていやがったが、吉田ゆかりの名前を口にした途端、奴の顔色が変わったぜ。その後不機嫌になったかと思ったら癇癪を起こして、突然取材は中止だと怒鳴って俺を追い返しやがった。やはり奴は絶対怪しい」
栗橋が勢い込んで捲くし立てるのを聞きながら植草は大きくため息をついた。
「そんなに一磨を殺人者に仕立て上げたいのか?」
「真一こそ何を根拠に一磨がシロだと言い張るんだ?」
「その証拠を今夜見せてやるよ。長屋側の出入口を調査するから一緒に来いよ」
栗橋は二つ返事で承諾をしたが、計画を聞きつけた奈緒が自分も同行するといってきかなかったのだ。おまけに執事である斎藤まで連れてきている。
「兄さん、そう邪険にするものじゃ無いわ。もし悪漢に襲われでもしたら、兄さんと栗橋さんじゃてんで敵わないでしょ。私と斎藤がコテンパンに――」
「判った、判った。それより斎藤さん、大丈夫ですか」
華奢な三人と違い武術で鍛えた肉体を持つ大男の斎藤にはこの体制で歩くのは苦行に近い。うんうんと唸り体中を擦り傷だらけにしながら牛歩で進んでいる。
漸く長屋の前に辿り着いたときにはブロック塀に擦れた全員の洋服が真白になっていた。
「ああもう、嫌になっちゃう。折角のスタイルが台無し」
「どうしてそんな黒装束で来たのですか?」栗橋が呆れた顔で尋ねる。
「スパイだって忍者だってキャッツ・アイだって他人の家に侵入するには黒ずくめと相場が決まっているでしょ。ルパン三世だって、普段は赤いジャケットだけど――」
尚も言い募る彼女を遮るように植草が言う。
「頼むから静かにしてくれ。栗橋も相手にするんじゃない。大体お前たちには緊張感が無さすぎる、遊びで来ているのじゃあないんだぞ」
そう小声で叱責しながら植草はLEDのペンライトで周囲を照らす。
栗橋は後日、記事にする時のために周辺の様子を頭に叩き込む。長屋は五軒連なっており、その奥、つまり介護施設との境に少し空間があるようだ。そちらにそっと忍び寄る。
奥は共同便所になっており、その手前の地面が大きな鉄板で覆われていた。丁度下水溝か地下ケーブルの埋設箇所によく敷いてある鉄板に似ている。
「ここかな?」そう呟くと植草が鉄板を持ち上げようとするがビクともしない。
「何をぼさっと眺めている。手伝えよ」
慌てて片側を持つが二人の力でも動かない。見かねた斎藤が二人を脇に下がらせると、やおら鉄板の持ち手を掴む。「ふんむ」と唸り、鉄板を持ち上げる。
ゴトッと鈍い音と共に鉄板が動いた。
「ほら、やっぱり私たちが来て良かったでしょ」
まるで自分が持ち上げたかのように奈緒が得意げに言う。
鉄板の下は直ぐに階段となっており、一向はゆっくりとそれを降りていく。地下の地面に降り立った所で壁に突き当たる。植草がLEDのペンライトを点し周囲を照らす。左に短い廊下が続いていた。つまり階段から折れ曲がって廊下となっていたのだ。廊下の先にドアが有った。
近づいて仔細に観察する。こちら側のドアもやはりシェルター用の頑丈なドアが取り付けてあるようだ。但し病院側のドアと大きく違うのは目の前のドアが全く錆付いておらず最近まで使用していたと思われる事であった。
ドアには鍵が掛っておらず簡単に開いた。ドア横の照明スイッチをオンにする。
煌々と照らされる室内を見回し全員が驚愕の声を上げた。広さ五十坪以上はあろうかと思われる室内、そこにはソファー、ベッドやテレビなど生活に必要な家具、電気製品が揃えられており隅にはバス・トイレも完備されていた。
「シェルターだから当然と言えば当然だが、それにしても凄い装備だな。高級ワンルーム・マンションのようだ」栗橋が辺りを見回して感心する。
「やはり思ったとおり部屋の一部が間仕切りしてある。見ろよ、奥の壁を」
植草が指差す。一面頑丈な壁で仕切られているが、奥の一部分だけは軽量鉄骨がむき出しで立てられそこに石膏ボードが取り付けられてある。
ボードの表面をノックするように植草がコツコツと叩いている。
「結構な厚みが有るようだ。斎藤さん、このパネルを思い切り蹴破ってくれますか」
「大丈夫か? それ位で突き破れるんだろうか」栗橋が訝る。
「内側からだと鉄骨の支柱ががっちりと組まれていて容易に突き破れないが、こちらからだと鉄骨とパネルを留めているビスさえ外れればパネルは簡単に内側に倒れる」
「皆さんは危ないですから後ろに下がってください」
斎藤が間仕切りに対峙すると全員に声を掛け、パネルの底辺の両角を思い切り足で蹴りつける。二度、三度、徐々にパネルの下部が鉄骨から浮く。
次にパネルの上部を拳で思い切り叩く。こちらは力が入れにくくびくともしない。
「斎藤、これを使ったら」いつの間にか奈緒がハンマーを手にしている。
「お前、いつの間にそんな物を」
「兄さんたちは見通しが甘いのよ。これ位の用意周到さが無いようじゃ駄目ね。やはり私が付いてなければ何にも出来ないじゃない」奈緒が得意げに鼻を動かして言う。
兄妹が言い合う間も斎藤は上のビス止めを外していく。やがて、パネルが一枚完全に鉄骨から剥がれ、フワッと内側にたおれていった。
鉄骨をすり抜けて全員が内側の部屋に潜りこむ。
内側は三十坪程度の広さで、こちら側で白骨が発見されたのだ。
間仕切りの内側には、セメントを上塗りし本物の壁と見紛う細工が施してある。
「成る程、頑丈なシェルターといった先入観で見れば、完全にコンクリートの壁だな。植草、お前の推理は当たっていたな。しかしそうなるといよいよ犯人は一磨に決まりじゃないのか? それとも親父の琢磨か」
「だからそうじゃない。犯人は別にいる。僕にはどうしても引っ掛かる点が幾つか有って、それを調べていたんだ。昼間はわざわざ法務局にも出向いた」
「法務局? 一体何を調べに行ったんだ?」
「土地の所有者さ。面白いことが判ったよ。この一帯の土地は元々佐々木家が所有していた事は知っているな。戦前の中央病院は内科専門で、駐車場も無く建物ももっと小さかった。当時、車などそうざらに持っている人はいなかったからね。総合病院として規模を拡大したのは戦後だし、駐車場を作ったのはもっと後の八十年代になってからだ。増築や改装を重ねるたびに佐々木家は周辺の土地を売って資金にしたようだ」
「それは知っているさ。マンションや商業ビル、宅地になっているのは見れば判る」
「じゃ、介護施設はどうだ? 長屋は?」
「介護施設は佐々木家が経営しているのだろ? 長屋だって、こんな八方塞りな場所は売れないだろ」
「私もそう思っていた。病院の付属施設として介護施設が有るんだとばかり思い込んで、てっきり佐々木家が経営していると思っていたわ」奈緒も意外だった様子でそう言う。
「だが実際は違った。施設と長屋の土地も他人に売却していたんだ」
「一体誰に? いや、それよりどうして気がついたんだ?」
「今回の犯人は、すべて人間の思い込みを上手く利用している」
「どういう事だ」
「いいかい。先ず警察も関係者も全員が、頑丈なシェルターだから蟻の這い出る隙間もない密室だと思い込んでいた事。実際はご覧のとおりさ。
第二に、この一帯の土地は佐々木家が所有しており、介護施設も当然病院の関連施設だと思い込んでいた。お前たちだって先刻までそう思っていただろ。
第三は通り沿いにビルやマンションが立ち並び、長屋などとうの昔に取り壊されているものと思い込んでいた。無理もない、この土地に永く住み着いている住民ほど誤った思い込みをしているのさ。かく言う僕自身も最初はそうだった。危うく一磨を疑うところだった」
「それらのことにいつ気がついたんだ?」
「警察が乗り込んだ時の様子をお前が話してくれただろ。漠然とだが何か引っかかった。部屋の大きさは三十坪程度だと言っていたよな。患者を収容するシェルターにしては狭い。そこで親父の文書を調べたら、近隣の住民も収容することも検討されたと記載されている。それが事実なら、そんなちっぽけな規模であるはずが無い。実際の部屋はもっと大きいはずだと考えたのさ。となると位置関係から地下のシェルターは病院の敷地をはみ出していることになる。そこで長屋の存在に気がついた。
b実際の目で確かめようと長屋を訪れた際に、喜一爺さんは旦那さんに煙草を貰ったと話してくれた。その時は、佐々木琢磨の事を指していると思っていた。しかし佐々木家の親子は煙草を吸わない」
「あっ、それで房江さんに確認していたのか」やっと合点がいった栗橋が納得する。
「あの時、喜一爺さんに旦那さんとは誰のことなのか確かめるべきだった。そうすれば法務局で調べなくとも直ぐに判明した」
「で、買い取った人物は誰なのだ」
「それは――」
植草が言いかけたその時、背後から男の声がした。全員が声のするほうを振り返ると堀清三郎が猟銃を構えて立っていた。
「こんな夜更けに何の騒ぎだ。コソ泥でも無いようだが、お前たち全員不法侵入で訴えてやる。大人しくしろ」そう言ってみんなの顔をにらみつける。
「おや植草の倅にそっちは雄太か。この悪ガキ共、大人になってもやんちゃが直らんようだな」見知った顔で安心したのか堀は構えていた猟銃を下ろす。
「堀さん、この壁はいつ建てられたのですか?」植草が尋ねる。
「いつだったかなど覚えておらん。その壁が隣地との境界線だからな、壁を立てたことを人様にどうこう言われる筋合いじゃない」
「しかしこのシェルターから白骨が出たのはご存知ですよね」
「勿論、知っている。しかしあの死体は病院側にあったのだろう。私には関係のない事だ。それに警察は既に事故死で片付けたのだ。お前たちは何を余計な詮索をしている」
「堀さん、貴方がこの土地を買ったのは介護施設用地としての目的と、もう一つはこのシェルターですね。ここならば誰の目を憚ることなく好きなことが出来る。業者から賄賂を受け取る事もね。しかし、女性を幽閉したとなると事は重大です」
厳しい口調で堀を糾弾する植草の言葉に栗橋は驚いて声を上げる。
「何だって、堀さんが看護士の吉田ゆかりをここに閉じ込めたと言うのか?」
「そうじゃない。閉じ込められたのは愛人さ」
「あ、黒田麗子か……」
「おい、雄太。植草の小倅の言うことを本気にするんじゃない。どうせ当てずっぽうで喋っているのだ。おい小倅、そこまで言うなら証拠はあるのか?」
「今警察は白骨の身元割り出しにやっきになっています。だが、膨大な失踪者や家出人リストからそれを探し当てるのは不可能に近い。しかし、逆に特定の人間がその白骨であるかどうかならば即座に割り出せます。DNA、歯の治療痕など、現在の科学捜査なら分析方法は幾らでも有ります。試しに黒田麗子さんと比較して貰いましょうか?」
「ふふん、小倅が得意げにぺらぺら喋りおって、馬鹿な奴だ。今の状況が判っておらんようだな。そこまで知っているのならば不法侵入程度では済まさん。悪いがお前たちも麗子同様ここで死んでもらう」堀が再び猟銃を構えなおす。
「どうして黒田麗子さんを?」植草が問う。
「仕方が無かったのだ。戦後すぐには片田舎だったK市もいまや政令指定都市のY市に次ぐ規模に成長した。誰のお陰だと思う。第三セクターを立ち上げ、駅舎移転と新駅前の再開発。すべて私の計画と実行力が有った上での成果だ。すべてはK市市民のためを思えばこそ、なのだ。ところがそんなやり方をワンマンだと言い出す馬鹿者たちが私のスキャンダルを暴露して失脚を図ろうとした。麗子は奴等に買収され私を裏切ったのだ」
「それは、自白ととって良いのですか?」
「ああ、冥土の土産に聞かせてやろう。この土地を購入したときは地下室があるなどとは知らなかった。病院との境界線に頑丈な壁を立てて秘密の部屋として使用していたのだが彼女を殺害するのに此処を利用することを思いついたのだ。LGS(軽量鉄骨)に固定した石膏ボードの真新しい表面にセメントを塗り、泥を擦り付け、周囲の床からかき集めた埃をばら撒いた。これで新品のパネルが古びたコンクリートのような雰囲気になる。次にそのパネルの周辺に速乾セメントを塗りたくった後LGSごと立ち上げ、扉の有ったパネルの代わりにそれで空間を塞いだのだ。
完全に部屋を塞ぐ前にもう一度中の様子を覗いたが、仰臥する彼女は微動だにしない事を確認した。当然だ、睡眠薬を飲ませたからな。最後にLGSの上部を天井に渡された鉄骨とバーナーで接合し、底辺はアンカー・ボルトで固定した。
地上に繋がるハッチだが、こればかりは日曜大工レベルではどうしようもないから、自分一人の力では無理なので建築業者に既に発注をした。どうだ? これで完全な密室の完成だ。これで誰にも知られないで完全犯罪を成し遂げられる。そう、そのはずだったのだ。それをお前たちは余計なお節介を……」
「完全犯罪などありえません。それに理由はどうあれ人を簡単に死に至らしめて良い訳がない。それに貴方は自分のお陰でK市が立派な都市になったと言いますが、それが住民にとって喜ばしいことばかりじゃないのですよ。新駅前や幹線道路沿線に全国チェーンのGMSが相次ぎ出店したことで、旧駅前の地元商店街はシャッター通りと化し、次々と地上げされていった。それだけじゃない。市立病院の建設計画はリーマンショックのお陰で頓挫したままです。増加し続ける住民は中央総合病院に頼るしかないのが実情です。しかし慢性の医者不足で病床も不足している。このままではK市の医療行政は破綻をきたします。佐々木一磨はそのために交際していた女性と別れ、T大学病院の教授の娘を娶(めと)る道を選んだのです」
「そうだったのか。一磨は病院や住民の事を考えて恋人と別れたのか」
栗橋は一瞬でも一磨を疑った自分を恥じる。
「うるさい。住民すべてが満足のいく行政など夢物語だ。一部の犠牲は仕方の無いことだ。それに麗子もミイラになって即身仏としてめでたく成仏したさ。お前たちもそうしてやる」
二人が口論している隙に奈緒と斎藤がアイコンタクトを取り、じりじりと間合いを詰める。堀がそれに気づく。
「おい、動くんじゃない。そこの小娘、お前だけこっちへ来い」
「小娘? 失礼ね」膨れっ面をしながら奈緒が堀のほうに近づく。
堀は強引に奈緒の腕を引っ張り人質に取ると、栗橋に向かって命令する。
「そこの棚に麻紐のロープが有るだろう。それで他の男を後ろ手に縛り上げろ。先ずそっちの図体の大きい奴からだ。ほら、早くしろ」
堀が右手に猟銃を抱え込み、左腕で奈緒を締め付ける。
栗橋はどうしたものかと植草の顔を見る。「言われたとおりにしろ」とばかりに植草が頷く。斎藤も目だけは堀を睨みつけているが、両手を後ろに回して大人しくしている。
無理も無い、奈緒が人質に取られている以上逆らえない。
でもこの危機的状況を何とか打開出来ないものだろうか。
他の二人は堀の命令にやけに従順だが、一体どういうつもりなのだろうかと、斎藤の手首に紐をかけながら栗橋は思った。
植草が拘束されている奈緒に目で合図を送る。
その瞬間、「トウリャー」と気合のこもった声とともに、堀の身体が宙を舞う。そのまま背中から地面に叩きつけられた。
栗橋の脇をすり抜け斎藤が仰向けになった堀の上に圧し掛かる。奈緒が猟銃を奪う。
一瞬の出来事で栗橋には何が起きたのか理解できなかった。
「堀さん、人質の人選を間違えましたね。選りによって一番手強い相手を懐に呼び込んじゃ駄目です。背負い投げを誘っているようなものだ」植草が気の毒そうに言う。
「小娘なんて言うからよ」奈緒が堀に向かってアカンベーをする。
植草も斎藤も奈緒が心配で大人しくしていた訳ではなかった。逆に彼女の反撃を待ち構えていたのだ。ようやく栗橋は納得できた。
「やったぞ、これは大スクープだ」
安心した栗橋はデジタルカメラであちらこちらを撮りまくる。
「雄太、ご多忙中恐れ入るがね、先ずは警察に連絡をしたらどうだ」
植草が、堀を縛り上げる斎藤を手助けしながらそう言うのだった。
警察に連行された堀清三郎は全てを自供した。
他社より早くスクープ出来た栗橋は、自分の記事を見せびらかしながら植草に話しかける。
「幼馴染の一磨が犯人でなくて本当に良かった」
「良く言うよ。彼が犯人だと記事に書こうとしたくせに」
「面目ない。だから、あの時はまだ記事にするなと言ったのか」
「そうさ、調べるうちに真犯人は別にいると確信したからね。だが犯人ではなかったものの、一磨の行為も余り褒められたことじゃない」
「そうだな。病院や住民のためとはいえ、政略結婚のために吉田ゆかりさんを捨て、病院からも追い出したんだからな。でも彼女は郷里に戻って結婚した。今や二児の母として幸せに暮らしているそうだ」
「そうか、それを聞いて安心した」
「しかし未だに判らない。何故今まで白骨が発見されなかったんだ? あの部屋は倉庫として利用されていたのならこれまでにも人の出入りは有っただろ。ドアの窓ガラス越しに見えそうなものだが」
「普通は、すぐに照明を点けるだろ。室内が明るくなると窓は鏡のように反射して奥は見えない。今回は医者と看護士が真っ暗闇に目が慣れるまで部屋にいたからこそ見えたのさ」
「あ、成程」
「それより僕が理解できないのは、一体そんな暗闇の中で医者と看護士は何をしていたのだろうか? そちらの方が謎だ」
「何をしていた? 決まっているじゃないか。男女が人目を忍んで二人きりなんだぜ」
栗原が呆れたように言う。
「駄目よ、雄太さん。お兄さんは博識だけれど、こと男女の事となるとからっきし疎いんだから」
奈緒はそう口を挟むと栗原に向かってウインクを寄越した。
完
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

マチコアイシテル
白河甚平@壺
ミステリー
行きつけのスナックへふらりと寄る大学生の豊(ゆたか)。
常連客の小児科の中田と子犬を抱きかかえた良太くんと話しをしていると
ママが帰ってきたのと同時に、滑り込むように男がドアから入りカウンターへと腰をかけに行った。
見るとその男はサラリーマン風で、胸のワイシャツから真っ赤な血をにじみ出していた。
スナックのママはその血まみれの男を恐れず近寄り、男に慰めの言葉をかける。
豊はママの身が心配になり二人に近づこうとするが、突然、胸が灼けるような痛みを感じ彼は床の上でのた打ち回る。
どうやら豊は血まみれの男と一心同体になってしまったらしい。
さっきまでカウンターにいた男はいつのまにやら消えてしまっていた・・・

時雨荘
葉羽
ミステリー
時雨荘という静かな山間の別荘で、著名な作家・鳴海陽介が刺殺される事件が発生する。高校生の天才探偵、葉羽は幼馴染の彩由美と共に事件の謎を解明するために動き出す。警察の捜査官である白石涼と協力し、葉羽は容疑者として、鳴海の部下桐生蓮、元恋人水無月花音、ビジネスパートナー九条蒼士の三人に注目する。
調査を進める中で、葉羽はそれぞれの容疑者が抱える嫉妬や未練、過去の関係が事件にどのように影響しているのかを探る。特に、鳴海が残した暗号が事件の鍵になる可能性があることに気づいた葉羽は、容疑者たちの言動や行動を鋭く観察し、彼らの心の奥に隠された感情を読み解く。
やがて、葉羽は九条が鳴海を守るつもりで殺害したことを突き止める。嫉妬心と恐怖が交錯し、事件を引き起こしたのだった。九条は告白し、鳴海の死の背後にある複雑な人間関係と感情の絡まりを明らかにする。
事件が解決した後、葉羽はそれぞれの登場人物が抱える痛みや後悔を受け止めながら、自らの探偵としての成長を誓う。鳴海の思いを胸に、彼は新たな旅立ちを迎えるのだった。
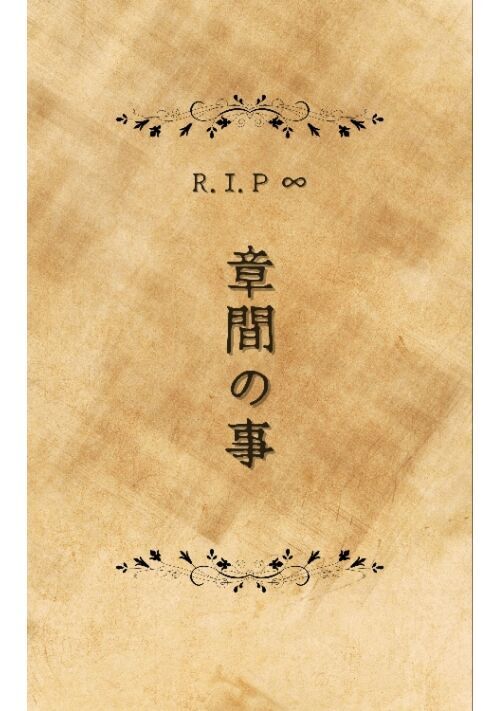


孤島の洋館と死者の証言
葉羽
ミステリー
高校2年生の神藤葉羽は、学年トップの成績を誇る天才だが、恋愛には奥手な少年。彼の平穏な日常は、幼馴染の望月彩由美と過ごす時間によって色付けされていた。しかし、ある日、彼が大好きな推理小説のイベントに参加するため、二人は不気味な孤島にある古びた洋館に向かうことになる。
その洋館で、参加者の一人が不審死を遂げ、事件は急速に混沌と化す。葉羽は推理の腕を振るい、彩由美と共に事件の真相を追い求めるが、彼らは次第に精神的な恐怖に巻き込まれていく。死者の霊が語る過去の真実、参加者たちの隠された秘密、そして自らの心の中に潜む恐怖。果たして彼らは、事件の謎を解き明かし、無事にこの恐ろしい洋館から脱出できるのか?

答えの出口
藤原雅倫
ミステリー
1995年、
僕が生きている世界でとりまく様々な人々。
現在から過去に於いて巡る遠い記憶と現実の中で、
何処へ、
何に向かって生きているのだろう。
ある日メールボックスに届いた署名のないメッセージ。
僕に巻き起こる「真実」と「絶望」の行方は、、。
この小説は、
古い格差社会やジェンダー問題によって繰り返されてきた
強大な音楽業界組織のスキャンダル隠蔽を、
恋愛とミステリーを通して暴き描いて行く
現代ファンタジー長編小説の群像劇となります。
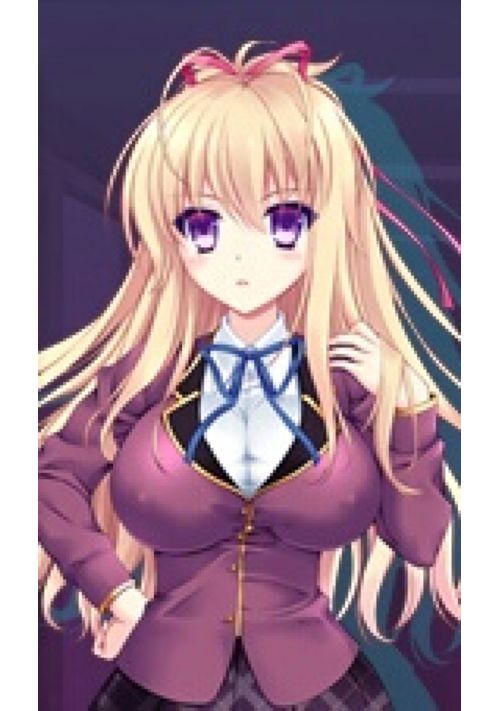
A Ghost Legacy
神能 秀臣
ミステリー
主人公である隆之介と真里奈は地元では有名な秀才の兄妹。
そんな二人に、「人生は楽しんだもの勝ち!」をモットーにしていた伯父の達哉が莫大な遺産を残したことが明らかになった。
ただし、受け取る為には妙な条件があった。それは、ある女性の為に達哉の「幽霊」を呼び出して欲しいと言うもの。訳が分からないと戸惑いながらも、二人は達哉の遺言に従って行動を開始する。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















