お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
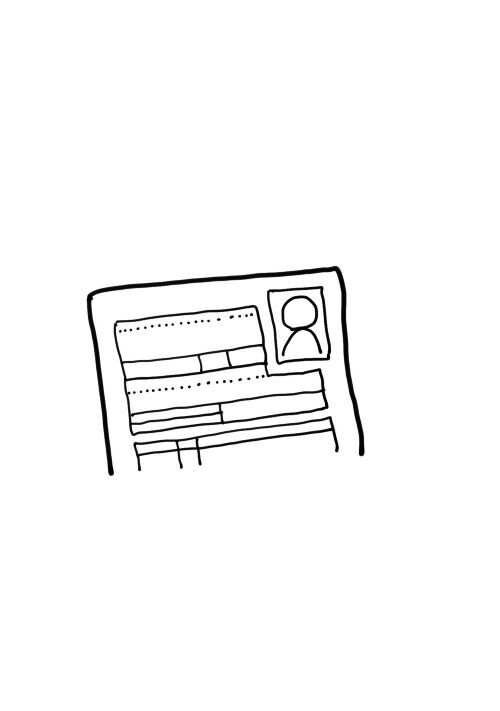
新たな基準
ちょこ
ライト文芸
就活はキビシイ。どうすればいいのか、考えてもどうにもならないレベルだ。
一方、会社は嘆いていた。おかしい。いつのまにか使えない社員ばかりだ、と。
これはとある人物の就活のおはなし。



イハン二ヨリケイヤクヲ
ちょこ
現代文学
いい天気だ。
青空が大きく広がる窓を背に座った人たちを前に、私はそんなことを思っていた。なにもかもがバカらしくなって、気持ちのよい青空を見続けてでもいなければ、脳みそも心臓も、動くのをやめてしまいそうだったから。

機織姫
ワルシャワ
ホラー
栃木県日光市にある鬼怒沼にある伝説にこんな話がありました。そこで、とある美しい姫が現れてカタンコトンと音を鳴らす。声をかけるとその姫は一変し沼の中へ誘うという恐ろしい話。一人の少年もまた誘われそうになり、どうにか命からがら助かったというが。その話はもはや忘れ去られてしまうほど時を超えた現代で起きた怖いお話。はじまりはじまり

消極的な会社の辞め方
白水緑
ライト文芸
秋山さんはふと思いついた。仕事を辞めたい!
けれども辞表を提出するほど辞めたい何かがあるわけではない……。
そうだ! クビにしてもらえばいいんだ!
相談相手に選ばれた私こと本谷と一緒に、クビにされるため頑張ります!

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















