お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


『盆綱引き』
篠崎俊樹
ホラー
福岡県朝倉市比良松を舞台に据えた、ホラー小説です。時代設定は、今から5年前という設定です。第6回ホラー・ミステリー小説大賞にエントリーいたします。大賞を狙いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
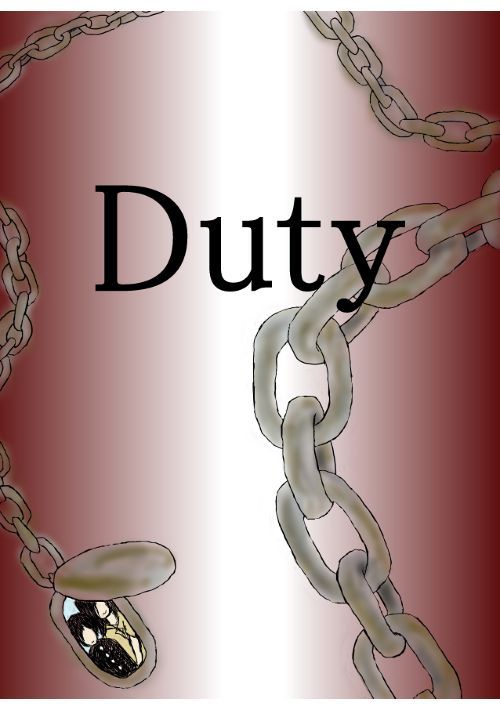
Duty
Kfumi
ホラー
「このクラスはおかしい」
鮮明なスクールカーストが存在するクラスから、一人また一人と生徒が死んでいく。
他人に迷惑行為を犯した人物は『罪人』に選ばれ、そして奇怪な放送が『審判』の時を告げる。
『只今よリ 罪人 ヲ 刑 に 処する 審判 を始めたいと思いま ウ』
クラスに巻き起こる『呪い』とは。
そして、呪いの元凶とはいったい『誰』なのか。
※現在ほぼ毎日更新中。
※この作品はフィクションです。多少グロテスクな表現があります。苦手な方はご注意ください。

フクロギ
ぽんぽこ@書籍発売中!!
ホラー
――フクロギを視たら、貴方も呪われる。
私の地元には、とある怪談がある。
それはフクロギという、梟の止まる木。
それを見た者は、数珠の様に次々と呪われてしまうらしい。
私は高校の友人に誘われ、フクロギのある雑木林へと向かったが……。
この物語は、実体験を元にしておりますが、フィクションです。また、法律・法令に反する行為を容認・推奨するものではありません。
表紙イラスト/ノーコピライトガール様より

#彼女を探して・・・
杉 孝子
ホラー
佳苗はある日、SNSで不気味なハッシュタグ『#彼女を探して』という投稿を偶然見かける。それは、特定の人物を探していると思われたが、少し不気味な雰囲気を醸し出していた。日が経つにつれて、そのタグの投稿が急増しSNS上では都市伝説の話も出始めていた。



ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















