お気に入りに追加
929
あなたにおすすめの小説

呪われ令嬢、王妃になる
八重
恋愛
「シェリー、お前とは婚約破棄させてもらう」
「はい、承知しました」
「いいのか……?」
「ええ、私の『呪い』のせいでしょう?」
シェリー・グローヴは自身の『呪い』のせいで、何度も婚約破棄される29歳の侯爵令嬢。
家族にも邪魔と虐げられる存在である彼女に、思わぬ婚約話が舞い込んできた。
「ジェラルド・ヴィンセント王から婚約の申し出が来た」
「──っ!?」
若き33歳の国王からの婚約の申し出に戸惑うシェリー。
だがそんな国王にも何やら思惑があるようで──
自身の『呪い』を気にせず溺愛してくる国王に、戸惑いつつも段々惹かれてそして、成長していくシェリーは、果たして『呪い』に打ち勝ち幸せを掴めるのか?
一方、今まで虐げてきた家族には次第に不幸が訪れるようになり……。
★この作品の特徴★
展開早めで進んでいきます。ざまぁの始まりは16話からの予定です。主人公であるシェリーとヒーローのジェラルドのラブラブや切ない恋の物語、あっと驚く、次が気になる!を目指して作品を書いています。
※小説家になろう先行公開中
※他サイトでも投稿しております(小説家になろうにて先行公開)
※アルファポリスにてホットランキングに載りました
※小説家になろう 日間異世界恋愛ランキングにのりました(初ランクイン2022.11.26)

悪女は愛より老後を望む
きゃる
恋愛
――悪女の夢は、縁側でひなたぼっこをしながらお茶をすすること!
もう何度目だろう? いろんな国や時代に転生を繰り返す私は、今は伯爵令嬢のミレディアとして生きている。でも、どの世界にいてもいつも若いうちに亡くなってしまって、老後がおくれない。その理由は、一番初めの人生のせいだ。貧乏だった私は、言葉巧みに何人もの男性を騙していた。たぶんその中の一人……もしくは全員の恨みを買ったため、転生を続けているんだと思う。生まれ変わっても心からの愛を告げられると、その夜に心臓が止まってしまうのがお約束。
だから私は今度こそ、恋愛とは縁のない生活をしようと心に決めていた。行き遅れまであと一年! 領地の片隅で、隠居生活をするのもいいわね?
そう考えて屋敷に引きこもっていたのに、ある日双子の王子の誕生を祝う舞踏会の招待状が届く。参加が義務付けられているけれど、地味な姿で壁に貼り付いているから……大丈夫よね?
*小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。

黄金の魔族姫
風和ふわ
恋愛
「エレナ・フィンスターニス! お前との婚約を今ここで破棄する! そして今から僕の婚約者はこの現聖女のレイナ・リュミエミルだ!」
「エレナ様、婚約者と神の寵愛をもらっちゃってごめんね? 譲ってくれて本当にありがとう!」
とある出来事をきっかけに聖女の恩恵を受けれなくなったエレナは「罪人の元聖女」として婚約者の王太子にも婚約破棄され、処刑された──はずだった!
──え!? どうして魔王が私を助けてくれるの!? しかも娘になれだって!?
これは、婚約破棄された元聖女が人外魔王(※実はとっても優しい)の娘になって、チートな治癒魔法を極めたり、地味で落ちこぼれと馬鹿にされていたはずの王太子(※実は超絶美形)と恋に落ちたりして、周りに愛されながら幸せになっていくお話です。
──え? 婚約破棄を取り消したい? もう一度やり直そう? もう想い人がいるので無理です!
※拙作「皆さん、紹介します。こちら私を溺愛するパパの“魔王”です!」のリメイク版。
※表紙は自作ではありません。

逆行転生した悪役令嬢だそうですけれど、反省なんてしてやりませんわ!
九重
恋愛
我儘で自分勝手な生き方をして処刑されたアマーリアは、時を遡り、幼い自分に逆行転生した。
しかし、彼女は、ここで反省できるような性格ではなかった。
アマーリアは、破滅を回避するために、自分を処刑した王子や聖女たちの方を変えてやろうと決意する。
これは、逆行転生した悪役令嬢が、まったく反省せずに、やりたい放題好き勝手に生きる物語。
ツイッターで先行して呟いています。
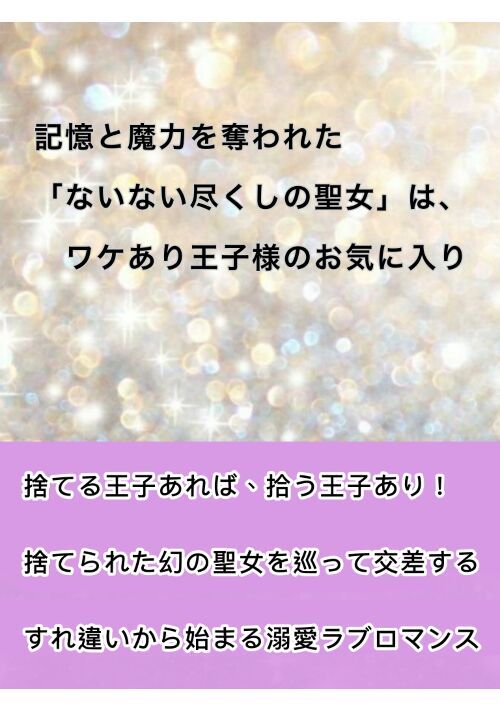
記憶と魔力を婚約者に奪われた「ないない尽くしの聖女」は、ワケあり王子様のお気に入り~王族とは知らずにそばにいた彼から なぜか溺愛されています
瑞貴◆後悔してる/手違いの妻2巻発売!
恋愛
【第一部完結】
婚約者を邪険に思う王太子が、婚約者の功績も知らずに婚約破棄を告げ、記憶も魔力も全て奪って捨て去って――。
ハイスぺのワケあり王子が、何も知らずに片想いの相手を拾ってきたのに、彼女の正体に気づかずに――。
▲以上、短いあらすじです。以下、長いあらすじ▼
膨大な魔力と光魔法の加護を持つルダイラ王国の公爵家令嬢ジュディット。彼女には、婚約者であるフィリベールと妹のリナがいる。
妹のリナが王太子と父親を唆し、ジュディットは王太子から婚約破棄を告げられた。
しかし、王太子の婚約は、陛下がまとめた縁談である。
ジュディットをそのまま捨てるだけでは都合が悪い。そこで、王族だけに受け継がれる闇魔法でジュディットの記憶と魔力を封印し、捨てることを思いつく――。
山道に捨てられ、自分に関する記憶も、魔力も、お金も、荷物も持たない、【ないない尽くしのジュディット】が出会ったのは、【ワケありな事情を抱えるアンドレ】だ。
ジュディットは持っていたハンカチの刺繍を元に『ジュディ』と名乗りアンドレと新たな生活を始める。
一方のアンドレは、ジュディのことを自分を害する暗殺者だと信じ込み、彼女に冷たい態度を取ってしまう。
だが、何故か最後まで冷たく仕切れない。
ジュディは送り込まれた刺客だと理解したうえでも彼女に惹かれ、不器用なアプローチをかける。
そんなジュディとアンドレの関係に少しづつ変化が見えてきた矢先。
全てを奪ってから捨てた元婚約者の功績に気づき、焦る王太子がジュディットを連れ戻そうと押しかけてきて――。
ワケあり王子が、叶わない恋と諦めていた【幻の聖女】その正体は、まさかのジュディだったのだ!
ジュディは自分を害する刺客ではないと気づいたアンフレッド殿下の溺愛が止まらない――。
「王太子殿下との婚約が白紙になって目の前に現れたんですから……縛り付けてでも僕のものにして逃がしませんよ」
嫉妬心剥き出しの、逆シンデレラストーリー開幕!
本作は、小説家になろう様とカクヨム様にて先行投稿を行っています。

愛を知らない「頭巾被り」の令嬢は最強の騎士、「氷の辺境伯」に溺愛される
守次 奏
恋愛
「わたしは、このお方に出会えて、初めてこの世に産まれることができた」
貴族の間では忌み子の象徴である赤銅色の髪を持って生まれてきた少女、リリアーヌは常に家族から、妹であるマリアンヌからすらも蔑まれ、その髪を隠すように頭巾を被って生きてきた。
そんなリリアーヌは十五歳を迎えた折に、辺境領を収める「氷の辺境伯」「血まみれ辺境伯」の二つ名で呼ばれる、スターク・フォン・ピースレイヤーの元に嫁がされてしまう。
厄介払いのような結婚だったが、それは幸せという言葉を知らない、「頭巾被り」のリリアーヌの運命を変える、そして世界の運命をも揺るがしていく出会いの始まりに過ぎなかった。
これは、一人の少女が生まれた意味を探すために駆け抜けた日々の記録であり、とある幸せな夫婦の物語である。
※この作品は「小説家になろう」「カクヨム」様にも短編という形で掲載しています。

二度目の召喚なんて、聞いてません!
みん
恋愛
私─神咲志乃は4年前の夏、たまたま学校の図書室に居た3人と共に異世界へと召喚されてしまった。
その異世界で淡い恋をした。それでも、志乃は義務を果たすと居残ると言う他の3人とは別れ、1人日本へと還った。
それから4年が経ったある日。何故かまた、異世界へと召喚されてしまう。「何で!?」
❋相変わらずのゆるふわ設定と、メンタルは豆腐並みなので、軽い気持ちで読んでいただけると助かります。
❋気を付けてはいますが、誤字が多いかもしれません。
❋他視点の話があります。

【完結】男装して会いに行ったら婚約破棄されていたので、近衛として地味に復讐したいと思います。
銀杏鹿
恋愛
次期皇后のアイリスは、婚約者である王に会うついでに驚かせようと、男に変装し近衛として近づく。
しかし、王が自分以外の者と結婚しようとしていると知り、怒りに震えた彼女は、男装を解かないまま、復讐しようと考える。
しかし、男装が完璧過ぎたのか、王の意中の相手やら、王弟殿下やら、その従者に目をつけられてしまい……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















