6 / 42
(六)有馬重則の死
しおりを挟む
松永久秀の元で九十九髪茄子を見る機会を得てからしばらくの後。
使番として葛屋を訪れ、自慢気に話す則頼に対して、珍しく言いにくそうに豊助が口ごもる。
「あまり耳触りのよろしくない報せをお聞かせせねばならぬかと」
どこまで演技なのか、それとも本心なのか。今もって則頼の眼力では、豊助の表情からは見抜けない。
「はて。どのような話であろうか」
則頼は見当もつかず、率直に問う。
「実は、有馬様のお父上、月公様にある噂がございましてな」
「月公、か。親父も、要らざる波風を立てる号を名乗ったものよ」
父の号を聞き、則頼は渋面を作った。
重則は居城を三津田から淡河に移した後、本家たる有馬郡分郡守護の有馬村秀が「月江」を号しているのにあやかるのだと称し、「月公」と名乗っている。
どのような意図があるのか最初は判らなかったが、どうやら「有馬のげっこう様」と領民に呼ばせることで、本家の有馬村秀と己を勘違いさせようとの意図があるらしかった。
子供だましじみているが、耳でその名を聞く領民には重則と村秀が別人であることを知るすべはないのも確かだ。
それは重則なりの慰撫策なのかもしれないが、どうにも小細工が過ぎる。則頼としては素直に感心できる話でもなかった。
「有馬様?」
「ああ、済まぬ。で、親父が如何したと」
知らぬうちに渋面を作っていることに気づいた則頼は、咳払いして豊助に話の先を促す。
「さらなる領地の拡大をもくろみ、松永様になにやら働きかけておられるご様子にござりまする」
先にも記したとおり、播磨の仕置きは、摂津滝山城を預かる松永弾正久秀に任されている。
もっとも、播磨の別所を従属させて以降、三好家は積極的に西に勢力圏を拡大させる動きは見せておらず、久秀にしても播磨にかかりきりではない。
有馬と淡河の位置関係を整理すると、まず有馬家が抑える三津田の地の東に戸田があり、さらにその東に淡河がある。
戸田と淡河の境には小さな峠があり、この峠を挟んで有馬家と淡河家は長年に渡って小競り合いを繰り返してきた。
しかし、淡河家を首尾よく手に入れた重則としては、三田の有馬家と別所家が既に三好に服属している限り、街道の東西を抑えられ、これ以上領地を拡大させる術がない。
(そのために、更なる戦さを求める、か。よほど、三好の討ち入れに乗じて淡河三城をかすめ取ったことに味を占めたとみえる)
危ういものを感じる則頼であった。
「その話、今少し詳しく聞かせてくれぬか。内容次第で、豊前守様にお報せせねばならぬ」
気にいらぬ父であるが、命取りになりかねぬ話を之虎に伝えねばならないのは心が痛む。しかし、親子の情で握り潰す様な真似があってはならぬのだ。
「心中、お察しいたしまする。では」
気の毒そうに表情を曇らせつつ、豊助は改めて噂話として配下の連雀が聞き知ったという重則の行状について説明を始めた。
則頼の懸念は的中した。
それから一月ほど後、有馬重則は死んだ。
その死因は史書ごとに記述が異なる有様で、謎が多い。
自ら月公などと号して、有馬月江村秀との混同を意図的に目論んでいた節もあり、重則と村秀と取り違えたと思われる記録も少なくないためだ。
いずれにせよ、その死には松永久秀が絡んでいるとされるとの記載が多い。
重則が摂津滝山城にて播磨を管轄する久秀と合戦に及ばねばならない理由はなく、また勝算がある筈もない。
正面切っての合戦による討死ではなく、謀殺であった可能性が高い。
「おおかた、要らぬ欲を出したためであろう」
呆気ない死に様を伝え聞いた則頼は驚きこそすれ、自分でも不思議なほどに哀しみの気持ちが沸かなかった。
むしろ、妻の振のほうが一度も会ったことのない義父の死を嘆き、すすり泣いていたほどだ。
だが、自分に上機嫌で九十九髪茄子を自慢していた久秀の顔を思い出すと、一月後にその父親を誅殺する男だったとはとても想像できず、則頼はいま一度背筋が寒くなる思いであった。
重則が死に至った理由はなんであれ、有馬家は長男である則重が継ぎ、城代として預かっていた三津田城の城主となった。
急な家督継承であったこともあり、淡河城に居を移すには今しばらく時間が必要となる様子であった。
幸いというべきか、重則が誅殺されても人質である則頼にはなんら咎めがなかった。
あるいは之虎のところで、久秀からの進言を差し止めてくれているのかもしれない。
「兄者がうまく家をまとめてくれれば良いのじゃがのう」
今のところ、有馬の家にあまり執着はないが、則頼にしても滅んでしまえなどと願っている訳ではない。
則頼の目からみた兄は頼りがいがあるとはとても言えないが、立場が人を作るとの言葉もある。なんとかうまくやって欲しい、というのはまぎれもない則頼の本音であった。
それからさらに一月ほど経った六月のある日。
夜半になって、則頼は之虎からの呼び出しを受けた。
どう考えても、良い話が舞い込む時間とは思われない。急いで身支度を調え、緊張の面持ちで屋敷に走り、之虎の部屋へと参上する。
「急に呼び立ててすまぬな。三津田より早打が届いたのでな」
畿内にて勇名を恣にする三好長慶の実弟ながら、人質の身である筈の則頼に対する之虎の口ぶりは、未だに丁寧なものだった。
ただ、燭台の灯りに照らされた暗い室内にあっても、之虎の顔にわずかばかり困惑の色が浮かんでいるのを、則頼は見逃さない。
「兄から、にございまするか」
「うむ。まずは読んでみよ」
之虎が差し出した書状をうやうやしく受け取った則頼は、急いで文面に目を走らせた。
そこには、三木城に逼塞していた筈の淡河元範の嫡子・淡河範之に淡河城と野瀬城を奪還されたこと、奪還にあたっては、範之が養子に迎えた弾正定範なる男が優れた働きを示したため淡河家中で重きをなしていること、三津田城もしばしば攻撃を受けており、立て直しのために弟を戻していただきたい、などといった内容が余裕のない筆跡でつづられていた。
書状の端を握りしめる則頼の指先が小刻みに震える。わななく唇から言葉を押し出すのに数拍の時間を要した。
「弟を頼るとは、我が兄ながらなんと不甲斐なきことよ。お目汚しの書状を寄越した兄に代わり、伏してお詫び申しあげまする」
目もくらむような怒りと恥ずかしさで泣き出したい気持ちになりながら、則頼は書状を床に放り捨てて平伏した。
書状には直接書かれてこそいないが、別所から三好に差し出した一門の姫・振を妻に迎えている則頼が帰還すれば、いま別所の後ろ盾を得て三津田城を脅かしている淡河家の勢いも鈍る、則重がそう目論んでいるのは明らかだった。
(浅慮、浅慮よ)
激発する感情を押さえかねている則頼とは対照的に、之虎は穏やかな表情を崩さない。
「まあ、そう邪険に致すな。そなたの兄も、父を失って家督を継いで間もない身の上のこと。家中を取りまとめるのも楽ではなかろう」
「されど、この体たらくではなおのこと家中にも示しがつきませぬ。この際、兵を差し向けて淡河を討つことは出来ぬのでしょうか」
悔しさあまってそんな提案もしてみるが、則頼の頭の冷静な部分は、「それは無理だろうな」と早々に結論づけてしまっている。
元々、播磨国では事を荒立てたくないからこそ、その意向に反する動きをみせていた重則が誅殺される羽目になったとも考えられる。
己の手で三津田の有馬家を弱体化させた挙げ句、その居城である三津田城の防衛の為に兵を出すなど、松永久秀が同意する筈もなかった。
案の定、之虎も静かに首を横に振った。
「お主の考えも判らぬではないが、残念ながら、今の三好に、地侍同士の争いを鎮めるために、改めて播州に兵を送る考えはない。騒擾は別所に鎮めさせることとなろう」
「……申し訳ござりませぬ。浅はかなことを申しました」
要するに、従属した別所に播磨の統治を任せている以上は、その支配下にある有馬家と別所家が寸土を巡って城を奪いあう程度のことでは、わざわざ三好家が直接介入はしないという話である。
別所家もそれと判っているからこそ、敵対的な存在の有馬家ではなく、友好的な淡河家の失地回復の後ろ盾となっているのだろう。
則頼も頭では判っているが、やはり割り切れなさは募る。
「殿に諮らねばならぬが、そなたの兄の願いは、おそらく聞き届けられるであろう。……儂としては、そなたの働きには随分と助けられておったのだがな」
「畏れ多いお言葉にございます」
「第一、考えてもみよ。お主の父が誅殺された以上、いつ松永弾正が気まぐれでそなたの首級を所望するか知れたものではないではないか」
「……確かに、それは失念しておりました」
不意の指摘に、則頼は言葉に詰まる。実家のことばかり考え、自分の身も危うい事実がすっかり頭から抜けていたのだ。
「それにな。有馬源次郎ほどの男が、ただ実家に戻るだけでは済ますまい、と儂は信じておるぞ」
之虎が含みを持たせた言葉の意味を、則頼はすぐに察した。
(確かに、このままでは済ませられぬ)
この時、則頼は己が別所の獅子身中の虫となって三好の為に働くこと、淡河家をこのままにはしておかぬこと、そして情けない書状を臆面もなく送りつけてきた兄から有馬家の実権を奪うことなど、様々な思いを瞬時に心中深くに期した。
「これまでのご厚恩、それがしは終生決して忘れませぬ。つきましては一つ、図々しいお願いがござる。それがしに受領名をお与えくださいませ」
則頼はたじろぐ己の気持ちに負けぬよう、一息でそう言い切った。
この時代、多くの武士が朝廷から正式な任官を受けずに官職名を名乗ることが常態化している。自ら勝手に称する場合もあれば、主君から家臣が授かる場合もある。
どうせ名乗るのであれば、之虎から与えられた名乗りであれば箔がつくとの思いが則頼にはあった。
「受領名か。なんでも良いのか」
之虎が面白げに問うた。
「欲を申せば、敢えて似合わぬ名乗りのほうが、それらしくある気も致します」
則頼の言葉に、之虎は薄く笑った。
「本当に欲深いわ。では、中務少輔などはどうじゃ」
もちろん、則頼は之虎から与えられる名であればなんでも構わなかったから、異論はない。
「ありがたき幸せ。今よりそれがしは、有馬中務少輔則頼と名乗りまする」
則頼は喜色を浮かべて平伏する。
こうして、則頼は播磨へと帰還することになった。
使番として葛屋を訪れ、自慢気に話す則頼に対して、珍しく言いにくそうに豊助が口ごもる。
「あまり耳触りのよろしくない報せをお聞かせせねばならぬかと」
どこまで演技なのか、それとも本心なのか。今もって則頼の眼力では、豊助の表情からは見抜けない。
「はて。どのような話であろうか」
則頼は見当もつかず、率直に問う。
「実は、有馬様のお父上、月公様にある噂がございましてな」
「月公、か。親父も、要らざる波風を立てる号を名乗ったものよ」
父の号を聞き、則頼は渋面を作った。
重則は居城を三津田から淡河に移した後、本家たる有馬郡分郡守護の有馬村秀が「月江」を号しているのにあやかるのだと称し、「月公」と名乗っている。
どのような意図があるのか最初は判らなかったが、どうやら「有馬のげっこう様」と領民に呼ばせることで、本家の有馬村秀と己を勘違いさせようとの意図があるらしかった。
子供だましじみているが、耳でその名を聞く領民には重則と村秀が別人であることを知るすべはないのも確かだ。
それは重則なりの慰撫策なのかもしれないが、どうにも小細工が過ぎる。則頼としては素直に感心できる話でもなかった。
「有馬様?」
「ああ、済まぬ。で、親父が如何したと」
知らぬうちに渋面を作っていることに気づいた則頼は、咳払いして豊助に話の先を促す。
「さらなる領地の拡大をもくろみ、松永様になにやら働きかけておられるご様子にござりまする」
先にも記したとおり、播磨の仕置きは、摂津滝山城を預かる松永弾正久秀に任されている。
もっとも、播磨の別所を従属させて以降、三好家は積極的に西に勢力圏を拡大させる動きは見せておらず、久秀にしても播磨にかかりきりではない。
有馬と淡河の位置関係を整理すると、まず有馬家が抑える三津田の地の東に戸田があり、さらにその東に淡河がある。
戸田と淡河の境には小さな峠があり、この峠を挟んで有馬家と淡河家は長年に渡って小競り合いを繰り返してきた。
しかし、淡河家を首尾よく手に入れた重則としては、三田の有馬家と別所家が既に三好に服属している限り、街道の東西を抑えられ、これ以上領地を拡大させる術がない。
(そのために、更なる戦さを求める、か。よほど、三好の討ち入れに乗じて淡河三城をかすめ取ったことに味を占めたとみえる)
危ういものを感じる則頼であった。
「その話、今少し詳しく聞かせてくれぬか。内容次第で、豊前守様にお報せせねばならぬ」
気にいらぬ父であるが、命取りになりかねぬ話を之虎に伝えねばならないのは心が痛む。しかし、親子の情で握り潰す様な真似があってはならぬのだ。
「心中、お察しいたしまする。では」
気の毒そうに表情を曇らせつつ、豊助は改めて噂話として配下の連雀が聞き知ったという重則の行状について説明を始めた。
則頼の懸念は的中した。
それから一月ほど後、有馬重則は死んだ。
その死因は史書ごとに記述が異なる有様で、謎が多い。
自ら月公などと号して、有馬月江村秀との混同を意図的に目論んでいた節もあり、重則と村秀と取り違えたと思われる記録も少なくないためだ。
いずれにせよ、その死には松永久秀が絡んでいるとされるとの記載が多い。
重則が摂津滝山城にて播磨を管轄する久秀と合戦に及ばねばならない理由はなく、また勝算がある筈もない。
正面切っての合戦による討死ではなく、謀殺であった可能性が高い。
「おおかた、要らぬ欲を出したためであろう」
呆気ない死に様を伝え聞いた則頼は驚きこそすれ、自分でも不思議なほどに哀しみの気持ちが沸かなかった。
むしろ、妻の振のほうが一度も会ったことのない義父の死を嘆き、すすり泣いていたほどだ。
だが、自分に上機嫌で九十九髪茄子を自慢していた久秀の顔を思い出すと、一月後にその父親を誅殺する男だったとはとても想像できず、則頼はいま一度背筋が寒くなる思いであった。
重則が死に至った理由はなんであれ、有馬家は長男である則重が継ぎ、城代として預かっていた三津田城の城主となった。
急な家督継承であったこともあり、淡河城に居を移すには今しばらく時間が必要となる様子であった。
幸いというべきか、重則が誅殺されても人質である則頼にはなんら咎めがなかった。
あるいは之虎のところで、久秀からの進言を差し止めてくれているのかもしれない。
「兄者がうまく家をまとめてくれれば良いのじゃがのう」
今のところ、有馬の家にあまり執着はないが、則頼にしても滅んでしまえなどと願っている訳ではない。
則頼の目からみた兄は頼りがいがあるとはとても言えないが、立場が人を作るとの言葉もある。なんとかうまくやって欲しい、というのはまぎれもない則頼の本音であった。
それからさらに一月ほど経った六月のある日。
夜半になって、則頼は之虎からの呼び出しを受けた。
どう考えても、良い話が舞い込む時間とは思われない。急いで身支度を調え、緊張の面持ちで屋敷に走り、之虎の部屋へと参上する。
「急に呼び立ててすまぬな。三津田より早打が届いたのでな」
畿内にて勇名を恣にする三好長慶の実弟ながら、人質の身である筈の則頼に対する之虎の口ぶりは、未だに丁寧なものだった。
ただ、燭台の灯りに照らされた暗い室内にあっても、之虎の顔にわずかばかり困惑の色が浮かんでいるのを、則頼は見逃さない。
「兄から、にございまするか」
「うむ。まずは読んでみよ」
之虎が差し出した書状をうやうやしく受け取った則頼は、急いで文面に目を走らせた。
そこには、三木城に逼塞していた筈の淡河元範の嫡子・淡河範之に淡河城と野瀬城を奪還されたこと、奪還にあたっては、範之が養子に迎えた弾正定範なる男が優れた働きを示したため淡河家中で重きをなしていること、三津田城もしばしば攻撃を受けており、立て直しのために弟を戻していただきたい、などといった内容が余裕のない筆跡でつづられていた。
書状の端を握りしめる則頼の指先が小刻みに震える。わななく唇から言葉を押し出すのに数拍の時間を要した。
「弟を頼るとは、我が兄ながらなんと不甲斐なきことよ。お目汚しの書状を寄越した兄に代わり、伏してお詫び申しあげまする」
目もくらむような怒りと恥ずかしさで泣き出したい気持ちになりながら、則頼は書状を床に放り捨てて平伏した。
書状には直接書かれてこそいないが、別所から三好に差し出した一門の姫・振を妻に迎えている則頼が帰還すれば、いま別所の後ろ盾を得て三津田城を脅かしている淡河家の勢いも鈍る、則重がそう目論んでいるのは明らかだった。
(浅慮、浅慮よ)
激発する感情を押さえかねている則頼とは対照的に、之虎は穏やかな表情を崩さない。
「まあ、そう邪険に致すな。そなたの兄も、父を失って家督を継いで間もない身の上のこと。家中を取りまとめるのも楽ではなかろう」
「されど、この体たらくではなおのこと家中にも示しがつきませぬ。この際、兵を差し向けて淡河を討つことは出来ぬのでしょうか」
悔しさあまってそんな提案もしてみるが、則頼の頭の冷静な部分は、「それは無理だろうな」と早々に結論づけてしまっている。
元々、播磨国では事を荒立てたくないからこそ、その意向に反する動きをみせていた重則が誅殺される羽目になったとも考えられる。
己の手で三津田の有馬家を弱体化させた挙げ句、その居城である三津田城の防衛の為に兵を出すなど、松永久秀が同意する筈もなかった。
案の定、之虎も静かに首を横に振った。
「お主の考えも判らぬではないが、残念ながら、今の三好に、地侍同士の争いを鎮めるために、改めて播州に兵を送る考えはない。騒擾は別所に鎮めさせることとなろう」
「……申し訳ござりませぬ。浅はかなことを申しました」
要するに、従属した別所に播磨の統治を任せている以上は、その支配下にある有馬家と別所家が寸土を巡って城を奪いあう程度のことでは、わざわざ三好家が直接介入はしないという話である。
別所家もそれと判っているからこそ、敵対的な存在の有馬家ではなく、友好的な淡河家の失地回復の後ろ盾となっているのだろう。
則頼も頭では判っているが、やはり割り切れなさは募る。
「殿に諮らねばならぬが、そなたの兄の願いは、おそらく聞き届けられるであろう。……儂としては、そなたの働きには随分と助けられておったのだがな」
「畏れ多いお言葉にございます」
「第一、考えてもみよ。お主の父が誅殺された以上、いつ松永弾正が気まぐれでそなたの首級を所望するか知れたものではないではないか」
「……確かに、それは失念しておりました」
不意の指摘に、則頼は言葉に詰まる。実家のことばかり考え、自分の身も危うい事実がすっかり頭から抜けていたのだ。
「それにな。有馬源次郎ほどの男が、ただ実家に戻るだけでは済ますまい、と儂は信じておるぞ」
之虎が含みを持たせた言葉の意味を、則頼はすぐに察した。
(確かに、このままでは済ませられぬ)
この時、則頼は己が別所の獅子身中の虫となって三好の為に働くこと、淡河家をこのままにはしておかぬこと、そして情けない書状を臆面もなく送りつけてきた兄から有馬家の実権を奪うことなど、様々な思いを瞬時に心中深くに期した。
「これまでのご厚恩、それがしは終生決して忘れませぬ。つきましては一つ、図々しいお願いがござる。それがしに受領名をお与えくださいませ」
則頼はたじろぐ己の気持ちに負けぬよう、一息でそう言い切った。
この時代、多くの武士が朝廷から正式な任官を受けずに官職名を名乗ることが常態化している。自ら勝手に称する場合もあれば、主君から家臣が授かる場合もある。
どうせ名乗るのであれば、之虎から与えられた名乗りであれば箔がつくとの思いが則頼にはあった。
「受領名か。なんでも良いのか」
之虎が面白げに問うた。
「欲を申せば、敢えて似合わぬ名乗りのほうが、それらしくある気も致します」
則頼の言葉に、之虎は薄く笑った。
「本当に欲深いわ。では、中務少輔などはどうじゃ」
もちろん、則頼は之虎から与えられる名であればなんでも構わなかったから、異論はない。
「ありがたき幸せ。今よりそれがしは、有馬中務少輔則頼と名乗りまする」
則頼は喜色を浮かべて平伏する。
こうして、則頼は播磨へと帰還することになった。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

北海帝国の秘密
尾瀬 有得
歴史・時代
十一世紀初頭。
幼い頃の記憶を失っているデンマークの農場の女ヴァナは、突如としてやってきた身体が動かないほどに年老いた戦士、トルケルの側仕えとなった。
ある日の朝、ヴァナは暇つぶしにと彼の考えたという話を聞かされることになる。
それは現イングランド・デンマークの王クヌートは偽物で、本当は彼の息子であるという話だった。
本物のクヌートはどうしたのか?
なぜトルケルの子が身代わりとなったのか?
そして、引退したトルケルはなぜ農場へやってきたのか?
トルケルが与太話と嘯きつつ語る自分の半生と、クヌートの秘密。
それは決して他言のできない歴史の裏側。


日本が危機に?第二次日露戦争
杏
歴史・時代
2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。
なろう、カクヨムでも連載しています。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

不屈の葵
ヌマサン
歴史・時代
戦国乱世、不屈の魂が未来を掴む!
これは三河の弱小国主から天下人へ、不屈の精神で戦国を駆け抜けた男の壮大な物語。
幾多の戦乱を生き抜き、不屈の精神で三河の弱小国衆から天下統一を成し遂げた男、徳川家康。
本作は家康の幼少期から晩年までを壮大なスケールで描き、戦国時代の激動と一人の男の成長物語を鮮やかに描く。
家康の苦悩、決断、そして成功と失敗。様々な人間ドラマを通して、人生とは何かを問いかける。
今川義元、織田信長、羽柴秀吉、武田信玄――家康の波乱万丈な人生を彩る個性豊かな名将たちも続々と登場。
家康との関わりを通して、彼らの生き様も鮮やかに描かれる。
笑いあり、涙ありの壮大なスケールで描く、単なる英雄譚ではなく、一人の人間として苦悩し、成長していく家康の姿を描いた壮大な歴史小説。
戦国時代の風雲児たちの活躍、人間ドラマ、そして家康の不屈の精神が、読者を戦国時代に誘う。
愛、友情、そして裏切り…戦国時代に渦巻く人間ドラマにも要注目!
歴史ファン必読の感動と興奮が止まらない歴史小説『不屈の葵』
ぜひ、手に取って、戦国時代の熱き息吹を感じてください!
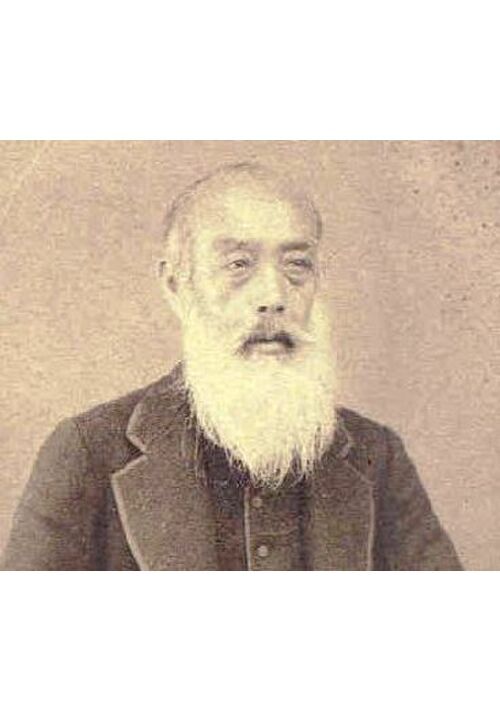

和ませ屋仇討ち始末
志波 連
歴史・時代
山名藩家老家次男の三沢新之助が学問所から戻ると、屋敷が異様な雰囲気に包まれていた。
門の近くにいた新之助をいち早く見つけ出した安藤久秀に手を引かれ、納戸の裏を通り台所から屋内へ入っる。
久秀に手を引かれ庭の見える納戸に入った新之助の目に飛び込んだのは、今まさに切腹しようとしている父長政の姿だった。
父が正座している筵の横には変わり果てた長兄の姿がある。
「目に焼き付けてください」
久秀の声に頷いた新之助だったが、介錯の刀が振り下ろされると同時に気を失ってしまった。
新之助が意識を取り戻したのは、城下から二番目の宿場町にある旅籠だった。
「江戸に向かいます」
同行するのは三沢家剣術指南役だった安藤久秀と、新之助付き侍女咲良のみ。
父と兄の死の真相を探り、その無念を晴らす旅が始まった。
他サイトでも掲載しています
表紙は写真ACより引用しています
R15は保険です
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















