お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

闇姫化伝
三塚 章
ファンタジー
荒ぶる神を和神(にぎがみ)に浄化する巫女、鹿子(かのこ)。彼女は、最近荒ぶる神の異変を感じていた。そんななか、行方不明になっていた先輩巫女柚木(ゆずき)と再会する。鹿子は喜ぶが……
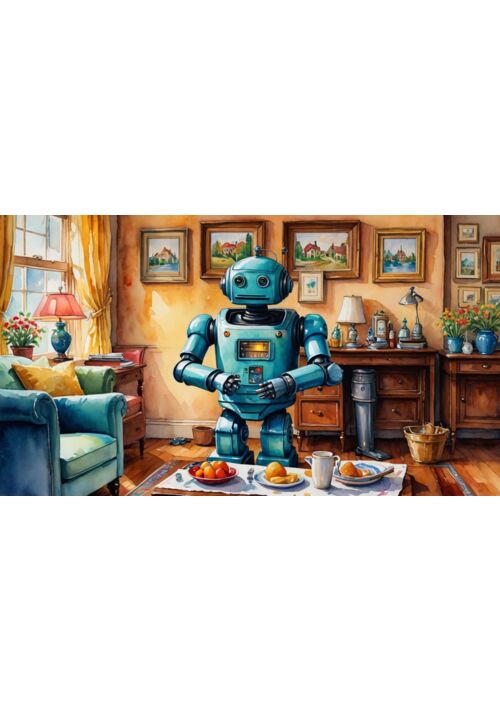
AI執事、今日もやらかす ~ポンコツだけど憎めない人工知能との奇妙な共同生活~
鷹栖 透
SF
AI執事アルフレッドは完璧なプレゼン資料を用意するが、主人公の花子は資料を捨て、自らの言葉でプレゼンに挑む。完璧を求めるAIと、不完全さの中にこそ真の創造性を見出す人間の対比を通して、人間の可能性とAIとの関係性を問う感動の物語。崖っぷちのデザイナー花子と、人間を理解しようと奮闘するAI執事アルフレッドの成長は、あなたに温かい涙と、未来への希望をもたらすだろう。

キャットクライシス!
三塚 章
ファンタジー
中学生のミズキは『自分自身』に襲われる。助けてくれた神話ハンターを名乗る男によると、呪いをかけられているというが……そんな中、猫が人間を襲う事件が起き……

スペースシエルさんReboot 〜宇宙生物に寄生されましたぁ!〜
柚亜紫翼
SF
真っ暗な宇宙を一人で旅するシエルさんはお父さんの遺してくれた小型宇宙船に乗ってハンターというお仕事をして暮らしています。
ステーションに住んでいるお友達のリンちゃんとの遠距離通話を楽しみにしている長命種の145歳、趣味は読書、夢は自然豊かな惑星で市民権とお家を手に入れのんびり暮らす事!。
「宇宙船にずっと引きこもっていたいけど、僕の船はボロボロ、修理代や食費、お薬代・・・生きる為にはお金が要るの、だから・・・嫌だけど、怖いけど、人と関わってお仕事をして・・・今日もお金を稼がなきゃ・・・」
これは「小説家になろう」「カクヨム」「アルファポリス」に投稿している「〜隻眼の令嬢、リーゼロッテさんはひきこもりたい!〜」の元になったお話のリメイクです、なので内容や登場人物が「リーゼロッテさん」とよく似ています。
時々鬱展開やスプラッタな要素が混ざりますが、シエルさんが優雅な引きこもり生活を夢見てのんびりまったり宇宙を旅するお話です。
遥か昔に書いたオリジナルを元にリメイクし、新しい要素を混ぜて最初から書き直していますので宇宙版の「リーゼロッテさん」として楽しんでもらえたら嬉しいです。
〜隻眼の令嬢、リーゼロッテさんはひきこもりたい!〜
https://www.alphapolis.co.jp/novel/652357507/282796475


我らアスター街ストレングス部隊~日常編~
三塚 章
ファンタジー
アスター街の治安を護る、ストレングス部隊のグダグダの一日。一話完結が何編かあります。
長編はこちら↓
https://www.alphapolis.co.jp/novel/423043246/763597692

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

暗夜刀花
三塚 章
ファンタジー
迷路のような町本防で、通り魔事件発生。有料道案内「送り提灯」の空也(そらや)は事件に巻き込まれる。 通り魔の正体は? 空也は想い人の真菜(まな)を守ることができるのか。
言霊をテーマにした和風ワンタジー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















