1 / 1
春と娘
しおりを挟む
魚のような雲が空に浮かんでいる。娘は足を止めて空を眺めた。透き通るような青空。日の光を浴びた雲がキラキラと泳いでいる。
さっき横切った公園から春の風が聞こえる。信号が赤から青に変わった。母は娘の手を引いて道路を渡る。途中、信号を待っている車の中に、パパにそっくりな人がいた。二人は駆け出す。母は慌てて、小石を蹴飛ばした。
「また、みんなで水族館に行きたいなあ」
娘が寂しそうに言うと、母は少し困った顔をした。
道端の桜が娘に笑いかける。娘は足を止める。しかし、娘はまた空を眺めた。桜は嫉妬した。だけど、母が笑いかけてくれたから、桜はうれしくなって微笑んだ。
魚のような雲は、青空を横切るように風に乗って泳いでいた。娘は腕を竿にして、小さな身体でその魚を釣ろうとする。青空は頬っぺたを膨らまして、娘の気を引こうとした。キラッと空が光った。太陽が雲をなでつけるように優しく輝いた。まるで大きな水槽。娘はぼんやりと、楽しかった思い出を釣り上げる。キラキラ光る大きな青空。手の届かない美しい光景。たくさんの宝石のような輝き。
まるで夢のような世界。
娘は泣きそうになった。母はいつだって娘を心配している。どこからか風に乗って、カレーの匂い。太陽が少しずつ傾いていく。目を閉じて、少しして開けると、もう夕暮れだった。
空がほんのりと赤みを帯びて、悲しいほど美しく見える。坂を下り、近所のファミリーレストランで少し早めの晩ご飯。
明日は入学式だった。
重たいドアを開ける。娘が先に入り、母が後ろを追いかけるようにドアを閉める。ふと、娘が悲しそうな顔をして、ある一点を見つめていた。母はドキッとした。ゆっくりと顔を向ける。いた。
パパと、知らない女性。
パパは娘に気がつくと、バツの悪そうな顔をして、一度視線を外したが、逃げられないと思ったのか、目の前の女性になにか一言二言ささやき、諦めた顔をして、再び母と娘に顔を向け、小さく手を振った。母は少し考えてから、パパに向かって、目を細め、自然な笑顔をつくった。パパの前に座っている女性は、肩をすぼめて、体を小さく折りたたむように縮めると、隠れるように、そうしてゆっくりと振り向き、二人を一瞬盗み見た。二人は、その顔を焼きつけるように、真っすぐ見つめ返した。
テーブルに案内された二人は、放心状態。メニューを開いたり閉じたり。そのとき、はらりと一枚の紙が落ち、見ると、春メニューのキャンペーン。色とりどりのデザートのかわいらしい絵がたくさん描かれていた。
「水族館みたい」
娘はそう言いながら、目から大きな涙をこぼした。パパと女性の帰っていく後ろ姿が遠くに見える。娘はテーブルにあった紙ナプキンを広げて、顔に押しつけた。涙がじわっと紙を濡らす。すると、紙ナプキンはまるで娘の顔をかたどったお面のようになったので、二人はそれを見て小さく笑った。
「今度、水族館行こっか」
「二人で?」
母は答えなかった。アツアツの料理が運ばれてくる。周りにある空気がシャボン玉のように膨らんで、二人を包み込んだ。それはあたたかく、希望に満ちていた。
「いつもごめんね」
娘は口をもぐもぐさせて頷いた。
「いつもありがとう」
外に出ると、いつの間にか星空が広がっていた。冷たい風。二人は手を握って、寄り添った。
春だった。空気の匂いも、風の冷たさも、星の瞬きも。二人は春の坂道をのぼる。山のてっぺんにいるお月さまが、明日の天気を低い声で教えてくれた。
「明日は、晴れ、晴れ」
娘の歩く傍らで、闇に紛れたクローバーたちの笑い声が聞こえた。公園にいた梅の木が陽気に歌を歌う。見上げると、あ、流れ星。
母は笑いながら、唐突に駆け出した。娘は母の後ろ姿を見つめながら、昼間見た魚の雲を思い浮かべる。
夜空にキラキラ星が光った。
まるで大きな水族館。
母が振り返って大きく手を振った。
娘もうれしくなって、走り出す。胸がドキドキした。周りにいるすべてのものが微笑んでいる気がした。ふと、パパの笑っている顔を思い出した。そうして、自分も大きく笑い返した。
母が坂の上から娘の名前を呼んでいる。
娘は春の夜が、少しだけ好きになった。
さっき横切った公園から春の風が聞こえる。信号が赤から青に変わった。母は娘の手を引いて道路を渡る。途中、信号を待っている車の中に、パパにそっくりな人がいた。二人は駆け出す。母は慌てて、小石を蹴飛ばした。
「また、みんなで水族館に行きたいなあ」
娘が寂しそうに言うと、母は少し困った顔をした。
道端の桜が娘に笑いかける。娘は足を止める。しかし、娘はまた空を眺めた。桜は嫉妬した。だけど、母が笑いかけてくれたから、桜はうれしくなって微笑んだ。
魚のような雲は、青空を横切るように風に乗って泳いでいた。娘は腕を竿にして、小さな身体でその魚を釣ろうとする。青空は頬っぺたを膨らまして、娘の気を引こうとした。キラッと空が光った。太陽が雲をなでつけるように優しく輝いた。まるで大きな水槽。娘はぼんやりと、楽しかった思い出を釣り上げる。キラキラ光る大きな青空。手の届かない美しい光景。たくさんの宝石のような輝き。
まるで夢のような世界。
娘は泣きそうになった。母はいつだって娘を心配している。どこからか風に乗って、カレーの匂い。太陽が少しずつ傾いていく。目を閉じて、少しして開けると、もう夕暮れだった。
空がほんのりと赤みを帯びて、悲しいほど美しく見える。坂を下り、近所のファミリーレストランで少し早めの晩ご飯。
明日は入学式だった。
重たいドアを開ける。娘が先に入り、母が後ろを追いかけるようにドアを閉める。ふと、娘が悲しそうな顔をして、ある一点を見つめていた。母はドキッとした。ゆっくりと顔を向ける。いた。
パパと、知らない女性。
パパは娘に気がつくと、バツの悪そうな顔をして、一度視線を外したが、逃げられないと思ったのか、目の前の女性になにか一言二言ささやき、諦めた顔をして、再び母と娘に顔を向け、小さく手を振った。母は少し考えてから、パパに向かって、目を細め、自然な笑顔をつくった。パパの前に座っている女性は、肩をすぼめて、体を小さく折りたたむように縮めると、隠れるように、そうしてゆっくりと振り向き、二人を一瞬盗み見た。二人は、その顔を焼きつけるように、真っすぐ見つめ返した。
テーブルに案内された二人は、放心状態。メニューを開いたり閉じたり。そのとき、はらりと一枚の紙が落ち、見ると、春メニューのキャンペーン。色とりどりのデザートのかわいらしい絵がたくさん描かれていた。
「水族館みたい」
娘はそう言いながら、目から大きな涙をこぼした。パパと女性の帰っていく後ろ姿が遠くに見える。娘はテーブルにあった紙ナプキンを広げて、顔に押しつけた。涙がじわっと紙を濡らす。すると、紙ナプキンはまるで娘の顔をかたどったお面のようになったので、二人はそれを見て小さく笑った。
「今度、水族館行こっか」
「二人で?」
母は答えなかった。アツアツの料理が運ばれてくる。周りにある空気がシャボン玉のように膨らんで、二人を包み込んだ。それはあたたかく、希望に満ちていた。
「いつもごめんね」
娘は口をもぐもぐさせて頷いた。
「いつもありがとう」
外に出ると、いつの間にか星空が広がっていた。冷たい風。二人は手を握って、寄り添った。
春だった。空気の匂いも、風の冷たさも、星の瞬きも。二人は春の坂道をのぼる。山のてっぺんにいるお月さまが、明日の天気を低い声で教えてくれた。
「明日は、晴れ、晴れ」
娘の歩く傍らで、闇に紛れたクローバーたちの笑い声が聞こえた。公園にいた梅の木が陽気に歌を歌う。見上げると、あ、流れ星。
母は笑いながら、唐突に駆け出した。娘は母の後ろ姿を見つめながら、昼間見た魚の雲を思い浮かべる。
夜空にキラキラ星が光った。
まるで大きな水族館。
母が振り返って大きく手を振った。
娘もうれしくなって、走り出す。胸がドキドキした。周りにいるすべてのものが微笑んでいる気がした。ふと、パパの笑っている顔を思い出した。そうして、自分も大きく笑い返した。
母が坂の上から娘の名前を呼んでいる。
娘は春の夜が、少しだけ好きになった。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

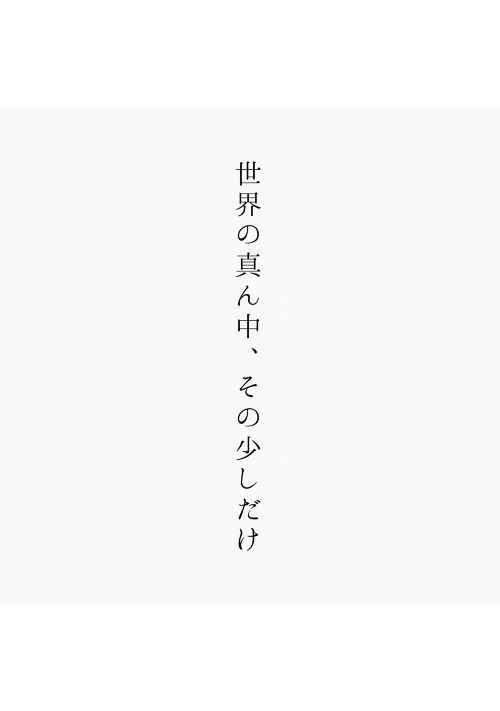



サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


詩「母。の夢」
有原野分
現代文学
※2022年1月の作品です。
読んでいただけると幸いです。
いいね、スキ、フォロー、シェア、コメント、サポート、支援などしていただけるととても嬉しいです。
これからも応援よろしくお願いします。
あなたの人生の
貴重な時間をどうもありがとう。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















