お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

パラサイト/ブランク
羊原ユウ
ホラー
舞台は200X年の日本。寄生生物(パラサイト)という未知の存在が日常に潜む宵ヶ沼市。地元の中学校に通う少年、坂咲青はある日同じクラスメイトの黒河朱莉に夜の旧校舎に呼び出されるのだが、そこで彼を待っていたのはパラサイトに変貌した朱莉の姿だった…。
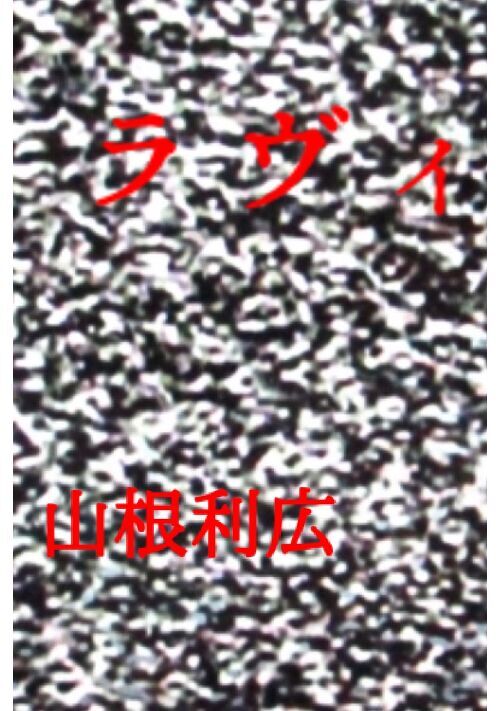
ラヴィ
山根利広
ホラー
男子高校生が不審死を遂げた。
現場から同じクラスの女子生徒のものと思しきペンが見つかる。
そして、解剖中の男子の遺体が突如消失してしまう。
捜査官の遠井マリナは、この事件の現場検証を行う中、奇妙な点に気づく。
「七年前にわたしが体験した出来事と酷似している——」
マリナは、まるで過去をなぞらえたような一連の展開に違和感を覚える。
そして、七年前同じように死んだクラスメイトの存在を思い出す。
だがそれは、連環する狂気の一端にすぎなかった……。

紺青の鬼
砂詠 飛来
ホラー
専門学校の卒業制作として執筆したものです。
千葉県のとある地域に言い伝えられている民話・伝承を砂詠イズムで書きました。
全3編、連作になっています。
江戸時代から現代までを大まかに書いていて、ちょっとややこしいのですがみなさん頑張ってついて来てください。
幾年も前の作品をほぼそのまま載せるので「なにこれ稚拙な文め」となると思いますが、砂詠もそう思ったのでその感覚は正しいです。
この作品を執筆していたとある秋の夜、原因不明の高熱にうなされ胃液を吐きまくるという現象に苛まれました。しぬかと思いましたが、いまではもう笑い話です。よかったいのちがあって。
其のいち・青鬼の井戸、生き肝の眼薬
──慕い合う気持ちは、歪み、いつしか井戸のなかへ消える。
その村には一軒の豪農と古い井戸があった。目の見えない老婆を救うためには、子どもの生き肝を喰わねばならぬという。怪しげな僧と女の童の思惑とは‥‥。
其のに・青鬼の面、鬼堂の大杉
──許されぬ欲望に身を任せた者は、孤独に苛まれ後悔さえ無駄になる。
その年頃の娘と青年は、決して結ばれてはならない。しかし、互いの懸想に気がついたときには、すでにすべてが遅かった。娘に宿った新たな命によって狂わされた運命に‥‥。
其のさん・青鬼の眼、耳切りの坂
──抗うことのできぬ輪廻は、ただ空回りしただけにすぎなかった。
その眼科医のもとをふいに訪れた患者が、思わぬ過去を携えてきた。自身の出生の秘密が解き明かされる。残酷さを刻み続けてきただけの時が、いまここでつながろうとは‥‥。

究極?のデスゲーム
Algo_Lighter
ホラー
気がつくと、見知らぬ島に集められた参加者たち。
黒いフードを被った謎のゲームマスターが告げる—— 「これは究極のデスゲームだ」。
生き残るのはただ一人。他の者に待つのは"ゲームオーバー"のみ。
次々に始まる試練、迫りくる恐怖、そして消えていく敗者たち。
しかし、ゲームが進むにつれて、どこか違和感を覚え始める主人公・ハル。
このデスゲーム、本当に"命がけ"なのか……?
絶望と笑いが交錯する、予測不能のサバイバルゲームが今、幕を開ける!

チェーンメール【マカシリーズ・8】
hosimure
ホラー
私の周囲の学生達は皆、チェーンメールに怯えています。
いつの頃か、学生限定で送られてくるメール。
他の人に送ると、自動的に消えるメール。
いつまでもケータイに残しておくと…。



ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















