お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

揚げ物、お好きですか?リメイク版
ツ~
ファンタジー
揚げ物処「大和」の店主ヤマトは、ひょんな事から、エルフの国『エルヘルム』へと連れて来られ、そこで店をひらけと女王に命令される。
お金の無いヤマトは、仲間に助けられ、ダンジョンに潜って、お金や食材を調達したり、依頼されたクエストをこなしたり、お客さんとのふれ合いだったり……と大忙し?
果たして、ヤマトの異世界生活はどうなるのか?!

魔王の息子に転生したら、いきなり魔王が討伐された
ふぉ
ファンタジー
魔王の息子に転生したら、生後三ヶ月で魔王が討伐される。
魔領の山で、幼くして他の魔族から隠れ住む生活。
逃亡の果て、気が付けば魔王の息子のはずなのに、辺境で豆スープをすする極貧の暮らし。
魔族や人間の陰謀に巻き込まれつつ、
いつも美味しいところを持って行くのはジイイ、ババア。
いつか強くなって無双できる日が来るんだろうか?
1章 辺境極貧生活編
2章 都会発明探偵編
3章 魔術師冒険者編
4章 似非魔法剣士編
5章 内政全知賢者編
6章 無双暗黒魔王編
7章 時操新代魔王編
終章 無双者一般人編
サブタイを駄洒落にしつつ、全261話まで突き進みます。
---------
《異界の国に召喚されたら、いきなり魔王に攻め滅ぼされた》
http://www.alphapolis.co.jp/content/cover/952068299/
同じ世界の別の場所での話になります。
オキス君が生まれる少し前から始まります。

悪役令嬢にざまぁされた王子のその後
柚木崎 史乃
ファンタジー
王子アルフレッドは、婚約者である侯爵令嬢レティシアに窃盗の濡れ衣を着せ陥れようとした罪で父王から廃嫡を言い渡され、国外に追放された。
その後、炭鉱の町で鉱夫として働くアルフレッドは反省するどころかレティシアや彼女の味方をした弟への恨みを募らせていく。
そんなある日、アルフレッドは行く当てのない訳ありの少女マリエルを拾う。
マリエルを養子として迎え、共に生活するうちにアルフレッドはやがて自身の過去の過ちを猛省するようになり改心していった。
人生がいい方向に変わったように見えたが……平穏な生活は長く続かず、事態は思わぬ方向へ動き出したのだった。
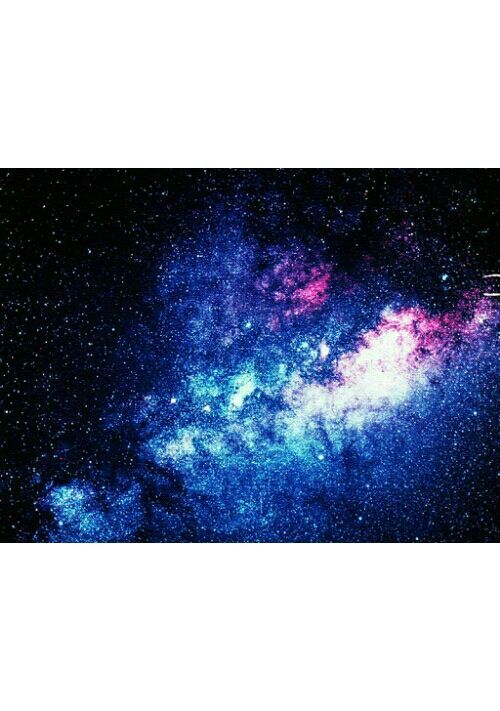
ステラ☆オーナーズ〜星の魔法使い〜
霜山 蛍
ファンタジー
中学生になった桜之宮菜奈花は、ごく普通の平凡な少女であった。そんな奈菜花は入学式の前夜に、不思議な夢を見ることになる。22枚の散らばったカード。それがアルカナであると知り、その不思議な力に触れた時、菜奈花の物語は動き出す。

異世界着ぐるみ転生
こまちゃも
ファンタジー
旧題:着ぐるみ転生
どこにでもいる、普通のOLだった。
会社と部屋を往復する毎日。趣味と言えば、十年以上続けているRPGオンラインゲーム。
ある日気が付くと、森の中だった。
誘拐?ちょっと待て、何この全身モフモフ!
自分の姿が、ゲームで使っていたアバター・・・二足歩行の巨大猫になっていた。
幸い、ゲームで培ったスキルや能力はそのまま。使っていたアイテムバッグも中身入り!
冒険者?そんな怖い事はしません!
目指せ、自給自足!
*小説家になろう様でも掲載中です
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















