111 / 215
碧の癒し
3
しおりを挟む
「それでもいいんだ!」
グッと拳を握り宣言し、今回は「それに」と付け加える。
「聴き方によっては、少しは違う事言うかもしんねぇし」
「――あのね。言っておくけど、時任は特別だよ」
「は?」
石段から足を離して彬に向き直った隆哉は、呆れたように上目遣いに彬を見遣って腕を組んだ。
「死んだ人間。特に何かしらの強い執着を持ってこっちに留まってる霊とは、まともに会話なんて出来やしないよ。それは年月を重ねれば重ねる程、難しくなる。向こうは言いたい事だけを言ってくるし、こっちが何を聴いても答えようともしない。その執着だけに支配されていくようになる。『人』だったという意識も薄れ、人ではない別の『存在』。言葉すらも通じない、『壊れた古いレコード』のように同じ言葉フレーズだけを繰り返す、そんな存在へと変貌していくんだ。
勿論、あの子はまだそこまでにはなってないけど、自分の名前すら答えない。時任のように普通に会話したり、笑ったりなんてのは、その執着を取り除くまでは絶対無理。つまり大下自身に彼女を思い出させて、その『友達の証し』が何だったのかを突き止めるまでは、最低でもね。彼女もそれを望んでる。他の人間なんてお呼びじゃない」
グッと拳を握り宣言し、今回は「それに」と付け加える。
「聴き方によっては、少しは違う事言うかもしんねぇし」
「――あのね。言っておくけど、時任は特別だよ」
「は?」
石段から足を離して彬に向き直った隆哉は、呆れたように上目遣いに彬を見遣って腕を組んだ。
「死んだ人間。特に何かしらの強い執着を持ってこっちに留まってる霊とは、まともに会話なんて出来やしないよ。それは年月を重ねれば重ねる程、難しくなる。向こうは言いたい事だけを言ってくるし、こっちが何を聴いても答えようともしない。その執着だけに支配されていくようになる。『人』だったという意識も薄れ、人ではない別の『存在』。言葉すらも通じない、『壊れた古いレコード』のように同じ言葉フレーズだけを繰り返す、そんな存在へと変貌していくんだ。
勿論、あの子はまだそこまでにはなってないけど、自分の名前すら答えない。時任のように普通に会話したり、笑ったりなんてのは、その執着を取り除くまでは絶対無理。つまり大下自身に彼女を思い出させて、その『友達の証し』が何だったのかを突き止めるまでは、最低でもね。彼女もそれを望んでる。他の人間なんてお呼びじゃない」
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

赤い部屋
白河甚平@壺
ホラー
ミネ子が大切にしているウサギを何者かに飼育小屋を荒らされ殺されていた。
ウサギたちの無残な死に方を見てミネ子は泣き崩れる。
彼女の前に現れたお蝶夫人が「みんなから同情されたくてあなたが殺したんでしょ」とクラスのみんなの前で彼女を責め、嫌がらせをしにきた。
助男はミネ子の前に立ちはだかりなんとかお蝶夫人を追っ払うことができたが、
気が付くと場面が変わり、彼はある地下牢に閉じ込められてしまった。
その隣に別の檻に入った怯えるお蝶夫人がいた。
そこに忍び寄るのは、お腹を空かせて狂人になったミネ子だった。
助男は震えながら凄まじい光景を目の当たりにする…。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が
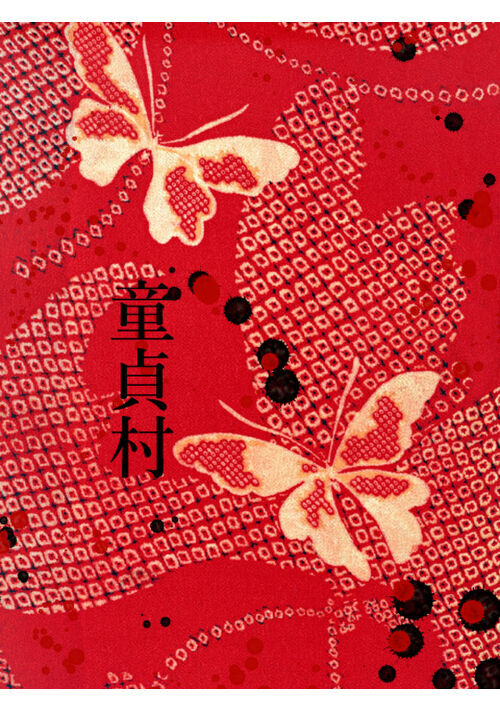
童貞村
雷尾
ホラー
動画サイトで配信活動をしている男の元に、ファンやリスナーから阿嘉黒町の奥地にある廃村の探索をしてほしいと要望が届いた。名前すらもわからないその村では、廃村のはずなのに今でも人が暮らしているだとか、過去に殺人事件があっただとか、その土地を知る者の間では禁足地扱いされているといった不穏な噂がまことしやかに囁かれていた。※BL要素ありです※
作中にでてくるユーチューバー氏は進行役件観測者なので、彼はBLしません。
※ユーチューバー氏はこちら
https://www.alphapolis.co.jp/manga/980286919/965721001

トランプデスゲーム
ホシヨノ クジラ
ホラー
暗闇の中、舞台は幕を開けた
恐怖のデスゲームが始まった
死にたい少女エルラ
元気な少女フジノ
強気な少女ツユキ
しっかり者の少女ラン
4人は戦う、それぞれの目標を胸に
約束を果たすために
デスゲームから明らかになる事実とは!?

極上の女
伏織綾美
ホラー
※他サイト閉鎖のときに転載。その際複数ページを1ページにまとめているので、1ページ1ページが長いです。
暗い過去を持つ主人公が、ある日引越しした先の家で様々な怪現象に見舞われます。
幾度となく主人公の前に現れる見知らぬ少年の幽霊。
何度も見る同じ夢。
一体主人公は何に巻き込まれて行くのでしょうか。
別のやつが終わったら加筆修正します。多分

受け継がれるローファー
ハヤサカツカサ
ホラー
「校舎にある片方だけのローファーの噂のこと知ってる?」
高校説明会後の自由時間。図書室で一冊の本を開いた少女の頭の中に、その言葉を皮切りに一人の女子高校生の記憶が流れ込んでくる。それはその高校のとある場所に新しいままであり続けるローファーに関するものだった。ローファーはなぜ新しくなり続けるのか?
その理由を知って、本を閉じた時何かが起こる!
*心臓が弱い方はあらかじめご遠慮ください
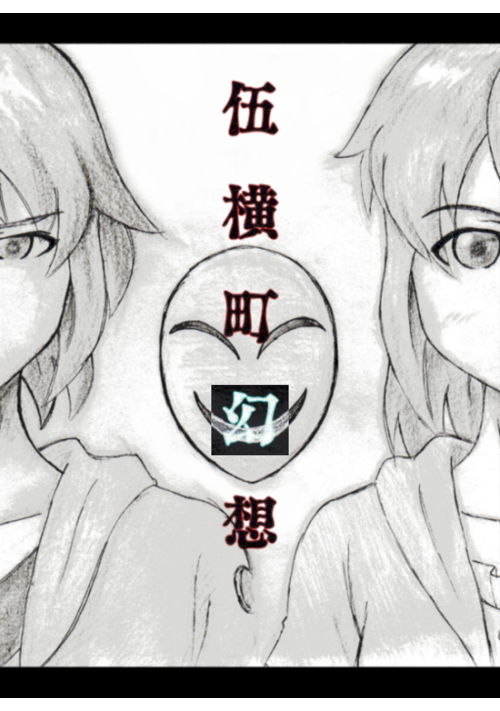
【連作ホラー】伍横町幻想 —Until the day we meet again—
至堂文斗
ホラー
――その幻想から、逃れられるか。
降霊術。それは死者を呼び出す禁忌の術式。
歴史を遡れば幾つも逸話はあれど、現実に死者を呼ぶことが出来たかは定かでない。
だがあるとき、長い実験の果てに、一人の男がその術式を生み出した。
降霊術は決して公に出ることはなかったものの、書物として世に残り続けた。
伍横町。そこは古くから気の流れが集まる場所と言われている小さな町。
そして、全ての始まりの町。
男が生み出した術式は、この町で幾つもの悲劇をもたらしていく。
運命を狂わされた者たちは、生と死の狭間で幾つもの涙を零す。
これは、四つの悲劇。
【魂】を巡る物語の始まりを飾る、四つの幻想曲――。
【霧夏邸幻想 ―Primal prayer-】
「――霧夏邸って知ってる?」
事故により最愛の娘を喪い、 降霊術に狂った男が住んでいた邸宅。
霊に会ってみたいと、邸内に忍び込んだ少年少女たちを待ち受けるものとは。
【三神院幻想 ―Dawn comes to the girl―】
「どうか、目を覚ましてはくれないだろうか」
眠りについたままの少女のために、 少年はただ祈り続ける。
その呼び声に呼応するかのように、 少女は記憶の世界に覚醒する。
【流刻園幻想 ―Omnia fert aetas―】
「……だから、違っていたんだ。沢山のことが」
七不思議の噂で有名な流刻園。夕暮れ時、教室には二人の少年少女がいた。
少年は、一通の便箋で呼び出され、少女と別れて屋上へと向かう。それが、悲劇の始まりであるとも知らずに。
【伍横町幻想 ―Until the day we meet again―】
「……ようやく、時が来た」
伍横町で降霊術の実験を繰り返してきた仮面の男。 最愛の女性のため、彼は最後の計画を始動する。
その計画を食い止めるべく、悲劇に巻き込まれた少年少女たちは苛酷な戦いに挑む。
伍横町の命運は、子どもたちの手に委ねられた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















