64 / 376
王位継承──前編
【39】決別と行く末(1)
しおりを挟む
あれから何時間が経過していたのか。椅子に座り、ベッドに伏せたままいつの間にか眠ってしまっていた瑠既は、また現実へと戻ってきた。
目が熱く、頭が痛い。──寝起きは最悪だ。ずっしりと重い上半身を起こす。
「やっとお目覚めですか」
幼いころに聞き慣れた声が、耳を通過する。──大臣の声だ。眠っている間に入ってきたのだろう。声をかけられても、瑠既には返答する気力が出ない。
「お目覚めですか?」
この声には驚き、まぶたが上下に開いて上半身が起き、首まで勝手に動く。──そこには沙稀もいた。
「現実は変えられない。悲しみ尽くして故人が生き返ることがあるのなら、今ごろ俺もそうしている」
「どういう……」
「戦地で心と、剣士としての生命を失った元相方が……先日、久しぶりに会い元気になってくれたと思っていたのに、絶命していた。今朝、埋葬の手続きを終えたところだ」
そういえば、この部屋に向かう途中で大臣は言っていた。『王が亡くなった』と。そして、瑠既の知らない、沙稀の元相方も。──つまり、倭穏だけが被害者だったわけではないという事実。
「何があったんだ? 俺がいなかった間に」
「奇襲にあった。今回命を落とした者、負傷した者の責任は、すべて俺にある」
よく見れば、沙稀の瞳はわずかに赤い。それは、悲しみからなのか、悔しさからなのか、後悔からなのか。瑠既の頭はグチャグチャで、結論は出ない。
『戦地で』という言葉に、ぼんやりと瑠既は想像だけの過酷な情景を思い浮かべる。過去の沙稀は、戦地へ赴いていたのだろうかと。
まとまらない頭は、思ってもいない感情を吐き出す。
「お前のせいじゃない。それに、そーゆー上辺だけの言葉は聞きたくない」
うしろめたさから顔を背ける。そのとき、
「沙稀様!」
と、大臣の声が聞こえた気がした。──ほぼ同時に右の肩を強く押され、上半身は反転する。間近で見るのは、リラの瞳。
「俺のせいだ。特に……この人の場合は! 俺は立場がありながら、恭姫を危険にさらした。その結果、どうにも助けられずに出してしまった犠牲がこの人だ! だから、俺を責めろ。憎しめ」
次第ににじむ瞳を見ていたはずなのに、涙を落としたのは瑠既の方で。唇は自制ができないほど震える。
「こいつは俺にとって……倭穏は俺と一緒に地獄に落ちてくれるような、ヤツだった。わかってる。俺は、卑怯者だ。誄姫を俺のいるようなところに引っ張っちゃダメだって、諦めた。倭穏は……こいつならって……」
「それなら這い上がれ」
リラの瞳はまっすぐと強く、瑠既を捉え続ける。
「お前が今、自分のいるところが地獄だというのなら、這い上がれ。好いた人を引きずり込まないなんて、当然だろ。男なんだから! 男なら、たとえ好いた人が地獄にいたとしても、救い上げる。……そうだろ?」
沙稀がまだ何かを言いたそうで、瑠既は待つ。だが、沙稀はもどかしそうに右手を強く握ると、瑠既の肩から左手を離し出て行ってしまった。
沙稀の姿を追って扉の方を向いた大臣が、振り向く。瑠既を見て苦笑いを浮かべる。
「あれでも……瑠既様を励ましているのですよ?」
「わかってるよ」
瑠既は慌てて涙を拭く。
「だって、俺たち……双子だもん」
「おや。双子というのはあんなに長く離れていても、感覚は昔のままでいられるのですか?」
「俺はさ……」
後ろ髪を引かれるように、瑠既は倭穏に体を向き直す。
「双子シンドロームってあるじゃん? 俺はさ、昔から……もし、沙稀が死んだら俺も死んじまうのかなって思ってたんだよ。だからもし……もし、そうなら。きっと逆もあんじゃん。そう思ったらさ、何がなんでも、どうあろうとも、生きていなきゃいけねぇなって……」
「感謝しなくてはいけませんね」
大臣の声が、あまりに近くて瑠既は驚く。
「では、これからも貴男に生き続けていただくために……まずは顔を洗って、着替えていただきましょうか」
目の前に出されたのは、鴻嫗城の嫡子に相応しいような立派な衣服。周到な行動に瑠既が見上げると、大臣はにっこりと微笑んでいた。
地下を出るとすでに昼を回っていた。
大臣が気を遣ってくれたのか、恭良とは会わず、食事は沙稀とふたりきり。
沙稀は相変わらず不機嫌そうで、特にこれと言った会話はない。けれど、時折視線が合っては、
「何?」
と、沙稀は不機嫌を増し、
「いやぁ?」
と、瑠既の機嫌は増すのだった。
昼食後は淡々と沙稀が何かを話したが、瑠既の頭には入ってこない。呆然としているのは、沙稀も重々承知のようで、
「とにかく、大臣が来るまでは俺もお前の部屋で待機する。いいな、俺は単にお前の見張り役。そういう存在でお前のそばにいると思っていろ」
と釘を刺す。──決して、双子の弟としてそばにいるわけではないと。
そう言った割には落ち着かないのか、
「風呂に入って、着替えをしろ」
と、沙稀は世話を焼く。
瑠既は言われて風呂場に足を入れるが、なんとも形容しがたい顔が鏡に映った。
また涙がにじみ、シャワーで流す。また涙は頬を流れ、浴槽に顔を浸す。──こんなにゆっくりと風呂場にいるのは、いつぶりか。ふと、そんなことを思って我に返り、浴室をあとにする。
フカフカのバスタオルに身を包むと、懐かしいやわらかさに腰も足も砕けて、横になってしまいそうになる。それをなんとか座り込むだけでとどめ、うずくまる。
懐かしさに引きずられて、記憶をさまよいそうになる。地に足が着かないような感覚で、現在に戻ろうとするが、深い悲しみで立ち止まりそうになる。
沈んでは浮かび、浮かんでは沈み、停滞しそうになりながら、もがく。
コンコンコン
強めのノック音に意識を戻し、慌てて置いてある服を着て出る。すると、なぜか沙稀は目を見開いて、急いで何かを取り、
「座れ」
と言ってきた。
素直に従うと、頭部はやわらかいもので覆われ、あたたかい風が髪をなでる。
「風邪をひくつもりか」
うんざりしたような冷たい口調。──それなのに、その言葉で瑠既はようやく生家に戻ってきたような感覚が沸いた。
夕方が近くなり、沙稀の言う通りに部屋を出る。案内されるままに歩いたが、沙稀の様子にふと、来た道を見る。そこは、地下に続く階段の前。
沙稀は足を止め、誰かを待っているかのようだった。
視線の先には、遠くに大臣の姿が見え──その奥に見慣れた男の姿も見えた。
瑠既は息を飲む。
口を堅く結び、首は下がっていく。
沙稀が去って行く気配がした。下を向く視界に、沙稀の遠のく足が見える。
しばらくして、
「一緒に来てください」
と聞こえた。大臣だ。──行き先は、見当がつく。
地下の階段を下り、しばらく三人で歩く。着いた先は予想通り、倭穏の体がある場所だった。
大臣が扉を開け、叔が入り、瑠既も続く。叔はヨロヨロと倭穏の枕元へと行く。
いつになく、叔の背中がちいさく見える。
しかし、かけられる言葉などない。
大臣は扉を閉め、立ち止まってしまった瑠既のとなりに並ぶ。そして、深々と頭を下げる。
「この度は大切なお嬢様を……取り返しのつかない事態に。申し訳ございません。こちらでできる限りのことはさせていただきます。もちろん、どんなことを尽くしても、決して許されることはありませんが……」
「ああ、当然だな。そちらの王子様に遊ばれた結果がこれか!」
大臣の言葉を叔は途中で遮り、憤りを露わにする。その言葉に瑠既は口を開かずにはいられない。今まで叔に、こんなにも他人行儀に扱われたことはないのだから。
「叔さん、そんな言い方!」
「本当、こ~んな城の王子様だったとはな」
瑠既の言葉は聞きたくないというように、叔は言葉を被せる。
想像をしていなかった言葉に、瑠既の思考が停止する。綺で過ごした年月は、なんだったのかと。
あたたかい思い出だけが駆け巡り、反論する言葉が出ない。
叔は瑠既の感情を一滴も汲もうとはせず、蔑んだ目を向ける。
「もう、二度と家には来ないでくれ」
「なっ?」
──何を、言われているのか。
「当たり前だろ」
叔に見えて、本当は叔ではないのではないか。そんな思いすら、瑠既には浮かぶ。
一方の叔は、ぐったりとした倭穏をしっかりと両手で支え、
「じゃあな」
と、足早に出ていく。
目が熱く、頭が痛い。──寝起きは最悪だ。ずっしりと重い上半身を起こす。
「やっとお目覚めですか」
幼いころに聞き慣れた声が、耳を通過する。──大臣の声だ。眠っている間に入ってきたのだろう。声をかけられても、瑠既には返答する気力が出ない。
「お目覚めですか?」
この声には驚き、まぶたが上下に開いて上半身が起き、首まで勝手に動く。──そこには沙稀もいた。
「現実は変えられない。悲しみ尽くして故人が生き返ることがあるのなら、今ごろ俺もそうしている」
「どういう……」
「戦地で心と、剣士としての生命を失った元相方が……先日、久しぶりに会い元気になってくれたと思っていたのに、絶命していた。今朝、埋葬の手続きを終えたところだ」
そういえば、この部屋に向かう途中で大臣は言っていた。『王が亡くなった』と。そして、瑠既の知らない、沙稀の元相方も。──つまり、倭穏だけが被害者だったわけではないという事実。
「何があったんだ? 俺がいなかった間に」
「奇襲にあった。今回命を落とした者、負傷した者の責任は、すべて俺にある」
よく見れば、沙稀の瞳はわずかに赤い。それは、悲しみからなのか、悔しさからなのか、後悔からなのか。瑠既の頭はグチャグチャで、結論は出ない。
『戦地で』という言葉に、ぼんやりと瑠既は想像だけの過酷な情景を思い浮かべる。過去の沙稀は、戦地へ赴いていたのだろうかと。
まとまらない頭は、思ってもいない感情を吐き出す。
「お前のせいじゃない。それに、そーゆー上辺だけの言葉は聞きたくない」
うしろめたさから顔を背ける。そのとき、
「沙稀様!」
と、大臣の声が聞こえた気がした。──ほぼ同時に右の肩を強く押され、上半身は反転する。間近で見るのは、リラの瞳。
「俺のせいだ。特に……この人の場合は! 俺は立場がありながら、恭姫を危険にさらした。その結果、どうにも助けられずに出してしまった犠牲がこの人だ! だから、俺を責めろ。憎しめ」
次第ににじむ瞳を見ていたはずなのに、涙を落としたのは瑠既の方で。唇は自制ができないほど震える。
「こいつは俺にとって……倭穏は俺と一緒に地獄に落ちてくれるような、ヤツだった。わかってる。俺は、卑怯者だ。誄姫を俺のいるようなところに引っ張っちゃダメだって、諦めた。倭穏は……こいつならって……」
「それなら這い上がれ」
リラの瞳はまっすぐと強く、瑠既を捉え続ける。
「お前が今、自分のいるところが地獄だというのなら、這い上がれ。好いた人を引きずり込まないなんて、当然だろ。男なんだから! 男なら、たとえ好いた人が地獄にいたとしても、救い上げる。……そうだろ?」
沙稀がまだ何かを言いたそうで、瑠既は待つ。だが、沙稀はもどかしそうに右手を強く握ると、瑠既の肩から左手を離し出て行ってしまった。
沙稀の姿を追って扉の方を向いた大臣が、振り向く。瑠既を見て苦笑いを浮かべる。
「あれでも……瑠既様を励ましているのですよ?」
「わかってるよ」
瑠既は慌てて涙を拭く。
「だって、俺たち……双子だもん」
「おや。双子というのはあんなに長く離れていても、感覚は昔のままでいられるのですか?」
「俺はさ……」
後ろ髪を引かれるように、瑠既は倭穏に体を向き直す。
「双子シンドロームってあるじゃん? 俺はさ、昔から……もし、沙稀が死んだら俺も死んじまうのかなって思ってたんだよ。だからもし……もし、そうなら。きっと逆もあんじゃん。そう思ったらさ、何がなんでも、どうあろうとも、生きていなきゃいけねぇなって……」
「感謝しなくてはいけませんね」
大臣の声が、あまりに近くて瑠既は驚く。
「では、これからも貴男に生き続けていただくために……まずは顔を洗って、着替えていただきましょうか」
目の前に出されたのは、鴻嫗城の嫡子に相応しいような立派な衣服。周到な行動に瑠既が見上げると、大臣はにっこりと微笑んでいた。
地下を出るとすでに昼を回っていた。
大臣が気を遣ってくれたのか、恭良とは会わず、食事は沙稀とふたりきり。
沙稀は相変わらず不機嫌そうで、特にこれと言った会話はない。けれど、時折視線が合っては、
「何?」
と、沙稀は不機嫌を増し、
「いやぁ?」
と、瑠既の機嫌は増すのだった。
昼食後は淡々と沙稀が何かを話したが、瑠既の頭には入ってこない。呆然としているのは、沙稀も重々承知のようで、
「とにかく、大臣が来るまでは俺もお前の部屋で待機する。いいな、俺は単にお前の見張り役。そういう存在でお前のそばにいると思っていろ」
と釘を刺す。──決して、双子の弟としてそばにいるわけではないと。
そう言った割には落ち着かないのか、
「風呂に入って、着替えをしろ」
と、沙稀は世話を焼く。
瑠既は言われて風呂場に足を入れるが、なんとも形容しがたい顔が鏡に映った。
また涙がにじみ、シャワーで流す。また涙は頬を流れ、浴槽に顔を浸す。──こんなにゆっくりと風呂場にいるのは、いつぶりか。ふと、そんなことを思って我に返り、浴室をあとにする。
フカフカのバスタオルに身を包むと、懐かしいやわらかさに腰も足も砕けて、横になってしまいそうになる。それをなんとか座り込むだけでとどめ、うずくまる。
懐かしさに引きずられて、記憶をさまよいそうになる。地に足が着かないような感覚で、現在に戻ろうとするが、深い悲しみで立ち止まりそうになる。
沈んでは浮かび、浮かんでは沈み、停滞しそうになりながら、もがく。
コンコンコン
強めのノック音に意識を戻し、慌てて置いてある服を着て出る。すると、なぜか沙稀は目を見開いて、急いで何かを取り、
「座れ」
と言ってきた。
素直に従うと、頭部はやわらかいもので覆われ、あたたかい風が髪をなでる。
「風邪をひくつもりか」
うんざりしたような冷たい口調。──それなのに、その言葉で瑠既はようやく生家に戻ってきたような感覚が沸いた。
夕方が近くなり、沙稀の言う通りに部屋を出る。案内されるままに歩いたが、沙稀の様子にふと、来た道を見る。そこは、地下に続く階段の前。
沙稀は足を止め、誰かを待っているかのようだった。
視線の先には、遠くに大臣の姿が見え──その奥に見慣れた男の姿も見えた。
瑠既は息を飲む。
口を堅く結び、首は下がっていく。
沙稀が去って行く気配がした。下を向く視界に、沙稀の遠のく足が見える。
しばらくして、
「一緒に来てください」
と聞こえた。大臣だ。──行き先は、見当がつく。
地下の階段を下り、しばらく三人で歩く。着いた先は予想通り、倭穏の体がある場所だった。
大臣が扉を開け、叔が入り、瑠既も続く。叔はヨロヨロと倭穏の枕元へと行く。
いつになく、叔の背中がちいさく見える。
しかし、かけられる言葉などない。
大臣は扉を閉め、立ち止まってしまった瑠既のとなりに並ぶ。そして、深々と頭を下げる。
「この度は大切なお嬢様を……取り返しのつかない事態に。申し訳ございません。こちらでできる限りのことはさせていただきます。もちろん、どんなことを尽くしても、決して許されることはありませんが……」
「ああ、当然だな。そちらの王子様に遊ばれた結果がこれか!」
大臣の言葉を叔は途中で遮り、憤りを露わにする。その言葉に瑠既は口を開かずにはいられない。今まで叔に、こんなにも他人行儀に扱われたことはないのだから。
「叔さん、そんな言い方!」
「本当、こ~んな城の王子様だったとはな」
瑠既の言葉は聞きたくないというように、叔は言葉を被せる。
想像をしていなかった言葉に、瑠既の思考が停止する。綺で過ごした年月は、なんだったのかと。
あたたかい思い出だけが駆け巡り、反論する言葉が出ない。
叔は瑠既の感情を一滴も汲もうとはせず、蔑んだ目を向ける。
「もう、二度と家には来ないでくれ」
「なっ?」
──何を、言われているのか。
「当たり前だろ」
叔に見えて、本当は叔ではないのではないか。そんな思いすら、瑠既には浮かぶ。
一方の叔は、ぐったりとした倭穏をしっかりと両手で支え、
「じゃあな」
と、足早に出ていく。
0
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

王が気づいたのはあれから十年後
基本二度寝
恋愛
王太子は妃の肩を抱き、反対の手には息子の手を握る。
妃はまだ小さい娘を抱えて、夫に寄り添っていた。
仲睦まじいその王族家族の姿は、国民にも評判がよかった。
側室を取ることもなく、子に恵まれた王家。
王太子は妃を優しく見つめ、妃も王太子を愛しく見つめ返す。
王太子は今日、父から王の座を譲り受けた。
新たな国王の誕生だった。
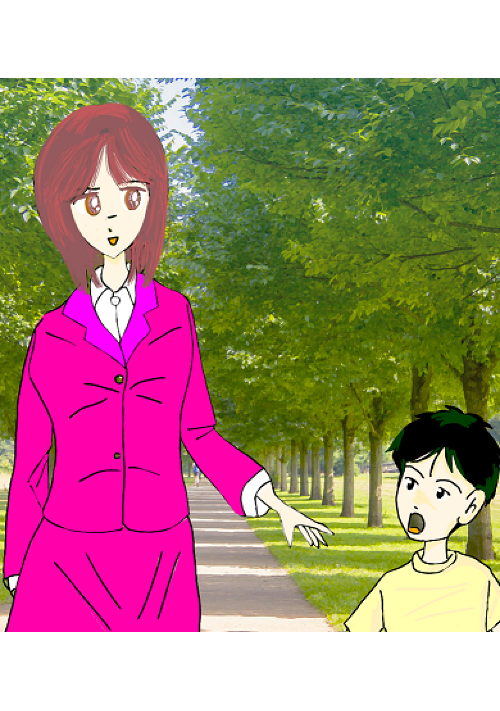
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。

娼館で元夫と再会しました
無味無臭(不定期更新)
恋愛
公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。
しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。
連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。
「シーク様…」
どうして貴方がここに?
元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

もう死んでしまった私へ
ツカノ
恋愛
私には前世の記憶がある。
幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?
今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!
ゆるゆる設定です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















