お気に入りに追加
36
あなたにおすすめの小説

わけありのイケメン捜査官は英国名家の御曹司、潜入先のロンドンで絶縁していた家族が事件に
川喜多アンヌ
ミステリー
あのイケメンが捜査官? 話せば長~いわけありで。
もしあなたの同僚が、潜入捜査官だったら? こんな人がいるんです。
ホークは十四歳で家出した。名門の家も学校も捨てた。以来ずっと偽名で生きている。だから他人に化ける演技は超一流。証券会社に潜入するのは問題ない……のはずだったんだけど――。
なりきり過ぎる捜査官の、どっちが本業かわからない潜入捜査。怒涛のような業務と客に振り回されて、任務を遂行できるのか? そんな中、家族を巻き込む事件に遭遇し……。
リアルなオフィスのあるあるに笑ってください。
主人公は4話目から登場します。表紙は自作です。
主な登場人物
ホーク……米国歳入庁(IRS)特別捜査官である主人公の暗号名。今回潜入中の名前はアラン・キャンベル。恋人の前ではデイヴィッド・コリンズ。
トニー・リナルディ……米国歳入庁の主任特別捜査官。ホークの上司。
メイリード・コリンズ……ワシントンでホークが同棲する恋人。
カルロ・バルディーニ……米国歳入庁捜査局ロンドン支部のリーダー。ホークのロンドンでの上司。
アダム・グリーンバーグ……LB証券でのホークの同僚。欧州株式営業部。
イーサン、ライアン、ルパート、ジョルジオ……同。
パメラ……同。営業アシスタント。
レイチェル・ハリー……同。審査部次長。
エディ・ミケルソン……同。株式部COO。
ハル・タキガワ……同。人事部スタッフ。東京支店のリストラでロンドンに転勤中。
ジェイミー・トールマン……LB証券でのホークの上司。株式営業本部長。
トマシュ・レコフ……ロマネスク海運の社長。ホークの客。
アンドレ・ブルラク……ロマネスク海運の財務担当者。
マリー・ラクロワ……トマシュ・レコフの愛人。ホークの客。
マーク・スチュアート……資産運用会社『セブンオークス』の社長。ホークの叔父。
グレン・スチュアート……マークの息子。

泣けない、泣かない。
黒蝶
ライト文芸
毎日絶望に耐えている少女・詩音と、偶然教育実習生として彼女の高校に行くことになった恋人・優翔。
ある事情から不登校になった少女・久遠と、通信制高校に通う恋人・大翔。
兄である優翔に憧れる弟の大翔。
しかし、そんな兄は弟の言葉に何度も救われている。
これは、そんな4人から為る物語。
《主な登場人物》
如月 詩音(きらさぎ しおん):大人しめな少女。歌うことが大好きだが、人前ではなかなか歌わない。
小野 優翔(おの ゆうと):詩音の恋人。養護教諭になる為、教育実習に偶然詩音の学校にやってくる。
水無月 久遠(みなづき くおん):家からほとんど出ない少女。読書家で努力家。
小野 大翔(おの ひろと):久遠の恋人。優翔とは兄弟。天真爛漫な性格で、人に好かれやすい。

魔法のせいだからって許せるわけがない
ユウユウ
ファンタジー
私は魅了魔法にかけられ、婚約者を裏切って、婚約破棄を宣言してしまった。同じように魔法にかけられても婚約者を強く愛していた者は魔法に抵抗したらしい。
すべてが明るみになり、魅了がとけた私は婚約者に謝罪してやり直そうと懇願したが、彼女はけして私を許さなかった。

私を幽閉した王子がこちらを気にしているのはなぜですか?
水谷繭
恋愛
婚約者である王太子リュシアンから日々疎まれながら過ごしてきたジスレーヌ。ある日のお茶会で、リュシアンが何者かに毒を盛られ倒れてしまう。
日ごろからジスレーヌをよく思っていなかった令嬢たちは、揃ってジスレーヌが毒を入れるところを見たと証言。令嬢たちの嘘を信じたリュシアンは、ジスレーヌを「裁きの家」というお屋敷に幽閉するよう指示する。
そこは二十年前に魔女と呼ばれた女が幽閉されて死んだ、いわくつきの屋敷だった。何とか幽閉期間を耐えようと怯えながら過ごすジスレーヌ。
一方、ジスレーヌを閉じ込めた張本人の王子はジスレーヌを気にしているようで……。
◇小説家になろうにも掲載中です!
◆表紙はGilry Drop様からお借りした画像を加工して使用しています

王女の中身は元自衛官だったので、継母に追放されたけど思い通りになりません
きぬがやあきら
恋愛
「妻はお妃様一人とお約束されたそうですが、今でもまだ同じことが言えますか?」
「正直なところ、不安を感じている」
久方ぶりに招かれた故郷、セレンティア城の月光満ちる庭園で、アシュレイは信じ難い光景を目撃するーー
激闘の末、王座に就いたアルダシールと結ばれた、元セレンティア王国の王女アシュレイ。
アラウァリア国では、新政権を勝ち取ったアシュレイを国母と崇めてくれる国民も多い。だが、結婚から2年、未だ後継ぎに恵まれないアルダシールに側室を推す声も上がり始める。そんな頃、弟シュナイゼルから結婚式の招待が舞い込んだ。
第2幕、連載開始しました!
お気に入り登録してくださった皆様、ありがとうございます! 心より御礼申し上げます。
以下、1章のあらすじです。
アシュレイは前世の記憶を持つ、セレンティア王国の皇女だった。後ろ盾もなく、継母である王妃に体よく追い出されてしまう。
表向きは外交の駒として、アラウァリア王国へ嫁ぐ形だが、国王は御年50歳で既に18人もの妃を持っている。
常に不遇の扱いを受けて、我慢の限界だったアシュレイは、大胆な計画を企てた。
それは輿入れの道中を、自ら雇った盗賊に襲撃させるもの。
サバイバルの知識もあるし、宝飾品を処分して生き抜けば、残りの人生を自由に謳歌できると踏んでいた。
しかし、輿入れ当日アシュレイを攫い出したのは、アラウァリアの第一王子・アルダシール。
盗賊団と共謀し、晴れて自由の身を望んでいたのに、アルダシールはアシュレイを手放してはくれず……。
アシュレイは自由と幸福を手に入れられるのか?
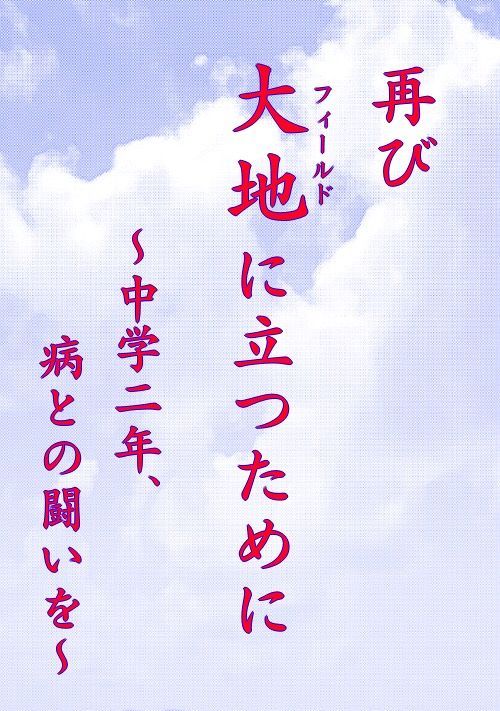
再び大地(フィールド)に立つために 〜中学二年、病との闘いを〜
長岡更紗
ライト文芸
島田颯斗はサッカー選手を目指す、普通の中学二年生。
しかし突然 病に襲われ、家族と離れて一人で入院することに。
中学二年生という多感な時期の殆どを病院で過ごした少年の、闘病の熾烈さと人との触れ合いを描いた、リアルを追求した物語です。
※闘病中の方、またその家族の方には辛い思いをさせる表現が混ざるかもしれません。了承出来ない方はブラウザバックお願いします。
※小説家になろうにて重複投稿しています。

僕の主治医さん
鏡野ゆう
ライト文芸
研修医の北川雛子先生が担当することになったのは、救急車で運び込まれた南山裕章さんという若き外務官僚さんでした。研修医さんと救急車で運ばれてきた患者さんとの恋の小話とちょっと不思議なあひるちゃんのお話。
【本編】+【アヒル事件簿】【事件です!】
※小説家になろう、カクヨムでも公開中※

少女漫画と君と巡る四季
白川ちさと
ライト文芸
尾形爽次郎はこの春、出版社に就職する。
そこで配属されたのが少女漫画雑誌、シュシュの編集部。しかも、指導係の瀬戸原に連れられて、憧れの少女漫画家、夢咲真子の元を訪れることに。
しかし、夢咲真子、本名小野田真咲はぐーたらな性格で、現在連載中の漫画終了と同時に漫画家を辞めようと思っているらしい。
呆然とする爽次郎に瀬戸原は、真咲と新しい企画を作るように言い渡す。しかも、新人歓迎会で先輩編集者たちに問題児作家だと明かされた。前途多難な中、新人編集者の奮闘が始まる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















