8 / 23
八月二十六日
きっと、
しおりを挟む
開きっぱなしの障子を抜けて、窓硝子越しに朧気な曙光が射し込んでくる。それが目蓋の裏を焼いたのか、僕は微睡みのなかで静かな起床の気配を感じていた。分かりやすく眉を顰める。それから重い腕をようよう持ち上げて、そのまま日差しを手で遮った。
──昨夜は何時に寝たろう。いつの間にか朝になっている。思い出したくもない昨日の話がやけに鮮明に思い出されて、そこからの自分の記憶というものは、面白いくらいに思い出せなかった。
『あやめちゃんはもう、死んでるんよ』たったそれだけの小夜の言葉が、僕の胸臆を鬱屈の二文字に染めきってしまっている。
そっと目蓋を開いて、窓硝子の向こうを眺めてみた。紗をかけたように仄暗い、暗澹な様の曇天が一面に広がっているらしい。溜息を吐く気力もなくて、僕はそのまま六時あたりを指している壁掛け時計の文字盤を茫然と見詰めていた。階下では祖父母が何か話している気配がする。正直、降りていく気にはなれない。
──あやめが死んでいるなんて、信じられなかった。この四年間で彼女の訃報なんて耳に入れていないし、何より僕は昨日、あの場所で彼女と会ったのだ。麦わら帽子に純白のワンピースを着て、昔と変わらない眉目良い顔貌をして、そこに存在していた。本当にあやめが死んでいるのなら、僕が再会を果たしたあの少女は、いったい、誰なのだろう。幽霊とでもいうのだろうか。
けれど、わざわざ小夜が『あやめちゃんはもう死んでいる』などと、そんな冗談を創り上げるとも思えない。もしかしたら彼女は、本当に死んでいるのかもしれない。──それなのに、僕はあやめのことを認識している。その齟齬があること自体、根本からおかしいのだ。いっそのこと小夜も連れて、彼女にもう一度、会いに行ってみようか。そうすれば何かが分かるかもしれない。
──そんな一縷の望みだけを胸に秘めて、僕は起き上がった。
◇
祖父母には朝の散歩と称して、僕と小夜は早々に家を出る。彼女は昨夜のことを誰にも話していないらしく、こちらが何かを言われることはなかった。ただ、朝早くに居間へと起床していた小夜の面持ちを見るに、何か言い知れぬ不安を胸の内に渦巻かせているらしい。立場は違っても、それは僕だって同じことだった。
瓦葺きの数奇屋門は、この曇天に降られている。鈍色をした紗の向こうから日差しが仄かに照るくらいで、だから枝葉の影も今日は、消え入りそうなほどに薄ぼけた色をしていた。夏の面影はもはや、アスファルトに篭める熱気と埃っぽさ、そうして、何処から匂うかも分からないぺトリコールみたようなそれだけだった。
「──彩織ちゃんは、本当にあやめちゃんに会ったん?」
門を抜けると、小夜は真っ先にそう訊いてくる。
「うん、会った。ずっと一緒にいたし、話もした」
「……死んでるのに?」
「……うん。僕はそんなこと、まったく知らなかったけど」
「だからって、死んだ人が見えて話せるん?」
「まさか。でも──少なくとも僕はそうだった」
「……それで、ウチを連れて試すんかぁ」
いつもの明朗快活な態度とは違って、小夜は珍しく弱気だった。それもそうだろう──死んだはずの人間と『会って話した』と言われれば、誰でもまずは嘘を疑うに決まっている。ただお互いにその相手が嘘を吐くなどとは思えないのだから、こうして臆する以外に仕様がないのだろう。僕だってきっと、そうしていた。
「でも、あやめちゃんが死んだっていうのは変わらないんよ」
「……うん」
「彩織ちゃんは、そのことをウチに伝えたいだけ?」
「……そう、だね」
返答に窮して、僕は小夜に諭されていることに気がついた。椎奈あやめは、もう死んでいる。それを自分が知らなかっただけだ。なのに、僕は僕の主張ばかりを繰り広げて、その結果に伝えたいことは、『自分は彼女の存在を認知している』というだけ。僕以外の人間からしたら、それは傍迷惑以外の何物でもないのだ。
「なんか、ごめん。僕もよく分かってなくて」
「……いや、いいんよ」
そのまま二人は、無言で歩いていった。何となく歩調を早めたいような、遅めたいような──そんな雑多な心持ちでいる。アスファルトに硬く鳴る靴音が響いて、何処かで雀が囀っていて、烏が啼いていた。蝉時雨にはまだ遠くて、それでも頬は生温い。あやめの家へと続く坂道が見えてくる。昔も、ここを通ってきた。
鈍色の空を仰いでいる木々は、やはり項垂れて悄然としている。消え入りそうな影がアスファルトに落ちては微かに揺れ、落ちてはまた揺れて、その薄ぼけた色合いとは掛け離れた、妙な胸の重苦しさを感じていた。もしかしたら、彼女はいないのかもしれない──そんな悲観した類推を、どこかで抱いたからなのだろう。
緩やかな坂ばいを進んでいく。青青とした木々の匂いも、立ち込める土草の匂いも、今の僕には届かなかった。ここまで来ても、蝉時雨にはまだ遠い。森閑とした空気の中に、たった何匹かの蝉が鳴いて、たった二人の足音がして、息遣いがして──それだけを聞くともなく聞いているうちに、視界は晴れてきてしまった。
──僕は思わず息が詰まる。
民家の軒先に、あやめはいた。昨日と変わらない場所で、変わらない格好で、ただ、やはり、何処かを茫洋と見詰めている。それがおかしいことに、僕はもう気が付いてしまったのだ。脈搏が段々と速度を増していく。心臓が締め付けられるように痛い。僕はいま、間違いなく彼女のことを凝視しているだろう。そんな自覚を胸の内に抱きながら、いきおい隣に並ぶ小夜へ目配せした。
「……いる、んだよね」
彼女は小声でそう洩らす。たった一言きりで、現状を再確認するのには充分すぎた。僕はそのまま頷いて、遠目にあやめを見る。
「……そっか」と小夜は呟いた。伏せがちにしたその瞳には、どんな感情の色が現れていたか、よく分からない。そうして矢庭に踵を返した彼女を、僕はどうしようも出来なかった。ここに引き止める理由も、かと言って引き止めてから素直に行かせる理由も、今の僕には有りはしない。その後ろ姿を、呆然として見送るきりだった。
視線を今一度、あやめに向ける。彼女はもう、死んでいるらしい。まったくそんな風には見えない。鈍い日差しに反照する黒髪も、その一筋一筋までが繊細に靡いていた。健康的な肌も、指先の爪も──とにかく彼女の存在そのものが、生きている人間そのもののように思われて仕様がない。そんな、望みにもならない、憐憫に値する愚考だけを、幾度も幾度も胸臆に渦巻かせている。
依然として、あやめは僕に気が付いていないらしかった。とにかくもう一度、彼女と話がしたい。その一心で歩を踏み出す。それが嫌に重かった。これはきっと、僕があやめに抱いている愚考の重さなのだろう。分かりきっている現実を直視できていない、自分自身の弱さでもある。それでも、進まなければいけなかった。
「……ぁ」
砂利を踏む足音で、ようやく彼女は僕に気が付いたらしい。不意を突かれたように肩を跳ねさせると、ほんの小さな、声にもならない声を、この虚空に洩らした。たった一、二メートルかそこらの距離を隔てて、お互いの息遣いが夏の朝に融けてゆく。玲瓏とした少女の瞳は僕を見詰めて、やや彷徨しているらしかった。
「……来ちゃったんだ」
あやめは僕から視線を落とすと、気恥ずかしいような物悲しいような、そんな何かが綯い交ぜになったらしい笑みを洩らした。彼女の言葉の意味が、今はよく分かる。──本当は来てはいけなかったのかもしれない。でも僕は、来てしまった。自分の標榜したエゴをここまで抱きかかえて、彼女に、会いに来てしまった。
「──来ない方がきっと、幸せだったのにね」
果たしてその言葉を、僕とあやめの、どちらが言ったのだろう。或いは、二人とも言ったのかもしれない。──来ない方がきっと、幸せだった。確かにその通りなのだ。僕も彼女も、きっと。
あやめは瞑目するように目蓋を閉じると、それが深く長い瞬きであるかのように、やがて瞳を覗かせる。そうして、もう一度、僕を見上げた。細やかに伸びた指先が、彼女の胸に添えられる。
「──私、もう死んでるんだよ」
脳髄をありったけの力で殴られたような気がした。酷く眩暈がする。血の気が引いていく感覚がする。思わず眉を顰めてしまった。立つのさえ限界だ。分かりきっていたことのはずなのに。
口の中が嫌に乾いてくる。呼吸が段々と浅くなる。心臓が締め付けられるように痛い。脈搏が幾つを打っているかなどは、意識する余裕すらなかった。現実を直視するのが関の山だった。
「……でも、それだけじゃなかったの」
あくまでも淡々と、彼女は告げる。
「──なんかね、目が見えないんだ」
──昨夜は何時に寝たろう。いつの間にか朝になっている。思い出したくもない昨日の話がやけに鮮明に思い出されて、そこからの自分の記憶というものは、面白いくらいに思い出せなかった。
『あやめちゃんはもう、死んでるんよ』たったそれだけの小夜の言葉が、僕の胸臆を鬱屈の二文字に染めきってしまっている。
そっと目蓋を開いて、窓硝子の向こうを眺めてみた。紗をかけたように仄暗い、暗澹な様の曇天が一面に広がっているらしい。溜息を吐く気力もなくて、僕はそのまま六時あたりを指している壁掛け時計の文字盤を茫然と見詰めていた。階下では祖父母が何か話している気配がする。正直、降りていく気にはなれない。
──あやめが死んでいるなんて、信じられなかった。この四年間で彼女の訃報なんて耳に入れていないし、何より僕は昨日、あの場所で彼女と会ったのだ。麦わら帽子に純白のワンピースを着て、昔と変わらない眉目良い顔貌をして、そこに存在していた。本当にあやめが死んでいるのなら、僕が再会を果たしたあの少女は、いったい、誰なのだろう。幽霊とでもいうのだろうか。
けれど、わざわざ小夜が『あやめちゃんはもう死んでいる』などと、そんな冗談を創り上げるとも思えない。もしかしたら彼女は、本当に死んでいるのかもしれない。──それなのに、僕はあやめのことを認識している。その齟齬があること自体、根本からおかしいのだ。いっそのこと小夜も連れて、彼女にもう一度、会いに行ってみようか。そうすれば何かが分かるかもしれない。
──そんな一縷の望みだけを胸に秘めて、僕は起き上がった。
◇
祖父母には朝の散歩と称して、僕と小夜は早々に家を出る。彼女は昨夜のことを誰にも話していないらしく、こちらが何かを言われることはなかった。ただ、朝早くに居間へと起床していた小夜の面持ちを見るに、何か言い知れぬ不安を胸の内に渦巻かせているらしい。立場は違っても、それは僕だって同じことだった。
瓦葺きの数奇屋門は、この曇天に降られている。鈍色をした紗の向こうから日差しが仄かに照るくらいで、だから枝葉の影も今日は、消え入りそうなほどに薄ぼけた色をしていた。夏の面影はもはや、アスファルトに篭める熱気と埃っぽさ、そうして、何処から匂うかも分からないぺトリコールみたようなそれだけだった。
「──彩織ちゃんは、本当にあやめちゃんに会ったん?」
門を抜けると、小夜は真っ先にそう訊いてくる。
「うん、会った。ずっと一緒にいたし、話もした」
「……死んでるのに?」
「……うん。僕はそんなこと、まったく知らなかったけど」
「だからって、死んだ人が見えて話せるん?」
「まさか。でも──少なくとも僕はそうだった」
「……それで、ウチを連れて試すんかぁ」
いつもの明朗快活な態度とは違って、小夜は珍しく弱気だった。それもそうだろう──死んだはずの人間と『会って話した』と言われれば、誰でもまずは嘘を疑うに決まっている。ただお互いにその相手が嘘を吐くなどとは思えないのだから、こうして臆する以外に仕様がないのだろう。僕だってきっと、そうしていた。
「でも、あやめちゃんが死んだっていうのは変わらないんよ」
「……うん」
「彩織ちゃんは、そのことをウチに伝えたいだけ?」
「……そう、だね」
返答に窮して、僕は小夜に諭されていることに気がついた。椎奈あやめは、もう死んでいる。それを自分が知らなかっただけだ。なのに、僕は僕の主張ばかりを繰り広げて、その結果に伝えたいことは、『自分は彼女の存在を認知している』というだけ。僕以外の人間からしたら、それは傍迷惑以外の何物でもないのだ。
「なんか、ごめん。僕もよく分かってなくて」
「……いや、いいんよ」
そのまま二人は、無言で歩いていった。何となく歩調を早めたいような、遅めたいような──そんな雑多な心持ちでいる。アスファルトに硬く鳴る靴音が響いて、何処かで雀が囀っていて、烏が啼いていた。蝉時雨にはまだ遠くて、それでも頬は生温い。あやめの家へと続く坂道が見えてくる。昔も、ここを通ってきた。
鈍色の空を仰いでいる木々は、やはり項垂れて悄然としている。消え入りそうな影がアスファルトに落ちては微かに揺れ、落ちてはまた揺れて、その薄ぼけた色合いとは掛け離れた、妙な胸の重苦しさを感じていた。もしかしたら、彼女はいないのかもしれない──そんな悲観した類推を、どこかで抱いたからなのだろう。
緩やかな坂ばいを進んでいく。青青とした木々の匂いも、立ち込める土草の匂いも、今の僕には届かなかった。ここまで来ても、蝉時雨にはまだ遠い。森閑とした空気の中に、たった何匹かの蝉が鳴いて、たった二人の足音がして、息遣いがして──それだけを聞くともなく聞いているうちに、視界は晴れてきてしまった。
──僕は思わず息が詰まる。
民家の軒先に、あやめはいた。昨日と変わらない場所で、変わらない格好で、ただ、やはり、何処かを茫洋と見詰めている。それがおかしいことに、僕はもう気が付いてしまったのだ。脈搏が段々と速度を増していく。心臓が締め付けられるように痛い。僕はいま、間違いなく彼女のことを凝視しているだろう。そんな自覚を胸の内に抱きながら、いきおい隣に並ぶ小夜へ目配せした。
「……いる、んだよね」
彼女は小声でそう洩らす。たった一言きりで、現状を再確認するのには充分すぎた。僕はそのまま頷いて、遠目にあやめを見る。
「……そっか」と小夜は呟いた。伏せがちにしたその瞳には、どんな感情の色が現れていたか、よく分からない。そうして矢庭に踵を返した彼女を、僕はどうしようも出来なかった。ここに引き止める理由も、かと言って引き止めてから素直に行かせる理由も、今の僕には有りはしない。その後ろ姿を、呆然として見送るきりだった。
視線を今一度、あやめに向ける。彼女はもう、死んでいるらしい。まったくそんな風には見えない。鈍い日差しに反照する黒髪も、その一筋一筋までが繊細に靡いていた。健康的な肌も、指先の爪も──とにかく彼女の存在そのものが、生きている人間そのもののように思われて仕様がない。そんな、望みにもならない、憐憫に値する愚考だけを、幾度も幾度も胸臆に渦巻かせている。
依然として、あやめは僕に気が付いていないらしかった。とにかくもう一度、彼女と話がしたい。その一心で歩を踏み出す。それが嫌に重かった。これはきっと、僕があやめに抱いている愚考の重さなのだろう。分かりきっている現実を直視できていない、自分自身の弱さでもある。それでも、進まなければいけなかった。
「……ぁ」
砂利を踏む足音で、ようやく彼女は僕に気が付いたらしい。不意を突かれたように肩を跳ねさせると、ほんの小さな、声にもならない声を、この虚空に洩らした。たった一、二メートルかそこらの距離を隔てて、お互いの息遣いが夏の朝に融けてゆく。玲瓏とした少女の瞳は僕を見詰めて、やや彷徨しているらしかった。
「……来ちゃったんだ」
あやめは僕から視線を落とすと、気恥ずかしいような物悲しいような、そんな何かが綯い交ぜになったらしい笑みを洩らした。彼女の言葉の意味が、今はよく分かる。──本当は来てはいけなかったのかもしれない。でも僕は、来てしまった。自分の標榜したエゴをここまで抱きかかえて、彼女に、会いに来てしまった。
「──来ない方がきっと、幸せだったのにね」
果たしてその言葉を、僕とあやめの、どちらが言ったのだろう。或いは、二人とも言ったのかもしれない。──来ない方がきっと、幸せだった。確かにその通りなのだ。僕も彼女も、きっと。
あやめは瞑目するように目蓋を閉じると、それが深く長い瞬きであるかのように、やがて瞳を覗かせる。そうして、もう一度、僕を見上げた。細やかに伸びた指先が、彼女の胸に添えられる。
「──私、もう死んでるんだよ」
脳髄をありったけの力で殴られたような気がした。酷く眩暈がする。血の気が引いていく感覚がする。思わず眉を顰めてしまった。立つのさえ限界だ。分かりきっていたことのはずなのに。
口の中が嫌に乾いてくる。呼吸が段々と浅くなる。心臓が締め付けられるように痛い。脈搏が幾つを打っているかなどは、意識する余裕すらなかった。現実を直視するのが関の山だった。
「……でも、それだけじゃなかったの」
あくまでも淡々と、彼女は告げる。
「──なんかね、目が見えないんだ」
0
お気に入りに追加
14
あなたにおすすめの小説

くろぼし少年スポーツ団
紅葉
ライト文芸
甲子園で選抜高校野球を観戦した幸太は、自分も野球を始めることを決意する。勉強もスポーツも平凡な幸太は、甲子園を夢に見、かつて全国制覇を成したことで有名な地域の少年野球クラブに入る、幸太のチームメイトは親も子も個性的で……。

【書籍発売中】バーン・ホワイトウェイブ ─夏の終わりに消滅した、花のような彼女─
水無月彩椰
ライト文芸
「──大丈夫です。私、八月三十一日に、寿命で消滅しますから」
人付き合いが苦手な高校生・四宮夏月が引き取ったのは、”白波”と名乗る祖父の遺産、余命一ヶ月のバーチャル・ヒューマノイドだった。
遺品整理のために田舎の離島へと帰省した彼は、夏休みの間だけ、白波のマスターとして一つ屋根の下で暮らすことに。
しかし家事もままならないポンコツヒューマノイドは、「マスターの頼みをなんでも叶えます!」と、自らの有用性を証明しようとする。夏月が頼んだのは、『十数年前にこの島で遊んだ初恋の相手』を探すことだった。
「──これが最後の夏休みなので、せめて、この夏休みを楽しく過ごせたら嬉しいです」
世界規模の海面上昇により沈みゆく運命にある小さな離島で、穏やかに消滅を迎えるヒューマノイドは、”最期の夏休み”をマスターと過ごす。
これは夏の哀愁とノスタルジー、そして”夏休みの過ごし方”を描いた、どこか懐かしくて物悲しい、狂おしくも儚い夏物語。
【書籍情報】
https://amzn.asia/d/ga9JWU6

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
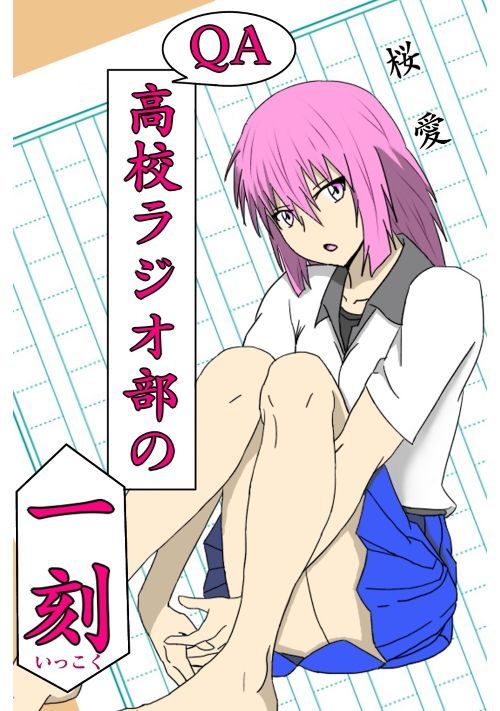
QA高校ラジオの一刻
upruru
ライト文芸
初めまして。upruruです。初めての小説投稿です。ジャンルは、コメディです。異世界に飛ばされてバトルを繰り広げる事も無ければ、主人公が理由もなく何故か最強キャラという事もありません。登場人物は、ちょっと個性的というだけの普通の人間です。そんな人達が繰り広げる戯れを、友人集団を観察している感覚でお付き合いして頂ければ幸いです。

その男、人の人生を狂わせるので注意が必要
いちごみるく
現代文学
「あいつに関わると、人生が狂わされる」
「密室で二人きりになるのが禁止になった」
「関わった人みんな好きになる…」
こんな伝説を残した男が、ある中学にいた。
見知らぬ小グレ集団、警察官、幼馴染の年上、担任教師、部活の後輩に顧問まで……
関わる人すべてを夢中にさせ、頭の中を自分のことで支配させてしまう。
無意識に人を惹き込むその少年を、人は魔性の男と呼ぶ。
そんな彼に関わった人たちがどのように人生を壊していくのか……
地位や年齢、性別は関係ない。
抱える悩みや劣等感を少し刺激されるだけで、人の人生は呆気なく崩れていく。
色んな人物が、ある一人の男によって人生をジワジワと壊していく様子をリアルに描いた物語。
嫉妬、自己顕示欲、愛情不足、孤立、虚言……
現代に溢れる人間の醜い部分を自覚する者と自覚せずに目を背ける者…。
彼らの運命は、主人公・醍醐隼に翻弄される中で確実に分かれていく。
※なお、筆者の拙作『あんなに堅物だった俺を、解してくれたお前の腕が』に出てくる人物たちがこの作品でもメインになります。ご興味があれば、そちらも是非!
※長い作品ですが、1話が300〜1500字程度です。少しずつ読んで頂くことも可能です!

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

三度目の庄司
西原衣都
ライト文芸
庄司有希の家族は複雑だ。
小学校に入学する前、両親が離婚した。
中学校に入学する前、両親が再婚した。
両親は別れたりくっついたりしている。同じ相手と再婚したのだ。
名字が大西から庄司に変わるのは二回目だ。
有希が高校三年生時、両親の関係が再びあやしくなってきた。もしかしたら、また大西になって、また庄司になるかもしれない。うんざりした有希はそんな両親に抗議すべく家出を決行した。
健全な家出だ。そこでよく知ってるのに、知らない男の子と一夏を過ごすことになった。有希はその子と話すうち、この境遇をどうでもよくなってしまった。彼も同じ境遇を引き受けた子供だったから。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















