13 / 33
第13話
しおりを挟む
「おい!二ノ宮!
大丈夫か?」
目を開けると森田君の心配そうな顔があった。ぼうっとしてここがどこか分からない。ゆっくり左右を見回して、保健室だと理解する。
「二ノ宮?」
「うん。起きた。」
心臓が、まだどきどきしている。夢の余韻をひきずったままだった。
深呼吸して、森田君に尋ねる。
「今、何時かな?」
森田君は腕時計を確認した。
「もうすぐ、5時だよ。二ノ宮が起きるのを待っていたんだけど、すごくうなされていたから起こした。
…さっきは、ごめん。」
「ううん。好きな人のことを心配するのは当然だよ。
だいぶん寝ちゃったんだね。
起してくれてありがとう。部活は?」
「あ、うん、今日は休んだよ。」
「そうなんだ。」
気まずい沈黙が流れる。私は、言葉を探す。ぽつりと出たのは、正直な思い。
「私も、なんだかよく分かんなくて不安なんだ。」
森田君がまっすぐに私を見て、うなずく。
「そりゃ、そうだよな。
…久野に、連絡はしてみた?」
「うん。
だけど電話してもつながらないんだ。携帯の電源が入っていないみたい。」
「そっか。
なぁ、今から一緒に久野の家に行ってみないか?」
「うん。行く。」
私は、間髪入れずに答えていた。本当は一人で行くつもりだったから。でも、一人で行くのは怖かった。だから、森田君の提案にすぐに飛びついた。そして、安堵していた。
それから二人、ミキの家まで向かっている。
私たちは始終、無言だった。重たい沈黙は冬の寂しい景色とあいまっていっそう私たちの心を重くした。
交差点にさしかかった時、遠くの方まで見える全ての信号がいっせいに赤へと変わった。混雑する時間帯でたくさんの車がとまり、テールランプが赤い光を放つ。信号とテールランプの赤い光が私に強く、何かを警告しているように感じる。
考えすぎだよね。
電車に乗る際、思い出したように森田君が言った。
「今更気づくようなことじゃないんだけど。
二ノ宮、体調は大丈夫?」
「うん。寝不足なだけだし、さっきたくさん寝たから大丈夫だよ。」
「そう。ごめん。」
「ふふ。
なんだか、さっきから謝ってばかりだね。」
「そうかな?」
「そうだよ。」
互いの緊張が少し緩んだ。固い表情を少しやわらげて森田君が言う。
「なぁ、金魚好きか?」
「金魚?突然どうしたの?」
「うちに今、一匹いてさ。それ、岸田先輩が夏の終わりに出店ですくったやつなんだ。家で飼えないからって、俺にくれてさ。
いる?」
「いいの?」
「うん。」
岸田先輩。
恋に落ちた日の先輩の表情が今も私の心にある。まぶしそうに顔をしかめたあの横顔。心に刻まれたワンシーン。
胸がきゅんと苦しくなった。
先輩、無事だよね?
きっと、悪い予感にとらわれているだけで、後から笑い話になるんだよ。
絶対そうだよ。
変な夢を見たのだって、きっと、私の嫉妬のせい。先輩に対する過剰な執着のせい。
自分に言い聞かせている間に、私は両の手を力いっぱい握りしめていたので、電車が目的地につくころには手がかちかちになっていた。
ミキの家は洒落た洋館で、駅からそう遠くはないところにある。なんども、遊びに行った場所。優しいミキのお母さんはよく自家製のプリンをおやつに出してくれた。
ミキの家の茶色の屋根が見えてきた。外からみる限り、家の中に明かりはなく、留守のようにみえる。
森田君と顔を見合わせた後、インターフォンを押してみる。
一回目、返答がない。
少し待って、二回目を押す。
返答はなかった。
「留守かな?」
「もう一回だけ、押してみよう。」
森田君が言ったので、私は、再びチャイムを鳴らす。
「あら、どうしたの?」
スーパーの袋を両手にさげた年配の女性が声をかけてきた。
「久野さんに、用があって訪ねたんですが、留守みたいで。」
森田君の答えを聞いて女性は眉をひそめる。
「久野さんって…。そちらのお宅、中村さんじゃなかったかしら。
とにかく、今は空き家のはずよ?」
「え?本当に?
どれくらい前からですか?」
「そうね、一年くらいたつんじゃないかしら。」
「二ノ宮、家を間違えたんじゃないの?」
「え?」
私は、呆然と洋館を振り返る。
そんな、暗いからって間違えるはずない!
つい、二週間くらい前にも遊びに来ていたのに。
けれど、手入れのされていない様子は前に訪れた時とは違っていた。玄関には大きな蜘蛛の巣がかかっているし、ところどころすすけて汚れている。表札もなくなっていた。
私は知らず知らずのうちに後ずさりしていた。
森田君はそんな私の様子を目にして、通りがかりの女性に聞いた。
「失礼ですが、こちらのご近所の方ですか?」
「ええ、そうよ。ここのはす向かいに住んでいるの。」
「この辺に、久野さんのお宅があるはずなんですが、ご存じないでしょうか?」
「うーん。聞いたことないわね。」
「そうですか。
すみません。ありがとうございました。」
森田君の体育会系の九十度のおじぎに、女性は会釈で答え、さきほど自分で言った通り、はす向かいのお宅へと帰っていった。
「ここで、間違いないんだな。」
「うん。」
私も、森田君も呆然としていた。
「一体何が起こっているんだ?」
森田君のつぶやきに、私はただ静かにうなずいた。
私たちは無言で帰途につく。来る時よりも、大きな胸のしこりをかかえて。
大丈夫か?」
目を開けると森田君の心配そうな顔があった。ぼうっとしてここがどこか分からない。ゆっくり左右を見回して、保健室だと理解する。
「二ノ宮?」
「うん。起きた。」
心臓が、まだどきどきしている。夢の余韻をひきずったままだった。
深呼吸して、森田君に尋ねる。
「今、何時かな?」
森田君は腕時計を確認した。
「もうすぐ、5時だよ。二ノ宮が起きるのを待っていたんだけど、すごくうなされていたから起こした。
…さっきは、ごめん。」
「ううん。好きな人のことを心配するのは当然だよ。
だいぶん寝ちゃったんだね。
起してくれてありがとう。部活は?」
「あ、うん、今日は休んだよ。」
「そうなんだ。」
気まずい沈黙が流れる。私は、言葉を探す。ぽつりと出たのは、正直な思い。
「私も、なんだかよく分かんなくて不安なんだ。」
森田君がまっすぐに私を見て、うなずく。
「そりゃ、そうだよな。
…久野に、連絡はしてみた?」
「うん。
だけど電話してもつながらないんだ。携帯の電源が入っていないみたい。」
「そっか。
なぁ、今から一緒に久野の家に行ってみないか?」
「うん。行く。」
私は、間髪入れずに答えていた。本当は一人で行くつもりだったから。でも、一人で行くのは怖かった。だから、森田君の提案にすぐに飛びついた。そして、安堵していた。
それから二人、ミキの家まで向かっている。
私たちは始終、無言だった。重たい沈黙は冬の寂しい景色とあいまっていっそう私たちの心を重くした。
交差点にさしかかった時、遠くの方まで見える全ての信号がいっせいに赤へと変わった。混雑する時間帯でたくさんの車がとまり、テールランプが赤い光を放つ。信号とテールランプの赤い光が私に強く、何かを警告しているように感じる。
考えすぎだよね。
電車に乗る際、思い出したように森田君が言った。
「今更気づくようなことじゃないんだけど。
二ノ宮、体調は大丈夫?」
「うん。寝不足なだけだし、さっきたくさん寝たから大丈夫だよ。」
「そう。ごめん。」
「ふふ。
なんだか、さっきから謝ってばかりだね。」
「そうかな?」
「そうだよ。」
互いの緊張が少し緩んだ。固い表情を少しやわらげて森田君が言う。
「なぁ、金魚好きか?」
「金魚?突然どうしたの?」
「うちに今、一匹いてさ。それ、岸田先輩が夏の終わりに出店ですくったやつなんだ。家で飼えないからって、俺にくれてさ。
いる?」
「いいの?」
「うん。」
岸田先輩。
恋に落ちた日の先輩の表情が今も私の心にある。まぶしそうに顔をしかめたあの横顔。心に刻まれたワンシーン。
胸がきゅんと苦しくなった。
先輩、無事だよね?
きっと、悪い予感にとらわれているだけで、後から笑い話になるんだよ。
絶対そうだよ。
変な夢を見たのだって、きっと、私の嫉妬のせい。先輩に対する過剰な執着のせい。
自分に言い聞かせている間に、私は両の手を力いっぱい握りしめていたので、電車が目的地につくころには手がかちかちになっていた。
ミキの家は洒落た洋館で、駅からそう遠くはないところにある。なんども、遊びに行った場所。優しいミキのお母さんはよく自家製のプリンをおやつに出してくれた。
ミキの家の茶色の屋根が見えてきた。外からみる限り、家の中に明かりはなく、留守のようにみえる。
森田君と顔を見合わせた後、インターフォンを押してみる。
一回目、返答がない。
少し待って、二回目を押す。
返答はなかった。
「留守かな?」
「もう一回だけ、押してみよう。」
森田君が言ったので、私は、再びチャイムを鳴らす。
「あら、どうしたの?」
スーパーの袋を両手にさげた年配の女性が声をかけてきた。
「久野さんに、用があって訪ねたんですが、留守みたいで。」
森田君の答えを聞いて女性は眉をひそめる。
「久野さんって…。そちらのお宅、中村さんじゃなかったかしら。
とにかく、今は空き家のはずよ?」
「え?本当に?
どれくらい前からですか?」
「そうね、一年くらいたつんじゃないかしら。」
「二ノ宮、家を間違えたんじゃないの?」
「え?」
私は、呆然と洋館を振り返る。
そんな、暗いからって間違えるはずない!
つい、二週間くらい前にも遊びに来ていたのに。
けれど、手入れのされていない様子は前に訪れた時とは違っていた。玄関には大きな蜘蛛の巣がかかっているし、ところどころすすけて汚れている。表札もなくなっていた。
私は知らず知らずのうちに後ずさりしていた。
森田君はそんな私の様子を目にして、通りがかりの女性に聞いた。
「失礼ですが、こちらのご近所の方ですか?」
「ええ、そうよ。ここのはす向かいに住んでいるの。」
「この辺に、久野さんのお宅があるはずなんですが、ご存じないでしょうか?」
「うーん。聞いたことないわね。」
「そうですか。
すみません。ありがとうございました。」
森田君の体育会系の九十度のおじぎに、女性は会釈で答え、さきほど自分で言った通り、はす向かいのお宅へと帰っていった。
「ここで、間違いないんだな。」
「うん。」
私も、森田君も呆然としていた。
「一体何が起こっているんだ?」
森田君のつぶやきに、私はただ静かにうなずいた。
私たちは無言で帰途につく。来る時よりも、大きな胸のしこりをかかえて。
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

機織姫
ワルシャワ
ホラー
栃木県日光市にある鬼怒沼にある伝説にこんな話がありました。そこで、とある美しい姫が現れてカタンコトンと音を鳴らす。声をかけるとその姫は一変し沼の中へ誘うという恐ろしい話。一人の少年もまた誘われそうになり、どうにか命からがら助かったというが。その話はもはや忘れ去られてしまうほど時を超えた現代で起きた怖いお話。はじまりはじまり
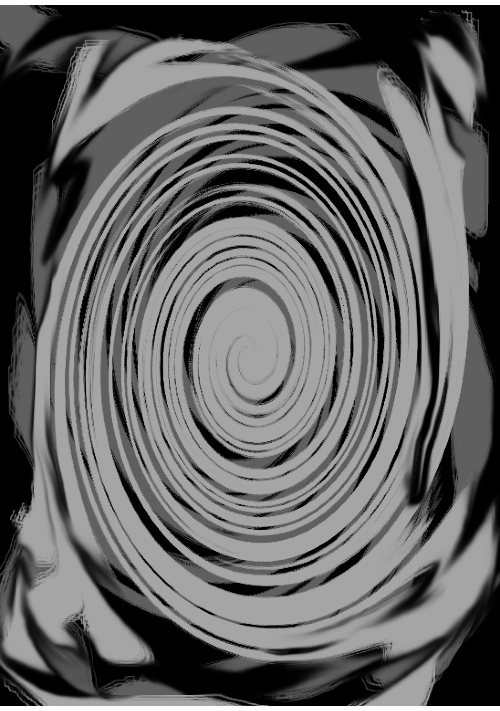

鬼村という作家
篠崎マーティ
ホラー
あの先生、あんまり深入りしない方が良いよ――……。
得体のしれない社会不適合女のホラー作家鬼村とその担当の不憫な一口が、日常の中に潜む何かと不意に同じ空間に存在してしまう瞬間のお話
第6回ホラー・ミステリー小説大賞で奨励賞を頂きました。投票してくださった皆様有難う御座いました!(二十二話時)




ジャクタ様と四十九人の生贄
はじめアキラ
ホラー
「知らなくても無理ないね。大人の間じゃ結構大騒ぎになってるの。……なんかね、禁域に入った馬鹿がいて、何かとんでもないことをやらかしてくれたんじゃないかって」
T県T群尺汰村。
人口数百人程度のこののどかな村で、事件が発生した。禁域とされている移転前の尺汰村、通称・旧尺汰村に東京から来た動画配信者たちが踏込んで、不自然な死に方をしたというのだ。
怯える大人達、不安がる子供達。
やがて恐れていたことが現実になる。村の守り神である“ジャクタ様”を祀る御堂家が、目覚めてしまったジャクタ様を封印するための儀式を始めたのだ。
結界に閉ざされた村で、必要な生贄は四十九人。怪物が放たれた箱庭の中、四十九人が死ぬまで惨劇は終わらない。
尺汰村分校に通う女子高校生の平塚花林と、男子小学生の弟・平塚亜林もまた、その儀式に巻き込まれることになり……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















