お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

あやかし不動産、営業中!
七海澄香
キャラ文芸
ブラック系不動産会社を退職し、勢いで地元に戻った青年、東雲悠弥。
朝霧不動産という小さな不動産屋に転職した悠弥は、風変わりな客と出会う。
「木の葉払いで保証人は大天狗様」内気そうな少年が発した言葉は、あやかしが住まいを探しに来たことを知らせる秘密の合言葉だった。
朝霧不動産では古くから、人間たちと共に生活をしようとするあやかし達に家を貸し、人間とともに暮らす手伝いをしているのだ。
悠弥は跡取り娘の遥と共に、不動産を通してあやかしと人間との縁を結び、絆を繋いでいく。

あやかし漫画家黒川さんは今日も涙目
真木ハヌイ
キャラ文芸
ストーカーから逃げるために、格安のオカルト物件に引っ越した赤城雪子。
だが、彼女が借りた部屋の隣に住む男、黒川一夜の正体は、売れない漫画家で、鬼の妖怪だった!
しかも、この男、鬼の妖怪というにはあまりにもしょぼくれていて、情けない。おまけにド貧乏。
担当編集に売り上げの数字でボコボコにされるし、同じ鬼の妖怪の弟にも、兄として尊敬されていない様子。
ダメダメ妖怪漫画家、黒川さんの明日はどっちだ?
この男、気が付けば、いつも涙目になっている……。
エブリスタ、小説家になろうにも掲載しています。十二万字程度で完結します。五章構成です。

君のハートに☆五寸釘!
鯨井イルカ
キャラ文芸
主人公カズノリと愛情の方向性がエキセントリックな彼女が巻き起こす、一方通行系怪奇ラブ(?)コメディー
下記2作の続編として執筆しています。
1作目「君に★首ったけ!」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/771412269/602178787
2作目「ローリン・マイハニー!」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/771412269/446191134

君に★首ったけ!
鯨井イルカ
キャラ文芸
冷蔵庫を開けると現れる「彼女」と、会社員である主人公ハヤカワのほのぼの日常怪奇コメディ
2018.7.6完結いたしました。
お忙しい中、拙作におつき合いいただき、誠にありがとうございました。
2018.10.16ジャンルをキャラ文芸に変更しました

ヴァーチャル・プライベート・ネットワーク・ガールズ:VPNGs
吉野茉莉
キャラ文芸
【キャライラストつき】【40文字×17行で300Pほど】
2024/01/15更新完了しました。
2042年。
瞳に装着されたレンズを通してネットに接続されている世界。
人々の暮らしは大きく変わり、世界中、月や火星まで家にいながら旅行できるようになった世界。
それでも、かろうじてリアルに学校制度が残っている世界。
これはそこで暮らす彼女たちの物語。
半ひきこもりでぼっちの久慈彩花は、週に一度の登校の帰り、寄り道をした場所で奇妙な指輪を受け取る。なんの気になしにその指輪をはめたとき、システムが勝手に起動し、女子高校生内で密かに行われているゲームに参加することになってしまう。

ま性戦隊シマパンダー
九情承太郎
キャラ文芸
魔性のオーパーツ「中二病プリンター」により、ノベルワナビー(小説家志望)の作品から次々に現れるアホ…個性的な敵キャラたちが、現実世界(特に関東地方)に被害を与えていた。
警察や軍隊で相手にしきれないアホ…個性的な敵キャラに対処するために、多くの民間戦隊が立ち上がった!
そんな戦隊の一つ、極秘戦隊スクリーマーズの一員ブルースクリーマー・入谷恐子は、迂闊な行動が重なり、シマパンの力で戦う戦士「シマパンダー」と勘違いされて悪目立ちしてしまう(笑)
誤解が解ける日は、果たして来るのであろうか?
たぶん、ない!
ま性(まぬけな性分)の戦士シマパンダーによるスーパー戦隊コメディの決定版。笑い死にを恐れぬならば、読むがいい!!
他の小説サイトでも公開しています。
表紙は、画像生成AIで出力したイラストです。

胡蝶の夢に生け
乃南羽緒
キャラ文芸
『栄枯盛衰の常の世に、不滅の名作と謳われる──』
それは、小倉百人一首。
現代の高校生や大学生の男女、ときどき大人が織りなす恋物語。
千年むかしも人は人──想うことはみな同じ。
情に寄りくる『言霊』をあつめるために今宵また、彼は夢路にやってくる。
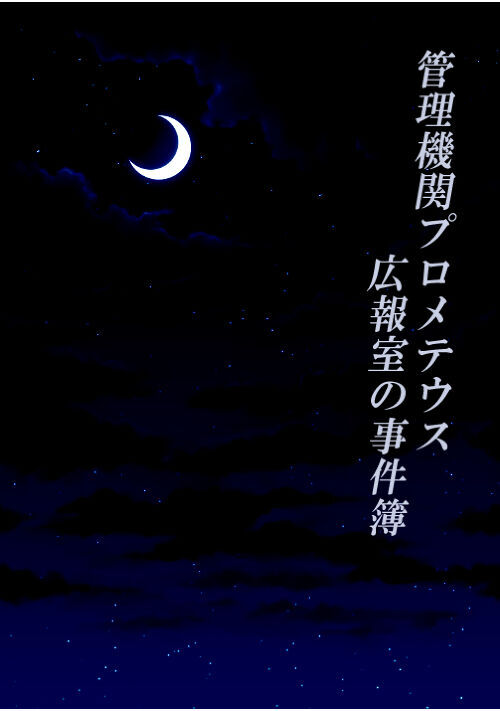
管理機関プロメテウス広報室の事件簿
石動なつめ
キャラ文芸
吸血鬼と人間が共存する世界――という建前で、実際には吸血鬼が人間を支配する世の中。
これは吸血鬼嫌いの人間の少女と、どうしようもなくこじらせた人間嫌いの吸血鬼が、何とも不安定な平穏を守るために暗躍したりしなかったりするお話。
小説家になろう様、ノベルアップ+様にも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















