お気に入りに追加
48
あなたにおすすめの小説
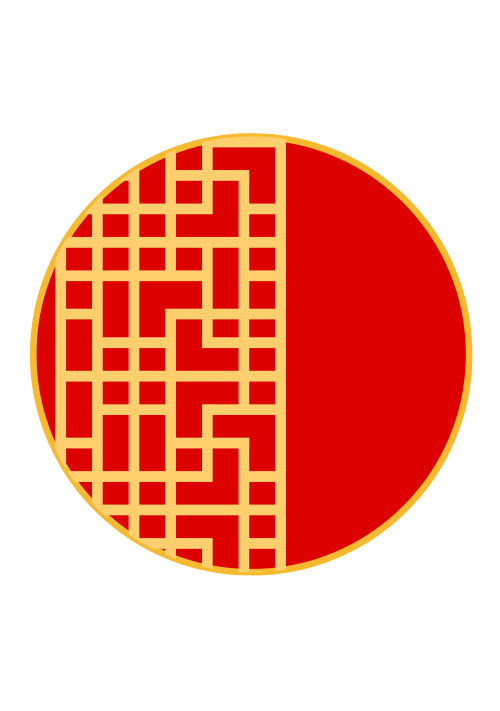
逃げるための後宮行きでしたが、なぜか奴が皇帝になっていました
吉高 花
恋愛
◆転生&ループの中華風ファンタジー◆
第15回恋愛小説大賞「中華・後宮ラブ賞」受賞しました!ありがとうございます!
かつて散々腐れ縁だったあいつが「俺たち、もし三十になってもお互いに独身だったら、結婚するか」
なんてことを言ったから、私は密かに三十になるのを待っていた。でもそんな私たちは、仲良く一緒にトラックに轢かれてしまった。
そして転生しても奴を忘れられなかった私は、ある日奴が綺麗なお嫁さんと仲良く微笑み合っている場面を見てしまう。
なにあれ! 許せん! 私も別の男と幸せになってやる!
しかしそんな決意もむなしく私はまた、今度は馬車に轢かれて逝ってしまう。
そして二度目。なんと今度は最後の人生をループした。ならば今度は前の記憶をフルに使って今度こそ幸せになってやる!
しかし私は気づいてしまった。このままでは、また奴の幸せな姿を見ることになるのでは?
それは嫌だ絶対に嫌だ。そうだ! 後宮に行ってしまえば、奴とは会わずにすむじゃない!
そうして私は意気揚々と、女官として後宮に潜り込んだのだった。
奴が、今世では皇帝になっているとも知らずに。
※タイトル試行錯誤中なのでたまに変わります。最初のタイトルは「ループの二度目は後宮で ~逃げるための後宮でしたが、なぜか奴が皇帝になっていました~」
※設定は架空なので史実には基づいて「おりません」

公爵様、契約通り、跡継ぎを身籠りました!-もう契約は満了ですわよ・・・ね?ちょっと待って、どうして契約が終わらないんでしょうかぁぁ?!-
猫まんじゅう
恋愛
そう、没落寸前の実家を助けて頂く代わりに、跡継ぎを産む事を条件にした契約結婚だったのです。
無事跡継ぎを妊娠したフィリス。夫であるバルモント公爵との契約達成は出産までの約9か月となった。
筈だったのです······が?
◆◇◆
「この結婚は契約結婚だ。貴女の実家の財の工面はする。代わりに、貴女には私の跡継ぎを産んでもらおう」
拝啓、公爵様。財政に悩んでいた私の家を助ける代わりに、跡継ぎを産むという一時的な契約結婚でございましたよね・・・?ええ、跡継ぎは産みました。なぜ、まだ契約が完了しないんでしょうか?
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいませええ!この契約!あと・・・、一体あと、何人子供を産めば契約が満了になるのですッ!!?」
溺愛と、悪阻(ツワリ)ルートは二人がお互いに想いを通じ合わせても終わらない?
◆◇◆
安心保障のR15設定。
描写の直接的な表現はありませんが、”匂わせ”も気になる吐き悪阻体質の方はご注意ください。
ゆるゆる設定のコメディ要素あり。
つわりに付随する嘔吐表現などが多く含まれます。
※妊娠に関する内容を含みます。
【2023/07/15/9:00〜07/17/15:00, HOTランキング1位ありがとうございます!】
こちらは小説家になろうでも完結掲載しております(詳細はあとがきにて、)

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです
青空あかな
恋愛
旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています
チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。
しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。
婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。
さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。
失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。
目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。
二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。
一方、義妹は仕事でミスばかり。
闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。
挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。
※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!
※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。

新婚なのに旦那様と会えません〜公爵夫人は宮廷魔術師〜
秋月乃衣
恋愛
ルクセイア公爵家の美形当主アレクセルの元に、嫁ぐこととなった宮廷魔術師シルヴィア。
宮廷魔術師を辞めたくないシルヴィアにとって、仕事は続けたままで良いとの好条件。
だけど新婚なのに旦那様に中々会えず、すれ違い結婚生活。旦那様には愛人がいるという噂も!?
※魔法のある特殊な世界なので公爵夫人がお仕事しています。

「無加護」で孤児な私は追い出されたのでのんびりスローライフ生活!…のはずが精霊王に甘く溺愛されてます!?
白井
恋愛
誰もが精霊の加護を受ける国で、リリアは何の精霊の加護も持たない『無加護』として生まれる。
「魂の罪人め、呪われた悪魔め!」
精霊に嫌われ、人に石を投げられ泥まみれ孤児院ではこき使われてきた。
それでも生きるしかないリリアは決心する。
誰にも迷惑をかけないように、森でスローライフをしよう!
それなのに―……
「麗しき私の乙女よ」
すっごい美形…。えっ精霊王!?
どうして無加護の私が精霊王に溺愛されてるの!?
森で出会った精霊王に愛され、リリアの運命は変わっていく。

婚約破棄された地味姫令嬢は獣人騎士団のブラッシング係に任命される
安眠にどね
恋愛
社交界で『地味姫』と嘲笑されている主人公、オルテシア・ケルンベルマは、ある日婚約破棄をされたことによって前世の記憶を取り戻す。
婚約破棄をされた直後、王城内で一匹の虎に出会う。婚約破棄と前世の記憶と取り戻すという二つのショックで呆然としていたオルテシアは、虎の求めるままブラッシングをしていた。その虎は、実は獣人が獣の姿になった状態だったのだ。虎の獣人であるアルディ・ザルミールに気に入られて、オルテシアは獣人が多く所属する第二騎士団のブラッシング係として働くことになり――!?
【第16回恋愛小説大賞 奨励賞受賞。ありがとうございました!】

一宿一飯の恩義で竜伯爵様に抱かれたら、なぜか監禁されちゃいました!
当麻月菜
恋愛
宮坂 朱音(みやさか あかね)は、電車に跳ねられる寸前に異世界転移した。そして異世界人を保護する役目を担う竜伯爵の元でお世話になることになった。
しかしある日の晩、竜伯爵当主であり、朱音の保護者であり、ひそかに恋心を抱いているデュアロスが瀕死の状態で屋敷に戻ってきた。
彼は強い媚薬を盛られて苦しんでいたのだ。
このまま一晩ナニをしなければ、死んでしまうと知って、朱音は一宿一飯の恩義と、淡い恋心からデュアロスにその身を捧げた。
しかしそこから、なぜだかわからないけれど監禁生活が始まってしまい……。
好きだからこそ身を捧げた異世界女性と、強い覚悟を持って異世界女性を抱いた男が異世界婚をするまでの、しょーもないアレコレですれ違う二人の恋のおはなし。
※いつもコメントありがとうございます!現在、返信が遅れて申し訳ありません(o*。_。)oペコッ 甘口も辛口もどれもありがたく読ませていただいてます(*´ω`*)
※他のサイトにも重複投稿しています。

「あなたの好きなひとを盗るつもりなんてなかった。どうか許して」と親友に謝られたけど、その男性は私の好きなひとではありません。まあいっか。
石河 翠
恋愛
真面目が取り柄のハリエットには、同い年の従姉妹エミリーがいる。母親同士の仲が悪く、二人は何かにつけ比較されてきた。
ある日招待されたお茶会にて、ハリエットは突然エミリーから謝られる。なんとエミリーは、ハリエットの好きなひとを盗ってしまったのだという。エミリーの母親は、ハリエットを出し抜けてご機嫌の様子。
ところが、紹介された男性はハリエットの好きなひととは全くの別人。しかもエミリーは勘違いしているわけではないらしい。そこでハリエットは伯母の誤解を解かないまま、エミリーの結婚式への出席を希望し……。
母親の束縛から逃れて初恋を叶えるしたたかなヒロインと恋人を溺愛する腹黒ヒーローの恋物語。ハッピーエンドです。
この作品は他サイトにも投稿しております。
扉絵は写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID:23852097)をお借りしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















