お気に入りに追加
22
あなたにおすすめの小説

40歳を過ぎても女性の手を繋いだことのない男性を私が守るのですか!?
鈴木トモヒロ
ライト文芸
実際にTVに出た人を見て、小説を書こうと思いました。
60代の男性。
愛した人は、若く病で亡くなったそうだ。
それ以降、その1人の女性だけを愛して時を過ごす。
その姿に少し感動し、光を当てたかった。
純粋に1人の女性を愛し続ける男性を少なからず私は知っています。
また、結婚したくても出来なかった男性の話も聞いたことがあります。
フィクションとして
「40歳を過ぎても女性の手を繋いだことのない男性を私が守るのですか!?」を書いてみたいと思いました。
若い女性を主人公に、男性とは違う視点を想像しながら文章を書いてみたいと思います。
どんなストーリーになるかは...
わたしも楽しみなところです。

私の主治医さん - 二人と一匹物語 -
鏡野ゆう
ライト文芸
とある病院の救命救急で働いている東出先生の元に運び込まれた急患は何故か川で溺れていた一人と一匹でした。救命救急で働くお医者さんと患者さん、そして小さな子猫の二人と一匹の恋の小話。
【本編完結】【小話】
※小説家になろうでも公開中※

いつか『幸せ』になる!
峠 凪
ライト文芸
ある日仲良し4人組の女の子達が異世界に勇者や聖女、賢者として国を守る為に呼ばれた。4人の内3人は勇者といった称号を持っていたが、1人は何もなく、代わりに『魔』属性を含む魔法が使えた。その国、否、世界では『魔』は魔王等の人に害をなすとされる者達のみが使える属性だった。
基本、『魔』属性を持つ女の子視点です。
※過激な表現を入れる予定です。苦手な方は注意して下さい。
暫く更新が不定期になります。

まずい飯が食べたくて
森園ことり
ライト文芸
有名店の仕事を辞めて、叔父の居酒屋を手伝うようになった料理人の新(あらた)。いい転職先の話が舞い込むが、新は居酒屋の仕事に惹かれていく。気になる女性も現れて…。
※この作品は「エブリスタ」にも投稿しています

【完結】雇われ見届け人 婿入り騒動
盤坂万
歴史・時代
チャンバラで解決しないお侍さんのお話。
武士がサラリーマン化した時代の武士の生き方のひとつを綴ります。
正解も間違いもない、今の世の中と似た雰囲気の漂う江戸中期。新三郎の特性は「興味本位」、武器は「情報収集能力」だけ。
平穏系武士の新境地を、新三郎が持ち前の特性と武器を活かして切り開きます。
※表紙絵は、cocoanco様のフリー素材を使用して作成しました


三度目の庄司
西原衣都
ライト文芸
庄司有希の家族は複雑だ。
小学校に入学する前、両親が離婚した。
中学校に入学する前、両親が再婚した。
両親は別れたりくっついたりしている。同じ相手と再婚したのだ。
名字が大西から庄司に変わるのは二回目だ。
有希が高校三年生時、両親の関係が再びあやしくなってきた。もしかしたら、また大西になって、また庄司になるかもしれない。うんざりした有希はそんな両親に抗議すべく家出を決行した。
健全な家出だ。そこでよく知ってるのに、知らない男の子と一夏を過ごすことになった。有希はその子と話すうち、この境遇をどうでもよくなってしまった。彼も同じ境遇を引き受けた子供だったから。
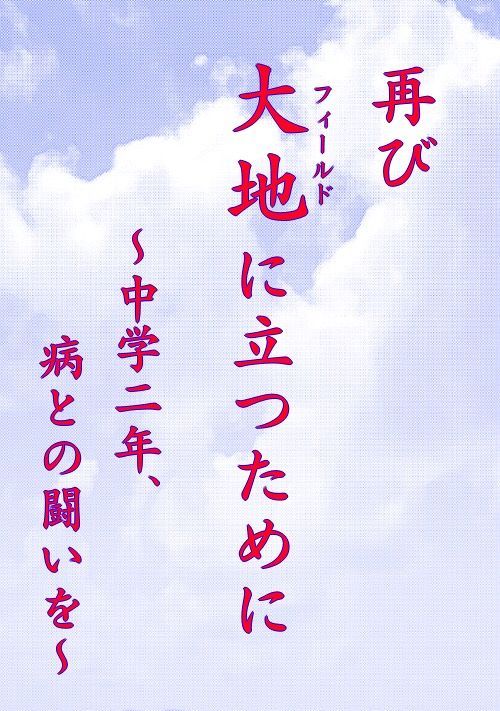
再び大地(フィールド)に立つために 〜中学二年、病との闘いを〜
長岡更紗
ライト文芸
島田颯斗はサッカー選手を目指す、普通の中学二年生。
しかし突然 病に襲われ、家族と離れて一人で入院することに。
中学二年生という多感な時期の殆どを病院で過ごした少年の、闘病の熾烈さと人との触れ合いを描いた、リアルを追求した物語です。
※闘病中の方、またその家族の方には辛い思いをさせる表現が混ざるかもしれません。了承出来ない方はブラウザバックお願いします。
※小説家になろうにて重複投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















