お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

クロワッサン物語
コダーマ
歴史・時代
1683年、城塞都市ウィーンはオスマン帝国の大軍に包囲されていた。
第二次ウィーン包囲である。
戦況厳しいウィーンからは皇帝も逃げ出し、市壁の中には守備隊の兵士と市民軍、避難できなかった市民ら一万人弱が立て籠もった。
彼らをまとめ、指揮するウィーン防衛司令官、その名をシュターレンベルクという。
敵の数は三十万。
戦況は絶望的に想えるものの、シュターレンベルクには策があった。
ドナウ河の水運に恵まれたウィーンは、ドナウ艦隊を蔵している。
内陸に位置するオーストリア唯一の海軍だ。
彼らをウィーンの切り札とするのだ。
戦闘には参加させず、外界との唯一の道として、連絡も補給も彼等に依る。
そのうち、ウィーンには厳しい冬が訪れる。
オスマン帝国軍は野営には耐えられまい。
そんなシュターレンベルクの元に届いた報は『ドナウ艦隊の全滅』であった。
もはや、市壁の中にこもって救援を待つしかないウィーンだが、敵軍のシャーヒー砲は、連日、市に降り注いだ。
戦闘、策略、裏切り、絶望──。
シュターレンベルクはウィーンを守り抜けるのか。
第二次ウィーン包囲の二か月間を描いた歴史小説です。

居候同心
紫紺
歴史・時代
臨時廻り同心風見壮真は実家の離れで訳あって居候中。
本日も頭の上がらない、母屋の主、筆頭与力である父親から呼び出された。
実は腕も立ち有能な同心である壮真は、通常の臨時とは違い、重要な案件を上からの密命で動く任務に就いている。
この日もまた、父親からもたらされた案件に、情報屋兼相棒の翔一郎と解決に乗り出した。
※完結しました。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

画仙紙に揺れる影ー幕末因幡に青梅の残香
冬樹 まさ
歴史・時代
米村誠三郎は鳥取藩お抱え絵師、小畑稲升の弟子である。
文久三年(一八六三年)八月に京で起きて鳥取の地に激震が走った本圀寺事件の後、御用絵師を目指す誠三郎は画技が伸び悩んだままで心を乱していた。大事件を起こした尊攘派の一人で、藩屈指の剣士である詫間樊六は竹馬の友であった。
幕末の鳥取藩政下、水戸出身の藩主の下で若手尊皇派が庇護される形となっていた。また鳥取では、家筋を限定せず実力のある優れた画工が御用絵師として藩に召しだされる伝統があった。
ーーその因幡の地で激動する時勢のうねりに翻弄されながら、歩むべき新たな道を模索して生きる侍たちの魂の交流を描いた幕末時代小説!
作中に出てくる因幡二十士事件周辺の出来事、鳥取藩御用絵師については史実に基づいています。
1人でも多くの読者に、幕末の鳥取藩有志たちの躍動を体感していただきたいです。

古色蒼然たる日々
minohigo-
歴史・時代
戦国時代の九州。舞台装置へ堕した肥後とそれを支配する豊後に属する人々の矜持について、諸将は過去と未来のために対話を繰り返す。肥後が独立を失い始めた永正元年(西暦1504年)から、破滅に至る天正十六年(西暦1588年)までを散文的に取り扱う。

三国志 群像譚 ~瞳の奥の天地~ 家族愛の三国志大河
墨笑
歴史・時代
『家族愛と人の心』『個性と社会性』をテーマにした三国志の大河小説です。
三国志を知らない方も楽しんでいただけるよう意識して書きました。
全体の文量はかなり多いのですが、半分以上は様々な人物を中心にした短編・中編の集まりです。
本編がちょっと長いので、お試しで読まれる方は後ろの方の短編・中編から読んでいただいても良いと思います。
おすすめは『小覇王の暗殺者(ep.216)』『呂布の娘の嫁入り噺(ep.239)』『段煨(ep.285)』あたりです。
本編では蜀において諸葛亮孔明に次ぐ官職を務めた許靖という人物を取り上げています。
戦乱に翻弄され、中国各地を放浪する波乱万丈の人生を送りました。
歴史ものとはいえ軽めに書いていますので、歴史が苦手、三国志を知らないという方でもぜひお気軽にお読みください。
※人名が分かりづらくなるのを避けるため、アザナは一切使わないことにしました。ご了承ください。
※切りのいい時には完結設定になっていますが、三国志小説の執筆は私のライフワークです。生きている限り話を追加し続けていくつもりですので、ブックマークしておいていただけると幸いです。
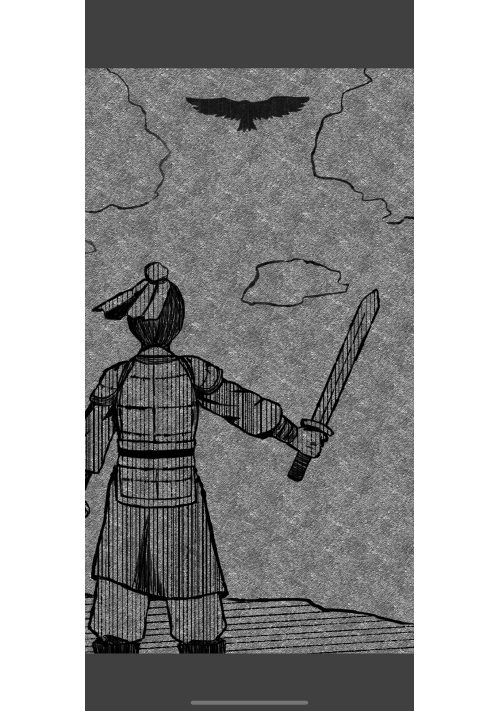
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

鎮魂の絵師
霞花怜
キャラ文芸
絵師・栄松斎長喜は、蔦屋重三郎が営む耕書堂に居住する絵師だ。ある春の日に、斎藤十郎兵衛と名乗る男が連れてきた「喜乃」という名の少女とで出会う。五歳の娘とは思えぬ美貌を持ちながら、周囲の人間に異常な敵愾心を抱く喜乃に興味を引かれる。耕書堂に居住で丁稚を始めた喜乃に懐かれ、共に過ごすようになる。長喜の真似をして絵を描き始めた喜乃に、自分の師匠である鳥山石燕を紹介する長喜。石燕の暮らす吾柳庵には、二人の妖怪が居住し、石燕の世話をしていた。妖怪とも仲良くなり、石燕の指導の下、絵の才覚を現していく喜乃。「絵師にはしてやれねぇ」という蔦重の真意がわからぬまま、喜乃を見守り続ける。ある日、喜乃にずっとついて回る黒い影に気が付いて、嫌な予感を覚える長喜。どう考えても訳ありな身の上である喜乃を気に掛ける長喜に「深入りするな」と忠言する京伝。様々な人々に囲まれながらも、どこか独りぼっちな喜乃を長喜は放っておけなかった。娘を育てるような気持で喜乃に接する長喜だが、師匠の石燕もまた、孫に接するように喜乃に接する。そんなある日、石燕から「俺の似絵を描いてくれ」と頼まれる。長喜が書いた似絵は、魂を冥府に誘う道標になる。それを知る石燕からの依頼であった。
【カクヨム・小説家になろう・アルファポリスに同作品掲載中】
※各話の最後に小噺を載せているのはアルファポリスさんだけです。(カクヨムは第1章だけ載ってますが需要ないのでやめました)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















