お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


月とガーネット[下]
雨音 礼韻
SF
西暦2093年、東京──。
その70年前にオーストラリア全域を壊滅させる巨大隕石が落下、地球内部のスピネル層が化学変化を起こし、厖大な特殊鉱脈が発見された。
人類は採取した鉱石をシールド状に改良し、上空を全て覆い尽くす。
隕石衝突で乱れた気流は『ムーン・シールド』によって安定し、世界は急速に発展を遂げた。
一方何もかもが上手くいかず、クサクサとしながらふらつく繁華街で、小学生時代のクラスメイトと偶然再会したクウヤ。
「今夜は懐が温かいんだ」と誘われたナイトクラブで豪遊する中、隣の美女から贈られるブラッディ・メアリー。
飲んだ途端激しい衝撃にのたうちまわり、クウヤは彼女のウィスキーに手を出してしまう。
その透明な液体に纏われていた物とは・・・?
舞台は東京からアジア、そしてヨーロッパへ。
突如事件に巻き込まれ、不本意ながらも美女に連れ去られるクウヤと共に、ハードな空の旅をお楽しみください☆彡
◆キャラクターのイメージ画がある各話には、サブタイトルにキャラのイニシャルが入った〈 〉がございます。
◆サブタイトルに「*」のある回には、イメージ画像がございます。
ただ飽くまでも作者自身の生きる「現代」の画像を利用しておりますので、70年後である本作では多少変わっているかと思われますf^_^;<
何卒ご了承くださいませ <(_ _)>
[上巻]を未読でお越しくださいました貴重な皆様♡
大変お手数ですが完結済の『月とガーネット』[上]を是非お目通しくださいませ(^人^)
第2~4話まで多少説明の多い回が続きますが、解説文は話半分くらいのご理解で十分ですのでご安心くださいm(_ _)m
関連のある展開に入りましたら、その都度説明させていただきます(=゚ω゚)ノ
クウヤと冷血顔面w美女のドタバタな空の旅に、是非ともお付き合いを☆
(^人^)どうぞ宜しくお願い申し上げます(^人^)


ハッチョーボリ・シュレディンガーズ
近畿ブロードウェイ
SF
なぜか就寝中、布団の中にさまざまな昆虫が潜り込んでくる友人の話を聞き、
悪ふざけ100%で、お酒を飲みながらふわふわと話を膨らませていった結果。
「布団の上のセミの死骸×シュレディンガー方程式×何か地獄みたいになってる国」
という作品が書きたくなったので、話が思いついたときに更新していきます。
小説家になろう で書いている話ですが、
せっかく アルファポリス のアカウントも作ったのでこっちでも更新します。
https://ncode.syosetu.com/n5143io/
・この物語はフィクションです。
作中の人物・団体などの名称は全て架空のものであり、
特定の事件・事象とも一切関係はありません
・特定の作品を馬鹿にするような意図もありません

長く短い真夏の殺意
神原オホカミ【書籍発売中】
SF
人間を襲わないはずのロボットによる殺人事件。その犯行の動機と真実――
とある真夏の昼下がり、惨殺された男性の死体が見つかった。
犯人は、人間を襲わないはずの執事型ロボット。
その犯行の動機と真実とは……?
◆表紙画像は簡単表紙メーカー様で作成しています。
◆無断転写や内容の模倣はご遠慮ください。
◆文章をAI学習に使うことは絶対にしないでください。
◆アルファポリスさん/エブリスタさん/カクヨムさん/なろうさんで掲載してます。
〇構想執筆:2020年、改稿投稿:2024年

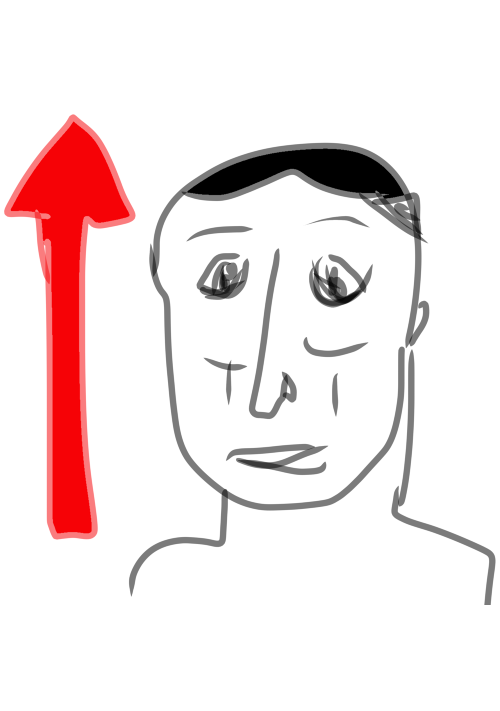
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















