37 / 38
3章 交錯
3-7.別れ
しおりを挟む
クロエは目の前のベッドで眠るアメリアを見つめた。
それからのことは、あまりはっきりと覚えていない。
アメリアは意識を失い、チャールズが部屋へ運んだ。
「クロエ、アメリアの様子は――」
身体を拭き、部屋を出ると外で待っていたチャールズが不安げな声をかけた。
クロエは首を振る。
「奥様はまだお目覚めになりません。ただ、顔色は良いですし――眠ってらっしゃる以外は特に異常はありません」
数日経つが彼女は目を覚まさない。
「そうか……、ありがとう、」
「いいえ、奥様のお世話をするのが私の仕事ですから」
頭を下げ、部屋を去る。
屋敷の仕事はいつも通りに山ほどある。
***
夜、クロエは自室のベッドに腰掛けて窓を開けた。
そこからはルークのいる別棟の壁が見える。
あれから――、食事を持っていき世話をすることはあっても、彼とは会話を交わしていなかった。何を話せばいいのかわからなかった。
(どうして)
クロエの心の中にあるのは虚しさだけだった。結局、何も得られなかった。あの柔らかくて温かい腕で抱きしめられて、そこに顔を埋めて、また髪を撫でてもらいたかっただけなのに。
(どうして、私ばかり、こんな気持ちにならないといけないの)
ずきりと、背中の傷跡が疼いた。
(どうして、)
幼いころに母が読んでくれた絵本を開いた。
王子様に出会って、幸せになれるとそう思っていた。だけど、現実は辛かった。やっと得たと思った自分の居場所からも追い出されてしまった。
***
――アメリアが屋敷から姿を消してしばらくした頃――
クロエはふと思い立って館の裏の森に入った。そして、昔水遊びをした池のところへで、彼女のいつもつけているピンク色のリボンが落ちているのを見つけた。辺りを見回すと、夜香花の小さなピンクの花が微かに揺れていることに気付いた。
その瞬間、脳裏に色々な光景が浮かんだ。
その花の押し花に、『いい香りね』と鼻を近づけるアメリア。
その花を無心に摘んでいた狼。
自分を助けた理由を聞いたときに、番の匂いがしたからと彼が答えたこと。
マクシムに着るように言われたアメリアの服。憧れた、上質な生地のドレス。
――『森に呼ばれる』
辺境に接するこの土地で稀に起こるというその現象を思い出した。
「……」
不意に姿を消した彼女の居場所がわかった気がした。
屋敷の裏の森に向かうと、昔遊んだ水辺に行く。
ルークの居場所も里の場所もわからない。――でも、自分はあそこには行くことができる。
周囲を深い森林に囲まれた高台の岩場。その場所を強く思う。風がないのに、草が揺れた気がした。そちらへ足を踏み出す。――景色が変わった。辺りを確認するように見回し、草苺の生えるなだらかな上り坂を登って行くと、景色が開けた。
(――着いた)
岩場には誰もいなかった。クロエは周りを見回す。そしてそこに落ちた銀色の毛に気付いた。
(――そう、ここに来たのね)
それを指で拾って、クロエは顔をしかめた。
幼いころ遊んだあの池のほとりを思い、また森を抜ける。そして、元いた場所に戻っていた。
「チャールズ様、お話があります」
クロエは彼に告げた。
――お姉さまは、森の中にいます、きっと。
半信半疑の彼を連れ、同じように岩場に行った。
「こんなことが……!?」
チャールズは信じられないと頭を抱えた。
「私は、ずっと野人の里にいました。チャールズ様はお聞きになったことがないかもしれませんね。辺境のあたりでは、昔から稀に、年頃の娘が『森に呼ばれて』姿を消すということがあります。お姉さまもきっと」
「――それで、消えた女性はどうなるんだ?」
「彼らは、野人の番――妻になります」
その言葉をチャールズが理解するまでに、しばらくの沈黙が流れた。彼は拳を握ると、噛み締めるように言った。
「妻? 野人の? 獣の? アメリアが?」
それからクロエを見つめる。
「君はなんで、戻って来たんだ?」
「――私は、ただ怪我をしていたところを助けられただけでしたから。彼らは、外からの人間は、番しか受け入れません」
「彼女の場所がわかるか?」
「ええ。――たぶん、ここにそのうちやって来る狼が――知っていると思います」
クロエは目線を落として、呟いた。
そして、夕日の沈むころルークはやってきた。
1人で藪を抜け現れると、丘に立って茜色に染まる森の海を見つめていた。
かつて、二人で見ていた風景を。
クロエは拳を握った。予想のとおり、もしアメリアが彼の『番』だったら――、
胸の中にどす黒い感情が渦巻くのを感じた。
草を揺らし、外に出る。突然の物音に気がついたルークは振り返り、そこにいたクロエと見知らぬ男の姿に驚いて瞳を大きく広げた。
「クロエ――っ!? なんでここに」
「森をね、抜けられたの、久しぶりね」
クロエは笑顔を作ろうとして、口元が引きつるのを感じた。
「アメリア、という女性を知っている?」
びくりと身体を震わせた狼の反応で、クロエは自分の予想が合っていることを感じた。
「――この方は、チャールズ様、アメリア――お姉さまの婚約者よ」
「お姉さま……っ?」
クロエの言葉に、ルークは身体を震わせた。
「野人、アメリアのことを知っているのか?」
チャールズは剣を抜き、構える。
クロエの中にどろどろとした感情が溢れる。
それは自然と、涙声を作った。
クロエはルークに近づくと耳打ちした。
「逆らわないで、ルーク――剣には、貴方の教えてくれた、貴方達によく効く毒を塗ってあるわ」
びくりとルークの身体が震えた。
「仕方がなかったの、教えろと脅されて……。里を滅ぼしたい? お姉さまを、いったん連れてきて」
彼を見つめて、声を震わす。
「後できちんと、逃がしてあげるから。私を信じて」
……そんなつもりは、もともとなかったけれど。
自分の中からどんどん、粘着質の黒い感情が溢れ出してくることを止められなかった。
***
(どうしてよ)
ベッドの下に手を伸ばして、母が昔読んでくれた絵本を取り出した。
『お姫様は王子様に出会って幸せに暮らしました。』
ただ、それだけの話。
小さいころはそのお姫様に憧れていた。
いつか、きっと、自分も自分の『王子様』に出会えると無邪気に信じていた。
もうその本は埃まみれだ。ページを開く気は起きなかった。
母親がこの本に挟んでいたピンク色の押し花を思い出す。
(あれは――、マクシムがお母様に送ったものだったのかしら?)
ふと、森の奥で死体になって消えたかつての執事長を思い出した。
(いつから、どうして、こうなってしまったの?)
ベッドの下を手でさぐると、冷たい金属に手が触れた。それを掴んで引き出すと、銀のナイフがが暗闇に光った。ルークを刺したナイフだった。
お母さまが死んでから、今までずっと辛かった。
森で、ルークと暮らして、ようやく居場所を見つけた気がしたけれど、それも手に入らなかった。
こんな、醜いどろどろした感情に満たされた女になるつもりはなかった。
物語の中のお姫様のようでいたかったのに。
背中の古傷が傷む。
(――私がこんな気持ちにならなくちゃいけないのは)
――あいつのせいよ。
ヴィクトリアの姿が思い浮かび、クロエはふらふらと立ち上がった。手のひらにナイフを握りしめて。
***
ルークは部屋の中で頭を抱えていた。あれから数日が経つ。
クロエは決まった時間に食事を置いていくと、言葉もなく出て行ってしまう。
一方でアメリアとの番としての繋がりが靴紐をほどくように消えて行くのを感じていた。
(そうか。俺は獣に戻るのか)
体感としてそれを感じた。人の姿をとろうとしても、形が変わらない。
きっと、番の何かを借りて、自分たちは人らしさを手に入れているのだという――何となく感じていたその感覚は合っていたのだと思った。
ぐっと腕に力を握る。痺れ草による手足の痺れはほぼなくなっていた。
(今なら)
力を入れたまま鎖を引っ張る。その先にある、鎖を巻き取った滑車がカタカタと揺れた。
さらに引っ張ると、がたり、と音がして、それは石の壁から外れた。
(森に帰ろう)
ルークは唸った。自分が生きるべき場所はそこしかない。
その時、ふと背中の毛に逆立つような寒気を感じた。
(……クロエ?)
嫌な予感を感じて、ルークは屋敷の方へ駆けた。
***
ふらふらとクロエは暗い屋敷を進む。
全てを断ち切りたいと思った。
ヴィクトリアの眠る寝室の扉を開ける。
ギィィィと軋んだ扉の音が響いた。
それでも、――自分が知らない間に、母をどこかに葬り、消えない傷を背中に負わせた女は規則正しい寝息を立てていた。
――お母さまが、生きていれば。
お姉さまと同じように、笑って、幸せに暮らしていたかもしれないのに。
――痛みのない場所を探して、マクシムさんに縋りつかなければ。
森に行くことはなく、ルークに会わなくて良かったかもしれないのに。
銀のナイフを握り、振り上げる。
――その瞬間。目の前に銀色の狼が飛び出した。ナイフはその毛皮にぶすりと埋まった。
「――っ、ルーク!?」
驚いたクロエは、どさりと床に腰をついて、銀の毛並みを血で濡らした人狼を見つめた。
「君が、そんなことをする必要はない」
ルークは呟くと、腕からナイフを抜いて、クロエの横に投げ捨てた。
「なんで」そう言おうとしたクロエの視線の先で、物音に気がついたヴィクトリアがむくりと起き上がった。
「……っ」
彼女は、目の前に立つ大きな獣の姿に気付き、大きく息を吸い込んで叫んだ。
「きゃああああああ」
「これが――『奥様』?」
『奥様の気が済まなかったから、叩かれただけよ』
いつかクロエの言っていた言葉を思い出した。
彼女はきっと、森の外で、もといた屋敷という場所で、辛い目に合っていたのだと気づいていた。だから、あの時、別れる時に言ったのに。
『クロエ、そこは出て――、どこか、別の場所で、』
幸せに、暮らして欲しい、そう伝えようと思った。
だけど、彼女はそれを遮った。
『私は、ヘクセン辺境伯の屋敷にいるわ。貴方を待ってる』
(――ここは、彼女の居場所じゃない)
それを、そこへ縛りつけたのは自分だ。
逃げようとするヴィクトリアの腕を掴み、その背中に爪を突き立てる。
寝具が破け、赤い血が滲む。
ぎゃああああああという、悲鳴が暗い室内に響いた。
クロエはのたうちまわる女主人を見つめて、呟いた。
「や……、やめて」
いったん下まで引っ張った手を再度持ち上げて、また上から突き立てようとしたルークの手を、つかむ。ルークはヴィクトリアから手を離すと、クロエの背中に手を回して言った。
「いいんだ、君がそんなことをしなくて」
「なんで、貴方がそんなことを言うのよ」
クロエは体を震わせた。ヴィクトリアの悲鳴を聞きつけたのか、外から足音が聞こえる。
ルークはクロエを抱えたまま、窓から外へ飛び出した。
そのまま裏庭に着地すると、クロエを屋敷の方へ降ろした。
それから、呟いた。
「――俺からも、ここからも離れて、笑っていて欲しい」
「なんで、そんなことを言うのよ。私のことなんか、どうとも思っていないくせに。愛してないくせに」
森の住人は、番以外の、家族以外に対する気持ちを表す言葉を知らない。
クロエに対して思っている感情はただ、
「――愛してはいないけど、君には笑っていてほしいと思ってる」
ルークはクロエに近づくと、背中を撫でた。
「いいんだ。――自由になって、幸せになっても」
2階のヴィクトリアの寝室からランプの灯りが突き出された。ルークは、クロエを暗闇の方へ押し出すと、灯りに向かって吠えた。
「いたぞ」「この前の人狼だ!」
騒々しい声が頭上から降り注ぐ。ルークはクロエを一瞥すると、そのまま裏の森の方へと駆け出した。
それからのことは、あまりはっきりと覚えていない。
アメリアは意識を失い、チャールズが部屋へ運んだ。
「クロエ、アメリアの様子は――」
身体を拭き、部屋を出ると外で待っていたチャールズが不安げな声をかけた。
クロエは首を振る。
「奥様はまだお目覚めになりません。ただ、顔色は良いですし――眠ってらっしゃる以外は特に異常はありません」
数日経つが彼女は目を覚まさない。
「そうか……、ありがとう、」
「いいえ、奥様のお世話をするのが私の仕事ですから」
頭を下げ、部屋を去る。
屋敷の仕事はいつも通りに山ほどある。
***
夜、クロエは自室のベッドに腰掛けて窓を開けた。
そこからはルークのいる別棟の壁が見える。
あれから――、食事を持っていき世話をすることはあっても、彼とは会話を交わしていなかった。何を話せばいいのかわからなかった。
(どうして)
クロエの心の中にあるのは虚しさだけだった。結局、何も得られなかった。あの柔らかくて温かい腕で抱きしめられて、そこに顔を埋めて、また髪を撫でてもらいたかっただけなのに。
(どうして、私ばかり、こんな気持ちにならないといけないの)
ずきりと、背中の傷跡が疼いた。
(どうして、)
幼いころに母が読んでくれた絵本を開いた。
王子様に出会って、幸せになれるとそう思っていた。だけど、現実は辛かった。やっと得たと思った自分の居場所からも追い出されてしまった。
***
――アメリアが屋敷から姿を消してしばらくした頃――
クロエはふと思い立って館の裏の森に入った。そして、昔水遊びをした池のところへで、彼女のいつもつけているピンク色のリボンが落ちているのを見つけた。辺りを見回すと、夜香花の小さなピンクの花が微かに揺れていることに気付いた。
その瞬間、脳裏に色々な光景が浮かんだ。
その花の押し花に、『いい香りね』と鼻を近づけるアメリア。
その花を無心に摘んでいた狼。
自分を助けた理由を聞いたときに、番の匂いがしたからと彼が答えたこと。
マクシムに着るように言われたアメリアの服。憧れた、上質な生地のドレス。
――『森に呼ばれる』
辺境に接するこの土地で稀に起こるというその現象を思い出した。
「……」
不意に姿を消した彼女の居場所がわかった気がした。
屋敷の裏の森に向かうと、昔遊んだ水辺に行く。
ルークの居場所も里の場所もわからない。――でも、自分はあそこには行くことができる。
周囲を深い森林に囲まれた高台の岩場。その場所を強く思う。風がないのに、草が揺れた気がした。そちらへ足を踏み出す。――景色が変わった。辺りを確認するように見回し、草苺の生えるなだらかな上り坂を登って行くと、景色が開けた。
(――着いた)
岩場には誰もいなかった。クロエは周りを見回す。そしてそこに落ちた銀色の毛に気付いた。
(――そう、ここに来たのね)
それを指で拾って、クロエは顔をしかめた。
幼いころ遊んだあの池のほとりを思い、また森を抜ける。そして、元いた場所に戻っていた。
「チャールズ様、お話があります」
クロエは彼に告げた。
――お姉さまは、森の中にいます、きっと。
半信半疑の彼を連れ、同じように岩場に行った。
「こんなことが……!?」
チャールズは信じられないと頭を抱えた。
「私は、ずっと野人の里にいました。チャールズ様はお聞きになったことがないかもしれませんね。辺境のあたりでは、昔から稀に、年頃の娘が『森に呼ばれて』姿を消すということがあります。お姉さまもきっと」
「――それで、消えた女性はどうなるんだ?」
「彼らは、野人の番――妻になります」
その言葉をチャールズが理解するまでに、しばらくの沈黙が流れた。彼は拳を握ると、噛み締めるように言った。
「妻? 野人の? 獣の? アメリアが?」
それからクロエを見つめる。
「君はなんで、戻って来たんだ?」
「――私は、ただ怪我をしていたところを助けられただけでしたから。彼らは、外からの人間は、番しか受け入れません」
「彼女の場所がわかるか?」
「ええ。――たぶん、ここにそのうちやって来る狼が――知っていると思います」
クロエは目線を落として、呟いた。
そして、夕日の沈むころルークはやってきた。
1人で藪を抜け現れると、丘に立って茜色に染まる森の海を見つめていた。
かつて、二人で見ていた風景を。
クロエは拳を握った。予想のとおり、もしアメリアが彼の『番』だったら――、
胸の中にどす黒い感情が渦巻くのを感じた。
草を揺らし、外に出る。突然の物音に気がついたルークは振り返り、そこにいたクロエと見知らぬ男の姿に驚いて瞳を大きく広げた。
「クロエ――っ!? なんでここに」
「森をね、抜けられたの、久しぶりね」
クロエは笑顔を作ろうとして、口元が引きつるのを感じた。
「アメリア、という女性を知っている?」
びくりと身体を震わせた狼の反応で、クロエは自分の予想が合っていることを感じた。
「――この方は、チャールズ様、アメリア――お姉さまの婚約者よ」
「お姉さま……っ?」
クロエの言葉に、ルークは身体を震わせた。
「野人、アメリアのことを知っているのか?」
チャールズは剣を抜き、構える。
クロエの中にどろどろとした感情が溢れる。
それは自然と、涙声を作った。
クロエはルークに近づくと耳打ちした。
「逆らわないで、ルーク――剣には、貴方の教えてくれた、貴方達によく効く毒を塗ってあるわ」
びくりとルークの身体が震えた。
「仕方がなかったの、教えろと脅されて……。里を滅ぼしたい? お姉さまを、いったん連れてきて」
彼を見つめて、声を震わす。
「後できちんと、逃がしてあげるから。私を信じて」
……そんなつもりは、もともとなかったけれど。
自分の中からどんどん、粘着質の黒い感情が溢れ出してくることを止められなかった。
***
(どうしてよ)
ベッドの下に手を伸ばして、母が昔読んでくれた絵本を取り出した。
『お姫様は王子様に出会って幸せに暮らしました。』
ただ、それだけの話。
小さいころはそのお姫様に憧れていた。
いつか、きっと、自分も自分の『王子様』に出会えると無邪気に信じていた。
もうその本は埃まみれだ。ページを開く気は起きなかった。
母親がこの本に挟んでいたピンク色の押し花を思い出す。
(あれは――、マクシムがお母様に送ったものだったのかしら?)
ふと、森の奥で死体になって消えたかつての執事長を思い出した。
(いつから、どうして、こうなってしまったの?)
ベッドの下を手でさぐると、冷たい金属に手が触れた。それを掴んで引き出すと、銀のナイフがが暗闇に光った。ルークを刺したナイフだった。
お母さまが死んでから、今までずっと辛かった。
森で、ルークと暮らして、ようやく居場所を見つけた気がしたけれど、それも手に入らなかった。
こんな、醜いどろどろした感情に満たされた女になるつもりはなかった。
物語の中のお姫様のようでいたかったのに。
背中の古傷が傷む。
(――私がこんな気持ちにならなくちゃいけないのは)
――あいつのせいよ。
ヴィクトリアの姿が思い浮かび、クロエはふらふらと立ち上がった。手のひらにナイフを握りしめて。
***
ルークは部屋の中で頭を抱えていた。あれから数日が経つ。
クロエは決まった時間に食事を置いていくと、言葉もなく出て行ってしまう。
一方でアメリアとの番としての繋がりが靴紐をほどくように消えて行くのを感じていた。
(そうか。俺は獣に戻るのか)
体感としてそれを感じた。人の姿をとろうとしても、形が変わらない。
きっと、番の何かを借りて、自分たちは人らしさを手に入れているのだという――何となく感じていたその感覚は合っていたのだと思った。
ぐっと腕に力を握る。痺れ草による手足の痺れはほぼなくなっていた。
(今なら)
力を入れたまま鎖を引っ張る。その先にある、鎖を巻き取った滑車がカタカタと揺れた。
さらに引っ張ると、がたり、と音がして、それは石の壁から外れた。
(森に帰ろう)
ルークは唸った。自分が生きるべき場所はそこしかない。
その時、ふと背中の毛に逆立つような寒気を感じた。
(……クロエ?)
嫌な予感を感じて、ルークは屋敷の方へ駆けた。
***
ふらふらとクロエは暗い屋敷を進む。
全てを断ち切りたいと思った。
ヴィクトリアの眠る寝室の扉を開ける。
ギィィィと軋んだ扉の音が響いた。
それでも、――自分が知らない間に、母をどこかに葬り、消えない傷を背中に負わせた女は規則正しい寝息を立てていた。
――お母さまが、生きていれば。
お姉さまと同じように、笑って、幸せに暮らしていたかもしれないのに。
――痛みのない場所を探して、マクシムさんに縋りつかなければ。
森に行くことはなく、ルークに会わなくて良かったかもしれないのに。
銀のナイフを握り、振り上げる。
――その瞬間。目の前に銀色の狼が飛び出した。ナイフはその毛皮にぶすりと埋まった。
「――っ、ルーク!?」
驚いたクロエは、どさりと床に腰をついて、銀の毛並みを血で濡らした人狼を見つめた。
「君が、そんなことをする必要はない」
ルークは呟くと、腕からナイフを抜いて、クロエの横に投げ捨てた。
「なんで」そう言おうとしたクロエの視線の先で、物音に気がついたヴィクトリアがむくりと起き上がった。
「……っ」
彼女は、目の前に立つ大きな獣の姿に気付き、大きく息を吸い込んで叫んだ。
「きゃああああああ」
「これが――『奥様』?」
『奥様の気が済まなかったから、叩かれただけよ』
いつかクロエの言っていた言葉を思い出した。
彼女はきっと、森の外で、もといた屋敷という場所で、辛い目に合っていたのだと気づいていた。だから、あの時、別れる時に言ったのに。
『クロエ、そこは出て――、どこか、別の場所で、』
幸せに、暮らして欲しい、そう伝えようと思った。
だけど、彼女はそれを遮った。
『私は、ヘクセン辺境伯の屋敷にいるわ。貴方を待ってる』
(――ここは、彼女の居場所じゃない)
それを、そこへ縛りつけたのは自分だ。
逃げようとするヴィクトリアの腕を掴み、その背中に爪を突き立てる。
寝具が破け、赤い血が滲む。
ぎゃああああああという、悲鳴が暗い室内に響いた。
クロエはのたうちまわる女主人を見つめて、呟いた。
「や……、やめて」
いったん下まで引っ張った手を再度持ち上げて、また上から突き立てようとしたルークの手を、つかむ。ルークはヴィクトリアから手を離すと、クロエの背中に手を回して言った。
「いいんだ、君がそんなことをしなくて」
「なんで、貴方がそんなことを言うのよ」
クロエは体を震わせた。ヴィクトリアの悲鳴を聞きつけたのか、外から足音が聞こえる。
ルークはクロエを抱えたまま、窓から外へ飛び出した。
そのまま裏庭に着地すると、クロエを屋敷の方へ降ろした。
それから、呟いた。
「――俺からも、ここからも離れて、笑っていて欲しい」
「なんで、そんなことを言うのよ。私のことなんか、どうとも思っていないくせに。愛してないくせに」
森の住人は、番以外の、家族以外に対する気持ちを表す言葉を知らない。
クロエに対して思っている感情はただ、
「――愛してはいないけど、君には笑っていてほしいと思ってる」
ルークはクロエに近づくと、背中を撫でた。
「いいんだ。――自由になって、幸せになっても」
2階のヴィクトリアの寝室からランプの灯りが突き出された。ルークは、クロエを暗闇の方へ押し出すと、灯りに向かって吠えた。
「いたぞ」「この前の人狼だ!」
騒々しい声が頭上から降り注ぐ。ルークはクロエを一瞥すると、そのまま裏の森の方へと駆け出した。
1
お気に入りに追加
249
あなたにおすすめの小説


婚約破棄したら食べられました(物理)
かぜかおる
恋愛
人族のリサは竜種のアレンに出会った時からいい匂いがするから食べたいと言われ続けている。
婚約者もいるから無理と言い続けるも、アレンもしつこく食べたいと言ってくる。
そんな日々が日常と化していたある日
リサは婚約者から婚約破棄を突きつけられる
グロは無し
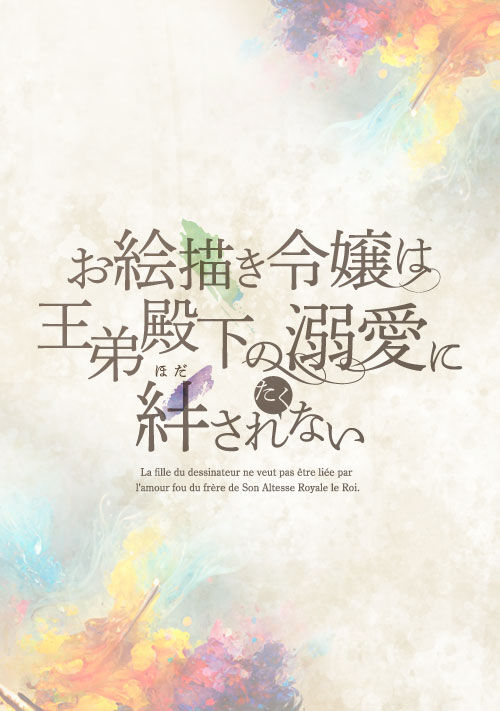
【完結】お絵描き令嬢は王弟殿下の溺愛に絆されたくない
オトカヨル
恋愛
絵を描くのが大好きな田舎の令嬢ネリー・ラヴィルニーはある日、王家主催の舞踏会へ招待される。
その舞踏会は次期王を決めるための試練の場だというのだが、父は彼女を送り出すのに心配で胃が痛い。
なにせ、王族を神官以外が描けば呪いをかけたと疑われても仕方ない国だと言うのに、ネリーは『描きたい』という衝動のまま行動しかねないからだ。
そしてその心配は現実に。
「こういうやり方は好きではないんだが」と、王族を描いてしまった絵を盾にされ
「描かせてくださるのですか? いくらでも?」と、報酬に釣られ、ネリーは王弟イアンと試練に挑むことになる。
※他サイト様にも掲載しております。

大好きなあなたを忘れる方法
山田ランチ
恋愛
あらすじ
王子と婚約関係にある侯爵令嬢のメリベルは、訳あってずっと秘密の婚約者のままにされていた。学園へ入学してすぐ、メリベルの魔廻が(魔術を使う為の魔素を貯めておく器官)が限界を向かえようとしている事に気が付いた大魔術師は、魔廻を小さくする事を提案する。その方法は、魔素が好むという悲しい記憶を失くしていくものだった。悲しい記憶を引っ張り出しては消していくという日々を過ごすうち、徐々に王子との記憶を失くしていくメリベル。そんな中、魔廻を奪う謎の者達に大魔術師とメリベルが襲われてしまう。
魔廻を奪おうとする者達は何者なのか。王子との婚約が隠されている訳と、重大な秘密を抱える大魔術師の正体が、メリベルの記憶に導かれ、やがて世界の始まりへと繋がっていく。
登場人物
・メリベル・アークトュラス 17歳、アークトゥラス侯爵の一人娘。ジャスパーの婚約者。
・ジャスパー・オリオン 17歳、第一王子。メリベルの婚約者。
・イーライ 学園の園芸員。
クレイシー・クレリック 17歳、クレリック侯爵の一人娘。
・リーヴァイ・ブルーマー 18歳、ブルーマー子爵家の嫡男でジャスパーの側近。
・アイザック・スチュアート 17歳、スチュアート侯爵の嫡男でジャスパーの側近。
・ノア・ワード 18歳、ワード騎士団長の息子でジャスパーの従騎士。
・シア・ガイザー 17歳、ガイザー男爵の娘でメリベルの友人。
・マイロ 17歳、メリベルの友人。
魔素→世界に漂っている物質。触れれば精神を侵され、生き物は主に凶暴化し魔獣となる。
魔廻→体内にある魔廻(まかい)と呼ばれる器官、魔素を取り込み貯める事が出来る。魔術師はこの器官がある事が必須。
ソル神とルナ神→太陽と月の男女神が魔素で満ちた混沌の大地に現れ、世界を二つに分けて浄化した。ソル神は昼間を、ルナ神は夜を受け持った。

星織りの歌【完結】
しょこら
恋愛
四枚羽根の少女フィリアは幼なじみの少年ランディスと約束をした。「わたし、絶対に星織姫になる!」「じゃあ、僕は近衛になってフィリアを護る」有翼の人々が住む青く美しいエレミアの星には、通常なら二枚の羽根を持って生まれてくるが、まれに四枚の羽根を持って生まれてくる少女たちがいた。彼女たちは星を護る女神となるべく修行し、星杖の選定を受けて女神「星織姫」となる。歌の力で星のバランスを保ち、安定させるのだ。フィリアはランディスの守護の元、もう一人の候補であるクレアとともに星織姫を目指す。だが《セラフィム》を名乗る刺客たちに襲われる中、星織姫を目指す候補の末路を聞かされ、衝撃を受ける。
星織姫を諦めたくない!でもランディスも失いたくない。大きく揺れながら、フィリアは決断していく。

結婚式をボイコットした王女
椿森
恋愛
請われて隣国の王太子の元に嫁ぐこととなった、王女のナルシア。
しかし、婚姻の儀の直前に王太子が不貞とも言える行動をしたためにボイコットすることにした。もちろん、婚約は解消させていただきます。
※初投稿のため生暖か目で見てくださると幸いです※
1/9:一応、本編完結です。今後、このお話に至るまでを書いていこうと思います。
1/17:王太子の名前を修正しました!申し訳ございませんでした···( ´ཫ`)

身代わりーダイヤモンドのように
Rj
恋愛
恋人のライアンには想い人がいる。その想い人に似ているから私を恋人にした。身代わりは本物にはなれない。
恋人のミッシェルが身代わりではいられないと自分のもとを去っていった。彼女の心に好きという言葉がとどかない。
お互い好きあっていたが破れた恋の話。
一話完結でしたが二話を加え全三話になりました。(6/24変更)

引きこもり少女、御子になる~お世話係は過保護な王子様~
浅海 景
恋愛
オッドアイで生まれた透花は家族から厄介者扱いをされて引きこもりの生活を送っていた。ある日、双子の姉に突き飛ばされて頭を強打するが、目を覚ましたのは見覚えのない場所だった。ハウゼンヒルト神聖国の王子であるフィルから、世界を救う御子(みこ)だと告げられた透花は自分には無理だと否定するが、御子であるかどうかを判断するために教育を受けることに。
御子至上主義なフィルは透花を大切にしてくれるが、自分が御子だと信じていない透花はフィルの優しさは一時的なものだと自分に言い聞かせる。
「きっといつかはこの人もまた自分に嫌悪し離れていくのだから」
自己肯定感ゼロの少女が過保護な王子や人との関わりによって、徐々に自分を取り戻す物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















