21 / 38
2章 森の中の生活
2-6.きっかけ(2)
しおりを挟む
家を出たルークは道をしばらく下ったところにある家に立ち寄った。家の外の竈ではパチパチと火が燃えていて、食べ物の匂いが漂って来る。その横では、ルークと同じ灰色の毛の人狼が丸太の椅子に座り火の様子を見ていた。叔父のブルーノだ。
10歳年上のこの叔父は、ルークにとっては兄のような存在だった。ルークには妹が1人いたが、3年前に違う里に番を見つけて出て行った。残った親族では、この叔父が一番年が近いのもあり、番のいないルークは叔父一家と食卓を共にすることが多かった。
「ルーク! おはよー」
ブルーノの陰からひょっこりと小さな少女が顔を出し、ルークに向かって手を振って駆けてきた。「おはよう」と言って姪を抱き上げると、肩車をする。
「あら、ルーク。朝食がちょうどできるところよ」
赤茶の毛並みの子犬のような息子を背負った、赤毛の女――ブルーノの番のリーシャが窓から顔を出して微笑んだ。ルークは手を上げて彼女に挨拶すると、叔父の横に腰を下ろした。
「聞きたいことがあるんだけど、」
耳を引っ張る姪っ子を肩から降ろし、父親に手渡しながら神妙な顔で彼に聞く。
「リーシャと出会った時はどんな感じだった?」
何だ急に、とブルーノは面食らった顔をした。
「いやさ、番って一目見たらわかるものか?」
ルークと同じ、銀色の毛の狼の姿をしている叔父は、人間の姿に戻ると目を細めた。狼の姿は人間の姿よりはっきりと言葉を発することが難しい。そのため、ルークたちは大事なことを話すときは、人間の姿で話すことが多かった。
「そりゃあ、ざわつくような気持ちで草をかき分けて……そこにリーシャの姿を見つけたときは、周りの全てが輝いて見えるような感じがしたよ。前にも言ったか、血が沸騰するようになって、一瞬頭が真っ白になって何も言葉が出なかった」
「おとーさん、何のはなし?」
いきなり人間の姿に戻った父親にびっくりしたのか、娘は膝から飛び降りて聞いた。
「お母さんと会った時の話だよ」
「お母さんは森の外から来たのよね」
「そうだ」
「あたしの番も外にいるのかなあ」
「どうだろうなあ」
ブルーノは娘の母親譲りの赤毛の頭を撫でながら笑った。
「だけど、何で急にそんなことを聞くんだ」
「いや――、なんでもないよ」
ルークは考えるように俯いた。
(彼女は番?)
叔父が言うような劇的な何かを感じる気配はない。
(でも人によって、感覚は違うものかもしれない)
ルークはクロエの笑顔と、居心地のいい感じがしたことを思い出した。
この里には、番以外の外の人間は立ち入ることはない。もし番でもないのに、連れてきたことがわかればややこしいことになるだろう。
(わからないけど、彼女のことはまだ言わない方が良い)
うん、と頷いて立ち上がる。
「お前もそのうち出会うよ。森の民なら、必ず、どこかに番がいるものだから」
ブルーノは笑うとルークの背中を叩いた。
リーシャがふかした芋と、肉の塊を持ってきた。ブルーノとルークは肉の塊を手で掴むと齧った。ルークは家から持ってきた鍋にスープを注ぐ。
「スープ持って帰ってもいいか?」
「珍しいわね」
リーシャが不思議そうに首を傾げた。ふだんは肉しか食べないからだ。
「たまには、野菜も食べようと思って」
「ここで食べて行けばいいのに」
「ちょっと――家でゆっくり食べようと思って。あとさ、食べ物いくらかもらってってもいいか?」
「遠慮なく持って行って。お肉は貴方が獲ってくれたものだし。干し肉と燻製にしてあるから。野菜は奥に積んであるわ」
「ありがとう、リーシャ」
食料と鍋を小脇に抱え家に戻ると囲炉裏に火をおこした。
「待たせてごめん、食べ物持ってきた。叔父の番のリーシャは、君と同じ森の外の人間だから――、俺が作るより、彼女の作ったものの方が口に合うと思って、もらってきたんだけど」
「つがい」
聞き慣れない言葉をクロエは繰り返す。ああ、とルークは頷いた。外には番というものはなく、夫と妻がそれにあたる、とリーシャが言っていたことを思い出す。
「――妻のこと」
そう、と頷くクロエにルークは碗に注いだスープを差し出した。色鮮やかな野菜と、肉が煮込まれている。狼の手でスプーンがうまく持てずに、手がすべる。
「――人の姿でもいいか」
クロエは仕方なく頷いた。ルークは銀髪の青年の姿に戻ると、すくったスープに息を吹きかけ、冷ましてクロエの口元に運んだ。ずっと温かいそれを吸い込んで、クロエは顔を輝かせた。塩気はほとんどなかったが、肉と野菜の旨味と、何より水が美味しいのか、うっすらとした甘さを感じた。
「美味い?」
ルークはクロエの反応に満足そうに笑うと、ふと肩にかかる栗色の髪に目を留めた。
「結んだ方がいいな」
食べ物に入りそうだと思ったので、手を伸ばすと、指で梳くと左右で緩く三つ編みに編んだ。姪の髪を結んでやることがあるので、動きはスムーズだった。紐で毛先を結び、これで良しと頷いてから、顔を赤らめ俯くクロエに気付く。
「――どうしたんだ。口に合わなかった?」
クロエは顔の目の前の、がっしりした肌色の胸板から目を逸らす。狼の姿だと、コディが二足歩行をしているように思うが、人間の姿になられると、どうしても相手が男性だという意識が湧いてくる。
「上着を、着て。あと、私にも服をください」
ルークは困り顔で自分の上半身を見た。狼の姿で過ごすことが多いので、上着は着ないことのほうが多い。でも、彼女の様子がおかしいのは、それが外の感覚なのだろう。
「わかった。ちょっと待ってろ」
部屋の隅の棚に積まれた荷物から、長袖の上衣を掘り出し被る。もう一枚も掘り出しクロエに着せた。細かい作業のためか、人間の姿のルークに人形のように服を着せられ、クロエは恥ずかしさに俯いた。
(野人っていうから、もっと)
野蛮な存在を想像していた。本宅にいる時は、ほとんど野人の話は聞いたことがなかったが、幼いころ、森に隣接した国境付近の別宅にいた時に聞いた話は、獣の様な姿の怪物は出くわすと襲って来るというものだった。
このルークと名乗った野人の男は、裸の自分に何もする気がなさそうな上、傷を手当した上、食事をあたえ、髪まで結って面倒を見てくる。
(何なのかしら)
「これでいいか」
「いいです」
「何で口調を変えるんだ」
「だって」
スープの匂いが鼻先に漂い、またクロエの腹が鳴った。急に空腹感に襲われる。
「――食べさせて、もらえますか」
おずおずと言うと、ルークは顔をしかめた。森の中では、一族は皆対等で、お互いに丁寧な口調で話すことはない。
「その口調は気持ち悪い」
クロエはう、と唸ってから言い直した。
「――食べさせて」
よし、とルークは笑うとまたスープを口元に運んだ。
10歳年上のこの叔父は、ルークにとっては兄のような存在だった。ルークには妹が1人いたが、3年前に違う里に番を見つけて出て行った。残った親族では、この叔父が一番年が近いのもあり、番のいないルークは叔父一家と食卓を共にすることが多かった。
「ルーク! おはよー」
ブルーノの陰からひょっこりと小さな少女が顔を出し、ルークに向かって手を振って駆けてきた。「おはよう」と言って姪を抱き上げると、肩車をする。
「あら、ルーク。朝食がちょうどできるところよ」
赤茶の毛並みの子犬のような息子を背負った、赤毛の女――ブルーノの番のリーシャが窓から顔を出して微笑んだ。ルークは手を上げて彼女に挨拶すると、叔父の横に腰を下ろした。
「聞きたいことがあるんだけど、」
耳を引っ張る姪っ子を肩から降ろし、父親に手渡しながら神妙な顔で彼に聞く。
「リーシャと出会った時はどんな感じだった?」
何だ急に、とブルーノは面食らった顔をした。
「いやさ、番って一目見たらわかるものか?」
ルークと同じ、銀色の毛の狼の姿をしている叔父は、人間の姿に戻ると目を細めた。狼の姿は人間の姿よりはっきりと言葉を発することが難しい。そのため、ルークたちは大事なことを話すときは、人間の姿で話すことが多かった。
「そりゃあ、ざわつくような気持ちで草をかき分けて……そこにリーシャの姿を見つけたときは、周りの全てが輝いて見えるような感じがしたよ。前にも言ったか、血が沸騰するようになって、一瞬頭が真っ白になって何も言葉が出なかった」
「おとーさん、何のはなし?」
いきなり人間の姿に戻った父親にびっくりしたのか、娘は膝から飛び降りて聞いた。
「お母さんと会った時の話だよ」
「お母さんは森の外から来たのよね」
「そうだ」
「あたしの番も外にいるのかなあ」
「どうだろうなあ」
ブルーノは娘の母親譲りの赤毛の頭を撫でながら笑った。
「だけど、何で急にそんなことを聞くんだ」
「いや――、なんでもないよ」
ルークは考えるように俯いた。
(彼女は番?)
叔父が言うような劇的な何かを感じる気配はない。
(でも人によって、感覚は違うものかもしれない)
ルークはクロエの笑顔と、居心地のいい感じがしたことを思い出した。
この里には、番以外の外の人間は立ち入ることはない。もし番でもないのに、連れてきたことがわかればややこしいことになるだろう。
(わからないけど、彼女のことはまだ言わない方が良い)
うん、と頷いて立ち上がる。
「お前もそのうち出会うよ。森の民なら、必ず、どこかに番がいるものだから」
ブルーノは笑うとルークの背中を叩いた。
リーシャがふかした芋と、肉の塊を持ってきた。ブルーノとルークは肉の塊を手で掴むと齧った。ルークは家から持ってきた鍋にスープを注ぐ。
「スープ持って帰ってもいいか?」
「珍しいわね」
リーシャが不思議そうに首を傾げた。ふだんは肉しか食べないからだ。
「たまには、野菜も食べようと思って」
「ここで食べて行けばいいのに」
「ちょっと――家でゆっくり食べようと思って。あとさ、食べ物いくらかもらってってもいいか?」
「遠慮なく持って行って。お肉は貴方が獲ってくれたものだし。干し肉と燻製にしてあるから。野菜は奥に積んであるわ」
「ありがとう、リーシャ」
食料と鍋を小脇に抱え家に戻ると囲炉裏に火をおこした。
「待たせてごめん、食べ物持ってきた。叔父の番のリーシャは、君と同じ森の外の人間だから――、俺が作るより、彼女の作ったものの方が口に合うと思って、もらってきたんだけど」
「つがい」
聞き慣れない言葉をクロエは繰り返す。ああ、とルークは頷いた。外には番というものはなく、夫と妻がそれにあたる、とリーシャが言っていたことを思い出す。
「――妻のこと」
そう、と頷くクロエにルークは碗に注いだスープを差し出した。色鮮やかな野菜と、肉が煮込まれている。狼の手でスプーンがうまく持てずに、手がすべる。
「――人の姿でもいいか」
クロエは仕方なく頷いた。ルークは銀髪の青年の姿に戻ると、すくったスープに息を吹きかけ、冷ましてクロエの口元に運んだ。ずっと温かいそれを吸い込んで、クロエは顔を輝かせた。塩気はほとんどなかったが、肉と野菜の旨味と、何より水が美味しいのか、うっすらとした甘さを感じた。
「美味い?」
ルークはクロエの反応に満足そうに笑うと、ふと肩にかかる栗色の髪に目を留めた。
「結んだ方がいいな」
食べ物に入りそうだと思ったので、手を伸ばすと、指で梳くと左右で緩く三つ編みに編んだ。姪の髪を結んでやることがあるので、動きはスムーズだった。紐で毛先を結び、これで良しと頷いてから、顔を赤らめ俯くクロエに気付く。
「――どうしたんだ。口に合わなかった?」
クロエは顔の目の前の、がっしりした肌色の胸板から目を逸らす。狼の姿だと、コディが二足歩行をしているように思うが、人間の姿になられると、どうしても相手が男性だという意識が湧いてくる。
「上着を、着て。あと、私にも服をください」
ルークは困り顔で自分の上半身を見た。狼の姿で過ごすことが多いので、上着は着ないことのほうが多い。でも、彼女の様子がおかしいのは、それが外の感覚なのだろう。
「わかった。ちょっと待ってろ」
部屋の隅の棚に積まれた荷物から、長袖の上衣を掘り出し被る。もう一枚も掘り出しクロエに着せた。細かい作業のためか、人間の姿のルークに人形のように服を着せられ、クロエは恥ずかしさに俯いた。
(野人っていうから、もっと)
野蛮な存在を想像していた。本宅にいる時は、ほとんど野人の話は聞いたことがなかったが、幼いころ、森に隣接した国境付近の別宅にいた時に聞いた話は、獣の様な姿の怪物は出くわすと襲って来るというものだった。
このルークと名乗った野人の男は、裸の自分に何もする気がなさそうな上、傷を手当した上、食事をあたえ、髪まで結って面倒を見てくる。
(何なのかしら)
「これでいいか」
「いいです」
「何で口調を変えるんだ」
「だって」
スープの匂いが鼻先に漂い、またクロエの腹が鳴った。急に空腹感に襲われる。
「――食べさせて、もらえますか」
おずおずと言うと、ルークは顔をしかめた。森の中では、一族は皆対等で、お互いに丁寧な口調で話すことはない。
「その口調は気持ち悪い」
クロエはう、と唸ってから言い直した。
「――食べさせて」
よし、とルークは笑うとまたスープを口元に運んだ。
0
お気に入りに追加
249
あなたにおすすめの小説


婚約破棄したら食べられました(物理)
かぜかおる
恋愛
人族のリサは竜種のアレンに出会った時からいい匂いがするから食べたいと言われ続けている。
婚約者もいるから無理と言い続けるも、アレンもしつこく食べたいと言ってくる。
そんな日々が日常と化していたある日
リサは婚約者から婚約破棄を突きつけられる
グロは無し
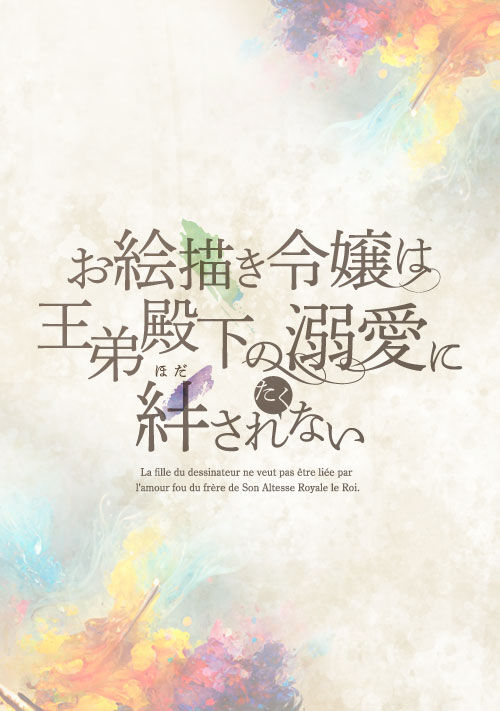
【完結】お絵描き令嬢は王弟殿下の溺愛に絆されたくない
オトカヨル
恋愛
絵を描くのが大好きな田舎の令嬢ネリー・ラヴィルニーはある日、王家主催の舞踏会へ招待される。
その舞踏会は次期王を決めるための試練の場だというのだが、父は彼女を送り出すのに心配で胃が痛い。
なにせ、王族を神官以外が描けば呪いをかけたと疑われても仕方ない国だと言うのに、ネリーは『描きたい』という衝動のまま行動しかねないからだ。
そしてその心配は現実に。
「こういうやり方は好きではないんだが」と、王族を描いてしまった絵を盾にされ
「描かせてくださるのですか? いくらでも?」と、報酬に釣られ、ネリーは王弟イアンと試練に挑むことになる。
※他サイト様にも掲載しております。

大好きなあなたを忘れる方法
山田ランチ
恋愛
あらすじ
王子と婚約関係にある侯爵令嬢のメリベルは、訳あってずっと秘密の婚約者のままにされていた。学園へ入学してすぐ、メリベルの魔廻が(魔術を使う為の魔素を貯めておく器官)が限界を向かえようとしている事に気が付いた大魔術師は、魔廻を小さくする事を提案する。その方法は、魔素が好むという悲しい記憶を失くしていくものだった。悲しい記憶を引っ張り出しては消していくという日々を過ごすうち、徐々に王子との記憶を失くしていくメリベル。そんな中、魔廻を奪う謎の者達に大魔術師とメリベルが襲われてしまう。
魔廻を奪おうとする者達は何者なのか。王子との婚約が隠されている訳と、重大な秘密を抱える大魔術師の正体が、メリベルの記憶に導かれ、やがて世界の始まりへと繋がっていく。
登場人物
・メリベル・アークトュラス 17歳、アークトゥラス侯爵の一人娘。ジャスパーの婚約者。
・ジャスパー・オリオン 17歳、第一王子。メリベルの婚約者。
・イーライ 学園の園芸員。
クレイシー・クレリック 17歳、クレリック侯爵の一人娘。
・リーヴァイ・ブルーマー 18歳、ブルーマー子爵家の嫡男でジャスパーの側近。
・アイザック・スチュアート 17歳、スチュアート侯爵の嫡男でジャスパーの側近。
・ノア・ワード 18歳、ワード騎士団長の息子でジャスパーの従騎士。
・シア・ガイザー 17歳、ガイザー男爵の娘でメリベルの友人。
・マイロ 17歳、メリベルの友人。
魔素→世界に漂っている物質。触れれば精神を侵され、生き物は主に凶暴化し魔獣となる。
魔廻→体内にある魔廻(まかい)と呼ばれる器官、魔素を取り込み貯める事が出来る。魔術師はこの器官がある事が必須。
ソル神とルナ神→太陽と月の男女神が魔素で満ちた混沌の大地に現れ、世界を二つに分けて浄化した。ソル神は昼間を、ルナ神は夜を受け持った。

星織りの歌【完結】
しょこら
恋愛
四枚羽根の少女フィリアは幼なじみの少年ランディスと約束をした。「わたし、絶対に星織姫になる!」「じゃあ、僕は近衛になってフィリアを護る」有翼の人々が住む青く美しいエレミアの星には、通常なら二枚の羽根を持って生まれてくるが、まれに四枚の羽根を持って生まれてくる少女たちがいた。彼女たちは星を護る女神となるべく修行し、星杖の選定を受けて女神「星織姫」となる。歌の力で星のバランスを保ち、安定させるのだ。フィリアはランディスの守護の元、もう一人の候補であるクレアとともに星織姫を目指す。だが《セラフィム》を名乗る刺客たちに襲われる中、星織姫を目指す候補の末路を聞かされ、衝撃を受ける。
星織姫を諦めたくない!でもランディスも失いたくない。大きく揺れながら、フィリアは決断していく。

結婚式をボイコットした王女
椿森
恋愛
請われて隣国の王太子の元に嫁ぐこととなった、王女のナルシア。
しかし、婚姻の儀の直前に王太子が不貞とも言える行動をしたためにボイコットすることにした。もちろん、婚約は解消させていただきます。
※初投稿のため生暖か目で見てくださると幸いです※
1/9:一応、本編完結です。今後、このお話に至るまでを書いていこうと思います。
1/17:王太子の名前を修正しました!申し訳ございませんでした···( ´ཫ`)

身代わりーダイヤモンドのように
Rj
恋愛
恋人のライアンには想い人がいる。その想い人に似ているから私を恋人にした。身代わりは本物にはなれない。
恋人のミッシェルが身代わりではいられないと自分のもとを去っていった。彼女の心に好きという言葉がとどかない。
お互い好きあっていたが破れた恋の話。
一話完結でしたが二話を加え全三話になりました。(6/24変更)

引きこもり少女、御子になる~お世話係は過保護な王子様~
浅海 景
恋愛
オッドアイで生まれた透花は家族から厄介者扱いをされて引きこもりの生活を送っていた。ある日、双子の姉に突き飛ばされて頭を強打するが、目を覚ましたのは見覚えのない場所だった。ハウゼンヒルト神聖国の王子であるフィルから、世界を救う御子(みこ)だと告げられた透花は自分には無理だと否定するが、御子であるかどうかを判断するために教育を受けることに。
御子至上主義なフィルは透花を大切にしてくれるが、自分が御子だと信じていない透花はフィルの優しさは一時的なものだと自分に言い聞かせる。
「きっといつかはこの人もまた自分に嫌悪し離れていくのだから」
自己肯定感ゼロの少女が過保護な王子や人との関わりによって、徐々に自分を取り戻す物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















