18 / 38
2章 森の中の生活
2-3.森の民
しおりを挟む
クロエが出て行った後、しんとした暗闇に包まれた部屋で、ルークは喉の奥から吠え声を上げた。首輪を掴んで砕こうとするが、腕に力が入らなかった。動く度、首輪の裏にある突起が首にあたり痛みを感じた。ジャラジャラと鎖の擦れる音だけが部屋に響く。
「クソ!」
四肢を投げ出し、天井を睨む。
「アメリア」
番の名を口にしてルークは咆哮を上げ、頭を押さえうずくまった。クロエが彼女に直接的に何か危害を加えることはないだろう、それよりも。
(夫といる)
そのことがルークの内側に、身体の半分を引き裂くような目に見えない痛みを与えていた。それと同時に、感じたことのないどろどろとした、怒りと焦燥感が混じったような感情で頭が支配されていくのを感じた。何日も空腹のところで、ようやく捕らえた獲物の肉を目前で奪われるような、そんな感覚だった。そのどろどろとした感覚は、アメリアと一緒にいるというチャールズという男に、何より自分自身に向いていた。
(俺が招いたことだ)
頭の奥底を刺激する微かな匂いを感じ、森の外へ近づいた時のことを思い出す。
そこには、地面に横たわる女とそれに覆いかぶさる人間の男が3人いた。
彼らは、自分たちのことを『野人』だの『獣』だの呼ぶが、どちらが獣かとルークは思う。
ルークたち、森の中に住む彼らは、自分たちのことを『森の民』と呼ぶ。
森の民の社会は、番同士の築く、血の繋がりで構成された、穏やかなーーまるで揺り籠にいるような社会だ。男は狼などの肉食獣の姿をとることができ、女は外の人間と同じ姿をしている。男は森で獲物を狩り、女は里で子どもを育て家庭を守る。それぞれが家族を作るための運命の相手、番を持っており、それは生まれた時から決まっている。森の民は一族ごとに里を形成し暮らしており、ほとんどの場合番は別の里に生まれ、20歳くらいまでに自然とめぐり合うようになっていた。不思議な力が働いているのか、番に出会わないということはなく、子どもも、それぞれ番として見合った数の男女が産まれるようだった。
ただ稀に、番となる娘が森の外からやって来ることがある。それは、外の血を入れるためなのか、理由はわからないが、彼女たちは、その時が来ると森の外からやってきた。彼女たちは『客番』と呼ばれ、有難がられる。なぜならば、穏やかで変わることのない森の中に変化をもたらすからだった。例えば、衣服に色を染めたり、作物を育てたり、寝心地の良い寝具を作ったり。また、新しい言葉や概念が、彼女たちからもたらされることもあった。
「愛している」
クロエの言葉を復唱して、ルークは頭を抱えた。『愛している』という言葉も、客番が森の中へもたらした言葉だ。もともと森の民たちはその言葉を持っていなかった。
彼らは基本的に番に対して以外、性的欲求を抱かない。番に出会うと血が沸くような昂ぶりを感じ、その首筋に男が牙を立てることで、番同士の繋がりが確立する。番は運命を共にする相手であり、片方が傷つけば、もう片方の同じ場所に痛みが生じるほどにお互いの全てを共有し、一生を添い遂げる。そんな安定した、絶対的な関係性の中で、森の中には外の世界のように恋愛というもよが存在しなかった。そのため番に対する感情を改めて表現する必要がなかった。
だが、その昔森の外からやってきた客番は、番の男に『愛してる』と言った。その言葉の響きは男の耳に心地よく響き、それから番同士で愛情を表現するためにその言葉が使われるようになった。
ルークはまた吠えた。
『愛している』という言葉をクロエに使わせ、彼女を焚きつけたのは自分なのだろうか。だが、彼女は自分の番ではない。自分がその言葉を使う相手は、アメリアだ。だが、彼女は今、夫――森の外で言うところの番と一緒にいるという。
森の中では、番同士の関係は絶対的なものだ。誰かの番が別の誰かと過ごすことなどありえない。だから、嫉妬という感情も存在しないし、それを表す言葉もない。
自分の番が、別の男と夜を過ごしているという状況はルークの想像しえないことで、その事実に自分の中に生じるどろどろとした感情をどう表現すればいいのか、彼はわからなかった。
(あの時、里に連れて行かなければ、いや、)
性行為は森の民にとっては番同士でのみ行われる清らかな行為だ。クロエに覆いかぶさり、下半身を露出した外の人間の男に不快感を覚えたルークは彼らをなぎ払った。
外の人間が森を切り開くことで、山賊のようになったならず者が森の奥に足を踏み入れてくることが増え、稀にそういう連中と接触することもあった。里は不思議な力で守られており、外の人間が足を踏み入れることはできない。だが、森の民は森の海を自由に行き来する力を持っており、狩りのときは様々な場所へ足を運ぶので、外の人里近くに行ってしまうこともあった。
客番以外の外の人間を里に連れて行くことはない。だが足から血を流し呻く彼女からは、どこはかとなく微かに、頭の奥を刺激する匂いを感じた。それに彼女は狼の姿の頬を愛おし気に撫でたのだ。普通なら外の人間はその姿を見れば、『野人だ』『化け物だ』などと悲鳴を上げるのに。
ルークは20歳になっても里の中で番に出会わなかった。ルークの叔父のブルーノの番であるリーシャは外からやってきた客番だった。ブルーノは甥に語り掛けた。
「お前の番も森の外にいるんだよ、きっと。時が来れば、わかる。相手とひとめ目が合うと頭が沸騰するような感じがするんだ」
その日狩りに出た先で、ふと鼻先を何か――身体の奥底を刺激するような匂いを感じた。それを辿ったところにクロエがいた。叔父の言っていた『頭が沸騰するような感じ』はしなかったが、自分の頬を愛おし気に撫でる彼女の手の感触と、「コディ」と誰かの名前を呟いたことが気になった。ぐったりした彼女はこのまま放っておいたら死ぬだろうと思い、焦ってそのまま里に連れて帰った。
アメリアが夫といるという事実に、自分が悶えているのは自身が招いたことだ。自分がクロエと関係を持ったのは事実なのだから。
「クソ!」
四肢を投げ出し、天井を睨む。
「アメリア」
番の名を口にしてルークは咆哮を上げ、頭を押さえうずくまった。クロエが彼女に直接的に何か危害を加えることはないだろう、それよりも。
(夫といる)
そのことがルークの内側に、身体の半分を引き裂くような目に見えない痛みを与えていた。それと同時に、感じたことのないどろどろとした、怒りと焦燥感が混じったような感情で頭が支配されていくのを感じた。何日も空腹のところで、ようやく捕らえた獲物の肉を目前で奪われるような、そんな感覚だった。そのどろどろとした感覚は、アメリアと一緒にいるというチャールズという男に、何より自分自身に向いていた。
(俺が招いたことだ)
頭の奥底を刺激する微かな匂いを感じ、森の外へ近づいた時のことを思い出す。
そこには、地面に横たわる女とそれに覆いかぶさる人間の男が3人いた。
彼らは、自分たちのことを『野人』だの『獣』だの呼ぶが、どちらが獣かとルークは思う。
ルークたち、森の中に住む彼らは、自分たちのことを『森の民』と呼ぶ。
森の民の社会は、番同士の築く、血の繋がりで構成された、穏やかなーーまるで揺り籠にいるような社会だ。男は狼などの肉食獣の姿をとることができ、女は外の人間と同じ姿をしている。男は森で獲物を狩り、女は里で子どもを育て家庭を守る。それぞれが家族を作るための運命の相手、番を持っており、それは生まれた時から決まっている。森の民は一族ごとに里を形成し暮らしており、ほとんどの場合番は別の里に生まれ、20歳くらいまでに自然とめぐり合うようになっていた。不思議な力が働いているのか、番に出会わないということはなく、子どもも、それぞれ番として見合った数の男女が産まれるようだった。
ただ稀に、番となる娘が森の外からやって来ることがある。それは、外の血を入れるためなのか、理由はわからないが、彼女たちは、その時が来ると森の外からやってきた。彼女たちは『客番』と呼ばれ、有難がられる。なぜならば、穏やかで変わることのない森の中に変化をもたらすからだった。例えば、衣服に色を染めたり、作物を育てたり、寝心地の良い寝具を作ったり。また、新しい言葉や概念が、彼女たちからもたらされることもあった。
「愛している」
クロエの言葉を復唱して、ルークは頭を抱えた。『愛している』という言葉も、客番が森の中へもたらした言葉だ。もともと森の民たちはその言葉を持っていなかった。
彼らは基本的に番に対して以外、性的欲求を抱かない。番に出会うと血が沸くような昂ぶりを感じ、その首筋に男が牙を立てることで、番同士の繋がりが確立する。番は運命を共にする相手であり、片方が傷つけば、もう片方の同じ場所に痛みが生じるほどにお互いの全てを共有し、一生を添い遂げる。そんな安定した、絶対的な関係性の中で、森の中には外の世界のように恋愛というもよが存在しなかった。そのため番に対する感情を改めて表現する必要がなかった。
だが、その昔森の外からやってきた客番は、番の男に『愛してる』と言った。その言葉の響きは男の耳に心地よく響き、それから番同士で愛情を表現するためにその言葉が使われるようになった。
ルークはまた吠えた。
『愛している』という言葉をクロエに使わせ、彼女を焚きつけたのは自分なのだろうか。だが、彼女は自分の番ではない。自分がその言葉を使う相手は、アメリアだ。だが、彼女は今、夫――森の外で言うところの番と一緒にいるという。
森の中では、番同士の関係は絶対的なものだ。誰かの番が別の誰かと過ごすことなどありえない。だから、嫉妬という感情も存在しないし、それを表す言葉もない。
自分の番が、別の男と夜を過ごしているという状況はルークの想像しえないことで、その事実に自分の中に生じるどろどろとした感情をどう表現すればいいのか、彼はわからなかった。
(あの時、里に連れて行かなければ、いや、)
性行為は森の民にとっては番同士でのみ行われる清らかな行為だ。クロエに覆いかぶさり、下半身を露出した外の人間の男に不快感を覚えたルークは彼らをなぎ払った。
外の人間が森を切り開くことで、山賊のようになったならず者が森の奥に足を踏み入れてくることが増え、稀にそういう連中と接触することもあった。里は不思議な力で守られており、外の人間が足を踏み入れることはできない。だが、森の民は森の海を自由に行き来する力を持っており、狩りのときは様々な場所へ足を運ぶので、外の人里近くに行ってしまうこともあった。
客番以外の外の人間を里に連れて行くことはない。だが足から血を流し呻く彼女からは、どこはかとなく微かに、頭の奥を刺激する匂いを感じた。それに彼女は狼の姿の頬を愛おし気に撫でたのだ。普通なら外の人間はその姿を見れば、『野人だ』『化け物だ』などと悲鳴を上げるのに。
ルークは20歳になっても里の中で番に出会わなかった。ルークの叔父のブルーノの番であるリーシャは外からやってきた客番だった。ブルーノは甥に語り掛けた。
「お前の番も森の外にいるんだよ、きっと。時が来れば、わかる。相手とひとめ目が合うと頭が沸騰するような感じがするんだ」
その日狩りに出た先で、ふと鼻先を何か――身体の奥底を刺激するような匂いを感じた。それを辿ったところにクロエがいた。叔父の言っていた『頭が沸騰するような感じ』はしなかったが、自分の頬を愛おし気に撫でる彼女の手の感触と、「コディ」と誰かの名前を呟いたことが気になった。ぐったりした彼女はこのまま放っておいたら死ぬだろうと思い、焦ってそのまま里に連れて帰った。
アメリアが夫といるという事実に、自分が悶えているのは自身が招いたことだ。自分がクロエと関係を持ったのは事実なのだから。
0
お気に入りに追加
249
あなたにおすすめの小説


婚約破棄したら食べられました(物理)
かぜかおる
恋愛
人族のリサは竜種のアレンに出会った時からいい匂いがするから食べたいと言われ続けている。
婚約者もいるから無理と言い続けるも、アレンもしつこく食べたいと言ってくる。
そんな日々が日常と化していたある日
リサは婚約者から婚約破棄を突きつけられる
グロは無し
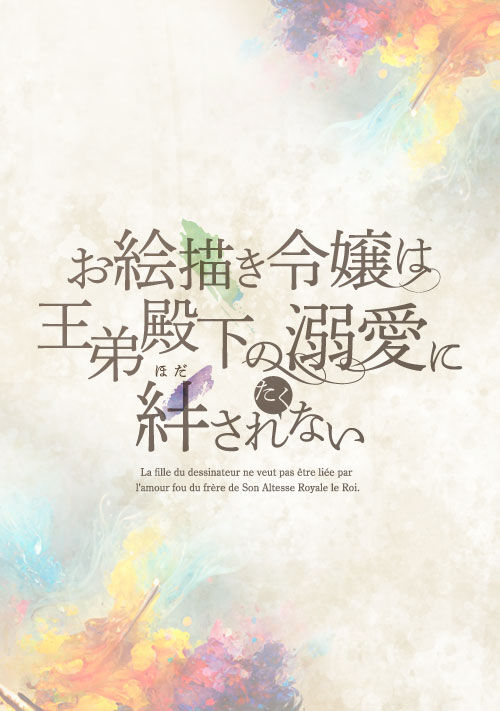
【完結】お絵描き令嬢は王弟殿下の溺愛に絆されたくない
オトカヨル
恋愛
絵を描くのが大好きな田舎の令嬢ネリー・ラヴィルニーはある日、王家主催の舞踏会へ招待される。
その舞踏会は次期王を決めるための試練の場だというのだが、父は彼女を送り出すのに心配で胃が痛い。
なにせ、王族を神官以外が描けば呪いをかけたと疑われても仕方ない国だと言うのに、ネリーは『描きたい』という衝動のまま行動しかねないからだ。
そしてその心配は現実に。
「こういうやり方は好きではないんだが」と、王族を描いてしまった絵を盾にされ
「描かせてくださるのですか? いくらでも?」と、報酬に釣られ、ネリーは王弟イアンと試練に挑むことになる。
※他サイト様にも掲載しております。

大好きなあなたを忘れる方法
山田ランチ
恋愛
あらすじ
王子と婚約関係にある侯爵令嬢のメリベルは、訳あってずっと秘密の婚約者のままにされていた。学園へ入学してすぐ、メリベルの魔廻が(魔術を使う為の魔素を貯めておく器官)が限界を向かえようとしている事に気が付いた大魔術師は、魔廻を小さくする事を提案する。その方法は、魔素が好むという悲しい記憶を失くしていくものだった。悲しい記憶を引っ張り出しては消していくという日々を過ごすうち、徐々に王子との記憶を失くしていくメリベル。そんな中、魔廻を奪う謎の者達に大魔術師とメリベルが襲われてしまう。
魔廻を奪おうとする者達は何者なのか。王子との婚約が隠されている訳と、重大な秘密を抱える大魔術師の正体が、メリベルの記憶に導かれ、やがて世界の始まりへと繋がっていく。
登場人物
・メリベル・アークトュラス 17歳、アークトゥラス侯爵の一人娘。ジャスパーの婚約者。
・ジャスパー・オリオン 17歳、第一王子。メリベルの婚約者。
・イーライ 学園の園芸員。
クレイシー・クレリック 17歳、クレリック侯爵の一人娘。
・リーヴァイ・ブルーマー 18歳、ブルーマー子爵家の嫡男でジャスパーの側近。
・アイザック・スチュアート 17歳、スチュアート侯爵の嫡男でジャスパーの側近。
・ノア・ワード 18歳、ワード騎士団長の息子でジャスパーの従騎士。
・シア・ガイザー 17歳、ガイザー男爵の娘でメリベルの友人。
・マイロ 17歳、メリベルの友人。
魔素→世界に漂っている物質。触れれば精神を侵され、生き物は主に凶暴化し魔獣となる。
魔廻→体内にある魔廻(まかい)と呼ばれる器官、魔素を取り込み貯める事が出来る。魔術師はこの器官がある事が必須。
ソル神とルナ神→太陽と月の男女神が魔素で満ちた混沌の大地に現れ、世界を二つに分けて浄化した。ソル神は昼間を、ルナ神は夜を受け持った。

星織りの歌【完結】
しょこら
恋愛
四枚羽根の少女フィリアは幼なじみの少年ランディスと約束をした。「わたし、絶対に星織姫になる!」「じゃあ、僕は近衛になってフィリアを護る」有翼の人々が住む青く美しいエレミアの星には、通常なら二枚の羽根を持って生まれてくるが、まれに四枚の羽根を持って生まれてくる少女たちがいた。彼女たちは星を護る女神となるべく修行し、星杖の選定を受けて女神「星織姫」となる。歌の力で星のバランスを保ち、安定させるのだ。フィリアはランディスの守護の元、もう一人の候補であるクレアとともに星織姫を目指す。だが《セラフィム》を名乗る刺客たちに襲われる中、星織姫を目指す候補の末路を聞かされ、衝撃を受ける。
星織姫を諦めたくない!でもランディスも失いたくない。大きく揺れながら、フィリアは決断していく。

結婚式をボイコットした王女
椿森
恋愛
請われて隣国の王太子の元に嫁ぐこととなった、王女のナルシア。
しかし、婚姻の儀の直前に王太子が不貞とも言える行動をしたためにボイコットすることにした。もちろん、婚約は解消させていただきます。
※初投稿のため生暖か目で見てくださると幸いです※
1/9:一応、本編完結です。今後、このお話に至るまでを書いていこうと思います。
1/17:王太子の名前を修正しました!申し訳ございませんでした···( ´ཫ`)

身代わりーダイヤモンドのように
Rj
恋愛
恋人のライアンには想い人がいる。その想い人に似ているから私を恋人にした。身代わりは本物にはなれない。
恋人のミッシェルが身代わりではいられないと自分のもとを去っていった。彼女の心に好きという言葉がとどかない。
お互い好きあっていたが破れた恋の話。
一話完結でしたが二話を加え全三話になりました。(6/24変更)

引きこもり少女、御子になる~お世話係は過保護な王子様~
浅海 景
恋愛
オッドアイで生まれた透花は家族から厄介者扱いをされて引きこもりの生活を送っていた。ある日、双子の姉に突き飛ばされて頭を強打するが、目を覚ましたのは見覚えのない場所だった。ハウゼンヒルト神聖国の王子であるフィルから、世界を救う御子(みこ)だと告げられた透花は自分には無理だと否定するが、御子であるかどうかを判断するために教育を受けることに。
御子至上主義なフィルは透花を大切にしてくれるが、自分が御子だと信じていない透花はフィルの優しさは一時的なものだと自分に言い聞かせる。
「きっといつかはこの人もまた自分に嫌悪し離れていくのだから」
自己肯定感ゼロの少女が過保護な王子や人との関わりによって、徐々に自分を取り戻す物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















