お気に入りに追加
44
あなたにおすすめの小説

夫の不貞現場を目撃してしまいました
秋月乃衣
恋愛
伯爵夫人ミレーユは、夫との間に子供が授からないまま、閨を共にしなくなって一年。
何故か夫から閨を拒否されてしまっているが、理由が分からない。
そんな時に夜会中の庭園で、夫と未亡人のマデリーンが、情事に耽っている場面を目撃してしまう。
なろう様でも掲載しております。

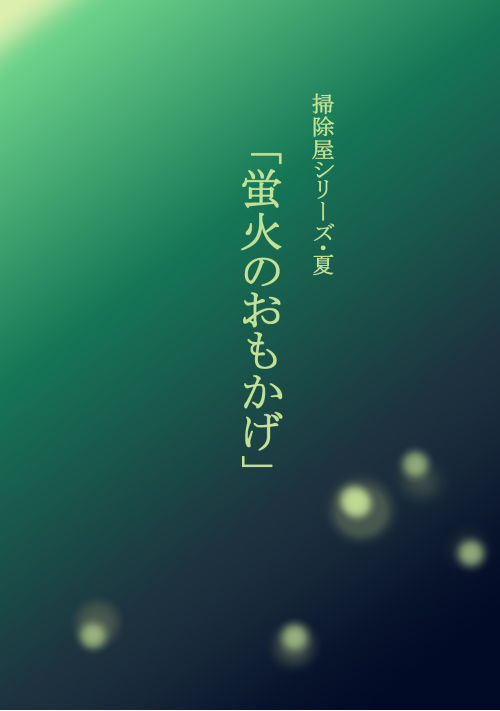
蛍火のおもかげ
藤田 蓮
ライト文芸
馨はある夏の夕暮れ、浴衣姿の「掃除屋」だと名乗る男に遭遇する。
「掃除屋」の男に礼を言って消えた老婆。手向けられた花。得体の知れない「掃除屋」との出会い。
それはただの遭遇に過ぎないかと思われた。
だが、馨は、それが忘れることの出来ぬ夏の日の始まりだということを、まだ知らなかった。
掃除屋シリーズ、第一弾。今回は「夏」です。

婚約者の浮気を目撃した後、私は死にました。けれど戻ってこれたので、人生やり直します
Kouei
恋愛
夜の寝所で裸で抱き合う男女。
女性は従姉、男性は私の婚約者だった。
私は泣きながらその場を走り去った。
涙で歪んだ視界は、足元の階段に気づけなかった。
階段から転がり落ち、頭を強打した私は死んだ……はずだった。
けれど目が覚めた私は、過去に戻っていた!
※この作品は、他サイトにも投稿しています。

私と継母の極めて平凡な日常
当麻月菜
ライト文芸
ある日突然、父が再婚した。そして再婚後、たった三ヶ月で失踪した。
残されたのは私、橋坂由依(高校二年生)と、継母の琴子さん(32歳のキャリアウーマン)の二人。
「ああ、この人も出て行くんだろうな。私にどれだけ自分が不幸かをぶちまけて」
そう思って覚悟もしたけれど、彼女は出て行かなかった。
そうして始まった継母と私の二人だけの日々は、とても淡々としていながら酷く穏やかで、極めて平凡なものでした。
※他のサイトにも重複投稿しています。

『別れても好きな人』
設樂理沙
ライト文芸
大好きな夫から好きな女性ができたから別れて欲しいと言われ、離婚した。
夫の想い人はとても美しく、自分など到底敵わないと思ったから。
ほんとうは別れたくなどなかった。
この先もずっと夫と一緒にいたかった……だけど世の中には
どうしようもないことがあるのだ。
自分で選択できないことがある。
悲しいけれど……。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
登場人物紹介
戸田貴理子 40才
戸田正義 44才
青木誠二 28才
嘉島優子 33才
小田聖也 35才
2024.4.11 ―― プロット作成日
💛イラストはAI生成自作画像


諦めて、もがき続ける。
りつ
恋愛
婚約者であったアルフォンスが自分ではない他の女性と浮気して、子どもまでできたと知ったユーディットは途方に暮れる。好きな人と結ばれことは叶わず、彼女は二十年上のブラウワー伯爵のもとへと嫁ぐことが決まった。伯爵の思うがままにされ、心をすり減らしていくユーディット。それでも彼女は、ある言葉を胸に、毎日を生きていた。
※表紙は「かんたん表紙メーカー」様で作成しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















