25 / 36
雪解けの前に
4
しおりを挟む
なんとか歩ける程度に回復した燈は鬼谷の病室までやってきていた。
ネームプレートを確認してみると面会謝絶の札はかかっていなくてホッとする。
ゆっくりと扉を開けると鬼谷はベッドの上にいて、普段の燈と同じように窓から見える景色を見ていた。
「あら、どうしたの?」
燈に気付いて鬼谷は笑みを作る。
「いつも僕の方に来られるからね。たまにはこっちから行ってやろうと思って」
「あはは、なにそれ」
元気に笑う鬼谷を見て、調子が戻ったのだと安心した。
「鬼谷さん。腎臓が悪いの?」
質問を投げかけてみると鬼谷はぴたりと笑い声を止めた。
「誰かから聞いた?」
「うん……医者が話してるのを偶然」
「そう……」
鬼谷は黙り込んで外を眺める。
もしかしたら聞いてはいけないことだったのだろうか。
彼女の様子を見てそう思った燈は追及することなく、同じようにして外の景色を眺めていた。
「外、寒そうだね」
「え……うん、そうだね」
外は昼間だというのに曇り空が太陽を隠して薄暗い。風が吹いているのか窓がキシキシと音を立てて寒さを感じさせていた。
「燈君はさ、ずっと外で過ごして凍えて死ぬか。それとも暖かい建物の中でじわじわと死ぬか。どっちが残酷だと思う?」
外を見ながら鬼谷が言う。
「なんだい、その物騒な話」
「なんとなく思いついただけだよ。燈君ならどっちがいい?」
「どっちかから選ばないとだめ?」
「だめ」
「う~ん……それなら、僕は外で凍え死ぬのを選ぶかな」
「どうして?」
「僕の人生はずっと病室に閉じこもったままだから。病気だって治す方法がなくてゆっくりと体が蝕まれていくのを止めることしかできない。それならいっそ外に出て、行きたいところにいって死んでしまった方がいいと思ったから」
どうせ死ぬしかないのなら、その方が絶対にいい。
燈がそう説明すると、鬼谷は「そっか」と呟く。
「私は後者を選択した。外の寒さはとても辛くて。ひもじくて。そんな場所から抜け出せるのなら、なんだって受け入れれるとそう思ったから。でも……結局私は受け入れられなかった。暖かくても、寂しさには耐えられなかった。だから、私は逃げ出した」
「逃げ出した? いったい何の話なのさ?」
「…………ごめん。なんでもない」
鬼谷はこちらを向いて笑った。
「外があまりに寒そうだから、ちょっと感傷的な気分になっちゃったみたい」
「らしくないよね」と言って笑う鬼谷を見て燈は悲しい気持ちになった。
いつもと変わらずに見える笑顔。それが今にも壊れてしまいそうに見えたから。
「鬼谷さんには僕がいるよ」
「燈君……」
「僕の病気は今の医療じゃ治すことが出来ないからね。ここから離れる事は出来ない。だから僕から離れることはないよ。鬼谷がいなくなるその時まで。僕はずっと一緒にいる。今までだってそうだったでしょ」
燈が言うと、鬼谷はくすくすと笑う。
「なにさ?」
「だって、なんだかそれ。告白……いえ、プロポーズみたいだもの」
「な……っ」
燈は驚き、顔を赤くする。
「いや~、モテるおなごは辛いですな」
「なんだよ……折角気を使ったのに」
「いや~ん。機嫌悪くならないで~。本当に嬉しかったよ~」
「もういいよ」
ふざける鬼谷に顔を逸らすと、氷のように冷たい感触が手に乗った。
「……本当に、嬉しいよ。そんな事言われたの――そんな風に扱われたのは初めて……だから私も約束するよ」
「鬼谷さん?」
「私も燈君と一緒にいる。何が起きても、私は君から離れない」
「……鬼谷さん」
彼女の真剣な眼差しに、燈はドキリとした。
すると間を置かずに鬼谷は表情を崩す。
「って、改めて言うまでもなく一緒にいるんだけどね~」
「……折角綺麗な表情だったのに、なんだか全部台無しだよ」
「お、嘘。美人だった?」
鬼谷は言ってからキリリと目に力を入れる。さっきまでの重い空気はなんだったのか。
燈は呆れた表情で鬼谷を見た。「全然美人じゃない」
「もう12月も中盤か」
病室に設置された卓上カレンダーを見ながら燈は言った。
12月に入ってからというもの、一度倒れはしたが体調は比較的安定していた。それに合わせて食事の量もほんの少しだけ増えていて。身体も普段より動くようになっていた。今年もなんとか超える事は出来そうだ。
長く入院しているせいで、このまま治るのでは。とは思えなかったがそれでも体調が良いと気分も上がってくるもので、燈の方から鬼谷の病室に向かう回数も増えていた。
「ご馳走様でした」
食事を終わらした燈はテーブルを避けるとベッドから降りる。
カレンダーの横にある雑誌を取って病室を出た。
手に持ってるのはクロスワードをまとめた雑誌だった。この間見舞いに来た親が購買用の小遣いを渡してくれて、燈はその日の内に購買に出向き、雑誌を購入していた。
燈は別段パズルが得意なわけではない。
だが購買の中で鬼谷と二人で遊ぶのはこれぐらいしかなかった。いわば妥協品だ。それでも燈は鬼谷の病室に向かう間、ずっとわくわくとした気持ちを持っていた。
処置室の前まで来て燈は足を止める。
頭の中には鬼谷の事を聞いた記憶が戻ってきていた。
鬼谷も燈と同じで好調が続いているようで、あの日以降一度も病室が閉じられている事はなかった。だけど悪い記憶が足を引っ張り、処置室の近くを通るのに物怖じしてしまう。
処置室の扉を監視するように見つめながら通り過ぎようとすると、話し声が聞こえてくる。
医者が詰めている場所だったから話し声がするのは当たり前ではあったのだが、燈はどきりとした。
「……」
燈はその場に止まる。
距離が遠くて何を話しているのかは聞こえていなかったが、もしも悪い話だったらどうしようと気になって仕方がなかった。
このまま近づいて、聞き耳を立てようか。
そう思う気持ちと葛藤して、悩んだ末に燈はその場を離れた。
余計な事を聞いてまたしても体調を崩してしまったら、鬼谷と遊ぶことが出来なくなってしまう。その気持ちが好奇心に勝っていた。
鬼谷の病室につくと扉が開いていた。部屋の中から鬼谷と別の女性の声が聞こえてくる。どうやら問診か何かしているようだ。
燈は終わるまで待っていようと扉の脇に座り込んだ。
「特に変化は見当たらないってことね」
「えぇ。今のところは。寧ろ一番元気かも知れません」
「そう、それはよかったけど……覚悟だけはしといた方がいいかもね」
「……はい」
聞こえてくる会話に燈はその場に座り込んだことを後悔した。
覚悟。僕たちみたいな延命処置をされている人間にとっては死の宣告にも等しい言葉。それが彼女の病室から聞こえてきてしまった。
まさかと思った。気が付けば持ってきた雑誌を強く握り、クシャクシャにしてしまっていた。燈はその事にも気づかず。耳に神経を集中させる。
「治ることは、ないんですか……?」
鬼谷の声が聞こえる。
「……はっきり言うけど。今生きてる時点で奇跡に近いの。症状も肝機能が目立つだけで他は軽度で収まっているけど、MRIの数値はあまり良くないし人工透析の頻度も上がってきている。回復は難しいと思うわ」
「じゃあ……どのくらい、生きれるんですか?」
「わからないわ。さっきも言ったけど、生きてるのが奇跡に近い状態なの。明日急変するかも知れないし。もっと長く生きれるかもしれない。でも、数か月……春を超えることは難しいかも知れない」
「……」
「もちろん私たちも努力する。燈君を死なせはしないつもりよ。でも、やはり万一があるから、急に彼がいなくなったとしても、鬼谷さんには理解しておいて欲しいの」
「……」
鬼谷が黙り込み、辺りが静かになる。そんな事が気にならないくらいに僕の心はざわついていた。
彼女が話していたのは僕の話だ。春を待たずに僕が死ぬという話をしているんだ。
驚くくらいに頭がすっきりとしている。その癖心臓はバクバクと身体を突き抜けるぐらいに鼓動していた。
「ごめんなさい。辛い事を言ってしまって」
「……いえ」
看護師の足音が聞こえて燈は慌てて病室を離れた。
自分の部屋に戻るとすぐさまベッドに飛び込んで布団で体を覆い隠す。頭の中ではさっきのやり取りをずっと反芻していた。
僕は、もうすぐ、死ぬ?
体は今までにないくらい元気だし、食べる量だって増えている。それなのに死んでしまうって?
燈は信じる事ができなかった。鬼谷は僕の存在に気付いていて、意地悪してそんな会話をしているのだとすら思った。
だが違う。彼女はそんな悪質な意地悪なんてしない。看護師だってそんな事に賛同したりはしない。
つまり、僕は死ぬのだ。
いつかその日が来るとはわかっていたけど、とうとうその日がやってくるのだ。
だから看護師は、特別仲がいい彼女に伝えに来たのだ。僕につられて体調を崩さないように。
「う……ふっ……ぐぅ…………」
涙が溢れ出てきて止めることが出来ない。一緒に声も溢れそうだったけど、口に手を当てて必死に押し殺した。
このタイミングで僕が泣き叫んでいたら聞き耳を立てていたことを気付かれてしまうかもしれない。それで鬼谷が気を病んでしまったらと考えると、自然と嗚咽を抑え込んでいた。
時間が止まったような感覚の中、燈はずっと泣き続けていた。
ネームプレートを確認してみると面会謝絶の札はかかっていなくてホッとする。
ゆっくりと扉を開けると鬼谷はベッドの上にいて、普段の燈と同じように窓から見える景色を見ていた。
「あら、どうしたの?」
燈に気付いて鬼谷は笑みを作る。
「いつも僕の方に来られるからね。たまにはこっちから行ってやろうと思って」
「あはは、なにそれ」
元気に笑う鬼谷を見て、調子が戻ったのだと安心した。
「鬼谷さん。腎臓が悪いの?」
質問を投げかけてみると鬼谷はぴたりと笑い声を止めた。
「誰かから聞いた?」
「うん……医者が話してるのを偶然」
「そう……」
鬼谷は黙り込んで外を眺める。
もしかしたら聞いてはいけないことだったのだろうか。
彼女の様子を見てそう思った燈は追及することなく、同じようにして外の景色を眺めていた。
「外、寒そうだね」
「え……うん、そうだね」
外は昼間だというのに曇り空が太陽を隠して薄暗い。風が吹いているのか窓がキシキシと音を立てて寒さを感じさせていた。
「燈君はさ、ずっと外で過ごして凍えて死ぬか。それとも暖かい建物の中でじわじわと死ぬか。どっちが残酷だと思う?」
外を見ながら鬼谷が言う。
「なんだい、その物騒な話」
「なんとなく思いついただけだよ。燈君ならどっちがいい?」
「どっちかから選ばないとだめ?」
「だめ」
「う~ん……それなら、僕は外で凍え死ぬのを選ぶかな」
「どうして?」
「僕の人生はずっと病室に閉じこもったままだから。病気だって治す方法がなくてゆっくりと体が蝕まれていくのを止めることしかできない。それならいっそ外に出て、行きたいところにいって死んでしまった方がいいと思ったから」
どうせ死ぬしかないのなら、その方が絶対にいい。
燈がそう説明すると、鬼谷は「そっか」と呟く。
「私は後者を選択した。外の寒さはとても辛くて。ひもじくて。そんな場所から抜け出せるのなら、なんだって受け入れれるとそう思ったから。でも……結局私は受け入れられなかった。暖かくても、寂しさには耐えられなかった。だから、私は逃げ出した」
「逃げ出した? いったい何の話なのさ?」
「…………ごめん。なんでもない」
鬼谷はこちらを向いて笑った。
「外があまりに寒そうだから、ちょっと感傷的な気分になっちゃったみたい」
「らしくないよね」と言って笑う鬼谷を見て燈は悲しい気持ちになった。
いつもと変わらずに見える笑顔。それが今にも壊れてしまいそうに見えたから。
「鬼谷さんには僕がいるよ」
「燈君……」
「僕の病気は今の医療じゃ治すことが出来ないからね。ここから離れる事は出来ない。だから僕から離れることはないよ。鬼谷がいなくなるその時まで。僕はずっと一緒にいる。今までだってそうだったでしょ」
燈が言うと、鬼谷はくすくすと笑う。
「なにさ?」
「だって、なんだかそれ。告白……いえ、プロポーズみたいだもの」
「な……っ」
燈は驚き、顔を赤くする。
「いや~、モテるおなごは辛いですな」
「なんだよ……折角気を使ったのに」
「いや~ん。機嫌悪くならないで~。本当に嬉しかったよ~」
「もういいよ」
ふざける鬼谷に顔を逸らすと、氷のように冷たい感触が手に乗った。
「……本当に、嬉しいよ。そんな事言われたの――そんな風に扱われたのは初めて……だから私も約束するよ」
「鬼谷さん?」
「私も燈君と一緒にいる。何が起きても、私は君から離れない」
「……鬼谷さん」
彼女の真剣な眼差しに、燈はドキリとした。
すると間を置かずに鬼谷は表情を崩す。
「って、改めて言うまでもなく一緒にいるんだけどね~」
「……折角綺麗な表情だったのに、なんだか全部台無しだよ」
「お、嘘。美人だった?」
鬼谷は言ってからキリリと目に力を入れる。さっきまでの重い空気はなんだったのか。
燈は呆れた表情で鬼谷を見た。「全然美人じゃない」
「もう12月も中盤か」
病室に設置された卓上カレンダーを見ながら燈は言った。
12月に入ってからというもの、一度倒れはしたが体調は比較的安定していた。それに合わせて食事の量もほんの少しだけ増えていて。身体も普段より動くようになっていた。今年もなんとか超える事は出来そうだ。
長く入院しているせいで、このまま治るのでは。とは思えなかったがそれでも体調が良いと気分も上がってくるもので、燈の方から鬼谷の病室に向かう回数も増えていた。
「ご馳走様でした」
食事を終わらした燈はテーブルを避けるとベッドから降りる。
カレンダーの横にある雑誌を取って病室を出た。
手に持ってるのはクロスワードをまとめた雑誌だった。この間見舞いに来た親が購買用の小遣いを渡してくれて、燈はその日の内に購買に出向き、雑誌を購入していた。
燈は別段パズルが得意なわけではない。
だが購買の中で鬼谷と二人で遊ぶのはこれぐらいしかなかった。いわば妥協品だ。それでも燈は鬼谷の病室に向かう間、ずっとわくわくとした気持ちを持っていた。
処置室の前まで来て燈は足を止める。
頭の中には鬼谷の事を聞いた記憶が戻ってきていた。
鬼谷も燈と同じで好調が続いているようで、あの日以降一度も病室が閉じられている事はなかった。だけど悪い記憶が足を引っ張り、処置室の近くを通るのに物怖じしてしまう。
処置室の扉を監視するように見つめながら通り過ぎようとすると、話し声が聞こえてくる。
医者が詰めている場所だったから話し声がするのは当たり前ではあったのだが、燈はどきりとした。
「……」
燈はその場に止まる。
距離が遠くて何を話しているのかは聞こえていなかったが、もしも悪い話だったらどうしようと気になって仕方がなかった。
このまま近づいて、聞き耳を立てようか。
そう思う気持ちと葛藤して、悩んだ末に燈はその場を離れた。
余計な事を聞いてまたしても体調を崩してしまったら、鬼谷と遊ぶことが出来なくなってしまう。その気持ちが好奇心に勝っていた。
鬼谷の病室につくと扉が開いていた。部屋の中から鬼谷と別の女性の声が聞こえてくる。どうやら問診か何かしているようだ。
燈は終わるまで待っていようと扉の脇に座り込んだ。
「特に変化は見当たらないってことね」
「えぇ。今のところは。寧ろ一番元気かも知れません」
「そう、それはよかったけど……覚悟だけはしといた方がいいかもね」
「……はい」
聞こえてくる会話に燈はその場に座り込んだことを後悔した。
覚悟。僕たちみたいな延命処置をされている人間にとっては死の宣告にも等しい言葉。それが彼女の病室から聞こえてきてしまった。
まさかと思った。気が付けば持ってきた雑誌を強く握り、クシャクシャにしてしまっていた。燈はその事にも気づかず。耳に神経を集中させる。
「治ることは、ないんですか……?」
鬼谷の声が聞こえる。
「……はっきり言うけど。今生きてる時点で奇跡に近いの。症状も肝機能が目立つだけで他は軽度で収まっているけど、MRIの数値はあまり良くないし人工透析の頻度も上がってきている。回復は難しいと思うわ」
「じゃあ……どのくらい、生きれるんですか?」
「わからないわ。さっきも言ったけど、生きてるのが奇跡に近い状態なの。明日急変するかも知れないし。もっと長く生きれるかもしれない。でも、数か月……春を超えることは難しいかも知れない」
「……」
「もちろん私たちも努力する。燈君を死なせはしないつもりよ。でも、やはり万一があるから、急に彼がいなくなったとしても、鬼谷さんには理解しておいて欲しいの」
「……」
鬼谷が黙り込み、辺りが静かになる。そんな事が気にならないくらいに僕の心はざわついていた。
彼女が話していたのは僕の話だ。春を待たずに僕が死ぬという話をしているんだ。
驚くくらいに頭がすっきりとしている。その癖心臓はバクバクと身体を突き抜けるぐらいに鼓動していた。
「ごめんなさい。辛い事を言ってしまって」
「……いえ」
看護師の足音が聞こえて燈は慌てて病室を離れた。
自分の部屋に戻るとすぐさまベッドに飛び込んで布団で体を覆い隠す。頭の中ではさっきのやり取りをずっと反芻していた。
僕は、もうすぐ、死ぬ?
体は今までにないくらい元気だし、食べる量だって増えている。それなのに死んでしまうって?
燈は信じる事ができなかった。鬼谷は僕の存在に気付いていて、意地悪してそんな会話をしているのだとすら思った。
だが違う。彼女はそんな悪質な意地悪なんてしない。看護師だってそんな事に賛同したりはしない。
つまり、僕は死ぬのだ。
いつかその日が来るとはわかっていたけど、とうとうその日がやってくるのだ。
だから看護師は、特別仲がいい彼女に伝えに来たのだ。僕につられて体調を崩さないように。
「う……ふっ……ぐぅ…………」
涙が溢れ出てきて止めることが出来ない。一緒に声も溢れそうだったけど、口に手を当てて必死に押し殺した。
このタイミングで僕が泣き叫んでいたら聞き耳を立てていたことを気付かれてしまうかもしれない。それで鬼谷が気を病んでしまったらと考えると、自然と嗚咽を抑え込んでいた。
時間が止まったような感覚の中、燈はずっと泣き続けていた。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


就職面接の感ドコロ!?
フルーツパフェ
大衆娯楽
今や十年前とは真逆の、売り手市場の就職活動。
学生達は賃金と休暇を貪欲に追い求め、いつ送られてくるかわからない採用辞退メールに怯えながら、それでも優秀な人材を発掘しようとしていた。
その業務ストレスのせいだろうか。
ある面接官は、女子学生達のリクルートスーツに興奮する性癖を備え、仕事のストレスから面接の現場を愉しむことに決めたのだった。

密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。
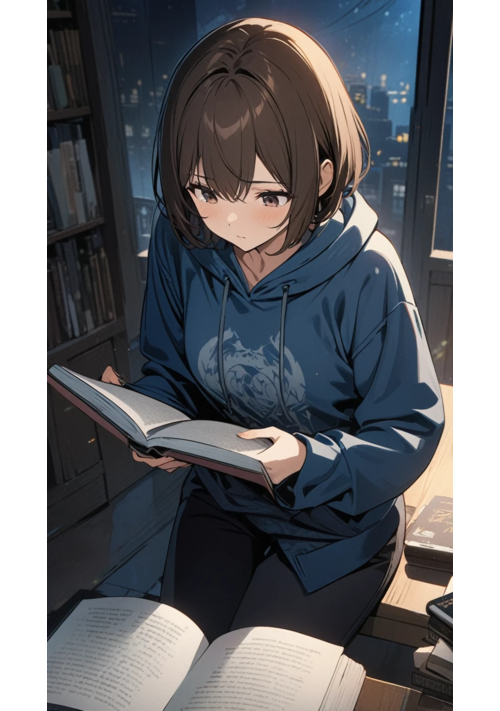
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

駒込の七不思議
中村音音(なかむらねおん)
ミステリー
地元のSNSで気になったこと・モノをエッセイふうに書いている。そんな流れの中で、駒込の七不思議を書いてみない? というご提案をいただいた。
7話で完結する駒込のミステリー。

双極の鏡
葉羽
ミステリー
神藤葉羽は、高校2年生にして天才的な頭脳を持つ少年。彼は推理小説を読み漁る日々を送っていたが、ある日、幼馴染の望月彩由美からの突然の依頼を受ける。彼女の友人が密室で発見された死体となり、周囲は不可解な状況に包まれていた。葉羽は、彼女の優しさに惹かれつつも、事件の真相を解明することに心血を注ぐ。
事件の背後には、視覚的な錯覚を利用した巧妙なトリックが隠されており、密室の真実を解き明かすために葉羽は思考を巡らせる。彼と彩由美の絆が深まる中、恐怖と謎が交錯する不気味な空間で、彼は人間の心の闇にも触れることになる。果たして、葉羽は真実を見抜くことができるのか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















