8 / 48
孤狼に愛の花束を (8)
しおりを挟む
必要に駆られて会話を交わす人間はいるけれど、人型に変化している状態でさえ、こちらへと深く踏み込んでこようとする存在はこれまで近くにはいなかった。きつい眼差しのせいなのか、言葉が少ないからなのかは分からない。いずれにせよ、俺が人との交流を望んでいないことが、態度に表れているのだろう。
人間なんかと特別親しくなりたいとも思っていない俺にとっては、当たり障りの無い会話ですら面倒に感じているから、寄って来られないというのはある意味有り難くもあった。
接点が無ければ、獣人だとばれるリスクも少なくなるし、何より煩わしくなくて良い。
父さんと母さんのように、一生を共に生きようと思える伴侶に出会いたいと思う気持ちがないわけではないけれど、一人で暮らすこの生活は気楽で、俺には性に合っているのだ。
守役などという職を甘んじて受けているのも、獣人界から振り込まれる手当てがあればこそ。そうでもなければ、他人の下に付いて使われるなんて勘弁願いたい。
そんなスタンスで生きてきた俺の前に、突然現れた小太郎という存在。あいつと過ごしたひと晩は、俺にとって不思議な時間だった。
「綺麗……か……」
変化を自己コントロール出来るようになって以来、人前で耳や尻尾を出したのは初めてのことだった。
両親から受け継いだ毛並みと毛色。
それは俺の自慢でもあり、同時に辛い記憶を思い出させるものだ。出来ることなら、あまり思い出したくは無い過去。
最初は余りに小太郎が脅えていたから、周囲に人間の気配が無いことを分かった上で見せた。
目を覚ました小太郎に強請られ再度半変化の状態を見せれば、その丸い瞳がキラキラと輝いた。心の底から言っているのだと伝わる賞賛の言葉に、気恥ずかしさすら感じた。
結局なぜ小太郎がこの森の中にいたのか、その理由は聞かず仕舞いだ。翌朝境界となっているトンネルまで連れて行ってやった俺に、小太郎は一方的な言葉を置いて帰っていったのだ。
「降る前に終わらせるか」
物珍しさからか、暇が出来るとついあの日のことを考えてしまう。休憩は終わりだと自分を律し、俺は再び斧へと手を伸ばした。
今の時期はまだ根雪になるほどではないけれど、冬の支度は早いに越したことは無い。
あの日小太郎に遭遇してしまったおかげで中途半端になっていた薪の準備。切り倒した樹木を、森の中で運び易い大きさに切り添えて家へと運ぶことが、このところの日課になっていた。
家まで運んでしまえば、多少雪が降ったところで薪割りくらいは出来る。積もり初めてしまってからでは、森から運び出すのも一苦労なだけに、天を睨みながらの作業が続いていた。
「アイツが背負ったら、立ち上がるのも苦労しそうだな」
背負い梯子に括れるだけの材木を積み、両手で持てる量を縛り上げた頃には、日暮れの早い山の冬空はオレンジに色付いていた。
背負った肩と腰に掛かる重さに、これよりも随分軽かった小太郎のことを思う。
「……寂しい、ね」
俺の話を聞いた小太郎は、それがまるで自分が置かれている状況かのように、泣き出しそうな顔をしていた。考えまいと思えば思うほど、なぜか思い出される小太郎の顔。
『でも……でも、そんなの寂しいよ! オレは寂しいと思うもん。誰かと支え合って、笑い合って生きるから、人生って素晴らしいんじゃないか!』
寂しくないのかと問われて、ほんの一瞬言葉に詰まった。
今の状況が寂しいのかと問われれば、本音では分からない。気楽な今の生活が気に入っているのだと返した俺に、小太郎は身を乗り出しながらそんな言葉を口にした。
自分でも気付かないようにしてきた感情を暴かれてしまったような気がして、大人気も無く苛付いた気持ちをそのまま返してしまった自分に、少しばかり後悔した。
『お前の価値観をオレに押し付けるな……』
告げた言葉は本心ではあったけれど、弱さを認めてしまうことへの恐れも含まれていたのかもしれないと、今になって思う。
「寂しい、か――」
足場の悪い森の中を、注意深くバランスを取りながら一歩一歩前に進みつつ、小太郎の言葉の意味へと思いを馳せる。
元来狼は仲間意識の強い動物だ。パートナーや家族のことは、命に掛けても守ろうとする。母が息も絶え絶えの状態でさえ、俺を逃がすために戻って来てくれたように。
徐々に冷たくなっていく母の体温を感じながら過ごした、爺さんに拾われるまでの時間。それは寂しさというよりも、怒りと心細さを感じさせられた時間だった。
もう二度と母の温もりも父の力強さも感じられないのだと悟ったあの時、俺は寂しいという感情を捨てた。母の亡骸と一緒に、爺さんの掘った穴の中へと埋めてきた。独りで生きていくためには、それは余計な感情だったからだ。
「支え合う関係だなんて……俺には関係ないことだな」
森を抜け出すまでもう少しというところで、取り止めの無い考えに終止符を打つ。これまで通りの生き方を変えるつもりなど無かったし、他人と馴れ合うことで自分が弱くなることがあっては堪らない。俺は独りで生きて行かなければならないのだから。
人の姿のまま、人間としてこの世界で生活している仲間はいるのだろう。幼い俺に対して父が言った 『 狼として生きる仲間はいない 』 という言葉は、裏を返せばそういうことなのだろうと、大人になった今だから分かる。
仲間に出会える可能性は残されているのかもしれないが、狼である事を捨てた連中と、共に生きて行きたいとは思えない。両親を殺した人間となんて論外だ。
「爺さんと同じように、独りで生きていくのも悪くは無いさ」
自分自身に言い聞かせるように呟きを漏らした時だった。
「銀さぁーんっ!」
「……あの声……小太郎?」
考え事をしながら歩いて来たせいなのか、欲張っていつもよりも多い量を抱え降りて来たせいなのか、その声を耳にするまで、気配がすることに気付かなかった。
既に境界線は越えているだけに、耳を出して確認することは出来ないけれど、人型の今の状態でもはっきりと聞こえた小太郎の声。くんと鼻を鳴らせば、家の前にいるらしい小太郎の匂いも嗅ぎ取れた。そして、小太郎の他にも誰か……違う匂いが交じっているのを感じ取る。
「……誰だ?」
思わず溜息が出てしまう。まさか本当に会いに来るなんて、思ってもいなかった。それも、誰だか知らない、他のヤツまで連れて来るなんて。
面倒に思いながらも帰らないわけにはいかない。さすがに向こうも俺の匂いに気付いたからこそ、大声を上げたのだろう。
背負った木の重さに輪を掛けて、重い物が圧し掛かって来た気がする。
「銀さぁーん! 銀さ……あっ、銀さんっ!」
「そんなに大声を出さなくても聞こえる」
足を止めることなく歩を進め、家が見える位置まで来たところで、向こうからも俺の姿が確認できたらしい。大声を上げていた小太郎が、俺に向かって一直線に駆けて来る。
今日は耳も尻尾も見えないけれど、出した状態であるなら、尻尾は多分振り千切れそうなほど揺れているのだろうと想像が付く。
「銀さんっ」
「……体調は良いのか?」
「うん、もうすっかり!」
キラキラと輝く瞳で俺を見つめる小太郎に構うこと無く、抱えた荷を降ろすべく家の裏へと向かう。途中、玄関前に立つスラリとした男の視線を感じた。探るようなその眼差しに、少しばかり苛立つ。
「こんなにいっぱい、重くないの?」
「軽くは無いがな――」
「すっげえ、俺には絶対無理だ。これ、何に使うの? ってか、これ何?」
無愛想な態度に怯みもせずに、小太郎がパタパタと後を付いてくる。
雨避けのためにと窯のある場所には屋根を付けてある。窯横のスペースには、切り出して来た木を積み重ねる場所も新たに作った。この場所にあれば、いちいち木を取りに行く手間も省ける。持ち帰ってきた木をその側に下ろせば、小太郎が興味深そうに辺りを見回す。
「窯だ……焼物に使う」
「銀さん陶芸するの? うっわぁ、マジすげえ」
「で、お前は何をしに来たんだ?」
素直な賞賛の言葉に、背中がむず痒くなる。
同時に感じた男の気配に、神経だけはそちらに集中させた。
俺と小太郎が戻ってこないことに焦れて、様子を窺いに来たのだろう。
「あっ、そうだった」
「……御礼を言いに来た」
「礼?」
「ゴローちゃんっ」
俺の問いに当初の目的を思い出したと苦笑するコタの声に被せるように、近付いて来た男から言葉が発せられた。
人間なんかと特別親しくなりたいとも思っていない俺にとっては、当たり障りの無い会話ですら面倒に感じているから、寄って来られないというのはある意味有り難くもあった。
接点が無ければ、獣人だとばれるリスクも少なくなるし、何より煩わしくなくて良い。
父さんと母さんのように、一生を共に生きようと思える伴侶に出会いたいと思う気持ちがないわけではないけれど、一人で暮らすこの生活は気楽で、俺には性に合っているのだ。
守役などという職を甘んじて受けているのも、獣人界から振り込まれる手当てがあればこそ。そうでもなければ、他人の下に付いて使われるなんて勘弁願いたい。
そんなスタンスで生きてきた俺の前に、突然現れた小太郎という存在。あいつと過ごしたひと晩は、俺にとって不思議な時間だった。
「綺麗……か……」
変化を自己コントロール出来るようになって以来、人前で耳や尻尾を出したのは初めてのことだった。
両親から受け継いだ毛並みと毛色。
それは俺の自慢でもあり、同時に辛い記憶を思い出させるものだ。出来ることなら、あまり思い出したくは無い過去。
最初は余りに小太郎が脅えていたから、周囲に人間の気配が無いことを分かった上で見せた。
目を覚ました小太郎に強請られ再度半変化の状態を見せれば、その丸い瞳がキラキラと輝いた。心の底から言っているのだと伝わる賞賛の言葉に、気恥ずかしさすら感じた。
結局なぜ小太郎がこの森の中にいたのか、その理由は聞かず仕舞いだ。翌朝境界となっているトンネルまで連れて行ってやった俺に、小太郎は一方的な言葉を置いて帰っていったのだ。
「降る前に終わらせるか」
物珍しさからか、暇が出来るとついあの日のことを考えてしまう。休憩は終わりだと自分を律し、俺は再び斧へと手を伸ばした。
今の時期はまだ根雪になるほどではないけれど、冬の支度は早いに越したことは無い。
あの日小太郎に遭遇してしまったおかげで中途半端になっていた薪の準備。切り倒した樹木を、森の中で運び易い大きさに切り添えて家へと運ぶことが、このところの日課になっていた。
家まで運んでしまえば、多少雪が降ったところで薪割りくらいは出来る。積もり初めてしまってからでは、森から運び出すのも一苦労なだけに、天を睨みながらの作業が続いていた。
「アイツが背負ったら、立ち上がるのも苦労しそうだな」
背負い梯子に括れるだけの材木を積み、両手で持てる量を縛り上げた頃には、日暮れの早い山の冬空はオレンジに色付いていた。
背負った肩と腰に掛かる重さに、これよりも随分軽かった小太郎のことを思う。
「……寂しい、ね」
俺の話を聞いた小太郎は、それがまるで自分が置かれている状況かのように、泣き出しそうな顔をしていた。考えまいと思えば思うほど、なぜか思い出される小太郎の顔。
『でも……でも、そんなの寂しいよ! オレは寂しいと思うもん。誰かと支え合って、笑い合って生きるから、人生って素晴らしいんじゃないか!』
寂しくないのかと問われて、ほんの一瞬言葉に詰まった。
今の状況が寂しいのかと問われれば、本音では分からない。気楽な今の生活が気に入っているのだと返した俺に、小太郎は身を乗り出しながらそんな言葉を口にした。
自分でも気付かないようにしてきた感情を暴かれてしまったような気がして、大人気も無く苛付いた気持ちをそのまま返してしまった自分に、少しばかり後悔した。
『お前の価値観をオレに押し付けるな……』
告げた言葉は本心ではあったけれど、弱さを認めてしまうことへの恐れも含まれていたのかもしれないと、今になって思う。
「寂しい、か――」
足場の悪い森の中を、注意深くバランスを取りながら一歩一歩前に進みつつ、小太郎の言葉の意味へと思いを馳せる。
元来狼は仲間意識の強い動物だ。パートナーや家族のことは、命に掛けても守ろうとする。母が息も絶え絶えの状態でさえ、俺を逃がすために戻って来てくれたように。
徐々に冷たくなっていく母の体温を感じながら過ごした、爺さんに拾われるまでの時間。それは寂しさというよりも、怒りと心細さを感じさせられた時間だった。
もう二度と母の温もりも父の力強さも感じられないのだと悟ったあの時、俺は寂しいという感情を捨てた。母の亡骸と一緒に、爺さんの掘った穴の中へと埋めてきた。独りで生きていくためには、それは余計な感情だったからだ。
「支え合う関係だなんて……俺には関係ないことだな」
森を抜け出すまでもう少しというところで、取り止めの無い考えに終止符を打つ。これまで通りの生き方を変えるつもりなど無かったし、他人と馴れ合うことで自分が弱くなることがあっては堪らない。俺は独りで生きて行かなければならないのだから。
人の姿のまま、人間としてこの世界で生活している仲間はいるのだろう。幼い俺に対して父が言った 『 狼として生きる仲間はいない 』 という言葉は、裏を返せばそういうことなのだろうと、大人になった今だから分かる。
仲間に出会える可能性は残されているのかもしれないが、狼である事を捨てた連中と、共に生きて行きたいとは思えない。両親を殺した人間となんて論外だ。
「爺さんと同じように、独りで生きていくのも悪くは無いさ」
自分自身に言い聞かせるように呟きを漏らした時だった。
「銀さぁーんっ!」
「……あの声……小太郎?」
考え事をしながら歩いて来たせいなのか、欲張っていつもよりも多い量を抱え降りて来たせいなのか、その声を耳にするまで、気配がすることに気付かなかった。
既に境界線は越えているだけに、耳を出して確認することは出来ないけれど、人型の今の状態でもはっきりと聞こえた小太郎の声。くんと鼻を鳴らせば、家の前にいるらしい小太郎の匂いも嗅ぎ取れた。そして、小太郎の他にも誰か……違う匂いが交じっているのを感じ取る。
「……誰だ?」
思わず溜息が出てしまう。まさか本当に会いに来るなんて、思ってもいなかった。それも、誰だか知らない、他のヤツまで連れて来るなんて。
面倒に思いながらも帰らないわけにはいかない。さすがに向こうも俺の匂いに気付いたからこそ、大声を上げたのだろう。
背負った木の重さに輪を掛けて、重い物が圧し掛かって来た気がする。
「銀さぁーん! 銀さ……あっ、銀さんっ!」
「そんなに大声を出さなくても聞こえる」
足を止めることなく歩を進め、家が見える位置まで来たところで、向こうからも俺の姿が確認できたらしい。大声を上げていた小太郎が、俺に向かって一直線に駆けて来る。
今日は耳も尻尾も見えないけれど、出した状態であるなら、尻尾は多分振り千切れそうなほど揺れているのだろうと想像が付く。
「銀さんっ」
「……体調は良いのか?」
「うん、もうすっかり!」
キラキラと輝く瞳で俺を見つめる小太郎に構うこと無く、抱えた荷を降ろすべく家の裏へと向かう。途中、玄関前に立つスラリとした男の視線を感じた。探るようなその眼差しに、少しばかり苛立つ。
「こんなにいっぱい、重くないの?」
「軽くは無いがな――」
「すっげえ、俺には絶対無理だ。これ、何に使うの? ってか、これ何?」
無愛想な態度に怯みもせずに、小太郎がパタパタと後を付いてくる。
雨避けのためにと窯のある場所には屋根を付けてある。窯横のスペースには、切り出して来た木を積み重ねる場所も新たに作った。この場所にあれば、いちいち木を取りに行く手間も省ける。持ち帰ってきた木をその側に下ろせば、小太郎が興味深そうに辺りを見回す。
「窯だ……焼物に使う」
「銀さん陶芸するの? うっわぁ、マジすげえ」
「で、お前は何をしに来たんだ?」
素直な賞賛の言葉に、背中がむず痒くなる。
同時に感じた男の気配に、神経だけはそちらに集中させた。
俺と小太郎が戻ってこないことに焦れて、様子を窺いに来たのだろう。
「あっ、そうだった」
「……御礼を言いに来た」
「礼?」
「ゴローちゃんっ」
俺の問いに当初の目的を思い出したと苦笑するコタの声に被せるように、近付いて来た男から言葉が発せられた。
0
お気に入りに追加
49
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

肌が白くて女の子みたいに綺麗な先輩。本当におしっこするのか気になり過ぎて…?
こじらせた処女
BL
槍本シュン(やりもとしゅん)の所属している部活、機器操作部は2つ上の先輩、白井瑞稀(しらいみずき)しか居ない。
自分より身長の高い大男のはずなのに、足の先まで綺麗な先輩。彼が近くに来ると、何故か落ち着かない槍本は、これが何なのか分からないでいた。
ある日の冬、大雪で帰れなくなった槍本は、一人暮らしをしている白井の家に泊まることになる。帰り道、おしっこしたいと呟く白井に、本当にトイレするのかと何故か疑問に思ってしまい…?




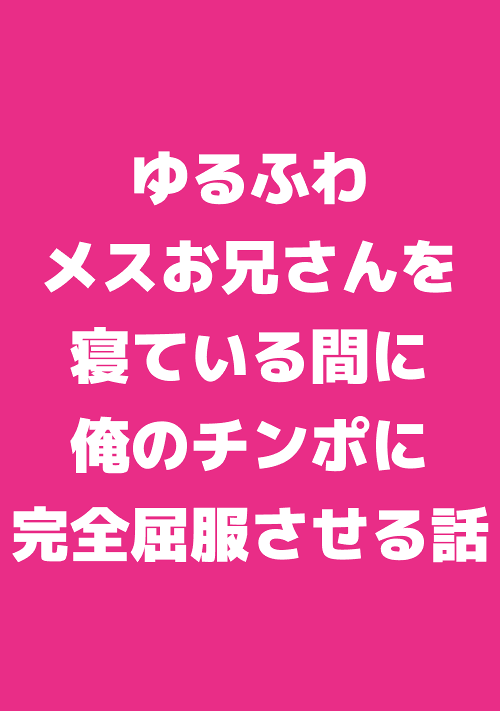
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















