4 / 7
PKゲーム
4 怖いです
しおりを挟む
何か物音が聞こえた。
うっすら目を開けると、例によって、森江がシンクの前に立っていた。
(今、何時なんだろう)
この事務所に窓はなかったが、壁に掛けられた円形のアナログ時計は、八時ちょっと前を指していた。
「……おはようございます……」
まだ半分寝ぼけながら森江に挨拶すると、森江は大仰なくらい驚いて彼を振り返った。
「もう起きたのか?」
「起きてもいい時間だと思いますが……」
「もしかして、音で起こしちまったか?」
森江は少しすまなそうに言って、また昨日と同じように、ミルク・砂糖・スプーンつきのインスタントコーヒーを差し出してきた。
「音で目が覚めたということは、それだけ眠りが浅くなっていたということだと思うので……」
だから森江は悪くないのだと遠回しに答えてから、今日はミルクと砂糖を入れてコーヒーを飲んだ。
「今、うちにろくなもんなくてな。目玉焼きとトーストでいいか?」
「いいです」
「じゃあ、その間に顔洗ってこい。……ジーンズは穿いていけよ」
「はあ……」
森江に言われるまま、彼は紙袋に入れたままだったジーンズを穿き――確かに、スーツとバスタオルは消えていた――寝起きと筋肉痛で重い体を引きずるようにしてユニットバスへと向かった。
洗面台で顔を洗うとき、鏡の中の自分の顔をしみじみと眺めてみたが、やはり自分のものだという実感はまったく持てなかった。
事務所に戻ってくると、森江が言っていた朝食の用意はほぼ完了していた。超簡単メニューとはいえ、手早いことは確かだ。
「目玉焼きにかけるのは、醤油・ケチャップ・ソース・その他、どれがいい?」
「その他って何ですか?」
「マヨネーズ・からし・わさび……」
「マヨネーズでお願いします」
「マヨラーか」
記憶がないので、その質問には答えられなかったが、彼はマーガリンを塗ったトーストに目玉焼きを載せて、そこにマヨネーズをたっぷりかけて食べた。何だか妙にうまく感じた。
森江はというと、調味料はいっさい使わず、トーストに目玉焼きを載せてそのまま食べていた。プレーン派らしい。
「九時におまえの家族がここに来る。それまでに身支度を済ませておけ」
「身支度……」
「とりあえず、その免許証をポケットに入れればいい。俺が預かってたおまえのものはそれだけだ」
「これだけでよく……」
「仕事だからな」
「あ、洗い物は俺がします」
「記憶喪失なのにできるのか?」
「それくらいの記憶はあります」
実際、自炊もしていたのか、彼はスムーズに仕事をこなして、再びソファに戻った。
「おっと。そのソファも元に戻しておかないとな」
「手伝います」
二人がかりですると、ソファベッドはあっというまに元のソファに戻ってしまった。ふと掛時計を見上げれば、時刻はもう八時五十分になっている。
(まだ、ここにいたいな)
彼がそう思った瞬間、まるでそれを見透かしたように呼び鈴が鳴った。森江は壁に設置されたインターホンのところに行ってしばらく話した後、彼に向き直って言った。
「お迎えだ」
予想はついていたが、実際そう言われると、嬉しいというより寂しい気がした。
ほどなく、タッチ式の自動ドアの向こうから現れたのは、青年実業家風の男とその秘書風の男の二人連れだった。家族というから、てっきり両親を想像していたのだが、青年実業家のほうは森江と同年代くらいである。自分の父親にはとても見えなかったし、見覚えもなかった。
「弟さんは、昨日のある時点以前のことは、いっさい思い出せなくなっています。おそらく、記憶操作をされたのでしょうが、どのような方法を用いたのかは、自分にはわかりません。専門の方に診てもらってください」
森江は彼に対するよりは愛想よく、青年実業家風の男に言った。
(俺が弟ということは、この人が兄なんだ……)
まったく実感が湧かない。そう言われてみれば何となく、自分と顔立ちが似ているような気がしないでもないが、彼はこの男を見た瞬間、親しさや懐かしさよりも近寄りがたさを感じて、森江のいるソファのほうへと避難していた。
「記憶喪失か……どこが専門だろうな」
兄という男が淡々と言った。きっと自分はこの兄と不仲だったに違いない。どう見ても、自分の無事を喜んでいるようには思えなかった。
「とにかく、よく連れ戻してきてくれた。これが残金だ。確認してくれ」
兄の声を合図に、秘書風の男が手に提げていたアタッシュケースをテーブルの上に置き、よどみなくケースを開いた。ケースの中には、札束が隙間なく詰めこまれていた。
「じゃあ、遠慮なく確認させていただきます。あ、どうぞおかけになってお待ちください」
「いや、このままでいい」
(失礼な奴だな)
最初から兄に好印象を抱いていなかった彼は、ソファに座って丁寧かつ迅速に札束を確認している森江の隣に、自分も腰を下ろした。
(記憶が戻るまで、ここにいたいな……)
彼は再びそう思ったが、そのとき森江が札束を確認しおえて、満足の笑みを浮かべた。
「確かに、すべて本物でお約束どおりの金額ですね。ではどうぞ、弟さんをお連れください」
「手数をかけた」
感情のこもらない声で兄は言い、初めてまともに彼を見た。
その瞬間、彼は怖くなって森江の腕をつかんだ。
「何だ、どうした?」
森江も驚いていたが、兄やその秘書(勝手に断定)も彼の行動に驚いていた。
「あー……記憶喪失だから不安なんでしょう」
ばつが悪そうに兄たちにそう言ってから、森江は小声で彼の耳許に囁いた。
「おい……何がそんなに怖い?」
――この男は、ちゃんとわかってくれている。
彼は安堵と歓喜から、いよいよ森江にしがみついた。
「ずいぶん懐かれたものだな」
兄の声は相変わらず平坦だったが、わずかに嫉妬の響きがあった。
「記憶喪失ですから」
森江はまた同じことを繰り返し、彼の手を二、三度軽く叩いた。
「もう大丈夫だから。早くうちに帰れ」
彼は無我夢中で首を横に振り、しまいに森江の腕に顔を押しつけた。
「えーと……」
さすがに森江も言葉を失っていたが、いきなり彼を引っ張り上げるようにして、ソファから立ち上がった。
「車でここに来られたんでしょう? 駐車場までこのまま連れていきます」
「嫌です!」
初めて彼は自分の感情を声に出した。
「俺はここにいたいです! もうどこにも行きたくありません! ……怖いです」
「怖いって……」
「怖いです……」
彼は自分の兄と秘書を真正面から見て言った。
「怖くて仕方がないんです……」
「明様……」
秘書が何事か言いかけたが、兄はそれを片手で制した。
「これほど怯えているものを、無理に連れ帰っても悪化させるだけだろう。……森江さん。申し訳ないが、しばらくこいつを預かっててもらえないか。その分の諸経費は、そちらの請求どおり支払う」
「ええっ!?」
秘書だけでなく、森江も驚愕の叫びを上げて兄を見た。
「記憶は戻らないだろうが、精神的には安定するだろう。……木村、帰るぞ」
「え? え?」
秘書――木村というらしい――は、兄と彼とを交互に見たが、結局、森江に一礼して、兄の後を追って出ていった。
「……俺の返事は聞かないのか……」
しばらくして、森江が独りごちた。彼は彼で、自分の要求がすんなり通ったことに戸惑っていた。自分を嫌っているから連れ帰ろうとしなかったのか。それとも、本当に自分の精神状態を慮ってのことなのか。彼にはよくわからなかった。
「怖い怖いって……何がそんなに怖いんだ?」
ようやくあきらめがついたのか、森江は溜め息をついて彼を見やった。
「……あの人、本当に俺の兄なんですか? あなたより他人な気がします……」
「重度だな」
森江は呆れたように言ったが、苦笑いして彼の頭を撫でた。
「まあ、怖いものは仕方ない。とりあえず、金庫に金を入れるのを手伝え。このままじゃコーヒーも飲めない」
うっすら目を開けると、例によって、森江がシンクの前に立っていた。
(今、何時なんだろう)
この事務所に窓はなかったが、壁に掛けられた円形のアナログ時計は、八時ちょっと前を指していた。
「……おはようございます……」
まだ半分寝ぼけながら森江に挨拶すると、森江は大仰なくらい驚いて彼を振り返った。
「もう起きたのか?」
「起きてもいい時間だと思いますが……」
「もしかして、音で起こしちまったか?」
森江は少しすまなそうに言って、また昨日と同じように、ミルク・砂糖・スプーンつきのインスタントコーヒーを差し出してきた。
「音で目が覚めたということは、それだけ眠りが浅くなっていたということだと思うので……」
だから森江は悪くないのだと遠回しに答えてから、今日はミルクと砂糖を入れてコーヒーを飲んだ。
「今、うちにろくなもんなくてな。目玉焼きとトーストでいいか?」
「いいです」
「じゃあ、その間に顔洗ってこい。……ジーンズは穿いていけよ」
「はあ……」
森江に言われるまま、彼は紙袋に入れたままだったジーンズを穿き――確かに、スーツとバスタオルは消えていた――寝起きと筋肉痛で重い体を引きずるようにしてユニットバスへと向かった。
洗面台で顔を洗うとき、鏡の中の自分の顔をしみじみと眺めてみたが、やはり自分のものだという実感はまったく持てなかった。
事務所に戻ってくると、森江が言っていた朝食の用意はほぼ完了していた。超簡単メニューとはいえ、手早いことは確かだ。
「目玉焼きにかけるのは、醤油・ケチャップ・ソース・その他、どれがいい?」
「その他って何ですか?」
「マヨネーズ・からし・わさび……」
「マヨネーズでお願いします」
「マヨラーか」
記憶がないので、その質問には答えられなかったが、彼はマーガリンを塗ったトーストに目玉焼きを載せて、そこにマヨネーズをたっぷりかけて食べた。何だか妙にうまく感じた。
森江はというと、調味料はいっさい使わず、トーストに目玉焼きを載せてそのまま食べていた。プレーン派らしい。
「九時におまえの家族がここに来る。それまでに身支度を済ませておけ」
「身支度……」
「とりあえず、その免許証をポケットに入れればいい。俺が預かってたおまえのものはそれだけだ」
「これだけでよく……」
「仕事だからな」
「あ、洗い物は俺がします」
「記憶喪失なのにできるのか?」
「それくらいの記憶はあります」
実際、自炊もしていたのか、彼はスムーズに仕事をこなして、再びソファに戻った。
「おっと。そのソファも元に戻しておかないとな」
「手伝います」
二人がかりですると、ソファベッドはあっというまに元のソファに戻ってしまった。ふと掛時計を見上げれば、時刻はもう八時五十分になっている。
(まだ、ここにいたいな)
彼がそう思った瞬間、まるでそれを見透かしたように呼び鈴が鳴った。森江は壁に設置されたインターホンのところに行ってしばらく話した後、彼に向き直って言った。
「お迎えだ」
予想はついていたが、実際そう言われると、嬉しいというより寂しい気がした。
ほどなく、タッチ式の自動ドアの向こうから現れたのは、青年実業家風の男とその秘書風の男の二人連れだった。家族というから、てっきり両親を想像していたのだが、青年実業家のほうは森江と同年代くらいである。自分の父親にはとても見えなかったし、見覚えもなかった。
「弟さんは、昨日のある時点以前のことは、いっさい思い出せなくなっています。おそらく、記憶操作をされたのでしょうが、どのような方法を用いたのかは、自分にはわかりません。専門の方に診てもらってください」
森江は彼に対するよりは愛想よく、青年実業家風の男に言った。
(俺が弟ということは、この人が兄なんだ……)
まったく実感が湧かない。そう言われてみれば何となく、自分と顔立ちが似ているような気がしないでもないが、彼はこの男を見た瞬間、親しさや懐かしさよりも近寄りがたさを感じて、森江のいるソファのほうへと避難していた。
「記憶喪失か……どこが専門だろうな」
兄という男が淡々と言った。きっと自分はこの兄と不仲だったに違いない。どう見ても、自分の無事を喜んでいるようには思えなかった。
「とにかく、よく連れ戻してきてくれた。これが残金だ。確認してくれ」
兄の声を合図に、秘書風の男が手に提げていたアタッシュケースをテーブルの上に置き、よどみなくケースを開いた。ケースの中には、札束が隙間なく詰めこまれていた。
「じゃあ、遠慮なく確認させていただきます。あ、どうぞおかけになってお待ちください」
「いや、このままでいい」
(失礼な奴だな)
最初から兄に好印象を抱いていなかった彼は、ソファに座って丁寧かつ迅速に札束を確認している森江の隣に、自分も腰を下ろした。
(記憶が戻るまで、ここにいたいな……)
彼は再びそう思ったが、そのとき森江が札束を確認しおえて、満足の笑みを浮かべた。
「確かに、すべて本物でお約束どおりの金額ですね。ではどうぞ、弟さんをお連れください」
「手数をかけた」
感情のこもらない声で兄は言い、初めてまともに彼を見た。
その瞬間、彼は怖くなって森江の腕をつかんだ。
「何だ、どうした?」
森江も驚いていたが、兄やその秘書(勝手に断定)も彼の行動に驚いていた。
「あー……記憶喪失だから不安なんでしょう」
ばつが悪そうに兄たちにそう言ってから、森江は小声で彼の耳許に囁いた。
「おい……何がそんなに怖い?」
――この男は、ちゃんとわかってくれている。
彼は安堵と歓喜から、いよいよ森江にしがみついた。
「ずいぶん懐かれたものだな」
兄の声は相変わらず平坦だったが、わずかに嫉妬の響きがあった。
「記憶喪失ですから」
森江はまた同じことを繰り返し、彼の手を二、三度軽く叩いた。
「もう大丈夫だから。早くうちに帰れ」
彼は無我夢中で首を横に振り、しまいに森江の腕に顔を押しつけた。
「えーと……」
さすがに森江も言葉を失っていたが、いきなり彼を引っ張り上げるようにして、ソファから立ち上がった。
「車でここに来られたんでしょう? 駐車場までこのまま連れていきます」
「嫌です!」
初めて彼は自分の感情を声に出した。
「俺はここにいたいです! もうどこにも行きたくありません! ……怖いです」
「怖いって……」
「怖いです……」
彼は自分の兄と秘書を真正面から見て言った。
「怖くて仕方がないんです……」
「明様……」
秘書が何事か言いかけたが、兄はそれを片手で制した。
「これほど怯えているものを、無理に連れ帰っても悪化させるだけだろう。……森江さん。申し訳ないが、しばらくこいつを預かっててもらえないか。その分の諸経費は、そちらの請求どおり支払う」
「ええっ!?」
秘書だけでなく、森江も驚愕の叫びを上げて兄を見た。
「記憶は戻らないだろうが、精神的には安定するだろう。……木村、帰るぞ」
「え? え?」
秘書――木村というらしい――は、兄と彼とを交互に見たが、結局、森江に一礼して、兄の後を追って出ていった。
「……俺の返事は聞かないのか……」
しばらくして、森江が独りごちた。彼は彼で、自分の要求がすんなり通ったことに戸惑っていた。自分を嫌っているから連れ帰ろうとしなかったのか。それとも、本当に自分の精神状態を慮ってのことなのか。彼にはよくわからなかった。
「怖い怖いって……何がそんなに怖いんだ?」
ようやくあきらめがついたのか、森江は溜め息をついて彼を見やった。
「……あの人、本当に俺の兄なんですか? あなたより他人な気がします……」
「重度だな」
森江は呆れたように言ったが、苦笑いして彼の頭を撫でた。
「まあ、怖いものは仕方ない。とりあえず、金庫に金を入れるのを手伝え。このままじゃコーヒーも飲めない」
0
お気に入りに追加
19
あなたにおすすめの小説

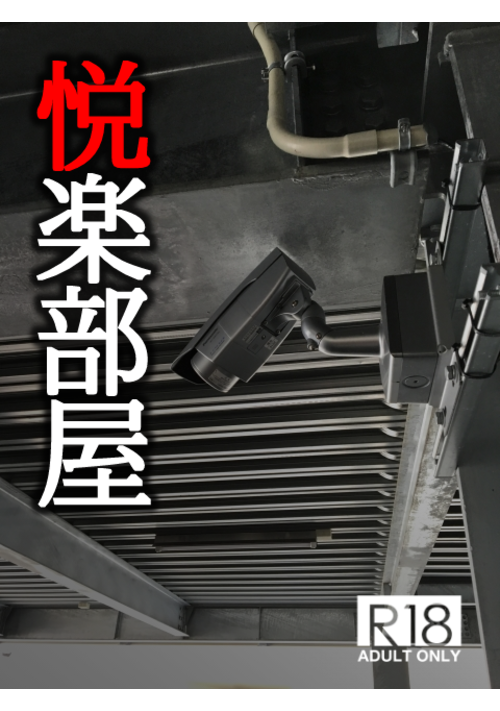
【完結】悦楽部屋【R18】
有喜多亜里
BL
【R18】『君のために、新しく部屋を作ったんだ』。宇宙船の人工知能によって改造された工作室で、人工の手やアレで犯された彼は、そのことを屈辱に思いつつも、その受け身の快楽が忘れられず、その部屋で寝るようになる。しかし、彼らには彼らの知らない秘密があった。

専業種夫
カタナカナタ
BL
精力旺盛な彼氏の性処理を完璧にこなす「専業種夫」。彼の徹底された性行為のおかげで、彼氏は外ではハイクラスに働き、帰宅するとまた彼を激しく犯す。そんなゲイカップルの日々のルーティーンを描く。


【完結】シャングリラ【R18】
有喜多亜里
BL
【R18】気がつくと、彼は全裸の男と共に、出入口のないトイレの個室の中にいた。彼は男に強姦されるが、そのとき男同士のセックスの快楽を知り、すっかり溺れこんでしまう。だが、強烈な眠気に襲われた彼に、男は時間切れだと宣告した――

肌が白くて女の子みたいに綺麗な先輩。本当におしっこするのか気になり過ぎて…?
こじらせた処女
BL
槍本シュン(やりもとしゅん)の所属している部活、機器操作部は2つ上の先輩、白井瑞稀(しらいみずき)しか居ない。
自分より身長の高い大男のはずなのに、足の先まで綺麗な先輩。彼が近くに来ると、何故か落ち着かない槍本は、これが何なのか分からないでいた。
ある日の冬、大雪で帰れなくなった槍本は、一人暮らしをしている白井の家に泊まることになる。帰り道、おしっこしたいと呟く白井に、本当にトイレするのかと何故か疑問に思ってしまい…?

生贄として捧げられたら人外にぐちゃぐちゃにされた
キルキ
BL
生贄になった主人公が、正体不明の何かにめちゃくちゃにされ挙げ句、いっぱい愛してもらう話。こんなタイトルですがハピエンです。
人外✕人間
♡喘ぎな分、いつもより過激です。
以下注意
♡喘ぎ/淫語/直腸責め/快楽墜ち/輪姦/異種姦/複数プレイ/フェラ/二輪挿し/無理矢理要素あり
2024/01/31追記
本作品はキルキのオリジナル小説です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















