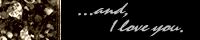30 / 64
第一章
嘘と真実 8
しおりを挟む伯爵家であるクラウディ家が名を馳せるようになったのは、二代前の事である。
それまでは貴族といいながらも、領地を持つ身でもなく、貴族院に所属するわけでもなく、王国の民の四分の一である貴族の中でも目立たない部類の家であった。
領地を与えられた貴族は管理する領民からの税金で、その手腕によっては贅の限りを尽くしたし、貴族院に所属する家系であれば国の政に携わる名誉もあった。しかし貴族の半分はそのどちらでも無い。何百年もの間に膨れた貴族の半分は昔取った杵柄に縋るか、職を持つかのどちらかだった。
それ故貴族という家名だけは誇れても、実情は少し裕福な民衆とさして変わらない者がほとんどだ。
クラウディ家もまた職持つ家系だった。始めは画商であった。まだ名の売れぬな絵描きの絵を本人から安く仕入れて何倍かで捌いていた程度のそれが軌道に乗ると、その商いは国内だけに留まらず諸外国にも広がり、やがては王族すら相手にする商家となった。その際の独自のルートが二代前にグランディア王家の目に留まり、外交官としての身分を与えられ貴族院に名を連ねるに至った。
その二代の間に貴族院の中でも確固たる地位を得た今、貴族社会に置いては無視できない権力を持って君臨している。
現当主バルバトス・クラウディは、その地位を野心持って高めようとしており、長兄であるガリオン・クラウディは有能な外交官として父の野心を手伝っていた。
クラウディ家の外交能力はグランディア王国にとって助かるものに違いなかったが、バルバトスの思惑を思えば些か、度が過ぎた。
エディアルド・アラクシス=グランディア・リカルド二世にとっては、意見の対立しがちな相手として厄介に感じられていた。
――果たしてそんなクラウディ家の次男として、誰をも羨む一族に連なる者として、ルークは生まれた。
長兄ガリオン、三男バルツァーとは腹違いのルークはクラウディ家の中では腫物の扱いではあったが、母親の美貌を受継いだ次男をバルバトスは溺愛しており、随分な自由を与えている。
その結果、享楽に溺れるのである。
成人して社交界に姿を現してすぐに、その名と共に、彼の豪遊振りが話題になった。
賭け事、酒、女だけに限らず、朝な夕、遊び呆けているという噂は真実以外の何物でもなく、かといってそれがクラウディ家やルークの名を貶めたかといえば、そんな事は一切なかった。
美貌以上にクラウディ家の外交感覚を受継いでいたルークは、人付き合いに置いて、欠点がなかった。
巧みな話術、気遣い、微笑み――それらは老若男女違わず、誰にとっても好感を持たせた。
彼のそれの十分の一でも、リカルド二世陛下にあれば良いのにと言われるぐらいのものである。
クラウディ家にとってルークは汚点では無く、家名を売る道具であり裕福さの象徴だった。
それ故の自由を謳歌しながら、ルーク・クラウディは二十歳になった。
ルークがティシア・アラクシス=グランディアを目にしたのは、そんな折だった。
まだ社交界のデビューには至らない十四歳の王女殿下。
その兄リカルド二世を思えば、花のように愛らしく天使のように清らかだといわれる彼女の美貌が噂だけのものではないと想像出来る事だったが、実際に目にするまで、ルークにとってそれは関係のない事だった。
どんなに美しく可憐であっても、冷血と恐れられる国王陛下の妹王女である。そして今まで公の場に出る事のほとんどない、国王陛下が目に入れても痛くない程に可愛がり(あくまでも冗談として噂されていた)王城の奥に隠してきた王女殿下である。
放蕩者の自覚があるルークは、兄王にも王女にも近づきたくはなかった。
遊び相手に選ぶには、面倒すぎる相手だ。
そう思い続けていたのに、ティシアを目にしたルークが抱いたのは、初めての感情だった。
それを一目惚れと呼ぶ事を、その時のルークは知らない。
程なくして父親から
「王女殿下とお近づきになりなさい」
と命じられた時、バルバトスの野心など知らないルークは、奇妙に高揚した己の胸中を持て余していただけだった。
バルバトス同様貴族院の多くがリカルド二世を快く感じて居ない事は知っていたが、まさか自分を足がかりに王女殿下を手駒にしよう等と考えているとはとても思っていなかったのだ。
自分の魅力が彼女にも通用するとは思えなかった。彼女の魅力の前には、自分はちっぽけでしかなく、まさか王女が自分に好意を持ってくれるなどと、傲慢にはなれなかった。
惹かれるままに時を過ごし、後戻りの出来ない恋心を自覚した時、ルークはそれを愛と呼んだ。
そして自分の今までの行いを恥じ、この後は清廉な自分に生まれ変わろうと決めた。
――ルークがバルバトスとリカルド二世の思惑に気付いたのは、それより後の事である。
「王女殿下のご婚約に関して、陛下はどのようにお考えか」
そのような事を貴族院に注進されたのは、ある日の議会の事だった。
緊張した面持ちの男を前に、言葉少ななそれだけで、リカルド二世は多くを理解した。
男の背後でバルバトス・クラウディが密かに笑ったのを見逃さなかった。
「どう、とは」
「あと二年で成人される王女殿下におかれては、まだご婚約もされておいでにならない。……つまり、王家の血筋に関しましては」
その後を言い淀む貴族院に、元老院が俄かに沸いた。王家アラクシスの血族は何もリカルド二世とティシアだけで絶えるものではない。叔父にあたるゲオルグ・アラクシスにも三人の息子がおり、王位を継げる存在は数多ある。何よりリカルド二世自体がまだ若く、病一つない健康体であるから、これから幾度でも子は望めよう。
リカルド二世の孕んだ怒気に気圧されたのか口を噤んだ男の代わりに、バルバトスが続きを引き取る。
「御子の事は、我らの心配が過ぎましょう。しかし、懸念せずにはおれない事とご理解下さい」
「無論」
「だから、というわけではございませんが、ティシア王女殿下には一刻も早くご婚約を頂ければ――我らも民も安心できましょう」
リカルド二世には二度の離婚歴がある。そして、子供は無い。一度目は随分口を酸っぱくして進言されたものだが、二度目のそれの際には、結婚や離婚に関しては何も言われなかった。それから三年が経とうと、それらの事は話題にすらされなかった。
それすら、今日の日の布石だったのかとリカルド二世は鼻白む。
「王女殿下にはもっと公の場に顔を出して頂きたいのです。王女殿下のお相手に、どうか我が子を目通す機会があれば、と」
バルバトスの後押しを受けてか、最初の男が声を高めた。
余が結婚して子供を儲ければ満足か、そう言おうとしてリカルド二世は止めた。
そういう問題ではない事を、理解はしていた。
保守的な貴族院とは対立する事も多く、お互いに排斥しようと時期を見計らっていた。
勿論彼らはリカルド二世を退位させようとしているわけでは無い。リカルド二世もクラウディ家の外交術を失う事は痛手だ。
つまり、どちらが優位に立てるかどうか、という事なのである。
その時期が、今。
「……よかろう」
権力に固執するバルバトスの思惑に、だからこそリカルド二世は乗ったのだ。
まさか放蕩息子と有名なバルバトスの次男に、ティシアが恋をするとは思わずに。
ルーク・クラウディという男は、バルバトスの次男というだけでもリカルド二世の許容範囲の外に居た。
その上に何故か好意的に語られる醜聞がある。
そしてまず、ルーク・クラウディには外面しか無い事をリカルド二世は見抜いていた。
外見だけでは、これから幾度も押し寄せる荒波を越えてはいけない。
ティシアを守る術にもならないのに、足を引っ張る要素だけはあるとくる。
どれだけルークが真摯にティシアを愛そうと、お互いに想い合っていようと、彼がティシアを幸せに出来るとは露程も思えなかった。
これまで自分に逆らう事をしなかった妹王女が幾度も自身に背いた事に驚きはしても、リカルド二世は自身の決定を覆さなかった。
そして駆け落ち等という馬鹿な行為に走った二人を強引に引き離す事を、一分も躊躇いはしなかった。
それによって貴族院との確執が深まろうとも。
――かくしてルークは辺境の地へ追い払われ、ティシアはツカサを召喚するに至る――。
0
お気に入りに追加
61
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

王命って何ですか?
まるまる⭐️
恋愛
その日、貴族裁判所前には多くの貴族達が傍聴券を求め、所狭しと行列を作っていた。
貴族達にとって注目すべき裁判が開かれるからだ。
現国王の妹王女の嫁ぎ先である建国以来の名門侯爵家が、新興貴族である伯爵家から訴えを起こされたこの裁判。
人々の関心を集めないはずがない。
裁判の冒頭、証言台に立った伯爵家長女は涙ながらに訴えた。
「私には婚約者がいました…。
彼を愛していました。でも、私とその方の婚約は破棄され、私は意に沿わぬ男性の元へと嫁ぎ、侯爵夫人となったのです。
そう…。誰も覆す事の出来ない王命と言う理不尽な制度によって…。
ですが、理不尽な制度には理不尽な扱いが待っていました…」
裁判開始早々、王命を理不尽だと公衆の面前で公言した彼女。裁判での証言でなければ不敬罪に問われても可笑しくはない発言だ。
だが、彼女はそんな事は全て承知の上であえてこの言葉を発した。
彼女はこれより少し前、嫁ぎ先の侯爵家から彼女の有責で離縁されている。原因は彼女の不貞行為だ。彼女はそれを否定し、この裁判に於いて自身の無実を証明しようとしているのだ。
次々に積み重ねられていく証言に次第追い込まれていく侯爵家。明らかになっていく真実に、傍聴席で見守る貴族達は息を飲む。
裁判の最後、彼女は傍聴席に向かって訴えかけた。
「王命って何ですか?」と。
✳︎不定期更新、設定ゆるゆるです。

セレナの居場所 ~下賜された側妃~
緑谷めい
恋愛
後宮が廃され、国王エドガルドの側妃だったセレナは、ルーベン・アルファーロ侯爵に下賜された。自らの新たな居場所を作ろうと努力するセレナだったが、夫ルーベンの幼馴染だという伯爵家令嬢クラーラが頻繁に屋敷を訪れることに違和感を覚える。

明智さんちの旦那さんたちR
明智 颯茄
恋愛
あの小高い丘の上に建つ大きなお屋敷には、一風変わった夫婦が住んでいる。それは、妻一人に夫十人のいわゆる逆ハーレム婚だ。
奥さんは何かと大変かと思いきやそうではないらしい。旦那さんたちは全員神がかりな美しさを持つイケメンで、奥さんはニヤケ放題らしい。
ほのぼのとしながらも、複数婚が巻き起こすおかしな日常が満載。
*BL描写あり
毎週月曜日と隔週の日曜日お休みします。

【完結】辺境伯令嬢は新聞で婚約破棄を知った
五色ひわ
恋愛
辺境伯令嬢としてのんびり領地で暮らしてきたアメリアは、カフェで見せられた新聞で自身の婚約破棄を知った。真実を確かめるため、アメリアは3年ぶりに王都へと旅立った。
※本編34話、番外編『皇太子殿下の苦悩』31+1話、おまけ4話

身分差婚~あなたの妻になれないはずだった~
椿蛍
恋愛
「息子と別れていただけないかしら?」
私を脅して、別れを決断させた彼の両親。
彼は高級住宅地『都久山』で王子様と呼ばれる存在。
私とは住む世界が違った……
別れを命じられ、私の恋が終わった。
叶わない身分差の恋だったはずが――
※R-15くらいなので※マークはありません。
※視点切り替えあり。
※2日間は1日3回更新、3日目から1日2回更新となります。

裏切りの先にあるもの
マツユキ
恋愛
侯爵令嬢のセシルには幼い頃に王家が決めた婚約者がいた。
結婚式の日取りも決まり数か月後の挙式を楽しみにしていたセシル。ある日姉の部屋を訪ねると婚約者であるはずの人が姉と口づけをかわしている所に遭遇する。傷つくセシルだったが新たな出会いがセシルを幸せへと導いていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる