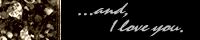27 / 64
第一章
嘘と真実 5
しおりを挟む部屋に通されたはいいけれど、肝心のルークさんは不在だった。
一瞬まさかこんな田舎町でも女遊びや賭け事なんかに興じてるんじゃあるまいな、と思ったけれど、執事らしい老紳士の話では、そういう事ではないらしい。というより、以前ライドに聞いた通りティアと出会って改心したルークさんは、それから未だに健全生活を送っているというのだ。まあ、ルークさん寄りの執事さんの話だから、どうだか分からないけど。
屋敷の裏という程近くは無いが、背後に聳えるヴェジラ山脈には野生馬が生息しているらしく、この村には時折怪我をして群れから離れた馬が迷い込んでくるらしい。そのうちの一頭をルークさんが散策か何かの折に保護したようで、その保護した馬の怪我の経過を毎日見に行っているのだそうだ。
村の外れの農場に居るルークさんに遣いを出したというから、すぐ戻ってくるだろう、とのこと。
一瞬もしや農場に若い娘でもいるんじゃないだろうなと邪推したが、メイドさんの一人が頭が取れそうな程激しく否定を見せたので、信じる事にした。
俺の中でのルークさんのイメージが、手当たり次第女性にこなを振っているイメージだから、執事さんやメイドさんには申し訳ないけれど、何かある度にそんな風に繋げてしまう。
待っている間は、クリフと一緒にノードという盤上ゲームをする事にした。チェスをした事がないからゲームとして似ているのかどうかは分からないけれど、枡のある四角い盤板と、ガラスや陶器の駒が馬や人を模しているので、チェスみたいだなという印象を持つ。
このノードというのはどの国でも知らない者の居ないくらい、メジャーなゲームのようだ。
駒のくびれの部分が赤と青の二種類。片方が赤で片方が青の駒を動かし、相手の王様を取る、という、分かり易いルールだ。
早ければ十五分程で終わってしまうそれで、雑談交じりにゆっくり遊ぶ。
気を遣ったのか、ただ単に居づらいだけなのか、執事さんもメイドさんも部屋の外だ。
「ツカサ様、その駒は斜め後ろには戻れません」
ノード自体は何度か遊んだ事があるけれど、駒の役割はまだ覚え切れていない。そんな俺に、時々クリフの注意が飛ぶ。
「あ、ごめん。じゃあこっちで」
「それだと私の駒が、一直線にキングを取れてしまいます」
「あ、そっか。……あれ、でもどっちにしろ俺、負けじゃない?」
「……恐れながら」
――とまあそんな感じで、勝負にならないくらいの有様だから、ただの暇潰しだ。
「クリフはルークさんに会った事あるんだっけ?」
何度目かの降参を告げた後、話のネタも尽きて来た俺は、そんな話を振る。
これから対峙する相手の情報を少しでも増やそう、と考えたのが今更では意味がないかもしれないけれど、とりあえず。
「遠目には幾度か」
クリフは逡巡した後、お役に立てるお話はございませんが、と生真面目な返答をくれる。
「アレクセス城で行われる夜会には私も警備に入る事がありますので、ロード・ルークが登城された折にお目にかかる事もあります。何分目立つ方ですから、そのお姿は記憶には残っておりますね」
「ああ、成程」
「夜会でのご様子は詳しく存じませんが、噂に違わず、という様子でいらっしゃったようです。私は内部の警備は管轄外ですので、聞く限りですが。華やかな社交振りが一年程前から潜んでおいでになるのは、既にツカサ様のご存知の通りです」
空になった俺のカップに紅茶を注いでくれながらのクリフに、俺は相槌を打つ。
一年程前というのが、調度ティアと云々の辺りらしい。何故改心したのかは定かでは無いが、ルークさんは人が変ったように大人しいというのがその当時の噂だと聞いた。それから何事か国王陛下の不興を買ったらしいルークさんは辺境のジェルダイン領に飛ばされた。
半年前のその時期にはルークさんの話で持ち切りだった王都も、今となっては記憶の彼方。社交の場では第二のルークさんが現れて、その手の醜聞もルークさんに取って変わった。
「その後のロードの生活は、私の耳には聞こえて参りません。ツカサ様がこちらの世界にやって来られて初めて、事実を知った程です」
実の所クリフがティアとルークの関係を知ったのは、数日前の事だ。俺がルークさんを訪ねると決意したあの日まで、クリフはティアが俺を召喚するに至った理由など、全く知らなかった。ティアとルークさんが駆け落ちしようとした事も、城に仕えるクリフすら知らない程、小規模の事だったのだ。
「ですから、私ではお役に立てません。ツカサ様のお目であれば、そのような情報など無くてもロードの人となりをご判断出来ましょう」
まるで自分の事のように胸を張って言い切るクリフは、俺という人間を誤解したままだ。クリフのこの信頼は一体どこからくるのだろう、なんて、俺の不用意な発言が招いたあれこれがいけないのだけれど思ってしまう。
俺に人を見る目なんてないんだけどな、なんて言っても詮無い事なので、口にはしないが。
ルークさんとティアを結婚させる、なんて息巻いて旅立ったけれど、その間に俺は若干の不安を覚え出していた。
ルークさんが噂通りの人で、改心なんて全くしてなくて、国王陛下がルークさんを拒否するだけの理由が本当にあった時、それでも俺は、二人を結婚させるのかとうか。
別段その噂以外に誰の口からもルークさんの人格を否定するような言葉は聞いた事がないけれど、何が国王陛下に「否」と言わせたのか、分からないままであった事を失念していた。
旅立つ前日。
『あいつがあいつである限り、事は中々に厳しいぞ』
とライドがため息交じりに言った時、その一端であろう問題を聞かせてもらったのだが、ルークさんが改心したかどうかは大きな問題ではないようだった。
勿論華々しい恋愛歴や自堕落な生活振りも理由ではあったが、それ以上にルークさんのおうち、クラウディ家の問題がある。
それから、ルークさん自体がティアの結婚相手として相応しくない、という点。
家柄は申し分ない。そして国王陛下はそれを判断基準に入れていない。
じゃあ何が相応しくないのか――という事は、終に誰も教えてくれなかった。
ここに、矛盾を感じてしまうのは俺だけだろうか。
最初は誰でも良かった筈で。家柄も身分も、国籍すら関係なく、相手は誰でも良かった筈で。
どんな家にティアが嫁ごうと、あるいは婿を取ろうと、利にもならなければ打撃にもならない。そういう話だった筈で。
それであれば【ルークさんがクラウディ家の人間】という事情があった所で、問題にならない筈で。
異世界から俺を召喚して、何から何までを教え込んで教育する必要なんかない筈で。
ルークさんがティアを幸せに出来ない理由は何か。
陛下の大らかな判断基準に引っかかる事情は何か。
そこの所がさっぱり分からない。
――分からないから。
例えば俺の眼鏡に適って、ルークさんが素晴らしい人格者だったとしても、ティアとルークさんの結婚の意志が一致しても。
その何かとやらが取り除けない限り、国王陛下の承諾が得られない。
全く何も進展していないような気がするのは、俺だけだろうか。
その不安を口に出来ないのは、肯定されても困るからだったりする。
のんびりとした動作で盤上の駒をスタートの位置に戻すクリフを眺めながら、俺は小さく嘆息する。
開け放たれた窓から外に目を移せば、手が届きそうだと錯覚しそうな位置に、山々の稜線が見える。真っ青な空に、なだらかな曲線を描いてどこまでも続く。
長閑、その一言に尽きる風景だ。
都会の生活から一転、何も娯楽のないような田舎の村で、一体ルークさんはどのように過ごしているのだろう。
自分だったらどうだろう、と考える。明日から剣道の鍛錬をしなくていいと、学校にも行かずにいいと言われたら――きっと退屈で死ねる。
朝五時なんて時間に起きなくて済むとか、夜更かしして深夜番組でも見れるとか、健康管理なんて気にせず好きな時に好きな物を食べて飲む生活だとか、今まで制限されていた事象を楽しめる、と嬉しいだろうが、恐らく馴染む事は出来ない。何だかんだ言って、剣道の鍛錬をしない生活なんて、俺には出来ない。
「……ルークさんはここでの生活に、満足してるのかなぁ」
ぽつり、独り言として呟いたのだけど、クリフは脈絡の無い俺の言葉に反応して、「どうでしょうね」等と返しながら悩むように眉根を寄せた。何時もの顎を撫でる動作もつく。
「勤めるべく仕事の無い貴族ですと、一日の大半を遊んで過ごすと聞きます。ほとんどを社交の場で過ごす生活は、こちらでは出来ませんでしょう。そういう意味では不満を感じる事はあると思いますが――」
「クリフだったら?」
「何もする事がない、というのは拷問のように感じます」
きっぱり、言い切るクリフに呆気に取られてしまう。これは遠まわしに、ルークさんはここの生活に満足していないと言っているのだろうか。それとも単純に、自分はという事なのだろうか。
少し思案してから、俺は言葉を変えた。
「ルークさんはここで、何をして過ごしているのかな」
「さあ、どうでしょう」
けれどもクリフからは、俺が求めるような応えは返ってこない。知らない、というのもあるだろうが、それよりも興味が無いと暗に語っている素っ気無さだ。
駒を綺麗に並べ終えたクリフは、顔を上げて微かに笑む。
「もう1ゲーム致しましょう」
――ルークさんの話はそれで打ち切られて、俺達はノードを再開した。
しばらくして老年の執事さんがルークさんの帰宅を告げにやって来て、それから数分後、件のルークさんが姿を現した。
「大変お待たせ致しました、シゼル。かような地へ、ようこそおいで下さいました」
ルーク・クラウディと名乗ったその人は、聞いていた通り整った顔立ちの、好青年だった。ウィリアムさんやシリウスさんのような女性の目を奪うような色気のある華やかさは無いが、第一印象でこの人モテルだろうなと確信できる容姿だった。口元に自然に浮かんだ微笑みといい、若干たれがちの優しい目元といい、先入観を持たずに出会えば間違いなく友達になりたい人ナンバー1という感じ。
ウェーブの掛かった紅茶色の髪の毛を、女性のように赤いリボンで結んでいる様がどこか可愛らしくもある。瞳の色は明るい藍色だ。
服のセンスが抜群に良く、けして派手という事はないのだが、カフスや髪の毛を束ねるリボン、凝った作りの編み上げブーツなど、どことなく洒落た感じがある。
「お目にかかれて光栄でございます」
と丁寧にお辞儀をした彼には、突然の客に対しての戸惑いは無く、十年来の友人でも迎え入れるような歓迎の意があった。
執事達さんとは違って、俺が誰であるかを知っているような口振りだった。
それもその筈、彼はダ・ブラッドという名とツカサという本名を、国王陛下から聞いているのだ。
ルークさんと目が合ってやっと驚きから解放された俺は、ひどく無機質な声音でルークさんの歓迎に答えた。
「こちらこそ、歓迎に感謝します」
笑み一つ返せぬ強張った態の俺に、それでもルークさんは嫌な顔を見せない。
俺が驚いてしまったのは、ルークさんが何も、好印象であったからでは無い。もっとちゃらんぽらんしたダメ男と思っていたのは間違いないし、思ったより好青年で、聞いていた噂話の片鱗も見えないようなしっかりした青年であるように感じるが、それよりもまず、彼の健康的な肌の色に目を見開いてしまう。その肌の色は、明らかに太陽に焼かれたそれなのだ。元々が地黒というわけではけしてなく、まるで日中を外で健康的に過ごす――例えるならスポーツ選手のそれのような状態で、社交界を賑わすという風にはとても見えない。
俺の持っていたルークさん像ががらがらと崩れ出して、戸惑う。
「失礼ですが、貴方はロード・ルークご本人ですか?」
想像の範疇外過ぎて、思わずそんな事を聞いてしまう。ルークさん本人が間に合わなくって、誰か影武者でも使った――なんて事はあるわけないが。
「勿論でございます」
ルークさんは一瞬目を見張ったが、それだけ。軽く頷いて、無表情を保つ事に失敗して狼狽した執事さんを退出させた。
それから立ち上がったままの俺とクリフを席に促して、自分も対面にかけた。
「……私がこの地に馴染んでいるのが、不思議でいらっしゃいますか」
そう、それだ!!
ルークさんが窺うようにして紡いだ言葉に、得心がいった。
つまりルークさんは、この自然溢れる田舎の村に違和感の無い、そういう雰囲気なのだ。容姿は牧歌的な長閑な村には似合わないし、物腰も服装も都会的なのだが、それなのにどうしてか、この村で生まれ育ったと聞いても納得できそうな不可思議さがある。
「ティシア王女への手紙を、失礼ながら私も拝見しました」
それをどう口にしたものか悩んだ末、俺は言葉を探しながら、事の発端を口にした。
それはルークさんの言葉に対しての反応には程遠かったし、性急過ぎた感は否めなかったが、ルークさんはただ目を細めて首肯しただけだった。
0
お気に入りに追加
61
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

王命って何ですか?
まるまる⭐️
恋愛
その日、貴族裁判所前には多くの貴族達が傍聴券を求め、所狭しと行列を作っていた。
貴族達にとって注目すべき裁判が開かれるからだ。
現国王の妹王女の嫁ぎ先である建国以来の名門侯爵家が、新興貴族である伯爵家から訴えを起こされたこの裁判。
人々の関心を集めないはずがない。
裁判の冒頭、証言台に立った伯爵家長女は涙ながらに訴えた。
「私には婚約者がいました…。
彼を愛していました。でも、私とその方の婚約は破棄され、私は意に沿わぬ男性の元へと嫁ぎ、侯爵夫人となったのです。
そう…。誰も覆す事の出来ない王命と言う理不尽な制度によって…。
ですが、理不尽な制度には理不尽な扱いが待っていました…」
裁判開始早々、王命を理不尽だと公衆の面前で公言した彼女。裁判での証言でなければ不敬罪に問われても可笑しくはない発言だ。
だが、彼女はそんな事は全て承知の上であえてこの言葉を発した。
彼女はこれより少し前、嫁ぎ先の侯爵家から彼女の有責で離縁されている。原因は彼女の不貞行為だ。彼女はそれを否定し、この裁判に於いて自身の無実を証明しようとしているのだ。
次々に積み重ねられていく証言に次第追い込まれていく侯爵家。明らかになっていく真実に、傍聴席で見守る貴族達は息を飲む。
裁判の最後、彼女は傍聴席に向かって訴えかけた。
「王命って何ですか?」と。
✳︎不定期更新、設定ゆるゆるです。

セレナの居場所 ~下賜された側妃~
緑谷めい
恋愛
後宮が廃され、国王エドガルドの側妃だったセレナは、ルーベン・アルファーロ侯爵に下賜された。自らの新たな居場所を作ろうと努力するセレナだったが、夫ルーベンの幼馴染だという伯爵家令嬢クラーラが頻繁に屋敷を訪れることに違和感を覚える。

明智さんちの旦那さんたちR
明智 颯茄
恋愛
あの小高い丘の上に建つ大きなお屋敷には、一風変わった夫婦が住んでいる。それは、妻一人に夫十人のいわゆる逆ハーレム婚だ。
奥さんは何かと大変かと思いきやそうではないらしい。旦那さんたちは全員神がかりな美しさを持つイケメンで、奥さんはニヤケ放題らしい。
ほのぼのとしながらも、複数婚が巻き起こすおかしな日常が満載。
*BL描写あり
毎週月曜日と隔週の日曜日お休みします。

【完結】辺境伯令嬢は新聞で婚約破棄を知った
五色ひわ
恋愛
辺境伯令嬢としてのんびり領地で暮らしてきたアメリアは、カフェで見せられた新聞で自身の婚約破棄を知った。真実を確かめるため、アメリアは3年ぶりに王都へと旅立った。
※本編34話、番外編『皇太子殿下の苦悩』31+1話、おまけ4話

身分差婚~あなたの妻になれないはずだった~
椿蛍
恋愛
「息子と別れていただけないかしら?」
私を脅して、別れを決断させた彼の両親。
彼は高級住宅地『都久山』で王子様と呼ばれる存在。
私とは住む世界が違った……
別れを命じられ、私の恋が終わった。
叶わない身分差の恋だったはずが――
※R-15くらいなので※マークはありません。
※視点切り替えあり。
※2日間は1日3回更新、3日目から1日2回更新となります。

裏切りの先にあるもの
マツユキ
恋愛
侯爵令嬢のセシルには幼い頃に王家が決めた婚約者がいた。
結婚式の日取りも決まり数か月後の挙式を楽しみにしていたセシル。ある日姉の部屋を訪ねると婚約者であるはずの人が姉と口づけをかわしている所に遭遇する。傷つくセシルだったが新たな出会いがセシルを幸せへと導いていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる