お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

宵どれ月衛の事件帖
Jem
キャラ文芸
舞台は大正時代。旧制高等学校高等科3年生の穂村烈生(ほむら・れつお 20歳)と神之屋月衛(かみのや・つきえ 21歳)の結成するミステリー研究会にはさまざまな怪奇事件が持ち込まれる。ある夏の日に持ち込まれたのは「髪が伸びる日本人形」。相談者は元の人形の持ち主である妹の身に何かあったのではないかと訴える。一見、ありきたりな謎のようだったが、翌日、相談者の妹から助けを求める電報が届き…!?
神社の息子で始祖の巫女を降ろして魔を斬る月衛と剣術の達人である烈生が、禁断の愛に悩みながら怪奇事件に挑みます。
登場人物
神之屋月衛(かみのや・つきえ 21歳):ある離島の神社の長男。始祖の巫女・ミノの依代として魔を斬る能力を持つ。白蛇の精を思わせる優婉な美貌に似合わぬ毒舌家で、富士ヶ嶺高等学校ミステリー研究会の頭脳。書生として身を寄せる穂村子爵家の嫡男である烈生との禁断の愛に悩む。
穂村烈生(ほむら・れつお 20歳):斜陽華族である穂村子爵家の嫡男。文武両道の爽やかな熱血漢で人望がある。紅毛に鳶色の瞳の美丈夫で、富士ヶ嶺高等学校ミステリー研究会の部長。書生の月衛を、身分を越えて熱愛する。
猿飛銀螺(さるとび・ぎんら 23歳):富士ヶ嶺高等学校高等科に留年を繰り返して居座る、伝説の3年生。逞しい長身に白皙の美貌を誇る発展家。ミステリー研究会に部員でもないのに昼寝しに押しかけてくる。育ちの良い烈生や潔癖な月衛の気付かない視点から、推理のヒントをくれることもなくはない。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

特撮特化エキストラ探偵
梶研吾
キャラ文芸
俺は特撮ドラマ専門のエキストラだ。
特撮ドラマだけに特化した俳優を目指して、日夜奮闘努力中だ。
しかし、現実という奴は厳しい。
俺にくる依頼は、出演依頼じゃなくて、撮影現場の裏のトラブル処理ばかり。
不満は募るが、そっちのほうの報酬で食っている身としては文句は言えない。
そして、今日もまた…。
(表紙イラスト・中村亮)
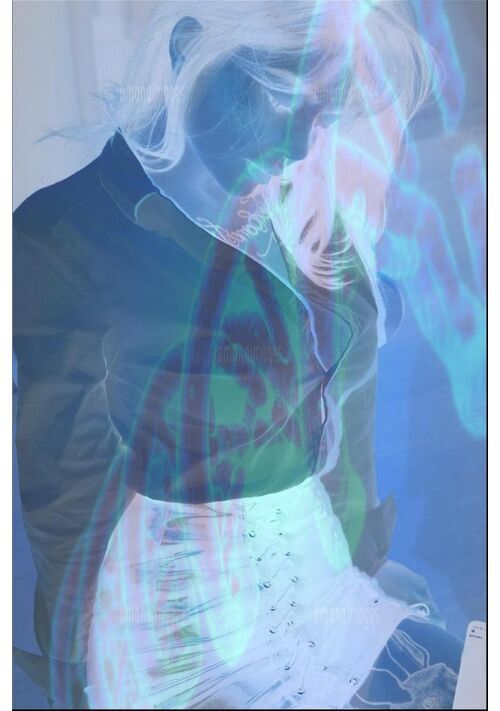
戒め
ムービーマスター
キャラ文芸
悪魔サタン=ルシファーの涙ほどの正義の意志から生まれたメイと、神が微かに抱いた悪意から生まれた天使・シンが出会う現世は、世界の滅びる時代なのか、地球上の人間や動物に次々と未知のウイルスが襲いかかり、ダークヒロイン・メイの不思議な超能力「戒め」も発動され、更なる混乱と恐怖が押し寄せる・・・

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

JOLENEジョリーン・鬼屋は人を許さない 『こわい』です。気を緩めると巻き込まれます。
尾駮アスマ(オブチアスマ おぶちあすま)
キャラ文芸
ホラー・ミステリー+ファンタジー作品です。残酷描写ありです。苦手な方は御注意ください。
完全フィクション作品です。
実在する個人・団体等とは一切関係ありません。
あらすじ
趣味で怪談を集めていた主人公は、ある取材で怪しい物件での出来事を知る。
そして、その建物について探り始める。
ほんの些細な調査のはずが大事件へと繋がってしまう・・・
やがて街を揺るがすほどの事件に主人公は巻き込まれ
特命・国家公務員たちと運命の「祭り」へと進み悪魔たちと対決することになる。
もう逃げ道は無い・・・・
読みやすいように、わざと行間を開けて執筆しています。
もしよければお気に入り登録・イイネ・感想など、よろしくお願いいたします。
大変励みになります。
ありがとうございます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















