お気に入りに追加
13
あなたにおすすめの小説

恋した貴方はαなロミオ
須藤慎弥
BL
Ω性の凛太が恋したのは、ロミオに扮したα性の結城先輩でした。
Ω性に引け目を感じている凛太。
凛太を運命の番だと信じているα性の結城。
すれ違う二人を引き寄せたヒート。
ほんわか現代BLオメガバース♡
※二人それぞれの視点が交互に展開します
※R 18要素はほとんどありませんが、表現と受け取り方に個人差があるものと判断しレーティングマークを付けさせていただきますm(*_ _)m
※fujossy様にて行われました「コスプレ」をテーマにした短編コンテスト出品作です


愛する者の腕に抱かれ、獣は甘い声を上げる
すいかちゃん
BL
獣の血を受け継ぐ一族。人間のままでいるためには・・・。
第一章 「優しい兄達の腕に抱かれ、弟は初めての発情期を迎える」
一族の中でも獣の血が濃く残ってしまった颯真。一族から疎まれる存在でしかなかった弟を、兄の亜蘭と玖蘭は密かに連れ出し育てる。3人だけで暮らすなか、颯真は初めての発情期を迎える。亜蘭と玖蘭は、颯真が獣にならないようにその身体を抱き締め支配する。
2人のイケメン兄達が、とにかく弟を可愛がるという話です。
第二章「孤独に育った獣は、愛する男の腕に抱かれ甘く啼く」
獣の血が濃い護は、幼い頃から家族から離されて暮らしていた。世話係りをしていた柳沢が引退する事となり、代わりに彼の孫である誠司がやってくる。真面目で優しい誠司に、護は次第に心を開いていく。やがて、2人は恋人同士となったが・・・。
第三章「獣と化した幼馴染みに、青年は変わらぬ愛を注ぎ続ける」
幼馴染み同士の凛と夏陽。成長しても、ずっと一緒だった。凛に片思いしている事に気が付き、夏陽は思い切って告白。凛も同じ気持ちだと言ってくれた。
だが、成人式の数日前。夏陽は、凛から別れを告げられる。そして、凛の兄である靖から彼の中に獣の血が流れている事を知らされる。発情期を迎えた凛の元に向かえば、靖がいきなり夏陽を羽交い締めにする。
獣が攻めとなる話です。また、時代もかなり現代に近くなっています。


黄色い水仙を君に贈る
えんがわ
BL
──────────
「ねぇ、別れよっか……俺たち……。」
「ああ、そうだな」
「っ……ばいばい……」
俺は……ただっ……
「うわああああああああ!」
君に愛して欲しかっただけなのに……

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

完結·助けた犬は騎士団長でした
禅
BL
母を亡くしたクレムは王都を見下ろす丘の森に一人で暮らしていた。
ある日、森の中で傷を負った犬を見つけて介抱する。犬との生活は穏やかで温かく、クレムの孤独を癒していった。
しかし、犬は突然いなくなり、ふたたび孤独な日々に寂しさを覚えていると、城から迎えが現れた。
強引に連れて行かれた王城でクレムの出生の秘密が明かされ……
※完結まで毎日投稿します
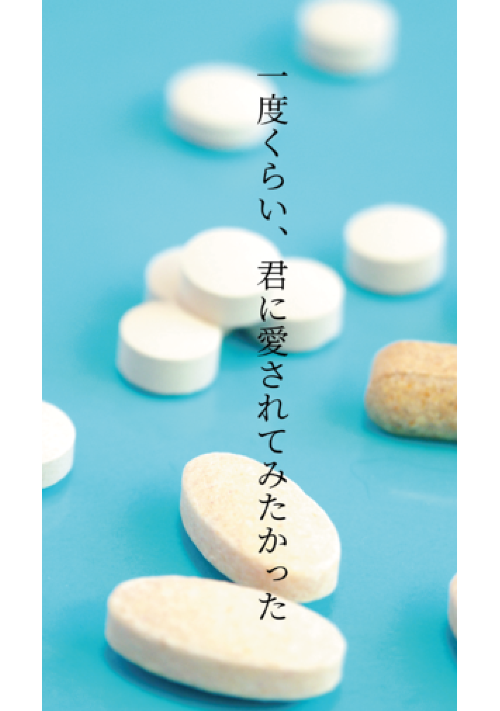
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















