17 / 45
VOL.17 ハンスのお悩み相談
しおりを挟む
桶に水を汲み、オリビアとクーヘンはブラシで床を磨く。
長年染みついた汚れは頑固。その上、生もののゴミを置いてあった辺りは限定的だがかなりしつこい汚れと臭いが染みついていた。
ごしごし…ジャッジャッ…ごしごし。
黙々と作業を進めて3日目の事だった。
道路に面した建付けの悪い扉をコツを使って開け、入ってきたのはハンスだった。
「どうしたんだ?ハンス」
「クーヘン…どうしよう。俺、俺…もう一家で夜逃げするしかない」
<< えっ?! >>
オリビアとクーヘンはブラシを手に動きを止めて顔を見合わせた。
「一体どうしたの?何かあったの?詐欺?」
「詐欺じゃないんだ。でも…やっちまったぁ!!うわぁぁ!」
髪を掻きむしって叫ぶハンスだが、2人にはどうしてそうなったか意味が判らない。
「落ち着いて。何があったか聞かせてくれない?力になれる事ならなりたいし。ね?クーヘンさんもいるから。聞かせて?」
「ハンス。何があったんだ?」
「それが…今日市場で新種の野菜が売り出されてな。大根だと思ったんだよ。すごく安い値段でずっと卸してくれるって言うからさ…。契約したんだけど…大根じゃなかった上に俺…単位を間違ってたんだ」
<< た、単位を?! >>
大問題だ。ハンスは何時ものように大根だと思って毎日仕入れるんだからと10kg分を契約したらなんとkgではなく「籠」だった。
1籠には30kgほど入っている。10kgと思ったら10籠。つまり300kg。それが毎日となればちょっと平民相手の青果店が捌ける量ではない。
「どういう事だ?野菜なんだろう?売れるんだろう?」
「それがダメなんだ…こんなの誰も買ってくれないよ。それを5年契約…馬鹿なことをしちまった」
「何の野菜を契約したのです?」
オリビアの問いにハンスは小さな声で答えた。
「甜菜だよ」
「甜菜?なんだそれ。初めて聞いたな」
新種の野菜と聞いて、籠に入った甜菜を見たハンスは「大根じゃないか」と通常の大根の20分の1の価格が提示されていたので、これはお買い得!と契約をしてしまったのだ。
しかし甜菜は通常食卓には登場しない。
生で食べる、煮て食べる、焼いて食べる。どれをとっても感じるのはエグ味と臭み。食べて害になる訳ではないが、食べられたものではない。
姿かたちは短めの大根で短い分少し不格好。
お手頃サイズで使いやすいかなとハンスは思ってしまったのだという。
クーヘンも甜菜は聞いたことがなく食べ方も知らなければ調理方法も知らない。
落ち込むハンス、励ますクーヘン。
だが、オリビアは違った。
――どこかで聞いた気がするのよね…どこだったかしら――
諸外国との折衝も担当せざるを得なかったオリビアは記憶の中で甜菜という名を聞いた気がするのだ。
「ハンスさん。その甜菜は新種なんでしょう?国内産?」
「違います。ポティト王国産です」
「ポティト王国?!ってことは…思い出した!あの甜菜!!」
<< 何、何、何~? >>
ハンスもクーヘンも突然オリビアが発した言葉に驚いた。
「ハンスさん、その甜菜はいつ入荷するの?」
「今日の分は‥もう運んだけど…明日も来るよ」
「グッジョブ!」
「は?」
驚く2人にオリビアは親指をグッと立ててサムズアップ。
「いい?甜菜はね、そのまま食べるんじゃないの。これは砂糖の代替品っていうか砂糖ね。蜂蜜も蓮華蜂蜜、アカシア蜂蜜とかってあるでしょう?砂糖にも種類があるのよ。甜菜の砂糖は甜菜糖って言うの」
「そうなんだ…」
「そうなのよ!実は他国では売られているのよ。ビーツって聞いたことない?」
「俺はないな…ハンスは知ってるのか?」
「聞いたことがあるな…赤い奴だよな。ボルシチに使ってたような気がする」
「ボルシチってなんだ?」
菓子作りにしか興味のないクーヘンは知らないが、ボルシチはロッシャー王国の民族料理。野菜を扱うハンスは滅多に入荷しないので数回しか見たことがないがビーツを知っていた。
「昔からビーツはあったんだけど、改良して出来たのが甜菜よ。食べられない事はないけど敢えて食べようとは思わないわね。でも砂糖の原料だからお役立ち野菜なのよ」
「とはいっても…」
ハンスは甜菜をどうにかしないとこの先5年。僅かな利益が飛んでしまい赤字になるのだ。
「何とかなりませんかね…」
「そうね…」
オリビアは考えた。そのままでは使えないし腐らせてしまうだけ。
――どうしたらいいかしら――
うーん…顎に手を当てて考えていると「あ!!」オリビアは閃いた。
長年染みついた汚れは頑固。その上、生もののゴミを置いてあった辺りは限定的だがかなりしつこい汚れと臭いが染みついていた。
ごしごし…ジャッジャッ…ごしごし。
黙々と作業を進めて3日目の事だった。
道路に面した建付けの悪い扉をコツを使って開け、入ってきたのはハンスだった。
「どうしたんだ?ハンス」
「クーヘン…どうしよう。俺、俺…もう一家で夜逃げするしかない」
<< えっ?! >>
オリビアとクーヘンはブラシを手に動きを止めて顔を見合わせた。
「一体どうしたの?何かあったの?詐欺?」
「詐欺じゃないんだ。でも…やっちまったぁ!!うわぁぁ!」
髪を掻きむしって叫ぶハンスだが、2人にはどうしてそうなったか意味が判らない。
「落ち着いて。何があったか聞かせてくれない?力になれる事ならなりたいし。ね?クーヘンさんもいるから。聞かせて?」
「ハンス。何があったんだ?」
「それが…今日市場で新種の野菜が売り出されてな。大根だと思ったんだよ。すごく安い値段でずっと卸してくれるって言うからさ…。契約したんだけど…大根じゃなかった上に俺…単位を間違ってたんだ」
<< た、単位を?! >>
大問題だ。ハンスは何時ものように大根だと思って毎日仕入れるんだからと10kg分を契約したらなんとkgではなく「籠」だった。
1籠には30kgほど入っている。10kgと思ったら10籠。つまり300kg。それが毎日となればちょっと平民相手の青果店が捌ける量ではない。
「どういう事だ?野菜なんだろう?売れるんだろう?」
「それがダメなんだ…こんなの誰も買ってくれないよ。それを5年契約…馬鹿なことをしちまった」
「何の野菜を契約したのです?」
オリビアの問いにハンスは小さな声で答えた。
「甜菜だよ」
「甜菜?なんだそれ。初めて聞いたな」
新種の野菜と聞いて、籠に入った甜菜を見たハンスは「大根じゃないか」と通常の大根の20分の1の価格が提示されていたので、これはお買い得!と契約をしてしまったのだ。
しかし甜菜は通常食卓には登場しない。
生で食べる、煮て食べる、焼いて食べる。どれをとっても感じるのはエグ味と臭み。食べて害になる訳ではないが、食べられたものではない。
姿かたちは短めの大根で短い分少し不格好。
お手頃サイズで使いやすいかなとハンスは思ってしまったのだという。
クーヘンも甜菜は聞いたことがなく食べ方も知らなければ調理方法も知らない。
落ち込むハンス、励ますクーヘン。
だが、オリビアは違った。
――どこかで聞いた気がするのよね…どこだったかしら――
諸外国との折衝も担当せざるを得なかったオリビアは記憶の中で甜菜という名を聞いた気がするのだ。
「ハンスさん。その甜菜は新種なんでしょう?国内産?」
「違います。ポティト王国産です」
「ポティト王国?!ってことは…思い出した!あの甜菜!!」
<< 何、何、何~? >>
ハンスもクーヘンも突然オリビアが発した言葉に驚いた。
「ハンスさん、その甜菜はいつ入荷するの?」
「今日の分は‥もう運んだけど…明日も来るよ」
「グッジョブ!」
「は?」
驚く2人にオリビアは親指をグッと立ててサムズアップ。
「いい?甜菜はね、そのまま食べるんじゃないの。これは砂糖の代替品っていうか砂糖ね。蜂蜜も蓮華蜂蜜、アカシア蜂蜜とかってあるでしょう?砂糖にも種類があるのよ。甜菜の砂糖は甜菜糖って言うの」
「そうなんだ…」
「そうなのよ!実は他国では売られているのよ。ビーツって聞いたことない?」
「俺はないな…ハンスは知ってるのか?」
「聞いたことがあるな…赤い奴だよな。ボルシチに使ってたような気がする」
「ボルシチってなんだ?」
菓子作りにしか興味のないクーヘンは知らないが、ボルシチはロッシャー王国の民族料理。野菜を扱うハンスは滅多に入荷しないので数回しか見たことがないがビーツを知っていた。
「昔からビーツはあったんだけど、改良して出来たのが甜菜よ。食べられない事はないけど敢えて食べようとは思わないわね。でも砂糖の原料だからお役立ち野菜なのよ」
「とはいっても…」
ハンスは甜菜をどうにかしないとこの先5年。僅かな利益が飛んでしまい赤字になるのだ。
「何とかなりませんかね…」
「そうね…」
オリビアは考えた。そのままでは使えないし腐らせてしまうだけ。
――どうしたらいいかしら――
うーん…顎に手を当てて考えていると「あ!!」オリビアは閃いた。
988
お気に入りに追加
2,020
あなたにおすすめの小説


何もできない王妃と言うのなら、出て行くことにします
天宮有
恋愛
国王ドスラは、王妃の私エルノアの魔法により国が守られていると信じていなかった。
側妃の発言を聞き「何もできない王妃」と言い出すようになり、私は城の人達から蔑まれてしまう。
それなら国から出て行くことにして――その後ドスラは、後悔するようになっていた。


初恋の兄嫁を優先する私の旦那様へ。惨めな思いをあとどのくらい我慢したらいいですか。
梅雨の人
恋愛
ハーゲンシュタイン公爵の娘ローズは王命で第二王子サミュエルの婚約者となった。
王命でなければ誰もサミュエルの婚約者になろうとする高位貴族の令嬢が現れなかったからだ。
第一王子ウィリアムの婚約者となったブリアナに一目ぼれしてしまったサミュエルは、駄目だと分かっていても次第に互いの距離を近くしていったためだった。
常識のある周囲の冷ややかな視線にも気が付かない愚鈍なサミュエルと義姉ブリアナ。
ローズへの必要最低限の役目はかろうじて行っていたサミュエルだったが、常にその視線の先にはブリアナがいた。
みじめな婚約者時代を経てサミュエルと結婚し、さらに思いがけず王妃になってしまったローズはただひたすらその不遇の境遇を耐えた。
そんな中でもサミュエルが時折見せる優しさに、ローズは胸を高鳴らせてしまうのだった。
しかし、サミュエルとブリアナの愚かな言動がローズを深く傷つけ続け、遂にサミュエルは己の行動を深く後悔することになる―――。

婚約破棄したので、元の自分に戻ります
しあ
恋愛
この国の王子の誕生日パーティで、私の婚約者であるショーン=ブリガルドは見知らぬ女の子をパートナーにしていた。
そして、ショーンはこう言った。
「可愛げのないお前が悪いんだから!お前みたいな地味で不細工なやつと結婚なんて悪夢だ!今すぐ婚約を破棄してくれ!」
王子の誕生日パーティで何してるんだ…。と呆れるけど、こんな大勢の前で婚約破棄を要求してくれてありがとうございます。
今すぐ婚約破棄して本来の自分の姿に戻ります!

彼女にも愛する人がいた
まるまる⭐️
恋愛
既に冷たくなった王妃を見つけたのは、彼女に食事を運んで来た侍女だった。
「宮廷医の見立てでは、王妃様の死因は餓死。然も彼が言うには、王妃様は亡くなってから既に2、3日は経過しているだろうとの事でした」
そう宰相から報告を受けた俺は、自分の耳を疑った。
餓死だと? この王宮で?
彼女は俺の従兄妹で隣国ジルハイムの王女だ。
俺の背中を嫌な汗が流れた。
では、亡くなってから今日まで、彼女がいない事に誰も気付きもしなかったと言うのか…?
そんな馬鹿な…。信じられなかった。
だがそんな俺を他所に宰相は更に告げる。
「亡くなった王妃様は陛下の子を懐妊されておりました」と…。
彼女がこの国へ嫁いで来て2年。漸く子が出来た事をこんな形で知るなんて…。
俺はその報告に愕然とした。
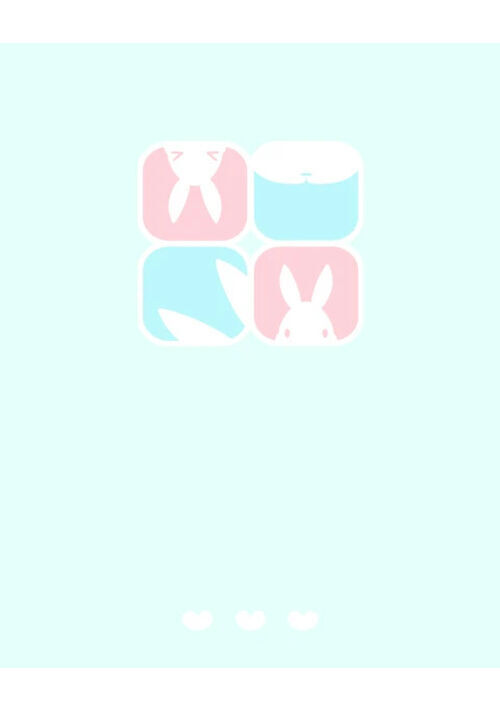
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。

侯爵夫人のハズですが、完全に無視されています
猫枕
恋愛
伯爵令嬢のシンディーは学園を卒業と同時にキャッシュ侯爵家に嫁がされた。
しかし婚姻から4年、旦那様に会ったのは一度きり、大きなお屋敷の端っこにある離れに住むように言われ、勝手な外出も禁じられている。
本宅にはシンディーの偽物が奥様と呼ばれて暮らしているらしい。
盛大な結婚式が行われたというがシンディーは出席していないし、今年3才になる息子がいるというが、もちろん産んだ覚えもない。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















