お気に入りに追加
120
あなたにおすすめの小説

この満ち足りた匣庭の中で 三章―Ghost of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
幾度繰り返そうとも、匣庭は――。
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
その裏では、医療センターによる謎めいた計画『WAWプログラム』が粛々と進行し、そして避け得ぬ惨劇が街を襲った。
舞台は繰り返す。
三度、二週間の物語は幕を開け、定められた終焉へと砂時計の砂は落ちていく。
変わらない世界の中で、真実を知悉する者は誰か。この世界の意図とは何か。
科学研究所、GHOST、ゴーレム計画。
人工地震、マイクロチップ、レッドアウト。
信号領域、残留思念、ブレイン・マシン・インターフェース……。
鬼の祟りに隠れ、暗躍する機関の影。
手遅れの中にある私たちの日々がほら――また、始まった。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

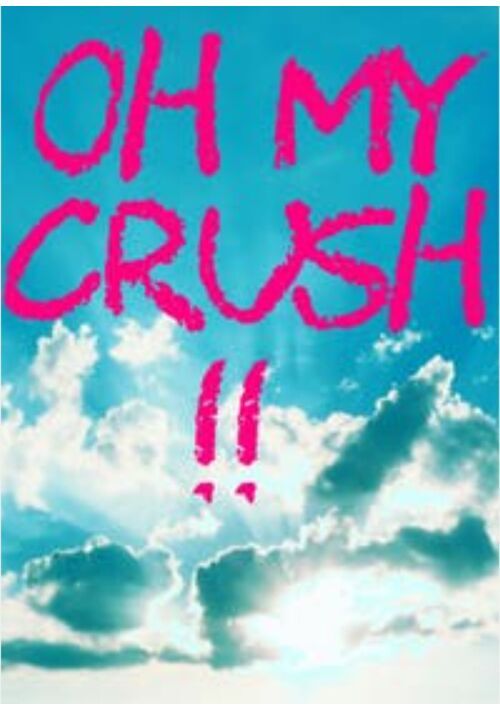


早く惚れてよ、怖がりナツ
ぱんなこった。
BL
幼少期のトラウマのせいで男性が怖くて苦手な男子高校生1年の那月(なつ)16歳。女友達はいるものの、男子と上手く話す事すらできず、ずっと周りに煙たがられていた。
このままではダメだと、高校でこそ克服しようと思いつつも何度も玉砕してしまう。
そしてある日、そんな那月をからかってきた同級生達に襲われそうになった時、偶然3年生の彩世(いろせ)がやってくる。
一見、真面目で大人しそうな彩世は、那月を助けてくれて…
那月は初めて、男子…それも先輩とまともに言葉を交わす。
ツンデレ溺愛先輩×男が怖い年下後輩
《表紙はフリーイラスト@oekakimikasuke様のものをお借りしました》

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

この欠け落ちた匣庭の中で 終章―Dream of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
ーーこれが、匣の中だったんだ。
二〇一八年の夏。廃墟となった満生台を訪れたのは二人の若者。
彼らもまた、かつてGHOSTの研究によって運命を弄ばれた者たちだった。
信号領域の研究が展開され、そして壊れたニュータウン。終焉を迎えた現実と、終焉を拒絶する仮想。
歪なる領域に足を踏み入れる二人は、果たして何か一つでも、その世界に救いを与えることが出来るだろうか。
幻想、幻影、エンケージ。
魂魄、領域、人類の進化。
802部隊、九命会、レッドアイ・オペレーション……。
さあ、あの光の先へと進んでいこう。たとえもう二度と時計の針が巻き戻らないとしても。
私たちの駆け抜けたあの日々は確かに満ち足りていたと、懐かしめるようになるはずだから。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















