10 / 77
第2章 悪魔を狩る刑事達
09: 傘男君の見立て
しおりを挟む
倉庫の内部は、この世にもしそのようなモノがあり得るならばの話だが、「人体パーツの生標本見本市」の様相を呈していた。
ある一角には、頭部が集められ、ある一角は胴体、ある一角は右腕、、。
その殆どの肌には、狂気を感じさせるタトゥーがびっしり刻み込まれていた。
つまりこの場所が、身体に彫り込まれたタトゥーの面積で力位置が決るギャング団、「闇の船」の最後の波止場だったのだ。
赤座は、頭部ばかりが碁石のように規則正しく床に並べられた場所で立ち止まった。
全ての顔が苦悶に歪んでいる。
それがズラリと並んでいる光景には、さすがの守門も戦慄を覚えざるを得なかった。
「中に一人、一般人が混じってるんだ。運悪くこいつらに拉致されていたようだ。殺された時は手足を拘束されていたから、やった方も、その人が他とは違うと判った筈なんだがな。・・・やはり関係なかったようだ。さっき隠蔽など目じゃないと言ったが、その人だけは違う。」
赤座は暗い目をして言った。
「理不尽な死、そしてその死まで、真実は闇の中。そんな死に方ってあるか、、。」
「ですね。なんとかなるなら、なんとかしたい。」
「兎に角、その人の為にも、目の前の事を片付ける。それが先だな。」
「ええ。」
「傘男、ここまでで見立てを言ってくれ。この悪魔憑きは、外で人を殺し、この中で、また人を殺し、何を思ったのか、それらの死体を全部ここに集めて分類して並べ直した。分類の為に改めて死体を切り直した跡さえある。」
傘男君の「君」が、外れていた。
「僕の知っている悪魔憑きは、こういう事をよくやります。人間に凄く興味があるんです。お気に入りの玩具みたいなものだ。で、暫く遊ぶとバラバラにして壊してしまう。それも遊びだ。肉体だけじゃありませんよ。精神もその対象になり、同様にもて遊ぶ。奴らは、この世界に出現した時、自分が心を持ってこの世に存在するという事自体に興奮して、いろんな事をするんです。自分達自身は、何も壊せない世界に存在していたから、この世界に受肉した時には、代わりに、人間を壊して色々と調べてみる。存在するという事の具体的な意味をね。」
そこで守門は一旦、言葉を区切って生首の陳列を見た。
「じゃ、人間はこういう事をしないのかというと、そうでもない。よく似た事をする、狂った人間もいる。快楽殺人とかですね。両者の間に、差はあるのか?あるいは、差を見いだす事に意味はあるのか?難しいですね。、、この世に、人間という肉を得た悪魔は最初、純粋な赤ちゃんの様に振る舞う。もちろん悪魔としてですが。それと快楽殺人とはどう違うのか?」
赤座は黙りこくって、守門の話に耳を傾けている。
人間が犯す快楽殺人の事例については、自分の方がよく知っている、とは思ったが、赤座は敢えて黙っているようだった。
「今まで見てきた事を総合すると、その破壊力を見ても、やった奴は普通じゃないのは一目瞭然だ。ただし非常に良く訓練された複数の人間たちが、何か特殊な武器を持って、事を起こせば、これくらいは可能な様な気がします。この人体パーツの展示も、何か他の隠された目的や意図があるなら、やってやれない事はないでしょう。」
赤座が軽く首を横にふった。
だがそれは、守門の言葉を否定したのではないようだった。
「出来る出来ないで、その人数に着目するなら、悪魔憑きの場合だと、力が強ければこれくらいの事は一人でやれるでしょうね。いや、こういう事をやっても全然、不思議じゃない。複数の人間が、これをやったと仮定するより、エクソシストである僕にはそちらの方が自然に思える。でもこれには、微妙に引っ掛かるところがあります。」
守門は少し腰をおって、頭部の陳列を覗き込むようにした。
「この並べ方、悪魔に取り憑かれた人間のこだわりが出ていると考えるのが妥当ですよね。、、実際、こういう事に、変質的な拘りを見せる悪魔に取り憑かれた人間は沢山います。しかしそれにしても、これは並べ方が規則的すぎる。まるで測量装置で測ったみたいだ。ほら、頭って大きさがそれぞれ違うから人間の普通の感覚でやったら、これとこれなんかは、もっと離しておくほうが自然に均等に並んで見える筈なんだけど、それをやらない。見た目より、実測値の方を優先してる。でも、こんな事の為に、わざわざメジャーみたいな物を使うんだろうか?」
守門は二つの切断された頭部を指差して言った。
守門は直感的に、これは今までの悪魔憑きが残した現場とは様相が違うと感じていたが、それを赤座に強調するのは止めようと判断したようだ。
それは、赤座の捜査を妨げる要因になると考えたのだ。
今はただ、事実だけを述べればいい。
そして赤座は、守門の言葉を微妙な表情で聞いている。
「メジャーな、、。他には、何か気になることがあるか?」
「身体の破壊の仕方ですね。神か人間か、野獣かの違い、」
「どう言う意味だ?」
「僕が今まで見てきた現場の死体は、大きく分けて三パターンです。人間が現在手に入れられないような不思議な技術で傷口が残るか、人間がよく使う刃物の類いで破壊されたか、獣が食いちぎったようにズタズタになるか。悪魔憑きがやると、多くの場合は、神か野獣のどちらかになる。」
そこで守門は一旦言葉を切った。
「、、でも、これは神と人間の中間の様な気がする。野獣ではない、かと言って神でもない。珍しい、、。、、後は何も分からないですね。」
守門だけが感じ取れる、悪魔憑きがその場に残しやすい時空操作後の気配が、ここにはまったくない事は伏せて置いた。
そうなら、この事件そのものに、悪魔憑きが関わっていない可能性も出てくる。
本当にそれがないのか、それとも守門の力の衰えで、それが感じ取れないのかが、分からない為ということもあった。
「それだけ、傘男君が、判れば十分だ。ここを出よう。我々用の時間も余りないしな。」
「我々用のって、ひょっとして、まだ警察は現場検証の途中なんですか?」
「そうだ。自分が無理を言って、中断させた。」
「あり得ない。僕なんかの為に。」
「有り得なくはない。広域捜査特殊課は、そういう強引さを認められた横断的機動捜査隊でもある。それにこういう事態に陥った時、自分たちには、お前しかいないんだよ。だから、お前が集中出来るように、こうした。初動での失敗は、後々まで響くもんだ。例え相手が、悪魔でもな。その意味でも、お前がこれを見ることが、最優先なんだよ。お前、警察の鑑識班に、悪魔憑きの何かが判るとでも思っているのか?」
いつの間にか、守門の呼び名は、傘男から、お前に変更されていた。
外に出た時、数人の人間たちがいた。
どうやら守門達が出てくるのを、待ち詫て、集まっていたようだ。
中には鑑識と思える人間たちもいた。
「待たせたな、済まなかった。再開してくれ」
そんな赤座の言葉を引き金にしたように、男たちはフェンスの向こうへ吸い込まれて行く。
「本当に僕の為に、中断をしたんですね?」
「貴男方は、こういうのに慣れてない。鑑識とか他に人がいたら、本来働く勘だって働かないでしょ?貴男方の中には、その現場で相手の残した気配とかを、感じ取れる人もいると聞いてますよ。だから配慮したんです。」
赤座は他に声が漏れないように、守門に近づき、更に念を込めるように小声で囁いた。
声色がガラッと変わった。
「まだ自分の事がよく分かっていないようだから何度でも言ってやる。そうさ、傘男君は特別扱いなんだよ。主役なんだ。これに対処出来るのは傘男君しかいない。こんな事に恐縮する暇があるなら、それを忘れないで、自分ら特殊課の為に、汗かいて働いてくれ。」
ある一角には、頭部が集められ、ある一角は胴体、ある一角は右腕、、。
その殆どの肌には、狂気を感じさせるタトゥーがびっしり刻み込まれていた。
つまりこの場所が、身体に彫り込まれたタトゥーの面積で力位置が決るギャング団、「闇の船」の最後の波止場だったのだ。
赤座は、頭部ばかりが碁石のように規則正しく床に並べられた場所で立ち止まった。
全ての顔が苦悶に歪んでいる。
それがズラリと並んでいる光景には、さすがの守門も戦慄を覚えざるを得なかった。
「中に一人、一般人が混じってるんだ。運悪くこいつらに拉致されていたようだ。殺された時は手足を拘束されていたから、やった方も、その人が他とは違うと判った筈なんだがな。・・・やはり関係なかったようだ。さっき隠蔽など目じゃないと言ったが、その人だけは違う。」
赤座は暗い目をして言った。
「理不尽な死、そしてその死まで、真実は闇の中。そんな死に方ってあるか、、。」
「ですね。なんとかなるなら、なんとかしたい。」
「兎に角、その人の為にも、目の前の事を片付ける。それが先だな。」
「ええ。」
「傘男、ここまでで見立てを言ってくれ。この悪魔憑きは、外で人を殺し、この中で、また人を殺し、何を思ったのか、それらの死体を全部ここに集めて分類して並べ直した。分類の為に改めて死体を切り直した跡さえある。」
傘男君の「君」が、外れていた。
「僕の知っている悪魔憑きは、こういう事をよくやります。人間に凄く興味があるんです。お気に入りの玩具みたいなものだ。で、暫く遊ぶとバラバラにして壊してしまう。それも遊びだ。肉体だけじゃありませんよ。精神もその対象になり、同様にもて遊ぶ。奴らは、この世界に出現した時、自分が心を持ってこの世に存在するという事自体に興奮して、いろんな事をするんです。自分達自身は、何も壊せない世界に存在していたから、この世界に受肉した時には、代わりに、人間を壊して色々と調べてみる。存在するという事の具体的な意味をね。」
そこで守門は一旦、言葉を区切って生首の陳列を見た。
「じゃ、人間はこういう事をしないのかというと、そうでもない。よく似た事をする、狂った人間もいる。快楽殺人とかですね。両者の間に、差はあるのか?あるいは、差を見いだす事に意味はあるのか?難しいですね。、、この世に、人間という肉を得た悪魔は最初、純粋な赤ちゃんの様に振る舞う。もちろん悪魔としてですが。それと快楽殺人とはどう違うのか?」
赤座は黙りこくって、守門の話に耳を傾けている。
人間が犯す快楽殺人の事例については、自分の方がよく知っている、とは思ったが、赤座は敢えて黙っているようだった。
「今まで見てきた事を総合すると、その破壊力を見ても、やった奴は普通じゃないのは一目瞭然だ。ただし非常に良く訓練された複数の人間たちが、何か特殊な武器を持って、事を起こせば、これくらいは可能な様な気がします。この人体パーツの展示も、何か他の隠された目的や意図があるなら、やってやれない事はないでしょう。」
赤座が軽く首を横にふった。
だがそれは、守門の言葉を否定したのではないようだった。
「出来る出来ないで、その人数に着目するなら、悪魔憑きの場合だと、力が強ければこれくらいの事は一人でやれるでしょうね。いや、こういう事をやっても全然、不思議じゃない。複数の人間が、これをやったと仮定するより、エクソシストである僕にはそちらの方が自然に思える。でもこれには、微妙に引っ掛かるところがあります。」
守門は少し腰をおって、頭部の陳列を覗き込むようにした。
「この並べ方、悪魔に取り憑かれた人間のこだわりが出ていると考えるのが妥当ですよね。、、実際、こういう事に、変質的な拘りを見せる悪魔に取り憑かれた人間は沢山います。しかしそれにしても、これは並べ方が規則的すぎる。まるで測量装置で測ったみたいだ。ほら、頭って大きさがそれぞれ違うから人間の普通の感覚でやったら、これとこれなんかは、もっと離しておくほうが自然に均等に並んで見える筈なんだけど、それをやらない。見た目より、実測値の方を優先してる。でも、こんな事の為に、わざわざメジャーみたいな物を使うんだろうか?」
守門は二つの切断された頭部を指差して言った。
守門は直感的に、これは今までの悪魔憑きが残した現場とは様相が違うと感じていたが、それを赤座に強調するのは止めようと判断したようだ。
それは、赤座の捜査を妨げる要因になると考えたのだ。
今はただ、事実だけを述べればいい。
そして赤座は、守門の言葉を微妙な表情で聞いている。
「メジャーな、、。他には、何か気になることがあるか?」
「身体の破壊の仕方ですね。神か人間か、野獣かの違い、」
「どう言う意味だ?」
「僕が今まで見てきた現場の死体は、大きく分けて三パターンです。人間が現在手に入れられないような不思議な技術で傷口が残るか、人間がよく使う刃物の類いで破壊されたか、獣が食いちぎったようにズタズタになるか。悪魔憑きがやると、多くの場合は、神か野獣のどちらかになる。」
そこで守門は一旦言葉を切った。
「、、でも、これは神と人間の中間の様な気がする。野獣ではない、かと言って神でもない。珍しい、、。、、後は何も分からないですね。」
守門だけが感じ取れる、悪魔憑きがその場に残しやすい時空操作後の気配が、ここにはまったくない事は伏せて置いた。
そうなら、この事件そのものに、悪魔憑きが関わっていない可能性も出てくる。
本当にそれがないのか、それとも守門の力の衰えで、それが感じ取れないのかが、分からない為ということもあった。
「それだけ、傘男君が、判れば十分だ。ここを出よう。我々用の時間も余りないしな。」
「我々用のって、ひょっとして、まだ警察は現場検証の途中なんですか?」
「そうだ。自分が無理を言って、中断させた。」
「あり得ない。僕なんかの為に。」
「有り得なくはない。広域捜査特殊課は、そういう強引さを認められた横断的機動捜査隊でもある。それにこういう事態に陥った時、自分たちには、お前しかいないんだよ。だから、お前が集中出来るように、こうした。初動での失敗は、後々まで響くもんだ。例え相手が、悪魔でもな。その意味でも、お前がこれを見ることが、最優先なんだよ。お前、警察の鑑識班に、悪魔憑きの何かが判るとでも思っているのか?」
いつの間にか、守門の呼び名は、傘男から、お前に変更されていた。
外に出た時、数人の人間たちがいた。
どうやら守門達が出てくるのを、待ち詫て、集まっていたようだ。
中には鑑識と思える人間たちもいた。
「待たせたな、済まなかった。再開してくれ」
そんな赤座の言葉を引き金にしたように、男たちはフェンスの向こうへ吸い込まれて行く。
「本当に僕の為に、中断をしたんですね?」
「貴男方は、こういうのに慣れてない。鑑識とか他に人がいたら、本来働く勘だって働かないでしょ?貴男方の中には、その現場で相手の残した気配とかを、感じ取れる人もいると聞いてますよ。だから配慮したんです。」
赤座は他に声が漏れないように、守門に近づき、更に念を込めるように小声で囁いた。
声色がガラッと変わった。
「まだ自分の事がよく分かっていないようだから何度でも言ってやる。そうさ、傘男君は特別扱いなんだよ。主役なんだ。これに対処出来るのは傘男君しかいない。こんな事に恐縮する暇があるなら、それを忘れないで、自分ら特殊課の為に、汗かいて働いてくれ。」
0
お気に入りに追加
120
あなたにおすすめの小説

この満ち足りた匣庭の中で 三章―Ghost of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
幾度繰り返そうとも、匣庭は――。
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
その裏では、医療センターによる謎めいた計画『WAWプログラム』が粛々と進行し、そして避け得ぬ惨劇が街を襲った。
舞台は繰り返す。
三度、二週間の物語は幕を開け、定められた終焉へと砂時計の砂は落ちていく。
変わらない世界の中で、真実を知悉する者は誰か。この世界の意図とは何か。
科学研究所、GHOST、ゴーレム計画。
人工地震、マイクロチップ、レッドアウト。
信号領域、残留思念、ブレイン・マシン・インターフェース……。
鬼の祟りに隠れ、暗躍する機関の影。
手遅れの中にある私たちの日々がほら――また、始まった。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

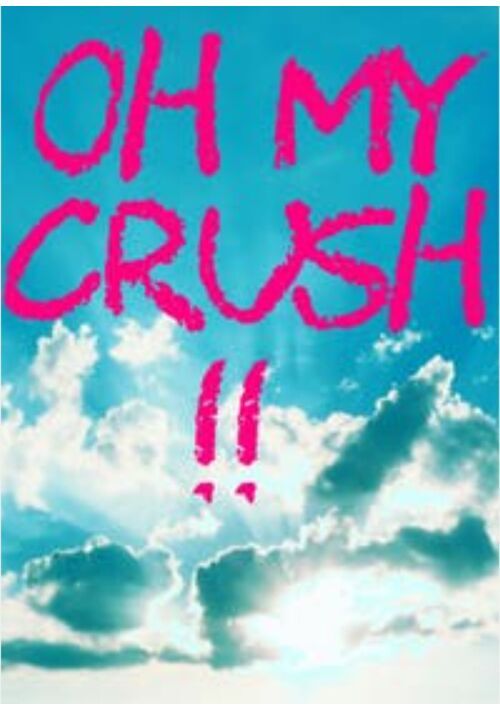


早く惚れてよ、怖がりナツ
ぱんなこった。
BL
幼少期のトラウマのせいで男性が怖くて苦手な男子高校生1年の那月(なつ)16歳。女友達はいるものの、男子と上手く話す事すらできず、ずっと周りに煙たがられていた。
このままではダメだと、高校でこそ克服しようと思いつつも何度も玉砕してしまう。
そしてある日、そんな那月をからかってきた同級生達に襲われそうになった時、偶然3年生の彩世(いろせ)がやってくる。
一見、真面目で大人しそうな彩世は、那月を助けてくれて…
那月は初めて、男子…それも先輩とまともに言葉を交わす。
ツンデレ溺愛先輩×男が怖い年下後輩
《表紙はフリーイラスト@oekakimikasuke様のものをお借りしました》

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

この欠け落ちた匣庭の中で 終章―Dream of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
ーーこれが、匣の中だったんだ。
二〇一八年の夏。廃墟となった満生台を訪れたのは二人の若者。
彼らもまた、かつてGHOSTの研究によって運命を弄ばれた者たちだった。
信号領域の研究が展開され、そして壊れたニュータウン。終焉を迎えた現実と、終焉を拒絶する仮想。
歪なる領域に足を踏み入れる二人は、果たして何か一つでも、その世界に救いを与えることが出来るだろうか。
幻想、幻影、エンケージ。
魂魄、領域、人類の進化。
802部隊、九命会、レッドアイ・オペレーション……。
さあ、あの光の先へと進んでいこう。たとえもう二度と時計の針が巻き戻らないとしても。
私たちの駆け抜けたあの日々は確かに満ち足りていたと、懐かしめるようになるはずだから。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















