お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説
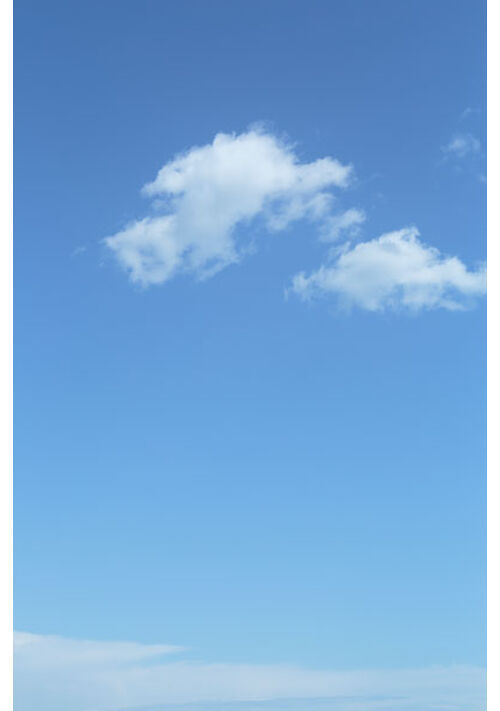

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~
黒井丸
歴史・時代
~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~
武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。
大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。
そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。
方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。
しかし、正しい事を書いても見向きもされない。
そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。

リモート刑事 笹本翔
雨垂 一滴
ミステリー
『リモート刑事 笹本翔』は、過去のトラウマと戦う一人の刑事が、リモート捜査で事件を解決していく、刑事ドラマです。
主人公の笹本翔は、かつて警察組織の中でトップクラスの捜査官でしたが、ある事件で仲間を失い、自身も重傷を負ったことで、外出恐怖症(アゴラフォビア)に陥り、現場に出ることができなくなってしまいます。
それでも、彼の卓越した分析力と冷静な判断力は衰えず、リモートで捜査指示を出しながら、次々と難事件を解決していきます。
物語の鍵を握るのは、翔の若き相棒・竹内優斗。熱血漢で行動力に満ちた優斗と、過去の傷を抱えながらも冷静に捜査を指揮する翔。二人の対照的なキャラクターが織りなすバディストーリーです。
翔は果たして過去のトラウマを克服し、再び現場に立つことができるのか?
翔と優斗が数々の難事件に挑戦します!

妖戦刀義
和山忍
歴史・時代
時は日本の江戸時代初期。
とある農村で、風太は母の病気を治せる人もしくは妖怪をさがす旅に出た父の帰りを待っていた。
しかし、その父とは思わぬ形で再会することとなった。
そして、風太は人でありながら妖力を得て・・・・・・。
※この物語はフィクションであり、実際の史実と異なる部分があります。
そして、実在の人物、団体、事件、その他いろいろとは一切関係ありません。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















