20 / 40
20.1000年後の今日、正午どき
しおりを挟む
「……魔族と人間は、一度は歩み寄ろうとしたのか」
「そうだ。もう1000年も前のことだがな」
「出来上がりかけた友好関係を、当時の宰相セロ・リューガンが滅茶苦茶にした?」
「そう。己の野望を果たすためならば犠牲をいとわない、塵屑のような男であった」
「それからずっと、人間と魔族の関係はこじれたままか」
「こじれたままだ。俺は事件の真相を誰にも語らなかった。当時の国王シルバ・アンドレイは、死の直前まで俺が一方的に宰相を惨殺したのだと信じていただろう。事件以後、俺を殺そうと何度も軍隊を差し向けてきた」
「なぜ真相を語らなかったんだ。強姦行為の証拠はいくらでもあっただろう。例えセロを殺してしまったとしても、宮殿から逃げ出さずにいれば、どちらが加害者であったかを説明することはできたはずだ」
「……俺に、何を説明しろと?」
低い声に気おされてイシュメルは黙り込んだ。強姦行為の被害者に「当時の状況を切々と語れ」ということはあまりにも酷だ。辛い記憶から逃れるために、がむしゃらにその場を離れたくなる気持ちは理解できた。
配慮に欠けた質問をしてしまったと、イシュメルはギオラから視線を外した。
今、ギオラは紺色の毛布丸々とくるまっている。イシュメルの勧めによりたっぷりと水を飲み、多少なりとも食事をとり、そしていくらかの睡眠。死人のようであった顔色はずいぶん良くなった。
イシュメルはといえば、毛布の片端にもぐりこみずっとギオラの寝顔を見守っていた。殴ることも剣を振りかざすこともしなかった。
そのことにより「もう貴方を欺くような真似はしない」というイシュメルの言葉は真実であると受け入れられたのだ。
だからこそこうして隠し続けていた過去を教えてくれたのだ。人間と魔族がいがみ合うきっかけとなった事件を。ギオラが人間を嫌うようになったきっかけを。セロと名乗る男との因縁を。
「ギオラ。1000年前の事件については理解した。だが一つ教えてくれ。先日この城にやってきたセロという名の男、あの男は何者なんだ。まさか宰相セロ・リューガンと同一人物ではないだろう?」
先日猫の姿で城に忍び込み、ギオラを犯した男セロ。しかし名前はセロであっても、宰相セロ・リューガンと同一人物であるはずはない。宰相セロはギオラに殺されている。一度死んだ人間が、まさか1000年の時を超えて蘇るはずもない。
「同一人物……ではないな。だが赤の他人と言うのも憚られる。宰相セロの記憶を持った他人、とでも言えば良いのだろうか」
「……どういう意味だ?」
「宰相セロの肉体は1000年前に死んだ。だが奴の魂は死ななかった。『蘇りの力』を持つ眷属として、再びこの世に生を受けたんだ」
イシュメルは息を飲んだ。
「宰相セロが魔王の眷属に……? 魔王の眷属とは、そんな簡単になれるものなのか」
「条件さえ揃えば、眷属になることは難しくない。まさかあのゴミクズ粘着野郎を眷属にしてしまうとは、俺としても想定外であったが」
「ちなみに魔王の眷属になる条件とは?」
「『眷属になる』という強い意志を持った人間の命を、『俺自身の手で』断つことだ。セロの場合は『眷属になる』ことを願ったというよりも、単純に俺への執着が強かったんだろう。死してもなお傍に在りたいと強く願った……実に面倒な奴だ」
ははぁ、とイシュメルはうなずいた。
ギオラが城へやって来た人間に対し「眷属になるか、死ぬか」と尋ねることには、しっかりとした理由があったということだ。
人間と魔族の険悪な間柄を考えれば、捕らえた人間をそのまま生かしていくわけにはいかない。何らかの形で魔族側の陣営に引き入れる必要がある。幸いにもギオラは人間を眷属にすることができるが、そうするためには人間側の強い意志が必要となる。「魔王の眷属となってでも生きたい」という強い意志が。
その者の肉体は一度死に、そして再びこの世に生を受ける。崇高な魔王の眷属として。
セロはその中でただ1人のイレギュラーだ。憎しみにより惨殺されたはずのセロは、皮肉にも魔王の眷属となる条件を満たしてしまった。ギオラへの異常な執着心ゆえに。
「セロは、今までに何度もこの城にやって来ているのか」
「ああ、来ているな。蘇りの力を持っているとはいえ、セロの肉体は人間のまま。人間として生まれ、歳をとり、死ぬ。そしてまた人間として生まれる。宰相セロの記憶と、それぞれの人生の記憶を宿した別人としてな。その繰り返される人生の中で、奴は何度も俺の元を訪れている」
「セロが城に来たときはどうしていた」
「基本的には追い返して終いだな。蘇りの力を持っているとはいえ、奴の肉体は正真正銘の人間だ。黒龍の力をもってすれば、恐れることなど何もなかった。何度蘇ろうが」
「それは……確かにそうだ」
1000年前、聖ミルギスタ王国の宰相として確固たる地位を築いていたセロ・リューガン。彼は別人としてこの世界に生を受ける中で、何度もギオラの元を訪れていた。しかし人間の身体では黒龍の力を宿すギオラを組み伏すことができずに、1000年もの間お預けを食らっていたというわけだ。
その膠着した関係をイシュメルが壊してしまった。ギオラの魔法を封じ、毒を含ませた。ロキの指輪を失くしたことも不味かった。ギオラにとっては何もかもが悪い方向へと向いてしまったのだ。そしてセロにとっては最高の状況へと。
「セロは……また城にやってくるだろうか」
「来るだろうな。ヘドロのように粘着質な奴だ。よからぬ事を企んでいなければいいが」
そう言ってギオラは溜息を吐いた。
ロキの指輪を手に入れたセロは、どのような生物にでも姿を変えることができる。イシュメルは指輪の効力を正確に把握しているわけではないが、猫に姿を変えられるのだから変身の幅はかなり広い。いくら城の守りに気を遣っていたとしても、例えばネズミに化けられてしまえば侵入を拒むことは困難だ。
そうしてギオラの元へとやって来て、次は何をするつもりなのだろう。1000年越しに再び野望を達成したセロは、次に何を企むのだろう。読めないからこそ恐ろしい。
思考にふけるギオラは、イシュメルの右手を用いて手遊びを始めていた。母指球をむにむにと揉んでみたり、指関節を曲げ伸ばしてみたり。至るところにできた剣だこが気になるようで、爪先でかりかりと引っ掻いたりもしている。くすぐったくて止めてほしいと思う反面、永遠に止めてくれるなとも思う。
このまま時が止まってしまえ、などと柄にもなく考えてしまう。
けれども目の前に転がる問題をどうにかしない限り、平穏なときが訪れることはない。
イシュメルは覚悟を決めた。
「ギオラ。聖ミルギスタ王国へ行かないか」
イシュメルの提案に、ギオラは銀色の目を見開いた。取り留めのない手遊びが止む。
「俺が聖ミルギスタ王国に? 冗談だろう。俺とあの国との関係がどれほど険悪であるかは説明しただろう。国境をまたいだ瞬間、即座に首を刎ねられるぞ」
「そんなことはない。なぜなら聖ミルギスタ王国の人間は、ギオラの顔を知らないからだ。ギオラが『俺様は魔王ギオラ』と書いた看板を背負って歩いていたところで、質の悪い冗談だと思われるだけだ」
「おい、俺に変な看板を背負わせるな」
などと文句を言いながらも、ギオラはいくらか納得した表情である。聖ミルギスタ王国と魔族の土地の間では、1000年に渡り国交が断絶されている。侵略や誘拐を除く民の往来はないのだから、当然聖ミルギスタ王国の民はギオラの顔を知らない。
ギオラの顔を知る者はイシュメルと、魔王討伐に赴いた聖女アリシア、そして2人の戦士だけだ。彼らとてギオラの顔を真正面からまじまじと見つめたわけではないのだから、例えばギオラが目元の化粧を落としてしまえば、ギオラを魔王だと判断することは不可能になるだろう。
イシュメルは説明を続けた。
「無事聖ミルギスタ王国の国土に入ったら、2人で王都を目指す。馬車を乗り継ぐ必要があるから、多少長旅にはなるだろう。そして王都に着いたら――聖女アリシアに謁見を願い出る。私の名前を使えば難しいことではない。神器の創り手である聖女に、呪印の解除を依頼するんだ」
聖女とは聖ミルギスタ王国でただ1人、神の力を借りて神器を創ることを許された者。アリシアの手にかかれば、いかなる神器の効力も思いのままに操ることができる。魔力封じの呪印についても例外ではない。
ギオラに魔法が戻れば、人間であるセロは怖くない。貞操の安全を第一に考えるのならば、最も確実な手段とも言える。
けれどもイシュメルの提案を聞いたギオラは呆れ顔だ。
「お前は阿呆か? 聖女アリシアを相手に、俺が何者だと説明するつもりだ。まさか律儀に『魔王の首にある魔力封じの呪印を消してくれ』と依頼するつもりではあるまい」
「その通りだ。正直に全てを話す」
ギオラは呆れを通り越し、皮肉るような表情を浮かべた。
「冗談だろう、その望みに聖女様が応じてくれるとでも? 魔王を名乗る男が、魔力を封じられた状態で国家の中心部へとやって来た。俺ならまず捕えてやろうと思うが」
「捕まって良いんだ。むしろ捕まえてくれなくては困る」
「……どういう意味だ。俺に罪人になれというのか?」
ギオラの顔に疑念の色が浮かんだ。まさかお前、また俺を欺くつもりではあるまいな?
イシュメルはゆっくりと首を横に振った。私はもう2度とギオラを欺かない。
「ギオラは罪人にはならない。なぜなら彼らにはギオラがギオラであると即座に証明する手段がないからだ。『魔王を名乗る男が、魔力を封じられた状態で国家の中心部へとやって来た。念のため拘束はするが男の身元は不明』、こういう状況になるわけだ」
ギオラは毛布にくるまったまま、こてりと首を傾げた。
「ほう、それで?」
「しかし男が魔王を名乗る以上、その主張を無視することはできない。となれば真実を明らかにする方法はただ一つ。男を神判にかけること」
「……神判?」
「聖女が開く裁判のことだ。神判には『ノルンの涙』と呼ばれる強力な神器が用いられ、発言者は嘘偽りを述べることができない。神判の場での発言は全てが真実として扱われるんだ。ギオラが本物の魔王であるという事も。供物の少女を悪戯に殺してはいない事も。1000年前の事件では被害者であった事も」
イシュメルはそこで言葉を切った。ギオラの両眼が、突き抜かんばかりにイシュメルを見つめていた。
「……俺に、神判の場で全てを語れと。あのゴミクズ野郎に良いようにされたことを?」
「冷たい言い方をすればそうなってしまう。けれど『真実を語ること』と『全てを語る』ことは同義ではない。聖女は慈愛に溢れたお方だ。魔王を相手にしても、まさか強姦行為の被害を赤裸々に語れとは言うまいよ」
「真実を語り、それからどうする」
「1から関係を作り直すんだ。ギオラは人間が嫌いだと言うが、全ての人間を滅ぼしたいと考えているわけじゃないんだろう? 一度は歩み寄ろうとしたんだろう? 人間だって同じなんだ。魔族の存在は恐ろしいが、心のどこかには共存を望む気持ちがある。憎み合うことなく殺し合うことなく、手を取り合って暮らしていければいいと思っているんだ。神判の場でギオラが一言『人間との共存を望む』と言えば、それが叶う」
聖ミルギスタ王国初代国王シルバ・アンドレイは魔族との共存を望んだ。ギオラも一度はそれに応えた。しかし宰相セロの凶行により、共存の未来は閉ざされてしまった。
それから1000年の時が経った。真実は長い歴史の中に埋もれ、ギオラと聖ミルギスタ王国の関係は拗れに拗れたまま。どちらかが歩み寄らなければ、両者の関係は永遠に険悪なままだ。
そしていびつに積み上がった歴史を根本から崩すことができる者はギオラの他にいない。ギオラの他に、真実を真実と証明できる者はいないのだから。
ベッドの上にあぐらを掻いたギオラは、イシュメルの瞳を瞬きもなく見つめていた。朝日に照らされるギオラの顔は透けるような美しさ。滑らかな濡羽の髪と、人形のように整った目鼻立ち。花びらの唇で言葉を紡ぐ。
「信じるぞ、いいのか」
「いい」
ギオラの瞳にはもう侮蔑の色はない。ダイヤモンドにも似た美しい光を湛えていた。しかしものの数秒経った頃には、その瞳は悪戯な色へと塗り変えられるのだ。
「では俺の魔力が戻るまで、命を賭けた決闘はお預けだ。寿命が延びて良かったな?」
「ん……そうだな。ではこの剣を――」
イシュメルは借り物の剣を差し出すが、ギオラはそれを受け取らなかった。代わりにとん、と左胸を小突かれた。
「貸しておく。大切な剣だ、失くすなよ」
かつて1人の勇敢な騎士が、魔王を討つため魔王城へとやって来た。騎士はギオラに敗北し命を落とすものの、剣だけは壊れずに残された。黒龍をも恐れぬ雄姿を称え、ギオラがその剣を大切に手元へ置いていたのだ。
100年の時が経ち、剣はイシュメルの手に託された。魔王を討つために作られた剣は、魔王と戦うために託にされた剣は、研ぎ澄まされた刃で何を切るというのか。
イシュメルは翡翠飾りの埋め込まれた柄を強く握りしめた。時刻は決闘の開始予定時刻、正午を迎えたところであった。
「そうだ。もう1000年も前のことだがな」
「出来上がりかけた友好関係を、当時の宰相セロ・リューガンが滅茶苦茶にした?」
「そう。己の野望を果たすためならば犠牲をいとわない、塵屑のような男であった」
「それからずっと、人間と魔族の関係はこじれたままか」
「こじれたままだ。俺は事件の真相を誰にも語らなかった。当時の国王シルバ・アンドレイは、死の直前まで俺が一方的に宰相を惨殺したのだと信じていただろう。事件以後、俺を殺そうと何度も軍隊を差し向けてきた」
「なぜ真相を語らなかったんだ。強姦行為の証拠はいくらでもあっただろう。例えセロを殺してしまったとしても、宮殿から逃げ出さずにいれば、どちらが加害者であったかを説明することはできたはずだ」
「……俺に、何を説明しろと?」
低い声に気おされてイシュメルは黙り込んだ。強姦行為の被害者に「当時の状況を切々と語れ」ということはあまりにも酷だ。辛い記憶から逃れるために、がむしゃらにその場を離れたくなる気持ちは理解できた。
配慮に欠けた質問をしてしまったと、イシュメルはギオラから視線を外した。
今、ギオラは紺色の毛布丸々とくるまっている。イシュメルの勧めによりたっぷりと水を飲み、多少なりとも食事をとり、そしていくらかの睡眠。死人のようであった顔色はずいぶん良くなった。
イシュメルはといえば、毛布の片端にもぐりこみずっとギオラの寝顔を見守っていた。殴ることも剣を振りかざすこともしなかった。
そのことにより「もう貴方を欺くような真似はしない」というイシュメルの言葉は真実であると受け入れられたのだ。
だからこそこうして隠し続けていた過去を教えてくれたのだ。人間と魔族がいがみ合うきっかけとなった事件を。ギオラが人間を嫌うようになったきっかけを。セロと名乗る男との因縁を。
「ギオラ。1000年前の事件については理解した。だが一つ教えてくれ。先日この城にやってきたセロという名の男、あの男は何者なんだ。まさか宰相セロ・リューガンと同一人物ではないだろう?」
先日猫の姿で城に忍び込み、ギオラを犯した男セロ。しかし名前はセロであっても、宰相セロ・リューガンと同一人物であるはずはない。宰相セロはギオラに殺されている。一度死んだ人間が、まさか1000年の時を超えて蘇るはずもない。
「同一人物……ではないな。だが赤の他人と言うのも憚られる。宰相セロの記憶を持った他人、とでも言えば良いのだろうか」
「……どういう意味だ?」
「宰相セロの肉体は1000年前に死んだ。だが奴の魂は死ななかった。『蘇りの力』を持つ眷属として、再びこの世に生を受けたんだ」
イシュメルは息を飲んだ。
「宰相セロが魔王の眷属に……? 魔王の眷属とは、そんな簡単になれるものなのか」
「条件さえ揃えば、眷属になることは難しくない。まさかあのゴミクズ粘着野郎を眷属にしてしまうとは、俺としても想定外であったが」
「ちなみに魔王の眷属になる条件とは?」
「『眷属になる』という強い意志を持った人間の命を、『俺自身の手で』断つことだ。セロの場合は『眷属になる』ことを願ったというよりも、単純に俺への執着が強かったんだろう。死してもなお傍に在りたいと強く願った……実に面倒な奴だ」
ははぁ、とイシュメルはうなずいた。
ギオラが城へやって来た人間に対し「眷属になるか、死ぬか」と尋ねることには、しっかりとした理由があったということだ。
人間と魔族の険悪な間柄を考えれば、捕らえた人間をそのまま生かしていくわけにはいかない。何らかの形で魔族側の陣営に引き入れる必要がある。幸いにもギオラは人間を眷属にすることができるが、そうするためには人間側の強い意志が必要となる。「魔王の眷属となってでも生きたい」という強い意志が。
その者の肉体は一度死に、そして再びこの世に生を受ける。崇高な魔王の眷属として。
セロはその中でただ1人のイレギュラーだ。憎しみにより惨殺されたはずのセロは、皮肉にも魔王の眷属となる条件を満たしてしまった。ギオラへの異常な執着心ゆえに。
「セロは、今までに何度もこの城にやって来ているのか」
「ああ、来ているな。蘇りの力を持っているとはいえ、セロの肉体は人間のまま。人間として生まれ、歳をとり、死ぬ。そしてまた人間として生まれる。宰相セロの記憶と、それぞれの人生の記憶を宿した別人としてな。その繰り返される人生の中で、奴は何度も俺の元を訪れている」
「セロが城に来たときはどうしていた」
「基本的には追い返して終いだな。蘇りの力を持っているとはいえ、奴の肉体は正真正銘の人間だ。黒龍の力をもってすれば、恐れることなど何もなかった。何度蘇ろうが」
「それは……確かにそうだ」
1000年前、聖ミルギスタ王国の宰相として確固たる地位を築いていたセロ・リューガン。彼は別人としてこの世界に生を受ける中で、何度もギオラの元を訪れていた。しかし人間の身体では黒龍の力を宿すギオラを組み伏すことができずに、1000年もの間お預けを食らっていたというわけだ。
その膠着した関係をイシュメルが壊してしまった。ギオラの魔法を封じ、毒を含ませた。ロキの指輪を失くしたことも不味かった。ギオラにとっては何もかもが悪い方向へと向いてしまったのだ。そしてセロにとっては最高の状況へと。
「セロは……また城にやってくるだろうか」
「来るだろうな。ヘドロのように粘着質な奴だ。よからぬ事を企んでいなければいいが」
そう言ってギオラは溜息を吐いた。
ロキの指輪を手に入れたセロは、どのような生物にでも姿を変えることができる。イシュメルは指輪の効力を正確に把握しているわけではないが、猫に姿を変えられるのだから変身の幅はかなり広い。いくら城の守りに気を遣っていたとしても、例えばネズミに化けられてしまえば侵入を拒むことは困難だ。
そうしてギオラの元へとやって来て、次は何をするつもりなのだろう。1000年越しに再び野望を達成したセロは、次に何を企むのだろう。読めないからこそ恐ろしい。
思考にふけるギオラは、イシュメルの右手を用いて手遊びを始めていた。母指球をむにむにと揉んでみたり、指関節を曲げ伸ばしてみたり。至るところにできた剣だこが気になるようで、爪先でかりかりと引っ掻いたりもしている。くすぐったくて止めてほしいと思う反面、永遠に止めてくれるなとも思う。
このまま時が止まってしまえ、などと柄にもなく考えてしまう。
けれども目の前に転がる問題をどうにかしない限り、平穏なときが訪れることはない。
イシュメルは覚悟を決めた。
「ギオラ。聖ミルギスタ王国へ行かないか」
イシュメルの提案に、ギオラは銀色の目を見開いた。取り留めのない手遊びが止む。
「俺が聖ミルギスタ王国に? 冗談だろう。俺とあの国との関係がどれほど険悪であるかは説明しただろう。国境をまたいだ瞬間、即座に首を刎ねられるぞ」
「そんなことはない。なぜなら聖ミルギスタ王国の人間は、ギオラの顔を知らないからだ。ギオラが『俺様は魔王ギオラ』と書いた看板を背負って歩いていたところで、質の悪い冗談だと思われるだけだ」
「おい、俺に変な看板を背負わせるな」
などと文句を言いながらも、ギオラはいくらか納得した表情である。聖ミルギスタ王国と魔族の土地の間では、1000年に渡り国交が断絶されている。侵略や誘拐を除く民の往来はないのだから、当然聖ミルギスタ王国の民はギオラの顔を知らない。
ギオラの顔を知る者はイシュメルと、魔王討伐に赴いた聖女アリシア、そして2人の戦士だけだ。彼らとてギオラの顔を真正面からまじまじと見つめたわけではないのだから、例えばギオラが目元の化粧を落としてしまえば、ギオラを魔王だと判断することは不可能になるだろう。
イシュメルは説明を続けた。
「無事聖ミルギスタ王国の国土に入ったら、2人で王都を目指す。馬車を乗り継ぐ必要があるから、多少長旅にはなるだろう。そして王都に着いたら――聖女アリシアに謁見を願い出る。私の名前を使えば難しいことではない。神器の創り手である聖女に、呪印の解除を依頼するんだ」
聖女とは聖ミルギスタ王国でただ1人、神の力を借りて神器を創ることを許された者。アリシアの手にかかれば、いかなる神器の効力も思いのままに操ることができる。魔力封じの呪印についても例外ではない。
ギオラに魔法が戻れば、人間であるセロは怖くない。貞操の安全を第一に考えるのならば、最も確実な手段とも言える。
けれどもイシュメルの提案を聞いたギオラは呆れ顔だ。
「お前は阿呆か? 聖女アリシアを相手に、俺が何者だと説明するつもりだ。まさか律儀に『魔王の首にある魔力封じの呪印を消してくれ』と依頼するつもりではあるまい」
「その通りだ。正直に全てを話す」
ギオラは呆れを通り越し、皮肉るような表情を浮かべた。
「冗談だろう、その望みに聖女様が応じてくれるとでも? 魔王を名乗る男が、魔力を封じられた状態で国家の中心部へとやって来た。俺ならまず捕えてやろうと思うが」
「捕まって良いんだ。むしろ捕まえてくれなくては困る」
「……どういう意味だ。俺に罪人になれというのか?」
ギオラの顔に疑念の色が浮かんだ。まさかお前、また俺を欺くつもりではあるまいな?
イシュメルはゆっくりと首を横に振った。私はもう2度とギオラを欺かない。
「ギオラは罪人にはならない。なぜなら彼らにはギオラがギオラであると即座に証明する手段がないからだ。『魔王を名乗る男が、魔力を封じられた状態で国家の中心部へとやって来た。念のため拘束はするが男の身元は不明』、こういう状況になるわけだ」
ギオラは毛布にくるまったまま、こてりと首を傾げた。
「ほう、それで?」
「しかし男が魔王を名乗る以上、その主張を無視することはできない。となれば真実を明らかにする方法はただ一つ。男を神判にかけること」
「……神判?」
「聖女が開く裁判のことだ。神判には『ノルンの涙』と呼ばれる強力な神器が用いられ、発言者は嘘偽りを述べることができない。神判の場での発言は全てが真実として扱われるんだ。ギオラが本物の魔王であるという事も。供物の少女を悪戯に殺してはいない事も。1000年前の事件では被害者であった事も」
イシュメルはそこで言葉を切った。ギオラの両眼が、突き抜かんばかりにイシュメルを見つめていた。
「……俺に、神判の場で全てを語れと。あのゴミクズ野郎に良いようにされたことを?」
「冷たい言い方をすればそうなってしまう。けれど『真実を語ること』と『全てを語る』ことは同義ではない。聖女は慈愛に溢れたお方だ。魔王を相手にしても、まさか強姦行為の被害を赤裸々に語れとは言うまいよ」
「真実を語り、それからどうする」
「1から関係を作り直すんだ。ギオラは人間が嫌いだと言うが、全ての人間を滅ぼしたいと考えているわけじゃないんだろう? 一度は歩み寄ろうとしたんだろう? 人間だって同じなんだ。魔族の存在は恐ろしいが、心のどこかには共存を望む気持ちがある。憎み合うことなく殺し合うことなく、手を取り合って暮らしていければいいと思っているんだ。神判の場でギオラが一言『人間との共存を望む』と言えば、それが叶う」
聖ミルギスタ王国初代国王シルバ・アンドレイは魔族との共存を望んだ。ギオラも一度はそれに応えた。しかし宰相セロの凶行により、共存の未来は閉ざされてしまった。
それから1000年の時が経った。真実は長い歴史の中に埋もれ、ギオラと聖ミルギスタ王国の関係は拗れに拗れたまま。どちらかが歩み寄らなければ、両者の関係は永遠に険悪なままだ。
そしていびつに積み上がった歴史を根本から崩すことができる者はギオラの他にいない。ギオラの他に、真実を真実と証明できる者はいないのだから。
ベッドの上にあぐらを掻いたギオラは、イシュメルの瞳を瞬きもなく見つめていた。朝日に照らされるギオラの顔は透けるような美しさ。滑らかな濡羽の髪と、人形のように整った目鼻立ち。花びらの唇で言葉を紡ぐ。
「信じるぞ、いいのか」
「いい」
ギオラの瞳にはもう侮蔑の色はない。ダイヤモンドにも似た美しい光を湛えていた。しかしものの数秒経った頃には、その瞳は悪戯な色へと塗り変えられるのだ。
「では俺の魔力が戻るまで、命を賭けた決闘はお預けだ。寿命が延びて良かったな?」
「ん……そうだな。ではこの剣を――」
イシュメルは借り物の剣を差し出すが、ギオラはそれを受け取らなかった。代わりにとん、と左胸を小突かれた。
「貸しておく。大切な剣だ、失くすなよ」
かつて1人の勇敢な騎士が、魔王を討つため魔王城へとやって来た。騎士はギオラに敗北し命を落とすものの、剣だけは壊れずに残された。黒龍をも恐れぬ雄姿を称え、ギオラがその剣を大切に手元へ置いていたのだ。
100年の時が経ち、剣はイシュメルの手に託された。魔王を討つために作られた剣は、魔王と戦うために託にされた剣は、研ぎ澄まされた刃で何を切るというのか。
イシュメルは翡翠飾りの埋め込まれた柄を強く握りしめた。時刻は決闘の開始予定時刻、正午を迎えたところであった。
0
お気に入りに追加
246
あなたにおすすめの小説

エロゲ世界のモブに転生したオレの一生のお願い!
たまむし
BL
大学受験に失敗して引きこもりニートになっていた湯島秋央は、二階の自室から転落して死んだ……はずが、直前までプレイしていたR18ゲームの世界に転移してしまった!
せっかくの異世界なのに、アキオは主人公のイケメン騎士でもヒロインでもなく、ゲーム序盤で退場するモブになっていて、いきなり投獄されてしまう。
失意の中、アキオは自分の身体から大事なもの(ち●ちん)がなくなっていることに気付く。
「オレは大事なものを取り戻して、エロゲの世界で女の子とエッチなことをする!」
アキオは固い決意を胸に、獄中で知り合った男と協力して牢を抜け出し、冒険の旅に出る。
でも、なぜかお色気イベントは全部男相手に発生するし、モブのはずが世界の命運を変えるアイテムを手にしてしまう。
ちん●んと世界、男と女、どっちを選ぶ? どうする、アキオ!?
完結済み番外編、連載中続編があります。「ファタリタ物語」でタグ検索していただければ出てきますので、そちらもどうぞ!
※同一内容をムーンライトノベルズにも投稿しています※
pixivリクエストボックスでイメージイラストを依頼して描いていただきました。
https://www.pixiv.net/artworks/105819552

悪役令息の七日間
リラックス@ピロー
BL
唐突に前世を思い出した俺、ユリシーズ=アディンソンは自分がスマホ配信アプリ"王宮の花〜神子は7色のバラに抱かれる〜"に登場する悪役だと気付く。しかし思い出すのが遅過ぎて、断罪イベントまで7日間しか残っていない。
気づいた時にはもう遅い、それでも足掻く悪役令息の話。【お知らせ:2024年1月18日書籍発売!】

花開かぬオメガの花嫁
朏猫(ミカヅキネコ)
BL
帝国には献上されたΩが住むΩ宮という建物がある。その中の蕾宮には、発情を迎えていない若いΩや皇帝のお渡りを受けていないΩが住んでいた。異国から来た金髪緑眼のΩ・キーシュも蕾宮に住む一人だ。三十になり皇帝のお渡りも望めないなか、あるαに下賜されることが決まる。しかしキーシュには密かに思う相手がいて……。※他サイトにも掲載
[高級官吏の息子α × 異国から来た金髪緑眼Ω / BL / R18]

虐げられ聖女(男)なので辺境に逃げたら溺愛系イケメン辺境伯が待ち構えていました【本編完結】(異世界恋愛オメガバース)
美咲アリス
BL
虐待を受けていたオメガ聖女のアレクシアは必死で辺境の地に逃げた。そこで出会ったのは逞しくてイケメンのアルファ辺境伯。「身バレしたら大変だ」と思ったアレクシアは芝居小屋で見た『悪役令息キャラ』の真似をしてみるが、どうやらそれが辺境伯の心を掴んでしまったようで、ものすごい溺愛がスタートしてしまう。けれども実は、辺境伯にはある考えがあるらしくて⋯⋯? オメガ聖女とアルファ辺境伯のキュンキュン異世界恋愛です、よろしくお願いします^_^ 本編完結しました、特別編を連載中です!
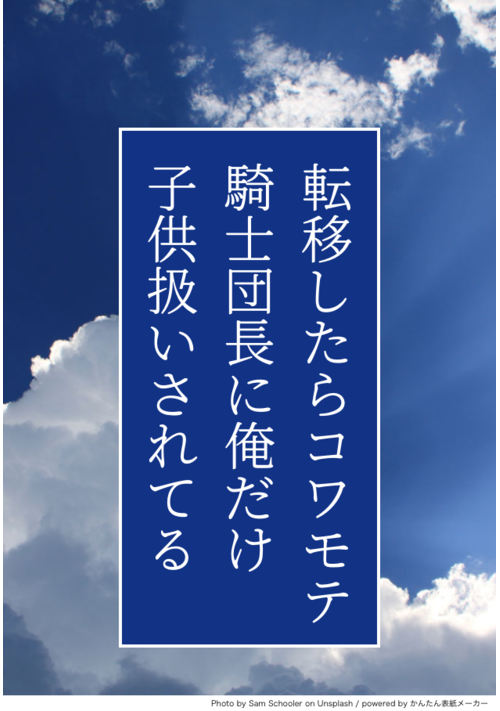
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【完結済】ラスボスの使い魔に転生したので世界を守るため全力でペットセラピーしてみたら……【溺愛こじらせドS攻め】
綺沙きさき(きさきさき)
BL
【溺愛ヤンデレ魔術師】×【黒猫使い魔】のドS・執着・溺愛をこじらせた攻めの話
<あらすじ>
魔術師ギディオンの使い魔であるシリルは、知っている。
この世界が前世でプレイしたゲーム『グランド・マギ』であること、そしてギディオンが世界滅亡を望む最凶のラスボスで、その先にはバッドエンドしか待っていないことも……。
そんな未来を回避すべく、シリルはギディオンの心の闇を癒やすため、猫の姿を最大限に活用してペットセラピーを行う。
その甲斐あって、ギディオンの心の闇は癒やされ、バッドエンドは回避できたと思われたが、ある日、目を覚ますと人間の姿になっていて――!?
========================
*表紙イラスト…はやし燈様(@umknb7)
*表紙デザイン…睦月様(https://mutsuki-design.tumblr.com/)
*9月23日(月)J.GARDEN56にて頒布予定の『異世界転生×執着攻め小説集』に収録している作品です。

狼騎士は異世界の男巫女(のおまけ)を追跡中!
Kokonuca.
BL
異世界!召喚!ケモ耳!な王道が書きたかったので
ある日、はるひは自分の護衛騎士と関係をもってしまう、けれどその護衛騎士ははるひの兄かすがの秘密の恋人で……
兄と護衛騎士を守りたいはるひは、二人の前から姿を消すことを選択した
完結しましたが、こぼれ話を更新いたします

Switch!〜僕とイケメンな地獄の裁判官様の溺愛異世界冒険記〜
天咲 琴葉
BL
幼い頃から精霊や神々の姿が見えていた悠理。
彼は美しい神社で、家族や仲間達に愛され、幸せに暮らしていた。
しかし、ある日、『燃える様な真紅の瞳』をした男と出逢ったことで、彼の運命は大きく変化していく。
幾重にも襲い掛かる運命の荒波の果て、悠理は一度解けてしまった絆を結び直せるのか――。
運命に翻弄されても尚、出逢い続ける――宿命と絆の和風ファンタジー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















