79 / 156
03白鷺トロフィーの行方
消えたトロフィー事件01
しおりを挟む
(二)消えたトロフィー事件
9月のカレンダーも残り僅かとなった。渋山台高校は例年通り、9月30日と10月1日の二日間、伝統行事の学園祭――名づけて『白鷺祭』――を開催する。今年は最初から数えて40周年目のメモリアルイヤーらしい。
渋山台高校の白鷺祭といえば、県内で知らぬ者はいないほど有名な、それはそれは盛大な催しである――というのは、過去に何度か一般客として遊びに来ていた俺の感想だ。今年は楽しむ側から楽しませる側に立場を変えるというわけで、今からワクワクして仕方がない。もっとも、生徒数は減っているので、往時の賑わいとまではいかないだろうけど。
来たる日に備え、1年から3年の各クラス、並びに各部活動は、一学期末に早々と出し物を決めていた。学園祭は専用の実行委員会を設置するのではなく、生徒会が監督・指揮統括する。彼らはそれぞれのチームの届け出を受理し、各種審議した上で認可を与え、予算を公平に分配していた。
大量の小道具がいる、例えば演劇のような催し物を申請したクラスなどは、夏休み期間中も登校して大小さまざまな雑事に取り組んできたらしい。見上げた根性である。
で、我が1年3組はどうかというと……
「俺に任せろよ、皆」
噂好き・祭り好きの久川浩介が、クラス会議で演説をぶった。今から二ヶ月前、一学期末のことだ。
「実は俺、ダーツがプロ級にうまくてさ。それで考えたんだ。喫茶店をやったろうってな」
どんぐりのような眼、突き出た頬骨、矢印のような鼻の、それほど美男子とも言えない彼だが、クラスの人気は高かった。1年3組の女子のリーダー的存在が奈緒なら、男子のそれは間違いなく久川だ。
委員長の夏島さんが続きを促すと、両手をこすり合わせて笑顔を撒き散らす。
「名づけて『ダーツ喫茶店』。お客さんがダーツで生徒代表と勝負し、勝てば紅茶が無料になる、というわけだ。どうだい、面白そうだろ?」
英二が腕を組んでせせら笑った。動物園で面白い生き物を見ているような趣きである。
「生徒代表が弱ければ一円にもならんぞ」
久川は右上腕に力こぶを作って叩いてみせた。白い歯がこぼれる。
「大丈夫、基本的に俺が投げるからよ。強いぞ、俺は」
三好が噴き出し、あっさり核心を突いた。
「お前がダーツをやりたいだけだろ」
それに引きずられるように、教室中から笑いが起きる。だが久川はめげずに認めた。
「まあそうとも言うな」
黒板前に立つ夏島委員長へ笑顔で目配せする。
「後で投票にかけてくれよ、夏島さん」
「分かりました」
純架は興味を示さず、スプーン曲げにチャレンジしていた。しかし彼の超能力はユリ・ゲラーやMr.マリックに遠く及ばず、どれだけ経っても食器は微動だにしない。やがて飽きたのか、純架は腕力で無理矢理折ろうと躍起になった。
もう超能力じゃねえよ。
結局他に案もなく、久川の要望通り、1年3組はダーツ喫茶店を開くこととなった。提案者は大いに満足し、いかにも楽しそうにダーツの矢を投げる真似をする。
「絶対ウケるものになるぜ。こりゃ間違いなく、最優秀賞の白鷺トロフィーはうちがいただきだな」
俺は初耳の言葉に思わず返した。
「白鷺トロフィー? 何だそりゃ」
久川は腰に両手を当ててふんぞり返る。他人の知らない雑学を披露するときの、彼の癖だった。
「知らないのか? この学園祭ではアンケートで顧客満足度を測って、もっとも優れた催し物に白鷺のトロフィーが与えられるんだ。まさに栄光栄誉の極みってやつさ。ねえ先生?」
「ああ、その通りだ」
宮古先生はうなずいた。気合を入れたらしく、立ち上がって腹から声を出す。
「やるからには勝つぞ、皆んな! どこに出しても恥ずかしくない、立派な店を作るんだ!」
久川がその大音じょうに乗った。一発手を叩き合わせる。
「もちろんですとも! 1年3組、いっちょ頑張ろうぜ!」
せっかくの学園祭である。これは盛り上がるかと思いきや、しかし俺の周りのクラスメイトたちはまばらな拍手でそれに応えるのみだった。
いまいち気の乗らない、中途半端な反応――
ダーツ勝負という特色こそあるものの、それがなければただの喫茶店だ。ありきたりの上に『超』がつく、本気度に欠けた催し物との感は否めない。宮古先生や久川の情熱は、クラスメイトにいまいち伝播したり浸透したりしてはいなかった――いや、俺が何となくそう思っただけなんだけど。
ともかくこうして1年3組は消極的に動き出した。
そして二学期。各クラス・各部活動が学園祭準備に奔走する中、純架は『探偵部』も出し物を用意すべきだと言い出した。
「部室として旧棟1年5組を与えられたからには、僕らも何かやるべきだよ。活発な意見を期待するね」
9月初めのことだ。奈緒がほとんど間をおかずに一案提示した。相変わらず元気で活発だ。
「そうね、探偵らしくお悩み相談なんかどうかしら」
日向が左右の頬に手の平を当てて賛成する。
「いいですね! それで行きましょう!」
英二が――こいつは日向に惚れているのだ――ぼそりと呟いた。
「悪くないな」
しかし俺は溜め息を吐く。たとえ好きで好きでたまらない奈緒が相手でも、意見は別だ。
「飯田さん、ちょっと無理があるよ。1年生揃いの俺たち相手に、客が悩みを打ち明けるかな? 年下相手に胸襟を開く奴なんかいないと思うけど」
結城が手を挙げた。クールだった彼女も、『探偵部』生活が長くなるうち、徐々にうち解けてきている――と思う。
「では、高級喫茶店などはいかがでしょう?」
純架が彼女の提案に目をぱちくりさせた。最後はまぶたを閉じる。
いや、最後は開けろよ。
「高級? 例えばどんな感じだい?」
「英二様が参加なさるにふさわしい、贅を尽くしたカフェを展開するのです。ブラジル直輸入の生豆を焙煎して手動ミルで挽き、コーヒーとしてお淹れする……。私にお任せくだされば、お客様の好みに合った味に仕上げてみせますよ」
純架は「オレたちひょうきん族」の神様のように、両手で大げさにバツ印を作った。
古過ぎる。
「駄目駄目、それじゃ菅野さんしか活躍できないよ。僕ら『探偵部』全員が役目を背負う感じでいきたいんだよね」
なるほど、言いたいことは分かる。一人がコーヒーを淹れて、他のメンバーは全員給仕ではバランスが悪すぎる。
「それ、あたしも入っとるんか」
ぷかぷか宙に浮いていたまどかが、自分を指差してわくわくしている。純架は微笑んで首肯した。
「もちろん。白石さんも立派な部員だからね」
俺は長机に頬杖をついた。空いている手の平を開く。
「幽霊をどうやって参加させるってんだ? それに、体が透き通ることがばれたらえらい騒ぎになるぞ」
英二が割り込む。名案が思いついたという語勢だった。
「白石の治癒能力は使えないか? おい白石、お前の技はただ傷を治すだけでなく、たとえば血行を良くしたり関節痛を緩和したり出来ないか?」
「どやろか。やったことあらへんからな。じゃ、試しに英二の体を治してみよか」
「えっ、俺?」
提案者のくせに、英二が怯えの色を見せた。豪胆な彼でも、やはり本物のお化けは苦手らしい。
「勘弁しろよ」
「まあまあそう言わんと。すぐ済むから」
まどかは英二のそばに寄ると、彼の額に手をかざした。俺たちの目には、まどかの指が英二の頭にめり込んでいるように見える。
「痛いの痛いの、飛んでけっ」
英二は目をつぶって恐怖に耐えていたが、その顔は安らかなものへと変化していった。結城が心配そうにはらはらと見つめる。
「英二様、大丈夫ですか?」
「いや待て、これは……」
まどかが離れた。英二はすっきりした相貌でまばたきする。頭部の癖毛をかき回した。
「凄いぞ。何だか頭が軽くなった。俺は黒服にマッサージしてもらうときもあるが、それとは雲泥の差だ」
俺はその熱気がこもる感想に口笛を吹いた。
「本当かよ。すげえな」
純架が興奮気味に、チョークで黒板に『第68代横綱・朝青龍』と書きなぐった。
関係ない。
「この治癒能力をお客さんに使えば、ちょっとしたセラピーになるね。上手い使い方はないものだろうか?」
奈緒が妙案を紡ぎ出したか、勢いよく挙手した。若干上ずった声を出す。
「肩叩きよ! 肩叩きなら、お客さんにもばれずに済むわ」
「それだ!」
純架はこの傑作なアイデアに飛びついた。興奮のせいか頬が上気している。
「つまりこうするんだ。衝立か何かでこの教室を二つに仕切り、奥で部員がお客さんに施術する。といってもその人は肩を叩くだけだ。ポイントは、部員と重なった白石さんが、被術者の肩に治癒を行なう点だ。叩かれている人に白石さんの姿を見られることなく、かつ白石さんも出し物に参加できる。まさに一石二鳥だ。ナイスアイデアだよ、飯田さん!」
「えへへ……」
奈緒は照れたような赤い顔で笑った。純架は椅子から離れて一同を見渡す。
「どうだい、飯田さんの話。僕はこれでいきたいと思う。異論があれば今のうちなら受け付けるよ。一回10万円でね」
とんでもない強欲だ。
9月のカレンダーも残り僅かとなった。渋山台高校は例年通り、9月30日と10月1日の二日間、伝統行事の学園祭――名づけて『白鷺祭』――を開催する。今年は最初から数えて40周年目のメモリアルイヤーらしい。
渋山台高校の白鷺祭といえば、県内で知らぬ者はいないほど有名な、それはそれは盛大な催しである――というのは、過去に何度か一般客として遊びに来ていた俺の感想だ。今年は楽しむ側から楽しませる側に立場を変えるというわけで、今からワクワクして仕方がない。もっとも、生徒数は減っているので、往時の賑わいとまではいかないだろうけど。
来たる日に備え、1年から3年の各クラス、並びに各部活動は、一学期末に早々と出し物を決めていた。学園祭は専用の実行委員会を設置するのではなく、生徒会が監督・指揮統括する。彼らはそれぞれのチームの届け出を受理し、各種審議した上で認可を与え、予算を公平に分配していた。
大量の小道具がいる、例えば演劇のような催し物を申請したクラスなどは、夏休み期間中も登校して大小さまざまな雑事に取り組んできたらしい。見上げた根性である。
で、我が1年3組はどうかというと……
「俺に任せろよ、皆」
噂好き・祭り好きの久川浩介が、クラス会議で演説をぶった。今から二ヶ月前、一学期末のことだ。
「実は俺、ダーツがプロ級にうまくてさ。それで考えたんだ。喫茶店をやったろうってな」
どんぐりのような眼、突き出た頬骨、矢印のような鼻の、それほど美男子とも言えない彼だが、クラスの人気は高かった。1年3組の女子のリーダー的存在が奈緒なら、男子のそれは間違いなく久川だ。
委員長の夏島さんが続きを促すと、両手をこすり合わせて笑顔を撒き散らす。
「名づけて『ダーツ喫茶店』。お客さんがダーツで生徒代表と勝負し、勝てば紅茶が無料になる、というわけだ。どうだい、面白そうだろ?」
英二が腕を組んでせせら笑った。動物園で面白い生き物を見ているような趣きである。
「生徒代表が弱ければ一円にもならんぞ」
久川は右上腕に力こぶを作って叩いてみせた。白い歯がこぼれる。
「大丈夫、基本的に俺が投げるからよ。強いぞ、俺は」
三好が噴き出し、あっさり核心を突いた。
「お前がダーツをやりたいだけだろ」
それに引きずられるように、教室中から笑いが起きる。だが久川はめげずに認めた。
「まあそうとも言うな」
黒板前に立つ夏島委員長へ笑顔で目配せする。
「後で投票にかけてくれよ、夏島さん」
「分かりました」
純架は興味を示さず、スプーン曲げにチャレンジしていた。しかし彼の超能力はユリ・ゲラーやMr.マリックに遠く及ばず、どれだけ経っても食器は微動だにしない。やがて飽きたのか、純架は腕力で無理矢理折ろうと躍起になった。
もう超能力じゃねえよ。
結局他に案もなく、久川の要望通り、1年3組はダーツ喫茶店を開くこととなった。提案者は大いに満足し、いかにも楽しそうにダーツの矢を投げる真似をする。
「絶対ウケるものになるぜ。こりゃ間違いなく、最優秀賞の白鷺トロフィーはうちがいただきだな」
俺は初耳の言葉に思わず返した。
「白鷺トロフィー? 何だそりゃ」
久川は腰に両手を当ててふんぞり返る。他人の知らない雑学を披露するときの、彼の癖だった。
「知らないのか? この学園祭ではアンケートで顧客満足度を測って、もっとも優れた催し物に白鷺のトロフィーが与えられるんだ。まさに栄光栄誉の極みってやつさ。ねえ先生?」
「ああ、その通りだ」
宮古先生はうなずいた。気合を入れたらしく、立ち上がって腹から声を出す。
「やるからには勝つぞ、皆んな! どこに出しても恥ずかしくない、立派な店を作るんだ!」
久川がその大音じょうに乗った。一発手を叩き合わせる。
「もちろんですとも! 1年3組、いっちょ頑張ろうぜ!」
せっかくの学園祭である。これは盛り上がるかと思いきや、しかし俺の周りのクラスメイトたちはまばらな拍手でそれに応えるのみだった。
いまいち気の乗らない、中途半端な反応――
ダーツ勝負という特色こそあるものの、それがなければただの喫茶店だ。ありきたりの上に『超』がつく、本気度に欠けた催し物との感は否めない。宮古先生や久川の情熱は、クラスメイトにいまいち伝播したり浸透したりしてはいなかった――いや、俺が何となくそう思っただけなんだけど。
ともかくこうして1年3組は消極的に動き出した。
そして二学期。各クラス・各部活動が学園祭準備に奔走する中、純架は『探偵部』も出し物を用意すべきだと言い出した。
「部室として旧棟1年5組を与えられたからには、僕らも何かやるべきだよ。活発な意見を期待するね」
9月初めのことだ。奈緒がほとんど間をおかずに一案提示した。相変わらず元気で活発だ。
「そうね、探偵らしくお悩み相談なんかどうかしら」
日向が左右の頬に手の平を当てて賛成する。
「いいですね! それで行きましょう!」
英二が――こいつは日向に惚れているのだ――ぼそりと呟いた。
「悪くないな」
しかし俺は溜め息を吐く。たとえ好きで好きでたまらない奈緒が相手でも、意見は別だ。
「飯田さん、ちょっと無理があるよ。1年生揃いの俺たち相手に、客が悩みを打ち明けるかな? 年下相手に胸襟を開く奴なんかいないと思うけど」
結城が手を挙げた。クールだった彼女も、『探偵部』生活が長くなるうち、徐々にうち解けてきている――と思う。
「では、高級喫茶店などはいかがでしょう?」
純架が彼女の提案に目をぱちくりさせた。最後はまぶたを閉じる。
いや、最後は開けろよ。
「高級? 例えばどんな感じだい?」
「英二様が参加なさるにふさわしい、贅を尽くしたカフェを展開するのです。ブラジル直輸入の生豆を焙煎して手動ミルで挽き、コーヒーとしてお淹れする……。私にお任せくだされば、お客様の好みに合った味に仕上げてみせますよ」
純架は「オレたちひょうきん族」の神様のように、両手で大げさにバツ印を作った。
古過ぎる。
「駄目駄目、それじゃ菅野さんしか活躍できないよ。僕ら『探偵部』全員が役目を背負う感じでいきたいんだよね」
なるほど、言いたいことは分かる。一人がコーヒーを淹れて、他のメンバーは全員給仕ではバランスが悪すぎる。
「それ、あたしも入っとるんか」
ぷかぷか宙に浮いていたまどかが、自分を指差してわくわくしている。純架は微笑んで首肯した。
「もちろん。白石さんも立派な部員だからね」
俺は長机に頬杖をついた。空いている手の平を開く。
「幽霊をどうやって参加させるってんだ? それに、体が透き通ることがばれたらえらい騒ぎになるぞ」
英二が割り込む。名案が思いついたという語勢だった。
「白石の治癒能力は使えないか? おい白石、お前の技はただ傷を治すだけでなく、たとえば血行を良くしたり関節痛を緩和したり出来ないか?」
「どやろか。やったことあらへんからな。じゃ、試しに英二の体を治してみよか」
「えっ、俺?」
提案者のくせに、英二が怯えの色を見せた。豪胆な彼でも、やはり本物のお化けは苦手らしい。
「勘弁しろよ」
「まあまあそう言わんと。すぐ済むから」
まどかは英二のそばに寄ると、彼の額に手をかざした。俺たちの目には、まどかの指が英二の頭にめり込んでいるように見える。
「痛いの痛いの、飛んでけっ」
英二は目をつぶって恐怖に耐えていたが、その顔は安らかなものへと変化していった。結城が心配そうにはらはらと見つめる。
「英二様、大丈夫ですか?」
「いや待て、これは……」
まどかが離れた。英二はすっきりした相貌でまばたきする。頭部の癖毛をかき回した。
「凄いぞ。何だか頭が軽くなった。俺は黒服にマッサージしてもらうときもあるが、それとは雲泥の差だ」
俺はその熱気がこもる感想に口笛を吹いた。
「本当かよ。すげえな」
純架が興奮気味に、チョークで黒板に『第68代横綱・朝青龍』と書きなぐった。
関係ない。
「この治癒能力をお客さんに使えば、ちょっとしたセラピーになるね。上手い使い方はないものだろうか?」
奈緒が妙案を紡ぎ出したか、勢いよく挙手した。若干上ずった声を出す。
「肩叩きよ! 肩叩きなら、お客さんにもばれずに済むわ」
「それだ!」
純架はこの傑作なアイデアに飛びついた。興奮のせいか頬が上気している。
「つまりこうするんだ。衝立か何かでこの教室を二つに仕切り、奥で部員がお客さんに施術する。といってもその人は肩を叩くだけだ。ポイントは、部員と重なった白石さんが、被術者の肩に治癒を行なう点だ。叩かれている人に白石さんの姿を見られることなく、かつ白石さんも出し物に参加できる。まさに一石二鳥だ。ナイスアイデアだよ、飯田さん!」
「えへへ……」
奈緒は照れたような赤い顔で笑った。純架は椅子から離れて一同を見渡す。
「どうだい、飯田さんの話。僕はこれでいきたいと思う。異論があれば今のうちなら受け付けるよ。一回10万円でね」
とんでもない強欲だ。
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


嘘つきカウンセラーの饒舌推理
真木ハヌイ
ミステリー
身近な心の問題をテーマにした連作短編。六章構成。狡猾で奇妙なカウンセラーの男が、カウンセリングを通じて相談者たちの心の悩みの正体を解き明かしていく。ただ、それで必ずしも相談者が満足する結果になるとは限らないようで……?(カクヨムにも掲載しています)
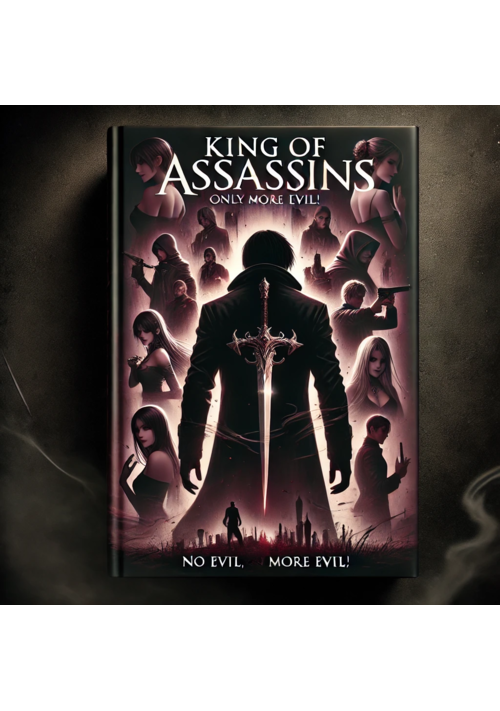

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

時の呪縛
葉羽
ミステリー
山間の孤立した村にある古びた時計塔。かつてこの村は繁栄していたが、失踪事件が連続して発生したことで、村人たちは恐れを抱き、時計塔は放置されたままとなった。17歳の天才高校生・神藤葉羽は、友人に誘われてこの村を訪れることになる。そこで彼は、幼馴染の望月彩由美と共に、村の秘密に迫ることになる。
葉羽と彩由美は、失踪事件に関する不気味な噂を耳にし、時計塔に隠された真実を解明しようとする。しかし、時計塔の内部には、過去の記憶を呼び起こす仕掛けが待ち受けていた。彼らは、時間が歪み、過去の失踪者たちの幻影に直面する中で、次第に自らの心の奥底に潜む恐怖と向き合わせることになる。
果たして、彼らは村の呪いを解き明かし、失踪事件の真相に辿り着けるのか?そして、彼らの友情と恋心は試される。緊迫感あふれる謎解きと心理的恐怖が交錯する本格推理小説。

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。

✖✖✖Sケープゴート
itti(イッチ)
ミステリー
病気を患っていた母が亡くなり、初めて出会った母の弟から手紙を見せられた祐二。
亡くなる前に弟に向けて書かれた手紙には、意味不明な言葉が。祐二の知らない母の秘密とは。
過去の出来事がひとつづつ解き明かされ、祐二は母の生まれた場所に引き寄せられる。
母の過去と、お地蔵さまにまつわる謎を祐二は解き明かせるのでしょうか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















