19 / 67
第十九話 二人きりのお茶会
しおりを挟む
翌日。
アンリは新しい家庭教師からの挨拶を受け、テオフィルと笑顔で別れた。
テオフィルの部屋の扉が閉まると、一抹の寂寥感を覚えた。
このあとグウェナエルとのお茶会の予定がなければ、気鬱な一日を過ごすことになっていたかもしれない。
もしかして、それを見越してお茶会を提案してくれたのだろうか。
――なんて、考えすぎかな。
「アンリ、どうした?」
自分がくすりと笑ったのを見て、隣で一緒に家庭教師の挨拶を受けていたグウェナエルは首を傾げていた。
「いいや、なんでもない。部屋に連れて行ってくれ。エスコートしてくれるのだろう?」
「もちろんだとも」
アンリが促すなりきょとんとしていた間抜け顔はどこへやら、きりっとした顔つきでさっと腕を差し出してくれた。
彼にエスコートされて、お茶会場へと向かった。
お茶会のための専用の部屋には、既にお茶会の準備がされていた。種々の焼き菓子が美しく盛られ、すぐにでもカップにお茶を注げるよう、侍女が控えていた。
二人が席につきお茶が淹れられると、グウェナエルは「二人きりになりたいから」と侍女たちを下がらせた。
「うちの侍女が淹れる茶は絶品でな。遠慮なく飲んでくれ」
グウェナエルは誇らしげに勧めてきた。
「ああ」
アンリはカップを傾け、紅茶を口に含んだ。
すっと芳香が鼻腔に広がり、飲み下すと清涼とした味が喉を通った。なるほど、自慢するだけのことはある。
前々から感じていたが、グウェナエルは使用人を身内のように扱う。早くに父を亡くした彼にとっては、使用人が家族なのかもしれない。
不意に、アンリは酷く羨ましさを覚えた。
父がいるのに孤独な人生を過ごしてきた自分と、大きく違うこと。自分にも家族のような距離感で接してくれる使用人がいれば、どれほどよかったことだろう。
「……美味だな」
身の内に生じた羨望を押し隠し、笑顔で感想を口にした。
「気に入ってもらえてよかった」
アンリの感想を聞いて、彼の尻尾がふぁさふぁさと無邪気に揺れている。
「一度、君とゆっくり話をしたかったのだ」
グウェナエルもまた、ゆっくりと紅茶を飲んだ。
「昨日も言っていたな。どんな話を?」
「例えば……あの日、君は国王陛下に『もう二度と会うことはない』と言っていたな。あれは本気なのか?」
「もちろんだ、もう王城に戻ることはない」
アンリはこくりと頷いた。
王城に戻るくらいならば、野山で生きる方がマシだ。
「では、契約が終わったあとは、君はどうするつもりなのだ?」
「契約が、終わったあと……」
答えようとして、何も答えられないことに気がついた。
契約婚を申し込まれてから今の今まで、ひたすらにテオフィルのことだけを考えてきた。テオフィルから離れてしたいことなど、何もなかった。
「特に何も考えていなかった」
アンリは正直に吐露した。
「そうか」
アンリの返事に、グウェナエルは紅茶を飲んで黙っている。左右の耳があちこちの方向に動いているので、なにやら思案を巡らせているらしいことはわかった。
しばらく待った末に、両耳がピンと前を向いたので、話し出すつもりなのだと予感できた。
「それなら、君がよければなのだが」
こくりと頷き、続きを促す。
「ずっとここにいてくれないだろうか」
申し出に、時が止まったように感じた。
「テオフィルは随分と君に懐いている。それに君も、テオフィルのことをよく見てくれている。もうすっかり本当の親子のようだ。特に行くあてがないのであれば、ずっとここにいてくれた方が、テオフィルも喜ぶ」
「それは……」
「いや、テオフィルを盾にするような言い方は卑怯だったな。オレ自身も、君にずっとここにいてほしいと思っている」
「グウェナエルも……? しかし、私がここに留まっていれば、その……対外的には私がグウェナエルの生涯の伴侶ということになってしまうだろう」
「それで構わない」
「構わない、のか……?」
アンリの声はわずかに震えていた。
急にグウェナエルが、理解不能な人物になってしまったように感じられたからだ。
グウェナエルは亡くなったフィアンセを裏切らないために、契約婚という形を選んだのではないのか。
肉体関係さえなければ、フィアンセが収まるはずだった場所に、自分が収まっても構わないというのか。それは裏切りのうちには入らないのか。
続いて怒りが湧いた。
使用人に家族のように親しみを持って囲まれてきて、亡きフィアンセとの絆もあって、継子のテオフィルにはさっそく懐かれている。
充分恵まれた人生を送っているではないか。この上、対外的な伴侶までほしいというのか。
「……そうか、私が第二王子だから手放すのが惜しくなったのか」
「え?」
「それとも、精霊の呼び手だとわかったからか?」
キトンブルーの瞳で冷たく睨みつけた。
「王族で精霊の呼び手である私が伴侶ならば、他領との力関係で優位に立つことができるのだろうな」
「いや、違う! アンリ、オレはそんなことを念頭に置いて提案したわけでは……!」
「では、どういうつもりだと?」
「それは……」
グウェナエルが口籠ったのを見て、アンリは席を立った。
「申し訳ないが、満腹でな。もう紅茶も菓子もいらない」
もちろん、満腹だというのは嘘だ。
アンリは精いっぱい冷静な振りをして、部屋をあとにしたのだった。
グウェナエルと共通の寝室に戻る気もなく、アンリは中庭に出た。
芝生の上の長椅子に、力なく腰かけた。
それから、後悔した。
なにも怒る必要はなかったかもしれない。まるで自分自身が裏切りを受けた亡きフィアンセであるかのように、怒りを感じてしまった。グウェナエルにとっては、意味不明だっただろう。
彼の提案が多少不誠実な面を含んでいるからといって、なんなのだ。そんなことは自分には関係ないではないか。
自分に行くあてがないのも、できればずっとテオフィルの傍にいたいのも本当だ。彼の提案はむしろ、ありがたいくらいではないか。
テオフィルはあっという間にここに馴染んだのに引き換え、自分の体たらくときたら。楽しみにしていたお茶会を台無しにしてしまった。
テオフィルと比べれば、自分は随分と性格の悪い人間なのかもしれない。
もしかすれば、王城で疎まれていたのは何も精霊が見えるからというだけではないのかもしれない。この性根の悪さとでもいうべきものが滲み出て、嫌われていたのではないだろうか。
キトンブルーの瞳から、一筋の涙が零れ落ちた。
思い悩んだせいだろうか、こめかみが締めつけられるように痛い。なんだか顔が全体的に熱いような気もする。
「あれ、どうしたんだ……?」
気がつけば何人かの精霊が集まってきて、ふよふよとアンリの周囲を漂っていた。またイバラに引っかかってしまった精霊がいるのだろうか。
力なく長椅子の背もたれに身体を預けながら、そうではないと気がついた。
精霊たちは、自分を心配しているのだ。熱が出るときは、こうして決まって精霊たちが心配してくれた。
悩んだせいではなく、実際に体調が悪いのだ。
「まあアンリ様、お庭でお昼寝をなさっていたのですか?」
しばらくして、アンリは侍女頭のエマに発見された。
「このようなところでは身体が冷えてしまい……まあ、大変! 誰か!」
すっかり身体が冷えて高熱を出したアンリは、使用人たちの手によって寝台まで運ばれたのだった。
アンリは新しい家庭教師からの挨拶を受け、テオフィルと笑顔で別れた。
テオフィルの部屋の扉が閉まると、一抹の寂寥感を覚えた。
このあとグウェナエルとのお茶会の予定がなければ、気鬱な一日を過ごすことになっていたかもしれない。
もしかして、それを見越してお茶会を提案してくれたのだろうか。
――なんて、考えすぎかな。
「アンリ、どうした?」
自分がくすりと笑ったのを見て、隣で一緒に家庭教師の挨拶を受けていたグウェナエルは首を傾げていた。
「いいや、なんでもない。部屋に連れて行ってくれ。エスコートしてくれるのだろう?」
「もちろんだとも」
アンリが促すなりきょとんとしていた間抜け顔はどこへやら、きりっとした顔つきでさっと腕を差し出してくれた。
彼にエスコートされて、お茶会場へと向かった。
お茶会のための専用の部屋には、既にお茶会の準備がされていた。種々の焼き菓子が美しく盛られ、すぐにでもカップにお茶を注げるよう、侍女が控えていた。
二人が席につきお茶が淹れられると、グウェナエルは「二人きりになりたいから」と侍女たちを下がらせた。
「うちの侍女が淹れる茶は絶品でな。遠慮なく飲んでくれ」
グウェナエルは誇らしげに勧めてきた。
「ああ」
アンリはカップを傾け、紅茶を口に含んだ。
すっと芳香が鼻腔に広がり、飲み下すと清涼とした味が喉を通った。なるほど、自慢するだけのことはある。
前々から感じていたが、グウェナエルは使用人を身内のように扱う。早くに父を亡くした彼にとっては、使用人が家族なのかもしれない。
不意に、アンリは酷く羨ましさを覚えた。
父がいるのに孤独な人生を過ごしてきた自分と、大きく違うこと。自分にも家族のような距離感で接してくれる使用人がいれば、どれほどよかったことだろう。
「……美味だな」
身の内に生じた羨望を押し隠し、笑顔で感想を口にした。
「気に入ってもらえてよかった」
アンリの感想を聞いて、彼の尻尾がふぁさふぁさと無邪気に揺れている。
「一度、君とゆっくり話をしたかったのだ」
グウェナエルもまた、ゆっくりと紅茶を飲んだ。
「昨日も言っていたな。どんな話を?」
「例えば……あの日、君は国王陛下に『もう二度と会うことはない』と言っていたな。あれは本気なのか?」
「もちろんだ、もう王城に戻ることはない」
アンリはこくりと頷いた。
王城に戻るくらいならば、野山で生きる方がマシだ。
「では、契約が終わったあとは、君はどうするつもりなのだ?」
「契約が、終わったあと……」
答えようとして、何も答えられないことに気がついた。
契約婚を申し込まれてから今の今まで、ひたすらにテオフィルのことだけを考えてきた。テオフィルから離れてしたいことなど、何もなかった。
「特に何も考えていなかった」
アンリは正直に吐露した。
「そうか」
アンリの返事に、グウェナエルは紅茶を飲んで黙っている。左右の耳があちこちの方向に動いているので、なにやら思案を巡らせているらしいことはわかった。
しばらく待った末に、両耳がピンと前を向いたので、話し出すつもりなのだと予感できた。
「それなら、君がよければなのだが」
こくりと頷き、続きを促す。
「ずっとここにいてくれないだろうか」
申し出に、時が止まったように感じた。
「テオフィルは随分と君に懐いている。それに君も、テオフィルのことをよく見てくれている。もうすっかり本当の親子のようだ。特に行くあてがないのであれば、ずっとここにいてくれた方が、テオフィルも喜ぶ」
「それは……」
「いや、テオフィルを盾にするような言い方は卑怯だったな。オレ自身も、君にずっとここにいてほしいと思っている」
「グウェナエルも……? しかし、私がここに留まっていれば、その……対外的には私がグウェナエルの生涯の伴侶ということになってしまうだろう」
「それで構わない」
「構わない、のか……?」
アンリの声はわずかに震えていた。
急にグウェナエルが、理解不能な人物になってしまったように感じられたからだ。
グウェナエルは亡くなったフィアンセを裏切らないために、契約婚という形を選んだのではないのか。
肉体関係さえなければ、フィアンセが収まるはずだった場所に、自分が収まっても構わないというのか。それは裏切りのうちには入らないのか。
続いて怒りが湧いた。
使用人に家族のように親しみを持って囲まれてきて、亡きフィアンセとの絆もあって、継子のテオフィルにはさっそく懐かれている。
充分恵まれた人生を送っているではないか。この上、対外的な伴侶までほしいというのか。
「……そうか、私が第二王子だから手放すのが惜しくなったのか」
「え?」
「それとも、精霊の呼び手だとわかったからか?」
キトンブルーの瞳で冷たく睨みつけた。
「王族で精霊の呼び手である私が伴侶ならば、他領との力関係で優位に立つことができるのだろうな」
「いや、違う! アンリ、オレはそんなことを念頭に置いて提案したわけでは……!」
「では、どういうつもりだと?」
「それは……」
グウェナエルが口籠ったのを見て、アンリは席を立った。
「申し訳ないが、満腹でな。もう紅茶も菓子もいらない」
もちろん、満腹だというのは嘘だ。
アンリは精いっぱい冷静な振りをして、部屋をあとにしたのだった。
グウェナエルと共通の寝室に戻る気もなく、アンリは中庭に出た。
芝生の上の長椅子に、力なく腰かけた。
それから、後悔した。
なにも怒る必要はなかったかもしれない。まるで自分自身が裏切りを受けた亡きフィアンセであるかのように、怒りを感じてしまった。グウェナエルにとっては、意味不明だっただろう。
彼の提案が多少不誠実な面を含んでいるからといって、なんなのだ。そんなことは自分には関係ないではないか。
自分に行くあてがないのも、できればずっとテオフィルの傍にいたいのも本当だ。彼の提案はむしろ、ありがたいくらいではないか。
テオフィルはあっという間にここに馴染んだのに引き換え、自分の体たらくときたら。楽しみにしていたお茶会を台無しにしてしまった。
テオフィルと比べれば、自分は随分と性格の悪い人間なのかもしれない。
もしかすれば、王城で疎まれていたのは何も精霊が見えるからというだけではないのかもしれない。この性根の悪さとでもいうべきものが滲み出て、嫌われていたのではないだろうか。
キトンブルーの瞳から、一筋の涙が零れ落ちた。
思い悩んだせいだろうか、こめかみが締めつけられるように痛い。なんだか顔が全体的に熱いような気もする。
「あれ、どうしたんだ……?」
気がつけば何人かの精霊が集まってきて、ふよふよとアンリの周囲を漂っていた。またイバラに引っかかってしまった精霊がいるのだろうか。
力なく長椅子の背もたれに身体を預けながら、そうではないと気がついた。
精霊たちは、自分を心配しているのだ。熱が出るときは、こうして決まって精霊たちが心配してくれた。
悩んだせいではなく、実際に体調が悪いのだ。
「まあアンリ様、お庭でお昼寝をなさっていたのですか?」
しばらくして、アンリは侍女頭のエマに発見された。
「このようなところでは身体が冷えてしまい……まあ、大変! 誰か!」
すっかり身体が冷えて高熱を出したアンリは、使用人たちの手によって寝台まで運ばれたのだった。
2,140
お気に入りに追加
2,963
あなたにおすすめの小説
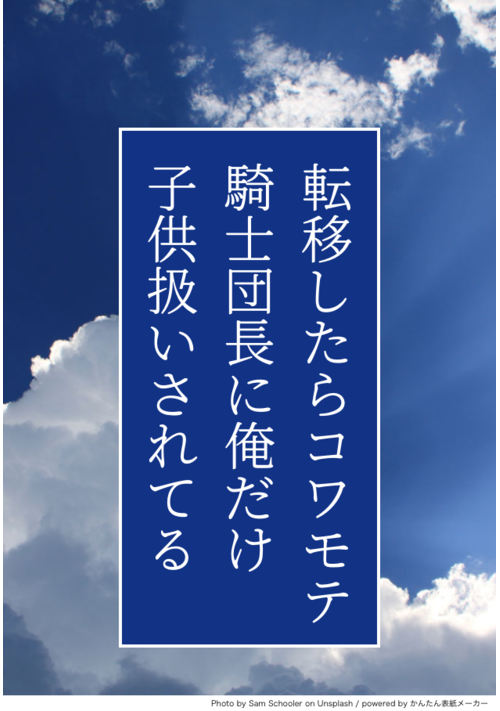
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【完結】愛執 ~愛されたい子供を拾って溺愛したのは邪神でした~
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
「なんだ、お前。鎖で繋がれてるのかよ! ひでぇな」
洞窟の神殿に鎖で繋がれた子供は、愛情も温もりも知らずに育った。
子供が欲しかったのは、自分を抱き締めてくれる腕――誰も与えてくれない温もりをくれたのは、人間ではなくて邪神。人間に害をなすとされた破壊神は、純粋な子供に絆され、子供に名をつけて溺愛し始める。
人のフリを長く続けたが愛情を理解できなかった破壊神と、初めての愛情を貪欲に欲しがる物知らぬ子供。愛を知らぬ者同士が徐々に惹かれ合う、ひたすら甘くて切ない恋物語。
「僕ね、セティのこと大好きだよ」
【注意事項】BL、R15、性的描写あり(※印)
【重複投稿】アルファポリス、カクヨム、小説家になろう、エブリスタ
【完結】2021/9/13
※2020/11/01 エブリスタ BLカテゴリー6位
※2021/09/09 エブリスタ、BLカテゴリー2位

幽閉王子は最強皇子に包まれる
皇洵璃音
BL
魔法使いであるせいで幼少期に幽閉された第三王子のアレクセイ。それから年数が経過し、ある日祖国は滅ぼされてしまう。毛布に包まっていたら、敵の帝国第二皇子のレイナードにより連行されてしまう。処刑場にて皇帝から二つの選択肢を提示されたのだが、二つ目の内容は「レイナードの花嫁になること」だった。初めて人から求められたこともあり、花嫁になることを承諾する。素直で元気いっぱいなド直球第二皇子×愛されることに慣れていない治癒魔法使いの第三王子の恋愛物語。
表紙担当者:白す(しらす)様に描いて頂きました。

転生令息は冒険者を目指す!?
葛城 惶
BL
ある時、日本に大規模災害が発生した。
救助活動中に取り残された少女を助けた自衛官、天海隆司は直後に土砂の崩落に巻き込まれ、意識を失う。
再び目を開けた時、彼は全く知らない世界に転生していた。
異世界で美貌の貴族令息に転生した脳筋の元自衛官は憧れの冒険者になれるのか?!
とってもお馬鹿なコメディです(;^_^A

【完結】最強公爵様に拾われた孤児、俺
福の島
BL
ゴリゴリに前世の記憶がある少年シオンは戸惑う。
目の前にいる男が、この世界最強の公爵様であり、ましてやシオンを養子にしたいとまで言ったのだから。
でも…まぁ…いっか…ご飯美味しいし、風呂は暖かい…
……あれ…?
…やばい…俺めちゃくちゃ公爵様が好きだ…
前置きが長いですがすぐくっつくのでシリアスのシの字もありません。
1万2000字前後です。
攻めのキャラがブレるし若干変態です。
無表情系クール最強公爵様×のんき転生主人公(無自覚美形)
おまけ完結済み

普段「はい」しか言わない僕は、そばに人がいると怖いのに、元マスターが迫ってきて弄ばれている
迷路を跳ぶ狐
BL
全105話*六月十一日に完結する予定です。
読んでいただき、エールやお気に入り、しおりなど、ありがとうございました(*≧∀≦*)
魔法の名手が生み出した失敗作と言われていた僕の処分は、ある日突然決まった。これから捨てられる城に置き去りにされるらしい。
ずっと前から廃棄処分は決まっていたし、殺されるかと思っていたのに、そうならなかったのはよかったんだけど、なぜか僕を嫌っていたはずのマスターまでその城に残っている。
それだけならよかったんだけど、ずっとついてくる。たまにちょっと怖い。
それだけならよかったんだけど、なんだか距離が近い気がする。
勘弁してほしい。
僕は、この人と話すのが、ものすごく怖いんだ。

宰相閣下の執愛は、平民の俺だけに向いている
飛鷹
BL
旧題:平民のはずの俺が、規格外の獣人に絡め取られて番になるまでの話
アホな貴族の両親から生まれた『俺』。色々あって、俺の身分は平民だけど、まぁそんな人生も悪くない。
無事に成長して、仕事に就くこともできたのに。
ここ最近、夢に魘されている。もう一ヶ月もの間、毎晩毎晩………。
朝起きたときには忘れてしまっている夢に疲弊している平民『レイ』と、彼を手に入れたくてウズウズしている獣人のお話。
連載の形にしていますが、攻め視点もUPするためなので、多分全2〜3話で完結予定です。
※6/20追記。
少しレイの過去と気持ちを追加したくて、『連載中』に戻しました。
今迄のお話で完結はしています。なので以降はレイの心情深堀の形となりますので、章を分けて表示します。
1話目はちょっと暗めですが………。
宜しかったらお付き合い下さいませ。
多分、10話前後で終わる予定。軽く読めるように、私としては1話ずつを短めにしております。
ストックが切れるまで、毎日更新予定です。

愛しい番の囲い方。 半端者の僕は最強の竜に愛されているようです
飛鷹
BL
獣人の国にあって、神から見放された存在とされている『後天性獣人』のティア。
獣人の特徴を全く持たずに生まれた故に獣人とは認められず、獣人と認められないから獣神を奉る神殿には入れない。神殿に入れないから婚姻も結べない『半端者』のティアだが、孤児院で共に過ごした幼馴染のアデルに大切に守られて成長していった。
しかし長く共にあったアデルは、『半端者』のティアではなく、別の人を伴侶に選んでしまう。
傷付きながらも「当然の結果」と全てを受け入れ、アデルと別れて獣人の国から出ていく事にしたティア。
蔑まれ冷遇される環境で生きるしかなかったティアが、番いと出会い獣人の姿を取り戻し幸せになるお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















