10 / 67
第十話 森を通って
しおりを挟む
辺境伯領までの道のりは、実に順調に進んでいた。
道中でテオフィルが馬車の揺れに酔ってしまったこともあったが、どこからともなく精霊が飛んできて治してくれた。
旅の生活は快適とは言い難かったが、テオフィルは不快さを覚えるよりも、新しいものだらけの旅を楽しんでくれた。
「テオフィル、遠くに森が見えるだろう」
「うん!」
グウェナエルは、馬車の外に見える景色を指し示した。
「オレたちはこれから、あの森を通る。森を突っ切るように、道が通っているのだ。父の代はこの道がなくて森を迂回しなくてはならず、酷く不便だったと聞く」
彼が示す先には、鬱蒼と生い茂る森が広がっている。あれを迂回するとなれば、旅程がどれだけ伸びることか。
自然が多い場所は精霊が多くいることもあって、森の中を突っ切ることに不安は覚えなかった。
「あの森さえ越えれば、辺境伯領はすぐそこだ」
「あたらしいおうち、つくの?」
「そうだとも」
「わーい、やったー!」
テオフィルは新しい環境に期待を抱けているようだ。
新しい環境の到来に怯えているよりは、ずっといい。あとは本当にテオフィルにとっていい環境になってくれるのを、願うばかりだ。
森が近づくほどにテオフィルの興奮は増し、尻尾のぶんぶんが大きくなっていくのを、アンリは微笑ましく見守っていた。
ほどなくして、馬車は森の中に突入した。
「わああ」
テオフィルが歓声を上げた。
森の中を、たくさんの精霊が飛び回っていたからだ。
大小さまざまな光が飛び回り、あちらこちらへと散っていく光景は幻想的だった。アンリもまた外の光景に視線が釘付けになる。
「みてみて、こびとさん! あ、あれはねこちゃんだよ!」
テオフィルは、アンリよりも精霊が「どんな精霊か」を感じ取る力が強いようだ。
アンリは近くにいる精霊ならなんとなく印象がわかるだけだが、テオフィルはまるで目に見えているようにどんな精霊か言い当ててみせる。いや実際、テオフィルにはアンリよりもはっきりと精霊が見えているのかもしれない。
「オレには見えないが、そんなにたくさんの精霊がいるのか」
「うん! ……あっ」
テオフィルは勢いよく頷いた後、耳をぺたんとさせながら両手で口を塞いだ。不安げに銀色の瞳を揺らしている。
「テオフィル、どうしたの?」
アンリはさりげなく手を伸ばし、テオフィルをそっと抱き寄せて事情を尋ねた。
どんな心配でも遠慮なく口にしてもいい、と伝わるように頭を撫でてあげる。
「……見えること、あんまり言っちゃいけない?」
テオフィルはグウェナエルを上目遣いに見つめながら、そっと聞いた。
見えること、とは「精霊が見えること」の意だろう。
「どうしてそう思ったんだい?」
彼は穏やかに尋ねた。
「だってこびとさんとか、ねこちゃんなんていないって、おかあさまが」
テオフィルは、実の母親に言われていたことを口にした。
「そうか、そんなことを言われていたのか」
グウェナエルは、こくりと頷く。
それから少し考えるかのような間があったあと、口を開いた。
「オレは精霊については詳しくないが、精霊が見えるというのはとても貴重な才能なのだと思う。自らの才を押し殺して生きる必要などない。辺境伯領では、誰にもテオフィルに酷いことは言わせないと約束する」
グウェナエルなりに、テオフィルに対して柔らかい言葉を使おうと努力しているようだ。
「見えること、言っていいの?」
「ああ、いいんだ」
テオフィルに問われ、彼は微笑んだ。
テオフィルの尻尾が、ふぁさふぁさと揺れ始める。
「言っていいんだって! アンリ! アンリも言っていいんだよ!」
テオフィルはこちらを向いて、笑いかけてくれる。
「私も?」
「うん、アンリもいっしょでしょ」
アンリもまた、精霊が見えるのが不気味に見えるのだと気がついてからは、なるべく隠して生きてきた。
テオフィルに言ったことはないのに、そういう生き方をしてきたと彼は自然と感じ取っていたようだ。
「そっか……それは嬉しいことだな」
ぽつり、呟いた。
じわじわと実感が湧いてくる。これからはもう、精霊のことを隠して生きなくていいのだ。
「無論、アンリにも酷いことは言わせない」
グウェナエルが請け負ってくれたので、アンリは目をぱちくりとさせた。まさか彼がそんな風に言ってくれるなんて。
「む、なんだその意外そうな顔は。オレは貴殿、いや、君のことも……」
グウェナエルは何か言おうとしたが、最後まで続かなかった。
「うひゃあ!」
テオフィルが驚いた声を上げた。
馬車が突然加速し出したからだ。
御者が馬たちに鞭打って、全速力を出させているようだ。
「何が起こったんだ?」
アンリは咄嗟にテオフィルを抱き締めた。彼を守るために。
「……熊だ」
馬車の外を見たグウェナエルが呟いた。
「熊!?」
アンリもまた馬車の外を見てみると、黒く大きな塊が、猛然と馬車を追ってきているのが見えた。熊とは、あんなに大きな生き物なのか。
「雪深い地の熊は大きくなるものだ。それにしても馬車を追いかけてくるとは、普通ではないな。人を食った熊かもしれん」
「人を……!?」
人を食べたことのある熊がこの馬車を追いかけてきているだなんて、恐ろしい。テオフィルを抱き締める腕に、思わず力が入る。
馬車を引く二頭の馬は全速力を出しているが、いかんせん馬車が重すぎるようだ。熊を引き離すことはできていない。それどころか、だんだんと距離が縮まってきているようにすら見える。
「人肉の味を覚えた熊は、人を恐れなくなる」
グウェナエルの言葉に、アンリは思わず想像してしまった。鋭い牙に引き裂かれて迎える最後を。
「テオたち、たべられちゃう?」
アンリの腕の中で、テオフィルは涙目で震えていた。
どう言ってあげたらいいかと逡巡したその瞬間、グウェナエルは馬車の中で立ち上がった。
「領主として、危険な獣の放置はできん」
「どうする気なんだ?」
彼は口端を上げ、笑みを見せた。
「案ずることはない。オレの剣にかかれば、熊一匹くらいどうということはない」
たしかに彼は腰に剣を佩いている。
でも、剣一本であんな恐ろしげなものに立ち向かうなんて。
「オレが降りたあとは、しっかり馬車の扉を閉めておけ」
「えっ」
馬車が全速力で走っている最中だというのに馬車の扉を開け放ち、ひらりと飛び降りてしまった。
万一にもテオフィルが馬車から落ちてしまわぬよう、アンリはすぐに扉を閉めた。
グウェナエルは音もなく地面の上に降り立ち、腰の剣を抜いた。刃が光を反射して、鈍く煌めく。
熊は凄まじい速度で、グウェナエルに迫る。
あっという間に彼の目の前に来ると、巨大な身体で立ち上がった。
グウェナエルの背丈は二メートル近くあるというのに、立ち上がった熊の体格はほとんど彼と変わらなかった。なんて大きな熊なのか。
熊はグウェナエルを挽肉にせんと、片手を振り上げる。
もう駄目だ。目を瞑ろうとした瞬間。
「ハァッ!」
刃が翻る。
剣は熊の身体を袈裟切りに切り裂き、なんと斜めに分断してしまった。二つに分かたれた身体から血が噴き出すのを見て、アンリはテオフィルの視界を手で塞いだ。子供に見せるには、あまりに凄惨に過ぎる。
熊だったものはどうと倒れ、ぴくりとも動かなくなった。
「どうしたの? グウェンはどうなったの?」
「大丈夫だよ。しっかり熊をやっつけてくれたよ」
「よかったあ」
御者が馬車を止めてくれたので、グウェナエルはゆっくり歩いて馬車の中に戻ってきた。
「血腥くてすまないな」
血腥いという割には、彼はわずかにしか返り血を浴びていなかった。
「いや、いい。そんなことより、怪我はないのか?」
「大丈夫だ。あの熊に食われた被害者がいるかもしれん。あとで街に着いたら、この街道沿いを調査するように伝えておかないとな」
まさか獣人がこんなに強いだなんて、知らなかった。
生き物の身体を、あんな風に両断できるなんて。身体の内側には、肉だけでなく骨だってあるはずなのに。どんな怪力であれば、そんな芸当が可能だというのか。
頼もしさを感じると同時に、少しも恐怖を感じなかったと言ったら嘘になる。
アンリは自分が獣人について何も知らないことに、ようやく気付いたのだった。
道中でテオフィルが馬車の揺れに酔ってしまったこともあったが、どこからともなく精霊が飛んできて治してくれた。
旅の生活は快適とは言い難かったが、テオフィルは不快さを覚えるよりも、新しいものだらけの旅を楽しんでくれた。
「テオフィル、遠くに森が見えるだろう」
「うん!」
グウェナエルは、馬車の外に見える景色を指し示した。
「オレたちはこれから、あの森を通る。森を突っ切るように、道が通っているのだ。父の代はこの道がなくて森を迂回しなくてはならず、酷く不便だったと聞く」
彼が示す先には、鬱蒼と生い茂る森が広がっている。あれを迂回するとなれば、旅程がどれだけ伸びることか。
自然が多い場所は精霊が多くいることもあって、森の中を突っ切ることに不安は覚えなかった。
「あの森さえ越えれば、辺境伯領はすぐそこだ」
「あたらしいおうち、つくの?」
「そうだとも」
「わーい、やったー!」
テオフィルは新しい環境に期待を抱けているようだ。
新しい環境の到来に怯えているよりは、ずっといい。あとは本当にテオフィルにとっていい環境になってくれるのを、願うばかりだ。
森が近づくほどにテオフィルの興奮は増し、尻尾のぶんぶんが大きくなっていくのを、アンリは微笑ましく見守っていた。
ほどなくして、馬車は森の中に突入した。
「わああ」
テオフィルが歓声を上げた。
森の中を、たくさんの精霊が飛び回っていたからだ。
大小さまざまな光が飛び回り、あちらこちらへと散っていく光景は幻想的だった。アンリもまた外の光景に視線が釘付けになる。
「みてみて、こびとさん! あ、あれはねこちゃんだよ!」
テオフィルは、アンリよりも精霊が「どんな精霊か」を感じ取る力が強いようだ。
アンリは近くにいる精霊ならなんとなく印象がわかるだけだが、テオフィルはまるで目に見えているようにどんな精霊か言い当ててみせる。いや実際、テオフィルにはアンリよりもはっきりと精霊が見えているのかもしれない。
「オレには見えないが、そんなにたくさんの精霊がいるのか」
「うん! ……あっ」
テオフィルは勢いよく頷いた後、耳をぺたんとさせながら両手で口を塞いだ。不安げに銀色の瞳を揺らしている。
「テオフィル、どうしたの?」
アンリはさりげなく手を伸ばし、テオフィルをそっと抱き寄せて事情を尋ねた。
どんな心配でも遠慮なく口にしてもいい、と伝わるように頭を撫でてあげる。
「……見えること、あんまり言っちゃいけない?」
テオフィルはグウェナエルを上目遣いに見つめながら、そっと聞いた。
見えること、とは「精霊が見えること」の意だろう。
「どうしてそう思ったんだい?」
彼は穏やかに尋ねた。
「だってこびとさんとか、ねこちゃんなんていないって、おかあさまが」
テオフィルは、実の母親に言われていたことを口にした。
「そうか、そんなことを言われていたのか」
グウェナエルは、こくりと頷く。
それから少し考えるかのような間があったあと、口を開いた。
「オレは精霊については詳しくないが、精霊が見えるというのはとても貴重な才能なのだと思う。自らの才を押し殺して生きる必要などない。辺境伯領では、誰にもテオフィルに酷いことは言わせないと約束する」
グウェナエルなりに、テオフィルに対して柔らかい言葉を使おうと努力しているようだ。
「見えること、言っていいの?」
「ああ、いいんだ」
テオフィルに問われ、彼は微笑んだ。
テオフィルの尻尾が、ふぁさふぁさと揺れ始める。
「言っていいんだって! アンリ! アンリも言っていいんだよ!」
テオフィルはこちらを向いて、笑いかけてくれる。
「私も?」
「うん、アンリもいっしょでしょ」
アンリもまた、精霊が見えるのが不気味に見えるのだと気がついてからは、なるべく隠して生きてきた。
テオフィルに言ったことはないのに、そういう生き方をしてきたと彼は自然と感じ取っていたようだ。
「そっか……それは嬉しいことだな」
ぽつり、呟いた。
じわじわと実感が湧いてくる。これからはもう、精霊のことを隠して生きなくていいのだ。
「無論、アンリにも酷いことは言わせない」
グウェナエルが請け負ってくれたので、アンリは目をぱちくりとさせた。まさか彼がそんな風に言ってくれるなんて。
「む、なんだその意外そうな顔は。オレは貴殿、いや、君のことも……」
グウェナエルは何か言おうとしたが、最後まで続かなかった。
「うひゃあ!」
テオフィルが驚いた声を上げた。
馬車が突然加速し出したからだ。
御者が馬たちに鞭打って、全速力を出させているようだ。
「何が起こったんだ?」
アンリは咄嗟にテオフィルを抱き締めた。彼を守るために。
「……熊だ」
馬車の外を見たグウェナエルが呟いた。
「熊!?」
アンリもまた馬車の外を見てみると、黒く大きな塊が、猛然と馬車を追ってきているのが見えた。熊とは、あんなに大きな生き物なのか。
「雪深い地の熊は大きくなるものだ。それにしても馬車を追いかけてくるとは、普通ではないな。人を食った熊かもしれん」
「人を……!?」
人を食べたことのある熊がこの馬車を追いかけてきているだなんて、恐ろしい。テオフィルを抱き締める腕に、思わず力が入る。
馬車を引く二頭の馬は全速力を出しているが、いかんせん馬車が重すぎるようだ。熊を引き離すことはできていない。それどころか、だんだんと距離が縮まってきているようにすら見える。
「人肉の味を覚えた熊は、人を恐れなくなる」
グウェナエルの言葉に、アンリは思わず想像してしまった。鋭い牙に引き裂かれて迎える最後を。
「テオたち、たべられちゃう?」
アンリの腕の中で、テオフィルは涙目で震えていた。
どう言ってあげたらいいかと逡巡したその瞬間、グウェナエルは馬車の中で立ち上がった。
「領主として、危険な獣の放置はできん」
「どうする気なんだ?」
彼は口端を上げ、笑みを見せた。
「案ずることはない。オレの剣にかかれば、熊一匹くらいどうということはない」
たしかに彼は腰に剣を佩いている。
でも、剣一本であんな恐ろしげなものに立ち向かうなんて。
「オレが降りたあとは、しっかり馬車の扉を閉めておけ」
「えっ」
馬車が全速力で走っている最中だというのに馬車の扉を開け放ち、ひらりと飛び降りてしまった。
万一にもテオフィルが馬車から落ちてしまわぬよう、アンリはすぐに扉を閉めた。
グウェナエルは音もなく地面の上に降り立ち、腰の剣を抜いた。刃が光を反射して、鈍く煌めく。
熊は凄まじい速度で、グウェナエルに迫る。
あっという間に彼の目の前に来ると、巨大な身体で立ち上がった。
グウェナエルの背丈は二メートル近くあるというのに、立ち上がった熊の体格はほとんど彼と変わらなかった。なんて大きな熊なのか。
熊はグウェナエルを挽肉にせんと、片手を振り上げる。
もう駄目だ。目を瞑ろうとした瞬間。
「ハァッ!」
刃が翻る。
剣は熊の身体を袈裟切りに切り裂き、なんと斜めに分断してしまった。二つに分かたれた身体から血が噴き出すのを見て、アンリはテオフィルの視界を手で塞いだ。子供に見せるには、あまりに凄惨に過ぎる。
熊だったものはどうと倒れ、ぴくりとも動かなくなった。
「どうしたの? グウェンはどうなったの?」
「大丈夫だよ。しっかり熊をやっつけてくれたよ」
「よかったあ」
御者が馬車を止めてくれたので、グウェナエルはゆっくり歩いて馬車の中に戻ってきた。
「血腥くてすまないな」
血腥いという割には、彼はわずかにしか返り血を浴びていなかった。
「いや、いい。そんなことより、怪我はないのか?」
「大丈夫だ。あの熊に食われた被害者がいるかもしれん。あとで街に着いたら、この街道沿いを調査するように伝えておかないとな」
まさか獣人がこんなに強いだなんて、知らなかった。
生き物の身体を、あんな風に両断できるなんて。身体の内側には、肉だけでなく骨だってあるはずなのに。どんな怪力であれば、そんな芸当が可能だというのか。
頼もしさを感じると同時に、少しも恐怖を感じなかったと言ったら嘘になる。
アンリは自分が獣人について何も知らないことに、ようやく気付いたのだった。
2,356
お気に入りに追加
2,963
あなたにおすすめの小説
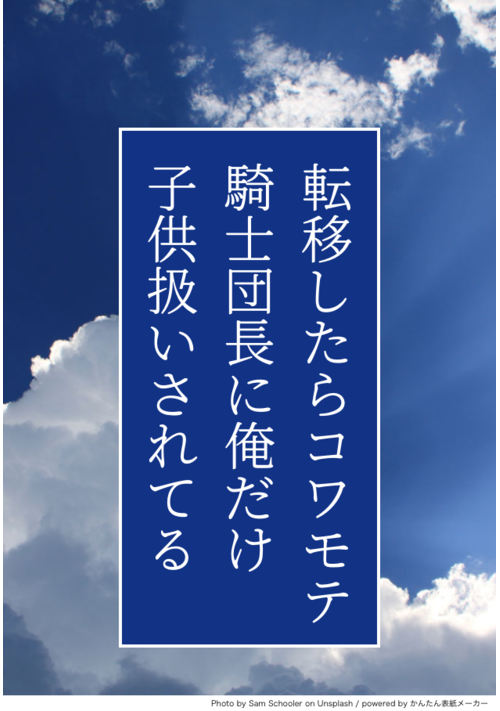
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【完結】愛執 ~愛されたい子供を拾って溺愛したのは邪神でした~
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
「なんだ、お前。鎖で繋がれてるのかよ! ひでぇな」
洞窟の神殿に鎖で繋がれた子供は、愛情も温もりも知らずに育った。
子供が欲しかったのは、自分を抱き締めてくれる腕――誰も与えてくれない温もりをくれたのは、人間ではなくて邪神。人間に害をなすとされた破壊神は、純粋な子供に絆され、子供に名をつけて溺愛し始める。
人のフリを長く続けたが愛情を理解できなかった破壊神と、初めての愛情を貪欲に欲しがる物知らぬ子供。愛を知らぬ者同士が徐々に惹かれ合う、ひたすら甘くて切ない恋物語。
「僕ね、セティのこと大好きだよ」
【注意事項】BL、R15、性的描写あり(※印)
【重複投稿】アルファポリス、カクヨム、小説家になろう、エブリスタ
【完結】2021/9/13
※2020/11/01 エブリスタ BLカテゴリー6位
※2021/09/09 エブリスタ、BLカテゴリー2位

幽閉王子は最強皇子に包まれる
皇洵璃音
BL
魔法使いであるせいで幼少期に幽閉された第三王子のアレクセイ。それから年数が経過し、ある日祖国は滅ぼされてしまう。毛布に包まっていたら、敵の帝国第二皇子のレイナードにより連行されてしまう。処刑場にて皇帝から二つの選択肢を提示されたのだが、二つ目の内容は「レイナードの花嫁になること」だった。初めて人から求められたこともあり、花嫁になることを承諾する。素直で元気いっぱいなド直球第二皇子×愛されることに慣れていない治癒魔法使いの第三王子の恋愛物語。
表紙担当者:白す(しらす)様に描いて頂きました。

転生令息は冒険者を目指す!?
葛城 惶
BL
ある時、日本に大規模災害が発生した。
救助活動中に取り残された少女を助けた自衛官、天海隆司は直後に土砂の崩落に巻き込まれ、意識を失う。
再び目を開けた時、彼は全く知らない世界に転生していた。
異世界で美貌の貴族令息に転生した脳筋の元自衛官は憧れの冒険者になれるのか?!
とってもお馬鹿なコメディです(;^_^A

【完結】最強公爵様に拾われた孤児、俺
福の島
BL
ゴリゴリに前世の記憶がある少年シオンは戸惑う。
目の前にいる男が、この世界最強の公爵様であり、ましてやシオンを養子にしたいとまで言ったのだから。
でも…まぁ…いっか…ご飯美味しいし、風呂は暖かい…
……あれ…?
…やばい…俺めちゃくちゃ公爵様が好きだ…
前置きが長いですがすぐくっつくのでシリアスのシの字もありません。
1万2000字前後です。
攻めのキャラがブレるし若干変態です。
無表情系クール最強公爵様×のんき転生主人公(無自覚美形)
おまけ完結済み

普段「はい」しか言わない僕は、そばに人がいると怖いのに、元マスターが迫ってきて弄ばれている
迷路を跳ぶ狐
BL
全105話*六月十一日に完結する予定です。
読んでいただき、エールやお気に入り、しおりなど、ありがとうございました(*≧∀≦*)
魔法の名手が生み出した失敗作と言われていた僕の処分は、ある日突然決まった。これから捨てられる城に置き去りにされるらしい。
ずっと前から廃棄処分は決まっていたし、殺されるかと思っていたのに、そうならなかったのはよかったんだけど、なぜか僕を嫌っていたはずのマスターまでその城に残っている。
それだけならよかったんだけど、ずっとついてくる。たまにちょっと怖い。
それだけならよかったんだけど、なんだか距離が近い気がする。
勘弁してほしい。
僕は、この人と話すのが、ものすごく怖いんだ。

宰相閣下の執愛は、平民の俺だけに向いている
飛鷹
BL
旧題:平民のはずの俺が、規格外の獣人に絡め取られて番になるまでの話
アホな貴族の両親から生まれた『俺』。色々あって、俺の身分は平民だけど、まぁそんな人生も悪くない。
無事に成長して、仕事に就くこともできたのに。
ここ最近、夢に魘されている。もう一ヶ月もの間、毎晩毎晩………。
朝起きたときには忘れてしまっている夢に疲弊している平民『レイ』と、彼を手に入れたくてウズウズしている獣人のお話。
連載の形にしていますが、攻め視点もUPするためなので、多分全2〜3話で完結予定です。
※6/20追記。
少しレイの過去と気持ちを追加したくて、『連載中』に戻しました。
今迄のお話で完結はしています。なので以降はレイの心情深堀の形となりますので、章を分けて表示します。
1話目はちょっと暗めですが………。
宜しかったらお付き合い下さいませ。
多分、10話前後で終わる予定。軽く読めるように、私としては1話ずつを短めにしております。
ストックが切れるまで、毎日更新予定です。

愛しい番の囲い方。 半端者の僕は最強の竜に愛されているようです
飛鷹
BL
獣人の国にあって、神から見放された存在とされている『後天性獣人』のティア。
獣人の特徴を全く持たずに生まれた故に獣人とは認められず、獣人と認められないから獣神を奉る神殿には入れない。神殿に入れないから婚姻も結べない『半端者』のティアだが、孤児院で共に過ごした幼馴染のアデルに大切に守られて成長していった。
しかし長く共にあったアデルは、『半端者』のティアではなく、別の人を伴侶に選んでしまう。
傷付きながらも「当然の結果」と全てを受け入れ、アデルと別れて獣人の国から出ていく事にしたティア。
蔑まれ冷遇される環境で生きるしかなかったティアが、番いと出会い獣人の姿を取り戻し幸せになるお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















