8 / 53
第8話 王の末息子、ラッセルの憂鬱
しおりを挟む
「セクストン副館長、やっとお会いできて嬉しい。ずっと会いたかったのにこれまで機会を作れなかった」
テレンス公爵夫人クララはそういって、手に持った扇を軽く振った。男子学生のような言葉づかいだが、見た目は優雅な貴婦人である。同色のレースを重ねたドレスは王立図書館の館長室にはあまりそぐわないが、本人は何ひとつ気にしていない。
クララは現王の最初の王女で、末子であるラッセルにとってはけっして頭のあがらない姉だった。ちなみに夫のテレンス公爵も同様らしい。
「こちらこそ、お会いできて光栄に存じます」
対するルークの表情は、緊張しているのかややこわばっている。しかしそれも美貌を損なうことはなく、逆に神秘的な雰囲気をかもしだしている。ラッセルは無意識にみとれていた自分にハッとして、あわてて顔をひきしめた。
「大叔父は学者肌だったから何の違和感もなかったが、弟は迷惑をかけているのではないか? 王の末子が館長になる決まりといっても、ラッセルはどちらかといえば――」クララは眉をひそめて言葉を探した。「そう、筋肉で考えるたぐいの人間だからな」
「姉上!」
ラッセルは思わず声をあげたが、ルークの顔はぴくりとも動かなかったし、ラッセルを見もしなかった。ところが意外にも、その口から出たのは褒め言葉だった。すくなくともラッセルはそう受け取った。
「いいえ、そんなことはありません。館長の決断力や外向的な対応にいつも感心しています」
クララはほう、という表情になった。
「筋肉で考える人間は決断が早かったりするからな」
「なるほど、そういうことでしょうか」
――いや、特に褒められたわけではなさそうだ。
ラッセルは二人の会話に口を挟みたかったが、昔からこの姉の話にはなぜかうまく割り込めないのである。
「ラッセルは子供のころから何かを決めて実行するのだけは早いんだ」
「優柔不断では館長は務まりませんから、その点は適任といえます」
「それはよかった。要するにあいつは体の方が先に動く性質なのさ。ところでルーク、と呼んでもいいだろうか」
「はい、もちろん」
「大叔父は高齢で退いたが、館長は基本的に終身職だ。歴代の副館長は、館長と昵懇の間柄で職務をこなしてきた。不束者の弟で申し訳ないが、よろしく頼む。王国図書館は我が国が古代帝国から継承した伝統で、財産でもある」
クララの言葉にルークの表情は和らいだが、眸には真剣な色がさしている。
「ええ、父からも同じ話を聞きました」
「有名な教授だったな。若い頃、一度だけ王領の近くでお会いしたことがある。休暇であのあたりに来られていたんだ。お茶に招いて学説を拝聴したよ。古代帝国が分裂する中、アルドレイク王国の祖が精霊族の加護を得た理由についての話だった」
ルークは意外そうな目つきになった。
「父にそのような学説が? 知りませんでした。どんな内容でしょうか?」
クララは扇を揺らし、小さく肩をすくめた。
「悪いな、細かいことは忘れてしまった。ただ教授の話を聞いて、王家に伝わるドラゴンの逸話に納得したのを覚えている。ドラゴンといえば、ルークもドラゴンを飼いはじめたと聞いたが?」
「姉上」
今度こそラッセルは口を挟んだ。
「副館長と話せて嬉しいのはわかるが、彼は忙しいんだ。俺も忙しい。姉上にドラゴンを見せる暇も、散歩につきあう暇もない」
クララはラッセルがそこにいることに初めて気づいたような顔をした。むろんわざとである。
「何をいってる。おまえのドラゴンじゃないくせに」
「ああ、副館長のドラゴンだ。しかし副館長のドラゴンは図書館のドラゴンも同然だから、館長の俺にも口出しする権利はある」
「弟よ、堂々と詭弁を吐くな」
「姉上、詭弁は堂々とやるものだ」
微妙な空気が漂ったそのとき、館長室のドアがこんこん、とノックされた。
「ご来客中に申し訳ありません。そちらに副館長はいらっしゃいますか?」
ルークがくるりと背中を向けてドアの方へ行った。呼びにきた職員に耳打ちされて、またラッセルの方を向く。
一瞬ぴたりと視線があった。青い月夜の色をした眸を正面からみてしまい、ラッセルは心臓を鷲掴みにされた気分になった。ふたりは同時に視線をそらした。
「申し訳ありません、至急の用事ができましたのでこれで失礼いたします。公爵夫人、申し訳ありませんが、またお目にかかる機会がありましたら」
クララは鷹揚に扇を振った。
「いや、ありがとう。今日は話せて嬉しかった」
ルークは一礼して館長室を出ていった。ドアが閉まったとたん、クララは扇をデスクに放り投げ、わざとらしく両手を広げてあきれ顔をしてみせた。およそ貴婦人らしからぬ仕草である。
「噂通り凄まじい美人だな! しかしおまえたち、どうしてもっと近寄らない。 大叔父上と前の副館長はいつもぺったりくっついていたらしいじゃないか。膝に乗りそうな雰囲気だったと」
ラッセルは小さくため息をついた。
「姉上、昼間からそういう冗談はよしてくれ。それに大叔父上とちがって、俺とルークは恋人でも伴侶でもない」
「ちがうのか?」
「……いまのところ」
そしてこの先も。かつて学寮仲間に仕掛けられた悪ふざけの顛末がラッセルの脳裏をよぎったが、クララにそれがわかるはずもない。
「しっかりしろ、王の末息子」
クララはラッセルの複雑な胸のうちを多少は察したようだったが、それでも無慈悲に弟を叱咤した。
「彼は図書館の申し子と呼ばれているそうじゃないか」
「ちがう、いとし子だ」
「似たようなものだ。筋肉頼みのおまえにあれ以上の相手は望めない。おまえだってそう思っているんだろう?」
「姉上」
「やはり来てよかった。おまえに縁談はもちこまないことにする」
「縁談?」
ラッセルは目を丸くして聞き返したが、クララはデスクにかがみこむと、さっき放り投げた扇を拾った。
「ああ、第七王子くらいがちょうどいいと考える輩が夫に話を持ってくるんだ。よりどりみどりといっていいくらいだ。おまえも興味があるかもしれないと思ったが、必要なかった」
「……」
「それに王家の末子が図書館長になる伝統も、本来娶るべきとされた伴侶がみつからなくなってから始まったものだ。おまえが娶るべきなのは――」
クララは急に言葉をとめた。
「何の音だ?」
どこかでカリカリとひっかくような音がしている。さっきルークが出て行ったドアの方向でも窓の方向でもない。
ラッセルはあたりをみまわし、大股でもう一方の壁へ近づいて、続き部屋のドアを開けた。そのとたん目の前をびゅん、と何かが横切った。
「ラッセル?」
「……いや、姉上。問題ない」
ラッセルは静かにドアを閉めた。ひっかくような音はもう聞こえなくなっていた。
テレンス公爵夫人クララはそういって、手に持った扇を軽く振った。男子学生のような言葉づかいだが、見た目は優雅な貴婦人である。同色のレースを重ねたドレスは王立図書館の館長室にはあまりそぐわないが、本人は何ひとつ気にしていない。
クララは現王の最初の王女で、末子であるラッセルにとってはけっして頭のあがらない姉だった。ちなみに夫のテレンス公爵も同様らしい。
「こちらこそ、お会いできて光栄に存じます」
対するルークの表情は、緊張しているのかややこわばっている。しかしそれも美貌を損なうことはなく、逆に神秘的な雰囲気をかもしだしている。ラッセルは無意識にみとれていた自分にハッとして、あわてて顔をひきしめた。
「大叔父は学者肌だったから何の違和感もなかったが、弟は迷惑をかけているのではないか? 王の末子が館長になる決まりといっても、ラッセルはどちらかといえば――」クララは眉をひそめて言葉を探した。「そう、筋肉で考えるたぐいの人間だからな」
「姉上!」
ラッセルは思わず声をあげたが、ルークの顔はぴくりとも動かなかったし、ラッセルを見もしなかった。ところが意外にも、その口から出たのは褒め言葉だった。すくなくともラッセルはそう受け取った。
「いいえ、そんなことはありません。館長の決断力や外向的な対応にいつも感心しています」
クララはほう、という表情になった。
「筋肉で考える人間は決断が早かったりするからな」
「なるほど、そういうことでしょうか」
――いや、特に褒められたわけではなさそうだ。
ラッセルは二人の会話に口を挟みたかったが、昔からこの姉の話にはなぜかうまく割り込めないのである。
「ラッセルは子供のころから何かを決めて実行するのだけは早いんだ」
「優柔不断では館長は務まりませんから、その点は適任といえます」
「それはよかった。要するにあいつは体の方が先に動く性質なのさ。ところでルーク、と呼んでもいいだろうか」
「はい、もちろん」
「大叔父は高齢で退いたが、館長は基本的に終身職だ。歴代の副館長は、館長と昵懇の間柄で職務をこなしてきた。不束者の弟で申し訳ないが、よろしく頼む。王国図書館は我が国が古代帝国から継承した伝統で、財産でもある」
クララの言葉にルークの表情は和らいだが、眸には真剣な色がさしている。
「ええ、父からも同じ話を聞きました」
「有名な教授だったな。若い頃、一度だけ王領の近くでお会いしたことがある。休暇であのあたりに来られていたんだ。お茶に招いて学説を拝聴したよ。古代帝国が分裂する中、アルドレイク王国の祖が精霊族の加護を得た理由についての話だった」
ルークは意外そうな目つきになった。
「父にそのような学説が? 知りませんでした。どんな内容でしょうか?」
クララは扇を揺らし、小さく肩をすくめた。
「悪いな、細かいことは忘れてしまった。ただ教授の話を聞いて、王家に伝わるドラゴンの逸話に納得したのを覚えている。ドラゴンといえば、ルークもドラゴンを飼いはじめたと聞いたが?」
「姉上」
今度こそラッセルは口を挟んだ。
「副館長と話せて嬉しいのはわかるが、彼は忙しいんだ。俺も忙しい。姉上にドラゴンを見せる暇も、散歩につきあう暇もない」
クララはラッセルがそこにいることに初めて気づいたような顔をした。むろんわざとである。
「何をいってる。おまえのドラゴンじゃないくせに」
「ああ、副館長のドラゴンだ。しかし副館長のドラゴンは図書館のドラゴンも同然だから、館長の俺にも口出しする権利はある」
「弟よ、堂々と詭弁を吐くな」
「姉上、詭弁は堂々とやるものだ」
微妙な空気が漂ったそのとき、館長室のドアがこんこん、とノックされた。
「ご来客中に申し訳ありません。そちらに副館長はいらっしゃいますか?」
ルークがくるりと背中を向けてドアの方へ行った。呼びにきた職員に耳打ちされて、またラッセルの方を向く。
一瞬ぴたりと視線があった。青い月夜の色をした眸を正面からみてしまい、ラッセルは心臓を鷲掴みにされた気分になった。ふたりは同時に視線をそらした。
「申し訳ありません、至急の用事ができましたのでこれで失礼いたします。公爵夫人、申し訳ありませんが、またお目にかかる機会がありましたら」
クララは鷹揚に扇を振った。
「いや、ありがとう。今日は話せて嬉しかった」
ルークは一礼して館長室を出ていった。ドアが閉まったとたん、クララは扇をデスクに放り投げ、わざとらしく両手を広げてあきれ顔をしてみせた。およそ貴婦人らしからぬ仕草である。
「噂通り凄まじい美人だな! しかしおまえたち、どうしてもっと近寄らない。 大叔父上と前の副館長はいつもぺったりくっついていたらしいじゃないか。膝に乗りそうな雰囲気だったと」
ラッセルは小さくため息をついた。
「姉上、昼間からそういう冗談はよしてくれ。それに大叔父上とちがって、俺とルークは恋人でも伴侶でもない」
「ちがうのか?」
「……いまのところ」
そしてこの先も。かつて学寮仲間に仕掛けられた悪ふざけの顛末がラッセルの脳裏をよぎったが、クララにそれがわかるはずもない。
「しっかりしろ、王の末息子」
クララはラッセルの複雑な胸のうちを多少は察したようだったが、それでも無慈悲に弟を叱咤した。
「彼は図書館の申し子と呼ばれているそうじゃないか」
「ちがう、いとし子だ」
「似たようなものだ。筋肉頼みのおまえにあれ以上の相手は望めない。おまえだってそう思っているんだろう?」
「姉上」
「やはり来てよかった。おまえに縁談はもちこまないことにする」
「縁談?」
ラッセルは目を丸くして聞き返したが、クララはデスクにかがみこむと、さっき放り投げた扇を拾った。
「ああ、第七王子くらいがちょうどいいと考える輩が夫に話を持ってくるんだ。よりどりみどりといっていいくらいだ。おまえも興味があるかもしれないと思ったが、必要なかった」
「……」
「それに王家の末子が図書館長になる伝統も、本来娶るべきとされた伴侶がみつからなくなってから始まったものだ。おまえが娶るべきなのは――」
クララは急に言葉をとめた。
「何の音だ?」
どこかでカリカリとひっかくような音がしている。さっきルークが出て行ったドアの方向でも窓の方向でもない。
ラッセルはあたりをみまわし、大股でもう一方の壁へ近づいて、続き部屋のドアを開けた。そのとたん目の前をびゅん、と何かが横切った。
「ラッセル?」
「……いや、姉上。問題ない」
ラッセルは静かにドアを閉めた。ひっかくような音はもう聞こえなくなっていた。
819
お気に入りに追加
1,292
あなたにおすすめの小説

俺は北国の王子の失脚を狙う悪の側近に転生したらしいが、寒いのは苦手なのでトンズラします
椿谷あずる
BL
ここはとある北の国。綺麗な金髪碧眼のイケメン王子様の側近に転生した俺は、どうやら彼を失脚させようと陰謀を張り巡らせていたらしい……。いやいや一切興味がないし!寒いところ嫌いだし!よし、やめよう!
こうして俺は逃亡することに決めた。
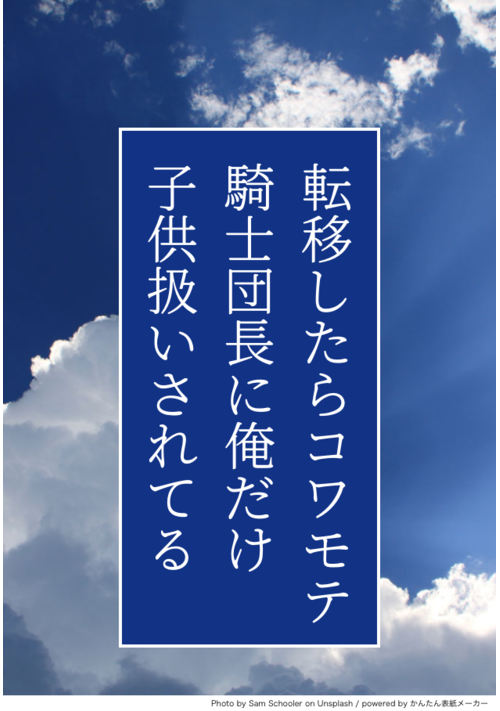
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

そばかす糸目はのんびりしたい
楢山幕府
BL
由緒ある名家の末っ子として生まれたユージン。
母親が後妻で、眉目秀麗な直系の遺伝を受け継がなかったことから、一族からは空気として扱われていた。
ただ一人、溺愛してくる老いた父親を除いて。
ユージンは、のんびりするのが好きだった。
いつでも、のんびりしたいと思っている。
でも何故か忙しい。
ひとたび出張へ出れば、冒険者に囲まれる始末。
いつになったら、のんびりできるのか。もう開き直って、のんびりしていいのか。
果たして、そばかす糸目はのんびりできるのか。
懐かれ体質が好きな方向けです。今のところ主人公は、のんびり重視の恋愛未満です。
全17話、約6万文字。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。


挙式後すぐに離婚届を手渡された私は、この結婚は予め捨てられることが確定していた事実を知らされました
結城芙由奈@12/27電子書籍配信
恋愛
【結婚した日に、「君にこれを預けておく」と離婚届を手渡されました】
今日、私は子供の頃からずっと大好きだった人と結婚した。しかし、式の後に絶望的な事を彼に言われた。
「ごめん、本当は君とは結婚したくなかったんだ。これを預けておくから、その気になったら提出してくれ」
そう言って手渡されたのは何と離婚届けだった。
そしてどこまでも冷たい態度の夫の行動に傷つけられていく私。
けれどその裏には私の知らない、ある深い事情が隠されていた。
その真意を知った時、私は―。
※暫く鬱展開が続きます
※他サイトでも投稿中

幽閉王子は最強皇子に包まれる
皇洵璃音
BL
魔法使いであるせいで幼少期に幽閉された第三王子のアレクセイ。それから年数が経過し、ある日祖国は滅ぼされてしまう。毛布に包まっていたら、敵の帝国第二皇子のレイナードにより連行されてしまう。処刑場にて皇帝から二つの選択肢を提示されたのだが、二つ目の内容は「レイナードの花嫁になること」だった。初めて人から求められたこともあり、花嫁になることを承諾する。素直で元気いっぱいなド直球第二皇子×愛されることに慣れていない治癒魔法使いの第三王子の恋愛物語。
表紙担当者:白す(しらす)様に描いて頂きました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















