18 / 34
九月九日 徳郁とサン、河原を散歩する
しおりを挟む
「きら、どうしたの……げんき、ない」
リビングで考え込んでいる徳郁の耳に、サンの声が聞こえてきた。顔を上げると、サンがこちらを見ている。彼女なりに心配してくれているようだ。さらに、クロベエとシロスケも、顔を上げてこちらを見ている。
「ああ、大丈夫だよ。心配してくれて、ありがとうな」
そう言って微笑んだ。しかし、不安は消えなかった。
昨日、藤村正人から聞いた話が、頭から離れてくれない。旧三日月村での騒ぎ。しかも裏社会の人間が、血眼になって何者かを探している。
それらの事態と、サンは関係あるのだろうか?
そうした疑問が頭を離れてくれず、朝からずっと考え込んでいた。
「きら、だいじょうぶ。きら、へいき」
不意に、サンが手を伸ばし頭を撫でてきた。徳郁は不意を突かれ、反射的に顔をしかめる。いつの間にか、サンは彼のそばに来ていたのだ。
徳郁の反応を見た彼女ほ、びくりとなり手を引っ込めた。
「きら、ごめん」
すまなそうな表情で頭を下げる。徳郁の反応を見て、自身が不快な思いをさせたと誤解しているらしい。
徳郁ほ、慌ててかぶりを振った。サンは悪くない。むしろ、悪いのは自分なのだ。うろたえた挙げ句、妙なことを口走っていた。
「違うんだよ。サンは悪くない。それより、今から一緒に外を歩かないか?」
直後、かーっと赤面していた。自分は、何を言っているのだろう。なぜ今、一瞬に外を歩かなければならないのだ。彼は、己のコミュニケーション能力のなさを痛烈に感じていた。
ところが、サンは嬉しそうに笑みを浮かべる。
「そと、あるく。きらと、いっしょ……そと、あるく。うれしい。いこう、いこう」
妙な成り行きで、徳郁はサンと一緒に林の中を歩いていた。悩んでいる間に、昼になっており太陽は高く昇っている。いい天気だ。
後ろからは、クロベエとシロスケがのそのそ付いて来ている。まるで、サンの忠実なる付き人のようだ。不思議な話である。シロスケもクロベエも、人に付いて歩くようなタイプではなかったはずだ。
サンには、奇妙な力がある。クロベエとシロスケは、今や完全にこの少女に懐いてしまっている。古い付き合いであるはずの自分に対するよりも、ずっと忠誠心を持っているように見える。しかも、意思の疎通まで出来ているらしい。プロの動物調教師でさえ、こんな真似は出来ないだろう。
徳郁がそんなことを思っていた時、不意にサンが手を握ってきた。ドキリとなるが、サンはこちらの心境などお構い無しだ。ニコニコしながら手を握ってくる。その不思議な色の瞳には、自分への純粋な親愛の情があった。
徳郁の頬が、またしても紅潮する。耳まで赤く染まるのを感じながらも、彼はサンの手を握り返した。
「きら、やさしい……から、だいすき」
たどたどしい口調で、語りかけてくるサン。徳郁はうろたえながらも、言葉を返す。
「あ、ああ。俺も好きだよ」
やがて二人と二匹は、河原にやって来た。徳郁とサンが出会った場所である。
すると、シロスケの態度が一変する。大はしゃぎで、川の周辺を走り出したのだ。
「お、おいシロスケ、あんまり騒ぐなよ」
徳郁が声を掛けるが、シロスケは聞く耳を持たなかった。興奮した様子ではあはあ息を荒げながら、一心不乱に河原を走り回っている。
唖然としている徳郁を尻目に、シロスケの動きはさらに激しくなる。いきなり川の中に飛び込み、じゃぶじゃぶと泳ぎだしたのだ。
一方、クロベエはサンの足元にいる。尻を地面に着け、お行儀よく前足を揃えた姿勢だ。尻尾を緩やかに動かしながら、サンの顔をじっと見ていた。時おり、小馬鹿にしているかのような表情でシロスケにも視線を向ける。
サンはというと、ニコニコしながら周りを見回している。嬉しくてたまらない、といった表情だ。
「サン、楽しいか?」
徳郁が尋ねると、サンは嬉しそうに頷いた。直後、その場に座り込む。つられて、徳郁も腰を下ろした。
「うん、たのしい。みんな、すき。いっしょに、いる。うれしい、たのしい」
横から語りかけてきたサン。彼女の操る言葉はたどたどしいが、それでも上手くなってきている。一日ずっとテレビを観て、そこから学習しているのだろう。
ふと、徳郁の頭にある考えが浮かぶ。サンは、常識はないが生活に必要なことは知っている。風呂、トイレの使い方、テレビの電源を入れる方法などなど。それらの知識は、何者かが教えたのだろう。
その何者かは、裏社会とかかわりのある人間なのではないか。ある日、血が流れるような事件に巻き込まれてしまい、サンを逃がし本人は死んだ。出会った時に付いていた血は、その時に付着したものかもしれない。そして、サンの親代わりの人間を殺した連中は、口封じのためにサンを探しているのではないか。
もし、徳郁の家にサンがいることを知られたら……その時は、どうすればいいのだろう。
サンを守るため、裏社会の連中を敵に回すのか?
自問自答する徳郁だったが、そんなものはお構い無しなのがシロスケであった。大はしゃぎで川の中で暴れていたかと思うと、気が済んだらしく上がって来たのだ。
シロスケはいったん大きく体を震わせ、体から水滴を弾き飛ばした。直後、サンめがけて走り寄ってくる──
そんな白犬の行動に、クロベエが反応した。唸り声を上げたかと思うと、シロスケの顔面に前足の一撃を食らわす。一瞬にして、その場の空気は変化した。
シロスケを睨み、背中の毛を逆立てながら威嚇の唸り声を上げるクロベエだったが、シロスケも怯む気配がない。鼻に皺を寄せて牙を剥き出しながら、クロベエを威嚇している。今にも殺し合いが始まりそうだ。せっかくの平和な空気がぶち壊しである。
「お、おい……」
止めに入ろうと、徳郁は立ち上がった。するも、サンが両者の方を向き口を開く。
「くろべえ、しろすけ。けんか、だめ。なかよく、するの」
彼女が言葉を発したとたん、二匹はうって変わっておとなしくなった。クロベエは喉をゴロゴロ鳴らしながら、サンの手に頬を擦り寄せていく。一方、シロスケもその場に伏せ、大人しくなった。
徳郁は思わず苦笑した。見事としか言いようがない。サーカス団の猛獣使いでも、このような真似は出来ないであろう。
「サン、お前は本当に凄いな」
そう言うと、サンは嬉しそうに微笑む。
「うん、さん、すごい」
二人と二匹は、河原にて寄り添っていた。クロベエとシロスケは、先ほどのいさかいが嘘のように大人しくしている。クロベエは仰向けに寝そべり、シロスケは地面に顎を付けていた。
二匹に挟まれた形のサンは、川を見ながらニコニコしている。時おり手を伸ばし、クロベエとシロスケを撫でていた。
そんな光景を見ているうちに、徳郁は満ち足りた気分になっていた。
このままずっと、サンやクロベエやシロスケたちと一緒に暮らしていたい。
もし願いが叶うなら……誰にも邪魔されることなく、静かに生活していたい。
そのためならば、俺は戦う。
サンと暮らすために、誰が相手だろうと戦う。
リビングで考え込んでいる徳郁の耳に、サンの声が聞こえてきた。顔を上げると、サンがこちらを見ている。彼女なりに心配してくれているようだ。さらに、クロベエとシロスケも、顔を上げてこちらを見ている。
「ああ、大丈夫だよ。心配してくれて、ありがとうな」
そう言って微笑んだ。しかし、不安は消えなかった。
昨日、藤村正人から聞いた話が、頭から離れてくれない。旧三日月村での騒ぎ。しかも裏社会の人間が、血眼になって何者かを探している。
それらの事態と、サンは関係あるのだろうか?
そうした疑問が頭を離れてくれず、朝からずっと考え込んでいた。
「きら、だいじょうぶ。きら、へいき」
不意に、サンが手を伸ばし頭を撫でてきた。徳郁は不意を突かれ、反射的に顔をしかめる。いつの間にか、サンは彼のそばに来ていたのだ。
徳郁の反応を見た彼女ほ、びくりとなり手を引っ込めた。
「きら、ごめん」
すまなそうな表情で頭を下げる。徳郁の反応を見て、自身が不快な思いをさせたと誤解しているらしい。
徳郁ほ、慌ててかぶりを振った。サンは悪くない。むしろ、悪いのは自分なのだ。うろたえた挙げ句、妙なことを口走っていた。
「違うんだよ。サンは悪くない。それより、今から一緒に外を歩かないか?」
直後、かーっと赤面していた。自分は、何を言っているのだろう。なぜ今、一瞬に外を歩かなければならないのだ。彼は、己のコミュニケーション能力のなさを痛烈に感じていた。
ところが、サンは嬉しそうに笑みを浮かべる。
「そと、あるく。きらと、いっしょ……そと、あるく。うれしい。いこう、いこう」
妙な成り行きで、徳郁はサンと一緒に林の中を歩いていた。悩んでいる間に、昼になっており太陽は高く昇っている。いい天気だ。
後ろからは、クロベエとシロスケがのそのそ付いて来ている。まるで、サンの忠実なる付き人のようだ。不思議な話である。シロスケもクロベエも、人に付いて歩くようなタイプではなかったはずだ。
サンには、奇妙な力がある。クロベエとシロスケは、今や完全にこの少女に懐いてしまっている。古い付き合いであるはずの自分に対するよりも、ずっと忠誠心を持っているように見える。しかも、意思の疎通まで出来ているらしい。プロの動物調教師でさえ、こんな真似は出来ないだろう。
徳郁がそんなことを思っていた時、不意にサンが手を握ってきた。ドキリとなるが、サンはこちらの心境などお構い無しだ。ニコニコしながら手を握ってくる。その不思議な色の瞳には、自分への純粋な親愛の情があった。
徳郁の頬が、またしても紅潮する。耳まで赤く染まるのを感じながらも、彼はサンの手を握り返した。
「きら、やさしい……から、だいすき」
たどたどしい口調で、語りかけてくるサン。徳郁はうろたえながらも、言葉を返す。
「あ、ああ。俺も好きだよ」
やがて二人と二匹は、河原にやって来た。徳郁とサンが出会った場所である。
すると、シロスケの態度が一変する。大はしゃぎで、川の周辺を走り出したのだ。
「お、おいシロスケ、あんまり騒ぐなよ」
徳郁が声を掛けるが、シロスケは聞く耳を持たなかった。興奮した様子ではあはあ息を荒げながら、一心不乱に河原を走り回っている。
唖然としている徳郁を尻目に、シロスケの動きはさらに激しくなる。いきなり川の中に飛び込み、じゃぶじゃぶと泳ぎだしたのだ。
一方、クロベエはサンの足元にいる。尻を地面に着け、お行儀よく前足を揃えた姿勢だ。尻尾を緩やかに動かしながら、サンの顔をじっと見ていた。時おり、小馬鹿にしているかのような表情でシロスケにも視線を向ける。
サンはというと、ニコニコしながら周りを見回している。嬉しくてたまらない、といった表情だ。
「サン、楽しいか?」
徳郁が尋ねると、サンは嬉しそうに頷いた。直後、その場に座り込む。つられて、徳郁も腰を下ろした。
「うん、たのしい。みんな、すき。いっしょに、いる。うれしい、たのしい」
横から語りかけてきたサン。彼女の操る言葉はたどたどしいが、それでも上手くなってきている。一日ずっとテレビを観て、そこから学習しているのだろう。
ふと、徳郁の頭にある考えが浮かぶ。サンは、常識はないが生活に必要なことは知っている。風呂、トイレの使い方、テレビの電源を入れる方法などなど。それらの知識は、何者かが教えたのだろう。
その何者かは、裏社会とかかわりのある人間なのではないか。ある日、血が流れるような事件に巻き込まれてしまい、サンを逃がし本人は死んだ。出会った時に付いていた血は、その時に付着したものかもしれない。そして、サンの親代わりの人間を殺した連中は、口封じのためにサンを探しているのではないか。
もし、徳郁の家にサンがいることを知られたら……その時は、どうすればいいのだろう。
サンを守るため、裏社会の連中を敵に回すのか?
自問自答する徳郁だったが、そんなものはお構い無しなのがシロスケであった。大はしゃぎで川の中で暴れていたかと思うと、気が済んだらしく上がって来たのだ。
シロスケはいったん大きく体を震わせ、体から水滴を弾き飛ばした。直後、サンめがけて走り寄ってくる──
そんな白犬の行動に、クロベエが反応した。唸り声を上げたかと思うと、シロスケの顔面に前足の一撃を食らわす。一瞬にして、その場の空気は変化した。
シロスケを睨み、背中の毛を逆立てながら威嚇の唸り声を上げるクロベエだったが、シロスケも怯む気配がない。鼻に皺を寄せて牙を剥き出しながら、クロベエを威嚇している。今にも殺し合いが始まりそうだ。せっかくの平和な空気がぶち壊しである。
「お、おい……」
止めに入ろうと、徳郁は立ち上がった。するも、サンが両者の方を向き口を開く。
「くろべえ、しろすけ。けんか、だめ。なかよく、するの」
彼女が言葉を発したとたん、二匹はうって変わっておとなしくなった。クロベエは喉をゴロゴロ鳴らしながら、サンの手に頬を擦り寄せていく。一方、シロスケもその場に伏せ、大人しくなった。
徳郁は思わず苦笑した。見事としか言いようがない。サーカス団の猛獣使いでも、このような真似は出来ないであろう。
「サン、お前は本当に凄いな」
そう言うと、サンは嬉しそうに微笑む。
「うん、さん、すごい」
二人と二匹は、河原にて寄り添っていた。クロベエとシロスケは、先ほどのいさかいが嘘のように大人しくしている。クロベエは仰向けに寝そべり、シロスケは地面に顎を付けていた。
二匹に挟まれた形のサンは、川を見ながらニコニコしている。時おり手を伸ばし、クロベエとシロスケを撫でていた。
そんな光景を見ているうちに、徳郁は満ち足りた気分になっていた。
このままずっと、サンやクロベエやシロスケたちと一緒に暮らしていたい。
もし願いが叶うなら……誰にも邪魔されることなく、静かに生活していたい。
そのためならば、俺は戦う。
サンと暮らすために、誰が相手だろうと戦う。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る



長く短い真夏の殺意
神原オホカミ【書籍発売中】
SF
人間を襲わないはずのロボットによる殺人事件。その犯行の動機と真実――
とある真夏の昼下がり、惨殺された男性の死体が見つかった。
犯人は、人間を襲わないはずの執事型ロボット。
その犯行の動機と真実とは……?
◆表紙画像は簡単表紙メーカー様で作成しています。
◆無断転写や内容の模倣はご遠慮ください。
◆文章をAI学習に使うことは絶対にしないでください。
◆アルファポリスさん/エブリスタさん/カクヨムさん/なろうさんで掲載してます。
〇構想執筆:2020年、改稿投稿:2024年

170≧の生命の歴史
輪島ライ
SF
「私、身長が170センチない人とはお付き合いしたくないんです。」 そう言われて交際を断られた男の屈辱から、新たな生命の歴史が始まる。
※この作品は「小説家になろう」「アルファポリス」「カクヨム」「エブリスタ」に投稿しています。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。
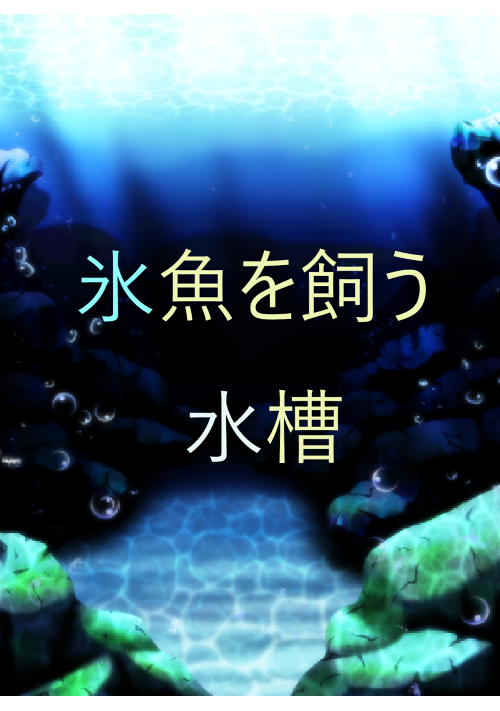
氷魚を飼う水槽 §社会倫理を逸脱した遺伝子実験は……§【完結】
竹比古
SF
サンフランシスコの精神病院に務める青年精神科医、椎名涼は、JNTバイオメディカル研究所に籍を置く女性科学者、ドナを送った帰りに、浮世離れした少年が検査衣姿で車に忍び込んでいるのを見つける。その少年は自分のことを何も語らず、外の世界のことも全く知らない謎の少年だった。検査衣姿でいたことから、椎名は彼が病院から抜け出して来たのではないか、と疑うが、病院に彼がいた事実はなく、行き場のない彼を椎名は自分の部屋に置くことにした。
純粋無垢で、幼子のような心を持つ少年は、椎名の心の傷を癒し、また、彼自身の持つ傷を椎名も知る。それは、ドナの務める研究所の所長、テイラーが行っていた社会倫理を逸脱した遺伝子組み換え実験であった。
椎名と少年――エディはテイラーに捕らわれ、最終実験が始まった。
神話の水蛇(ヒュドラー)と現在棲息するヒドラ。それは学者の夢であった。
※以前、他サイトで掲載していたものです。
※一部、性描写(必要描写です)があります。苦手な方はお気を付けください。
※表紙画:フリーイラストの加工です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















