113 / 162
かつて倫子や萬壽姫の療治に当たった医師たちは家基の療治に携わった医師で占められており、それを推挙したのは稲葉正明であった
しおりを挟む
「しかもその…、家基を療治せし、いや、見殺しにせし中川専庵義方と遊佐卜庵信庭、関本春臺壽熈、それに千田玄知温恭と岡井運南道晟、そして山脇道作玄陶と畠山隆川常赴の七名は倫子や萬壽の療治にも携わっていたのだ…」
家治は如何にも口惜しげにそう告げ、意知を驚愕させた。
倫子とは将軍・家治の正室であり、萬壽はその倫子が家治との間になした姫君であった。
だが倫子も萬壽も今はもう亡い。
倫子は12年前の明和8(1771)年8月20日に、そして萬壽も母・倫子の後を追うようにそれから2年後の、つまりはちょうど10年前の安永2(1773)年2月20日にそれぞれ卒した。
だが二人の死もまた、家基同様、病死ではなく他殺、それも毒殺の可能性があることを家治より示唆されたために、意知は驚愕したのであった。
「やはりそれも深谷盛朝が探索にて?」
意次が家治に確かめるように尋ねた。
「左様…、されば盛朝がその10人の医師の経歴と共に過去をも調べし過程で判明せし事実にて…」
「ちなみに外の…、峯岸春庵瑞興と、それに中川隆玄瑞照と片山宗哲玄年の3人は畏れ多くも御台様と姫君様の療治には…、いえ、見殺しには加わりませなんだので?」
意知が口を挟んだ。
「されば峯岸春庵は萬壽の療治、いや、見殺しにのみ加わり…、春庵めが番医に取り立てられしは…、いや、最終的には余が決裁したわけだが…、安永元(1772)年にて…」
そうであれば倫子が卒した、いや、毒殺された明和8(1771)年の時点では峯岸春庵は未だ表番医師ではなかったわけで、そうであればその峯岸春庵には倫子を療治と称して見殺しにすることは不可能というわけであった。
だが峯岸春庵が今の表番医師に取り立てられてから1年後の安永2(1773)年にやはり毒殺された萬壽姫に対しては療治と称して見殺しに加わったということらしい。
「残る中川隆玄めと片山宗哲めは…」
意知は家治に重ねて尋ねた。
「されば中川隆玄めは安永7(1778)年の年の瀬に番医に取り立てたために…」
それよりも前に毒殺された倫子や萬壽姫をその中川隆玄が見殺しにすることは不可能ということであった。
「また、片山宗哲めは倫子が身罷りし前、明和6(1769)年に番医に取り立てしも、なれど、宗哲めが息・亀太郎が遊佐卜庵めが養女を娶りしはやはり安永7(1778)年のことにて…」
片山宗哲にしても、倫子や萬壽姫が毒殺、それも一橋治済の手により毒殺された頃にはまだ、一橋治済とは所縁がなかったために、見殺しには加わらなかったということらしい。
「畏れながら…」
意知はそう切り出すと、かねてより疑問に思っていたことを家治にぶつけた。
「上様は何ゆえに斯様な…、一橋卿殿と所縁のありし医師に畏れ多くも大納言様やそれに御台様、姫君様の療治に当たらせましたので?いや、畏れ多くも大納言様におかせられましては西之丸におわされ致し方なしとしても…」
ここ本丸は紛れもなく将軍・家治の「居城」なのだから、そして正室の倫子とその娘の萬壽姫はその本丸の大奥にて暮らしていたわけだから、家治がそのつもりでおれば一橋家と所縁のある医師を近付けさせないことが出来たのではないのか…。
それこそが意知がかねてより抱いていた疑問であり、しかしそれは多分に将軍・家治に対する非難とも受け取られかねず、そのことを直ぐに、敏感に気付いた意次が息・意知に対して、
「口を慎めっ!」
そう叱責を浴びせた。
するとそれに対して家治は、「構わぬ…」と意次を制してみせたかと思うと、
「意知が疑問も尤もである。何しろ余が倫子や萬壽、そして家基をみすみす見殺しに致したも同然にて…」
家治が自嘲気味にそう認めたことから意知を大いに恐縮させたものである。
「滅相もござりませぬ…」
意知は平伏しながらそう応じた。
「いや、意知が申す通りぞ。余がいま少し気をつけておれば倫子や萬壽を死なせずに済んだやも知れぬ。それに家基もな…」
家治は心底、忸怩たる面持ちでそう呟いた。
意次はそのような家治の姿に居た堪れなくなり、
「左様に御身をお責めあそばされませぬように…」
家治を労わってみせると同時に、相変わらず平伏したままの意知をねめつけたものだった。
ともあれ家治は意次の心遣いに感謝すると同時に、その心遣いに報いるかのようにまた直ぐに元の姿を取り戻すと意知の頭を上げさせた。
「いや、言い訳になるが、斯かる一橋と所縁の有りし医師どもに倫子や萬壽が療治に当たらせたは若年寄の酒井石見が強い推挙にて…」
家治がそう切り出すと、意次もその当時の記憶が甦り、「ああ…」と声を上げた。
家治が口にした通り、倫子や萬壽姫の療治に当たらせる医師の人選について、「リーダーシップ」を発揮したのは若年寄の酒井石見こと石見守忠休であった。
「それなればこの意次も覚えておりまする…、されば水野壱岐が口も差し挟ませずに…」
水野壱岐とは、倫子が薨去した明和8(1771)年から萬壽姫が薨去した安永2(1773)年にかけて若年寄を、それも筆頭たる勝手掛を務めていた壱岐守忠見のことである。
ここ江戸城に勤める医師、所謂官医は若年寄の支配下にあり、それゆえ将軍や、或いは御台所、そして次期将軍や姫君などが病気の場合、どの医師に療治に当たらせるか、それを決めるのは若年寄であった。
そしてその若年寄の筆頭であったのが水野壱岐守忠見であった。
水野忠見は勝手掛若年寄として本来ならば、どの医師に倫子や萬壽姫の療治に当たらせるか、その人選に大いに「リーダーシップ」を発揮出来る立場にいた。
ところがその時…、倫子や萬壽姫が斃れた時に限って言えばそれは当て嵌まらなかった。
即ち、その時は若年寄の次席に位置していた酒井忠休が水野忠見を出し抜く格好で倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師を決めたのであった。つまりは一橋家と所縁のある医師を選んだというわけだ。
「そのことで水野壱岐も大いに憤慨しておりました…」
意次がその時のことを思い出してそう口にすると家治も頷いた。
若年寄の筆頭はあくまで水野忠見である。そうであれば次席に過ぎなかった酒井忠休がその水野忠見を出し抜くと言っても限界があっただろう。
だが酒井忠休には強力な味方がいたのだ。誰あろう、御側御用取次の稲葉越中守正明であった。
御側御用取次は中奥の最高長官として、老中以上の力を発揮し、何より大奥を取り仕切る年寄と常に内談に及ぶために、それゆえその大奥にて暮らしていた倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師の人選について、御側御用取次の意見が大いにものを言う。
酒井忠休はその御側御用取次である稲葉正明と謂わば、
「タッグを組んで…」
勝手掛若年寄であった水野忠見を出し抜く格好で倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師を決めたのであった。
それに対して水野忠見はと言うと、倫子の療治に当たらせるべき医師の人選については、つまりは明和8(1771)年の8月の時には酒井忠休の顔を立てて黙って引き下がったそうだが、それから2年後の安永2(1773)年、2月にも今度は萬壽姫の療治に当たらせるべき医師の人選について、またしても酒井忠休は水野忠見を出し抜く格好にて、倫子の療治に当たった医師に加えて、そこに新たに峯岸春庵をも召し加えようとしたので、水野忠見も若年寄の筆頭たる己を蔑ろにする酒井忠休のこの行動には流石に我慢がならず、そこで巻き返しに出たのであった。
即ち、水野忠見は同族にして、相役…、同僚であった水野出羽守忠友に泣きついたのであった。
水野忠友は若年寄の中でも一番の新任であり、それゆえ若年寄の末席に位置していた。
しかし忠友は中奥兼帯の若年寄として、中奥にて将軍・家治に近侍していた。つまりは表向の役人ではありながら、中奥に出入りすることが許されていたのだ。
そこで忠友は己と立場が同じ意次に相談を持ちかけることにした。
それと言うのもこの時…、安永2(1773)年の時点で意次もまた、中奥兼帯の老中であり、意次と水野忠友は共に中奥兼帯として…、表向の役人でありながら、将軍・家治に近侍する者同士、親しく付き合っていたからだ。
こうして水野忠友は意次に同族の水野忠見を引き合わせた上で、忠見より意次へと相談を持ちかけさせたのであった。
その折、水野忠見は憤慨しながら意次に相談したもので、それに対して意次はと言うと、倫子の療治に当たるべき医師の人選についてそのような蠢きがあったのかと、その事に初めて気づかされ仰天させられたものだった。
そして意次としてはこのまま捨て置くことは出来ぬと、そこでまずはもう一人の御側御用取次であった白須甲斐守政賢を使うことを思いついた。
意次は白須政賢に対して、水野忠見より聞いた話をそのまま伝えたのであった。
すると白須政賢は意次が期待した通りの反応を示してくれた。
即ち、白須政賢は稲葉正明に対して不快感を抱いてくれたのであった。
水野忠見が酒井忠休に出し抜かれたのと同様に、白須政賢もまた、稲葉正明に出し抜かれたようなもので、それを今の今まで気づかなかったことが余計に稲葉正明に対する不快感を倍加させたのであった。
こうして意次は白須政賢を抱き込むことに成功すると、二人で手分けして平御側をも抱き込むことにしたのだ。
ちなみにその当時の平御側の「メンバー」であるが、
「小笠原若狭守信喜」
「巨勢伊豆守至忠」
「水野山城守忠徹」
「津田日向守信之」
以上の4名であり、このうち小笠原信喜は稲葉正明と正に、
「ズブズブ…」
その関係にあったのは周知の事実、公知といっても良く、そこで意次と白須政賢は小笠原信喜を除く3人の平御側に照準を合わせたのであった。
その謂わば、
「抱き込み工作…」
その過程で意次は小姓組番頭格の御側御用取次見習であった横田筑後守準松と同じく小姓組番頭格の御側衆見習であった松平因幡守康眞をも抱き込むことを思いつき、こうして意次は白須政賢と共に彼らを抱き込むと、勢揃いして将軍・家治の御前へと赴いては、萬壽姫の療治に当たるべき医師については奥医師に一任すべきと陳情したのであった。
これに驚いたのは言うまでもなく稲葉正明であった。稲葉正明としては何としてでも巻き返しを図りたいところであったが、しかし、小笠原信喜を除く平御側が皆、意次に抱き込まれたとあっては、その上、御側御用取次見習の横田準松と御側衆見習の松平康眞までが抱き込まれたとあっては、
「万事休す…」
かに思えた。
だがそれでも稲葉正明は最後の手段に出た。
稲葉正明は何と、萬壽姫附の老女を担いだのであった。
即ち、当時、萬壽姫に老女として仕えていた梅岡を味方につけて中央突破を図ろうとしたのであった。
結局、将軍たる家治は奥医師と、そして正明が推挙した医師の双方を萬壽姫の療治に当たらせることにしたのであった。謂わば、
「中を取った…」
そのようなものであった。
「だがそれは間違いであったやも知れぬな…」
家治は意次と意知に、とりわけ意知に対して当時の事情…、愛妻の倫子や愛娘の萬壽姫の療治に当たるべき医師の人選についての事情を語り終えるとしみじみとした口調でそう呟いた。
それに対して意知はそんな家治を励ますべく、
「左様にお気に召されませぬように…」
そう口にしようとして、しかし、慌てて口を噤んだ。そのような月並みな励ましを口にしたところで何の意味もない、いや、それどころか家治の受けた心の傷に塩を塗り込むことにもなりかねないからだ。
それと言うのも、気にするなということは、それはそのまま、
「倫子や萬壽姫の命は救えなかった…」
その冷厳とも言うべき事実を家治に突き付けることになり、且つ家治にそう受け取られる恐れがあったからだ。少なくとも意知が家治の立場であったならばそう受け取るであろう。それゆえ意知は月並みな励ましを口にすることは控えたのであった。海千山千の父・意次に較べると人の気持ちというものには疎い意知もその程度の想像力はあった。
ともあれ意知は黙って家治に寄り添うに止めた。
家治は如何にも口惜しげにそう告げ、意知を驚愕させた。
倫子とは将軍・家治の正室であり、萬壽はその倫子が家治との間になした姫君であった。
だが倫子も萬壽も今はもう亡い。
倫子は12年前の明和8(1771)年8月20日に、そして萬壽も母・倫子の後を追うようにそれから2年後の、つまりはちょうど10年前の安永2(1773)年2月20日にそれぞれ卒した。
だが二人の死もまた、家基同様、病死ではなく他殺、それも毒殺の可能性があることを家治より示唆されたために、意知は驚愕したのであった。
「やはりそれも深谷盛朝が探索にて?」
意次が家治に確かめるように尋ねた。
「左様…、されば盛朝がその10人の医師の経歴と共に過去をも調べし過程で判明せし事実にて…」
「ちなみに外の…、峯岸春庵瑞興と、それに中川隆玄瑞照と片山宗哲玄年の3人は畏れ多くも御台様と姫君様の療治には…、いえ、見殺しには加わりませなんだので?」
意知が口を挟んだ。
「されば峯岸春庵は萬壽の療治、いや、見殺しにのみ加わり…、春庵めが番医に取り立てられしは…、いや、最終的には余が決裁したわけだが…、安永元(1772)年にて…」
そうであれば倫子が卒した、いや、毒殺された明和8(1771)年の時点では峯岸春庵は未だ表番医師ではなかったわけで、そうであればその峯岸春庵には倫子を療治と称して見殺しにすることは不可能というわけであった。
だが峯岸春庵が今の表番医師に取り立てられてから1年後の安永2(1773)年にやはり毒殺された萬壽姫に対しては療治と称して見殺しに加わったということらしい。
「残る中川隆玄めと片山宗哲めは…」
意知は家治に重ねて尋ねた。
「されば中川隆玄めは安永7(1778)年の年の瀬に番医に取り立てたために…」
それよりも前に毒殺された倫子や萬壽姫をその中川隆玄が見殺しにすることは不可能ということであった。
「また、片山宗哲めは倫子が身罷りし前、明和6(1769)年に番医に取り立てしも、なれど、宗哲めが息・亀太郎が遊佐卜庵めが養女を娶りしはやはり安永7(1778)年のことにて…」
片山宗哲にしても、倫子や萬壽姫が毒殺、それも一橋治済の手により毒殺された頃にはまだ、一橋治済とは所縁がなかったために、見殺しには加わらなかったということらしい。
「畏れながら…」
意知はそう切り出すと、かねてより疑問に思っていたことを家治にぶつけた。
「上様は何ゆえに斯様な…、一橋卿殿と所縁のありし医師に畏れ多くも大納言様やそれに御台様、姫君様の療治に当たらせましたので?いや、畏れ多くも大納言様におかせられましては西之丸におわされ致し方なしとしても…」
ここ本丸は紛れもなく将軍・家治の「居城」なのだから、そして正室の倫子とその娘の萬壽姫はその本丸の大奥にて暮らしていたわけだから、家治がそのつもりでおれば一橋家と所縁のある医師を近付けさせないことが出来たのではないのか…。
それこそが意知がかねてより抱いていた疑問であり、しかしそれは多分に将軍・家治に対する非難とも受け取られかねず、そのことを直ぐに、敏感に気付いた意次が息・意知に対して、
「口を慎めっ!」
そう叱責を浴びせた。
するとそれに対して家治は、「構わぬ…」と意次を制してみせたかと思うと、
「意知が疑問も尤もである。何しろ余が倫子や萬壽、そして家基をみすみす見殺しに致したも同然にて…」
家治が自嘲気味にそう認めたことから意知を大いに恐縮させたものである。
「滅相もござりませぬ…」
意知は平伏しながらそう応じた。
「いや、意知が申す通りぞ。余がいま少し気をつけておれば倫子や萬壽を死なせずに済んだやも知れぬ。それに家基もな…」
家治は心底、忸怩たる面持ちでそう呟いた。
意次はそのような家治の姿に居た堪れなくなり、
「左様に御身をお責めあそばされませぬように…」
家治を労わってみせると同時に、相変わらず平伏したままの意知をねめつけたものだった。
ともあれ家治は意次の心遣いに感謝すると同時に、その心遣いに報いるかのようにまた直ぐに元の姿を取り戻すと意知の頭を上げさせた。
「いや、言い訳になるが、斯かる一橋と所縁の有りし医師どもに倫子や萬壽が療治に当たらせたは若年寄の酒井石見が強い推挙にて…」
家治がそう切り出すと、意次もその当時の記憶が甦り、「ああ…」と声を上げた。
家治が口にした通り、倫子や萬壽姫の療治に当たらせる医師の人選について、「リーダーシップ」を発揮したのは若年寄の酒井石見こと石見守忠休であった。
「それなればこの意次も覚えておりまする…、されば水野壱岐が口も差し挟ませずに…」
水野壱岐とは、倫子が薨去した明和8(1771)年から萬壽姫が薨去した安永2(1773)年にかけて若年寄を、それも筆頭たる勝手掛を務めていた壱岐守忠見のことである。
ここ江戸城に勤める医師、所謂官医は若年寄の支配下にあり、それゆえ将軍や、或いは御台所、そして次期将軍や姫君などが病気の場合、どの医師に療治に当たらせるか、それを決めるのは若年寄であった。
そしてその若年寄の筆頭であったのが水野壱岐守忠見であった。
水野忠見は勝手掛若年寄として本来ならば、どの医師に倫子や萬壽姫の療治に当たらせるか、その人選に大いに「リーダーシップ」を発揮出来る立場にいた。
ところがその時…、倫子や萬壽姫が斃れた時に限って言えばそれは当て嵌まらなかった。
即ち、その時は若年寄の次席に位置していた酒井忠休が水野忠見を出し抜く格好で倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師を決めたのであった。つまりは一橋家と所縁のある医師を選んだというわけだ。
「そのことで水野壱岐も大いに憤慨しておりました…」
意次がその時のことを思い出してそう口にすると家治も頷いた。
若年寄の筆頭はあくまで水野忠見である。そうであれば次席に過ぎなかった酒井忠休がその水野忠見を出し抜くと言っても限界があっただろう。
だが酒井忠休には強力な味方がいたのだ。誰あろう、御側御用取次の稲葉越中守正明であった。
御側御用取次は中奥の最高長官として、老中以上の力を発揮し、何より大奥を取り仕切る年寄と常に内談に及ぶために、それゆえその大奥にて暮らしていた倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師の人選について、御側御用取次の意見が大いにものを言う。
酒井忠休はその御側御用取次である稲葉正明と謂わば、
「タッグを組んで…」
勝手掛若年寄であった水野忠見を出し抜く格好で倫子や萬壽姫の療治に当たらせるべき医師を決めたのであった。
それに対して水野忠見はと言うと、倫子の療治に当たらせるべき医師の人選については、つまりは明和8(1771)年の8月の時には酒井忠休の顔を立てて黙って引き下がったそうだが、それから2年後の安永2(1773)年、2月にも今度は萬壽姫の療治に当たらせるべき医師の人選について、またしても酒井忠休は水野忠見を出し抜く格好にて、倫子の療治に当たった医師に加えて、そこに新たに峯岸春庵をも召し加えようとしたので、水野忠見も若年寄の筆頭たる己を蔑ろにする酒井忠休のこの行動には流石に我慢がならず、そこで巻き返しに出たのであった。
即ち、水野忠見は同族にして、相役…、同僚であった水野出羽守忠友に泣きついたのであった。
水野忠友は若年寄の中でも一番の新任であり、それゆえ若年寄の末席に位置していた。
しかし忠友は中奥兼帯の若年寄として、中奥にて将軍・家治に近侍していた。つまりは表向の役人ではありながら、中奥に出入りすることが許されていたのだ。
そこで忠友は己と立場が同じ意次に相談を持ちかけることにした。
それと言うのもこの時…、安永2(1773)年の時点で意次もまた、中奥兼帯の老中であり、意次と水野忠友は共に中奥兼帯として…、表向の役人でありながら、将軍・家治に近侍する者同士、親しく付き合っていたからだ。
こうして水野忠友は意次に同族の水野忠見を引き合わせた上で、忠見より意次へと相談を持ちかけさせたのであった。
その折、水野忠見は憤慨しながら意次に相談したもので、それに対して意次はと言うと、倫子の療治に当たるべき医師の人選についてそのような蠢きがあったのかと、その事に初めて気づかされ仰天させられたものだった。
そして意次としてはこのまま捨て置くことは出来ぬと、そこでまずはもう一人の御側御用取次であった白須甲斐守政賢を使うことを思いついた。
意次は白須政賢に対して、水野忠見より聞いた話をそのまま伝えたのであった。
すると白須政賢は意次が期待した通りの反応を示してくれた。
即ち、白須政賢は稲葉正明に対して不快感を抱いてくれたのであった。
水野忠見が酒井忠休に出し抜かれたのと同様に、白須政賢もまた、稲葉正明に出し抜かれたようなもので、それを今の今まで気づかなかったことが余計に稲葉正明に対する不快感を倍加させたのであった。
こうして意次は白須政賢を抱き込むことに成功すると、二人で手分けして平御側をも抱き込むことにしたのだ。
ちなみにその当時の平御側の「メンバー」であるが、
「小笠原若狭守信喜」
「巨勢伊豆守至忠」
「水野山城守忠徹」
「津田日向守信之」
以上の4名であり、このうち小笠原信喜は稲葉正明と正に、
「ズブズブ…」
その関係にあったのは周知の事実、公知といっても良く、そこで意次と白須政賢は小笠原信喜を除く3人の平御側に照準を合わせたのであった。
その謂わば、
「抱き込み工作…」
その過程で意次は小姓組番頭格の御側御用取次見習であった横田筑後守準松と同じく小姓組番頭格の御側衆見習であった松平因幡守康眞をも抱き込むことを思いつき、こうして意次は白須政賢と共に彼らを抱き込むと、勢揃いして将軍・家治の御前へと赴いては、萬壽姫の療治に当たるべき医師については奥医師に一任すべきと陳情したのであった。
これに驚いたのは言うまでもなく稲葉正明であった。稲葉正明としては何としてでも巻き返しを図りたいところであったが、しかし、小笠原信喜を除く平御側が皆、意次に抱き込まれたとあっては、その上、御側御用取次見習の横田準松と御側衆見習の松平康眞までが抱き込まれたとあっては、
「万事休す…」
かに思えた。
だがそれでも稲葉正明は最後の手段に出た。
稲葉正明は何と、萬壽姫附の老女を担いだのであった。
即ち、当時、萬壽姫に老女として仕えていた梅岡を味方につけて中央突破を図ろうとしたのであった。
結局、将軍たる家治は奥医師と、そして正明が推挙した医師の双方を萬壽姫の療治に当たらせることにしたのであった。謂わば、
「中を取った…」
そのようなものであった。
「だがそれは間違いであったやも知れぬな…」
家治は意次と意知に、とりわけ意知に対して当時の事情…、愛妻の倫子や愛娘の萬壽姫の療治に当たるべき医師の人選についての事情を語り終えるとしみじみとした口調でそう呟いた。
それに対して意知はそんな家治を励ますべく、
「左様にお気に召されませぬように…」
そう口にしようとして、しかし、慌てて口を噤んだ。そのような月並みな励ましを口にしたところで何の意味もない、いや、それどころか家治の受けた心の傷に塩を塗り込むことにもなりかねないからだ。
それと言うのも、気にするなということは、それはそのまま、
「倫子や萬壽姫の命は救えなかった…」
その冷厳とも言うべき事実を家治に突き付けることになり、且つ家治にそう受け取られる恐れがあったからだ。少なくとも意知が家治の立場であったならばそう受け取るであろう。それゆえ意知は月並みな励ましを口にすることは控えたのであった。海千山千の父・意次に較べると人の気持ちというものには疎い意知もその程度の想像力はあった。
ともあれ意知は黙って家治に寄り添うに止めた。
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

天明繚乱 ~次期将軍の座~
ご隠居
歴史・時代
時は天明、幼少のみぎりには定火消の役屋敷でガエンと共に暮らしたこともあるバサラな旗本、鷲巣(わしのす)益五郎(ますごろう)とそんな彼を取り巻く者たちの物語。それに11代将軍の座をめぐる争いあり、徳川家基の死の真相をめぐる争いあり、そんな物語です。

連合航空艦隊
ypaaaaaaa
歴史・時代
1929年のロンドン海軍軍縮条約を機に海軍内では新時代の軍備についての議論が活発に行われるようになった。その中で生れたのが”航空艦隊主義”だった。この考えは当初、一部の中堅将校や青年将校が唱えていたものだが途中からいわゆる海軍左派である山本五十六や米内光政がこの考えを支持し始めて実現のためにの政治力を駆使し始めた。この航空艦隊主義と言うものは”重巡以上の大型艦を全て空母に改装する”というかなり極端なものだった。それでも1936年の条約失効を持って日本海軍は航空艦隊主義に傾注していくことになる。
デモ版と言っては何ですが、こんなものも書く予定があるんだなぁ程度に思ってい頂けると幸いです。


【おんJ】 彡(゚)(゚)ファッ!?ワイが天下分け目の関ヶ原の戦いに!?
俊也
SF
これまた、かつて私がおーぷん2ちゃんねるに載せ、ご好評頂きました戦国架空戦記SSです。
この他、
「新訳 零戦戦記」
「総統戦記」もよろしくお願いします。
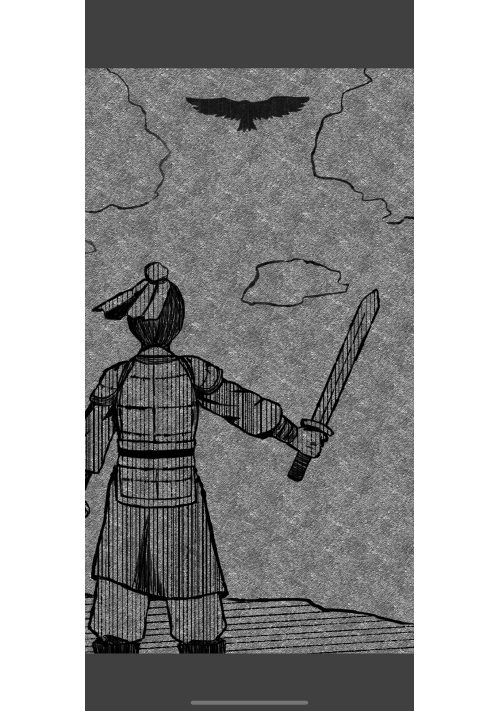
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

信長の秘書
にゃんこ先生
歴史・時代
右筆(ゆうひつ)。
それは、武家の秘書役を行う文官のことである。
文章の代筆が本来の職務であったが、時代が進むにつれて公文書や記録の作成などを行い、事務官僚としての役目を担うようになった。
この物語は、とある男が武家に右筆として仕官し、無自覚に主家を動かし、戦国乱世を生き抜く物語である。
などと格好つけてしまいましたが、実際はただのゆる~いお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















