お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
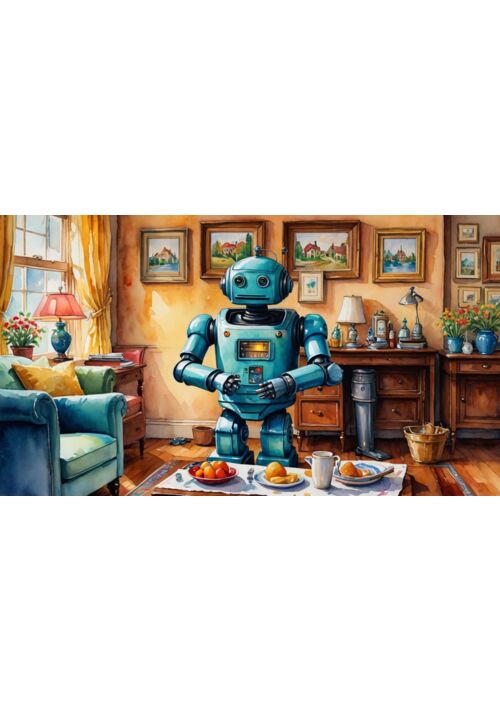
AI執事、今日もやらかす ~ポンコツだけど憎めない人工知能との奇妙な共同生活~
鷹栖 透
SF
AI執事アルフレッドは完璧なプレゼン資料を用意するが、主人公の花子は資料を捨て、自らの言葉でプレゼンに挑む。完璧を求めるAIと、不完全さの中にこそ真の創造性を見出す人間の対比を通して、人間の可能性とAIとの関係性を問う感動の物語。崖っぷちのデザイナー花子と、人間を理解しようと奮闘するAI執事アルフレッドの成長は、あなたに温かい涙と、未来への希望をもたらすだろう。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

法術装甲隊ダグフェロン 永遠に続く世紀末の国で 『修羅の国』での死闘
橋本 直
SF
その文明は出会うべきではなかった
その人との出会いは歓迎すべきものではなかった
これは悲しい『出会い』の物語
『特殊な部隊』と出会うことで青年にはある『宿命』がせおわされることになる
法術装甲隊ダグフェロン 第三部
遼州人の青年『神前誠(しんぜんまこと)』は法術の新たな可能性を追求する司法局の要請により『05式広域制圧砲』と言う新兵器の実験に駆り出される。その兵器は法術の特性を生かして敵を殺傷せずにその意識を奪うと言う兵器で、対ゲリラ戦等の『特殊な部隊』と呼ばれる司法局実働部隊に適した兵器だった。
一方、遼州系第二惑星の大国『甲武』では、国家の意思決定最高機関『殿上会』が開かれようとしていた。それに出席するために殿上貴族である『特殊な部隊』の部隊長、嵯峨惟基は甲武へと向かった。
その間隙を縫ったかのように『修羅の国』と呼ばれる紛争の巣窟、ベルルカン大陸のバルキスタン共和国で行われる予定だった選挙合意を反政府勢力が破棄し機動兵器を使った大規模攻勢に打って出て停戦合意が破綻したとの報が『特殊な部隊』に届く。
この停戦合意の破棄を理由に甲武とアメリカは合同で介入を企てようとしていた。その阻止のため、神前誠以下『特殊な部隊』の面々は輸送機でバルキスタン共和国へ向かった。切り札は『05式広域鎮圧砲』とそれを操る誠。『特殊な部隊』の制式シュツルム・パンツァー05式の機動性の無さが作戦を難しいものに変える。
そんな時間との戦いの中、『特殊な部隊』を見守る影があった。
『廃帝ハド』、『ビッグブラザー』、そしてネオナチ。
誠は反政府勢力の攻勢を『05式広域鎮圧砲』を使用して止めることが出来るのか?それとも……。
SFお仕事ギャグロマン小説。
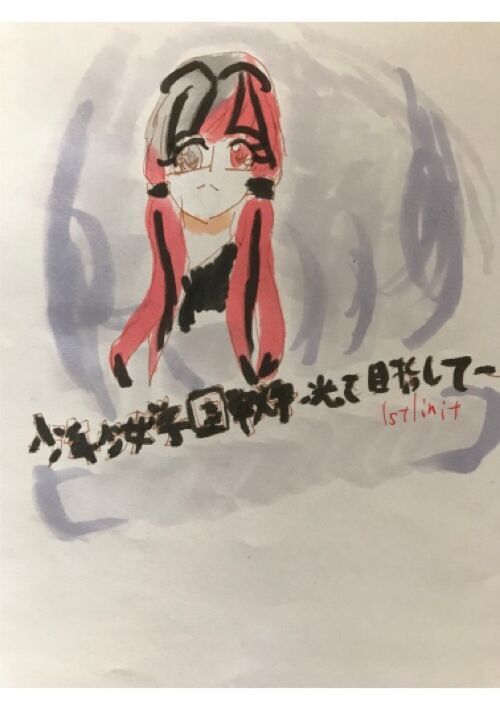
少年少女学園戦争-光を目指して-
白波光里
SF
2060年4月、令和の世も終わりつつあるが、そんな中姫川市立南光中学に入学した少女柊イズミ(ひいらぎいずみ)は同級生の越ヶ原悠司(こえがはらゆうじ)や笹原リンド(ささはらりんど)、焼美色(やきみいろ)が南光区を白姫教会(ホワイトプリンセスチャッチ)から守る為に彼ら彼女らは能力(チカラ)を手に取る!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















