15 / 21
土管
しおりを挟む
僕の住む町には大きな銭湯があった。
祖父が子どものときから始まったので古風な宮型造りで、灰色の太い煙突が天に向かって伸びている。
町中の人から愛されていて、クラスの友達も全員が一度は湯船につかったことがあった。
「おい、行くぞ」
2週間に一度の銭湯の日。僕は祖父の無愛想な掛け声で連れ出され、銭湯へ向かう。家にも大きなヒノキ風呂があったけれど、銭湯で過ごす時間はいつも特別だった。
祖父に手を引かれて町を歩く。
幼かった僕が暗くなってから出かけることができるのは祭りと銭湯の日だけだった。祖父は一緒に風呂に使っている間、色んなことを教えてくれた。昔のおもちゃや遊び。今ではありふれた食べ物が初めて日本にやってきた日のこと。祖母と結婚する前に心の底から愛した女性がいたこと。その人を事故で失ったこと。
大人になってから考えてみると、祖父の話には孫相手にしていいとは思えない内容も多々あったが、その分、一人の人間として対等に接してもらえている喜びを感じていた。
今回はそんな祖父から聞いた、この銭湯にまつわる少し不思議な話をしようと思う。
「スミヤは空地の土管で遊んだことがあるか?」
祖父は頭の上に手ぬぐいを乗せ、浴槽の縁にもたれかかり、肩まですっぽりと湯につかっていた。
「ないなあ。今時は空地には立ち入り禁止の看板が立ててあるから」
僕は祖父の真似をしていたが、どうしても身長が足りない。首を頑張って伸ばして呼吸をしていた。
「俺が子どもの頃は、よく土管で遊んだもんだ。どこにでもあるわけじゃないから、友達と在処を探し回ってな。土管の中は子どもにとっては秘密基地だった。かくれんぼで隠れようとしてもいつも先客がいるくらいにな。家出をしたときや友達と喧嘩をしたときにも土管に隠れて自分が泣き止むのを待った。町の中で一人きりになれる場所でもあったんだよ」
祖父は昔を懐かしむように目を細めた。
「じいちゃんも一人で泣いていたんだ」
職人気質で弱音を吐かない祖父が友達と喧嘩してめそめそ泣いている姿は想像できなかった。
「なんで喧嘩したのかはよく覚えてないがな」
祖父は手ぬぐいを取って顔をごしごし拭いた。
「……いや、あれだけは覚えているなあ。これまでの人生で何度も色んなやつと喧嘩をしてきたが、好きな子と大喧嘩したのはただの一度きりだった」
「好きな子?」
「同じクラスの女の子で、美人だった。そのせいで皆がちょっかいを出していた」
「じいちゃんも?」
「俺は硬派だからそんなことはせんよ。遊び仲間だったから気を惹こうなんて考えもせんかった」
「でも喧嘩したんでしょ?」
「毎日からかわれてストレスが溜まっていたんだろう。一緒に蝉を取っていた時、おしっこをかけられたのを見て笑っちまったんだ。そこであの子の中で何かがぷつんと切れて、たまたま俺にぶつかってしまった。交通事故みたいなもんさ」
「多分、その女の子はじいちゃんのこと好きだったと思うぞ」
「そうか。気づかんかったな」
祖父は嬉しそうに笑っていた。
「だが、そのままずっと口を利かんかった」
「寂しいね」
「お互い意地を張っていた。だけど、ある日、彼女は親の都合で転校することになった。俺はもう悲しくて悲しくて、彼女が転校する前日に学校へ行かなかった」
「仲直りできなかったの?」
「それが何故かできたんだよ」
祖父は天井を見上げた。手ぬぐいが落ちそうになって咄嗟に押さえる。
「じいちゃんはな、そのとき空地の土管に潜って泣いていた。彼女とも遊んだ思い出のある場所だった。友達と喧嘩したまま離れ離れになるのは辛かったけど、どうやって仲直りしていいかもわからんかった。もう会えないんだからいっそのことこのまま別れた方がいいんじゃないかとも考えた。めそめそしながら葛藤していると、気がつけば彼女は土管の出口で仁王立ちして、俺が出てくるのを待っていた。最後のお別れを告げるために町中を探してくれたんだと思う。ところが、俺は恥ずかしさと悲しさで『お前の顔なんか見たくもねえ』そう言ってしまったんじゃ」
僕は祖父の気持ちがなんとなくわかった。
「ああ、しまった。本当はこんなことを言うつもりじゃなかった。気持ちよく別れられるように男としてしっかりしなければいけなかった。そう弱い自分を悔いた。ところが彼女は『私も仲直りしたかった』と言ってきた。俺はびっくりした。会話の脈絡がなさ過ぎて悲しい気持ちはどこかへ飛んで行ってしまった。俺は土管から這い出して『俺の方こそ意地を張って悪かった』と謝った。それで、無事仲直りできて、転校後もしばらく交流が続いた」
「よかったね。でも何でじいちゃんが仲直りしたいって気持ちが伝わったんだろう」
首をかしげながら、僕は尋ねた。
「それは俺にもずっと不思議だった。しかし、この銭湯が造られてから初めて理由がわかったんだ」
「銭湯?」
僕にはさっぱりだった。
「この銭湯が人気の理由は何だと思う?」
祖父が意味ありげに微笑んだ。
「お湯につかっていると嫌な気持ちとか出来事を忘れることができるからだって先生たちは言っていたよ。それから、学校では空気を浄化する煙を出しているからだって。今はボイラー給油方式に変わったから当然だけど、木材を燃やしていた昔から煙は出していなかったし、煤払いをしているところも見たことがないって。銭湯のおじさんはその仕組みを誰にも教えてくれないんだけどね」
「そう、その人気の理由が俺のことを後押ししてくれてたんだ」
嫌な気持ちを忘れることと煙が出ないことがどう関係していたんだろう。
「俺は彼女が転校した後も、仲直りをした空地に一人でやってきては土管の上に座り込み、空を眺めて考えていた。気持ちが伝わったのは嬉しかったが、その理由がわからずに悶々としていたんだ。友達に打ち明けても寝ぼけていたんじゃないかとあしらわれてしまった。それでも毎日のように通っていたら、とんでもない夕立に襲われてしまった。俺はその日も土管の上に座っていたから、慌てて降りて転んでしまった。服は泥まみれになり、膝を擦りむいてしまった。仕方なく、夕立が弱まるのを土管の中で待つことにした。幸い中は乾いていてどうにか凌ぐことができたんだ。そして、雨が止み土管から這い出すと不思議なことが起こっていた」
祖父は思わせぶりに言葉を切った。
「服の汚れも膝の擦り傷も無くなっていたんだよ」
祖父の目は真剣そのもので、僕はその視線に気圧されるように信じてしまう。
「土管を通り抜けると何もかもが綺麗になって出てくる、俺はそう思ったんだ」
確かに辻褄が合うのだ。土管の中から祖父が放った顔も見たくないという言葉は表面的な意味しかなく、根底には友達と仲直りしたいという思いが根底にあった。
だから土管を通して聞いた彼女は祖父の心の叫びを受け取ることができたのだ。
「でも、土管と銭湯に何の関係があるの?」
「その不思議な土管はこの銭湯の煙突に使われているんだよ」
祖父は満面の笑みを浮かべていた。
「ねえ、パパ。銭湯は無くなっちゃうの?」
僕の背中で眠っていた娘が目を覚ました。今年で七歳になる。僕が祖父から土管の話を聞いたのと同じ年だった。
「そうだよ。この銭湯はパパのおじいちゃんが子どものころからあったからね。もうボロボロなんだ」
今日は町のシンボルだった銭湯が取り壊される日。何度も大きな地震を耐え抜いて町を支えてきた場所も時の流れには逆らえなかった。
「無くなるのは寂しいなあ」
隣で妻が呟いた。
彼女もまたこの町の出身で何度も銭湯にはお世話になっていた。妻は少しずつ取り壊されていく銭湯を眺めながら、幼い頃を追憶している。
「ここのお湯につかると、嫌なこと全部忘れられたのに」
僕は知っている。それが本当はお湯の力ではないことを。
あの日、祖父を救った土管。いや、町中の悩みや悲しみを吸い続けた煙突は今日でその役目を終える。クレーン車で取り外され、アスファルトに横たわる煙突の内側からは、真っ黒な煤が誇らしげに町を覗いていた。
祖父が子どものときから始まったので古風な宮型造りで、灰色の太い煙突が天に向かって伸びている。
町中の人から愛されていて、クラスの友達も全員が一度は湯船につかったことがあった。
「おい、行くぞ」
2週間に一度の銭湯の日。僕は祖父の無愛想な掛け声で連れ出され、銭湯へ向かう。家にも大きなヒノキ風呂があったけれど、銭湯で過ごす時間はいつも特別だった。
祖父に手を引かれて町を歩く。
幼かった僕が暗くなってから出かけることができるのは祭りと銭湯の日だけだった。祖父は一緒に風呂に使っている間、色んなことを教えてくれた。昔のおもちゃや遊び。今ではありふれた食べ物が初めて日本にやってきた日のこと。祖母と結婚する前に心の底から愛した女性がいたこと。その人を事故で失ったこと。
大人になってから考えてみると、祖父の話には孫相手にしていいとは思えない内容も多々あったが、その分、一人の人間として対等に接してもらえている喜びを感じていた。
今回はそんな祖父から聞いた、この銭湯にまつわる少し不思議な話をしようと思う。
「スミヤは空地の土管で遊んだことがあるか?」
祖父は頭の上に手ぬぐいを乗せ、浴槽の縁にもたれかかり、肩まですっぽりと湯につかっていた。
「ないなあ。今時は空地には立ち入り禁止の看板が立ててあるから」
僕は祖父の真似をしていたが、どうしても身長が足りない。首を頑張って伸ばして呼吸をしていた。
「俺が子どもの頃は、よく土管で遊んだもんだ。どこにでもあるわけじゃないから、友達と在処を探し回ってな。土管の中は子どもにとっては秘密基地だった。かくれんぼで隠れようとしてもいつも先客がいるくらいにな。家出をしたときや友達と喧嘩をしたときにも土管に隠れて自分が泣き止むのを待った。町の中で一人きりになれる場所でもあったんだよ」
祖父は昔を懐かしむように目を細めた。
「じいちゃんも一人で泣いていたんだ」
職人気質で弱音を吐かない祖父が友達と喧嘩してめそめそ泣いている姿は想像できなかった。
「なんで喧嘩したのかはよく覚えてないがな」
祖父は手ぬぐいを取って顔をごしごし拭いた。
「……いや、あれだけは覚えているなあ。これまでの人生で何度も色んなやつと喧嘩をしてきたが、好きな子と大喧嘩したのはただの一度きりだった」
「好きな子?」
「同じクラスの女の子で、美人だった。そのせいで皆がちょっかいを出していた」
「じいちゃんも?」
「俺は硬派だからそんなことはせんよ。遊び仲間だったから気を惹こうなんて考えもせんかった」
「でも喧嘩したんでしょ?」
「毎日からかわれてストレスが溜まっていたんだろう。一緒に蝉を取っていた時、おしっこをかけられたのを見て笑っちまったんだ。そこであの子の中で何かがぷつんと切れて、たまたま俺にぶつかってしまった。交通事故みたいなもんさ」
「多分、その女の子はじいちゃんのこと好きだったと思うぞ」
「そうか。気づかんかったな」
祖父は嬉しそうに笑っていた。
「だが、そのままずっと口を利かんかった」
「寂しいね」
「お互い意地を張っていた。だけど、ある日、彼女は親の都合で転校することになった。俺はもう悲しくて悲しくて、彼女が転校する前日に学校へ行かなかった」
「仲直りできなかったの?」
「それが何故かできたんだよ」
祖父は天井を見上げた。手ぬぐいが落ちそうになって咄嗟に押さえる。
「じいちゃんはな、そのとき空地の土管に潜って泣いていた。彼女とも遊んだ思い出のある場所だった。友達と喧嘩したまま離れ離れになるのは辛かったけど、どうやって仲直りしていいかもわからんかった。もう会えないんだからいっそのことこのまま別れた方がいいんじゃないかとも考えた。めそめそしながら葛藤していると、気がつけば彼女は土管の出口で仁王立ちして、俺が出てくるのを待っていた。最後のお別れを告げるために町中を探してくれたんだと思う。ところが、俺は恥ずかしさと悲しさで『お前の顔なんか見たくもねえ』そう言ってしまったんじゃ」
僕は祖父の気持ちがなんとなくわかった。
「ああ、しまった。本当はこんなことを言うつもりじゃなかった。気持ちよく別れられるように男としてしっかりしなければいけなかった。そう弱い自分を悔いた。ところが彼女は『私も仲直りしたかった』と言ってきた。俺はびっくりした。会話の脈絡がなさ過ぎて悲しい気持ちはどこかへ飛んで行ってしまった。俺は土管から這い出して『俺の方こそ意地を張って悪かった』と謝った。それで、無事仲直りできて、転校後もしばらく交流が続いた」
「よかったね。でも何でじいちゃんが仲直りしたいって気持ちが伝わったんだろう」
首をかしげながら、僕は尋ねた。
「それは俺にもずっと不思議だった。しかし、この銭湯が造られてから初めて理由がわかったんだ」
「銭湯?」
僕にはさっぱりだった。
「この銭湯が人気の理由は何だと思う?」
祖父が意味ありげに微笑んだ。
「お湯につかっていると嫌な気持ちとか出来事を忘れることができるからだって先生たちは言っていたよ。それから、学校では空気を浄化する煙を出しているからだって。今はボイラー給油方式に変わったから当然だけど、木材を燃やしていた昔から煙は出していなかったし、煤払いをしているところも見たことがないって。銭湯のおじさんはその仕組みを誰にも教えてくれないんだけどね」
「そう、その人気の理由が俺のことを後押ししてくれてたんだ」
嫌な気持ちを忘れることと煙が出ないことがどう関係していたんだろう。
「俺は彼女が転校した後も、仲直りをした空地に一人でやってきては土管の上に座り込み、空を眺めて考えていた。気持ちが伝わったのは嬉しかったが、その理由がわからずに悶々としていたんだ。友達に打ち明けても寝ぼけていたんじゃないかとあしらわれてしまった。それでも毎日のように通っていたら、とんでもない夕立に襲われてしまった。俺はその日も土管の上に座っていたから、慌てて降りて転んでしまった。服は泥まみれになり、膝を擦りむいてしまった。仕方なく、夕立が弱まるのを土管の中で待つことにした。幸い中は乾いていてどうにか凌ぐことができたんだ。そして、雨が止み土管から這い出すと不思議なことが起こっていた」
祖父は思わせぶりに言葉を切った。
「服の汚れも膝の擦り傷も無くなっていたんだよ」
祖父の目は真剣そのもので、僕はその視線に気圧されるように信じてしまう。
「土管を通り抜けると何もかもが綺麗になって出てくる、俺はそう思ったんだ」
確かに辻褄が合うのだ。土管の中から祖父が放った顔も見たくないという言葉は表面的な意味しかなく、根底には友達と仲直りしたいという思いが根底にあった。
だから土管を通して聞いた彼女は祖父の心の叫びを受け取ることができたのだ。
「でも、土管と銭湯に何の関係があるの?」
「その不思議な土管はこの銭湯の煙突に使われているんだよ」
祖父は満面の笑みを浮かべていた。
「ねえ、パパ。銭湯は無くなっちゃうの?」
僕の背中で眠っていた娘が目を覚ました。今年で七歳になる。僕が祖父から土管の話を聞いたのと同じ年だった。
「そうだよ。この銭湯はパパのおじいちゃんが子どものころからあったからね。もうボロボロなんだ」
今日は町のシンボルだった銭湯が取り壊される日。何度も大きな地震を耐え抜いて町を支えてきた場所も時の流れには逆らえなかった。
「無くなるのは寂しいなあ」
隣で妻が呟いた。
彼女もまたこの町の出身で何度も銭湯にはお世話になっていた。妻は少しずつ取り壊されていく銭湯を眺めながら、幼い頃を追憶している。
「ここのお湯につかると、嫌なこと全部忘れられたのに」
僕は知っている。それが本当はお湯の力ではないことを。
あの日、祖父を救った土管。いや、町中の悩みや悲しみを吸い続けた煙突は今日でその役目を終える。クレーン車で取り外され、アスファルトに横たわる煙突の内側からは、真っ黒な煤が誇らしげに町を覗いていた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


暑苦しい方程式
空川億里
SF
すでにアルファポリスに掲載中の『クールな方程式』に引き続き、再び『方程式物』を書かせていただきました。
アメリカのSF作家トム・ゴドウィンの短編小説に『冷たい方程式』という作品があります。
これに着想を得て『方程式物』と呼ばれるSF作品のバリエーションが数多く書かれてきました。
以前私も微力ながら挑戦し『クールな方程式』を書きました。今回は2度目の挑戦です。
舞台は22世紀の宇宙。ぎりぎりの燃料しか積んでいない緊急艇に密航者がいました。
この密航者を宇宙空間に遺棄しないと緊急艇は目的地の惑星で墜落しかねないのですが……。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。




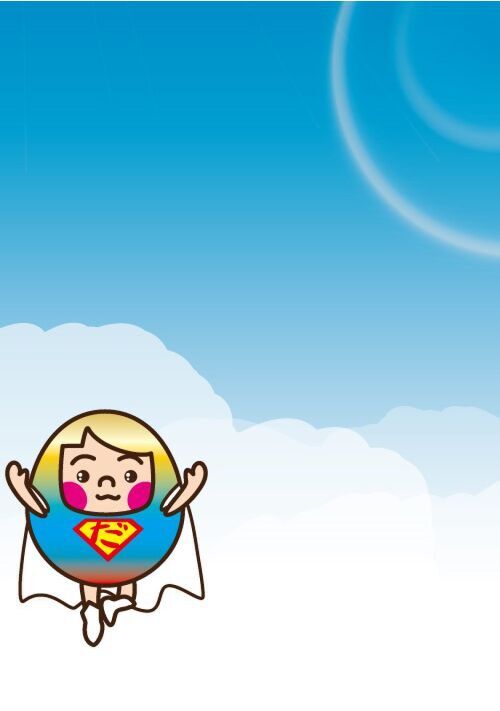
エスカレーター・ガール
転生新語
SF
永遠不変の一八才である、スーパーヒロインの私は、決戦の直前を二十代半ばの恋人と過ごしている。
戦うのは私、一人。負ければ地球は壊滅するだろう。ま、安心してよ私は勝つから。それが私、エスカレーター・ガールだ!
カクヨム、小説家になろうに投稿しています。
カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330660868319317
小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n5833ii/
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















