1 / 1
Calling! 〜ある魔法使いの召喚記録より〜
しおりを挟む
――――また、失敗してしまった。
目の前に描かれた円の中央に残されたものを見る。何度も目をこするが、それは変わらない。
グリンディーの胸に抱かれているのは、魔法論を綴っている分厚い本だ。所々にしおりが挟まれ、赤い字で書き込みがなされている。グリンディーがその本のページをめくっていく。
何度も何度も本の内容と床に描かれた円の文字や図形を確認していく。そして、最後、口から出た言葉は。
「なんで、召喚できないんだあっ!?」
グリンディーは頭を抱え込む。
本来なら、魔法の構文にあわせて、召喚魔法が発動する。そして、円の中には水の精霊がいる、というのが、グリンディーが目指したところだった。だが、目の前にいるのは、カエルである。
「水の精霊………」
ぽつりとつぶやく。
確かに、カエルは水に棲む生き物だ。だが、精霊ではない。いや、ひょっとしたら、グリンディーが思い描いている精霊──かわいらしい少女、もしくはずっと落ち着いた雰囲気を持つ大人の女性、ではなく、このカエルが精霊なのかもしれない。
「一応、書いておこう」
と、召喚結果をノートにまとめ始めた。それをじっと見守っていたカエルは突然動き始めた。部屋の中を勢いよく飛び跳ねる。
「あ、こらっ! 大事な召喚品っ!」
グリンディーがノートを放り出してカエルを捕まえようとした。が、直前でするりとグリンディーの手をすり抜けていく。
「くっそー! 待てっ!」
グリンディーがカエルを捕まえようとした瞬間、彼の頭にカエルは着地し、さらに高いところを目指して──天窓のあたりにむかってジャンプをした。
そして、届かなかった代わりに、ちょうどタイミング良く開いた扉から中に入ってきた若い男――祭司長の頭に着地をした。
「あ、あのっ……」
あたふたするグリンディーをあざ笑うかのように、ゲロ、とカエルが鳴いた。
祭司長はゆっくりと部屋の中を見渡す。たった今、召喚がなされた痕跡はここかしこにある。そして、あたふたする「問題児」。何が起こったのかはすぐに察しがついた。
「グリンディー!」
祭司長の怒りがグリンディーの頭上に落ちてきた。
「まったく、何で召喚できないのに、ここに配属されたんだか……」
祭司長はグリンディーに書類を見せながらため息をつく。
「……すみません」
「いや、君が謝ることじゃない」
祭司長に言われて、グリンディーは安堵の表情を浮かべるが、反対に祭司長は深いため息を落とす。
「君の才能に秘めた力を感じた国王様の判断を間違っていると批判した私がいけないのだよ。そして、早々に君の才能が開花しないのをのんきに待っていた私が間違っていたのだよ。早々に君を城から出した方が君のためかもしれない。もちろん、名目は「修行」だろう。そうでもしなければ君の経歴にだって、『クビ』だなんていう傷をつけざるを得なくなってしまった──」
次々と飛び出してくる否定的な言葉に、グリンディーはあきれ返る。よくもまあ、こんな風に言えるものだ。しかも、「毎回毎回」。
「もう、いいです……俺だって」
がんばっている、と言う言葉を飲み込む。
配属になって2年になる。最初の年は召喚術を得意とする先輩について召喚に関することを学んだ。魔法の使い方から、魔法の呪文の構成、発動に不可欠な円陣の描き方。どれもこれも、しっかり学んだ。本も読んで、実践も行ってみた。多分、召喚の広間を人一倍使っていることは記録を見れば確かで、グリンディーの名前は至る所に刻まれている。
けれども、その努力とは裏腹に、同時に召喚できたものの記録を辿っていくと、評価できるようなものではなかった。
先ほどのように、水の精霊を呼び出したつもりが、カエルだったり。
竜を呼び出したつもりが竜族に所属する世界最弱と言われているトカゲだったり。
故人の魂を召喚するはずが、その者の朽ち果てた身体だったり。
成功したことの方が少ないと、自分でも思っている。
つまり、思うものを正しく呼び出したことがないのだ。
そのたびに、魔法の力と構成文、呼び出しに使った円の描き方を確認してもらうのだが、間違いはない。そして、他の神官はグリンディーのやり方できちんと目的の物を召喚してみせるのだった。
最初こそ、「大丈夫だよ」と言われていたけれども、今じゃなにも言われない。そして、結論として、「センスがないんだよ」と言うことに落ち着くのだ。
――――センスって、なんなんだ?
グリンディーの問いかけに誰も答えてはくれなかった。
「書類、読んだか?」
「あ、今読みます」
グリンディーは文字を追っていく。
国王からの発信文書だった。
このところ、人ならざる物の動きが活発化している。魔物に襲われた人がいると書いてある。そして、読み進めると、魔物を鎮めるために伝説の乙女を召喚して欲しい、と書いてあった。
「召喚、するんですか?」
グリンディーは読み終えた書類を祭司長に返した。祭司長の眉がピクリと上がった気がしたのは、気のせいだろう。
「もちろん。魔物を鎮めることができるのは、伝説の乙女だけ。ただ、残念ながら、この召喚は特殊な魔法を使わなければならない」
そういって深々とため息をついた。
「まあ、召喚を生業とする人間はたくさんいますから、誰か一人くらいはできるでしょう?」
祭司長の眉が再び上がった、のは間違いではなさそうだ。急にもやもやした気持ちが心の中に芽生え始めるが、それにあえて蓋をする。
「……まあ、そうだな。だが、そのひとりが全く召喚のセンスがないやつなんだ。国王も頭を抱えていらっしゃった」
「それは……大変ですね」
次の瞬間、祭司長はグリンディーの目の前に今まで彼が読んでいた書類を突きつけた。
「お前、本当にこの文書を読んだのか? ここを見ろ!」
と、左上の宛名を指で示した。
グリンディー・デリシャス。
グリンディーの正式名がそこに記されている。
「……俺、ですか?」
勢いよく祭司長が机をたたいた。
「お前以外に召喚業の輩はたくさんいるが、お前の魔法しかできない召喚なんだよ! あー、よりによってなんでお前なんだか……せめて、お前の親族が生きていてくれたら」
「生きてますっ! 勝手に殺さないでください! ちょっと遠い山奥に隠居しているだけです!」
あまりの勢いに祭司長は耳を指でふさぐ。
「大体、親族が隠居したのは前の国王のせいじゃないですか!」
「引っ張り出すことがわかってるから、お前をここに置いたんだろうが! あの人たちのやりそうなことだ。お前はあいつらのいけにえにされたんだよ。あー、この話はこれで終わりだ。とりあえず、お前に全責任がある。ちゃんと事前に練習しておけよ! 事前に練習して召喚できたらできたで問題はないから」
それだけ言うと、祭司長は書類をテーブルの上において、グリンディーに背中を向けた。
グリンディーはため息をついて書類を受け取ると、一礼して祭司長の部屋を後にした。
グリンディーが落ちこぼれとはいえ、この城にいなければならないのには理由がある。
彼の家系はもともと召喚を生業としていた。代々この城に仕え、事あるごとにさまざまなものを召喚してきた。時には勇者とよばれる異界の若者も召喚したことがある。
そういう力を持っていることを、前の国王、カルアミー1世は面白半分に要求したという。
「どうせなら、天女を召喚してくれないか?」
理由はよくわからなかったが、グリンディーの親族は召喚した。そして、こともあろうに国王はこの天女を自分の妃としてしまったのだ。怒ったのは、天女の父といわれる天帝だった。戦を仕掛けてくるところを何とかおさめて、グリンディーの親族を城から追放したのだ。
とはいっても、グリンディーの一族の魔法の力というのはほかの召喚士と比べ物にならないほど強いものだった。国王は彼らの復讐を恐れて、幼い子供を人質に城へ残すように強要したのだった。
それが、グリンディーである。
いつまでも城でただで養うわけにもいかず、10のころから城で下働きをしている。先代がなくなると今の国王がグリンディーの腕を見込んで、召喚をメインとする神事を司るセクションに彼をおくようにした。幸か不幸か、グリンディーの召喚の腕は親族の中でも落ちこぼれといっても過言ではないものだった。今でも「荷物」になっていることに違いはない。
とぼとぼと廊下を歩きながら、自分の実験室ともいえる部屋に入る。
今まで読んだ本はこの城にある図書館分以上だろう。今もこの部屋の中にはありとあらゆる本が積み上げられている。本棚には入りきれず、机の上にはもちろん、ベッドの周りにも本が積まれている。
そして、新たな顔ぶれとして、机の上におかれた水槽の中に、グリンディーが召喚したカエルがいた。
書類を机の上に無造作に置くと、彼は水槽の中をじっと見た。
カエルと目が合う。
「そっか。君も水の中に戻してあげないとね」
ケロケロ、とカエルが鳴く。
グリンディーはカエルの水槽を抱えると、再び召喚用の部屋へと歩き始めた。
召喚用の部屋に入ると、ろうそくに灯をともす。ほのかな明かりに照らされると、グリンディーは床の上に召喚用の円を書き始めた。
時々、分厚い本を見ながら、丁寧に文字や図を入れていく。
それが完成すると、今度はその中央にカエルを水槽ごとおいた。
「さて……うまく帰れるといいな」
カエルに声をかけて、グリンディーは円の外側に立つ。
呪文の構成文を確認して、それを読み上げていく。ほとんど、暗記しているため、本を見ることはほとんどない。
右手を円の上にかざす。
呪文の朗詠が終わると同時に、手を軽く振り上げた。
呪文が発動する。描いた円から光が放たれる。そして、中央の水槽へと光が集まっていく。
じっとその経過をグリンディーは見る。中央に光が集まったことで、呪文はうまく働いてくれている。
問題はその後だ。
グリンディーの呪文では、水槽は残り、カエルの姿が消えていることになっている。
だが。
光が収まっていくと、そこには一人の少女がいた。年はグリンディーと変わらない……年のころなら、16くらいだろうか。そのせいで、グリンディーの視線は彼女の体にくぎ付けとなる。
お互いに視線を合わせたまま、動けない。
先に、大きな悲鳴があがった。
……カエルは、服を着ていなかったから。
女性の悲鳴を聞きつけて部屋に入ってきた兵士たちは、グリンディーを取り押さえてるなり、城の地下にある取調室へと連行した。
「だから! 召喚に失敗したカエルをもとの世界に帰そうとしただけだ」
グリンディーの話をうんうん、と聞きながらも、取調官は、ずい、と身を乗り出して、
「でも、君は召喚士だよね?」
「……だから、なんだっていうんですか」
「ほら、女性でも召喚できるんじゃないの? 特に君みたいに若い子はさ、そういうことに興味があったりするんじゃないの?」
明らかに疑われている。そのことだけでも腹が立つのに、取調官の言葉の裏側にある好奇心のような物にはもっと腹が立つ。
グリンディーの顔を見て、どうなの? と取調官は顔をのぞき込んだ。
「そんなこと、しません! 大体、俺がここにいるのだって……公務ですから!」
グリンディーがふてくされると、扉が開いて、祭司長が入ってきた。
どうせ、すみません、うちの馬鹿な部下が、と話を始めるのだろうと思っていると、祭司長は取調官を隅に呼ぶと、何やら話を始める。かなり神妙な顔つきに、グリンディーは最悪の事態を考えてしまう。
本当にクビになるのだから、さっさと取り調べを終わらせて城から追放してほしい、とか言っているんじゃないだろうか。
この城を出たら、何をするんだろう、俺。
中途半端な召喚の腕では、食べることは難しいだろう。とはいえ、そうそう魔法を使う仕事があるわけでもないし、そういう協会に登録したとしても、すぐに仕事がもらえるわけでもない。多少の蓄えはあるけれど、済むところの家賃や生活費を考えると、すぐに底をつくのは見えている。あてもなくさまようとしても、本当にあてはないし。
家族のもとに帰ったとしても、温かく迎え入れられるわけでもないだろう。
自分の力があるのにその中途半端さに、今更ながらにあきれてしまう。
そうこうしているうちに、
「グリンディー、国王様がお呼びだ」
と、祭司長が言った。
「……やっぱり」
クビを言われるのだろう。直接の雇い主である、国王様から。
グリンディーは重い腰を上げて、とぼとぼと歩きだした。
長い廊下を歩きながら、先を行く祭司長の背中を眺める。
この人だってできない時代は――――あったかもしれないけれど、きっと誰もが温かく見守ってくれていたんだろうなあ。
祭司長、という神事を扱う部署でのトップ。才能もある。人を引き付ける魅力もある。
不意に祭司長が立ち止った。
「グリンディー」
名前を呼んで振り返る。気が付くと、すでに謁見の間の前に来ていた。
「さ、行って来い」
ぽん、と背中を押される。いつもにない動きに、グリンディーは戸惑いを覚える。祭司長の顔色を窺えば、いつものように暗雲が立ち込めている雰囲気ではない。どちらかといえば、晴天、だ。
きっと、自分と離れることが、この人にとっては喜ばしいことなんだろうなあ。
重い足取りで扉に近づくと、そっとその扉を押し開けた。
ゆっくりと国王様の前へ歩いていく。
「グリンディー・デリシャスです」
膝をついて名乗ると、
「挨拶はよい」
と、深い声が上から降ってきた。
「グリンディー、顔を上げてくれないか」
ゆっくりと顔を上げて、国王を見た。
「君が、この姫君を助けてくれたんだね」
国王の隣にいる王子が言った。その隣には、カエルが姿を変えた娘が正装をして立っていた。
「……あの?」
クビを言い渡されるにしては、雰囲気がおかしいことにグリンディーは首をかしげる。
「詳しい話は、彼女……ミクル殿から伺いました」
「はあ……? あの、どういうことでしょうか?」
ミクルと呼ばれた娘がグリンディーの前に進み出る。そして、軽くドレスの裾を妻んでお辞儀をすると、
「あなたが私を救ってくださったのです。私はもともと、『水の精霊』でした。私の世界は悪い魔女に支配されそうになっていて、私の持つ精霊の力を使って魔女を退治しようとしたんです。でも、逆にその力を取られてしまって、カエルに姿を変えられてしまっていたのです」
グリンディーは気のない返事をする。
「そこへ、あなたから呼び出しがかかったのです。私は間違いなく『水の精霊』ではありましたが、カエルの姿では精霊の力がないことさえも伝えることができずに、申し訳ありません……」
「つまり、君の召喚魔法とやらは成功していたのだよ」
成功。せいこう。
その言葉をようやく理解して、グリンディーは目を潤ませた。
「それだけじゃない」
グリンディーに国王が声をかけた。
「君は彼女にかけられていた魔法を解いたんだよ。そして、水の精霊としての力も取り戻してくれたのだよ」
「……魔女にとられていたのに?」
「正確に言えば、改めて与えられたのです」
ミクルはそういうと、グリンディーの手をぎゅっと握りしめた。
女性に手を握られることなど、初めてのことに、グリンディーは思わずその手を引っ込めようとした。それをミクルはしっかりととらえて、
「ありがとう」
と、微笑んだ。
「そういうわけで、祭司長に依頼した召喚の件、父がなんと言おうと僕からはぜひともお願いしたい」
こんな風に自分の仕事をお願いされるのは初めてのことではないだろうか。
いつも、散々祭司長から文句ばかりを言われて、「もういい」とさえも言われている。
グリンディーの胸が熱くなる。
「かしこまりました……ただ、王子様もご存じのとおり、……私は、あまり召喚の腕はよくありません。今回たまたま、うまくできただけの事……」
「それでも、君がどれくらい努力しているのかは、聞いている。それに、そのような腕で君がどうしてここにいるのかも。だからこそ、僕は君にお願いしたいんだ。もう一度、言い換えていいかい?
グリンディー・デリシャス。国王の名において命じる。
魔物を鎮めるための伝説の巫女を召喚せよ」
声高らかに、王子は言った。
そして、数日後。
祭司長は指先をまるでリズムを取るかのように叩いている。机の上には、報告書が置かれている。
明らかに祭司長の不機嫌な様子に、グリンディーは今にも背を向けて帰りたくなる。帰るあてもないのだが。
「どうしたら、そうなるのか……教えてくれないか?」
穏やかな口調ではあるものの、明らかに失望の色が現れている。
「乙女、といえば女性のはずだが……」
と、グリンディーの隣にいる、彼と年の変わらない少年をみる。
「さあ……」
グリンディーはちらりと少年を見る。
先ほど、国王と王子から頼まれた、伝説の乙女を召喚する、という仕事をやり終えた。
結果として魔法陣の中に現れたのは、グリンディーと同じ年くらいの少年だった。その姿を見た瞬間、グリンディーはあわてて彼の服を脱がして確認しようとして大騒ぎになり、挙句の果てに取っ組み合いのけんかとなったところをまたしても例の取調官に取り押さえられたのであった。
最終的には祭司長に助けられたものの、取調官からは、いわくありげな笑顔を向けられて、
「ほどほどにするように」
といわれて、思わず、
「公務ですから!」
と、どなり返してしまった。
殴り合い、とまではいかないものの、あちこちに打ち身、擦り傷がある。それはグリンディーの隣にいる少年も同じだ。
そして、今、その少年とともに祭司長のもとに連れてこられたのだった。
グリンディーの視線に気づいた少年は、小さくため息をついて、制服の上着から手帳を取り出す。
写真の張られている身分証明書をグリンディーと祭司長に向けて、
「ここに書かれているのは、俺の身分だ。俺は、私立明翔学園高校2年の音留裕樹だ」
「オトメユウキ?」
読めない字が書いてあるのは、おそらくそれがこの少年の住んでいる世界での文字だからだろう。
少年は「オトメユウキ」と名乗った。
「この召喚士、どうせ下手な召喚しかできないんだろう? 乙女っていうの女じゃなくて、俺の名前と勘違いしたんじゃねーの?」
少年の話に祭司長は納得し、グリンディーはため息を落とす。
「……もういい、そういうことにしておく……君の能力を過大評価しないように、通達をしてもらおう。いいか、しばらく召喚以外の仕事をしろ!」
祭司長はそういうと、一連のことを報告するために部屋を出て行った。
その直後、ユウキがつぶやく一言を、グリンディーは聞き逃さなかった。
思わず目を見張る。
ユウキがグリンディーを見て、にっと笑う。
「いいじゃん、召喚以外の仕事として、俺にこの国で生活するために必要なことを教えてくれ」
人懐こい笑顔。
初めての世界。元いた世界と全く異なる世界。それなのに、すごく前向き。不安だって多いはずだ。それなのに、こんなに笑顔でいられるなんて。
グリンディーも不安に思わせないように、笑顔を向ける。
「いいよ。俺は、グリンディー・デリシャス」
す、と手を出すと、ユウキの手ががっしりとグリンディーの手をつかんだ。
「よろしくな」
ユウキにあれこれと教えながら、時々、ユウキの一言を思い出す。
――――正しいよ。俺は姉貴の代わりだから。
それが、どういう意味を持つのか、グリンディーが知るのはずいぶん先のことになる。
目の前に描かれた円の中央に残されたものを見る。何度も目をこするが、それは変わらない。
グリンディーの胸に抱かれているのは、魔法論を綴っている分厚い本だ。所々にしおりが挟まれ、赤い字で書き込みがなされている。グリンディーがその本のページをめくっていく。
何度も何度も本の内容と床に描かれた円の文字や図形を確認していく。そして、最後、口から出た言葉は。
「なんで、召喚できないんだあっ!?」
グリンディーは頭を抱え込む。
本来なら、魔法の構文にあわせて、召喚魔法が発動する。そして、円の中には水の精霊がいる、というのが、グリンディーが目指したところだった。だが、目の前にいるのは、カエルである。
「水の精霊………」
ぽつりとつぶやく。
確かに、カエルは水に棲む生き物だ。だが、精霊ではない。いや、ひょっとしたら、グリンディーが思い描いている精霊──かわいらしい少女、もしくはずっと落ち着いた雰囲気を持つ大人の女性、ではなく、このカエルが精霊なのかもしれない。
「一応、書いておこう」
と、召喚結果をノートにまとめ始めた。それをじっと見守っていたカエルは突然動き始めた。部屋の中を勢いよく飛び跳ねる。
「あ、こらっ! 大事な召喚品っ!」
グリンディーがノートを放り出してカエルを捕まえようとした。が、直前でするりとグリンディーの手をすり抜けていく。
「くっそー! 待てっ!」
グリンディーがカエルを捕まえようとした瞬間、彼の頭にカエルは着地し、さらに高いところを目指して──天窓のあたりにむかってジャンプをした。
そして、届かなかった代わりに、ちょうどタイミング良く開いた扉から中に入ってきた若い男――祭司長の頭に着地をした。
「あ、あのっ……」
あたふたするグリンディーをあざ笑うかのように、ゲロ、とカエルが鳴いた。
祭司長はゆっくりと部屋の中を見渡す。たった今、召喚がなされた痕跡はここかしこにある。そして、あたふたする「問題児」。何が起こったのかはすぐに察しがついた。
「グリンディー!」
祭司長の怒りがグリンディーの頭上に落ちてきた。
「まったく、何で召喚できないのに、ここに配属されたんだか……」
祭司長はグリンディーに書類を見せながらため息をつく。
「……すみません」
「いや、君が謝ることじゃない」
祭司長に言われて、グリンディーは安堵の表情を浮かべるが、反対に祭司長は深いため息を落とす。
「君の才能に秘めた力を感じた国王様の判断を間違っていると批判した私がいけないのだよ。そして、早々に君の才能が開花しないのをのんきに待っていた私が間違っていたのだよ。早々に君を城から出した方が君のためかもしれない。もちろん、名目は「修行」だろう。そうでもしなければ君の経歴にだって、『クビ』だなんていう傷をつけざるを得なくなってしまった──」
次々と飛び出してくる否定的な言葉に、グリンディーはあきれ返る。よくもまあ、こんな風に言えるものだ。しかも、「毎回毎回」。
「もう、いいです……俺だって」
がんばっている、と言う言葉を飲み込む。
配属になって2年になる。最初の年は召喚術を得意とする先輩について召喚に関することを学んだ。魔法の使い方から、魔法の呪文の構成、発動に不可欠な円陣の描き方。どれもこれも、しっかり学んだ。本も読んで、実践も行ってみた。多分、召喚の広間を人一倍使っていることは記録を見れば確かで、グリンディーの名前は至る所に刻まれている。
けれども、その努力とは裏腹に、同時に召喚できたものの記録を辿っていくと、評価できるようなものではなかった。
先ほどのように、水の精霊を呼び出したつもりが、カエルだったり。
竜を呼び出したつもりが竜族に所属する世界最弱と言われているトカゲだったり。
故人の魂を召喚するはずが、その者の朽ち果てた身体だったり。
成功したことの方が少ないと、自分でも思っている。
つまり、思うものを正しく呼び出したことがないのだ。
そのたびに、魔法の力と構成文、呼び出しに使った円の描き方を確認してもらうのだが、間違いはない。そして、他の神官はグリンディーのやり方できちんと目的の物を召喚してみせるのだった。
最初こそ、「大丈夫だよ」と言われていたけれども、今じゃなにも言われない。そして、結論として、「センスがないんだよ」と言うことに落ち着くのだ。
――――センスって、なんなんだ?
グリンディーの問いかけに誰も答えてはくれなかった。
「書類、読んだか?」
「あ、今読みます」
グリンディーは文字を追っていく。
国王からの発信文書だった。
このところ、人ならざる物の動きが活発化している。魔物に襲われた人がいると書いてある。そして、読み進めると、魔物を鎮めるために伝説の乙女を召喚して欲しい、と書いてあった。
「召喚、するんですか?」
グリンディーは読み終えた書類を祭司長に返した。祭司長の眉がピクリと上がった気がしたのは、気のせいだろう。
「もちろん。魔物を鎮めることができるのは、伝説の乙女だけ。ただ、残念ながら、この召喚は特殊な魔法を使わなければならない」
そういって深々とため息をついた。
「まあ、召喚を生業とする人間はたくさんいますから、誰か一人くらいはできるでしょう?」
祭司長の眉が再び上がった、のは間違いではなさそうだ。急にもやもやした気持ちが心の中に芽生え始めるが、それにあえて蓋をする。
「……まあ、そうだな。だが、そのひとりが全く召喚のセンスがないやつなんだ。国王も頭を抱えていらっしゃった」
「それは……大変ですね」
次の瞬間、祭司長はグリンディーの目の前に今まで彼が読んでいた書類を突きつけた。
「お前、本当にこの文書を読んだのか? ここを見ろ!」
と、左上の宛名を指で示した。
グリンディー・デリシャス。
グリンディーの正式名がそこに記されている。
「……俺、ですか?」
勢いよく祭司長が机をたたいた。
「お前以外に召喚業の輩はたくさんいるが、お前の魔法しかできない召喚なんだよ! あー、よりによってなんでお前なんだか……せめて、お前の親族が生きていてくれたら」
「生きてますっ! 勝手に殺さないでください! ちょっと遠い山奥に隠居しているだけです!」
あまりの勢いに祭司長は耳を指でふさぐ。
「大体、親族が隠居したのは前の国王のせいじゃないですか!」
「引っ張り出すことがわかってるから、お前をここに置いたんだろうが! あの人たちのやりそうなことだ。お前はあいつらのいけにえにされたんだよ。あー、この話はこれで終わりだ。とりあえず、お前に全責任がある。ちゃんと事前に練習しておけよ! 事前に練習して召喚できたらできたで問題はないから」
それだけ言うと、祭司長は書類をテーブルの上において、グリンディーに背中を向けた。
グリンディーはため息をついて書類を受け取ると、一礼して祭司長の部屋を後にした。
グリンディーが落ちこぼれとはいえ、この城にいなければならないのには理由がある。
彼の家系はもともと召喚を生業としていた。代々この城に仕え、事あるごとにさまざまなものを召喚してきた。時には勇者とよばれる異界の若者も召喚したことがある。
そういう力を持っていることを、前の国王、カルアミー1世は面白半分に要求したという。
「どうせなら、天女を召喚してくれないか?」
理由はよくわからなかったが、グリンディーの親族は召喚した。そして、こともあろうに国王はこの天女を自分の妃としてしまったのだ。怒ったのは、天女の父といわれる天帝だった。戦を仕掛けてくるところを何とかおさめて、グリンディーの親族を城から追放したのだ。
とはいっても、グリンディーの一族の魔法の力というのはほかの召喚士と比べ物にならないほど強いものだった。国王は彼らの復讐を恐れて、幼い子供を人質に城へ残すように強要したのだった。
それが、グリンディーである。
いつまでも城でただで養うわけにもいかず、10のころから城で下働きをしている。先代がなくなると今の国王がグリンディーの腕を見込んで、召喚をメインとする神事を司るセクションに彼をおくようにした。幸か不幸か、グリンディーの召喚の腕は親族の中でも落ちこぼれといっても過言ではないものだった。今でも「荷物」になっていることに違いはない。
とぼとぼと廊下を歩きながら、自分の実験室ともいえる部屋に入る。
今まで読んだ本はこの城にある図書館分以上だろう。今もこの部屋の中にはありとあらゆる本が積み上げられている。本棚には入りきれず、机の上にはもちろん、ベッドの周りにも本が積まれている。
そして、新たな顔ぶれとして、机の上におかれた水槽の中に、グリンディーが召喚したカエルがいた。
書類を机の上に無造作に置くと、彼は水槽の中をじっと見た。
カエルと目が合う。
「そっか。君も水の中に戻してあげないとね」
ケロケロ、とカエルが鳴く。
グリンディーはカエルの水槽を抱えると、再び召喚用の部屋へと歩き始めた。
召喚用の部屋に入ると、ろうそくに灯をともす。ほのかな明かりに照らされると、グリンディーは床の上に召喚用の円を書き始めた。
時々、分厚い本を見ながら、丁寧に文字や図を入れていく。
それが完成すると、今度はその中央にカエルを水槽ごとおいた。
「さて……うまく帰れるといいな」
カエルに声をかけて、グリンディーは円の外側に立つ。
呪文の構成文を確認して、それを読み上げていく。ほとんど、暗記しているため、本を見ることはほとんどない。
右手を円の上にかざす。
呪文の朗詠が終わると同時に、手を軽く振り上げた。
呪文が発動する。描いた円から光が放たれる。そして、中央の水槽へと光が集まっていく。
じっとその経過をグリンディーは見る。中央に光が集まったことで、呪文はうまく働いてくれている。
問題はその後だ。
グリンディーの呪文では、水槽は残り、カエルの姿が消えていることになっている。
だが。
光が収まっていくと、そこには一人の少女がいた。年はグリンディーと変わらない……年のころなら、16くらいだろうか。そのせいで、グリンディーの視線は彼女の体にくぎ付けとなる。
お互いに視線を合わせたまま、動けない。
先に、大きな悲鳴があがった。
……カエルは、服を着ていなかったから。
女性の悲鳴を聞きつけて部屋に入ってきた兵士たちは、グリンディーを取り押さえてるなり、城の地下にある取調室へと連行した。
「だから! 召喚に失敗したカエルをもとの世界に帰そうとしただけだ」
グリンディーの話をうんうん、と聞きながらも、取調官は、ずい、と身を乗り出して、
「でも、君は召喚士だよね?」
「……だから、なんだっていうんですか」
「ほら、女性でも召喚できるんじゃないの? 特に君みたいに若い子はさ、そういうことに興味があったりするんじゃないの?」
明らかに疑われている。そのことだけでも腹が立つのに、取調官の言葉の裏側にある好奇心のような物にはもっと腹が立つ。
グリンディーの顔を見て、どうなの? と取調官は顔をのぞき込んだ。
「そんなこと、しません! 大体、俺がここにいるのだって……公務ですから!」
グリンディーがふてくされると、扉が開いて、祭司長が入ってきた。
どうせ、すみません、うちの馬鹿な部下が、と話を始めるのだろうと思っていると、祭司長は取調官を隅に呼ぶと、何やら話を始める。かなり神妙な顔つきに、グリンディーは最悪の事態を考えてしまう。
本当にクビになるのだから、さっさと取り調べを終わらせて城から追放してほしい、とか言っているんじゃないだろうか。
この城を出たら、何をするんだろう、俺。
中途半端な召喚の腕では、食べることは難しいだろう。とはいえ、そうそう魔法を使う仕事があるわけでもないし、そういう協会に登録したとしても、すぐに仕事がもらえるわけでもない。多少の蓄えはあるけれど、済むところの家賃や生活費を考えると、すぐに底をつくのは見えている。あてもなくさまようとしても、本当にあてはないし。
家族のもとに帰ったとしても、温かく迎え入れられるわけでもないだろう。
自分の力があるのにその中途半端さに、今更ながらにあきれてしまう。
そうこうしているうちに、
「グリンディー、国王様がお呼びだ」
と、祭司長が言った。
「……やっぱり」
クビを言われるのだろう。直接の雇い主である、国王様から。
グリンディーは重い腰を上げて、とぼとぼと歩きだした。
長い廊下を歩きながら、先を行く祭司長の背中を眺める。
この人だってできない時代は――――あったかもしれないけれど、きっと誰もが温かく見守ってくれていたんだろうなあ。
祭司長、という神事を扱う部署でのトップ。才能もある。人を引き付ける魅力もある。
不意に祭司長が立ち止った。
「グリンディー」
名前を呼んで振り返る。気が付くと、すでに謁見の間の前に来ていた。
「さ、行って来い」
ぽん、と背中を押される。いつもにない動きに、グリンディーは戸惑いを覚える。祭司長の顔色を窺えば、いつものように暗雲が立ち込めている雰囲気ではない。どちらかといえば、晴天、だ。
きっと、自分と離れることが、この人にとっては喜ばしいことなんだろうなあ。
重い足取りで扉に近づくと、そっとその扉を押し開けた。
ゆっくりと国王様の前へ歩いていく。
「グリンディー・デリシャスです」
膝をついて名乗ると、
「挨拶はよい」
と、深い声が上から降ってきた。
「グリンディー、顔を上げてくれないか」
ゆっくりと顔を上げて、国王を見た。
「君が、この姫君を助けてくれたんだね」
国王の隣にいる王子が言った。その隣には、カエルが姿を変えた娘が正装をして立っていた。
「……あの?」
クビを言い渡されるにしては、雰囲気がおかしいことにグリンディーは首をかしげる。
「詳しい話は、彼女……ミクル殿から伺いました」
「はあ……? あの、どういうことでしょうか?」
ミクルと呼ばれた娘がグリンディーの前に進み出る。そして、軽くドレスの裾を妻んでお辞儀をすると、
「あなたが私を救ってくださったのです。私はもともと、『水の精霊』でした。私の世界は悪い魔女に支配されそうになっていて、私の持つ精霊の力を使って魔女を退治しようとしたんです。でも、逆にその力を取られてしまって、カエルに姿を変えられてしまっていたのです」
グリンディーは気のない返事をする。
「そこへ、あなたから呼び出しがかかったのです。私は間違いなく『水の精霊』ではありましたが、カエルの姿では精霊の力がないことさえも伝えることができずに、申し訳ありません……」
「つまり、君の召喚魔法とやらは成功していたのだよ」
成功。せいこう。
その言葉をようやく理解して、グリンディーは目を潤ませた。
「それだけじゃない」
グリンディーに国王が声をかけた。
「君は彼女にかけられていた魔法を解いたんだよ。そして、水の精霊としての力も取り戻してくれたのだよ」
「……魔女にとられていたのに?」
「正確に言えば、改めて与えられたのです」
ミクルはそういうと、グリンディーの手をぎゅっと握りしめた。
女性に手を握られることなど、初めてのことに、グリンディーは思わずその手を引っ込めようとした。それをミクルはしっかりととらえて、
「ありがとう」
と、微笑んだ。
「そういうわけで、祭司長に依頼した召喚の件、父がなんと言おうと僕からはぜひともお願いしたい」
こんな風に自分の仕事をお願いされるのは初めてのことではないだろうか。
いつも、散々祭司長から文句ばかりを言われて、「もういい」とさえも言われている。
グリンディーの胸が熱くなる。
「かしこまりました……ただ、王子様もご存じのとおり、……私は、あまり召喚の腕はよくありません。今回たまたま、うまくできただけの事……」
「それでも、君がどれくらい努力しているのかは、聞いている。それに、そのような腕で君がどうしてここにいるのかも。だからこそ、僕は君にお願いしたいんだ。もう一度、言い換えていいかい?
グリンディー・デリシャス。国王の名において命じる。
魔物を鎮めるための伝説の巫女を召喚せよ」
声高らかに、王子は言った。
そして、数日後。
祭司長は指先をまるでリズムを取るかのように叩いている。机の上には、報告書が置かれている。
明らかに祭司長の不機嫌な様子に、グリンディーは今にも背を向けて帰りたくなる。帰るあてもないのだが。
「どうしたら、そうなるのか……教えてくれないか?」
穏やかな口調ではあるものの、明らかに失望の色が現れている。
「乙女、といえば女性のはずだが……」
と、グリンディーの隣にいる、彼と年の変わらない少年をみる。
「さあ……」
グリンディーはちらりと少年を見る。
先ほど、国王と王子から頼まれた、伝説の乙女を召喚する、という仕事をやり終えた。
結果として魔法陣の中に現れたのは、グリンディーと同じ年くらいの少年だった。その姿を見た瞬間、グリンディーはあわてて彼の服を脱がして確認しようとして大騒ぎになり、挙句の果てに取っ組み合いのけんかとなったところをまたしても例の取調官に取り押さえられたのであった。
最終的には祭司長に助けられたものの、取調官からは、いわくありげな笑顔を向けられて、
「ほどほどにするように」
といわれて、思わず、
「公務ですから!」
と、どなり返してしまった。
殴り合い、とまではいかないものの、あちこちに打ち身、擦り傷がある。それはグリンディーの隣にいる少年も同じだ。
そして、今、その少年とともに祭司長のもとに連れてこられたのだった。
グリンディーの視線に気づいた少年は、小さくため息をついて、制服の上着から手帳を取り出す。
写真の張られている身分証明書をグリンディーと祭司長に向けて、
「ここに書かれているのは、俺の身分だ。俺は、私立明翔学園高校2年の音留裕樹だ」
「オトメユウキ?」
読めない字が書いてあるのは、おそらくそれがこの少年の住んでいる世界での文字だからだろう。
少年は「オトメユウキ」と名乗った。
「この召喚士、どうせ下手な召喚しかできないんだろう? 乙女っていうの女じゃなくて、俺の名前と勘違いしたんじゃねーの?」
少年の話に祭司長は納得し、グリンディーはため息を落とす。
「……もういい、そういうことにしておく……君の能力を過大評価しないように、通達をしてもらおう。いいか、しばらく召喚以外の仕事をしろ!」
祭司長はそういうと、一連のことを報告するために部屋を出て行った。
その直後、ユウキがつぶやく一言を、グリンディーは聞き逃さなかった。
思わず目を見張る。
ユウキがグリンディーを見て、にっと笑う。
「いいじゃん、召喚以外の仕事として、俺にこの国で生活するために必要なことを教えてくれ」
人懐こい笑顔。
初めての世界。元いた世界と全く異なる世界。それなのに、すごく前向き。不安だって多いはずだ。それなのに、こんなに笑顔でいられるなんて。
グリンディーも不安に思わせないように、笑顔を向ける。
「いいよ。俺は、グリンディー・デリシャス」
す、と手を出すと、ユウキの手ががっしりとグリンディーの手をつかんだ。
「よろしくな」
ユウキにあれこれと教えながら、時々、ユウキの一言を思い出す。
――――正しいよ。俺は姉貴の代わりだから。
それが、どういう意味を持つのか、グリンディーが知るのはずいぶん先のことになる。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

パペット・ブライド ~傀儡姫のお輿入れ~
一花カナウ
ファンタジー
「――墓前に供える花なんかもらって、不吉だな」
「不吉ってあんたねっ! 好意でくれたものに対して失礼じゃない!」
「おうおう。敵国に嫁ぐってのにずいぶんと余裕なことだな。――で、依頼されてたルークスの最終調整が終わったぜ。連れて行くんだろ?」
--------
絡操技術を駆使して作られた人形で栄えたアスター王国。
しかしロゼット帝国から侵略を受け、
十六になったばかりのメローネ姫は帝国に嫁ぐことになった。
先の戦争にて国を守り、傀儡姫と親しまれる彼女は、少々気が強くて頑張り屋な少女。
戦火が再び国に迫るのを防ぐため、
彼女は幼なじみの絡操技師エンシの作った絡操人形を連れて故郷を発つのだが――
※なお、当作品は他のサイトでも公開されています。
軽微な修正による多少の差異はありますが同一作品ですので、ご了承くださいませ。

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。

魔法使いフウリン
烏帽子 博
ファンタジー
風魔法がちょっとだけ使える女の子のフウリン
自分の出生の秘密と共に明かされる本当の姿を知り新たな人生を歩みます
人を育てる中で自分も成長してゆきます。
どう生きるか、幸せとは何か、悩んだり、突き進んだり、恋したり
そして、逆ハーレムも

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

スケートリンクでバイトしてたら大惨事を目撃した件
フルーツパフェ
大衆娯楽
比較的気温の高い今年もようやく冬らしい気候になりました。
寒くなって本格的になるのがスケートリンク場。
プロもアマチュアも関係なしに氷上を滑る女の子達ですが、なぜかスカートを履いた女の子が多い?
そんな格好していたら転んだ時に大変・・・・・・ほら、言わんこっちゃない!
スケートリンクでアルバイトをする男性の些細な日常コメディです。

勇者一行から追放された二刀流使い~仲間から捜索願いを出されるが、もう遅い!~新たな仲間と共に魔王を討伐ス
R666
ファンタジー
アマチュアニートの【二龍隆史】こと36歳のおっさんは、ある日を境に実の両親達の手によって包丁で腹部を何度も刺されて地獄のような痛みを味わい死亡。
そして彼の魂はそのまま天界へ向かう筈であったが女神を自称する危ない女に呼び止められると、ギフトと呼ばれる最強の特典を一つだけ選んで、異世界で勇者達が魔王を討伐できるように手助けをして欲しいと頼み込まれた。
最初こそ余り乗り気ではない隆史ではあったが第二の人生を始めるのも悪くないとして、ギフトを一つ選び女神に言われた通りに勇者一行の手助けをするべく異世界へと乗り込む。
そして異世界にて真面目に勇者達の手助けをしていたらチキン野郎の役立たずという烙印を押されてしまい隆史は勇者一行から追放されてしまう。
※これは勇者一行から追放された最凶の二刀流使いの隆史が新たな仲間を自ら探して、自分達が新たな勇者一行となり魔王を討伐するまでの物語である※
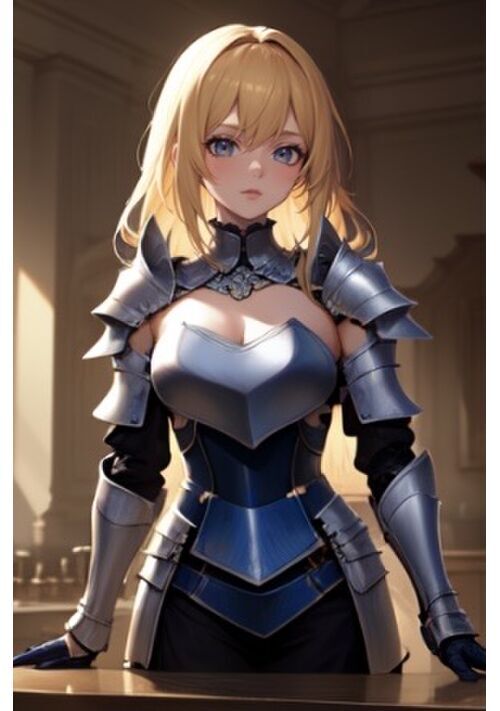
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















