2 / 14
背中を追って
しおりを挟む暗闇の世界に一筋の光。
雲の切れ目から太陽の光が差し込む。
小さな青い空に、この手を伸ばすだけ。
背中を追って
嫁いだ次の日から義母に、子を成せ、子を成せと、日々言われ続ける。一度言い始めると、〝結果が出るまで〟なかなか終わらない。自身が満足するまで止まることがない。よく動く口だ、よく疲れないなと、わたしはいつも思う。
女は、政の道具。
女は、子を産む道具。
そのようなことを一般常識のように言われていた。
今は、戦で血を流していた血生臭い混沌の時代。
戦国時代の、ある小さな国の話。
ある日。
目を覚ますと肌寒く、朝露で草木が光に照らされて綺麗だった。
義母はいくら言っても子を成さないわたしに、ついに手を挙げた。
ヒリヒリと痛む左頬をさする。何を叫んでいるのかよく分からない義母を見上げることなく、ただ彼女の足元を虚ろな目で見ていた。
すると頭上から罵声が落ちてくる。
「こちらを見なさい!」
わたしが義母を見たら、その目はなんだと怒ってくるくせに。なにを思ってそんなことを言うのか理解できない。
義母が起こすであろう先が分かってしまうから、わたしは見上げることを躊躇う。
「子を成さないのは貴女のせいですよ!」
鬱陶しい婆だ。
「世継ぎを早く産みなさい!」
できたらとっくにしてるよ。
「この役立たずが!!」
チラッと見遣ると、それが気に入らなかったようで扇が投げつけてきた。
素早く顔を背け、頭に扇があたり痛みが走る。
そして義母は「同じ一族に入れてやったのに、情けない!! 恥を知れ!!」と吐き捨てて、足早に去っていった。布を擦る音と足音が次第に遠のいていく。
わたしはズキズキと痛む頭に手をやる。指でこするようにさすり、痛みを和らげようとした。
慣れてる。
傷つけるための言葉を吐かれるのも、行き場のない怒りの痛みを受けるのも。
それでも立場上、言い返すことができなくて、悔しくて。いつも目に涙を浮かべる。泣いたら負けだと言い聞かせ、血が滲むほど唇を噛み締めて、その痛みで涙を止めていた。
味方と言われる夫は、今は戦に赴いておりいない。
もし側にいてくれたら、あの義母は良い義母を演じるために大人しくしてくれる。嫁いできた嫁に優しくする母の姿を。
息子に嫌われたくない良母という皮を被った鬼は、その時ばかりは怖いくらい笑顔で親切にしてくれる。その気味が悪い笑顔を見ると吐き気がしてくる。
わたしの心の内は、そんな猫を被っている姿が憎たらしくて憎たらしくて、感情が激しく渦巻く。良い義母という皮を剥ぎ取って、本来の素顔を晒して、顔を殴って。そんなことができたらいいのに。
「……糞食らえ」
わたしができる反抗は、こうやって聞こえないところで呟くことだけ。
それから数日後。
戦から帰ってきた夫は戦での熱が冷めないのか、朝から外で素振りをしていた。
わたしは縁側に座り、その姿を見ていた。
目に映るものは、着物を着崩して羽織り、露わになった戦の勲章と言われる刀傷を持つ体。
鍛えられ、凹凸のある筋肉。
そんな男の体を見ると、いつも胸が苦しくなる。
いっそのこと、わたしも男になって戦で散ることができたらいいのにと、いつの間にかそんなことを考えていた。でもそれもまた〝逃げ〟なのだと気づいていた。義母と言う名の鬼からの逃げだと。
ぼーっと眺めていると、その視線に気づいた夫は一旦手を止めた。
「どうした」
流れ落ちる汗を、刀を持たない手で拭う。
わたしは視線が交わってから、ふと思った。こうやって目を合わせたのはいつぶりだろうかと。久方ぶりだ。
そっと微笑んだ。
「なんでもない」
わたしのぶっきらぼうな物言いを気にすることなく、夫もまた微笑んだ。
「そうか」
短く答えると、握りしめていた刀をするりと鞘に収める。止まらない汗を腕で拭った。
そして右手を伸ばし、
「ん、手ぬぐい」
わたしが持っている手ぬぐいを求められる。しかし、わたしは手で床を叩いた。
「拭いてあげるからここにおいで」
わたしがそう言うと、予想をしていない言葉に夫はぎょっと驚きながらも、すぐにスタスタとやって来た。先に鞘を置き、わたしの隣に座ると、広い背中を見せてくれる。夫婦だと言うのに、どこか恥ずかしそうな面持ちだった。
汗で光る背中をゆっくりと拭き始めた。それから暫く言葉を交わすことはなかった。
背中にある傷は大きいものから小さいものまで様々ではあるが、所謂刀傷だと思われるものがはっきりと残っている。血がうっすらと滲み、治りきっていない傷を見つけると、拭っていた手を止めた。
わたしはいつもこの人に守られている。
この人は、どれだけ傷つけられていても、何度も地についた膝を伸ばし、敵の前で立ち続ける。
己が命を捨てることになろうとも、敵の首を狩る為に刀を握り、刃先を敵に向ける。
この傷の数ほど、わたしは守られているのだ。
一つ一つの傷がどれだけ痛かったのだろう。
女のわたしには思いつかないほどの痛みなのだろう。
わたしが城で受ける痛みなど、きっとこの傷に比べたら痛くない。覚悟の重さが、違うから。
そっと、夫の背中に額を当てた。
持っていた手ぬぐいを、力限り握りしめる。
「どうした」
手を止め、微かに震えていたわたしに気づいたのだろうか。夫は振り返らずに前を向いたまま口を開いた。
「俺は餓鬼ん頃から戦しか頭にない。女心がさっぱり分からん。今、どうしてお前が泣く?」
確かにこの人は頭の中は戦ばかりで、初めて会った時は女のわたしに全く興味を示さなかった。最初はこの人のことを知らないからいろいろと苦労したり、自信をなくしたりしたな。今思い出すと笑ってしまうことばかりだ。この人はただ不器用なだけ。
「貴方の背中にも、傷があるから」
「なら、お前は泣かんでいい」
体に傷を残す俺が未熟っちゅーこっちゃと言って、自笑する。
「俺の傷見て泣いたんは、お前が初めてよ」
皆口を揃えて、背中傷は臆病者の証じゃと笑うぞ。敵に背を向けるなんぞ恥じゃとな。
そう言って、ワハハと楽しそうに笑う。
「でも切られたってことでしょ? 血が出たんでしょ? それって痛いじゃない……いっぱいいっぱい……痛かったでしょう……?」
傷を数えるように傷を見つめ、震える指先でそっとなぞる。
溢れ落ちるわたしの涙が、この大きな背中に流れる。
「……ありがとう……ありがとう……」
この背中に守られている。こんなにも傷つきながらも、その後ろでわたしはのうのうと無傷で生きている。なんて卑怯なんだろう。わたしは彼のなんの役にも立てない。
「可愛いのう」
夫はそう言って肩を揺らした。
顔を見なくてもわかる。きっと今の夫の顔は笑顔だ。だからわたしも。夫にしか聞こえない声で呟く。
「…………好き」
すると夫は「俺もじゃ」と言って、くるっとわたしと向き合い、力強く抱き締めた。そして優しく頭を撫でてくれた。
ある大きな戦が起きた。
彼がいる軍が負けた。
撤退する際にある者を逃す為に、我が身と、ある者に慕う兵達が盾となって、本隊が逃げる為の時間を稼いだと言う。撤退戦で辛うじて生き残った数名の兵が本隊と合流し、この国に帰ってきてすぐの報告だった。
その撤退戦で彼は死んだ。
全てを護る為に。
命を投げ出して。
報告を聞いた義母は泣いた。狂ったように泣き叫んだ。
なんで私の息子が死ななければならなかったのか、と。
せめて亡骸だけでもと懇願しても、誰も首を縦に振らなかった。
なに一つ、彼に関する〝モノ〟は城へ帰らなかった。
義母は生き残って帰ってきた兵を睨みつける。恨みの眼差しは刃の様に鋭かった。
「お前達はなんで帰ってきた!! 私の息子は帰ることができなかったのに!!」
子を失った悲しみをただ受け止められない母の姿。
酷く取り乱した義母に皆は戸惑うばかりで、落ち着かせようと様々な言葉を投げかけるが、どの言葉も義母には届かない。
あらゆる物を手に取り、人に投げ始めた義母に、恐る恐るわたしは近づく。
「お義母様、おやめ下さい。皆に当たらなくても……!!」
義母は文机に置いてあった筆を拾い上げると、力任せに〝敵〟であるわたしへ投げつけてきた。わたしはそれを体で受け止めるしかなかった。そして悲痛な言葉が落ちてくる。
「貴女はなにも感じないのですか!? なにも思わないのですか!? 息子を置いて帰り、更には亡骸さえも迎えに行かないと言うのですよ!! 弔うことすら許されないのですよ!!」
すると慌てて兵の一人が口を開く。
「……戦に勝ったなら可能ではありますが、我々は敗けてしまったので」
言葉をかぶせるように義母は食らいつく。
「敗けたからなによ! 早く行きなさいよ!! さあ! 早く!! なにもかも奪われる前に!!」
戦の敗者側は戦で亡くなった死者を回収することは叶わない。付近に住む住人が憐れみ、供養をしてくれることをただ祈るしかないのだ。供養さえしてくれないかもしれないが。
落ち着いて下さいと声をかけられても、義母は落ち着く様子はない。暫く部屋にあるあらゆる物を兵やわたしに投げつけると、顔を両手で覆い、その場に力なく座り込んだ。
「この世に息子がいないのなら…………生きる意味など、ないではありませんか……」
怒りが落ち着いた次は、悲しみのどん底に身を沈める。
わたしはその姿を見つめた。
もし、今わたしが声をかけたとしても、その言葉は一時の慰みにもならない。
床に崩れ落ちる義母を背に、わたしは歩き出した。嗚咽を漏らしながら泣く声が、徐々に遠くなっていくのを聞きながら。
もう、あの人はいない。
護ってくれた背中は、ない。
戦さ場に赴いていた夫と共に過ごした時間はほんの一握りで。
その短い間でも、彼はわたしをよく見てくれた。
戦さ場から帰ってくると、必ず花を一輪持ってきてくれた。
帰りの道端で咲いていた、どこにでもある花でも、わたしを想ってくれたことに変わりはなく、その心遣いが嬉しくて、そしてそんな彼に惹かれた。
彼が死んだことは義母と共に聞いた時は、わたしも涙が出そうになった。
わたしも泣きたかった。
でも義母を前にすると涙は流れなくて、むしろ頭の中が冴えていくのを感じていた。
もうここにはいられないと。
もし彼の残り香が残るここにいたいと願っても、義母がそれを決して許さない。余所者は余所者らしく、他所へ行けと追い出すだろう。
ここを出て行こう。
故郷へ帰ろう。
彼の残り香を感じる度に胸が苦しくなるぐらいなら。
彼の残り香を感じない場所へ逃げよう。
この城を発つ時、一人の兵が枝を杖代わりに使い、体をよろめかせながら、わたしの元に来た。
撤退戦で生き残った一人か。城から出てきたようではない。たった今、帰還してきた者のようだ。
彼は怪我をしているせい為か、ふらふらとしながら膝を折る。ポタリと大地に血を落とす。痛みで震える手には、あの手ぬぐいを持っていた。
「姫様」
呼ばれたわたしは伏目がちになった。
もう、誰にも呼び止められるとは思っていなかったから。
彼は誰にも聞こえないように声を潜める。
「この手ぬぐいを……お受け取り下さい」
わたしは首を横に振る。
すると兵は返答が分かっていたかのようにニッコリと笑った。すると、顔に巻かれた布に血が滲んだ。
「……から姫様への〝最期〟の贈り物です。どうか……この手ぬぐいをお開き下さい」
よく見れば手ぬぐいはなにかを包んでいるようだ。少しだけ膨らんでいる。
わたしは躊躇いながらも、そっと手ぬぐいを捲ってみた。
「あ……」
一輪の花。
白い花びら。
しおれた花。
その花を手に取ろうとして、あるモノが目に入り、ピタッと手を止めた。
その茎に付いた、赤黒いモノ。
「あぁ……」
それを見た途端、それがなにであるか理解した。説明はいらないほど。
出てこようとする言葉を飲み込む。喉の奥から焼けるような痛みが這い上がってくるように走ってきた。
視界が歪む。
目頭が熱く、痛い。
兵はそんなわたしの様子を見て、丁寧に花を手ぬぐいで包む。壊れやすくて大事なものを護るように。
「死ぬ間際に姫様へと握りしめておられました」
そっとわたしに手ぬぐいを差し出す。
「私はなんとか体が動きましたので、時間がかかりましだ這い寄ることができました」
彼からの愛情を感じて震える手で、その手ぬぐいを受け取った。
「全身を槍で突かれたというのに普段と変わらぬ顔で、私にその花を預けて下さいました」
これを小夜に。
そう私に言うと、姫様への言葉を残されました。
わたしは兵の言葉を静かに待った。
俺は先に逝く。
だからお前は故郷へ帰れ。
もう泣くな。
「それが最期の言葉です」
手ぬぐいをぎゅっと握り締め、胸元に引き寄せる。
彼の言葉を聞いて分かった。一度故郷に戻り、新しい夫へ嫁ぎ、幸せになれと言っている。
あの人の背中を拭いたこれに詰まってる。
あの人の残り香も。
あの人の言葉も。
そして一輪の花も。
なにも持って帰るつもりはなかった。
でも、この手ぬぐいも、花も、一目見てしまったら置いていけない。
漏れそうになる声を殺し、目をぎゅっと閉じる。
溢れる涙を見られないように俯く。
こんなにもわたしは愛されていたのか。
そして、わたしがここまで彼を想っていたなんて。
ぎゅうぎゅうと締め付けるように胸が苦しい。
溢れる涙が止まらない。
わたしは落ち着いてから、兵に視線を向ける。
「ありがとう」
籠に乗り、わたしは彼の城を後にした。
晴れ晴れとした青い空。
なにも変わらない空。
手を伸ばしても、もう決して彼の背中には届かない。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
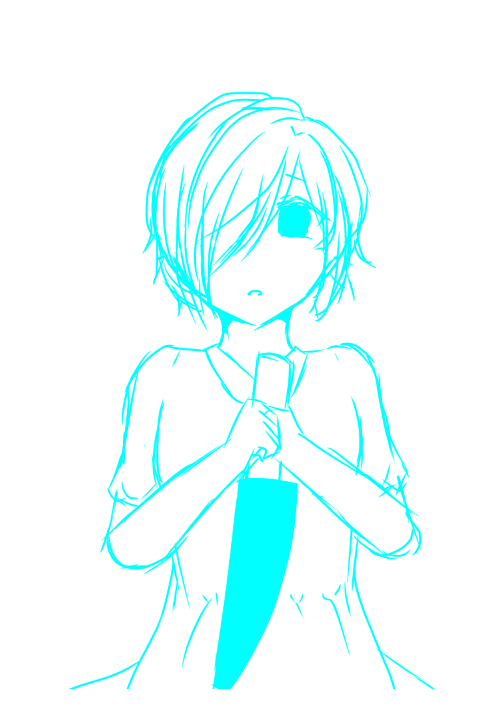

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

孤独少女の願い事
双子烏丸
キャラ文芸
ある理由のせいで、笑顔もなく暗い雰囲気の少女、浅倉裕羽。
そんな彼女が見つけたもの……それは、大昔に一匹の妖精が封印された、神秘的な壷だった。
妖精と少女の出会いは、互いの運命をどう変えるのか、そして二人の過去とは、ぜひ一読して確かめて下さい

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

カフェひなたぼっこ
松田 詩依
キャラ文芸
関東圏にある小さな町「日和町」
駅を降りると皆、大河川に架かる橋を渡り我が家へと帰ってゆく。そしてそんな彼らが必ず通るのが「ひより商店街」である。
日和町にデパートなくとも、ひより商店街で揃わぬ物はなし。とまで言わしめる程、多種多様な店舗が立ち並び、昼夜問わず人々で賑わっている昔ながらの商店街。
その中に、ひっそりと佇む十坪にも満たない小さな小さなカフェ「ひなたぼっこ」
店内は六つのカウンター席のみ。狭い店内には日中その名を表すように、ぽかぽかとした心地よい陽気が差し込む。
店先に置かれた小さな座布団の近くには「看板猫 虎次郎」と書かれた手作り感溢れる看板が置かれている。だが、その者が仕事を勤めているかはその日の気分次第。
「おまかせランチ」と「おまかせスイーツ」のたった二つのメニューを下げたその店を一人で営むのは--泣く子も黙る、般若のような強面を下げた男、瀬野弘太郎である。
※2020.4.12 新装開店致しました 不定期更新※

Arachne ~君のために垂らす蜘蛛の糸~
聖
キャラ文芸
貧乏学生・鳥辺野ソラは、条件の良さそうな求人に惹かれて『Arachne』のアルバイトに応募する。
『Arachne』はwebサイトとYouTubeを中心に活動する、中高生をターゲットにした学習支援メディアだった。
動画編集の仕事を任されることになった彼は、学歴や意識の高いメンバーたちと上手くやっていくことができるのか。そして、この仕事を通じて何を得るのか。
世間から求められる「賢い人」として生きてきたはずの彼らだが、それぞれ秘密や問題を抱えているようで……?
これから受験を迎える人。かつて受験生だった人。あるいは、そうでなかった人。
全ての人に捧げたい、勉強系お仕事小説。
※第8回キャラ文芸大賞にエントリー中。
締め切りに向けて、毎日1話ずつ投稿していく予定です。
原稿は完成済みですので、お気に入りボタンを押してお待ちいただけると嬉しいです!
⇒待ちきれない!またはPDFで一括で読みたい!という方はこちらからどうぞ
https://ashikamosei.booth.pm/items/6426280

骨董品鑑定士ハリエットと「呪い」の指環
雲井咲穂(くもいさほ)
キャラ文芸
家族と共に小さな骨董品店を営むハリエット・マルグレーンの元に、「霊媒師」を自称する青年アルフレッドが訪れる。彼はハリエットの「とある能力」を見込んで一つの依頼を持ち掛けた。伯爵家の「ガーネットの指環」にかけられた「呪い」の正体を暴き出し、隠された真実を見つけ出して欲しいということなのだが…。
胡散臭い厄介ごとに関わりたくないと一度は断るものの、差し迫った事情――トラブルメーカーな兄が作った多額の「賠償金」の肩代わりを条件に、ハリエットはしぶしぶアルフレッドに協力することになるのだが…。次から次に押し寄せる、「不可解な現象」から逃げ出さず、依頼を完遂することはできるのだろうか――?

心に白い曼珠沙華
夜鳥すぱり
キャラ文芸
柔和な顔つきにひょろりとした体躯で、良くも悪くもあまり目立たない子供、藤原鷹雪(ふじわらのたかゆき)は十二になったばかり。
平安の都、長月半ばの早朝、都では大きな祭りが取り行われようとしていた。
鷹雪は遠くから聞こえる笛の音に誘われるように、六条の屋敷を抜けだし、お供も付けずに、徒歩で都の大通りへと向かった。あっちこっちと、もの珍しいものに足を止めては、キョロキョロ物色しながらゆっくりと大通りを歩いていると、路地裏でなにやら揉め事が。鷹雪と同い年くらいの、美しい可憐な少女が争いに巻き込まれている。助け逃げたは良いが、鷹雪は倒れてしまって……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















