24 / 31
破天の日 その3
しおりを挟む
靄の立ち込める早朝。山間の道を往く東国武士団の列を見下ろしながら、セナたちは山の中を早足で駆けていた。小高い山々が連なる鈴鹿山脈には、かなりの標高を誇る山もいくつか点在している。
その中の一つ、那須ヶ原山にセナは狙いを定めた。
「そこは柘植ノ平まであと少しの位置。鬼童丸なら――いや、私なら兵士たちの気が緩み始めた頃を襲う」
起伏が激しい広大な山の中を、たった一人の敵を探して歩き回る。まったく無謀な作戦だったが、誰も異を唱えずについて来た。
すると、あたりに濃い霧が立ち込めた。祭子がくんくんと鼻を利かせる。
「どうやら当たりのようだ……」
セナも実真も異変に気付いていた。
「これは……煙幕か」
白い煙霧の中、目の前に人影が浮かび上がる。袖の長い鈴懸に、一本歯の下駄を履いている。そして奇怪な迦楼羅面――蘆名義遠だった。
実真や祭子、精兵たちはすぐさま刀を抜いた。
「何者だ」
「我が名は蘆名義遠……隠れし者なり……」
セナはまだ煙を注意深く嗅いでいる。ハッとあることに気付いた。かすかに麻の匂いがする。すり潰して痛み止めの軟膏としても使うものだ。
「煙を吸ってはダメ! 動きが鈍くなる!」
全員が即座に袖で口を覆うも、煙が全身に行き渡るのは時間の問題だった。
「ヤツを射殺せ! ただちに突破する!」
祭子が号令を出すと、精兵たちは一斉に短弓(小型の弓)を構え、次々に矢を発射した。が、いずれも木の幹に当たり、軽々と蘆名にかわされ、決定的な一矢を放つことが出来ない。
平地での戦を得意とする東国武士たちは飛距離のある長弓(大型の弓)を愛用した。そのため短弓の練度は低く、効果的に使うことが出来ずにいた。
「これが東国の武士か……ぬるい」
蘆名は長く幅の広い袖をひらりと外套(マント)のようにひるがえし、飛矢の力を削いでたやすく無力化してしまった。
「矢が効かぬなら斬り捨てるまで」
祭子がすばやく突貫し、蘆名に斬りかかる。蘆名は一本歯の下駄を履いているにもかかわらず、軽業師のように宙を回転しながら回避した。いくら慣れない戦闘であるとはいえ、『姫夜叉』の攻撃がかすりもしない。
蘆名は袖をすばやくひるがえした。キラリと光った瞬間、鉄の針が連続で飛んでくる。祭子は打ち刀で叩き落とすも防戦一方。いったん身を退いた。
「なんだこいつは。攻め手の軸がつかめん……」
「まるで娥眉丸だな」実真は言った。
「娥眉丸……猿神童子の妻の暁姫の弟の泰寿坊の配下の娥眉丸か?」
「そうだ」
「ならば幻術使いか」
「そうでなければいいが……」
実真と祭子が話している間に、後方から悲鳴が上がった。精兵たちが襲撃を受けている。見ると、蘆名とまったく同じ姿の者が三人。そして前方にいた蘆名もまた左右に二人ずつ姿を増やした。
「分かつ身命の術……」
全部で八人の蘆名義遠があらわれ、すっかり囲まれてしまった。怪我人を抱えて突っ切ることは困難。このままでは、じわじわとなぶり殺されてしまう。
「セナ、何をしている」
実真が目をやると、セナは地面に刺さっていた矢を何本か拾っていた。
「弓を貸して」
祭子から弓を借りると矢をつがえた。
「最初に出て来たヤツがたぶんこの集団の頭。私が頭を潰す」
そう言って残りの矢を口にくわえ、疾風のように駆け出した。
セナは弓を構え、迦楼羅面の集団に向かって突撃した。矢の先端を振り、狙いを五人すべてに定める。五人の蘆名は四方に散らばった。木々の間を飛び跳ね、交差しながら巧みに狙いをかわす。
そして交差の瞬間、鉄の針がすばやく飛んでくる。セナは転がって回避し、起きざまに矢を放った。が、当たらない。次の矢も難なく袖で払われた。
「無駄だ……娘よ」
「見えた」
セナは五人の蘆名の中に突入した。するとセナは一本の木を駆け登り、蘆名たちのはるか頭上を制すると、跳躍して滞空したまま狙いを定めた。
ビュンッ――と、それまでとは比較にならない速度で矢が空を切る。五人の蘆名のうち、一人の左胸を貫いた。その蘆名はどさりと地面に落ちた。
「所詮は人。鹿よりも遅い」
セナは音もなく着地した。最初からこれを狙っていた。矢を見切られないように何度か遅く放ち、最後に全速で仕留める。そして狙いを外さないように標的から一瞬たりとも目は離さない。並々ならぬ動体視力によるものである。
「異界の戦いか……これほどとはな」
祭子は感心して言った。
「頭を潰せば指揮が乱れる。各個撃破しろ!」
実真が命令を下した瞬間、胸を射抜かれた蘆名がバッタのごとく跳ね起きる。
「蘇っただと? ちっ、やはり幻術使いか」
実真も祭子も刀を構え直した。するとセナが小声で言った。
「ヤツの身体をよく見て」
二人は言われたとおり蘇った蘆名を見た。なんと白い鈴懸の袖に赤い線が入っている。射抜かれた胸の穴のまわりにも赤い色が付着していた。
「矢に口紅を塗っておいた。仕留めきれなかった時のために」
「いつの間に……」
実真はセナの唇に紅が残っているのを確認した。なるほど、矢をくわえる時に密かに塗っていたらしい。口紅は舞人が常に携行しているものだ。
「私も戦場で紅を塗るべきか――どう思う? 実真殿」
祭子が軽い調子で言った。実真はフッと笑う。
「戦場でなくとも、好きな時に塗ればいい」
「なぜだ?」
「今でも美しいが、より美しくなる」
祭子はあっと口を開け、紅をさしたように頬を紅潮させた。そしてそれを隠すように蘆名に向き直り、刃を向ける。
「ねっ、狙いはついた。実真殿――援護を」
実真はこくりと頷く。祭子と実真は図ったように同じ時機、違う方向に駆け出した。祭子が印のついた蘆名を狙い、実真が他を引きつける。数では劣勢にも関わらず、二人の連携に蘆名たちは追い詰められた。
「獲った――」
ついに、祭子の一閃が印のついた蘆名の首を刎ねた。迦楼羅面をつけた頭部が転がり落ち、残った胴体もばたりと倒れる。
文字通り『頭』を失い、残りの七人は指揮が乱れるはずだった。しかしいずれの迦楼羅面の男もまったく動揺していない。
「おかしい……手ごたえがない」
祭子が疑問を口にした直後、首を刎ねたはずの蘆名の死骸が、むくりと起き上がった。すると後方にいた三人のうち一人の迦楼羅面の男が言った。
「蘆名の頭は頭にあらず」
また別の迦楼羅面の男が同じ声と口調で次々としゃべりだす。
「我らは一人で八人」
「我らは八人で一人」
「我らはすべて蘆名義遠」
八人の蘆名は、その発言を裏付けせんとばかりに、まったく同じ動作でセナたちを取り囲んだ。一挙手一投足が鏡写しのように乱れがない。
「何だこいつら……アヤカシか!?」
「あるいはこの煙のせいか……」
「どのみちこのままでは」
セナたちは背中合わせに追い込まれる。
その時だった――。白濁した煙霧の中から、濃い人影が一つあらわれた。
「何をしている」鬼童丸だった。
鬼童丸は一人の蘆名の背後に立ったかと思うと、脳天から太刀を振り降ろした。
あっという間もなく蘆名が真っ二つになる。
すると、中から一人の子供が飛び出した。子供は驚愕した表情で、鬼童丸から急いで離れる。他の蘆名たちも集合し、三すくみの状態となった。
「なるほど、これが仕掛けか」
鬼童丸は蘆名が着ていた鈴懸を手に取った。幅広で長い袖は、本来の腕の長さを隠すためのもの。一本歯の下駄は、裾に覆われた膝から実際の歯が伸びていて身長を高く見せるように作られている。
迦楼羅面の中は空洞。胴体にすっぽりと子供が入れるようになっていた。
「正体は……子供だったのか」
実真は驚きを口にした。
「否――子供にあらず」
どう見ても子供の顔をしている蘆名の声は、まさしく大人のそれである。
「若体不老の術にて」
怒気を放った鬼童丸は迦楼羅面を踏み潰した。
「手を出すなと言ったはずだ! 邪魔をするならお前も敵だ!」
鬼童丸はたった一人。だが、その武威に押されて蘆名たちは身構える。
「正体は見破った。消えろ。でなければ生きて帰れると思うな」
鬼童丸は太刀を構える。すると八人の蘆名たちは無言で撤退を始めた。不思議なことに、蘆名が去ると同時に煙霧がサッと晴れてゆく。
追撃しようとする兵士たちを、実真は手で制止した。
「祭子、負傷兵と共に山を下りて鍛治谷と合流してくれ。敵の本隊が来ている」
「承知した……忘れるな、実真殿――私が仕えるのはそなただけだ」
「ああ、忘れるものか」
実真は鬼童丸に向き直った。そして、セナも。
「鬼童丸!」
セナは叫んだ。鬼童丸は鋭い目で一瞥する。
永遠のような刹那の時だった。セナは束ねた髪から黒い笄を抜き取る。
蠱毒を用いて戦うのか――と、思った次の瞬間、黒い笄で左の手の甲をサッと切り、血のにじむ傷を掲げて鬼童丸に見せた。そして、再び名を叫ぶ。
「鬼童丸!」
※
「ひっ、ひひひ、姫様!」
その光景を見た景平はわなわなと震え、膝から崩れそうになった。
渡会の屋敷の修練場にて、静乃が弓を引いている。だけでなく、その手に手を重ね、静乃の背中にピッタリと密着して一緒に弓を引く九馬の姿があった。
景平は太刀を抜いた。ずんずんと大地を踏み抜いて九馬の首を狙う。
殺気に気付いて振り向いた九馬は、あわてて静乃から離れた。逃げ出そうとするも腰が抜けて動けない。
「かかかか景平殿! や、やや、やはり!」
「やはり……なんだ?」
景平は太刀を頭上に構えた。脳天から真っ二つにするつもりである。
「やはり、こんなことはよくない……」
「ああん?」
「おやめなさい、景平!」
静乃がぴしゃりと言い放つ。景平は九馬を睨みながら太刀を納めた。
「私が九馬さんにお願いしたのです。弓を教えて欲しいと」
「何故そのような。弓なら私に言ってくだされば」
「言ったところでムダでしょ。それに九馬さんはとても弓がお上手なのよ」
景平は頭を殴られたような衝撃を受けた。実際、教える気などない。麗しい姫の可憐な指に弓など持たせたくはない。だが、それをたやすく見抜かれ、こいつは話にならないと烙印を押されたことが痛かった。
すなわち九馬に負けた――。こんな若造に。景平は顔面蒼白である。
「うぅ……そ、それはともかく……姫はなぜ弓を?」
「都に帰るためです」
「都に? それがどうして弓など」
「予感がするの……嵐の予感が」
「嵐……」
それは景平も感じていた。血の嵐が吹き荒れる予感を。
今、水野実真は兵を起こした。兵力を用いて御堂晴隆の罪を明らかにし、幽閉された帝を救出するため。たとえ敵が追討使であっても、それは偽りの権力者から派遣されたものだ。帝を救出できれば実真はたちまち救国の英雄となる。
しかし――どうにも胸騒ぎがする。
兵を使って三関の一つ『鈴鹿の関』を突破したのは事実だ。
そして事実だけを見れば、実真はまさに反乱を起こして京に攻め上っている途中である。
「それと、確かめることがあります」
景平は残った左目の眼光を鋭くした。
「寿老上人……ですか」
今、渡会の屋敷に寿老上人が訪れている。静乃は、実真が軍を発して京の都に向かったこの時機を待っていた。
「あの奇怪な坊主、我らのことを詳しく知っていたようですな」
「……本人に確かめましょう」
その頃――渡会の屋敷の居室にて、上條常正と寿老上人が向かい合って座っていた。寿老は微笑を浮かべて『茶』を飲んでいる。茶は大陸の交易品で、薬としての効能もあり、貴族たちしか口に出来ない貴重な物だった。
「今はまだ舶来の物しかないが、日ノ本でも茶畑を作ろうと思う」
そう言ったのは寿老上人である。
「茶を日ノ本で……ですか」
常正は半信半疑で聞いている。
「然様。そなたの所領は茶を作るのに良さそうじゃ。引退したあとは茶畑の主にならぬか? のんびりと茶の香りを楽しめばよい」
「ふむ、それもようございますな。ただ……」
寿老は常正の思惑を推し量るように右の眉を上げた。
「はたして、大戦になるのでしょうか」
大戦――不穏な言葉の響きが残る中、庭で小鳥がさえずっている。
「嵐は小さな風から巻き起こる。一度吹いた風は誰にも止められぬよ」
静乃と景平がやって来たのは、その時である。
寿老は相を崩して二人を居室に招き入れた。
「さて、何用かな――お二人さん」
ずずずと茶をすする。景平は眉をひそめた。静乃が恭しく礼をした。
「寿老様。さぞ徳の高いお坊様とお見受けいたします」
「うむ! 拙僧は徳のたか~い坊主である」
「一つ、お聞きしたいことがございます」
「一つでいいのかね? 静姫」
緊張が走る。静乃は寿老の並々ならぬ存在感に圧倒されそうになった。
「なぜ『わし』がお前たちのことを知っているのか……なに、物事は意外と単純である。そなたの父・高階義明から聞いただけのこと」
「父が」
「然様。高階はそなたのことたいそう心配しておるぞ」
「生きているのですか!?」
静乃は腰を浮かせた。寿老はニヤリと笑う。
「陸奥国にて身を潜めておる。わしが生きておるのも、高階のように陰より支えてくれる者たちのおかげである」
一人、真実にたどり着いた景平の額に冷たい汗がひと筋流れた。
「姫様、この僧侶は……いや、このお方は」
その続きを、ずっと瞑目していた常正が答えた。
「時の帝の弟君……彰人親王であらせられる」
彰人親王――かつて永現の乱で、兄である現在の帝と対決し、敗走して京の都を追われた男である。山中で自害したとも、鬼に食われたとも言われ、ずっと行方知れずとなっていた。
高階家は兄親王派、つまり帝側について戦った。
景平にとって、かつての敵の首魁が目の前にいるのである。
「静姫よ、じき都に嵐が訪れる。ここらで陸奥国に行ってはどうかのう?」
静乃の呼吸がかすかに震えた。死んだと思っていた父が生きている。その事実が静乃の足に羽を生やし、今すぐにでも陸奥国に飛んで行きたくなった。
だが――謡舞寮のみんなの顔が浮かぶ。りつ、サギリ、そして、セナ。
自分の居場所は、みんなとともにある。
「私は謡舞寮の生徒。今は生きているとわかっただけで十分でございます」
景平は静乃の凛とした表情を見て、胸に熱が広がった。
姫は真に強くおなりだ――最初は、その強さを見て悲しみを感じた。強くなければならなかった境遇を想い、守りきれなかった己を責めた。
しかし今は違う。姫は真の強さを獲得したのだ。弓の上手も刀の達人も、けっして及ぶことのない真の心の強さを。
(姫様! この景平! 一生ついてゆきますぞ!!!)
景平は心で咽び泣いた。そしてこうも思った。
(佐門よ……戻って来い。お前の主はここにいるぞ)
※
実真はセナに駆け寄った。
「何をしている!? 今すぐ毒を吸い出さないと」
セナは鬼童丸から目を離さず、首を横に振る。
「平気……毒じゃないから」
「毒じゃ……ない……?」
当惑した実真の視線はセナと黒い笄を経て、鬼童丸に向かった。セナは紅い傷の入った手を軽く握りしめる。
「この黒い笄は蠱毒の武器じゃなかった。それどころか、薬で鍛えた癒しの武器だった……でしょう? 鬼童丸」
鬼童丸は答えない。セナの目を正面から見据えた。
「あの時、私に放った黒い笄には毒と薬とが混じっていた。こうして生きているのが証拠。鬼童丸、どうして私を殺さなかった。どうして生かそうとした」
「……生かそうとした……本当なのか」
実真は驚きを隠せない。じわりと額に汗が浮かぶ。
「あなたは私に帝を殺せと命じて、黒い笄を持たせた。でも、蠱毒の武器なんかじゃなかった。私を謡舞寮に送ったのはなぜ?」
鬼童丸は聞きながら歯を見せてカカカと笑った。
「答えて鬼童丸。あなたからは武器の扱いも殺しの術も、文字も舞の指し方も教わった。私は一体何のために今まで――」
「来世……お前は」
実真がその名を呼んだ瞬間、鬼童丸は太刀でそばにあった枯木を一閃した。濡れたような静けさに包まれていた山中に木が倒れる音が響く。
「実真よォ……俺は運命なんて信じちゃいねえが……いつかはこうなるような気がしていたよ」
「どういうことだ」
「まだわからねえのか――あの日お前が浮世を殺した時、すべては始まった」
実真の脳裡に過去の情景が突風のようによみがえる。
「真の黒鬼はお前だ……実真」
実真はカッと目を見開いた。
※
「私がお聞きしたいことは一つです」
静乃は寿老上人を正面に捉え、まっすぐ問いを放った。
「あの時、どうして実真様は浮世の髑髏を壊そうとしたのですか?」
浮世の髑髏――以前、寿老が実真の屋敷に持って来た物である。それを見た実真は瞳から色を失い、怒れる獣のように破壊しようとした。
静乃はそれを言っている。
寿老はおどけた様子でぽりぽりとあごを掻く。
「そんなこともあったかのう……」
「お答えください、彰人親王」
「寿老でよい。いや、寿老と呼んでくれ。彰人はもう死んだっ、ワハハ」
軽い調子だが、寿老の言葉は重い。しばしの沈黙が訪れたが、いっこうに視線を揺るがせない静乃に負けて、寿老は大きな息を吐く。
「やれやれ……こうと決めた女は押しても動かぬからのう」
そう言って、首にかけていた頭陀袋から髑髏を取り出す。
「これは大乱の折、わしを守って死んだ女官の物である。名は知らぬ。顔もその時初めて見た。なのに、わしの代わりに死んだ」
寿老は慈しむように髑髏をゆっくりと撫でた。
「実真はこの髑髏が浮世ではないと知っていたのだ。ゆえに怒った。だが、本気で壊す気だったなら、コレはここにはなかろうよ」
静かに、そして激烈に怒りを発露した実真。静乃はあの時の無に近い表情を思い出し、胸に小さくも鋭い凍えを覚えた。
「わしは水野実真という男を大乱の最中からずっと見ておった。古今二人とない鬼神のごとき武力は、いずれ嵐の目となるであろうと」
「嵐の目……」
「大乱を生き延びたわしは名を捨てて日ノ本をさすらい歩いた。まったく稀有なことであった。帝の血脈であるわしが供も付けずに諸国を巡り、知ったのだ。この大地の隅々に人々がおり、そこに無数の日ノ本がある。すなわち、この世のすべてだったはずの都など片隅に過ぎぬと」
寿老はまっすぐ向けられた静乃の目に応えるように顔を上げた。
「実真はすべてを帝に奪われ、ついに嵐は巻き起こるはずだった。驕り高ぶった天朝の器を砕き、日ノ本をすべての民に返す時が」
だが――と、寿老は目を細める。
「風は止んでしまった……」
その時、庭のほうから声がした。
「それについては、拙者がお話しせねばなりますまい」
甲冑を身につけた安長だった。寿老に向かって恭しく頭を垂れる。
「彰人親王とはつゆ知らず、数々の無礼をお許しくだされ」
「かまわぬ。今やただの僧侶。気にするな」
顔を上げると、静乃にも目礼した。
「すまぬのう、わしはそなたに嘘を吐いておった」
「嘘?」
「実真様は浮世を見つけられなかったと言ったが、真実は違う。見つけたのだ。ある海辺で……浮世の姿を」
その中の一つ、那須ヶ原山にセナは狙いを定めた。
「そこは柘植ノ平まであと少しの位置。鬼童丸なら――いや、私なら兵士たちの気が緩み始めた頃を襲う」
起伏が激しい広大な山の中を、たった一人の敵を探して歩き回る。まったく無謀な作戦だったが、誰も異を唱えずについて来た。
すると、あたりに濃い霧が立ち込めた。祭子がくんくんと鼻を利かせる。
「どうやら当たりのようだ……」
セナも実真も異変に気付いていた。
「これは……煙幕か」
白い煙霧の中、目の前に人影が浮かび上がる。袖の長い鈴懸に、一本歯の下駄を履いている。そして奇怪な迦楼羅面――蘆名義遠だった。
実真や祭子、精兵たちはすぐさま刀を抜いた。
「何者だ」
「我が名は蘆名義遠……隠れし者なり……」
セナはまだ煙を注意深く嗅いでいる。ハッとあることに気付いた。かすかに麻の匂いがする。すり潰して痛み止めの軟膏としても使うものだ。
「煙を吸ってはダメ! 動きが鈍くなる!」
全員が即座に袖で口を覆うも、煙が全身に行き渡るのは時間の問題だった。
「ヤツを射殺せ! ただちに突破する!」
祭子が号令を出すと、精兵たちは一斉に短弓(小型の弓)を構え、次々に矢を発射した。が、いずれも木の幹に当たり、軽々と蘆名にかわされ、決定的な一矢を放つことが出来ない。
平地での戦を得意とする東国武士たちは飛距離のある長弓(大型の弓)を愛用した。そのため短弓の練度は低く、効果的に使うことが出来ずにいた。
「これが東国の武士か……ぬるい」
蘆名は長く幅の広い袖をひらりと外套(マント)のようにひるがえし、飛矢の力を削いでたやすく無力化してしまった。
「矢が効かぬなら斬り捨てるまで」
祭子がすばやく突貫し、蘆名に斬りかかる。蘆名は一本歯の下駄を履いているにもかかわらず、軽業師のように宙を回転しながら回避した。いくら慣れない戦闘であるとはいえ、『姫夜叉』の攻撃がかすりもしない。
蘆名は袖をすばやくひるがえした。キラリと光った瞬間、鉄の針が連続で飛んでくる。祭子は打ち刀で叩き落とすも防戦一方。いったん身を退いた。
「なんだこいつは。攻め手の軸がつかめん……」
「まるで娥眉丸だな」実真は言った。
「娥眉丸……猿神童子の妻の暁姫の弟の泰寿坊の配下の娥眉丸か?」
「そうだ」
「ならば幻術使いか」
「そうでなければいいが……」
実真と祭子が話している間に、後方から悲鳴が上がった。精兵たちが襲撃を受けている。見ると、蘆名とまったく同じ姿の者が三人。そして前方にいた蘆名もまた左右に二人ずつ姿を増やした。
「分かつ身命の術……」
全部で八人の蘆名義遠があらわれ、すっかり囲まれてしまった。怪我人を抱えて突っ切ることは困難。このままでは、じわじわとなぶり殺されてしまう。
「セナ、何をしている」
実真が目をやると、セナは地面に刺さっていた矢を何本か拾っていた。
「弓を貸して」
祭子から弓を借りると矢をつがえた。
「最初に出て来たヤツがたぶんこの集団の頭。私が頭を潰す」
そう言って残りの矢を口にくわえ、疾風のように駆け出した。
セナは弓を構え、迦楼羅面の集団に向かって突撃した。矢の先端を振り、狙いを五人すべてに定める。五人の蘆名は四方に散らばった。木々の間を飛び跳ね、交差しながら巧みに狙いをかわす。
そして交差の瞬間、鉄の針がすばやく飛んでくる。セナは転がって回避し、起きざまに矢を放った。が、当たらない。次の矢も難なく袖で払われた。
「無駄だ……娘よ」
「見えた」
セナは五人の蘆名の中に突入した。するとセナは一本の木を駆け登り、蘆名たちのはるか頭上を制すると、跳躍して滞空したまま狙いを定めた。
ビュンッ――と、それまでとは比較にならない速度で矢が空を切る。五人の蘆名のうち、一人の左胸を貫いた。その蘆名はどさりと地面に落ちた。
「所詮は人。鹿よりも遅い」
セナは音もなく着地した。最初からこれを狙っていた。矢を見切られないように何度か遅く放ち、最後に全速で仕留める。そして狙いを外さないように標的から一瞬たりとも目は離さない。並々ならぬ動体視力によるものである。
「異界の戦いか……これほどとはな」
祭子は感心して言った。
「頭を潰せば指揮が乱れる。各個撃破しろ!」
実真が命令を下した瞬間、胸を射抜かれた蘆名がバッタのごとく跳ね起きる。
「蘇っただと? ちっ、やはり幻術使いか」
実真も祭子も刀を構え直した。するとセナが小声で言った。
「ヤツの身体をよく見て」
二人は言われたとおり蘇った蘆名を見た。なんと白い鈴懸の袖に赤い線が入っている。射抜かれた胸の穴のまわりにも赤い色が付着していた。
「矢に口紅を塗っておいた。仕留めきれなかった時のために」
「いつの間に……」
実真はセナの唇に紅が残っているのを確認した。なるほど、矢をくわえる時に密かに塗っていたらしい。口紅は舞人が常に携行しているものだ。
「私も戦場で紅を塗るべきか――どう思う? 実真殿」
祭子が軽い調子で言った。実真はフッと笑う。
「戦場でなくとも、好きな時に塗ればいい」
「なぜだ?」
「今でも美しいが、より美しくなる」
祭子はあっと口を開け、紅をさしたように頬を紅潮させた。そしてそれを隠すように蘆名に向き直り、刃を向ける。
「ねっ、狙いはついた。実真殿――援護を」
実真はこくりと頷く。祭子と実真は図ったように同じ時機、違う方向に駆け出した。祭子が印のついた蘆名を狙い、実真が他を引きつける。数では劣勢にも関わらず、二人の連携に蘆名たちは追い詰められた。
「獲った――」
ついに、祭子の一閃が印のついた蘆名の首を刎ねた。迦楼羅面をつけた頭部が転がり落ち、残った胴体もばたりと倒れる。
文字通り『頭』を失い、残りの七人は指揮が乱れるはずだった。しかしいずれの迦楼羅面の男もまったく動揺していない。
「おかしい……手ごたえがない」
祭子が疑問を口にした直後、首を刎ねたはずの蘆名の死骸が、むくりと起き上がった。すると後方にいた三人のうち一人の迦楼羅面の男が言った。
「蘆名の頭は頭にあらず」
また別の迦楼羅面の男が同じ声と口調で次々としゃべりだす。
「我らは一人で八人」
「我らは八人で一人」
「我らはすべて蘆名義遠」
八人の蘆名は、その発言を裏付けせんとばかりに、まったく同じ動作でセナたちを取り囲んだ。一挙手一投足が鏡写しのように乱れがない。
「何だこいつら……アヤカシか!?」
「あるいはこの煙のせいか……」
「どのみちこのままでは」
セナたちは背中合わせに追い込まれる。
その時だった――。白濁した煙霧の中から、濃い人影が一つあらわれた。
「何をしている」鬼童丸だった。
鬼童丸は一人の蘆名の背後に立ったかと思うと、脳天から太刀を振り降ろした。
あっという間もなく蘆名が真っ二つになる。
すると、中から一人の子供が飛び出した。子供は驚愕した表情で、鬼童丸から急いで離れる。他の蘆名たちも集合し、三すくみの状態となった。
「なるほど、これが仕掛けか」
鬼童丸は蘆名が着ていた鈴懸を手に取った。幅広で長い袖は、本来の腕の長さを隠すためのもの。一本歯の下駄は、裾に覆われた膝から実際の歯が伸びていて身長を高く見せるように作られている。
迦楼羅面の中は空洞。胴体にすっぽりと子供が入れるようになっていた。
「正体は……子供だったのか」
実真は驚きを口にした。
「否――子供にあらず」
どう見ても子供の顔をしている蘆名の声は、まさしく大人のそれである。
「若体不老の術にて」
怒気を放った鬼童丸は迦楼羅面を踏み潰した。
「手を出すなと言ったはずだ! 邪魔をするならお前も敵だ!」
鬼童丸はたった一人。だが、その武威に押されて蘆名たちは身構える。
「正体は見破った。消えろ。でなければ生きて帰れると思うな」
鬼童丸は太刀を構える。すると八人の蘆名たちは無言で撤退を始めた。不思議なことに、蘆名が去ると同時に煙霧がサッと晴れてゆく。
追撃しようとする兵士たちを、実真は手で制止した。
「祭子、負傷兵と共に山を下りて鍛治谷と合流してくれ。敵の本隊が来ている」
「承知した……忘れるな、実真殿――私が仕えるのはそなただけだ」
「ああ、忘れるものか」
実真は鬼童丸に向き直った。そして、セナも。
「鬼童丸!」
セナは叫んだ。鬼童丸は鋭い目で一瞥する。
永遠のような刹那の時だった。セナは束ねた髪から黒い笄を抜き取る。
蠱毒を用いて戦うのか――と、思った次の瞬間、黒い笄で左の手の甲をサッと切り、血のにじむ傷を掲げて鬼童丸に見せた。そして、再び名を叫ぶ。
「鬼童丸!」
※
「ひっ、ひひひ、姫様!」
その光景を見た景平はわなわなと震え、膝から崩れそうになった。
渡会の屋敷の修練場にて、静乃が弓を引いている。だけでなく、その手に手を重ね、静乃の背中にピッタリと密着して一緒に弓を引く九馬の姿があった。
景平は太刀を抜いた。ずんずんと大地を踏み抜いて九馬の首を狙う。
殺気に気付いて振り向いた九馬は、あわてて静乃から離れた。逃げ出そうとするも腰が抜けて動けない。
「かかかか景平殿! や、やや、やはり!」
「やはり……なんだ?」
景平は太刀を頭上に構えた。脳天から真っ二つにするつもりである。
「やはり、こんなことはよくない……」
「ああん?」
「おやめなさい、景平!」
静乃がぴしゃりと言い放つ。景平は九馬を睨みながら太刀を納めた。
「私が九馬さんにお願いしたのです。弓を教えて欲しいと」
「何故そのような。弓なら私に言ってくだされば」
「言ったところでムダでしょ。それに九馬さんはとても弓がお上手なのよ」
景平は頭を殴られたような衝撃を受けた。実際、教える気などない。麗しい姫の可憐な指に弓など持たせたくはない。だが、それをたやすく見抜かれ、こいつは話にならないと烙印を押されたことが痛かった。
すなわち九馬に負けた――。こんな若造に。景平は顔面蒼白である。
「うぅ……そ、それはともかく……姫はなぜ弓を?」
「都に帰るためです」
「都に? それがどうして弓など」
「予感がするの……嵐の予感が」
「嵐……」
それは景平も感じていた。血の嵐が吹き荒れる予感を。
今、水野実真は兵を起こした。兵力を用いて御堂晴隆の罪を明らかにし、幽閉された帝を救出するため。たとえ敵が追討使であっても、それは偽りの権力者から派遣されたものだ。帝を救出できれば実真はたちまち救国の英雄となる。
しかし――どうにも胸騒ぎがする。
兵を使って三関の一つ『鈴鹿の関』を突破したのは事実だ。
そして事実だけを見れば、実真はまさに反乱を起こして京に攻め上っている途中である。
「それと、確かめることがあります」
景平は残った左目の眼光を鋭くした。
「寿老上人……ですか」
今、渡会の屋敷に寿老上人が訪れている。静乃は、実真が軍を発して京の都に向かったこの時機を待っていた。
「あの奇怪な坊主、我らのことを詳しく知っていたようですな」
「……本人に確かめましょう」
その頃――渡会の屋敷の居室にて、上條常正と寿老上人が向かい合って座っていた。寿老は微笑を浮かべて『茶』を飲んでいる。茶は大陸の交易品で、薬としての効能もあり、貴族たちしか口に出来ない貴重な物だった。
「今はまだ舶来の物しかないが、日ノ本でも茶畑を作ろうと思う」
そう言ったのは寿老上人である。
「茶を日ノ本で……ですか」
常正は半信半疑で聞いている。
「然様。そなたの所領は茶を作るのに良さそうじゃ。引退したあとは茶畑の主にならぬか? のんびりと茶の香りを楽しめばよい」
「ふむ、それもようございますな。ただ……」
寿老は常正の思惑を推し量るように右の眉を上げた。
「はたして、大戦になるのでしょうか」
大戦――不穏な言葉の響きが残る中、庭で小鳥がさえずっている。
「嵐は小さな風から巻き起こる。一度吹いた風は誰にも止められぬよ」
静乃と景平がやって来たのは、その時である。
寿老は相を崩して二人を居室に招き入れた。
「さて、何用かな――お二人さん」
ずずずと茶をすする。景平は眉をひそめた。静乃が恭しく礼をした。
「寿老様。さぞ徳の高いお坊様とお見受けいたします」
「うむ! 拙僧は徳のたか~い坊主である」
「一つ、お聞きしたいことがございます」
「一つでいいのかね? 静姫」
緊張が走る。静乃は寿老の並々ならぬ存在感に圧倒されそうになった。
「なぜ『わし』がお前たちのことを知っているのか……なに、物事は意外と単純である。そなたの父・高階義明から聞いただけのこと」
「父が」
「然様。高階はそなたのことたいそう心配しておるぞ」
「生きているのですか!?」
静乃は腰を浮かせた。寿老はニヤリと笑う。
「陸奥国にて身を潜めておる。わしが生きておるのも、高階のように陰より支えてくれる者たちのおかげである」
一人、真実にたどり着いた景平の額に冷たい汗がひと筋流れた。
「姫様、この僧侶は……いや、このお方は」
その続きを、ずっと瞑目していた常正が答えた。
「時の帝の弟君……彰人親王であらせられる」
彰人親王――かつて永現の乱で、兄である現在の帝と対決し、敗走して京の都を追われた男である。山中で自害したとも、鬼に食われたとも言われ、ずっと行方知れずとなっていた。
高階家は兄親王派、つまり帝側について戦った。
景平にとって、かつての敵の首魁が目の前にいるのである。
「静姫よ、じき都に嵐が訪れる。ここらで陸奥国に行ってはどうかのう?」
静乃の呼吸がかすかに震えた。死んだと思っていた父が生きている。その事実が静乃の足に羽を生やし、今すぐにでも陸奥国に飛んで行きたくなった。
だが――謡舞寮のみんなの顔が浮かぶ。りつ、サギリ、そして、セナ。
自分の居場所は、みんなとともにある。
「私は謡舞寮の生徒。今は生きているとわかっただけで十分でございます」
景平は静乃の凛とした表情を見て、胸に熱が広がった。
姫は真に強くおなりだ――最初は、その強さを見て悲しみを感じた。強くなければならなかった境遇を想い、守りきれなかった己を責めた。
しかし今は違う。姫は真の強さを獲得したのだ。弓の上手も刀の達人も、けっして及ぶことのない真の心の強さを。
(姫様! この景平! 一生ついてゆきますぞ!!!)
景平は心で咽び泣いた。そしてこうも思った。
(佐門よ……戻って来い。お前の主はここにいるぞ)
※
実真はセナに駆け寄った。
「何をしている!? 今すぐ毒を吸い出さないと」
セナは鬼童丸から目を離さず、首を横に振る。
「平気……毒じゃないから」
「毒じゃ……ない……?」
当惑した実真の視線はセナと黒い笄を経て、鬼童丸に向かった。セナは紅い傷の入った手を軽く握りしめる。
「この黒い笄は蠱毒の武器じゃなかった。それどころか、薬で鍛えた癒しの武器だった……でしょう? 鬼童丸」
鬼童丸は答えない。セナの目を正面から見据えた。
「あの時、私に放った黒い笄には毒と薬とが混じっていた。こうして生きているのが証拠。鬼童丸、どうして私を殺さなかった。どうして生かそうとした」
「……生かそうとした……本当なのか」
実真は驚きを隠せない。じわりと額に汗が浮かぶ。
「あなたは私に帝を殺せと命じて、黒い笄を持たせた。でも、蠱毒の武器なんかじゃなかった。私を謡舞寮に送ったのはなぜ?」
鬼童丸は聞きながら歯を見せてカカカと笑った。
「答えて鬼童丸。あなたからは武器の扱いも殺しの術も、文字も舞の指し方も教わった。私は一体何のために今まで――」
「来世……お前は」
実真がその名を呼んだ瞬間、鬼童丸は太刀でそばにあった枯木を一閃した。濡れたような静けさに包まれていた山中に木が倒れる音が響く。
「実真よォ……俺は運命なんて信じちゃいねえが……いつかはこうなるような気がしていたよ」
「どういうことだ」
「まだわからねえのか――あの日お前が浮世を殺した時、すべては始まった」
実真の脳裡に過去の情景が突風のようによみがえる。
「真の黒鬼はお前だ……実真」
実真はカッと目を見開いた。
※
「私がお聞きしたいことは一つです」
静乃は寿老上人を正面に捉え、まっすぐ問いを放った。
「あの時、どうして実真様は浮世の髑髏を壊そうとしたのですか?」
浮世の髑髏――以前、寿老が実真の屋敷に持って来た物である。それを見た実真は瞳から色を失い、怒れる獣のように破壊しようとした。
静乃はそれを言っている。
寿老はおどけた様子でぽりぽりとあごを掻く。
「そんなこともあったかのう……」
「お答えください、彰人親王」
「寿老でよい。いや、寿老と呼んでくれ。彰人はもう死んだっ、ワハハ」
軽い調子だが、寿老の言葉は重い。しばしの沈黙が訪れたが、いっこうに視線を揺るがせない静乃に負けて、寿老は大きな息を吐く。
「やれやれ……こうと決めた女は押しても動かぬからのう」
そう言って、首にかけていた頭陀袋から髑髏を取り出す。
「これは大乱の折、わしを守って死んだ女官の物である。名は知らぬ。顔もその時初めて見た。なのに、わしの代わりに死んだ」
寿老は慈しむように髑髏をゆっくりと撫でた。
「実真はこの髑髏が浮世ではないと知っていたのだ。ゆえに怒った。だが、本気で壊す気だったなら、コレはここにはなかろうよ」
静かに、そして激烈に怒りを発露した実真。静乃はあの時の無に近い表情を思い出し、胸に小さくも鋭い凍えを覚えた。
「わしは水野実真という男を大乱の最中からずっと見ておった。古今二人とない鬼神のごとき武力は、いずれ嵐の目となるであろうと」
「嵐の目……」
「大乱を生き延びたわしは名を捨てて日ノ本をさすらい歩いた。まったく稀有なことであった。帝の血脈であるわしが供も付けずに諸国を巡り、知ったのだ。この大地の隅々に人々がおり、そこに無数の日ノ本がある。すなわち、この世のすべてだったはずの都など片隅に過ぎぬと」
寿老はまっすぐ向けられた静乃の目に応えるように顔を上げた。
「実真はすべてを帝に奪われ、ついに嵐は巻き起こるはずだった。驕り高ぶった天朝の器を砕き、日ノ本をすべての民に返す時が」
だが――と、寿老は目を細める。
「風は止んでしまった……」
その時、庭のほうから声がした。
「それについては、拙者がお話しせねばなりますまい」
甲冑を身につけた安長だった。寿老に向かって恭しく頭を垂れる。
「彰人親王とはつゆ知らず、数々の無礼をお許しくだされ」
「かまわぬ。今やただの僧侶。気にするな」
顔を上げると、静乃にも目礼した。
「すまぬのう、わしはそなたに嘘を吐いておった」
「嘘?」
「実真様は浮世を見つけられなかったと言ったが、真実は違う。見つけたのだ。ある海辺で……浮世の姿を」
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

夜珠あやかし手帖 ろくろくび
井田いづ
歴史・時代
あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。
+++
今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。
団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。
町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!
(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

大江戸の番人 〜吉原髪切り捕物帖〜
佐倉 蘭
歴史・時代
★第9回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★
「近頃、吉原にて次々と遊女の美髪を根元より切りたる『髪切り』現れり。狐か……はたまた、物の怪〈もののけ〉或いは、妖〈あやかし〉の仕業か——」
江戸の人々が行き交う天下の往来で、声高らかに触れ回る讀賣(瓦版)を、平生は鳶の火消しでありながら岡っ引きだった亡き祖父に憧れて、奉行所の「手先」の修行もしている与太は、我慢ならぬ顔で見ていた。
「是っ非とも、おいらがそいつの正体暴いてよ——お縄にしてやるぜ」
※「今宵は遣らずの雨」 「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」に関連したお話でネタバレを含みます。

懴悔(さんげ)
蒼あかり
歴史・時代
嵐のような晩だった。
銀次は押し込み強盗「おかめ盗賊」の一味だった。「金は盗っても命は取らぬ」と誓っていたのに、仲間が失態をおかし、人殺し盗賊に成り下がってしまう。銀次は何の因果かその家の一人娘を連れ去ることに。
そして、おかめ強盗に命を散らされた女中、鈴の兄源助は、妹の敵を討つために一人、旅に出るのだった。
追われ、追いかけ、過去を悔い、そんな人生の長い旅路を過ごす者達の物語。
※ 地名などは全て架空のものです。
※ 詳しい下調べはおこなっておりません。作者のつたない記憶の中から絞り出しましたので、歴史の中の史実と違うこともあるかと思います。その辺をご理解のほど、よろしくお願いいたします。

検非違使異聞 読星師
魔茶来
歴史・時代
京の「陰陽師の末裔」でありながら「検非違使」である主人公が、江戸時代を舞台にモフモフなネコ式神達と活躍する。
時代は江戸時代中期、六代将軍家宣の死後、後の将軍鍋松は朝廷から諱(イミナ)を与えられ七代将軍家継となり、さらに将軍家継の婚約者となったのは皇女である八十宮吉子内親王であった。
徳川幕府と朝廷が大きく接近した時期、今後の覇権を睨み朝廷から特殊任務を授けて裏検非違使佐官の読星師を江戸に差し向けた。
しかし、話は当初から思わぬ方向に進んで行く。

父(とと)さん 母(かか)さん 求めたし
佐倉 蘭
歴史・時代
★第10回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★
ある日、丑丸(うしまる)の父親が流行病でこの世を去った。
貧乏裏店(長屋)暮らしゆえ、家守(大家)のツケでなんとか弔いを終えたと思いきや……
脱藩浪人だった父親が江戸に出てきてから知り合い夫婦(めおと)となった母親が、裏店の連中がなけなしの金を叩いて出し合った線香代(香典)をすべて持って夜逃げした。
齢八つにして丑丸はたった一人、無一文で残された——
※「今宵は遣らずの雨」 「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」にうっすらと関連したお話ですが単独でお読みいただけます。

圭佳国物語
真愛つむり
歴史・時代
生まれて間もなく、花街に捨てられた姉妹。2人は楼主に拾われ、将来の花魁候補として育てられる。しかし妹が9歳で結核を患い、帰らぬ人に。唯一の血縁者を失った11歳の姉は絶望し憔悴するも、妹との最後の約束を果たさんと奔走する。
そんな中、都からとある貴人が妾探しに来るという噂を聞く。はじめは興味がなかった姉だが、傾国の美貌を持っているらしいと聞いて一目だけでも見てみることに。そして目の前に現れた美丈夫に一目惚れしかけるも、最低な性格の持ち主だと知り幻滅。思わず蔑みの目を向けてしまい、不敬として連行される。貴人は「最後のチャンスをやる。一生敬いますと言えば許して下女にしてやるぞ」と言うが、姉は「信念を曲げるくらいなら死を選ぶ」と啖呵を切った。処刑される寸前、家臣たちの話が耳に入る。どうやら貴人は帝の命で『蘇りの石』を探しているらしい。姉は妹を生き返らせる方法があるならと貴人に頭を下げた。そんな姉を見て何を思ったか、貴人は処刑をとりやめ姉を下女にする。姉は貴人の身の回りの世話をしつつ石探しを手伝うことになる。
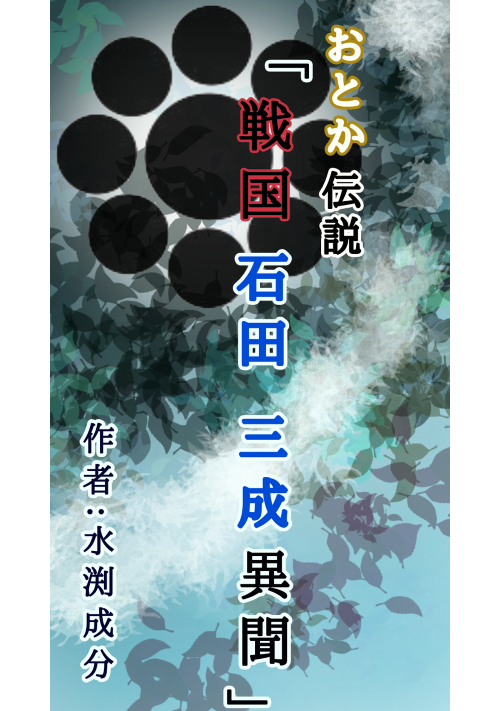
おとか伝説「戦国石田三成異聞」
水渕成分
歴史・時代
関東北部のある市に伝わる伝説を基に創作しました。
前半はその市に伝わる「おとか伝説」をですます調で、
後半は「小田原征伐」に参加した石田三成と「おとか伝説」の衝突について、
断定調で著述しています。
小説家になろうでは「おとか外伝『戦国石田三成異聞』」の題名で掲載されています。
完結済です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















